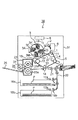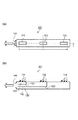JP4902393B2 - ダクト、及び画像形成装置 - Google Patents
ダクト、及び画像形成装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4902393B2 JP4902393B2 JP2007046088A JP2007046088A JP4902393B2 JP 4902393 B2 JP4902393 B2 JP 4902393B2 JP 2007046088 A JP2007046088 A JP 2007046088A JP 2007046088 A JP2007046088 A JP 2007046088A JP 4902393 B2 JP4902393 B2 JP 4902393B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- opening
- duct
- suction
- air
- port
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/06—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
- G03G15/08—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
- G03G15/0896—Arrangements or disposition of the complete developer unit or parts thereof not provided for by groups G03G15/08 - G03G15/0894
- G03G15/0898—Arrangements or disposition of the complete developer unit or parts thereof not provided for by groups G03G15/08 - G03G15/0894 for preventing toner scattering during operation, e.g. seals
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes
- G03G2215/01—Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies
- G03G2215/0167—Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies single electrographic recording member
- G03G2215/0174—Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies single electrographic recording member plural rotations of recording member to produce multicoloured copy
- G03G2215/0177—Rotating set of developing units
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Control Or Security For Electrophotography (AREA)
- Dry Development In Electrophotography (AREA)
- Electrophotography Configuration And Component (AREA)
Description
図1は本発明の実施形態の画像形成装置の概略断面構成を示す説明図である。図1に示すように、画像形成装置30は、電子写真方式で中間転写方式のフルカラー画像形成可能なレーザプリンタである。画像形成装置30は、装置本体31内に像担持体としての感光ドラム1を備えている。感光ドラム1の周囲には、感光ドラム1の回転方向に沿って帯電器2、露光装置8、現像装置3、一次転写ローラ4、クリーニング装置6が設置される。
図2はダクトである吸引ダクトの外観と配置との説明図、図3は吸引ダクトの長手方向の断面図、図4は第2ダクトにおける壁隔壁の間隔と流路長との関係の説明図、図5は流量分布のシミュレーション演算結果の説明図である。図2中、(a)は全体図、(b)はA断面図である。図3中、(a)は第2ダクト、(b)は第1ダクトである。図5中、(a)は本実施形態、(b)は比較例1である。
D<L
としてある。図4に示すように、逆にD>Lの関係とすると、排気口44側に引っ張られる力が強くなり、壁隔壁43による整流が十分に機能しなくなる。結果、吸入口42から接続開口45への風向が傾きやすくなり、吸入口42からの均一な吸引をすることができなくなる。D<Lの構成とすることで、壁隔壁43による整流性能が高まり、吸入口42からの気流の方向の傾きを小さくでき、吸引ダクト27の長手方向で均一な吸引が可能となる。
図6は変形例の吸引ダクトの斜視図、図7は吸引ダクトの流路抵抗の概念的な説明図である。変形例の吸引ダクト227は、図1に示す吸引ダクト27を置き換えて配置され、吸入口242と接続開口245以外は図1に示す吸引ダクト27と等しく構成される。従って、図6、図7中、吸引ダクト27と同一な構成には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。また、吸入口242、接続開口245は、吸引ダクト27のそれぞれ吸入口42、接続開口45と間口幅(配列方向の長さ)が異なるだけである。
図8は比較例2の吸引ダクトの説明図である。図8中、(a)は吸入側から見た平面図、(b)は吸入面を上にした側面図である。
2 帯電器
3 現像装置
6 クリーニング装置
8 露光装置
23 定着装置
27、227 ダクト(吸引ダクト)
30 画像形成装置
31 装置本体
40 連絡路(第2ダクト)
41 風路(第1ダクト)
42、242 開口部(吸入口)
43 仕切り板(壁隔壁)
44 吸引口(排気口)
45、245 連絡口(接続開口)
46 床隔壁
50 吸入ファン
51 トナー回収フィルタ
Claims (10)
- 記録材に像を形成する画像形成装置に用いられるダクトにおいて、
空気を排出するための排出口と、前記排出口の近傍に取り付けられて空気を排出するためのファンと、空気が吸込まれる第一開口部及び第二開口部と、前記第一開口部及び第二開口部を通じて吸引された空気を案内する第一案内部と、前記第一案内部に設けられて前記第一開口部から吸引された空気流と前記第二開口部から吸引された空気流とを仕切る仕切り部材と、前記第一案内部に重ねて配置され、前記第一案内部から流れ込んだ空気流を前記排出口へ案内する第二案内部と、前記第一開口部からの空気流を前記第一案内部から前記第二案内部へ送り込む第一連絡口と、前記第二開口部からの空気流を前記第一案内部から前記第二案内部へ送り込む第二連絡口とを備え、
前記第一連絡口は、前記第二連絡口よりも前記排出口に近く、前記第一連絡口の大きさは前記第二連絡口の大きさよりも小さいことを特徴とするダクト。 - 前記第一開口部の開口面積と前記第二開口部の開口面積は等しいことを特徴とする請求項1に記載のダクト。
- 前記第一開口部から前記第一連絡口までの距離は、前記第二開口部から前記第二連絡口までの距離よりも大きいことを特徴とする請求項1又は2に記載のダクト。
- 前記第一開口部と前記第二開口部とは、前記第一案内部と前記第二案内部とが重なっている方向と直行する方向に並べて配置されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のダクト。
- 前記排出口は、前記第一開口部と前記第二開口部とが並べて配置されている方向における前記第二案内部の側面に設けられていることを特徴とする請求項4記載のダクト。
- トナー像を担持する回転可能な像担持体と、前記像担持体に対向して配置されて前記像担持体側から空気を吸引するダクトとを備えた画像形成装置において、
前記ダクトは、空気を排出するための排出口と、前記排出口の近傍に取り付けられて空気を排出するためのファンと、空気が吸込まれる第一開口部及び第二開口部と、前記第一開口部及び第二開口部を通じて吸引された空気を案内する第一案内部と、前記第一案内部に設けられて前記第一開口部から吸引された空気流と前記第二開口部から吸引された空気流とを仕切る仕切り部材と、前記第一案内部に重ねて配置され、前記第一案内部から流れ込んだ空気流を前記排出口へ案内する第二案内部と、前記第一開口部からの空気流を前記第一案内部から前記第二案内部へ送り込む第一連絡口と、前記第二開口部からの空気流を前記第一案内部から前記第二案内部へ送り込む第二連絡口とを備え、
前記第一連絡口は、前記第二連絡口よりも前記排出口に近く、前記第一連絡口の大きさは前記第二連絡口の大きさよりも小さいことを特徴とする画像形成装置。 - 前記第一開口部の開口面積と前記第二開口部の開口面積は等しいことを特徴とする請求項6記載の画像形成装置。
- 前記第一開口部から前記第一連絡口までの距離は、前記第二開口部から前記第二連絡口までの距離よりも大きいことを特徴とする請求項6又は7記載の画像形成装置。
- 前記第一開口部と前記第二開口部とは、前記第一案内部と前記第二案内部とが重なっている方向と直行する方向に並べて配置されていることを特徴とする請求項6乃至8のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記排出口は、前記第一開口部と前記第二開口部とが並べて配置されている方向における前記第二案内部の側面に設けられていることを特徴とする請求項9記載の画像形成装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007046088A JP4902393B2 (ja) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | ダクト、及び画像形成装置 |
| US12/036,589 US7809304B2 (en) | 2007-02-26 | 2008-02-25 | Duct for image forming apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007046088A JP4902393B2 (ja) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | ダクト、及び画像形成装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2008209649A JP2008209649A (ja) | 2008-09-11 |
| JP2008209649A5 JP2008209649A5 (ja) | 2010-04-15 |
| JP4902393B2 true JP4902393B2 (ja) | 2012-03-21 |
Family
ID=39716054
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007046088A Expired - Fee Related JP4902393B2 (ja) | 2007-02-26 | 2007-02-26 | ダクト、及び画像形成装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7809304B2 (ja) |
| JP (1) | JP4902393B2 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5463951B2 (ja) * | 2010-02-26 | 2014-04-09 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |
| US8488989B2 (en) * | 2010-03-08 | 2013-07-16 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Image forming device having exhaust channel for exhausting air out of the device |
| US20120107011A1 (en) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Brown Kenneth J | Reducing contamination by regulating flow |
| JP5478649B2 (ja) * | 2012-02-20 | 2014-04-23 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 画像形成装置 |
| JP2013174755A (ja) * | 2012-02-27 | 2013-09-05 | Ricoh Co Ltd | 濃度センサ清掃機構付き電子写真記録装置 |
| JP6358176B2 (ja) * | 2015-06-17 | 2018-07-18 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 現像装置、画像形成装置 |
| JP2019012178A (ja) * | 2017-06-30 | 2019-01-24 | キヤノン株式会社 | 定着装置 |
| JP2022006916A (ja) * | 2020-06-25 | 2022-01-13 | コニカミノルタ株式会社 | 画像形成装置 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4693588A (en) * | 1986-04-09 | 1987-09-15 | Xerox Corporation | Thermal air curtain for a copying/printing machine |
| JPH0720753A (ja) * | 1993-07-05 | 1995-01-24 | Canon Inc | 画像形成装置 |
| JPH09127836A (ja) * | 1995-11-06 | 1997-05-16 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置 |
| JP4759161B2 (ja) * | 2001-04-25 | 2011-08-31 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP2004093708A (ja) * | 2002-08-30 | 2004-03-25 | Brother Ind Ltd | 画像形成装置 |
| JP2005140971A (ja) * | 2003-11-06 | 2005-06-02 | Ricoh Co Ltd | 飛散粉塵吸引装置、現像装置及び画像形成装置 |
| JP2005215232A (ja) | 2004-01-29 | 2005-08-11 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 現像装置および画像形成装置 |
| JP2006163135A (ja) * | 2004-12-09 | 2006-06-22 | Seiko Epson Corp | 画像形成装置 |
| US7447462B2 (en) * | 2004-12-09 | 2008-11-04 | Seiko Epson Corporation | Image forming apparatus with exhaust duct |
| JP2006267944A (ja) * | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Sharp Corp | 画像形成装置 |
| JP2007025496A (ja) * | 2005-07-20 | 2007-02-01 | Brother Ind Ltd | 画像形成装置 |
| JP4569407B2 (ja) * | 2005-07-22 | 2010-10-27 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4759468B2 (ja) * | 2006-08-07 | 2011-08-31 | キヤノン株式会社 | シート搬送装置及び画像形成装置 |
| JP4693725B2 (ja) * | 2006-08-07 | 2011-06-01 | キヤノン株式会社 | シート搬送装置及び画像形成装置 |
-
2007
- 2007-02-26 JP JP2007046088A patent/JP4902393B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-02-25 US US12/036,589 patent/US7809304B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2008209649A (ja) | 2008-09-11 |
| US20080205925A1 (en) | 2008-08-28 |
| US7809304B2 (en) | 2010-10-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4902393B2 (ja) | ダクト、及び画像形成装置 | |
| US8494400B2 (en) | Developing device with moveable flexible sheet for preventing toner deposition on developing device casing and image forming apparatus including the same | |
| JP5447320B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| US7231157B2 (en) | Image forming apparatus | |
| JP5742011B2 (ja) | 作像装置、画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |
| US9031449B2 (en) | Toner collector and image forming apparatus including same | |
| JP5239498B2 (ja) | 無端状部材駆動装置および画像形成装置 | |
| JP2006250973A (ja) | 現像装置及びこれを用いた画像形成装置 | |
| JP2016206330A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |
| JP2010237451A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4740389B2 (ja) | 画像形成装置及び異物受け取り方法 | |
| JP2017097039A (ja) | 廃トナー搬送装置およびそれを備えた画像形成装置 | |
| JP5246484B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2019015911A (ja) | 定着装置および画像形成装置 | |
| JP5958801B2 (ja) | 現像装置、及び画像形成装置 | |
| JP5817375B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6674651B2 (ja) | 作像装置及び画像形成装置 | |
| JP2006001686A (ja) | 記録体搬送装置及び画像形成装置 | |
| JP5822093B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6097680B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4760323B2 (ja) | カラー画像形成装置 | |
| JP4218268B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2011170288A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |
| JP2021110909A (ja) | 現像装置、及び画像形成装置 | |
| JP4138353B2 (ja) | カラー画像形成装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100225 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100225 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20111227 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20111228 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150113 Year of fee payment: 3 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |