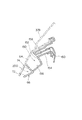JP5259221B2 - 車両の前照灯構造 - Google Patents
車両の前照灯構造 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5259221B2 JP5259221B2 JP2008079701A JP2008079701A JP5259221B2 JP 5259221 B2 JP5259221 B2 JP 5259221B2 JP 2008079701 A JP2008079701 A JP 2008079701A JP 2008079701 A JP2008079701 A JP 2008079701A JP 5259221 B2 JP5259221 B2 JP 5259221B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- position valve
- reflector
- light
- bulb
- vertical wall
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Description
この構成によれば、ハウジングに一体に設けた仕切り部と縦壁部とによってポジションバルブの光を遮ることができると共に、車体正面から見て、目視されるポジションバルブの発光面が目立たないようになる。
この構成によれば、車体前方へ照射されるポジションバルブの光を縦壁部によって遮ることができる。他方、金型の分割方向に向けて縦壁部を形成することができる。
この構成によれば、ヘッドライトバルブの光とポジションバルブの光とを、光を遮る空間によって、より明確に仕切ることができる。
この構成によれば、ポジションバルブの背面に位置するリフレクタを有効に利用することができる。
この構成によれば、縦壁部を目立たないようにすることができる。
この構成によれば、ポジションバルブの前方のレンズを結露等によってくもり難くすることができる。
また、前記ポジションバルブ(70)は、当該ポジションバルブ(70)の先端部の上球体部(70a)の約半分が正面視で見える角度まで前記軸線(X)が前傾している構成としても良い。
また、ポジションバルブ自体が一部露出するため、ポジションバルブの直接光を一部利用でき、また、ポジションバルブの軸線が車両の前後方向に垂直な面に沿い、縦壁部とポジションバルブの後方のハウジングにリフレクタ部が設けられているため、ポジションバルブが縦壁部に隠れている部分の光も反射させて外部に照射させることができる。
図1は、本発明の実施の形態に係る鞍乗り型車両の一例たる自動2輪車を示す側面図である。なお、以下の説明中、前後左右及び上下といった方向の記載は車体に対してのものとする。また、図中矢印FRは車体前方を、矢印Rは車体右方を、矢印UPは車体上方をそれぞれ示している。
さらに、ヘッドパイプ11の前方には、後述するフロントトップカバー37Bから車体前方に表出する態様で前照灯25が設けられている。
エアクリーナ19は、メインパイプ12の前側下方であって、パワーユニット50の前方に取り付けられている。このエアクリーナ19は、パワーユニット50とエアクリーナ19との間に配置されたスロットルボディ30Aに吸気パイプ30を介して接続されており、このスロットルボディ30Aは、パワーユニット50と接続されている。エアクリーナ19で取り込んだ走行中の外気は、スロットルボディ30Aへと供給される。スロットルボディ30Aは、燃料と空気を混合し、パワーユニット50へと供給する。
また、パワーユニット50の下方中央部であって、車体右側には、エンジン51を始動させるキックペダル34が設けられている。また、パワーユニット50の車体左側には、車体を傾けた状態で停めるためのサイドスタンド35が設けられている。
さらに、エンジン51の下方後端部には、運転者の足で操作するブレーキペダル60が回動自在に支持されている。
これらの収納ボックス27及び燃料タンク28の上方は、タンデム式のシート29によって覆われている。このシート29は、収納ボックス27の前側に設けられたヒンジ軸を中心に回動させることができ、これにより、収納時及び給油時にシート29を開閉させることができるようになっている。また、収納ボックス27の上側開口の上縁部には、シート29の底板と当接して内部に雨水等が入り込まないように、シール部材(図示せず)が設けられている。
また、リアフレーム14の後端部には、後輪21の上方を覆うリアフェンダ39及びテールランプ40が取り付けられている。
車体前方を覆うフロントトップカバー37Bには、その中央部に前照灯25が設けられている。また、前照灯25の左右には、一対のウインカー62が設けられている。
前照灯25は、その前面を覆うレンズ64と、このレンズ64の後方に位置し、反射板としての機能を果たすハウジング66と、このハウジング66のほぼ中心に取り付けられるヘッドライトバルブ68と、ハウジング66の上側の両端部に取り付けられる2つのポジションバルブ70とを備えている。レンズ64の外縁部は、ハウジング66の外縁部にすき間なく取り付けられ、ハウジング66の内部に雨水等が入り込まないようになっている。
また、ハウジング66は、これらの仕切り部72および縦壁部74によってそれぞれの室に区分けされている。より詳細には、ハウジング66は、図3に示すように、ヘッドライトバルブ68の光を車体前方に向けて反射させるためのヘッドライトバルブ用リフレクタ部100と、ポジションバルブ70の光を車体前方に向けて反射させるための2つのポジションバルブ用リフレクタ部150と、これらのヘッドライトバルブ68、ポジションバルブ70の光を遮るための遮光部200とを備えている。
ハウジング66には、図5に示すように、ヘッドライトバルブ用リフレクタ部100の後側に配線支持部182が一体に成形されている。この配線180は、ヘッドライトバルブ68やポジションバルブ70等に接続されるものである。この配線支持部182は、ハウジング66の左右2箇所に対称に設けられており、ねじ等を用いずに配線180を上方から押し込んでクラップすることができるようになっている。
なお、ヘッドライトバルブ用リフレクタ部100にも、その内部が曇らないように同様の構造を有している。
本実施の形態では、遮光部200およびダイヤモンドカット65を略三角形状にしているが、縦壁部74を形成することによってポジションライトが細長で、かつ、その外形状が鮮明に見えるようなものであれば、他の形状、例えば、四角形以上の角を有する形状であってもかまわない。また、多角形でなく、丸みを帯びた形状であってもかまわない。
10 車体フレーム
11 ヘッドパイプ
18 前輪
21 後輪
25 前照灯
37 車体カバー
37B フロントトップカバー
62 ウインカー
64 レンズ
65 ダイヤモンドカット
66 ハウジング
66A 上辺部
66B 下辺部
66C 側辺部
68 ヘッドライトバルブ
70 ポジションバルブ
70a 上球体部
72 仕切り部
74 縦壁部
100 ヘッドライトバルブ用リフレクタ部
102 屈曲線
104 リフレクタ
106 底部
150 ポジションバルブ用リフレクタ部
152 上壁面
153 換気用穴部
154 リフレクタ
156 底部
158 空気穴
160 ラビリンスパイプ
182 配線支持部
200 遮光部
Claims (7)
- ヘッドライトバルブ(68)と、
ポジションバルブ(70)と、
前記ヘッドライトバルブ(68)及び前記ポジションバルブ(70)を収容するハウジング(66)と、
前記ヘッドライトバルブ(68)及び前記ポジションバルブ(70)の前方に設けられ、光を透過するレンズ(64)とを備え、
前記ハウジング(66)は、ヘッドライトバルブ(68)の光を反射するヘッドライトバルブ用リフレクタ部(100)と、当該ヘッドライトバルブ用リフレクタ部(100)と仕切り部(72)を介して別室になるポジションバルブ用リフレクタ部(150)とを備えた車両の前照灯構造において、
前記仕切り部(72)を前記レンズ(64)まで延出するとともに、ポジションバルブ(70)の前方に位置させ、前記ポジションバルブ用リフレクタ部(150)として機能する縦壁部(74)を前記ハウジング(66)に一体に設け、
前記ポジションバルブ(70)は、その軸線(X)が車体前方へ昇り傾斜となるように上下方向に沿わせて配置され、前記ポジションバルブ(70)の後方のハウジング(66)には前記ポジションバルブ用リフレクタ部(150)として機能する上壁面(152)が設けられ、
前記ポジションバルブ(70)は、正面視で前記縦壁部(74)に一部を覆われると共に、ポジションバルブ(70)の上部が露出する態様で配置されていることを特徴とする車両の前照灯構造。 - 前記縦壁部(74)を水平方向に対して車体前方へ昇り傾斜となるように形成したことを特徴とする請求項1に記載の車両の前照灯構造。
- 前記縦壁部(74)と前記仕切り部(72)との間に、光を遮る空間である遮光部(200)を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の車両の前照灯構造。
- 前記ポジションバルブ(70)は、前記軸線(X)が車体前方へ昇り傾斜となるように上下方向に沿わせて前記ポジションバルブ用リフレクタ部(150)に収容されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1つに記載の車両の前照灯構造。
- 前記レンズ(64)には、前記縦壁部(74)よりも前方の部分で、ダイヤモンドカット(65)が施されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1つに記載の車両の前照灯構造。
- 前記ポジションバルブ用リフレクタ部(150)にラビリンス構造の空気穴(158)を設けたことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1つに記載の車両の前照灯構造。
- 前記ポジションバルブ(70)は、当該ポジションバルブ(70)の先端部の上球体部(70a)の約半分が正面視で見える角度まで前記軸線(X)が前傾していることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1つに記載の車両の前照灯構造。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008079701A JP5259221B2 (ja) | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 車両の前照灯構造 |
| BRPI0900687A BRPI0900687B8 (pt) | 2008-03-26 | 2009-02-18 | estrutura de farol de um veículo |
| CN2009100067782A CN101545603B (zh) | 2008-03-26 | 2009-02-27 | 车辆的前照灯结构 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008079701A JP5259221B2 (ja) | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 車両の前照灯構造 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2009238412A JP2009238412A (ja) | 2009-10-15 |
| JP5259221B2 true JP5259221B2 (ja) | 2013-08-07 |
Family
ID=41192896
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2008079701A Expired - Fee Related JP5259221B2 (ja) | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 車両の前照灯構造 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5259221B2 (ja) |
| CN (1) | CN101545603B (ja) |
| BR (1) | BRPI0900687B8 (ja) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102233918B (zh) * | 2010-05-07 | 2014-06-11 | 本田技研工业株式会社 | 机动二轮车的前照灯装置 |
| JP5557607B2 (ja) * | 2010-06-10 | 2014-07-23 | 本田技研工業株式会社 | 灯火器及び自動二輪車 |
| JP5808924B2 (ja) | 2011-03-18 | 2015-11-10 | 本田技研工業株式会社 | 前照灯装置 |
| JP5908813B2 (ja) * | 2012-09-13 | 2016-04-26 | 川崎重工業株式会社 | 乗物用ヘッドランプユニット |
| JP6057772B2 (ja) * | 2013-02-21 | 2017-01-11 | 本田技研工業株式会社 | 灯火器 |
| CN103868023A (zh) * | 2014-04-02 | 2014-06-18 | 宁波山力士户外用品有限公司 | 一种反光杯及具有该反光杯的自行车灯 |
| CN115303174A (zh) * | 2022-08-31 | 2022-11-08 | 长城汽车股份有限公司 | 车灯控制方法、车灯控制装置和车辆 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2544592Y2 (ja) * | 1991-10-29 | 1997-08-20 | スタンレー電気株式会社 | 車幅灯内蔵前照灯 |
| JPH1083702A (ja) * | 1996-09-06 | 1998-03-31 | Koito Mfg Co Ltd | 車輌用灯具 |
| JP3089006B1 (ja) * | 1999-09-24 | 2000-09-18 | 川崎重工業株式会社 | 自動二輪車のランプユニット |
| JP4188131B2 (ja) * | 2003-04-24 | 2008-11-26 | 本田技研工業株式会社 | コンビネーションランプ |
| JP4196284B2 (ja) * | 2004-01-23 | 2008-12-17 | 日通商事株式会社 | 車両用表示灯 |
| JP4417230B2 (ja) * | 2004-11-24 | 2010-02-17 | 本田技研工業株式会社 | 車両用灯火装置 |
-
2008
- 2008-03-26 JP JP2008079701A patent/JP5259221B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-02-18 BR BRPI0900687A patent/BRPI0900687B8/pt not_active IP Right Cessation
- 2009-02-27 CN CN2009100067782A patent/CN101545603B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| BRPI0900687A2 (pt) | 2010-01-19 |
| CN101545603A (zh) | 2009-09-30 |
| BRPI0900687B8 (pt) | 2020-01-14 |
| BRPI0900687B1 (pt) | 2019-01-08 |
| CN101545603B (zh) | 2011-03-09 |
| JP2009238412A (ja) | 2009-10-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5259221B2 (ja) | 車両の前照灯構造 | |
| TWI389811B (zh) | Locomotive position lights and lighting fixtures | |
| JP5551979B2 (ja) | 乗物のランプ配置構造 | |
| CN103672660B (zh) | 交通工具用前照灯单元 | |
| CN107406113B (zh) | 包括辅助照明的照明装置结构 | |
| JP4594205B2 (ja) | 車両用方向指示灯 | |
| JP2011111029A (ja) | 鞍乗り型車両の前部灯火器構造 | |
| JP2016005942A (ja) | 鞍乗型車両 | |
| US7314297B2 (en) | Vehicle lighting apparatus | |
| JP2012240425A (ja) | テールライトユニット及び自動二輪車 | |
| JP5538787B2 (ja) | テールランプユニット | |
| CN107878622B (zh) | 跨骑型车辆的导风构造 | |
| JP4630780B2 (ja) | スクータ型車両の灯火器配置構造 | |
| JP2009158409A (ja) | 車両用灯火器構造 | |
| CN100572898C (zh) | 机动二轮车的后组合灯构造 | |
| JP4853913B2 (ja) | 自動二輪車の前照灯装置 | |
| JP7157721B2 (ja) | ヘッドライト装置 | |
| TWI572512B (zh) | 跨坐型車輛 | |
| JP6827525B2 (ja) | 鞍乗型車両の灯火装置 | |
| CN1975243B (zh) | 照明装置 | |
| JP4545555B2 (ja) | 自動二輪車のウインカ構造 | |
| TWI584988B (zh) | Speed Keda vehicles | |
| JP6885982B2 (ja) | 鞍乗り型車両のヘッドライト構造 | |
| JP6894696B2 (ja) | 鞍乗型車両 | |
| JP2006199292A (ja) | スクータ型自動二輪車 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20101126 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120416 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120424 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120622 |
|
| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20120622 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120821 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121010 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130416 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130424 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160502 Year of fee payment: 3 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |