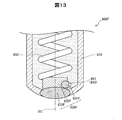JP6280853B2 - グロープラグ - Google Patents
グロープラグ Download PDFInfo
- Publication number
- JP6280853B2 JP6280853B2 JP2014206153A JP2014206153A JP6280853B2 JP 6280853 B2 JP6280853 B2 JP 6280853B2 JP 2014206153 A JP2014206153 A JP 2014206153A JP 2014206153 A JP2014206153 A JP 2014206153A JP 6280853 B2 JP6280853 B2 JP 6280853B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- end side
- glow plug
- rear end
- sheath tube
- chromium
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23Q—IGNITION; EXTINGUISHING-DEVICES
- F23Q7/00—Incandescent ignition; Igniters using electrically-produced heat, e.g. lighters for cigarettes; Electrically-heated glowing plugs
- F23Q7/001—Glowing plugs for internal-combustion engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23Q—IGNITION; EXTINGUISHING-DEVICES
- F23Q7/00—Incandescent ignition; Igniters using electrically-produced heat, e.g. lighters for cigarettes; Electrically-heated glowing plugs
- F23Q7/001—Glowing plugs for internal-combustion engines
- F23Q2007/004—Manufacturing or assembling methods
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Resistance Heating (AREA)
Description
本発明の一形態によれば、筒状を成す筒状体と;前記筒状体の内側に設けられ、通電によって発熱する発熱体と;前記筒状体と前記発熱体との間を接続する接続部であって、前記発熱体との溶接によって形成された溶融部を有する接続部とを備えるグロープラグが提供される。このグロープラグにおいて、前記発熱体は、タングステン(W)またはモリブデン(Mo)から主に成り、前記溶融部における前記発熱体との界面から少なくとも20μmまでの部位は、ニッケル(Ni)を含有しない。この形態によれば、溶融部における耐熱性を向上させることができる。その結果、グロープラグの耐久性を向上させることができる。
A1.グロープラグの構成
図1は、グロープラグ10の構成を示す説明図である。図1には、グロープラグ10の中心軸SCを境界として、紙面右側にグロープラグ10の外観形状が図示され、紙面左側にグロープラグ10の断面形状が図示されている。本実施形態の説明では、グロープラグ10における図1の紙面下側を「先端側」といい、図1の紙面上側を「後端側」という。
図6は、グロープラグ10の製造方法を示す工程図である。図7は、グロープラグ10を製造する様子を示す説明図である。
図8は、タングステン(W)から主に成る発熱コイル850を備えるグロープラグの耐久性を評価した結果を示す表である。図9は、モリブデン(Mo)から主に成る発熱コイル850を備えるグロープラグの耐久性を評価した結果を示す表である。
・試料A1,B1:鉄(Fe)を主成分として、18質量%のクロム(Cr)を含有するステンレス鋼(SUS430)
・試料A2,B2:鉄(Fe)を主成分として、18質量%のクロム(Cr)と、3質量%のアルミニウム(Al)を含有するステンレス鋼(SUH21)
・試料A3,B3:鉄(Fe)を主成分として、12質量%のクロム(Cr)を含有するステンレス鋼(SUS403)
・試料A4,B4:鉄(Fe)を主成分として、10質量%のクロム(Cr)を含有するステンレス鋼
・試料A5,B5:ニッケル(Ni)を主成分として、23質量%のクロム(Cr)と、14質量%の鉄(Fe)と、1.4質量%のアルミニウム(Al)とを含有するニッケル基合金(インコネル601)
・試料A6,B6:鉄(Fe)を主成分として、26質量%のクロム(Cr)と、22質量%のニッケル(Ni)を含有するステンレス鋼(SUS310s)
(手順1)シースチューブ810の外側表面における先端Aから中心軸SCに沿って2mmの位置MLが1200℃になるように、試料であるグロープラグに通電
(手順2)シースチューブ810の位置MLが1200℃になった後、グロープラグに対する通電を継続することによって、シースチューブ810の位置MLが1200℃となる状態を10分間維持
(手順3)シースチューブ810の位置MLが1200℃となる状態を10分間維持した後、グロープラグに対する通電を遮断し、送風によってシースチューブ810を2分間冷却
◎(優):10000≦断線サイクル
○(良):8000≦断線サイクル<10000
△(可):6000≦断線サイクル<8000
×(不可):断線サイクル<6000
以上説明した実施形態によれば、発熱コイル850は、タングステン(W)またはモリブデン(Mo)から主に成り、後端側溶融部831における発熱コイル850との界面839から少なくとも20μmまでの部位は、ニッケル(Ni)を含有しないため、後端側溶融部831における耐熱性を向上させることができる。その結果、グロープラグ10の耐久性を向上させることができる。
本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部または全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部または全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
110…Oリング
120…絶縁ブッシュ
130…リング
140…ナット
200…中軸
210…先端部
290…後端部
500…主体金具
510…軸孔
520…工具係合部
540…ネジ部
600…パッキン
800,800B〜800F…シースヒータ
810…シースチューブ
811…先端部
811h…開口
819…後端部
830,830B〜830F…接続部
831,831C〜831F…後端側溶融部
832,832C〜832F…先端側溶融部
835…線材部
835C〜835F…鋲材部
835p…線材
839…界面
850…発熱コイル
851…先端部
859…後端部
870…絶縁粉末
Claims (4)
- 筒状を成す筒状体と、
前記筒状体の内側に設けられ、通電によって発熱する発熱体と、
前記筒状体と前記発熱体との間を接続する接続部であって、前記発熱体との溶接によって形成された溶融部を有する接続部と
を備えるグロープラグであって、
前記発熱体は、タングステン(W)またはモリブデン(Mo)から主に成り、
前記溶融部における前記発熱体との界面から少なくとも20μmまでの部位は、ニッケル(Ni)を含有しないことを特徴とするグロープラグ。 - 前記接続部は、鉄(Fe)から主に成るとともにクロム(Cr)を含有する部位と、クロム(Cr)から主に成る部位との少なくとも一方の部位を有する、請求項1に記載のグロープラグ。
- 請求項1または請求項2に記載のグロープラグであって、
前記筒状体は、ニッケル(Ni)または鉄(Fe)から主に成るとともに、先端側に位置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記中心軸に沿って100μmまでの部位に含まれるクロム(Cr)の含有量は、13質量%以上である、グロープラグ。 - 請求項1または請求項2に記載のグロープラグであって、
前記筒状体は、ニッケル(Ni)または鉄(Fe)から主に成るとともに、先端側に位置する先端部と、後端側に位置する後端部とを備え、
前記筒状体の中心軸上に位置する前記先端部の部位のうち、前記筒状体の外側から前記中心軸に沿って100μmまでの部位に含まれるクロム(Cr)の含有量は、18質量%以上である、グロープラグ。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014206153A JP6280853B2 (ja) | 2013-10-15 | 2014-10-07 | グロープラグ |
| EP14188920.4A EP2863126B1 (en) | 2013-10-15 | 2014-10-15 | Glow plug |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013214848 | 2013-10-15 | ||
| JP2013214848 | 2013-10-15 | ||
| JP2014206153A JP6280853B2 (ja) | 2013-10-15 | 2014-10-07 | グロープラグ |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2015099008A JP2015099008A (ja) | 2015-05-28 |
| JP2015099008A5 JP2015099008A5 (ja) | 2017-07-27 |
| JP6280853B2 true JP6280853B2 (ja) | 2018-02-14 |
Family
ID=52006790
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014206153A Expired - Fee Related JP6280853B2 (ja) | 2013-10-15 | 2014-10-07 | グロープラグ |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2863126B1 (ja) |
| JP (1) | JP6280853B2 (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6771964B2 (ja) * | 2015-10-30 | 2020-10-21 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグの製造方法及びグロープラグ |
| JP6587501B2 (ja) * | 2015-10-30 | 2019-10-09 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグ |
| JP6796957B2 (ja) * | 2016-06-22 | 2020-12-09 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグ |
| JP6781599B2 (ja) * | 2016-09-26 | 2020-11-04 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグ |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5251589A (en) * | 1992-03-16 | 1993-10-12 | Wellman Automotive Products, Inc. | Hot tip glow plug and method for making |
| JP2806195B2 (ja) * | 1993-01-14 | 1998-09-30 | 株式会社デンソー | グロープラグ |
| DE19907229C2 (de) * | 1999-02-19 | 2003-06-12 | Beru Ag | Stabglühkerze |
| JP2006317145A (ja) * | 2006-07-24 | 2006-11-24 | Ngk Spark Plug Co Ltd | グロープラグ及びその製造方法 |
| US20090184101A1 (en) * | 2007-12-17 | 2009-07-23 | John Hoffman | Sheathed glow plug |
| JP2009158431A (ja) * | 2007-12-28 | 2009-07-16 | Ngk Spark Plug Co Ltd | シースヒータ及びグロープラグ |
| JP5255706B2 (ja) * | 2010-06-22 | 2013-08-07 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグ及びその製造方法、並びに、加熱装置 |
| JP5437956B2 (ja) * | 2010-09-06 | 2014-03-12 | 日本特殊陶業株式会社 | グロープラグ及びその製造方法 |
-
2014
- 2014-10-07 JP JP2014206153A patent/JP6280853B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2014-10-15 EP EP14188920.4A patent/EP2863126B1/en not_active Not-in-force
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2015099008A (ja) | 2015-05-28 |
| EP2863126A1 (en) | 2015-04-22 |
| EP2863126B1 (en) | 2017-04-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6280853B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP2015078784A (ja) | グロープラグ | |
| JP2016075468A (ja) | グロープラグ | |
| JP5584370B2 (ja) | グロープラグ | |
| CN103931065A (zh) | 火花塞 | |
| JP6525616B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6392000B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6393124B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP2016148506A (ja) | グロープラグ及びその製造方法 | |
| JP6279925B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP4885837B2 (ja) | スパークプラグの製造方法 | |
| JP6537893B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6960848B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6587501B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6592372B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP2014137170A (ja) | グロープラグの製造方法およびグロープラグ | |
| JP6374651B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6965153B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6781599B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP2008204917A (ja) | スパークプラグ及びスパークプラグの製造方法 | |
| JP6796957B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6746453B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6794176B2 (ja) | グロープラグ | |
| JP6960394B2 (ja) | グロープラグ及びグロープラグの製造方法 | |
| EP3396249B1 (en) | Glow plug |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170303 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170613 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20171211 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180109 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180122 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6280853 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |