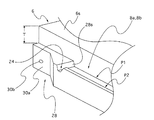JP2014173291A - 境界ブロック - Google Patents
境界ブロック Download PDFInfo
- Publication number
- JP2014173291A JP2014173291A JP2013045482A JP2013045482A JP2014173291A JP 2014173291 A JP2014173291 A JP 2014173291A JP 2013045482 A JP2013045482 A JP 2013045482A JP 2013045482 A JP2013045482 A JP 2013045482A JP 2014173291 A JP2014173291 A JP 2014173291A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- road
- boundary
- boundary block
- block
- engaging
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Road Paving Structures (AREA)
Abstract
【解決手段】ブロック本体4の一部を道路に向けて突出させた突出片6には、道路の舗装構造が一部入り込んで係合することで、当該道路との位置関係を一定に維持させる係合部8a,8b(凹部P1、凸部P2)が設けられ、敷設以前の境界ブロック2において、表面(例えば、ブロック本体4の表面4s、各突出片6の表面6s)に付着した異物(例えば、水や塵埃など)は、凹部P1に沿って集めて除去可能であり、敷設以後の境界ブロック2において、道路の舗装構造の一部が凸部P2を超えて凹部P1に入り込んで係合することで、当該道路と境界ブロック2とを互いに隙間無く隣接した状態に維持可能である。
【選択図】図1
Description
本発明において、係合部は、凸部を一部切り欠いて凹部と連通させた連通部をさらに備えて構成されており、道路との境界に敷設される以前の当該境界ブロックにおいて、その表面に付着した異物は、当該表面の清掃処理に際し、係合部の凹部に沿って集められ、連通部を介して除去することが可能である。
本発明では、係合部において、その凹部を構成する底面は、凸部側に向って下り勾配を成して構成されており、道路との境界に敷設される以前の当該境界ブロックにおいて、その表面の清掃処理に際し、係合部の凹部に沿って集められた異物は、当該凹部の底面に沿って自由落下し、連通部を介して除去される。
本発明では、係合部において、その連通部を構成する底面は、凹部の底面から連続した下り勾配を成して構成されている。
本発明において、境界ブロックの構成としては、当該境界ブロックの用途に応じて道路との間に介在させることが可能であって、かつ、一方側が突出片の係合部に係合すると共に、他方側に当該係合部と同一の係合部が設けられたアタッチメント構造をさらに備えており、当該アタッチメント構造としては、プレキャスト工法により予め所定形状に材料を固化させたもの、或いは、現場打ち工法により所定形状に材料を固化させたものの双方が含まれる。
4 ブロック本体
4s ブロック本体の表面
6 突出片
6s 突出片の表面
8a,8b 係合部
P1 凹部
P2 凸部
Claims (5)
- 所定の舗装構造によって構築される道路との境界に沿って配設される境界ブロックであって、
道路との境界に沿って連続して立ち上げられた状態に位置付けられるブロック本体と、
ブロック本体の一部を道路に向けて突出させて構成され、当該道路に沿って連続的に位置付けられる突出片とを有し、
突出片の突出端には、道路の舗装構造が一部入り込んで係合することで、当該道路との位置関係を一定に維持させる係合部が設けられていると共に、
係合部は、道路に沿って連続して窪ませた凹部と、当該凹部よりも道路側に位置し、当該道路に沿って連続して突設させた凸部とを備えて構成されており、
道路との境界に敷設される以前の当該境界ブロックにおいて、その表面に付着した異物は、当該表面の清掃処理に際し、係合部の凹部に沿って集めて除去することが可能であると共に、
道路との境界に敷設された以後の当該境界ブロックにおいて、道路の舗装構造の一部が凸部を超えて凹部に入り込んで係合することで、当該道路と境界ブロックとを互いに隙間無く隣接した状態に維持させることが可能であることを特徴とする境界ブロック。 - 係合部は、凸部を一部切り欠いて凹部と連通させた連通部をさらに備えて構成されており、
道路との境界に敷設される以前の当該境界ブロックにおいて、その表面に付着した異物は、当該表面の清掃処理に際し、係合部の凹部に沿って集められ、連通部を介して除去することが可能であることを特徴とする請求項1に記載の境界ブロック。 - 係合部において、その凹部を構成する底面は、凸部側に向って下り勾配を成して構成されており、
道路との境界に敷設される以前の当該境界ブロックにおいて、その表面の清掃処理に際し、係合部の凹部に沿って集められた異物は、当該凹部の底面に沿って自由落下し、連通部を介して除去されることを特徴とする請求項2に記載の境界ブロック。 - 係合部において、その連通部を構成する底面は、凹部の底面から連続した下り勾配を成して構成されていることを特徴とする請求項3に記載の境界ブロック。
- 境界ブロックの構成としては、当該境界ブロックの用途に応じて道路との間に介在させることが可能であって、かつ、一方側が突出片の係合部に係合すると共に、他方側に当該係合部と同一の係合部が設けられたアタッチメント構造をさらに備えており、
当該アタッチメント構造としては、プレキャスト工法により予め所定形状に材料を固化させたもの、或いは、現場打ち工法により所定形状に材料を固化させたものの双方が含まれることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の境界ブロック。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013045482A JP5893577B2 (ja) | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 境界ブロック |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013045482A JP5893577B2 (ja) | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 境界ブロック |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2015223640A Division JP6144319B2 (ja) | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 境界ブロック |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014173291A true JP2014173291A (ja) | 2014-09-22 |
| JP5893577B2 JP5893577B2 (ja) | 2016-03-23 |
Family
ID=51694826
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2013045482A Active JP5893577B2 (ja) | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 境界ブロック |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5893577B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017031780A (ja) * | 2015-07-28 | 2017-02-09 | 正剛 大嶋 | エプロンにアスファルト舗装するプレキャストコンクリート街渠用l形ブロック |
| JP2018003353A (ja) * | 2016-06-29 | 2018-01-11 | 株式会社ニッコン | 歩車道境界ブロック |
Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56107075U (ja) * | 1980-01-18 | 1981-08-20 | ||
| JPS6140405U (ja) * | 1984-08-20 | 1986-03-14 | 三井鋼材産業株式会社 | 縁石 |
| JPH0348080U (ja) * | 1989-09-14 | 1991-05-08 | ||
| JPH0712503U (ja) * | 1993-08-04 | 1995-03-03 | 揖斐川コンクリート工業株式会社 | 縁石用コンクリートブロック |
| JPH07243748A (ja) * | 1994-03-04 | 1995-09-19 | Hoshizaki Electric Co Ltd | 冷蔵庫等における冷凍機構の配設構造 |
| JPH08113906A (ja) * | 1994-10-13 | 1996-05-07 | Yutaka Matsumoto | コンクリートブロックとコンクリート壁およびコンクリート壁の製造のための部材 |
| JP3024381U (ja) * | 1995-11-07 | 1996-05-21 | 浩 大野 | 縁 石 |
| JPH1037115A (ja) * | 1996-07-22 | 1998-02-10 | Minami:Kk | 草止めエプロンブロック |
| JPH1113199A (ja) * | 1997-06-24 | 1999-01-19 | Hetsugi Doboku Riyokuchi Kensetsu Kk | コンクリート境界ブロック |
| JP2006152623A (ja) * | 2004-11-26 | 2006-06-15 | Sekisui Chem Co Ltd | 床の集塵装置 |
| JP2007291825A (ja) * | 2005-09-26 | 2007-11-08 | Shigeru Ishikawa | 構造物の目地の構造 |
| JP2009285637A (ja) * | 2008-05-31 | 2009-12-10 | Masaru Okuno | 塗装ブース |
| JP3181117U (ja) * | 2012-11-09 | 2013-01-24 | 松岡コンクリート工業株式会社 | コンクリート製ブロック |
-
2013
- 2013-03-07 JP JP2013045482A patent/JP5893577B2/ja active Active
Patent Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56107075U (ja) * | 1980-01-18 | 1981-08-20 | ||
| JPS6140405U (ja) * | 1984-08-20 | 1986-03-14 | 三井鋼材産業株式会社 | 縁石 |
| JPH0348080U (ja) * | 1989-09-14 | 1991-05-08 | ||
| JPH0712503U (ja) * | 1993-08-04 | 1995-03-03 | 揖斐川コンクリート工業株式会社 | 縁石用コンクリートブロック |
| JPH07243748A (ja) * | 1994-03-04 | 1995-09-19 | Hoshizaki Electric Co Ltd | 冷蔵庫等における冷凍機構の配設構造 |
| JPH08113906A (ja) * | 1994-10-13 | 1996-05-07 | Yutaka Matsumoto | コンクリートブロックとコンクリート壁およびコンクリート壁の製造のための部材 |
| JP3024381U (ja) * | 1995-11-07 | 1996-05-21 | 浩 大野 | 縁 石 |
| JPH1037115A (ja) * | 1996-07-22 | 1998-02-10 | Minami:Kk | 草止めエプロンブロック |
| JPH1113199A (ja) * | 1997-06-24 | 1999-01-19 | Hetsugi Doboku Riyokuchi Kensetsu Kk | コンクリート境界ブロック |
| JP2006152623A (ja) * | 2004-11-26 | 2006-06-15 | Sekisui Chem Co Ltd | 床の集塵装置 |
| JP2007291825A (ja) * | 2005-09-26 | 2007-11-08 | Shigeru Ishikawa | 構造物の目地の構造 |
| JP2009285637A (ja) * | 2008-05-31 | 2009-12-10 | Masaru Okuno | 塗装ブース |
| JP3181117U (ja) * | 2012-11-09 | 2013-01-24 | 松岡コンクリート工業株式会社 | コンクリート製ブロック |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017031780A (ja) * | 2015-07-28 | 2017-02-09 | 正剛 大嶋 | エプロンにアスファルト舗装するプレキャストコンクリート街渠用l形ブロック |
| JP2018003353A (ja) * | 2016-06-29 | 2018-01-11 | 株式会社ニッコン | 歩車道境界ブロック |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5893577B2 (ja) | 2016-03-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2014066057A (ja) | 舗装道路用側溝 | |
| JP6074378B2 (ja) | 伸縮装置の取替え方法と仮設覆工版構造 | |
| JP5893577B2 (ja) | 境界ブロック | |
| JP6144319B2 (ja) | 境界ブロック | |
| KR101047930B1 (ko) | 도로용 블록의 시공구조 및 도로용 블록의 시공방법 | |
| JP2011106208A (ja) | 平板ブロック及び平板ブロック用枠体 | |
| JP5370634B2 (ja) | 音響道路の施工方法 | |
| JP2518390Y2 (ja) | 張出歩道ブロック及びそれを用いた張出歩道構造 | |
| KR100981323B1 (ko) | 프리캐스트 블록 및 이를 이용하는 프리캐스트 구조물 | |
| JP5318257B1 (ja) | コンクリート製張出歩道構成体及び該構成体を用いた張出歩道を有する車道の建設方法 | |
| JP5565821B1 (ja) | 舗装構造物 | |
| JP4020918B2 (ja) | 桁橋の架橋構造 | |
| KR100723646B1 (ko) | 옹벽격자블록 | |
| JP3022195U (ja) | 排水路合設歩車道境界ブロック | |
| JP2014134018A (ja) | 歩車道境界用縁石ブロック | |
| JP6758840B2 (ja) | 縁石一体型側溝ブロックおよびその製造方法 | |
| JP3112511U (ja) | 道路仮復旧用敷設ブロックマット | |
| JP7522404B1 (ja) | 防草構造及び防草用部材 | |
| KR100443620B1 (ko) | 차도 인도 경계석 | |
| CN214168616U (zh) | 一种城市干道节点的道路 | |
| JP5176201B2 (ja) | 透水性ブロック舗装用枠体 | |
| KR200212558Y1 (ko) | 인터록킹형 도로 경계블록 | |
| KR200248495Y1 (ko) | 차도 인도 경계석 | |
| KR101025496B1 (ko) | 블록형 아스팔트 | |
| JP3066227U (ja) | コンクリ―ト製排水溝ブロックの蓋 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150129 |
|
| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20150714 |
|
| A975 | Report on accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20150903 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150915 |
|
| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20150918 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151116 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160126 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160224 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5893577 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
| R360 | Written notification for declining of transfer of rights |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |
|
| R360 | Written notification for declining of transfer of rights |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |
|
| R371 | Transfer withdrawn |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |