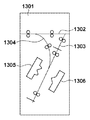JP6366375B2 - シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム - Google Patents
シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP6366375B2 JP6366375B2 JP2014124681A JP2014124681A JP6366375B2 JP 6366375 B2 JP6366375 B2 JP 6366375B2 JP 2014124681 A JP2014124681 A JP 2014124681A JP 2014124681 A JP2014124681 A JP 2014124681A JP 6366375 B2 JP6366375 B2 JP 6366375B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- creasing
- sheet
- setting
- image forming
- paper
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Folding Of Thin Sheet-Like Materials, Special Discharging Devices, And Others (AREA)
Description
特許文献1は、筋つけを行う際に、用紙搬送方向の上流側と下流側とに配置された把持部によって用紙に張力を与え、撓みを矯正する技術が提案されている。これにより、用紙の厚みにより折り部に膨らみが発生せず、生産性を低下させることなく、折り部の折り高さを低くすることができる。
<画像形成システムの構成>
まず、図1を参照して、本発明の実施形態に係る画像形成システムの構成について説明する。本画像形成システムは、以下の構成を有する。図1において、101は画像形成装置であり、102が画像定着装置である。画像形成装置101には給紙装置120が接続されている。給紙装置は複数接続することが可能であり、給紙装置120には別の給紙装置121が接続されている。画像定着装置102には、シート処理装置の一例である筋つけ装置151が接続されており、印刷後の用紙(シート)に対して筋つけを行う。筋つけ装置151には。排紙装置134が接続されている。なお、ここでは、画像形成装置101と、筋つけ装置151とを個別の装置として説明するが、本発明はこれに限定されず、画像形成装置101が筋つけ装置151を含む構成であってもよい。
次に、図2を参照して、画像形成装置101のメインコントローラ201の制御構成について説明する。画像形成装置101のメインコントローラ201は、CPU205、RAM206、操作部I/F207、ネットワークI/F208、モデム209、ROM210、及びHDD211を備える。また、メインコントローラ201は、イメージバスI/F213を介し、RIPI/F214、データ圧縮部215、デバイスI/F216、及び画像処理部217を備える。また、212はCPUバスであり、228はイメージバスである。給紙装置120、給紙装置121、筋つけ装置151、排紙装置134は、データバス221を介し接続さており、メインコントローラ201が動作の制御を行うことができる。ネットワークI/F208には、外部機器とネットワークによって接続を行うためのネットワークケーブル203が接続される。モデム209には、外部機器と電話回線によって接続を行うための回線ケーブル204が接続される。
次に、図3乃至図6を参照して、筋つけについて説明する。図3は筋つけ前の用紙301と筋つけ後の用紙303を横から見た図を示す。筋つけ後の用紙303には、筋つけ302が施されている。図3に示す通り、筋つけ前の用紙の全長304と比較し、筋つけ後の用紙303の全長305は、短くなっている。
次に、図15を参照して、本実施形態における画像形成処理、筋つけ処理及び後処理の処理手順について説明する。以下で説明する処理は、画像形成装置101のメインコントローラ201のCPU205がROM210に格納されたプログラムに従って行う。なお、以下で説明する処理は、画像形成装置101のCPU205によって実現される場合について説明するが、本発明はこれに限定されず、シート処理装置である筋つけ装置151の制御部によって実現されてもよい。
次に、図7を参照して、CPU205が筋つけ時に行う処理の手順について説明する。以下で説明する処理は、画像形成装置101のメインコントローラ201のCPU205がROM210に格納されたプログラムに従って行う。なお、以下で説明する処理は、画像形成装置101のCPU205によって実現される場合について説明するが、本発明はこれに限定されず、シート処理装置である筋つけ装置151の制御部によって実現されてもよい。
次に、図8を参照して、筋つけ位置を用紙先端側から測定する場合の筋つけ位置について説明する。ユーザから設定された筋つけ位置として、筋つけ位置801は用紙先端から70.0mm、筋つけ位置802は用紙先端から140.0mm、筋つけ位置803は用紙先端から210.0mmの位置とする。筋つけの順序を、筋つけ位置801、筋つけ位置802、筋つけ位置803の順に行う場合について説明する。
以下では、本発明の第2の実施形態について説明する。上記第1の実施形態では、筋つけ位置の制御が用紙先端から測定する場合の処理の流れを説明したが、本実施形態では、筋つけ位置を用紙中央から測定する場合について説明する。二つ折りの製本時など、折り処理や筋つけ処理は、用紙の中央に施される場合がある。用紙中央から筋つけ位置を制御することで、用紙先端から筋つけ位置を制御した場合の搬送距離を計算する際の誤差を低減できる。
まず、図13を参照して、本実施形態に係る筋つけ装置について説明する。本実施形態に係る筋つけ装置1301は、図1に示す筋つけ装置151の別の形態である。筋つけ装置1301において、用紙搬送路1303を通って搬送された用紙は、凸型の筋つけダイ1306と、凹型の筋つけダイ1305で用紙を挟むことによって、折り筋が付けられる。筋つけが行われた用紙は用紙搬送路1304を通って、排紙装置134に搬送される。用紙に筋つけが行われない場合には、用紙搬送路1302を通って、排紙装置134に搬送される。
本実施形態において、画像形成処理、筋つけ処理及び後処理の処理手順については、上記第1の実施形態で説明した図15のフローチャートと同様であるため説明を省略する。筋つけ処理の手順については図7に示すフローチャート同様であるが、本実施形態では、S706の判定で、筋つけ位置を用紙中央からの距離で測定すると判定するため、S710に進む。その他の処理については同様であるため重複する説明は省略する。なお、以下で説明する処理は、画像形成装置101のCPU205によって実現される場合について説明するが、本発明はこれに限定されず、シート処理装置である筋つけ装置151の制御部によって実現されてもよい。
次に、図9を参照して、本実施形態に係る筋つけ位置を用紙中央から測定する場合の筋つけ位置について説明する。ユーザから設定された筋つけ位置として、筋つけ位置901は用紙中央から+10.0mm、筋つけ位置902は用紙中央から0.0mm、筋つけ位置903は用紙中央から−10.0mmの位置とする。筋つけの順序を、筋つけ位置902、筋つけ位置901、筋つけ位置903の順に行う場合について説明する。
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
Claims (13)
- シート処理装置であって、
画像形成されたシートに筋をつける筋つけ手段と、
前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行する、該シートの中の筋つけ位置を設定する設定手段と、
シートの種別に対応づけて、筋つけ処理を行った場合のシートの縮み量を記憶する記憶手段と、
前記設定手段によって1つのシートの中で複数の筋つけ位置に筋つけ処理の実行が設定されると、1回目の筋つけ位置については、前記設定手段によって設定された筋つけ位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させ、2回目以降の筋つけ処理については、前記設定手段によって設定された筋つけ位置を、当該シートの種別に対応づけて前記記憶手段に記憶されている縮み量に基づいて修正し、該修正した位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させる制御手段と
を備えることを特徴とするシート処理装置。 - 前記設定手段は、ユーザ入力に応じて、シートに対して1つ以上の筋つけ位置を設定することを特徴とする請求項1に記載のシート処理装置。
- 前記設定手段は、前記シート処理装置において搬送されるシートの搬送方向に対して該シートの先端からの距離で筋つけ位置を設定することを特徴とする請求項2に記載のシート処理装置。
- 前記制御手段は、
2回目以降の筋つけ処理において、既に完了した筋つけ処理の回数をAとし、前記記憶手段に記憶された縮み量をEとすると、A*Eの値だけ、前記設定手段によって設定された筋つけ位置を前記シートの先端側にずらすことを特徴とする請求項3に記載のシート処理装置。 - 前記設定手段は、前記シート処理装置において搬送されるシートの搬送方向に対して該シートの中央からの距離で筋つけ位置を設定することを特徴とする請求項2に記載のシート処理装置。
- 前記制御手段は、
2回目以降の筋つけ処理において、対象の筋つけ処理の筋つけ位置よりもシートの先端側で既に完了した筋つけ処理の回数をAとし、対象の筋つけ処理の筋つけ位置よりもシートの後端側で既に完了した筋つけ処理の回数をBとし、前記記憶手段に記憶された縮み量をEとすると、(A−B)*E/2の値だけ、前記設定手段によって設定された筋つけ位置を前記シートの先端側にずらすことを特徴とする請求項5に記載のシート処理装置。 - ユーザ入力に応じてシートの種別を設定する手段をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載のシート処理装置。
- 画像形成装置であって、
シートに画像を形成する画像形成手段と、
前記画像形成手段によって画像形成されたシートに筋をつける筋つけ手段と、
前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行する、該シートの中の筋つけ位置を設定する設定手段と、
シートの種別に対応づけて、筋つけ処理を行った場合のシートの縮み量を記憶する記憶手段と、
前記設定手段によって1つのシートの中で複数の筋つけ位置に筋つけ処理の実行が設定されると、1回目の筋つけ位置については、前記設定手段によって設定された筋つけ位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させ、2回目以降の筋つけ処理については、前記設定手段によって設定された筋つけ位置を、当該シートの種別に対応づけて前記記憶手段に記憶されている縮み量に基づいて修正し、該修正した位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させる制御手段と
を備えることを特徴とする画像形成装置。 - 画像形成されたシートに筋をつける筋つけ手段と、シートの種別に対応づけて、筋つけ処理を行った場合のシートの縮み量を記憶する記憶手段と、を備えるシート処理装置の制御方法であって、
設定手段が、前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行する、該シートの中の筋つけ位置を設定する設定工程と、
制御手段が、前記設定工程で1つのシートの中で複数の筋つけ位置に筋つけ処理の実行が設定されると、1回目の筋つけ位置については、前記設定工程で設定された筋つけ位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させ、2回目以降の筋つけ処理については、前記設定工程で設定された筋つけ位置を、当該シートの種別に対応づけて前記記憶手段に記憶されている縮み量に基づいて修正した位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させる制御工程と
を実行することを特徴とするシート処理装置の制御方法。 - シートに画像を形成する画像形成手段と、前記画像形成手段によって画像形成されたシートに筋をつける筋つけ手段と、シートの種別に対応づけて、筋つけ処理を行った場合のシートの縮み量を記憶する記憶手段と、を備える画像形成装置の制御方法であって、
設定手段が、前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行する、該シートの中の筋つけ位置を設定する設定工程と、
制御手段が、前記設定工程で1つのシートの中で複数の筋つけ位置に筋つけ処理の実行が設定されると、1回目の筋つけ位置については、前記設定工程で設定された筋つけ位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させ、2回目以降の筋つけ処理については、前記設定工程で設定された筋つけ位置を、当該シートの種別に対応づけて前記記憶手段に記憶されている縮み量に基づいて修正した位置において前記筋つけ手段によって筋つけ処理を実行させる制御工程と
を実行することを特徴とする画像形成装置の制御方法。 - 請求項1乃至7の何れか1項に記載のシート処理装置としてコンピュータを機能させるための該コンピュータで読み取り可能なプログラム。
- 請求項8に記載の画像形成装置としてコンピュータを機能させるための該コンピュータで読み取り可能なプログラム。
- シートに画像を形成する画像形成装置と、
前記画像形成装置に接続される、請求項1乃至7の何れか1項に記載のシート処理装置とを備える画像形成システム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014124681A JP6366375B2 (ja) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014124681A JP6366375B2 (ja) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2016003115A JP2016003115A (ja) | 2016-01-12 |
| JP2016003115A5 JP2016003115A5 (ja) | 2017-07-27 |
| JP6366375B2 true JP6366375B2 (ja) | 2018-08-01 |
Family
ID=55222688
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014124681A Expired - Fee Related JP6366375B2 (ja) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6366375B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6571834B2 (ja) * | 2017-06-16 | 2019-09-04 | キヤノンファインテックニスカ株式会社 | シート処理装置、画像形成システム、およびシート処理方法 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5471211B2 (ja) * | 2009-09-09 | 2014-04-16 | 株式会社リコー | 折り目付け装置、用紙処理装置、画像形成装置、及び折り目付け方法 |
| JP2012012220A (ja) * | 2010-06-04 | 2012-01-19 | Ricoh Co Ltd | 画像形成システム、用紙処理装置、及び折り処理方法 |
| JP5910038B2 (ja) * | 2011-11-30 | 2016-04-27 | コニカミノルタ株式会社 | 後処理方法及び後処理装置 |
| JP2013119451A (ja) * | 2011-12-07 | 2013-06-17 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成システム |
| JP2013121669A (ja) * | 2011-12-09 | 2013-06-20 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成方法及び画像形成装置 |
| JP2015003436A (ja) * | 2013-06-20 | 2015-01-08 | コニカミノルタ株式会社 | 製本装置及び製本システム |
-
2014
- 2014-06-17 JP JP2014124681A patent/JP6366375B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2016003115A (ja) | 2016-01-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9902586B2 (en) | Sheet processing apparatus capable of creating fold section, method of controlling the same, and storage medium | |
| CN107792716B (zh) | 后处理装置 | |
| US8905509B2 (en) | Printing apparatus | |
| US9298148B2 (en) | Printing apparatus, method of controlling printing apparatus, and storage medium | |
| JP6366375B2 (ja) | シート処理装置、画像形成装置、それらの制御方法、プログラム、及び画像形成システム | |
| US10747157B2 (en) | Image forming apparatus, image forming system, and non-transitory recording medium storing computer-readable program for image forming apparatus | |
| JP4752667B2 (ja) | 画像形成システム及びプログラム | |
| US9586431B2 (en) | Image forming system, image forming apparatus, finisher and method of controlling image forming system | |
| US8931774B2 (en) | Sheet processing apparatus and method, as well as controlling apparatus | |
| JP2016108090A (ja) | 画像形成システム、画像形成装置、後処理装置および搬送異常検出プログラム | |
| JP5772061B2 (ja) | 折り装置、画像形成システム、折り処理制御プログラム及び折り方法 | |
| US9682841B2 (en) | Sheet folding apparatus and image forming system | |
| JP2019064233A (ja) | 画像形成装置及び画像形成システム | |
| JP6593218B2 (ja) | 画像形成システム、画像形成装置、後処理装置、およびそれらの制御方法 | |
| JP4970182B2 (ja) | 製本装置及びこれを備えた画像形成システム | |
| US9802435B2 (en) | Image forming apparatus and computer-readable recording medium storing program | |
| JP2015182850A (ja) | 画像形成装置及びその制御方法、並びにプログラム | |
| JP3864653B2 (ja) | 用紙処理装置および方法 | |
| KR20160102115A (ko) | 후처리 제어장치, 후처리 제어장치의 제어방법, 시트 처리 시스템 및 기억매체 | |
| US9315350B2 (en) | Initiating alignment correction of printed media sheets | |
| JP6330336B2 (ja) | 画像形成システム、画像形成制御方法及び画像形成制御プログラム | |
| JP5494376B2 (ja) | シート処理システム、画像形成システム及び小口断裁位置決定方法 | |
| JP5217671B2 (ja) | 画像形成システム、画像形成装置及び画像形成制御プログラム | |
| JP3958043B2 (ja) | シート材後処理装置及び方法 | |
| JP6582853B2 (ja) | 後処理装置及び画像形成システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170613 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170613 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180316 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180326 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180523 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180604 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180703 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6366375 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |