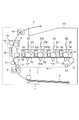JP6061505B2 - 光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 - Google Patents
光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6061505B2 JP6061505B2 JP2012131291A JP2012131291A JP6061505B2 JP 6061505 B2 JP6061505 B2 JP 6061505B2 JP 2012131291 A JP2012131291 A JP 2012131291A JP 2012131291 A JP2012131291 A JP 2012131291A JP 6061505 B2 JP6061505 B2 JP 6061505B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- emitting element
- light emission
- light emitting
- emission intensity
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/04—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for exposing, i.e. imagewise exposure by optically projecting the original image on a photoconductive recording material
- G03G15/043—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for exposing, i.e. imagewise exposure by optically projecting the original image on a photoconductive recording material with means for controlling illumination or exposure
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
- G02B26/08—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
- G02B26/10—Scanning systems
- G02B26/12—Scanning systems using multifaceted mirrors
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
- G02B26/08—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
- G02B26/10—Scanning systems
- G02B26/12—Scanning systems using multifaceted mirrors
- G02B26/127—Adaptive control of the scanning light beam, e.g. using the feedback from one or more detectors
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/04—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for exposing, i.e. imagewise exposure by optically projecting the original image on a photoconductive recording material
- G03G15/04036—Details of illuminating systems, e.g. lamps, reflectors
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/04—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for exposing, i.e. imagewise exposure by optically projecting the original image on a photoconductive recording material
- G03G15/04036—Details of illuminating systems, e.g. lamps, reflectors
- G03G15/04045—Details of illuminating systems, e.g. lamps, reflectors for exposing image information provided otherwise than by directly projecting the original image onto the photoconductive recording material, e.g. digital copiers
- G03G15/04072—Details of illuminating systems, e.g. lamps, reflectors for exposing image information provided otherwise than by directly projecting the original image onto the photoconductive recording material, e.g. digital copiers by laser
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Laser Beam Printer (AREA)
- Exposure Or Original Feeding In Electrophotography (AREA)
- Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
- Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
Description
以下に、図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
図1は、カラー画像形成装置の概略断面図である。尚、以下の説明においては、カラー画像形成装置を用いて説明を行うが、それに限定されるものではない。後述にて詳しく説明する非画像部の微少発光については、例えば、単色の画像形成装置にも適用することが出来る。また、以下においては、インライン方式のカラー画像形成装置を例に説明を行うが、例えばロータリー方式のカラー画像形成装置でも良い。以下、インライン方式のカラー画像形成装置を例に詳述する。
図2は、光学走査装置9の概略図を示す。この光学走査装置9は1つの感光ドラム5を露光するものであり、光学走査装置9は各感光ドラム5Y,5M,5C,5Kに対応して同様の光学走査装置9Y,9M,9C,9Kがそれぞれ設けられている。これら光学走査装置9Y,9M,9C,9Kは同様の構成であるので、以下では、その1つを光学走査装置9として代表として説明する。
[レーザー駆動システム]
図3は、非画像部において、感光ドラム上にトナー付着をさせないようにし、且つかぶりや反転かぶりを発生させないように、微少発光するうえでのLD107の適切な光量レベルを自動調整するレーザー駆動システム回路(駆動手段)である。
コンパレータ回路111、101の正極端子には、それぞれ第1の基準電圧Vref11、第2の基準電圧Vref21が入力されており、出力はそれぞれサンプル/ホールド回路112、102に入力されている。サンプル/ホールド回路112、102にはそれぞれホールドコンデンサ113、103が接続されている。この基準電圧Vref11は、微少発光用の発光レベル(第1発光強度)の目標電圧として設定されている。また、基準電圧Vref21は、通常の印字用の発光レベル(第2発光強度)の目標電圧として設定されている。
スイッチング回路116、106の出力端は、LD107のカソードに接続されており、駆動電流Ib、Idrvを供給している。LD107のアノードは、電源Vccに接続されている。LD107の光量をモニターするPD108のカソードは、電源Vccに接続されており、PD108のアノードは電流電圧変換回路109に接続されてモニター電流Imを電流電圧変換回路109に流すことにより、モニター電圧Vmを発生させている。このモニター電圧はコンパレータ111、101の負極端子に負帰還入力されている。
以下、レーザー駆動システム回路130において実行される、発光素子の2水準発光レベルに関する微少発光用APC及び印字発光用APCの動作について説明する。
非画像部微少発光は、駆動電流Ibを、LD107の閾値電流Ithを超え、微少発光レベルPbとなるように設定する。尚、微少発光レベル(第2発光強度)とは、そのレベルのレーザー照射によっても感光ドラムにトナー等の現像剤が実質的に帯電付着しない(顕像化されない)光量レベルで、且つトナーかぶり状態が良好な光量レベルを意味する。また微少発光レベルPbはIthを超える領域(図中A)とする。仮に、このときの微少発光レベルPbがIthに満たない領域であった場合、スペクトルの波長分布が拡がり、レーザーの定格の波長に対して広い波長分布になる。この為、感光ドラムの感度が乱れ、表面電位が不安定になってしまう。従って、微少発光レベルPbはIthを超える領域に設定することが好ましい。
次に光学走査装置(レーザースキャナ)9の起動に関する課題について説明する。レーザースキャナ起動時には、スキャナモータを加速し、スキャナモータの回転速度が画像形成を行う為の速度(目標速度Vtg)となるように制御する(スキャナモータを立ち上げる)。この時、スキャナモータの回転速度を検知すべく、レーザーダイオード107を強制発光させ、BD検出素子121でレーザー光を検出し、BD信号を生成し、生成されたBD信号に基づいて算出されるBD周期をモニターする。即ち、スキャナモータの回転速度が速い程BD周期が短くなるという相関関係があるので、このBD周期からスキャナモータの回転速度に関連する値を得ることができ、スキャナモータの回転速度が目標速度Vtgに収束したかを判断できる。そして、スキャナモータの回転速度が目標速度Vtgに収束した(スキャナモータが立ち上がった)と判断した後、画像形成装置は画像形成動作を開始する。
そこで、本実施例では、レーザースキャナ起動時のAPC動作を工夫している。以下、レーザースキャナ起動時(レーザー駆動システム回路130の起動時)の動作について説明する。
次に実施例2について説明する。実施例2は、実施例1に対し、レーザースキャナの起動シーケンスの一部が異なる。即ち、実施例2では、第1微少発光用APCと印字発光用APCを複数回繰り返し行う起動シーケンスについて説明する。その他の画像形成装置の構成、及び、光学走査装置9の構成、レーザー駆動システム回路130等の構成は実施例1と同様であるため説明を省略し、実施例1と異なる点についてのみ説明を行う。
S201〜S204においては実施例1で説明したS101〜S104と同様の処理を行う。つまり、先ず微小発光用APCを実行する。尚、S203の所定時間T2は、S103の所定時間T1としても良い。S205において、CPU1222は、所定時間T3が経過するまで印字発光用APCを継続する。ここで、所定時間T3とは、ASIC1221がBD周期を算出するのに十分な時間である。つまり、印字発光用APCの実行期間中に少なくとも連続2回以上のBD信号を検出できる時間である。
次に実施例3について説明する。実施例3は、実施例1に対し、レーザースキャナの起動シーケンスの一部が異なる。即ち、微少発光用APCと印字発光用APCの実行に加えレーザー消灯期間を加え、これを複数回繰り返し行う起動シーケンスについて説明する。その他の、本実施例に係る画像形成装置の構成、および光学走査装置9の構成、レーザー駆動システム回路130等の構成は実施例1と同様であるため説明を省略し、実施例1と異なる点についてのみ説明する。
次に実施例4について説明する。上述の実施例1〜3では、最初に微小発光用APCを行うレーザースキャナの起動シーケンスについて説明したが、実施例4は、最初に印字発光用APCを行うレーザースキャナの起動シーケンスについて説明する。尚、本実施例に係る画像形成装置の構成、および光学走査装置8の構成、レーザー駆動システム回路130の構成は実施例1と同様であるため説明を省略し、実施例1と異なる点についてのみ説明する。
図13は、前述のS403の処理における所定時間T8を説明するためのLD107に流れる電流と光量の関係示す図である。同図実線で表わされる特性において、上記の[レーザースキャナの起動に関する課題]で説明した様に、印字発光用APCの実行から最初に実行した場合、2回目の印字発光用APCの実行直後のLD107に供給される駆動電流は、I1に対してI2が重畳されたI1+I2となる。これがオーバーシュートとなって現れる。その後、I1+Idrv=I2となるように駆動電流Idrv(=I2−I1)を減少させるように調整する。この駆動電流I1+I2に相当する光量レベルが定格レベルPlimitを超えてしまう恐れがある。このPlimitを超えないようにするためには、最初の印字発光用APCの実行により、調整期間中のIdrvの値が所定の電流値に達する前に微少発光用APCへ切り替えれば良い。ここで、所定の電流値とは、Plimitに相当する駆動電流をIlimitとすると、Ilimit−I1としても良いし、これ以下の値としても良い。
本発明の第5の実施形態では、印字発光用APCから最初に実行した場合でも、駆動電流Ibを予め所定の値に設定しておくことのできるレーザー駆動システム回路について説明する。尚、本実施例に係る画像形成装置の構成、および光学走査装置9等の構成は第1実施例と同様であるため説明を省略する。
S402においてCPU1222は、印字発光用APCの実行を指示するとともに、Base2信号を介してコンデンサ119と電流増幅回路114を接続状態に制御する。つまり、所定の値のIbとしてIini1(所定の値の第2駆動電流)がLD107に供給されることになる。これにより、LD107にはIini1+Idrvの駆動電流が供給される。次のS403においてCPU1222は、所定時間経過するまで待つ。尚、所定時間T8は実施例1と同様にIdrvの調整が十分に完了する時間であればよい。これにより、駆動電流Idrvは、Iini1+Idrvに相当するLD107の光量が印字発光レベルPdrvとなるIdrv_iniとなるように調整される。
9(9Y,9M,9C,9K) 光学走査装置
107 レーザーダイオード
108 フォトダイオード
120 スキャナモータ
121 BD検出素子
122 エンジンコントローラ
123 ビデオコントローラ
130 レーザー駆動システム回路
Claims (12)
- レーザー光を発する発光素子と、駆動電流によって前記発光素子を駆動させる駆動手段と、所定速度で回転することで前記レーザー光を被走査面上で走査させる回転多面鏡と、前記発光素子から発せられ、前記回転多面鏡で反射したレーザー光を受光する受光手段と、前記回転多面鏡を駆動する回転多面鏡駆動手段と、前記回転多面鏡駆動手段の回転速度を制御する制御手段と、を有し、前記駆動手段は、第1発光強度及び前記第1発光強度よりも低い第2発光強度で前記発光素子を発光させることが可能な光学走査装置であって、
前記駆動手段は、第1駆動電流に第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着する画像部に向かって前記第1発光強度で発光させ、且つ、前記第2駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着しない非画像部に向かって前記第2発光強度で発光させ、
前記駆動手段は、前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する第1調整工程と、前記発光素子を前記第2発光強度で発光させて前記第2駆動電流を調整する第2調整工程を実行可能で、
前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を行い、前記回転多面鏡が回転を開始した後で且つ前記第1調整工程を行う前に、前記第2調整工程を行い、
前記制御手段は、前記第2調整工程が行われている場合は、前記受光手段によるレーザー光の受光が行われているか否かに関わらず前記回転多面鏡駆動手段の回転速度を制御し、前記第1調整工程が行われている場合は、前記受光手段による受光結果に応じて前記回転多面鏡駆動手段の回転速度を制御することを特徴とする光学走査装置。 - レーザー光を発する発光素子と、駆動電流によって前記発光素子を駆動させる駆動手段と、所定速度で回転することで前記レーザー光を被走査面上で走査させる回転多面鏡と、を有し、前記駆動手段は、第1発光強度及び前記第1発光強度よりも低い第2発光強度で前記発光素子を発光させることが可能な光学走査装置であって、
前記駆動手段は、第1駆動電流に第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着する画像部に向かって前記第1発光強度で発光させ、且つ、前記第2駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着しない非画像部に向かって前記第2発光強度で発光させ、
前記駆動手段は、前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する第1調整工程と、前記発光素子を前記第2発光強度で発光させて前記第2駆動電流を調整する第2調整工程を実行可能で、
前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を行い、前記回転多面鏡が回転を開始した後で且つ前記第1調整工程及び第2調整工程を行う前に、前記発光素子を前記第1発光強度よりも低い第3発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する第3調整工程を行うことを特徴とする光学走査装置。 - レーザー光を発する発光素子と、駆動電流によって前記発光素子を駆動させる駆動手段と、所定速度で回転することで前記レーザー光を被走査面上で走査させる回転多面鏡と、を有し、前記駆動手段は、第1発光強度及び前記第1発光強度よりも低い第2発光強度で前記発光素子を発光させることが可能な光学走査装置であって、
前記駆動手段は、第1駆動電流に第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着する画像部に向かって前記第1発光強度で発光させ、且つ、前記第2駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着しない非画像部に向かって前記第2発光強度で発光させ、
前記駆動手段は、前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する第1調整工程と、前記発光素子を前記第2発光強度で発光させて前記第2駆動電流を調整する第2調整工程を実行可能で、
前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を行い、前記回転多面鏡が回転を開始した後で且つ前記第2調整工程を行う前に、前記第1駆動電流に所定の値の前記第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する前記第1調整工程を行うことを特徴とする光学走査装置。 - レーザー光を発する発光素子と、駆動電流によって前記発光素子を駆動させる駆動手段と、所定速度で回転することで前記レーザー光を被走査面上で走査させる回転多面鏡と、を有し、前記駆動手段は、第1発光強度及び前記第1発光強度よりも低い第2発光強度で前記発光素子を発光させることが可能な光学走査装置であって、
前記駆動手段は、第1駆動電流に第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着する画像部に向かって前記第1発光強度で発光させ、且つ、前記第2駆動電流によって前記発光素子を感光体のトナーが付着しない非画像部に向かって前記第2発光強度で発光させ、
前記駆動手段は、前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する第1調整工程と、前記発光素子を前記第2発光強度で発光させて前記第2駆動電流を調整する第2調整工程を実行可能で、
前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を行い、前記回転多面鏡が回転を開始した後で且つ前記第1調整工程を行う前に、前記第2調整工程を行い、
前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定の速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を交互にそれぞれ複数回実行することを特徴とする光学走査装置。 - 前記駆動手段は、前記第2調整工程を行った後に、前記第1駆動電流に前記第2駆動電流を加えた駆動電流によって前記発光素子を前記第1発光強度で発光させて前記第1駆動電流を調整する前記第1調整工程を行うことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の光学走査装置。
- 前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定の速度となるまでの間で、前記第1調整工程及び前記第2調整工程を交互にそれぞれ複数回実行することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光学走査装置。
- 前記駆動手段は、前記回転多面鏡が回転を開始してから前記所定速度となるまでの間に、前記発光素子を発光させない期間を少なくとも1回設けることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の光学走査装置。
- 前記回転多面鏡が回転を開始した後、前記回転多面鏡の速度が前記所定速度よりも遅い別の所定速度以上となると、前記駆動手段は前記第1調整工程を行うことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の光学走査装置。
- 前記発光素子から発せられ、前記回転多面鏡で反射したレーザー光を受光する受光手段を有し、前記受光手段からの出力に基づいて前記回転多面鏡の回転速度に関連する値を検出することを特徴とする請求項2乃至7のいずれか一項に記載の光学走査装置。
- 前記受光手段は、前記第1調整工程が行われている場合は、受光結果としての前記回転多面鏡の回転速度に関連する値を検出可能であることを特徴とする請求項1又は9に記載の光学走査装置。
- 請求項1乃至10のいずれか一項に記載の光学走査装置と、前記被走査面としての感光体と、前記感光体にトナーを付着させる現像手段と、を有し、前記レーザー光によって走査された前記感光体に前記現像手段がトナーを付着させることで画像を形成する画像形成装置であって、
前記駆動手段は、前記感光体上のトナーを付着させる画像部に対して、トナーを付着させるための前記第1発光強度で前記発光素子を発光させ、且つ、前記感光体上のトナーを付着させない非画像部に対して、トナーを付着させないための前記第2発光強度で前記発光素子を発光させることを特徴とする画像形成装置。 - 前記感光体を複数有し、前記光学走査装置が前記複数の感光体を夫々レーザー光で走査することで、複数色の画像を形成する請求項11に記載の画像形成装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012131291A JP6061505B2 (ja) | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 |
| US13/909,877 US9250557B2 (en) | 2012-06-08 | 2013-06-04 | Optical scanning device and image forming apparatus provided with same |
| US14/976,654 US9632450B2 (en) | 2012-06-08 | 2015-12-21 | Image forming apparatus controlling driving current for adjusting light emission intensity of light-emitting element |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012131291A JP6061505B2 (ja) | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2013254173A JP2013254173A (ja) | 2013-12-19 |
| JP2013254173A5 JP2013254173A5 (ja) | 2015-07-23 |
| JP6061505B2 true JP6061505B2 (ja) | 2017-01-18 |
Family
ID=49714975
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012131291A Active JP6061505B2 (ja) | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9250557B2 (ja) |
| JP (1) | JP6061505B2 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6409420B2 (ja) | 2014-08-29 | 2018-10-24 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP2016051047A (ja) * | 2014-08-29 | 2016-04-11 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成システム、集積回路チップ、画像形成装置 |
| JP6463112B2 (ja) | 2014-12-10 | 2019-01-30 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP6886235B2 (ja) * | 2015-09-24 | 2021-06-16 | キヤノン株式会社 | 記録装置および発光素子駆動用基板 |
| JP6681270B2 (ja) * | 2016-05-19 | 2020-04-15 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及び走査装置 |
| JP6942450B2 (ja) | 2016-08-30 | 2021-09-29 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| US10520848B2 (en) | 2017-11-28 | 2019-12-31 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus with variable light emission amounts |
| JP2019148643A (ja) * | 2018-02-26 | 2019-09-05 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2593613B1 (fr) * | 1985-11-29 | 1993-01-08 | Ricoh Kk | Ensemble, dispositif et appareil de deviation de faisceau pour imprimante |
| US4890288A (en) * | 1986-08-27 | 1989-12-26 | Canon Kabushiki Kaisha | Light quantity control device |
| JPH0969662A (ja) * | 1995-08-31 | 1997-03-11 | Asahi Optical Co Ltd | 光走査装置の光強度変調回路 |
| JP2001158130A (ja) | 1999-12-03 | 2001-06-12 | Hitachi Koki Co Ltd | 電子写真装置のレーザ制御方法 |
| JP2003312050A (ja) * | 2002-04-23 | 2003-11-06 | Canon Inc | 画像形成装置 |
| JP2004122442A (ja) | 2002-09-30 | 2004-04-22 | Canon Inc | 画像形成装置、画像形成方法、画像形成装置制御用プログラム及び記録媒体 |
| JP2005153451A (ja) | 2003-11-28 | 2005-06-16 | Fuji Photo Film Co Ltd | 光量調整方法、光量調整装置及び画像形成装置 |
| US7158163B2 (en) * | 2004-03-22 | 2007-01-02 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Light beam scanning apparatus capable of shortening the standby time and image forming apparatus capable of shortening the standby time |
| JP4687962B2 (ja) * | 2005-07-27 | 2011-05-25 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP2007192967A (ja) | 2006-01-18 | 2007-08-02 | Pentax Corp | 光走査装置 |
| JP2007253386A (ja) * | 2006-03-22 | 2007-10-04 | Brother Ind Ltd | 画像形成装置 |
| JP5864863B2 (ja) * | 2010-03-09 | 2016-02-17 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP5885472B2 (ja) | 2010-12-10 | 2016-03-15 | キヤノン株式会社 | カラー画像形成装置 |
-
2012
- 2012-06-08 JP JP2012131291A patent/JP6061505B2/ja active Active
-
2013
- 2013-06-04 US US13/909,877 patent/US9250557B2/en active Active
-
2015
- 2015-12-21 US US14/976,654 patent/US9632450B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20130328986A1 (en) | 2013-12-12 |
| US20160103400A1 (en) | 2016-04-14 |
| US9632450B2 (en) | 2017-04-25 |
| JP2013254173A (ja) | 2013-12-19 |
| US9250557B2 (en) | 2016-02-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6061505B2 (ja) | 光学走査装置及びそれを有する画像形成装置 | |
| US10948844B2 (en) | Color image forming apparatus | |
| US9465312B2 (en) | Image forming apparatus and method for adjustment of light amount during weak light emission | |
| JP6238560B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| US10520848B2 (en) | Image forming apparatus with variable light emission amounts | |
| JP2014228656A (ja) | 画像形成装置 | |
| US10788769B2 (en) | Image forming apparatus | |
| US9341976B2 (en) | Multi-station image forming apparatus with start-up control | |
| US9632449B2 (en) | Image forming apparatus having controlled light emission using current adjustment | |
| JP6091668B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2014228657A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2021074957A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2016141099A (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |
| JP7039217B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6191276B2 (ja) | 書込駆動制御装置、書込駆動制御方法、光書込装置、及び画像形成装置 | |
| JP2020109433A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2019098527A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2019070702A (ja) | 走査装置及び画像形成装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150608 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150608 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160323 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160426 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160622 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161115 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161213 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6061505 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |