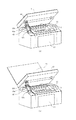JP5773675B2 - 画像形成装置 - Google Patents
画像形成装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5773675B2 JP5773675B2 JP2011024020A JP2011024020A JP5773675B2 JP 5773675 B2 JP5773675 B2 JP 5773675B2 JP 2011024020 A JP2011024020 A JP 2011024020A JP 2011024020 A JP2011024020 A JP 2011024020A JP 5773675 B2 JP5773675 B2 JP 5773675B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- cartridge
- opening
- closing member
- contact surface
- image forming
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G21/00—Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge
- G03G21/16—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements
- G03G21/18—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements using a processing cartridge, whereby the process cartridge comprises at least two image processing means in a single unit
- G03G21/1839—Means for handling the process cartridge in the apparatus body
- G03G21/1842—Means for handling the process cartridge in the apparatus body for guiding and mounting the process cartridge, positioning, alignment, locks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electrophotography Configuration And Component (AREA)
- Fixing For Electrophotography (AREA)
Description
また本発明は、置本体に対して回動して前記装置本体の内部を閉じた閉位置と、前記装置本体の内部を開放してカートリッジを前記装置本体に着脱可能な開位置との間を移動する開閉部材と、前記開閉部材に対して移動可能に前記開閉部材に支持され、前記カートリッジが前記装置本体の装着位置に取り付けられて前記開閉部材が閉じた位置にある時に、前記カートリッジの前記装置本体から外れる方向への移動を規制するカートリッジ当接部材と、を有し、前記カートリッジが前記装着位置に取り付けられた状態で画像形成を行う画像形成装置において、前記カートリッジ当接部材は、前記カートリッジと当接するカートリッジ当接面と、前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に前記開閉部材に当接し、前記カートリッジ当接面の法線上に配置され、前記カートリッジ当接面に略平行な開閉部材当接面と、前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に、前記カートリッジ当接面から前記開閉部材当接面へ力を伝達し、前記カートリッジ当接面の法線方向に延び、前記カートリッジ当接面と前記開閉部材当接面との間を直線的に繋ぐ部分を備える力伝達部と、を有し、前記開閉部材が前記開閉部材当接面から受ける力は前記開閉部材が閉位置から開位置に移動する方向に作用しないことを特徴とする。
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従って特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
次に図6を用いて、本発明の第2の実施形態に係る画像形成装置について説明する。また本実施形態において、前述した第1の実施形態と同等の機能を有する部材及び、同様の構成については同一記号を付し、その説明を省略する。図6に開閉カバー141、プロセスカートリッジ1及び定着装置付近を示す。図6(a)は開閉カバー141が閉まっている時の斜視図であり、図6(b)は開閉カバー141が閉まっている時の装置正面の左側からみた断面図であり、図6(c)は開閉カバー141が開いている時の装置正面の左側からみた断面図である。なおここでは以降の論述に対して不要な部品の図示及び説明を省略している。
次に図7を用いて、本発明の第3の実施形態に係る画像形成装置について説明する。本実施形態において、前述した第1、2の実施形態と同等の機能を有する部材及び、同様の構成については同一記号を付し、その説明を省略する。図7は本体正面の左側からみときのプロセスカートリッジと開閉カバー付近の断面図を示す。図7(a)はプロセスカートリッジの装着が完了し開閉カバー241を閉じた状態の断面図であり、図7(b)は開閉カバー241が開いてプロセスカートリッジを着脱可能な状態の断面図である。なおここでは以降の論述に対して不要な部品の図示及び説明を省略している。図7に示すように第3の実施形態では第1の実施形態と比べて、開閉カバーの回転中心241cの位置と、連結アームのレール部227aの形状が変更されている点が主に異なる。
20 画像形成部
27、127、227 連結アーム
27a、227a 連結アームレール部
27b、227b 連結アームカートリッジ押し込み部
27c 連結アームカートリッジ受け面
27d 連結アーム開閉カバー当接面
27e 力伝達部
41、141、241 開閉カバー
41a、241a 開閉カバー突起部
41b、141b、241b 開閉カバー継ぎ手部
41c、241c 開閉カバー回転中心
Claims (12)
- 装置本体に対して回動して前記装置本体の内部を閉じた閉位置と、前記装置本体の内部を開放してカートリッジを前記装置本体に着脱可能な開位置との間を移動する開閉部材と、
前記開閉部材に対して移動可能に前記開閉部材に支持され、前記開閉部材が前記開位置から前記閉位置に向かって移動する際に、前記カートリッジを装着位置に向かって移動するよう押圧可能なカートリッジ当接部材と、
を有し、前記カートリッジが前記装着位置に取り付けられた状態で画像形成を行う画像形成装置において、
前記カートリッジ当接部材は、
前記カートリッジと当接するカートリッジ当接面と、
前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に前記開閉部材に当接し、前記カートリッジ当接面の法線上に配置され、前記カートリッジ当接面に略平行な開閉部材当接面と、
前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に、前記カートリッジ当接面から前記開閉部材当接面へ力を伝達し、前記カートリッジ当接面の法線方向に延び、前記カートリッジ当接面と前記開閉部材当接面との間を直線的に繋ぐ部分を備える力伝達部と、を有し、
前記開閉部材が前記開閉部材当接面から受ける力は前記開閉部材が閉位置から開位置に移動する方向に作用しないことを特徴とする画像形成装置。 - 前記開閉部材は回転軸を中心に回転し、前記回動軸と、前記開閉部材が前記カートリッジ当接部材の前記開閉部材当接面の中心点から受ける力のベクトルの延長線との位置関係は、前記開閉部材が前記開閉部材当接面から受ける力が、前記開閉部材が閉位置から開位置に移動する方向に作用しないような関係であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 前記回転軸は、前記開閉部材が前記カートリッジ当接部材の前記開閉部材当接面の中心から受ける力のベクトルを含む線上にあることを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
- 前記カートリッジは、前記カートリッジが前記装着位置で前記開閉部材が前記閉位置にある状態において、前記カートリッジ当接面に略平行で、前記カートリッジ当接面に対向する突き当て面を備え、
前記カートリッジが前記装置本体から外れる方向に移動すると、前記突き当て面は前記カートリッジ当接面に略垂直に移動して前記カートリッジ当接面に当接することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の画像形成装置。 - 前記カートリッジ着脱の際の装置本体内における前記カートリッジの移動をガイドするガイド部を備え、
前記ガイド部は、前記カートリッジが前記装着位置にある状態から装置本体から取り外す方向に移動した際に、前記カートリッジが前記カートリッジ当接面に略垂直な方向に移動するよう、前記カートリッジの移動をガイドすることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の画像形成装置。 - 前記画像形成は記録材にトナー像を転写し、該トナー像を加圧して定着することで行われ、
記録材に転写されたトナー像を加圧し定着させるための加圧定着手段を有し、前記カートリッジ当接部材は、前記開閉部材の移動に連動して移動することにより、前記加圧定着手段の加圧力を変化させることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 装置本体に対して回動して前記装置本体の内部を閉じた閉位置と、前記装置本体の内部を開放してカートリッジを前記装置本体に着脱可能な開位置との間を移動する開閉部材と、
前記開閉部材に対して移動可能に前記開閉部材に支持され、前記カートリッジが前記装置本体の装着位置に取り付けられて前記開閉部材が閉じた位置にある時に、前記カートリッジの前記装置本体から外れる方向への移動を規制するカートリッジ当接部材と、
を有し、前記カートリッジが前記装着位置に取り付けられた状態で画像形成を行う画像形成装置において、
前記カートリッジ当接部材は、
前記カートリッジと当接するカートリッジ当接面と、
前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に前記開閉部材に当接し、前記カートリッジ当接面の法線上に配置され、前記カートリッジ当接面に略平行な開閉部材当接面と、
前記カートリッジ当接部材が前記カートリッジを押圧した時に、前記カートリッジ当接面から前記開閉部材当接面へ力を伝達し、前記カートリッジ当接面の法線方向に延び、前記カートリッジ当接面と前記開閉部材当接面との間を直線的に繋ぐ部分を備える力伝達部と、を有し、
前記開閉部材が前記開閉部材当接面から受ける力は前記開閉部材が閉位置から開位置に移動する方向に作用しないことを特徴とする画像形成装置。 - 前記開閉部材は回転軸を中心に回転し、前記回動軸と、前記開閉部材が前記カートリッジ当接部材の前記開閉部材当接面の中心点から受ける力のベクトルの延長線との位置関係は、前記開閉部材が前記開閉部材当接面から受ける力が、前記開閉部材が閉位置から開位置に移動する方向に作用しないような関係であることを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
- 前記回転軸は、前記開閉部材が前記カートリッジ当接部材の前記開閉部材当接面の中心から受ける力のベクトルを含む線上にあることを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
- 前記カートリッジは、前記カートリッジが前記装着位置で前記開閉部材が前記閉位置にある状態において、前記カートリッジ当接面に略平行で、前記カートリッジ当接面に対向する突き当て面を備え、
前記カートリッジが前記装置本体から外れる方向に移動すると、前記突き当て面は前記カートリッジ当接面に略垂直に移動して前記カートリッジ当接面に当接することを特徴とする請求項7乃至9のいずれか一項に記載の画像形成装置。 - 前記カートリッジ着脱の際の装置本体内における前記カートリッジの移動をガイドするガイド部を備え、
前記ガイド部は、前記カートリッジが前記装着位置にある状態から装置本体から取り外す方向に移動した際に、前記カートリッジが前記カートリッジ当接面に略垂直な方向に移動するよう、前記カートリッジの移動をガイドすることを特徴とする請求項7乃至10のいずれか一項に記載の画像形成装置。 - 前記画像形成は記録材にトナー像を転写し、該トナー像を加圧して定着することで行われ、
記録材に転写されたトナー像を加圧し定着させるための加圧定着手段を有し、前記カートリッジ当接部材は、前記開閉部材の移動に連動して移動することにより、前記加圧定着手段の加圧力を変化させることを特徴とする請求項7乃至11のいずれか1項に記載の画像形成装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2011024020A JP5773675B2 (ja) | 2010-03-31 | 2011-02-07 | 画像形成装置 |
| US13/074,951 US8606141B2 (en) | 2010-03-31 | 2011-03-29 | Image forming apparatus operable for installing attachable/detachable cartidge therein |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2010082830 | 2010-03-31 | ||
| JP2010082830 | 2010-03-31 | ||
| JP2011024020A JP5773675B2 (ja) | 2010-03-31 | 2011-02-07 | 画像形成装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2011227457A JP2011227457A (ja) | 2011-11-10 |
| JP2011227457A5 JP2011227457A5 (ja) | 2014-03-27 |
| JP5773675B2 true JP5773675B2 (ja) | 2015-09-02 |
Family
ID=44709838
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2011024020A Active JP5773675B2 (ja) | 2010-03-31 | 2011-02-07 | 画像形成装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8606141B2 (ja) |
| JP (1) | JP5773675B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10444665B2 (en) | 2017-10-03 | 2019-10-15 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus |
| US10649400B2 (en) | 2017-10-30 | 2020-05-12 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus with features that suppress deformation of door caused by counterforce from cartridge |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5928879B2 (ja) * | 2012-03-30 | 2016-06-01 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP5982961B2 (ja) | 2012-03-30 | 2016-08-31 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP5895668B2 (ja) * | 2012-03-30 | 2016-03-30 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP6137026B2 (ja) | 2014-03-31 | 2017-05-31 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP6512864B2 (ja) * | 2015-02-27 | 2019-05-15 | キヤノン株式会社 | カートリッジ、プロセスカートリッジ、画像形成装置 |
| CN106959598B (zh) * | 2016-01-12 | 2021-05-04 | 纳思达股份有限公司 | 处理盒及图像形成装置 |
| JP6808364B2 (ja) | 2016-06-14 | 2021-01-06 | キヤノン株式会社 | 電子写真画像形成装置 |
| JP6789683B2 (ja) * | 2016-06-14 | 2020-11-25 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| CN106647208B (zh) * | 2016-11-07 | 2019-10-15 | 纳思达股份有限公司 | 一种处理盒 |
| JP7242413B2 (ja) * | 2019-05-07 | 2023-03-20 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP7087051B2 (ja) * | 2020-12-08 | 2022-06-20 | キヤノン株式会社 | 電子写真画像形成装置 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10254328A (ja) * | 1997-03-10 | 1998-09-25 | Canon Inc | 電子写真画像形成装置及びプロセスカートリッジ |
| JPH11184353A (ja) * | 1997-12-17 | 1999-07-09 | Canon Inc | プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置 |
| JP3672067B2 (ja) * | 1998-01-20 | 2005-07-13 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |
| JP3347686B2 (ja) * | 1999-04-02 | 2002-11-20 | キヤノン株式会社 | 電子写真画像形成装置及びプロセスカートリッジ押込み機構 |
| JP4447870B2 (ja) | 2003-08-29 | 2010-04-07 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4474178B2 (ja) * | 2004-02-27 | 2010-06-02 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4721464B2 (ja) * | 2008-04-25 | 2011-07-13 | キヤノン株式会社 | 電子写真画像形成装置 |
-
2011
- 2011-02-07 JP JP2011024020A patent/JP5773675B2/ja active Active
- 2011-03-29 US US13/074,951 patent/US8606141B2/en active Active
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10444665B2 (en) | 2017-10-03 | 2019-10-15 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus |
| US10649400B2 (en) | 2017-10-30 | 2020-05-12 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus with features that suppress deformation of door caused by counterforce from cartridge |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20110243601A1 (en) | 2011-10-06 |
| US8606141B2 (en) | 2013-12-10 |
| JP2011227457A (ja) | 2011-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5773675B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| US10831149B2 (en) | Image forming apparatus having mountable and demountable photosensitive member cartridge and developing cartridge | |
| JP5435411B2 (ja) | 画像形成装置及び開閉装置 | |
| JP5316564B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4721464B2 (ja) | 電子写真画像形成装置 | |
| JP2011070142A (ja) | 電子写真画像形成装置 | |
| US8752825B2 (en) | Image forming apparatus and sheet transporting apparatus with cover and guide member pivotable with respect to apparatus body | |
| US8328182B2 (en) | Image forming apparatus | |
| JP5103821B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6070361B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6003522B2 (ja) | シート搬送装置 | |
| JP2009234690A (ja) | シート送り装置及び画像形成装置 | |
| JP4958467B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2015212204A (ja) | シート積載装置及び画像形成装置 | |
| JP5095341B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP5440282B2 (ja) | 定着装置および画像形成装置 | |
| JP2018077336A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP5914400B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6485748B2 (ja) | 画像形成装置及び定着装置 | |
| JP5928281B2 (ja) | シート搬送装置 | |
| JP2009063749A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6996076B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP7471805B2 (ja) | シート給送装置及び画像形成装置 | |
| JP5333360B2 (ja) | 定着装置および画像形成装置 | |
| KR101075230B1 (ko) | 현상장치 및 이를 구비한 화상형성장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140207 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140207 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20141031 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20141111 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150113 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150602 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150630 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 5773675 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |