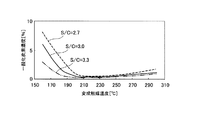JP5138986B2 - 水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム - Google Patents
水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP5138986B2 JP5138986B2 JP2007155124A JP2007155124A JP5138986B2 JP 5138986 B2 JP5138986 B2 JP 5138986B2 JP 2007155124 A JP2007155124 A JP 2007155124A JP 2007155124 A JP2007155124 A JP 2007155124A JP 5138986 B2 JP5138986 B2 JP 5138986B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- temperature
- water
- amount
- supply amount
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 title claims description 275
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 title claims description 275
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 273
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims description 63
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 332
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 197
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 151
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 124
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 109
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 106
- 238000002407 reforming Methods 0.000 claims description 90
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 49
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 claims description 49
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 44
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 claims description 32
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 27
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 26
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 23
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 20
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 10
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 9
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 claims description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 88
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 52
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 50
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 50
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 46
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 39
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 15
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 13
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 13
- 238000000629 steam reforming Methods 0.000 description 12
- 238000006057 reforming reaction Methods 0.000 description 9
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 8
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 8
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 6
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 6
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910017518 Cu Zn Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910017752 Cu-Zn Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910017943 Cu—Zn Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 5
- TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N copper zinc Chemical compound [Cu].[Zn] TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 5
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 5
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 4
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 description 3
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000004092 self-diagnosis Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005526 G1 to G0 transition Effects 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000008246 gaseous mixture Substances 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
Description
先ず、本発明の実施の形態1に係る水素生成装置の基本的な構成について説明する。
本発明の実施の形態2に係る水素生成装置のハードウェアの構成及びそれを駆動するための付加的なハードウェアの構成、及び、水素生成装置の基本的な動作については、実施の形態1の場合と同様である。従って、本発明の実施の形態2では、それらの説明については省略する。
本発明の実施の形態3に係る水素生成装置のハードウェアの構成及びそれを駆動するための付加的なハードウェアの構成、及び、水素生成装置の基本的な動作については、実施の形態1及び2の場合と同様である。従って、本発明の実施の形態3では、それらの説明については省略する。
本発明の実施の形態4に係る水素生成装置のハードウェアの構成及びそれを駆動するための付加的なハードウェアの構成、及び、水素生成装置の基本的な動作については、実施の形態1〜3の場合と同様である。従って、本発明の実施の形態4では、それらの説明については省略する。
2 改質部
2a 改質触媒
2b 温度検出部
3 変成部
3a 変成触媒
3b,3c 温度検出部
4 選択酸化部
4a 選択酸化触媒
4b 温度検出部
5 燃焼ガス流路
6 予熱蒸発部
6a 蒸発棒
7 水トラップ部
8 熱交換部
9 水供給器
10 原料供給器
11 燃焼用空気供給器
12 選択酸化用空気供給器
13a,13b 流路切り替え弁
14 制御器
a 上壁部
b 下壁部
A 外壁部
B 内壁部
B1 第1の内壁部
B2 第2の内壁部
B3 第3の内壁部
C 隔壁部
C1 第1の隔壁部
C2 第2の隔壁部
C3 第3の隔壁部
C4 第4の隔壁部
P1 蒸発部
P2 熱交換部
100a,100b 水素生成装置
101 水供給口
102 原料供給口
103 空気供給口
104 間隙
105 燃料ガス取り出し口
Claims (10)
- 燃焼用燃料と燃焼用空気との混合気を燃焼して燃焼ガスを生成する加熱器と、
前記加熱器が生成する前記燃焼ガスにより原料及び水が加熱されて該原料と水蒸気との混合気を生成する環状の予熱蒸発器と、
前記予熱蒸発器の下方に、前記予熱蒸発器が生成する前記混合気を前記燃焼ガスにより加熱された改質触媒に通過させることにより水素含有ガスを生成する環状の改質器と、
前記予熱蒸発器から排出された液水をトラップする水トラップ部と、
前記予熱蒸発器の外周に、前記改質器で生成された前記水素含有ガス中の一酸化炭素をシフト反応により低減する変成触媒を内蔵する環状の変成器と、
前記加熱器に前記燃焼用空気を供給する燃焼用空気供給器と、
前記予熱蒸発器に前記水を供給する水供給器と、
前記変成器が内蔵する前記変成触媒の温度を検出する温度検出器と、
制御器と、を備え、
前記改質器から前記変成器に供給される前記水素含有ガスと前記水トラップ部内の液水とが熱交換するように構成され、
前記制御器が、前記温度検出器により検出される前記変成触媒の温度に基づき前記水供給器から前記予熱蒸発器への水供給量及び前記燃焼用空気供給器から前記加熱器への燃焼用空気供給量の少なくとも一方を制御する、水素生成装置。 - 前記加熱器の外方に、前記予熱蒸発器と、前記水トラップ部と、前記改質器及び前記変成器とを各々筒状に備え、
前記予熱蒸発器に前記変成器が周設され、
前記予熱蒸発器と、前記水トラップ部と、前記改質器とが、該予熱蒸発器から該水トラップ部を介して該改質器に前記混合気が供給されるように連設され、
前記改質器で生成された前記水素含有ガスが前記変成器に供給される前に前記水トラップ部と接触するように構成されている、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記原料の供給口及び前記水の供給口を、前記予熱蒸発器の前記水トラップ部が連設されない他端側に備えている、請求項2記載の水素生成装置。
- 前記変成触媒の温度制御に係る上限温度及び下限温度の情報を有する記憶器を備え、
前記制御器が、前記温度検出器の検出温度が前記上限温度以上になった場合には前記予熱蒸発器への水供給量を増量させるよう前記水供給器を制御し、前記温度検出器の検出温度が前記下限温度以下になった場合には前記予熱蒸発器への水供給量を減量させるよう前記水供給器を制御する、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記記憶器が前記水供給量の制御に係る上限供給量及び下限供給量の情報を更に有し、
前記制御器が、前記水供給器から前記予熱蒸発器への水供給量が前記上限供給量以上になった場合又は前記水供給器から前記予熱蒸発器への水供給量が前記下限供給量以下になった場合に異常と判断する、請求項4記載の水素生成装置。 - 前記変成触媒の温度制御に係る上限温度及び下限温度の情報を有する記憶器を備え、
前記制御器が、前記温度検出器の検出温度が前記上限温度以上になった場合には前記加熱器への燃焼用空気供給量を減量させるよう前記燃焼用空気供給器を制御し、前記温度検出器の検出温度が前記下限温度以下になった場合には前記加熱器への燃焼用空気供給量を増量させるよう前記燃焼用空気供給器を制御する、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記記憶器が前記燃焼用空気供給量の制御に係る上限供給量及び下限供給量の情報を更に有し、
前記制御器が、前記燃焼用空気供給器から前記加熱器への燃焼用空気供給量が前記上限供給量以上になった場合又は前記燃焼用空気供給器から前記加熱器への燃焼用空気供給量が前記下限供給量以下になった場合に異常と判断する、請求項6記載の水素生成装置。 - 前記変成触媒の温度制御に係る上限温度及び下限温度の情報と前記水供給量の制御に係る上限供給量及び下限供給量の情報とを有する記憶器を備え、
前記制御器が、前記変成触媒の温度が前記上限温度以上になりかつ前記水供給器から前記予熱蒸発器への水供給量が前記上限供給量以上になった場合には前記加熱器への燃焼用空気供給量を減量させるよう前記燃焼用空気供給器を制御し、前記変成触媒の温度が前記下限温度以下になりかつ前記水供給器から前記予熱蒸発器への水供給量が前記下限供給量以下になった場合には前記加熱器への燃焼用空気供給量を増量させるよう前記燃焼用空気供給器を制御する、請求項1記載の水素生成装置。 - 前記変成触媒の温度制御に係る上限温度及び下限温度の情報と前記燃焼用空気供給量の制御に係る上限供給量及び下限供給量の情報とを有する記憶器を備え、
前記制御器が、前記変成触媒の温度が前記上限温度以上になりかつ前記燃焼用空気供給器から前記加熱器への燃焼用空気供給量が前記下限供給量以下になった場合には前記予熱蒸発器への水供給量を増量させるよう前記水供給器を制御し、前記変成触媒の温度が前記下限温度以下になりかつ前記燃焼用空気供給器から前記加熱器への燃焼用空気供給量が前記上限供給量以上になった場合には前記予熱蒸発器への水供給量を減量させるよう前記水供給器を制御する、請求項1記載の水素生成装置。 - 請求項1乃至9のいずれか1項に記載の水素生成装置と、
前記水素生成装置から供給される前記水素含有ガスと酸素含有ガスとを用いて発電する燃料電池と、
を少なくとも備えている、燃料電池システム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007155124A JP5138986B2 (ja) | 2006-06-12 | 2007-06-12 | 水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2006162614 | 2006-06-12 | ||
| JP2006162614 | 2006-06-12 | ||
| JP2007155124A JP5138986B2 (ja) | 2006-06-12 | 2007-06-12 | 水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2008019159A JP2008019159A (ja) | 2008-01-31 |
| JP2008019159A5 JP2008019159A5 (ja) | 2010-05-13 |
| JP5138986B2 true JP5138986B2 (ja) | 2013-02-06 |
Family
ID=39075416
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007155124A Active JP5138986B2 (ja) | 2006-06-12 | 2007-06-12 | 水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5138986B2 (ja) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4740277B2 (ja) * | 2008-03-18 | 2011-08-03 | アイシン精機株式会社 | 改質装置 |
| JP5274986B2 (ja) * | 2008-11-06 | 2013-08-28 | 東京瓦斯株式会社 | 燃料電池用多重円筒型水蒸気改質器 |
| JP5348481B2 (ja) * | 2009-03-30 | 2013-11-20 | アイシン精機株式会社 | 燃料電池システム |
| JP5423112B2 (ja) * | 2009-04-10 | 2014-02-19 | パナソニック株式会社 | 水素生成装置 |
| JP5428531B2 (ja) * | 2009-05-26 | 2014-02-26 | パナソニック株式会社 | 水素製造装置 |
| JP5371013B2 (ja) * | 2010-03-02 | 2013-12-18 | 東京瓦斯株式会社 | 多重円筒型水蒸気改質器 |
| WO2011108264A1 (ja) * | 2010-03-04 | 2011-09-09 | パナソニック株式会社 | 水素生成装置および燃料電池発電システム |
| JP5818456B2 (ja) * | 2011-02-21 | 2015-11-18 | 京セラ株式会社 | 燃料電池装置 |
| JP2014005171A (ja) * | 2012-06-25 | 2014-01-16 | Panasonic Corp | 燃料処理装置およびその製造方法 |
| WO2014002472A1 (ja) | 2012-06-25 | 2014-01-03 | パナソニック株式会社 | 燃料処理装置 |
| WO2014002468A1 (en) | 2012-06-25 | 2014-01-03 | Panasonic Corporation | Fuel processor |
| JP5483787B1 (ja) * | 2012-06-25 | 2014-05-07 | パナソニック株式会社 | 燃料処理装置 |
| JP6437791B2 (ja) * | 2014-11-07 | 2018-12-12 | フタバ産業株式会社 | 燃料改質装置 |
| JP6601683B2 (ja) * | 2016-07-28 | 2019-11-06 | Toto株式会社 | 固体酸化物形燃料電池装置 |
| JP6743261B2 (ja) * | 2019-10-03 | 2020-08-19 | 森村Sofcテクノロジー株式会社 | 固体酸化物形燃料電池装置 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2478797C (en) * | 2002-03-15 | 2010-05-04 | Matsushita Electric Works, Ltd. | Reforming apparatus and operation method thereof |
| JP2004006093A (ja) * | 2002-05-31 | 2004-01-08 | Ebara Ballard Corp | 燃料処理装置、燃料電池発電システム |
| JP4204291B2 (ja) * | 2002-09-26 | 2009-01-07 | アイシン精機株式会社 | 改質装置 |
| JP4504616B2 (ja) * | 2002-12-26 | 2010-07-14 | 株式会社荏原製作所 | 燃料電池発電システム |
| JP4458890B2 (ja) * | 2004-03-23 | 2010-04-28 | 株式会社コロナ | 燃料改質装置 |
| JP4784047B2 (ja) * | 2004-06-09 | 2011-09-28 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システム |
-
2007
- 2007-06-12 JP JP2007155124A patent/JP5138986B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2008019159A (ja) | 2008-01-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5138986B2 (ja) | 水素生成装置及びそれを備える燃料電池システム | |
| US8273489B2 (en) | Hydrogen generator and fuel cell system including the same | |
| JP4105758B2 (ja) | 燃料電池システム | |
| WO2001048851A1 (fr) | Dispositif de production d'energie et procede de fonctionnement | |
| JPWO2006088018A1 (ja) | 水素生成装置及びその運転方法並びに燃料電池システム | |
| JP5409486B2 (ja) | 水素製造装置及び燃料電池システム | |
| JP5057938B2 (ja) | 水素生成装置、およびこれを備えた燃料電池システム | |
| JP2004006093A (ja) | 燃料処理装置、燃料電池発電システム | |
| JP2005170784A (ja) | 水素発生装置及びその運転方法ならびに燃料電池発電システム | |
| JP4870499B2 (ja) | 水素製造装置及び燃料電池発電装置 | |
| JP2009079155A (ja) | 液体燃料脱硫装置及び液体燃料脱硫システム | |
| JP2005174745A (ja) | 燃料電池システムの運転方法及び燃料電池システム | |
| JP2007022826A (ja) | 水素生成装置および燃料電池システム | |
| JP2007331951A (ja) | 水素生成装置および燃料電池システム | |
| JP2008103278A (ja) | 燃料電池システム | |
| JP2017048079A (ja) | 水素生成装置及びそれを用いた燃料電池システム | |
| JP5634729B2 (ja) | 水素製造装置及び燃料電池システム | |
| JP2005216615A (ja) | 燃料処理装置及び燃料電池発電システム | |
| JP6467591B2 (ja) | 水素生成装置 | |
| JP2012119244A (ja) | 燃料電池システム | |
| JP2007191338A (ja) | 水素製造装置の運転方法、水素製造装置および燃料電池発電装置 | |
| WO2012032744A1 (ja) | 燃料電池システム | |
| JP4835273B2 (ja) | 水素生成装置および燃料電池システム | |
| JP5057910B2 (ja) | 水素生成装置、およびその起動方法 | |
| JP2009107876A (ja) | 水素生成装置、および燃料電池発電システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20090324 |
|
| A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20090325 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20090324 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20090325 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100326 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100326 |
|
| A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20120113 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120704 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120717 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120724 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20121023 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121115 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5138986 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151122 Year of fee payment: 3 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
| S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |