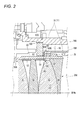JP5538136B2 - 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 - Google Patents
偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5538136B2 JP5538136B2 JP2010181437A JP2010181437A JP5538136B2 JP 5538136 B2 JP5538136 B2 JP 5538136B2 JP 2010181437 A JP2010181437 A JP 2010181437A JP 2010181437 A JP2010181437 A JP 2010181437A JP 5538136 B2 JP5538136 B2 JP 5538136B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- lens
- lens frame
- optical axis
- barrel
- lens barrel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
- G02B7/02—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
- G02B7/023—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses permitting adjustment
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/62—Optical apparatus specially adapted for adjusting optical elements during the assembly of optical systems
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lens Barrels (AREA)
Description
11 固定筒
12 中央固定筒
14 前側固定筒
16 後側固定筒
16A 外側円筒部
16B 内側円筒部
17 移動筒
20 フォーカス光学系
22 ズーム光学系
24 アイリス
26 マスター光学系
20A 固定フォーカスレンズ群
20B 移動フォーカスレンズ群
22A 変倍系レンズ群
22B 補正系レンズ群
26A 前側マスターレンズ群
26B 後側マスターレンズ群
50 レンズ枠
52、54 間隔環
60 フランジ部
60A 前側壁面
60B 後側壁面
62 突部
70 突条部
72 垂直面
74 傾斜面
80 板バネ
82 押さえ環
90、90A、90B 貫通孔
G1、G2、G3、G3′ レンズ
Claims (4)
- レンズ鏡筒の光学系を構成する所定のレンズを保持するレンズ枠と、
前記レンズ鏡筒の固定筒にネジ結合され、前記固定筒に前記レンズ枠を光軸周りに回動可能に支持させるために前記レンズ枠の所定部位を前記固定筒の所定部位とで狭持する押さえ環と、
前記レンズ枠の外周面に突出形成される係合部であって、前記レンズ枠の外周面の周方向に所定間隔おきに複数形成される係合部と、
前記レンズ鏡筒の少なくとも前記固定筒の外側から前記係合部の位置まで貫通するように径方向に設けられ、前記係合部の周方向側の側面と係合して前記レンズ枠を光軸周りに回転させて前記レンズ枠に保持されたレンズの偏心調整を行うための工具が挿入される工具挿通孔と、
前記係合部の周方向側の側面であって、前記固定筒にネジ結合された前記押さえ環を弛める回転方向側に形成されると共に、前記押さえ環を締め込む回転方向への前記レンズ枠の回転を可能にするために前記工具と係合可能に形成された係合面と、
前記係合部の周方向側の側面であって、前記固定筒にネジ結合された前記押さえ環を締め込む回転方向側に形成されると共に、前記押さえ環を弛める回転方向への前記レンズ枠の回転を不能にするために前記工具と係合不能に形成された非係合面と、
を備え、
前記係合面は、前記レンズ枠の外周面に対して略垂直な垂直面であり、
前記非係合面は、前記レンズ枠の外周面に対して垂直な方向から斜めに傾斜した傾斜面であって、前記レンズ枠の外周面から離れる程、前記垂直面との間隔が狭まる傾斜面であることを特徴とする偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒。 - 前記非係合面は、前記レンズ枠の外周面に対して垂直な方向から斜め約45度傾斜した傾斜面であることを特徴とする請求項1記載の偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒。
- 前記工具挿通孔は、前記レンズ鏡筒を偏心調整のための測定装置に設置した状態において、光軸よりも上方の位置で、かつ、前記押さえ環を締め込む回転方向に前記レンズ枠を回転させるときに前記係合部が上から下に向かって移動する位置に形成されることを特徴とする請求項1又は2記載の偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒。
- 前記工具挿通孔は、光軸に直交する断面において光軸上の点からみた方位角にして隣接する前記係合部の間隔角度に略一致する範囲に形成されたことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項記載の偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2010181437A JP5538136B2 (ja) | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 |
| EP11177321.4A EP2418527B1 (en) | 2010-08-13 | 2011-08-11 | Lens barrel having an eccentricity adjusting mechanism |
| US13/208,782 US8400723B2 (en) | 2010-08-13 | 2011-08-12 | Lens barrel having an eccentricity adjusting mechanism |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2010181437A JP5538136B2 (ja) | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2012042542A JP2012042542A (ja) | 2012-03-01 |
| JP5538136B2 true JP5538136B2 (ja) | 2014-07-02 |
Family
ID=44677481
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2010181437A Expired - Fee Related JP5538136B2 (ja) | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8400723B2 (ja) |
| EP (1) | EP2418527B1 (ja) |
| JP (1) | JP5538136B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6558093B2 (ja) * | 2015-06-22 | 2019-08-14 | セイコーエプソン株式会社 | 投写光学系及びプロジェクター |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3500438B2 (ja) * | 1995-11-28 | 2004-02-23 | 株式会社ニコン | レンズ鏡筒 |
| JPH11174301A (ja) | 1997-12-17 | 1999-07-02 | Canon Inc | レンズ装置およびこれを備えた光学機器 |
| JP2000075182A (ja) * | 1998-08-28 | 2000-03-14 | Fuji Photo Optical Co Ltd | レンズ鏡筒及びレンズ鏡筒の偏心調整装置 |
| US6204979B1 (en) * | 1998-08-21 | 2001-03-20 | Fuji Photo Optical Co., Ltd. | Lens assembly and eccentricity adjustment apparatus thereof |
| JP2000066076A (ja) | 1998-08-21 | 2000-03-03 | Fuji Photo Optical Co Ltd | レンズ鏡筒 |
| JP2000075183A (ja) * | 1998-08-28 | 2000-03-14 | Canon Inc | 撮影用レンズの調整機構 |
| JP4612764B2 (ja) * | 2000-05-30 | 2011-01-12 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒および光学機器 |
| JP4571839B2 (ja) * | 2004-09-02 | 2010-10-27 | Hoya株式会社 | 偏心調整機構を有するレンズ鏡筒 |
| JP4817876B2 (ja) * | 2006-02-20 | 2011-11-16 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒およびカメラシステム |
-
2010
- 2010-08-13 JP JP2010181437A patent/JP5538136B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-08-11 EP EP11177321.4A patent/EP2418527B1/en not_active Not-in-force
- 2011-08-12 US US13/208,782 patent/US8400723B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US8400723B2 (en) | 2013-03-19 |
| JP2012042542A (ja) | 2012-03-01 |
| US20120038992A1 (en) | 2012-02-16 |
| EP2418527B1 (en) | 2014-03-19 |
| EP2418527A1 (en) | 2012-02-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7815379B2 (en) | Lens apparatus focus adjustment support device and focus adjusting method | |
| JP5600440B2 (ja) | 監視カメラ用レンズ装置 | |
| JP7770900B2 (ja) | レンズ装置および撮像装置 | |
| JP5538135B2 (ja) | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 | |
| JP2000066076A (ja) | レンズ鏡筒 | |
| US10495841B2 (en) | Lens barrel and imaging device | |
| WO2017115465A1 (ja) | レンズ鏡筒およびこれを備えたカメラ | |
| JP5538136B2 (ja) | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 | |
| US8743472B2 (en) | Lens device | |
| JP2006301290A (ja) | レンズ鏡胴 | |
| JP6500240B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |
| US8498060B2 (en) | Lens barrel | |
| JP2008046440A (ja) | フォーカス調整機構を備えたレンズ鏡筒 | |
| JP2018189788A (ja) | レンズ鏡筒および光学機器 | |
| JP2008065164A (ja) | レンズ鏡胴 | |
| JP6669025B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |
| JP7551297B2 (ja) | レンズ装置および撮像装置 | |
| JP6508932B2 (ja) | レンズ鏡筒および光学機器 | |
| JP2007219023A (ja) | レンズ鏡胴 | |
| JP2012042540A (ja) | 偏心調整機構を備えたレンズ鏡筒 | |
| JP2023000443A (ja) | レンズ鏡筒及びそれを有する撮像装置 | |
| JP3962470B2 (ja) | レンズ鏡筒およびカメラ | |
| WO2012128202A1 (ja) | レンズ装置 | |
| JP4660141B2 (ja) | ズームレンズ鏡筒 | |
| JP2005043494A (ja) | バリフォーカルレンズ |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20111216 |
|
| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20121005 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130118 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131220 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140121 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140314 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140401 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5538136 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140428 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |