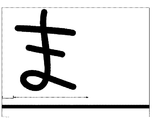JP4995056B2 - 画像表示装置、その制御方法、及びプログラム - Google Patents
画像表示装置、その制御方法、及びプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP4995056B2 JP4995056B2 JP2007315801A JP2007315801A JP4995056B2 JP 4995056 B2 JP4995056 B2 JP 4995056B2 JP 2007315801 A JP2007315801 A JP 2007315801A JP 2007315801 A JP2007315801 A JP 2007315801A JP 4995056 B2 JP4995056 B2 JP 4995056B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- input
- image
- character
- unit
- display unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- User Interface Of Digital Computer (AREA)
- Processing Or Creating Images (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
Description
また、横罫線としての利用を選択し、入力領域としては跨った領域を指定した場合は、図16(b)のように、拡大領域(入力領域)はガイド線103の上側と下側とで均等となる。また、横罫線としての利用を選択し、入力領域としては上側を指定した場合は、図16(c)のように、拡大領域(入力領域)はガイド線103の上側が広く下側が狭くなる。
拡大表示画面102の横幅=(予測文字間隔×3+予測文字サイズ×2)×Z
なお、図17では、符号301で示した領域が文字間隔に対応し、符号302で示した領域が文字入力領域(すなわち文字サイズ)に対応している。また、数式1における予測文字サイズ・文字間隔は、ステップS205において拡大用情報テーブルに「予測値」として設定されたものであり、拡大処理後の値を示すものではない。
また、ステップS212では、主制御部1101は、ステップS210の処理で文字サイズを変更した場合は、その変更に係る文字サイズを上記の文字分のサイズとして用いる。
101…全体表示画面
102…拡大表示画面
103…ガイド線
104…切出枠
1101…主制御部
1105…表示部
1150…拡大画像処理部
1154…拡大率算出部
1155…拡大処理部
1156…回転処理部
1160…全体画像処理部
1162…切出枠設定部
Claims (10)
- 画像の全体を表示する全体表示部と、
前記全体表示部に表示中の画像の一部分を表示する部分表示部と、
前記全体表示部に表示中の画像における座標位置を指定する位置指定手段と、
前記全体表示部に表示中の画像に対し前記位置指定手段を用いて入力された線分の一部を含み、当該表示中の画像の一部分を切出し、切出した画像の領域を示す切出枠を前記全体表示部に表示する切出手段と、
前記切出手段により切出された画像を前記部分表示部に拡大表示させる第1の表示制御手段と、
前記部分表示部に表示中の画像に対して文字を入力するための入力手段と、
前記入力手段により文字が入力されたことに応じて、前記切出手段での切出しの対象となる画像の領域を、前記位置指定手段を用いて入力された線分に沿って移動させる移動制御手段と、
前記位置指定手段を用いて入力される線分または前記入力手段により入力される文字の太さを、ペンの太さとして、ユーザに選択させるための選択手段と、
前記ペンの太さ毎に、文字サイズと文字間隔が登録されたデータベースと、
前記選択手段にてユーザにより選択されたペンの太さと前記データベースとを用いて、ユーザが入力する文字の文字サイズと文字間隔を予測する予測する予測手段とを備え、
前記切出手段は、前記予測手段により予測した文字サイズと文字間隔に基づいて、前記切出枠を決定することを特徴とする画像表示装置。 - 前記切出手段により切出された画像を回転する回転手段をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
- 前記回転手段は、前記部分表示部に表示中の画像の天地方向と前記入力手段による入力文字の天地方向とが、前記位置指定手段を用いて入力された線分について指定された罫線としての方向との関係で一致するように回転処理を行うことを特徴とする請求項2に記載の画像表示装置。
- 前記部分表示部に表示中の画像に対して前記入力手段を用いて入力された文字を縮小して前記全体表示部に表示させる第2の表示制御手段を有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像表示装置。
- 前記選択手段にて選択されたペンの太さと、前記予測手段により予測された文字サイズ、文字間隔に基づいて、前記データベースを更新する更新手段をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
- 前記切出手段は、少なくとも直前に入力された1つの文字の領域と、少なくとも次の1つの文字を入力するための入力予定領域とを前記線分に沿って切出すことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
- 前記移動制御手段は、前記入力予定領域への手書き文字の入力が完了した場合に、前記切出手段での切出しの対象となる画像の領域を移動させることを特徴とする請求項6に記載の画像表示装置。
- 前記部分表示部において前記位置指定手段を用いて入力された線分の終端位置まで前記入力手段により文字が入力された場合に、前記部分表示部の表示内容と、前記全体表示部に表示中の前記線分を消去する消去手段をさらに有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像表示装置。
- 画像の全体を表示する全体表示部と、前記全体表示部に表示中の画像の一部分を表示する部分表示部とを有する画像表示装置の制御方法であって、
前記全体表示部に表示中の画像における座標位置を指定する位置指定工程と、
前記全体表示部に表示中の画像に対し位置指定工程にて入力された線分の一部を含み、当該表示中の画像の一部分を切出し、切出した画像の領域を示す切出枠を前記全体表示部に表示する切出工程と、
前記切出工程により切出された画像を前記部分表示部に拡大表示させる第1の表示制御工程と、
前記部分表示部に表示中の画像に対して文字を入力するための入力工程と、
前記入力工程にて文字が入力されたことに応じて、前記切出工程での切出しの対象となる画像の領域を、前記位置指定工程にて入力された線分に沿って移動させる移動制御工程と、
前記位置指定工程にて入力される線分または前記入力工程にて入力される文字の太さを、ペンの太さとして、ユーザに選択させるための選択工程と、
前記選択工程にてユーザにより選択されたペンの太さと前記ペンの太さ毎に、文字サイズと文字間隔が登録されたデータベースとを用いて、ユーザが入力する文字の文字サイズと文字間隔を予測する予測する予測工程とを備え、
前記切出工程は、前記予測工程にて予測した文字サイズと文字間隔に基づいて、前記切出枠を決定することを特徴とする画像表示装置の制御方法。 - 請求項9に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007315801A JP4995056B2 (ja) | 2007-12-06 | 2007-12-06 | 画像表示装置、その制御方法、及びプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007315801A JP4995056B2 (ja) | 2007-12-06 | 2007-12-06 | 画像表示装置、その制御方法、及びプログラム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2009140223A JP2009140223A (ja) | 2009-06-25 |
| JP2009140223A5 JP2009140223A5 (ja) | 2011-01-20 |
| JP4995056B2 true JP4995056B2 (ja) | 2012-08-08 |
Family
ID=40870770
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007315801A Expired - Fee Related JP4995056B2 (ja) | 2007-12-06 | 2007-12-06 | 画像表示装置、その制御方法、及びプログラム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4995056B2 (ja) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5299349B2 (ja) * | 2010-04-30 | 2013-09-25 | ブラザー工業株式会社 | 入力制御装置、入力制御方法及び入力制御プログラム |
| JP2012003189A (ja) * | 2010-06-21 | 2012-01-05 | Sony Corp | 画像表示装置、画像表示方法およびプログラム |
| JP5740888B2 (ja) * | 2010-09-28 | 2015-07-01 | 株式会社ニコン | 画像処理装置、電子カメラ及びプログラム |
| JP5683375B2 (ja) * | 2011-05-02 | 2015-03-11 | シャープ株式会社 | 表示装置および表示プログラム |
| JP5884294B2 (ja) * | 2011-05-19 | 2016-03-15 | 日本電気株式会社 | コンテンツ表示装置、コンテンツ表示システム、サーバ、端末、コンテンツ表示方法、および、コンピュータ・プログラム |
| JP5901163B2 (ja) * | 2011-07-08 | 2016-04-06 | シャープ株式会社 | 加熱調理器 |
| JP5886662B2 (ja) * | 2012-03-16 | 2016-03-16 | シャープ株式会社 | 画像表示装置 |
| JP5664719B2 (ja) * | 2013-07-24 | 2015-02-04 | ブラザー工業株式会社 | 印刷装置、合成画像データ生成装置、及び、合成画像データ生成プログラム |
| JP7180323B2 (ja) * | 2018-11-29 | 2022-11-30 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 表示装置、表示方法および表示システム |
| CN112286430B (zh) * | 2020-10-29 | 2022-07-05 | 维沃移动通信有限公司 | 图像处理方法、装置、设备及介质 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0635651A (ja) * | 1992-07-21 | 1994-02-10 | Hitachi Ltd | 情報処理装置 |
| JPH0736607A (ja) * | 1993-07-16 | 1995-02-07 | Sony Corp | 手書き文字入力装置 |
| JPH0764998A (ja) * | 1993-08-25 | 1995-03-10 | Toshiba Corp | 文書作成装置及び文字軌跡入力方法 |
| JPH08115438A (ja) * | 1994-10-18 | 1996-05-07 | Hitachi Ltd | 図表示装置 |
| JPH08335277A (ja) * | 1995-06-07 | 1996-12-17 | Casio Comput Co Ltd | 図形処理装置 |
| JPH10340075A (ja) * | 1997-06-06 | 1998-12-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 画像表示方法 |
-
2007
- 2007-12-06 JP JP2007315801A patent/JP4995056B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2009140223A (ja) | 2009-06-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4995056B2 (ja) | 画像表示装置、その制御方法、及びプログラム | |
| JP4742132B2 (ja) | 入力装置、画像処理プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 | |
| JP4762070B2 (ja) | 手書き入力装置、手書き入力方法、及びコンピュータプログラム | |
| JP5429060B2 (ja) | 表示制御装置、表示制御方法、表示制御プログラム並びにこの表示制御プログラムが記録された記録媒体 | |
| JP4611031B2 (ja) | 手書き入力装置及び方法 | |
| RU2371753C2 (ru) | Автоматическая регулировка высоты для электронных перьев и координатно-указательных устройств типа "мышь", служащих для выделения информации на экране дисплея | |
| US20130080979A1 (en) | Explicit touch selection and cursor placement | |
| EP2759919A2 (en) | Methods and devices for simultaneous multi-touch input | |
| US9594432B2 (en) | Electronic device, control setting method and program | |
| US20060288312A1 (en) | Information processing apparatus and recording medium storing program | |
| JP6125467B2 (ja) | プリント注文受付機とその作動方法および作動プログラム | |
| JP5400578B2 (ja) | 表示制御装置、及びその制御方法 | |
| EP2613228A1 (en) | Display apparatus and method of editing displayed letters in the display apparatus | |
| US20150012884A1 (en) | Edit processing apparatus and storage medium | |
| US7742095B2 (en) | Information processing apparatus, method and storage medium | |
| JPH064607A (ja) | データ表示装置 | |
| JP6274132B2 (ja) | 楽譜表示装置および楽譜表示方法 | |
| JP2007122286A (ja) | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法及びその制御方法を実行させるプログラム | |
| JP2001042992A (ja) | 手書き文字処理装置および方法 | |
| JP6800714B2 (ja) | 電子機器および表示制御方法 | |
| US9940914B2 (en) | Score displaying method and storage medium | |
| JP5779422B2 (ja) | 表示システムおよび表示プログラム | |
| JP2007334691A (ja) | 情報処理装置及び表示方法 | |
| JP4441966B2 (ja) | 手書き文字入力装置及びそれを実現するためのプログラムを記録した記録媒体 | |
| JP5066877B2 (ja) | 画像表示装置、画像表示方法、およびプログラム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101129 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20101129 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120120 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120124 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120326 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120410 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120509 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150518 Year of fee payment: 3 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150518 Year of fee payment: 3 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |