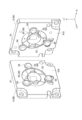JP7392530B2 - 拡散装置、光学装置及びプロジェクター - Google Patents
拡散装置、光学装置及びプロジェクター Download PDFInfo
- Publication number
- JP7392530B2 JP7392530B2 JP2020042696A JP2020042696A JP7392530B2 JP 7392530 B2 JP7392530 B2 JP 7392530B2 JP 2020042696 A JP2020042696 A JP 2020042696A JP 2020042696 A JP2020042696 A JP 2020042696A JP 7392530 B2 JP7392530 B2 JP 7392530B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- lens
- light
- section
- diffusion
- pressing member
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 title claims description 140
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 106
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 100
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 53
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 30
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 24
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 15
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 14
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 8
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 8
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 6
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 5
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 5
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N novaluron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(OC(F)(F)F)F)=CC=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 2
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
- G02B7/02—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
- G02B7/026—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses using retaining rings or springs
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/09—Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
- G02B27/0927—Systems for changing the beam intensity distribution, e.g. Gaussian to top-hat
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/20—Lamp housings
- G03B21/2006—Lamp housings characterised by the light source
- G03B21/2033—LED or laser light sources
- G03B21/204—LED or laser light sources using secondary light emission, e.g. luminescence or fluorescence
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B19/00—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
- G02B19/0033—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
- G02B19/0047—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/09—Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
- G02B27/0938—Using specific optical elements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/02—Diffusing elements; Afocal elements
- G02B5/0273—Diffusing elements; Afocal elements characterized by the use
- G02B5/0278—Diffusing elements; Afocal elements characterized by the use used in transmission
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/145—Housing details, e.g. position adjustments thereof
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/20—Lamp housings
- G03B21/208—Homogenising, shaping of the illumination light
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Projection Apparatus (AREA)
- Securing Globes, Refractors, Reflectors Or The Like (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Description
しかしながら、特許文献1に記載の光源装置では、第1の集光光学系を構成する2つのピックアップレンズは、本体部に固定され、蛍光体層は、本体部に固定される基板に支持されている。このため、本体部の公差及び基板の公差によって、ピックアップレンズと蛍光体層との間の距離がばらつくおそれがあった。そして、ピックアップレンズと蛍光体層との間の距離が適切な値でない場合には、光源装置の光学性能が低下するおそれがあった。
[プロジェクターの概略構成]
図1は、本実施形態に係るプロジェクター1の概略構成を示す模式図である。
本実施形態に係るプロジェクター1は、光源から出射された光を変調して画像情報に応じた画像を形成し、形成された画像をスクリーン等の被投射面に拡大投射する。プロジェクター1は、図1に示すように、外装筐体2及び画像投射部3を備える。この他、図示を省略するが、プロジェクター1は、プロジェクター1を構成する電子部品に電力を供給する電源部、プロジェクター1の動作を制御する制御部、及び、プロジェクター1を構成する冷却対象を冷却する冷却部を備える。
外装筐体2は、プロジェクター1の外装を構成し、画像投射部3、電源部、制御部及び冷却部を内部に収容する。
外装筐体2は、正面部21、背面部22、左側面部23及び右側面部24を有する。図示を省略するが、外装筐体2は、各面部21~24における一方の端部間を接続する天面部と、各面部21~24における他方の端部間を接続する底面部と、を有する。外装筐体2は、例えば略直方体形状に形成される。
正面部21は、正面部21における略中央に位置する通過口211を有する。後述する投射光学装置36から投射された光は、通過口211を通過する。
正面部21は、正面部21における左側面部23側に位置する排気口212を有する。排気口212は、外装筐体2内に設けられた冷却対象を冷却した空気を、外装筐体2の外部に排出する。
図示を省略するが、+X方向の反対方向を-X方向とし、+Y方向の反対方向を-Y方向とし、+Z方向の反対方向を-Z方向とする。
画像投射部3は、制御部から入力される画像情報に応じた画像を形成し、形成された画像を投射する。画像投射部3は、光源装置4、均一化部31、色分離部32、リレー部33、画像形成部34、光学部品用筐体35及び投射光学装置36を備える。
なお、光源装置4の構成については、後に詳述する。
色分離部32は、均一化部31から入射される光を赤、緑及び青の各色光に分離する。色分離部32は、2つのダイクロイックミラー321,322と、ダイクロイックミラー321によって分離された青色光を反射させる反射ミラー323と、を備える。
色合成部346は、光変調装置343B,343G,343Rによって変調された3つの色光を合成して画像を形成し、形成した画像を投射光学装置36に出射する。本実施形態では、色合成部346は、クロスダイクロイックプリズムによって構成されているが、これに限らず、例えば複数のダイクロイックミラーによって構成することも可能である。
図2は、光源装置4の構成を示す模式図である。
光源装置4は、光変調装置343を照明する光を均一化部31に出射する。光源装置4は、図2に示すように、光源部41、拡散透過部42、光分離部43、第1集光レンズ44、第2集光レンズ45、波長変換部46、第3集光レンズ47、第4集光レンズ48、拡散反射部49及び位相差部50と、筐体7と、を備える。
なお、詳しくは後述するが、第2集光レンズ45及び波長変換部46は、拡散装置6に含まれる第1拡散装置6Aを構成し、第4集光レンズ48及び拡散反射部49は、拡散装置6に含まれる第2拡散装置6Bを構成する。すなわち、光源装置4は、光源部41、拡散透過部42、光分離部43、第1集光レンズ44、第1拡散装置6A、第3集光レンズ47、第2拡散装置6B及び位相差部50と、筐体7と、を備える。
また、光源部41を除く光源装置4の構成は、光源411から出射された光が入射する光学装置DVを構成する。光学装置DVの構成のうち、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bを除く構成は、光源部41から出射された光を第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bに導く導光装置GDである。すなわち、光学装置DVは、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bと、導光装置GDと、を備える。
光分離部43、第3集光レンズ47、第4集光レンズ48、拡散反射部49及び位相差部50は、光源装置4に設定され、かつ、照明光軸Ax1に直交する照明光軸Ax2上に配置されている。すなわち、光分離部43は、照明光軸Ax1と照明光軸Ax2との交差部に配置されている。
なお、照明光軸Ax2は、レンズアレイ311の位置にて、照明光軸Axと一致する。換言すると、照明光軸Ax2は、照明光軸Axの延長線上に設定されている。
光源部41は、光を出射する光源411及びコリメーターレンズ412を備える。
光源411は、図示を省略するが、青色光を出射する複数の半導体レーザーによって構成されている。
コリメーターレンズ412は、光源411から出射された光を平行化する。
拡散透過部42は、入射された光を通過させる過程にて拡散させて、出射される光の照度分布を均一化する。拡散透過部42は、ホログラムを有する構成、複数の小レンズが光軸直交面に配列された構成、及び、光が通過する面が粗面である構成を例示できる。
なお、拡散透過部42に代えて、一対のマルチレンズアレイを有するホモジナイザー光学素子を採用してもよい。一方、拡散透過部42が採用される場合には、ホモジナイザー光学素子が採用される場合に比べて、光源部41から光分離部43までの距離を短縮できる。
拡散透過部42から出射された光は、光分離部43に入射する。
光分離部43は、光源部41から拡散透過部42を介して入射される光のうち、一部の光を通過させ、残りの光を反射させるハーフミラーの機能を有する。この他、光分離部43は、拡散反射部49から入射される青色光を通過させ、波長変換部46から入射され、青色光の波長よりも長い波長を有する光を反射させるダイクロイックミラーの機能を有する。
詳述すると、光分離部43は、拡散透過部42から入射される青色光のうち、一部の青色光である第1部分光を通過させて第1集光レンズ44に入射させ、残りの青色光である第2部分光を反射させて第3集光レンズ47に入射させる。
本実施形態では、波長変換部46における光の吸収を考慮して、光分離部43は、第1部分光の光量を、第2部分光の光量よりも大きくしている。しかしながら、これに限らず、第1部分光の光量は、第2部分光の光量と同じでもよく、第2部分光の光量よりも小さくてもよい。
第1集光レンズ44及び第2集光レンズ45は、光分離部43を通過した第1部分光を波長変換部46に集光する。また、第1集光レンズ44及び第2集光レンズ45は、波長変換部46から入射される蛍光を平行化する。
第1集光レンズ44及び第2集光レンズ45のうち、波長変換部46に近い第2集光レンズ45は、本開示の第1レンズに相当し、後述する第1拡散装置6Aを構成する。第1集光レンズ44及び第2集光レンズ45のうち、波長変換部46から遠い第1集光レンズ44は、本開示の第1拡散装置用第2レンズに相当し、筐体7のレンズ取付部82に取り付けられる。
本実施形態では、第1集光レンズ44は、+Z方向に位置する曲面44Aと、-Z方向に位置する曲面44Bと、第1集光レンズ44の光軸を中心として径方向外側に突出するフランジ44Cと、を有する。本実施形態では、曲面44Aは、+Z方向に突出する凸曲面である。
波長変換部46は、第1拡散装置6Aにおいて後述する拡散部65を構成する。波長変換部46は、入射される光の波長を変換した光を、入射される光の入射方向とは反対方向に拡散させて出射する。詳述すると、波長変換部46は、青色光が入射されることによって励起されて、入射された青色光よりも波長が長い蛍光を第2集光レンズ45に向けて拡散させて出射する。換言すると、波長変換部46は、入射された光の波長を変換し、変換された光を拡散させて出射する。波長変換部46から出射される光は、例えば、ピーク波長が500~700nmの蛍光である。
波長変換部46は、波長変換層461及び反射層462を有する。波長変換層461は、入射される青色光の波長を変換した非偏光光である蛍光を拡散して出射する蛍光体を含む。反射層462は、波長変換層461に対して青色光の入射側とは反対側に位置し、波長変換層461から入射される蛍光を波長変換層461側に反射させる。
波長変換部46から出射された蛍光は、照明光軸Ax1に沿って第2集光レンズ45及び第1集光レンズ44を通過した後、光分離部43に入射される。光分離部43に入射された蛍光は、光分離部43にて照明光軸Ax2に沿う方向に反射されて、位相差部50に入射される。
第3集光レンズ47及び第4集光レンズ48は、光分離部43にて反射されて入射される第2部分光を拡散反射部49に集光する。また、第3集光レンズ47及び第4集光レンズ48は、拡散反射部49から入射される青色光を平行化する。
なお、第3集光レンズ47及び第4集光レンズ48のうち、拡散反射部49に近い第4集光レンズ48は、本開示の第1レンズに相当し、後述する第2拡散装置6Bを構成する。第3集光レンズ47及び第4集光レンズ48のうち、拡散反射部49から遠い第3集光レンズ47は、本開示の第2拡散装置用第2レンズに相当し、筐体7のレンズ取付部83に固定される。
本実施形態では、第3集光レンズ47は、+X方向に位置する曲面47Aと、-X方向に位置する曲面47Bと、第3集光レンズ47の光軸を中心として径方向外側に突出するフランジ47Cと、を有する。本実施形態では、曲面47Aは、+X方向に突出する凸曲面である。
拡散反射部49は、第2拡散装置6Bにおいて後述する拡散部65を構成する。拡散反射部49は、波長変換部46から出射される蛍光と同様の拡散角で、入射された青色光を反射して拡散させる。すなわち、拡散反射部49は、入射された光の波長を変換せずに、入射される光を反射して拡散させる。
拡散反射部49にて反射された青色光は、第4集光レンズ48及び第3集光レンズ47を通過した後、光分離部43を通過して、位相差部50に入射される。すなわち、光分離部43から位相差部50に入射される光は、青色光及び蛍光が混在した白色光である。
位相差部50は、光分離部43から入射される白色光をs偏光及びp偏光が混在する光に変換する。このように変換された白色の照明光は、上記した均一化部31に入射される。
図3は、外部からの光の入射側から見た拡散装置6を示す斜視図であり、図4は、拡散装置6を示す分解斜視図である。
以下、拡散装置6の構成について詳述する。
拡散装置6は、光源装置4に採用される第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bの基本構成を有するものであり、入射される光を拡散させるものである。
拡散装置6は、図3及び図4に示すように、基板61、レンズ62、押圧部材63及び固定部材64を備える他、図4に示すように、拡散部65を備える。
なお、拡散装置6において、互いに直交する三方向を+L方向、+M方向及び+N方向とする。これらのうち、+N方向を拡散装置6に入射される光の進行方向とする。また、+L方向の反対方向を-L方向とし、+M方向の反対方向を-M方向とし、+N方向の反対方向を-N方向とする。
基板61は、例えば熱伝導性を有する金属によって板状に形成されており、レンズ62、押圧部材63、固定部材64及び拡散部65を支持するとともに、拡散部65から伝達される熱を外部に放熱する。
基板61は、図4に示すように、第1凹部611、第2凹部612、第3凹部613、複数の固定部614及び複数の取付部615を有する。
第1凹部611は、面61Aの略中央に位置する。第1凹部611は、-N方向から見て略円形状に形成されている。第1凹部611は、+N方向に直交する第1底面611Aと、第1底面611Aの周縁から-N方向に起立する第1側面611Bと、を有する。
第1底面611Aには、拡散部65が配置される。
第2凹部612は、+N方向に直交する第2底面612Aと、第2底面612Aの周縁から-N方向に起立する第2側面612Bと、を有する。
第2底面612Aは、第1側面611Bにおける-N方向の端部と接続される。第2底面612Aには、レンズ62が配置される平坦面である。
第2側面612Bは、+L方向及び-L方向に凹む部位を有する。しかしながら、このような部位は無くてもよく、第2凹部612は、-N方向から見て略円形状に形成されていてもよい。
第3凹部613は、+N方向に直交する第3底面613Aと、第3底面613Aの周縁から-N方向に起立する第3側面613Bと、を有する。
第3底面613Aは、第2側面612Bにおける-N方向の端部と接続される。第3底面613Aには、図3に示すように、押圧部材63が配置される。
図4に示すように、第2凹部612は、第3凹部613の第3底面613Aに設けられ、第1凹部611は、第2凹部612の第2底面612Aに設けられている。
各固定部614は、ねじ孔6141を有し、ねじ孔6141には、押圧部材63を基板61に固定する固定部材64が固定される。
取付部615は、筐体7に拡散装置6を固定する固定具FMが挿通する孔部6151を有する。
レンズ62は、拡散装置6に入射される光を、第1底面611Aに配置される拡散部65に集光する。また、レンズ62は、拡散部65から-N方向に出射された光を-N方向に通過させる過程にて平行化する。
レンズ62は、曲面62Aと、曲面62Aとは反対側に位置する平坦面62Bと、を有する。レンズ62は、曲面62Aが-N方向を向き、平坦面62Bが第2底面612Aと接触するように、第2凹部612に配置される。このように、平坦面62Bと第2底面612Aとが接触するように、レンズ62が基板61に配置された場合には、第1凹部611内の空間は、レンズ62によって閉塞されて密閉される。
なお、本実施形態では、レンズ62の曲面62Aは、-N方向に突出する凸曲面である。しかしながら、これに限らず、レンズ62における-N方向の面は、凹曲面であってもよく、平面であってもよい。
このようなレンズ62は、押圧部材63によって基板61に固定される。すなわち、レンズ62は、接着剤を用いずに、押圧部材63によって基板61に固定される。
押圧部材63は、線材を折曲加工して形成されたばねであり、レンズ62を第2底面612Aに押圧して固定する枠状部材である。押圧部材63は、中心から周方向に120°ずつ等間隔に位置する3つの当接部631と、3つの当接部631のそれぞれから外側に延出する6つの延出部632と、6つの延出部632のうち、同方向に延出する2つの延出部632における延出方向先端部に位置する3つの被固定部633と、を有する。
3つの当接部631のそれぞれは、レンズ62の曲面62Aに当接して、レンズ62を第2底面612Aに押圧する。すなわち、押圧部材63は、曲面62Aの複数箇所に当接して、レンズ62を第2底面612Aに押圧して固定する。
3つの被固定部633は、固定部材64によって固定部614に固定される。すなわち、押圧部材63は、第3底面613Aに固定されている。
本実施形態では、固定部材64は、ねじ孔6141に固定されるねじである。しかしながら、固定部材64は、ねじとは異なる固定具であってもよい。
拡散部65は、レンズ62によって密閉される第1凹部611の第1底面611Aに配置される。拡散部65は、光を拡散させる。本実施形態では、拡散部65は、拡散部65に対する光の入射方向とは反対方向に光を拡散させる。
拡散部65としては、上記した波長変換部46及び拡散反射部49を例示できる。
図5は、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bを示す斜視図である。
拡散装置6は、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bを含む。第1拡散装置6Aと第2拡散装置6Bとは、図5に示すように、レンズ62及び拡散部65の構成が異なる他は、それぞれ同じ構成を有する。
すなわち、第1拡散装置6Aは、基板61、押圧部材63及び複数の固定部材64の他、レンズ62として第2集光レンズ45を有し、拡散部65として波長変換部46を有する。第2拡散装置6Bは、基板61、押圧部材63及び複数の固定部材64の他、レンズ62として第4集光レンズ48を有し、拡散部65として拡散反射部49を有する。なお、拡散反射部49は、第1底面611Aに設けられる拡散反射層により構成してもよく、第1底面611Aに形成される微小な凹凸によって構成してもよい。
ここで、第1拡散装置6Aが備える押圧部材63及び固定部材64は、第1押圧部材及び第1固定部材に相当し、第2拡散装置6Bが備える押圧部材63及び固定部材64は、第2押圧部材及び第2固定部材に相当する。
そして、光源装置4は、図2に示したように、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bとして備える。
図6は、光源装置4の筐体7を示す斜視図である。図7は、筐体7を示す分解斜視図である。
筐体7は、光源装置4を構成する光源部41、拡散透過部42、光分離部43、第1集光レンズ44、第3集光レンズ47及び位相差部50を保持するとともに、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bが取り付けられる略立方体形状の光源用筐体である。
筐体7は、図6及び図7に示すように、筐体本体8及びカバー部材9を備える。
カバー部材9は、筐体本体8の後述する第4側面部814及び第5側面部815を覆うように、筐体本体8に取り付けられる。カバー部材9は、図7に示すように、第4側面部814を覆う部位に、位相差部50から出射された光が通過する開口部91が設けられている。開口部91は、図示しない透光性部材によって閉塞される。
筐体本体8は、図6及び図7に示すように、第1側面部811、第2側面部812、第3側面部813、第4側面部814、第5側面部815、台座部816を有する他、図7に示すように、レンズ取付部82,83と、後述する押圧部材84,85及び複数の固定部材86,87と、を有する。この他、図示を省略するが、筐体本体8は、拡散透過部42、光分離部43及び位相差部50のそれぞれが固定される固定部を有する。
第2側面部812は、筐体本体8において-Z方向に位置する側面部である。第2側面部812には、基板61の面61Aが第2側面部812に対向する向きにて、第1拡散装置6Aが、取付部615を挿通する固定具FMによって取り付けられる。このとき、第1拡散装置6Aは、+N方向が-Z方向と一致し、かつ、+L方向が+Y方向と一致するように、第2側面部812に固定される。
なお、第1拡散装置6Aの基板61と第2側面部812との間には、発泡樹脂等によって形成された封止部材SM1が介装される。
なお、第2拡散装置6Bの基板61と第3側面部813との間には、封止部材SM1と同様の封止部材SM2が介装される。
第4側面部814は、筐体本体8において+X方向に位置する側面部である。第4側面部814は、カバー部材9によって覆われる。
第5側面部815において、開口部8151の周囲には、封止部材SM1,SM2と同様の封止部材SM3が取り付けられる。第5側面部815には、封止部材SM3を覆うように、カバー部材9が取り付けられる。
台座部816は、図6及び図7に示すように、筐体本体8において-Y方向に位置し、外装筐体2の内面に固定される部位である。これにより、筐体7、ひいては、光源装置4が外装筐体2の内面に固定される。
図8は、-Z方向から見たレンズ取付部82を示す図である。図9は、筐体本体8、第1集光レンズ44、押圧部材84及び固定部材86を示す分解斜視図である。
レンズ取付部82は、筐体本体8において第2側面部812の内側に位置し、第1集光レンズ44が取り付けられる部位である。レンズ取付部82は、図8及び図9に示すように、第1凹部821、第2凹部822、第3凹部823、複数の固定部824及び複数の段差部825を有する。
第1底面821Aには、第1集光レンズ44のフランジ44Cにおける+Z方向の面が当接する。第1底面821Aの略中央には、第1集光レンズ44における曲面44Aの一部が配置される開口部8211が形成されている。
第2凹部822は、+Z方向に直交する第2底面822Aと、第2底面822Aの周縁から-Z方向に起立する第2側面822Bと、を有する。第2底面822Aは、第1側面821Bにおける-Z方向の端部と接続される。
第2凹部822には、押圧部材84が配置される。
第3凹部823は、+Z方向に直交する第3底面823Aと、第3底面823Aの周縁から-Z方向に起立する第3側面823Bと、を有する。
このように、第2凹部822は、第3凹部823の第3底面823Aに設けられ、第1凹部821は、第2凹部822の第2底面822Aに設けられている。
各固定部824は、図9に示すように、押圧部材84をレンズ取付部82に固定する固定部材86が固定されるねじ孔8241を有する。
複数の固定部材86は、押圧部材84をレンズ取付部82に固定する固定具であり、本実施形態では、ねじによって構成されている。
押圧部材84は、第1集光レンズ44において-Z方向に位置する曲面44Bに当接した状態にて、複数の固定部材86のそれぞれが対応するねじ孔8241に固定されることによって、レンズ取付部82に固定される。これにより、第1集光レンズ44は、図8に示すように、押圧部材84によって、第1底面821Aに押圧されて固定される。
第1拡散装置6Aが、第2側面部812に取り付けられた場合、複数の固定部材64のそれぞれは、図10に示すように、-Z方向から見て、複数の段差部825のうち対応する段差部825に配置される。
このとき、複数の固定部材64のそれぞれの中心は、-Z方向から見たときに、第1集光レンズ44の光軸ALを中心とする第1仮想円VC1上に位置する。また、複数の固定部材86のそれぞれの中心は、-Z方向から見たときに、光軸ALを中心とし、かつ、第1仮想円VC1の直径よりも大きい直径を有する第2仮想円VC2上に位置する。
更に、複数の固定部材64は、光軸ALを中心とする周方向において、複数の固定部材86のそれぞれの間に配置される。
これにより、複数の固定部材64を、第1集光レンズ44の外縁と複数の固定部材86との間、及び、複数の固定部材86のそれぞれの間に配置できる。従って、固定部材64が第1集光レンズ44と接触しない状態にて、複数の固定部材64及び複数の固定部材86を密に配置できる。
レンズ取付部83は、筐体本体8において第3側面部813の内側に位置し、第3集光レンズ47が取り付けられる部位である。レンズ取付部83は、レンズ取付部82と同様の構成を有する。すなわち、レンズ取付部83は、図11に示すように、第1凹部821、第2凹部822、第3凹部823、複数の固定部824及び複数の段差部825と同様の第1凹部831、第2凹部832、第3凹部833、複数の固定部834及び複数の段差部835を有する。第1凹部831は、第3集光レンズ47の一部が配置される開口部8311を有する。
レンズ取付部83には、対応する固定部834に固定される複数の固定部材86によってレンズ取付部83に固定される押圧部材85が固定され、押圧部材85が第3集光レンズ47を第1凹部831の第1底面に押圧して固定する。
このような構成により、第3集光レンズ47は、レンズ取付部83に固定される。
なお、レンズ取付部83は、2つの段差部835を有する他、第2凹部832の第2側面832Bから第3集光レンズ47側に突出する突出部832Cが設けられている点で、レンズ取付部82と相違する。しかしながら、これに限らず、レンズ取付部82,83のそれぞれは、同じ構成を備えていてもよい。
以上説明した本実施形態に係る拡散装置6は、以下の効果を奏し得る。
拡散装置6は、光を拡散させる拡散部65と、拡散部65が固定される基板61と、拡散部65に対向して基板61に固定される第1レンズとしてのレンズ62と、を備える。
レンズ62は、曲面62Aと、曲面62Aとは反対側に位置する平坦面62Bと、を有する。
基板61は、第1凹部611と、第2凹部612と、を備える。第1凹部611は、第1底面611Aと、第1底面611Aから-N方向に起立する第1側面611Bと、を有する。第2凹部612は、第1側面611Bと接続される第2底面612Aと、第2底面612Aから-N方向に起立する第2側面612Bと、を有する。
レンズ62は、平坦面62Bが第2底面612Aと当接するように、第2凹部612に配置される。拡散部65は、第1底面611Aに固定されている。
また、レンズ62の平坦面62Bが、第2底面612Aと当接するので、第1凹部611及び拡散部65とレンズ62とによって形成される第1凹部611内の空間を密閉できる。このため、拡散部65におけるレンズ62側の面に塵埃が付着することを抑制できる。従って、拡散装置6の防塵性能を高めることができる他、塵埃の付着によって拡散装置6の光学性能が低下することを抑制できる。
このような構成によれば、第3底面613Aに固定される押圧部材63によって、レンズ62が第2底面612Aに押圧されて固定されるので、押圧部材63を接着剤によって固定する必要がない。これによれば、接着剤が気化する等して、第1凹部611内にガスが発生することを抑制できる。従って、ガスによって拡散部65による光拡散性能が低下することを防止できる。
また、押圧部材63は、第3底面613Aに固定される。すなわち、押圧部材63は、第3凹部613内に配置されるので、レンズか62ら拡散部65に向かう方向である+N方向における拡散装置6の寸法が大きくなることを抑制できる。従って、拡散装置6の大型化を抑制できる。
このような構成によれば、押圧部材63を簡易に構成できる。また、押圧部材63が曲面62Aと当接してレンズ62を第2底面612Aに押圧するので、第1凹部611内の密閉状態を維持できる。
光学装置DVは、拡散装置6に含まれる第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bと、基板61が固定される筐体7と、第2レンズとしての第1集光レンズ44及び第3集光レンズ47と、第2押圧部材としての押圧部材84,85と、を備える。
第1集光レンズ44は、第1拡散装置6Aに第1レンズとして採用される第2集光レンズ45に対向して設けられる。第3集光レンズ47は、第2拡散装置6Bに第1レンズとして採用される第4集光レンズ48に対向して設けられる。
筐体7を構成する筐体本体8は、第1集光レンズ44が取り付けられるレンズ取付部82と、第3集光レンズ47が取り付けられるレンズ取付部83と、を有する。
押圧部材84は、筐体本体8に固定されて、第1集光レンズ44をレンズ取付部82に押圧し、押圧部材85は、筐体本体8に固定されて、第3集光レンズ47をレンズ取付部83に押圧する。
また、第1集光レンズ44及び第3集光レンズ47は、押圧部材84,85によってレンズ取付部82,83に押圧されて固定される。このため、接着剤を用いて第1集光レンズ44及び第3集光レンズ47を固定する必要がない。従って、ガスの発生を抑制でき、ガスが各集光レンズ44,45,47,48に付着することを抑制でき、光の利用効率が低下することを抑制できる。
拡散装置6は、基板61、第1レンズとしてのレンズ62、第1押圧部材としての押圧部材63、複数の第1固定部材としての複数の固定部材64と、拡散部65と、を備える。基板61には、拡散部65が固定される。レンズ62は、拡散部65に対向して基板61に固定される。押圧部材63は、レンズ62を基板61に押圧する。複数の固定部材64は、基板61に固定されて押圧部材63を保持する。
第1拡散装置6Aにおいて、レンズ62は、第2集光レンズ45であり、拡散部65は、波長変換部46である、第2拡散装置6Bにおいて、レンズ62は、第4集光レンズ48であり、拡散部65は、拡散反射部49である。
基板61は、第1凹部611と、第1凹部611を囲む第2凹部612と、を備える。
第1凹部611は、第1底面611Aと、第1底面611Aから-N方向に起立する第1側面611Bと、を有する。第2凹部612は、第1側面611Bと接続される第2底面612Aと、第2底面612Aから-N方向に起立する第2側面612Bを有する。
第1拡散装置6Aにおいて、第2集光レンズ45は、平坦面45Bが第2底面612Aと当接するように、押圧部材63に押圧されて第2凹部612に配置される。第2拡散装置6Bにおいて、第4集光レンズ48は、平坦面48Bが第2底面612Aと当接するように、押圧部材63に押圧されて第2凹部612内に配置される。
筐体7には、基板61が固定される。第1集光レンズ44は、第1レンズに相当する第2集光レンズ45に対向して筐体7に設けられる。第3集光レンズ47は、第1レンズに相当する第4集光レンズ48に対向して筐体7に設けられる。押圧部材84は、第1集光レンズ44を筐体7に押圧する。押圧部材85は、第3集光レンズ47を筐体7に押圧する。複数の固定部材86は、筐体7に固定されて押圧部材84を保持し、複数の固定部材87は、筐体7に固定されて押圧部材85を保持する。
また、第1拡散装置6Aの複数の固定部材64が第1集光レンズ44及び複数の固定部材86に接触しない状態で、複数の固定部材64,86を密に配置できる。同様に、第2拡散装置6Bの複数の固定部材64が第3集光レンズ47及び複数の固定部材87に接触しない状態で、複数の固定部材64,87を密に配置できる。従って、筐体7、ひいては、光学装置DVの大型化を抑制できる。
このような構成によれば、第1集光レンズ44に固定部材64が接触することを抑制できるので、第1集光レンズ44と第2集光レンズ45との距離を短くすることができる。同様に、第3集光レンズ47に固定部材64が接触することを抑制できるので、第3集光レンズ47と第4集光レンズ48との距離を短くすることができる。従って、段差部825が無い筐体7を備える場合に比べて、光学装置DVを小型化できる。
光源装置4は、光を出射する光源411と、光学装置DVと、を備える。
光学装置DVは、光源411から出射された光を第1部分光及び第2部分光に分離する光分離部43を備える。光源装置4が備える拡散装置6は、筐体7に固定され、第1部分光が拡散部65に入射される第1拡散装置6Aと、筐体7に固定され、第2部分光が拡散部65に入射される第2拡散装置6Bと、を含む。
第1拡散装置6Aの拡散部65は、入射される光の波長を変換した光を、入射される光の入射方向とは反対方向に拡散させて出射する波長変換部46である。第2拡散装置6Bの拡散部65は、波長を変換せずに、入射される光を拡散させて反射させる拡散反射部49である。光分離部43は、第1拡散装置6Aから出射された光と、第2拡散装置6Bから出射された光とを合成して出射する。
また、光学装置DVは、第1レンズとしての第2集光レンズ45に対向して筐体本体8に設けられる第1拡散装置用第2レンズである第1集光レンズ44と、第1レンズとしての第4集光レンズ48に対向して筐体本体8に設けられる第2拡散装置用第2レンズとしての第3集光レンズ47と、を有する。
また、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bは、拡散部65の構成が異なる他は略同じ構成であるので、光源装置4の構成を簡略化できる。
更に、第1拡散装置6A及び第2拡散装置6Bが固定される筐体7に、第1集光レンズ44及び第3集光レンズ47が取り付けられる。これによれば、波長変換部46に応じて設けられる第1集光レンズ44及び第2集光レンズ45を保持するレンズホルダー、及び、拡散反射部49に応じて設けられる第3集光レンズ47及び第4集光レンズ48を保持するレンズホルダーを有する筐体が採用される場合に比べて、光源装置4が大型化することを抑制できる。
プロジェクター1は、光を出射する光源411と、光源411から出射された光が入射する光学装置DVと、光学装置DVから出射された光を変調する光変調装置343と、光変調装置343によって変調された光を投射する投射光学装置36と、を備える。
このような構成によれば、プロジェクター1の大型化を抑制できる。
プロジェクター1は、光を出射する光源411と、光源411から出射された光が入射する拡散装置6と、拡散装置6から出射された光を変調する光変調装置343と、光変調装置343によって変調された光を投射する投射光学装置36と、を備える。
このような構成によれば、プロジェクター1の大型化を抑制できる。
本開示は、上記実施形態に限定されるものではなく、本開示の目的を達成できる範囲での変形及び改良等は、本開示に含まれるものである。
上記実施形態では、拡散部65として、波長変換層461及び反射層462を有し、入射された光の波長を変換した光を、光の入射方向とは反対方向に拡散して出射する波長変換部46と、波長を変換せずに、入射された光を拡散して反射させる拡散反射部49と、を例示した。しかしながら、これに限らず、拡散装置に採用される拡散部は、入射された光の波長を変換した光を、光の入射方向に沿って拡散して出射する構成であってもよく、入射された光の波長を変換せずに、光の入射方向に沿って拡散して出射する構成であってもよい。すなわち、拡散部は、拡散部に対する光の入射方向と、拡散部からの光の出射方向とが、互いに反対方向となる構成に限らず、拡散部に対する光の入射方向と、拡散部からの光の出射方向とが、同じ方向であってもよい。
なお、この場合、第1底面611Aに、光が通過する通過口を設けることにより、拡散部を通過した光を、拡散部に対してレンズとは反対側に出射できる。更に、この場合、通過口に拡散部を設けてもよい。
また、押圧部材63は、線材によって形成され、図3及び図4に示した形状を有する枠状部材であるとした。しかしながら、これに限らず、押圧部材は、レンズ62を第2底面612Aに押圧しつつ固定されればよく、押圧部材の構成は、上記に限定されない。例えば、押圧部材は、板状のばねであってもよい。
この他、押圧部材63は、レンズ62の曲面62Aに当接する3つの当接部631を有するとした。しかしながら、これに限らず、押圧部材63は、2つ以上の当接部631を備えていればよい。
また、押圧部材63は、第3凹部613に固定されなくてもよい。
第2拡散装置6Bに設けられた第1固定部材としての固定部材64、及び、第3集光レンズ47を押圧する押圧部材85をレンズ取付部83に固定する固定部材87についても同様である。
上記実施形態では、光変調装置343は、光入射面と光出射面とが異なる透過型の液晶パネルであるとした。しかしながら、これに限らず、光変調装置として、光入射面と光出射面とが同一となる反射型の液晶パネルを用いてもよい。また、入射光束を変調して画像情報に応じた画像を形成可能な光変調装置であれば、マイクロミラーを用いたデバイス、例えば、DMD(Digital Micromirror Device)等を利用したものなど、液晶以外の光変調装置を用いてもよい。
以下、本開示のまとめを付記する。
本開示の第1態様に係る拡散装置は、光を拡散させる拡散部と、前記拡散部が固定される基板と、曲面と、前記曲面とは反対側に位置する平坦面と、を有し、前記拡散部に対向して前記基板に固定される第1レンズと、を備え、前記基板は、第1底面と、前記第1底面から起立する第1側面と、を有する第1凹部と、前記第1側面と接続される第2底面と、前記第2底面から起立する第2側面と、を有する第2凹部と、を備え、前記第1レンズは、前記平坦面が前記第2底面と当接するように、前記第2凹部に配置され、前記拡散部は、前記第1底面に固定されている。
また、第1レンズの平坦面が、第2底面と当接するので、第1凹部及び拡散部と第1レンズとによって形成される第1凹部内の空間を密閉できる。このため、少なくとも拡散部における第1レンズ側の面に塵埃が付着することを抑制できる。従って、拡散装置の防塵性能を高めることができる他、塵埃の付着によって拡散装置の光学性能が低下することを抑制できる。
このような構成によれば、第3底面に固定される第1押圧部材によって、第1レンズが第2底面に押圧されて固定されるので、第1押圧部材を接着剤によって固定する必要がない。これによれば、接着剤が気化する等して、第1凹部内にガスが発生することを抑制できる。従って、ガスによって拡散部による光拡散性能が低下することを防止できる。
また、第1押圧部材は、第3底面に固定される。すなわち、第1押圧部材は、第3凹部内に配置されるので、第1レンズから拡散部に向かう方向における拡散装置の寸法が大きくなることを抑制できる。従って、拡散装置の大型化を抑制できる。
このような構成によれば、第1押圧部材を簡易に構成できる。また、第1押圧部材が曲面と当接して第1レンズを第2底面に押圧するので、第1凹部内の密閉状態を維持できる。
また、第2レンズは、第2押圧部材によってレンズ取付部に押圧されて固定される。このため、上記のように、接着剤を用いて第2レンズを固定する必要がない。従って、ガスの発生を抑制でき、ガスが第1レンズ及び第2レンズに付着することを抑制でき、光の利用効率が低下することを抑制できる。
このような構成によれば、プロジェクターの大型化を抑制できる。
このような構成によれば、プロジェクターの大型化を抑制できる。
Claims (4)
- 筐体と、第2レンズと、第2押圧部材と、拡散装置と、を備える光学装置であって、
前記拡散装置は、
光を拡散させる拡散部と、
前記拡散部が固定される基板と、
曲面と、前記曲面とは反対側に位置する平坦面と、を有し、前記拡散部に対向して前記基板に固定される第1レンズと、
前記第1レンズを押圧する第1押圧部材と、を備え、
前記基板は、
第1底面と、前記第1底面から起立する第1側面と、を有する第1凹部と、
前記第1側面と接続される第2底面と、前記第2底面から起立する第2側面と、を有する第2凹部と、を備え、
前記第1押圧部材は、前記第1レンズを前記第2底面に押圧し、
前記第1レンズは、前記第1押圧部材により前記平坦面が前記第2底面と当接するように、前記第2凹部に配置され、
前記拡散部は、前記第1底面に固定され、
前記基板は、前記筐体に固定され、
前記第2レンズは、前記第1レンズに対向して設けられ、
前記第2押圧部材は、前記第2レンズを前記筐体に対して押圧し、
前記筐体は、前記第2レンズが取り付けられるレンズ取付部を有し、
前記第2押圧部材は、前記筐体に固定されて、前記第2レンズを前記レンズ取付部に押圧することを特徴とする光学装置。 - 請求項1に記載の光学装置において、
前記基板は、前記第2側面と接続される第3底面と、前記第3底面から起立する第3側面と、を有する第3凹部を備え、
前記第1押圧部材は、前記第3底面に固定されていることを特徴とする光学装置。 - 請求項2に記載の光学装置において、
前記第1押圧部材は、線材により構成され、前記曲面における複数箇所に当接して、前記第1レンズを前記第2底面に押圧することを特徴とする光学装置。 - 光を出射する光源と、
前記光源から出射された光が入射する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光学装置と、
前記光学装置から出射された光を変調する光変調装置と、
前記光変調装置によって変調された光を投射する投射光学装置と、を備えることを特徴とするプロジェクター。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2020042696A JP7392530B2 (ja) | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 拡散装置、光学装置及びプロジェクター |
| CN202110260145.5A CN113391511B (zh) | 2020-03-12 | 2021-03-10 | 扩散装置、光学装置以及投影仪 |
| US17/199,537 US11543617B2 (en) | 2020-03-12 | 2021-03-12 | Diffusion apparatus, optical apparatus, and projector |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2020042696A JP7392530B2 (ja) | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 拡散装置、光学装置及びプロジェクター |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2021144145A JP2021144145A (ja) | 2021-09-24 |
| JP2021144145A5 JP2021144145A5 (ja) | 2022-11-24 |
| JP7392530B2 true JP7392530B2 (ja) | 2023-12-06 |
Family
ID=77617454
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2020042696A Active JP7392530B2 (ja) | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 拡散装置、光学装置及びプロジェクター |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11543617B2 (ja) |
| JP (1) | JP7392530B2 (ja) |
| CN (1) | CN113391511B (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7361408B2 (ja) * | 2021-09-03 | 2023-10-16 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 遊技機 |
| WO2024048307A1 (ja) * | 2022-08-30 | 2024-03-07 | 京セラ株式会社 | 照明装置 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007240770A (ja) | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Funai Electric Co Ltd | プロジェクタ |
| JP2014123014A (ja) | 2012-12-21 | 2014-07-03 | Casio Comput Co Ltd | 光源装置、プロジェクタ |
| JP2014165058A (ja) | 2013-02-26 | 2014-09-08 | Seiko Epson Corp | 光源装置、光源装置の製造方法およびプロジェクター |
| JP2017138376A (ja) | 2016-02-02 | 2017-08-10 | セイコーエプソン株式会社 | 光源装置及びプロジェクター |
| WO2018203363A1 (ja) | 2017-05-01 | 2018-11-08 | 株式会社島津製作所 | ビームスプリッタ組立品 |
| WO2019069563A1 (ja) | 2017-10-05 | 2019-04-11 | ソニー株式会社 | 光源装置および投射型表示装置 |
| JP2018180107A5 (ja) | 2017-04-06 | 2020-04-30 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012083623A (ja) * | 2010-10-13 | 2012-04-26 | Sanyo Electric Co Ltd | プロジェクタ |
| JP2015038618A (ja) * | 2014-09-18 | 2015-02-26 | カシオ計算機株式会社 | 発光ユニット及びプロジェクタ |
| JP6888381B2 (ja) | 2017-04-06 | 2021-06-16 | セイコーエプソン株式会社 | 光源装置及びプロジェクター |
-
2020
- 2020-03-12 JP JP2020042696A patent/JP7392530B2/ja active Active
-
2021
- 2021-03-10 CN CN202110260145.5A patent/CN113391511B/zh active Active
- 2021-03-12 US US17/199,537 patent/US11543617B2/en active Active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007240770A (ja) | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Funai Electric Co Ltd | プロジェクタ |
| JP2014123014A (ja) | 2012-12-21 | 2014-07-03 | Casio Comput Co Ltd | 光源装置、プロジェクタ |
| JP2014165058A (ja) | 2013-02-26 | 2014-09-08 | Seiko Epson Corp | 光源装置、光源装置の製造方法およびプロジェクター |
| JP2017138376A (ja) | 2016-02-02 | 2017-08-10 | セイコーエプソン株式会社 | 光源装置及びプロジェクター |
| JP2018180107A5 (ja) | 2017-04-06 | 2020-04-30 | ||
| WO2018203363A1 (ja) | 2017-05-01 | 2018-11-08 | 株式会社島津製作所 | ビームスプリッタ組立品 |
| WO2019069563A1 (ja) | 2017-10-05 | 2019-04-11 | ソニー株式会社 | 光源装置および投射型表示装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2021144145A (ja) | 2021-09-24 |
| CN113391511B (zh) | 2023-01-13 |
| US20210286147A1 (en) | 2021-09-16 |
| CN113391511A (zh) | 2021-09-14 |
| US11543617B2 (en) | 2023-01-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN108604050B (zh) | 光源装置和投影仪 | |
| JP2003121937A (ja) | 光学装置、およびプロジェクタ | |
| WO2004099871A1 (ja) | 光学装置、およびプロジェクタ | |
| JP7392530B2 (ja) | 拡散装置、光学装置及びプロジェクター | |
| US20030197934A1 (en) | Polarization converter, illumination optical device having the polarization converter and projector | |
| US7559675B2 (en) | Light source device and projector | |
| US11789346B2 (en) | Light source device and projector | |
| US20110032486A1 (en) | Projector and method for manufacturing projector | |
| US20090079947A1 (en) | Light source assembly and projector having same | |
| US7137705B2 (en) | Optical device with optical modulator fixation-enhancing structure and projector | |
| US7891827B2 (en) | Projector | |
| JP2007240604A (ja) | 光学装置およびプロジェクタ | |
| JP2014145995A (ja) | 画像投影装置および照明光学系 | |
| JP4466147B2 (ja) | 光学装置およびプロジェクタ | |
| JP2020194061A (ja) | 投射型表示装置 | |
| JP4561289B2 (ja) | 光学装置及びプロジェクタ | |
| JP4423998B2 (ja) | 光学装置およびプロジェクタ | |
| JP4492168B2 (ja) | 光学装置およびプロジェクタ | |
| JP2007199279A (ja) | プロジェクタ | |
| WO2018047870A1 (ja) | 光学レンズ、プロジェクター、及び光学レンズの製造方法 | |
| JP2002350977A (ja) | プロジェクタ | |
| JP2018180321A (ja) | プロジェクター | |
| JP2022039289A (ja) | 波長変換素子、波長変換装置、光源装置、プロジェクター、及び、波長変換素子の製造方法 | |
| JP2021167897A (ja) | 光源装置及びプロジェクター | |
| JP5035399B2 (ja) | プロジェクタ |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD07 | Notification of extinguishment of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7427 Effective date: 20200827 |
|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20210916 |
|
| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20211104 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20221115 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20221115 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20230803 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20230817 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20231013 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20231024 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20231106 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7392530 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |