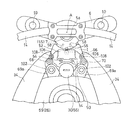JP6130115B2 - 鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 - Google Patents
鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6130115B2 JP6130115B2 JP2012206871A JP2012206871A JP6130115B2 JP 6130115 B2 JP6130115 B2 JP 6130115B2 JP 2012206871 A JP2012206871 A JP 2012206871A JP 2012206871 A JP2012206871 A JP 2012206871A JP 6130115 B2 JP6130115 B2 JP 6130115B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- main frame
- lock mechanism
- head pipe
- lock
- handle lock
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 7
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 51
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 51
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 17
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Lock And Its Accessories (AREA)
- Automatic Cycles, And Cycles In General (AREA)
Description
5 ヘッドパイプ
5a ステアリング挿通孔
6 アッパブラケット
7 ステアリングシャフト
50 スイッチブラケット(支持部材)
52 ハンドルロック機構
56 ロックピン
58 ロック孔
60 フレーム片
62 取付部材
66 第1締結部材
68 第2締結部材
70 第3締結部材
72 第1のねじ孔
74 第2のねじ孔
78 メインフレーム第1位置
80 メインフレーム第2位置
82 メインフレーム第3位置
94 第1挿通孔(締結部材挿通孔)
96 第2挿通孔(締結部材挿通孔)
98 第3挿通孔(締結部材挿通孔)
110 フレーム基体
Claims (4)
- メインフレームの前端に接続されたヘッドパイプと、
前記ヘッドパイプに操向自在に支持されたアッパブラケットと、
前記メインフレームの上面に取り付けられてハンドルロック機構を支持する支持部材とを備え、
前記ハンドルロック機構が、ロック操作時に前記アッパブラケットのロック孔に係合するロックピンを有し、
前記支持部材が、ロック操作時の前記ロック孔に前後方向に対向するメインフレーム第1位置で、第1締結部材により前記メインフレームに締結され、前記メインフレーム第1位置とは異なる他のメインフレーム位置で、他の締結部材により前記メインフレームに締結され、
前記ロックピンは、車幅方向中央部に位置し、前後方向に進退自在であり、
前記ロック孔は、ロック操作時において、車幅方向中央部に位置し、
前記メインフレーム第1位置は、車幅方向中央部で、前記他のメインフレーム位置よりも前記ヘッドパイプの近傍に設けられている鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造。 - 請求項1に記載の鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造において、前記第1締結部材の外径と前記メインフレーム第1位置に形成される挿通孔の内径との隙間が、前記他の締結部材の外径と前記他のメインフレーム位置に形成される挿通孔の内径との隙間よりも小さく形成されている鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造。
- メインフレームの前端に接続されたヘッドパイプと、
前記ヘッドパイプに操向自在に支持されたアッパブラケットと、
前記メインフレームの上面に取り付けられてハンドルロック機構を支持する支持部材とを備え、
前記ハンドルロック機構が、ロック操作時に前記アッパブラケットのロック孔に係合するロックピンを有し、
前記支持部材が、前記ロック孔に対向するメインフレーム第1位置で、第1締結部材により前記メインフレームに締結され、前記メインフレーム第1位置とは異なる他のメインフレーム位置で、他の締結部材により前記メインフレームに締結され、
前記他のメインフレーム位置は、メインフレーム第2および第3位置を含み、
前記他の締結部材は第2および第3締結部材を含み、
前記支持部材は、前記メインフレーム第2位置で、前記第2締結部材により前記メインフレームに締結され、さらに、前記第3締結部材によって、前記メインフレーム第1位置と前記メインフレーム第2位置とを結ぶ直線上とは異なる前記メインフレーム第3位置で、前記メインフレームに締結され、
前記第1〜3締結部材は、前記支持部材の円形の第1〜第3挿通孔に挿通されるねじ体であり、
前記第1締結部材の外径と第1挿通孔の内径との第1隙間が、前記第3締結部材の外径と前記第3挿通孔の内径との第3隙間よりも小さく形成されている鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造。 - メインフレームの前端に接続されたヘッドパイプと、
前記ヘッドパイプに操向自在に支持されたアッパブラケットと、
前記メインフレームの上面に取り付けられてハンドルロック機構を支持する支持部材とを備え、
前記ハンドルロック機構が、ロック操作時に前記アッパブラケットのロック孔に係合するロックピンを有し、
前記支持部材が、ロック操作時の前記ロック孔に前記ロックピンの進退方向に対向するメインフレーム第1位置で、第1締結部材により前記メインフレームに締結され、前記メインフレーム第1位置とは異なる他のメインフレーム位置で、他の締結部材により前記メインフレームに締結され、
前記メインフレーム第1位置は、前記他のメインフレーム位置よりも前記ヘッドパイプの近傍に設けられている鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012206871A JP6130115B2 (ja) | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 |
| CN201320574127.5U CN203511846U (zh) | 2012-09-20 | 2013-09-17 | 跨乘式车辆的把手锁定机构安装结构 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012206871A JP6130115B2 (ja) | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014061742A JP2014061742A (ja) | 2014-04-10 |
| JP2014061742A5 JP2014061742A5 (ja) | 2015-05-28 |
| JP6130115B2 true JP6130115B2 (ja) | 2017-05-17 |
Family
ID=50370821
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012206871A Expired - Fee Related JP6130115B2 (ja) | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6130115B2 (ja) |
| CN (1) | CN203511846U (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017019385A (ja) | 2015-07-10 | 2017-01-26 | ヤマハ発動機株式会社 | 鞍乗型車両 |
| JP6511096B2 (ja) * | 2017-06-30 | 2019-05-15 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両のハンドルロック装置 |
| JP6625686B2 (ja) * | 2018-03-29 | 2019-12-25 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3175428B2 (ja) * | 1993-10-12 | 2001-06-11 | スズキ株式会社 | 自動二輪車の車体カバー |
| JP3531359B2 (ja) * | 1996-06-17 | 2004-05-31 | スズキ株式会社 | 自動二輪車の盗難防止装置 |
| JP3434481B2 (ja) * | 2000-01-13 | 2003-08-11 | 川崎重工業株式会社 | 自動二輪車のハンドルロック装置 |
| JP4836254B2 (ja) * | 2006-09-29 | 2011-12-14 | 本田技研工業株式会社 | 灯体ユニットの支持構造 |
| JP5095486B2 (ja) * | 2007-05-30 | 2012-12-12 | ヤマハ発動機株式会社 | 車両 |
| TWI373424B (en) * | 2009-02-17 | 2012-10-01 | Delta Electronics Inc | Electronic ignition-lock apparatus for motorcycle |
| JP5553555B2 (ja) * | 2009-08-27 | 2014-07-16 | 川崎重工業株式会社 | 自動二輪車の標示プレート取付構造 |
| JP5953096B2 (ja) * | 2012-04-20 | 2016-07-20 | 本田技研工業株式会社 | 鞍乗り型車両の前部構造 |
| JP2013256154A (ja) * | 2012-06-11 | 2013-12-26 | Honda Motor Co Ltd | 鞍乗型車両 |
-
2012
- 2012-09-20 JP JP2012206871A patent/JP6130115B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-09-17 CN CN201320574127.5U patent/CN203511846U/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN203511846U (zh) | 2014-04-02 |
| JP2014061742A (ja) | 2014-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9145028B2 (en) | Mounting structure of wheel speed sensor ring | |
| EP2213559B1 (en) | Rear fender structure for motorcycle and motorcycle | |
| US8500169B2 (en) | Saddle-ride type vehicle | |
| JP5046994B2 (ja) | 自動二輪車のサイドスタンド取り付け構造 | |
| JP2009214717A (ja) | 鞍乗り型車両の車体後部構造 | |
| JP6045903B2 (ja) | 自動二輪車 | |
| JP6130115B2 (ja) | 鞍乗型車両のハンドルロック機構取付構造およびその取付方法 | |
| US7584814B2 (en) | Motorcycle | |
| US8297397B2 (en) | Servo motor layout structure of saddle-ride type vehicle | |
| JP6158943B2 (ja) | 鞍乗型車両の車体フレーム構造 | |
| US7114588B2 (en) | Vehicle body frame structure of two-wheeler | |
| US10053176B2 (en) | Fuel tank structure for motorcycle | |
| US11292537B2 (en) | Saddle-riding type vehicle and side stand bracket | |
| US10093381B2 (en) | Component mounting structure of vehicle | |
| JP2012062014A (ja) | ウインカー及びこれを備えた鞍乗り型車両 | |
| CN108025790B (zh) | 轴的轴承结构 | |
| JP4459045B2 (ja) | 自動二輪車の操向ハンドルストッパ構造 | |
| EP2711277B1 (en) | Frame structure for saddle-riding type automotive vehicle | |
| JP2018030441A (ja) | 鞍乗型車両の燃料タンク取付構造 | |
| US8360676B2 (en) | Shaft support structure for a vehicle | |
| JP6965224B2 (ja) | 鞍乗り型車両 | |
| JP7369750B2 (ja) | 鞍乗り型車両 | |
| JP2016032949A (ja) | 鞍乗り型車両におけるステップ構造 | |
| JP2017121924A (ja) | 鞍乗り型車両 | |
| WO2020066216A1 (ja) | 排気構造 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150408 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150408 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160218 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160301 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160408 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20161004 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161031 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170404 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170413 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6130115 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |