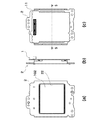JP6057538B2 - 撮像装置 - Google Patents
撮像装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6057538B2 JP6057538B2 JP2012102873A JP2012102873A JP6057538B2 JP 6057538 B2 JP6057538 B2 JP 6057538B2 JP 2012102873 A JP2012102873 A JP 2012102873A JP 2012102873 A JP2012102873 A JP 2012102873A JP 6057538 B2 JP6057538 B2 JP 6057538B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- image sensor
- plate
- unit
- standing wall
- imaging
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/50—Constructional details
- H04N23/54—Mounting of pick-up tubes, electronic image sensors, deviation or focusing coils
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
- Studio Devices (AREA)
- Camera Bodies And Camera Details Or Accessories (AREA)
Description
図1は、本実施形態に係る撮像装置が備える撮像素子ユニット1の概略構造を示す図であり、(a)は正面図を、(b)は右側面図(図1(a)を右側から見た図)を、(c)は背面図をそれぞれ示している。撮像素子ユニット1は、撮像素子10が自動実装により配線基板11(以下「基板11」と記する)に実装され、一体化されたものである。
図2は、撮像素子ユニット1が位置決め固定される固定部材の一例であるプレート2の構造を示す図であり、(a)は背面図、(b)は底面図、(c)は背面斜視図である。なお、本実施形態では、プレート2について、図2(a)の左右方向を「幅方向」と定義する。
図3は、プレート2に対する撮像素子ユニット1の位置決め固定方法を示す側面図であり、図1(b)と同様に撮像素子ユニット1の右側面図として示している。図3に示すように、撮像素子ユニット1は、プレート2の背面側からプレート2に対して矢印A方向、立壁部23a,23bによって挟まれた領域に撮像素子10が収容されるように、配置される。そのため、撮像素子10において立壁部23a,23bと対向する二辺であるパッケージ側面105a,105b間の幅寸法は、立壁部23a,23bの間の幅寸法より狭くなっている。
前述の通り、カバーガラス102の端面と開口部22の側面との間には、プレート2の幅方向において寸法βのクリアランスが形成される。
図6に示すように、接着剤が充填される空間(射出部31の先端から先方の空間)は、パッケージ側面105aとプレート側当接面24aと立壁部23aとによって三方を囲まれた袋形状(溝形状)の空間になっていることがわかる。このように、接着剤が充填される空間を袋形状の空間に構成することにより、接着剤がプレート2の幅方向に流れ出るのを防止する。この効果は、撮像素子ユニット1をプレート2に対して所定の力で押圧しながら接着剤を充填する場合に、より顕著に得ることができる。
撮像素子10の発熱対策として、熱伝導シートを撮像素子プレートユニットに装着する方法について説明する。図9は、撮像素子プレートユニットに装着される熱伝導シートユニット4の斜視図であり、(a)は背面斜視図、(b)は正面斜視図である。
以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。例えば、上記実施形態では、撮像装置本体に対して固定されるプレート2に撮像素子ユニット1を接着固定するとしたが、撮像装置本体がプレート2と同等形状の部位を備え、この同等形状部位に撮像素子ユニット1を接着固定してもよい。
2 プレート
4 熱伝導シートユニット
10 撮像素子
11 基板(配線基板)
12 空隙部
21 平面部
23a,23b 立壁部
25a 凸部
25b 凹部
32 接着剤
Claims (3)
- 配線基板と、前記配線基板に実装された撮像素子と、前記撮像素子が位置決め固定される固定部材とを備える撮像装置であって、
前記固定部材は、
前記撮像素子の撮像面を露出させる開口部と、
前記開口部の外周において前記撮像素子と当接する当接面と、
前記撮像素子の側面と対向するように前記当接面から立設される立壁部と、を有し、
前記配線基板において前記撮像素子が実装された面が所定の間隔を空けて前記当接面と対向する状態で、前記撮像素子は前記当接面と当接し、
前記撮像素子の側面と、前記立壁部において前記撮像素子の側面と対向する側面と、前記当接面の3つの面によって形成される溝形状の空間において前記3つの面に接する接着剤により前記撮像素子が前記固定部材に固定され、
前記配線基板は前記空間を覆わないことを特徴とする撮像装置。 - 前記立壁部から前記配線基板の前記立壁部に対向する端までの距離が前記立壁部から前記撮像素子の側面までの距離よりも長いことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 前記撮像装置は、熱伝導シートを備え、
前記立壁部は、前記開口部を挟んで対向する第1の立壁部及び第2の立壁部を有し、
前記第1の立壁部の端部は凸部を有し、
前記第2の立壁部の端部は凹部を有し、
前記撮像素子と前記配線基板との間には空隙部が形成され、前記熱伝導シートは、前記凹部に挿入され、且つ、前記凸部に当接した状態で前記空隙部に配置されていることを特徴とする請求項1又は2記載の撮像装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012102873A JP6057538B2 (ja) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 撮像装置 |
| US13/834,093 US9065989B2 (en) | 2012-04-27 | 2013-03-15 | Image pickup apparatus having image pickup device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012102873A JP6057538B2 (ja) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 撮像装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2013232732A JP2013232732A (ja) | 2013-11-14 |
| JP2013232732A5 JP2013232732A5 (ja) | 2015-06-18 |
| JP6057538B2 true JP6057538B2 (ja) | 2017-01-11 |
Family
ID=49476956
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012102873A Active JP6057538B2 (ja) | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 撮像装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9065989B2 (ja) |
| JP (1) | JP6057538B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6639290B2 (ja) * | 2016-03-18 | 2020-02-05 | キヤノン株式会社 | 撮像装置 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6147389A (en) * | 1999-06-04 | 2000-11-14 | Silicon Film Technologies, Inc. | Image sensor package with image plane reference |
| US6734419B1 (en) * | 2001-06-28 | 2004-05-11 | Amkor Technology, Inc. | Method for forming an image sensor package with vision die in lens housing |
| US7274094B2 (en) * | 2002-08-28 | 2007-09-25 | Micron Technology, Inc. | Leadless packaging for image sensor devices |
| JP4225860B2 (ja) | 2003-07-29 | 2009-02-18 | Hoya株式会社 | デジタルカメラ |
| JP2005121912A (ja) * | 2003-10-16 | 2005-05-12 | Sony Corp | レンズ鏡筒および撮像装置 |
| JP3827089B2 (ja) * | 2003-10-20 | 2006-09-27 | ソニー株式会社 | レンズ鏡筒および撮像装置 |
| KR100873248B1 (ko) * | 2004-12-14 | 2008-12-11 | 세이코 프레시죤 가부시키가이샤 | 고체 촬상 장치 및 전자 기기 |
| US7750279B2 (en) * | 2006-02-23 | 2010-07-06 | Olympus Imaging Corp. | Image pickup apparatus and image pickup unit |
| JP2008312040A (ja) * | 2007-06-15 | 2008-12-25 | Fujinon Corp | 撮影ユニット、撮影装置、携帯機器、および撮影ユニットの組立方法 |
| JP5376865B2 (ja) * | 2008-08-19 | 2013-12-25 | キヤノン株式会社 | 固体撮像装置及び電子撮像装置 |
| JP5064585B2 (ja) * | 2010-06-14 | 2012-10-31 | パナソニック株式会社 | 遮蔽構造および撮像素子支持構造 |
| KR101720772B1 (ko) * | 2010-08-27 | 2017-04-03 | 삼성전자주식회사 | 이미지 센서 조립체 |
-
2012
- 2012-04-27 JP JP2012102873A patent/JP6057538B2/ja active Active
-
2013
- 2013-03-15 US US13/834,093 patent/US9065989B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2013232732A (ja) | 2013-11-14 |
| US9065989B2 (en) | 2015-06-23 |
| US20130286281A1 (en) | 2013-10-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4405062B2 (ja) | 固体撮像装置 | |
| EP1708278A2 (en) | Optical device module, lens holding device, and method for manufacturing optical device module | |
| KR101455124B1 (ko) | 촬상 센서 패키지를 구비한 촬상장치 | |
| CN101848326B (zh) | 摄像设备 | |
| JP6639290B2 (ja) | 撮像装置 | |
| JP6232789B2 (ja) | 撮像ユニット及び撮像装置 | |
| JP6057538B2 (ja) | 撮像装置 | |
| JP2018038054A (ja) | 撮像ユニット及び撮像装置 | |
| JP4943413B2 (ja) | カメラ組立構造 | |
| JP2012083556A (ja) | カメラモジュール | |
| JP6149442B2 (ja) | 撮像ユニット及び撮像装置 | |
| JP6191254B2 (ja) | 撮像ユニットおよび撮像装置 | |
| JP2015015529A (ja) | 撮像ユニット及び撮像装置 | |
| JP6443494B2 (ja) | 撮像ユニット及び撮像装置 | |
| JP6756357B2 (ja) | 撮像装置 | |
| JP2013222772A (ja) | 撮像素子パッケージおよび撮像装置 | |
| KR20020084541A (ko) | 이동형 단말기기에 적용 가능한 초박형 영상모듈의 구현 | |
| JP6675241B2 (ja) | 撮像装置 | |
| JP7078151B2 (ja) | 撮像ユニットおよび撮像装置 | |
| JP6849016B2 (ja) | 撮像ユニットおよび撮像装置 | |
| JP6145988B2 (ja) | カメラモジュール | |
| JP5601081B2 (ja) | 撮像素子ユニットおよび撮像装置 | |
| KR100483721B1 (ko) | 고체 촬상장치 | |
| JP6547799B2 (ja) | 撮像ユニットおよび撮像装置 | |
| JP2011211379A (ja) | 撮像装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150424 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150424 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160210 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160301 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160427 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160531 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160720 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161108 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161206 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6057538 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |