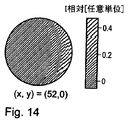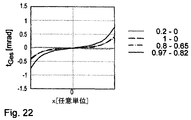JP5319706B2 - 照明光学系及び投影露光装置 - Google Patents
照明光学系及び投影露光装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5319706B2 JP5319706B2 JP2010544588A JP2010544588A JP5319706B2 JP 5319706 B2 JP5319706 B2 JP 5319706B2 JP 2010544588 A JP2010544588 A JP 2010544588A JP 2010544588 A JP2010544588 A JP 2010544588A JP 5319706 B2 JP5319706 B2 JP 5319706B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical system
- illumination
- illumination optical
- object field
- displacement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03F—PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
- G03F7/00—Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
- G03F7/70—Microphotolithographic exposure; Apparatus therefor
- G03F7/70058—Mask illumination systems
- G03F7/70141—Illumination system adjustment, e.g. adjustments during exposure or alignment during assembly of illumination system
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03F—PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
- G03F7/00—Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
- G03F7/70—Microphotolithographic exposure; Apparatus therefor
- G03F7/70058—Mask illumination systems
- G03F7/7015—Details of optical elements
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03F—PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
- G03F7/00—Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
- G03F7/70—Microphotolithographic exposure; Apparatus therefor
- G03F7/70058—Mask illumination systems
- G03F7/70191—Optical correction elements, filters or phase plates for controlling intensity, wavelength, polarisation, phase or the like
Description
p(h) = [((1/r)h2)/( + SQRT(1 - (1 + K)(1/r)2h2))] + C1 ・ h4 + C2 ・ h6 + ....
1/rは、非球面の頂点における面の曲率である。hは、光学面の回転対称軸、言い換えれば、z方向に延びる光軸からの光学非球面上のある点の距離である。サジタル高さp(h)は、回転対称軸から距離h(h2=x2+y2)の位置にある特定の点を光学非球面の頂点、言い換えれば、光学面上のh=0の点と比較したこれらの点の間のz距離である。係数C3以降は、h8から始まるhを底とする更に別の偶数指数である。
tGes=tx+tpb,x
tpb,x=pbx・NA
ここで、NAは、有効光4の開口数である。
15 コンデンサー群
18 対物光学素子群
FLG4、FLG5 コンデンサー群の構成要素
REMA1、REMA2 対物光学素子群の構成要素
Claims (21)
- マイクロリソグラフィのための投影露光装置(1)の物体視野(14)の照明のための照明光学系(5)であって、
前記照明光学系(5)の瞳平面(9)の下流に配置された、有効光の束(4)を誘導する光学構成要素のコンデンサー群(15)、及び
有効光の経路において前記コンデンサー群(15)の下流に配置された光束誘導構成要素の対物光学素子群(18)、
を含み、
コンデンサー群(15)のうちの少なくとも1つの構成要素(FLG4、FLG5)、及び
対物光学素子群(18)のうちの少なくとも1つの構成要素(REMA1、REMA2)、
が、物体視野(14)の、望ましい照明状態に対する実際の照明状態のずれの補償のために変位可能である、
ことを特徴とする照明光学系。 - 前記変位可能構成要素(FLG4,FLG5,REMA1,REMA2)のうちの少なくとも1つが、制御デバイス(33)と信号接続状態にある変位駆動体(28,34,36,38)に接続されることを特徴とする請求項1に記載の照明光学系。
- 前記変位可能構成要素(FLG4,FLG5,REMA1,REMA2)は、中心物体視野点(21)の主光線方向(2)に沿って変位可能であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の照明光学系。
- 前記変位駆動体(28,34,36,38)は、前記中心物体視野点(21)の前記主光線方向(2)に沿って1mmの範囲の変位経路を可能にすることを特徴とする請求項3に記載の照明光学系。
- 前記変位駆動体(28,34,36,38)は、50μmよりも良好な位置決め精度を有することを特徴とする請求項4に記載の照明光学系。
- 前記変位可能構成要素(FLG4,FLG5,REMA1,REMA2)のうちの少なくとも1つが、中心物体視野点(21)の主光線方向(2)に対して垂直な少なくとも1つの軸(x,y)に沿って変位可能であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 偏心変位駆動体(28,34,36,38)が、400μmの範囲の偏心変位経路を提供することを特徴とする請求項6に記載の照明光学系。
- 前記偏心変位駆動体(38,34,36,38)は、少なくとも20μmの位置決め精度を有することを特徴とする請求項7に記載の照明光学系。
- 前記変位可能構成要素(FLG4,FLG5,REMA1,REMA2)のうちの少なくとも1つが、中心物体視野点(21)の主光線方向(2)に対して垂直な少なくとも1つの傾斜軸(x,y)の回りに傾斜可能であることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 傾斜変位駆動体(28,34,36,38)が、角度で10分の範囲の傾斜変位経路を有することを特徴とする請求項9に記載の照明光学系。
- 前記傾斜変位駆動体(28,34,36,38)は、角度で0.5分よりも良好な位置決め精度を有することを特徴とする請求項10に記載の照明光学系。
- 前記コンデンサー群(15)の前記変位可能構成要素(FLG3,FLG4,FLG5)は、第1のもの(40)が中心物体視野点(21)に属し、かつ第2のもの(41)が縁部での物体視野点(22)に属する2つの放射線部分束(40、41)が、該2つの物体視野点を含む子午断面(xy)内で最大で70%だけ重なり合う構成要素であることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記対物光学素子群(18)の前記変位可能構成要素(REMA1,REMA2,REMA3)は、第1のもの(40)が中心視野点(21)に属し、かつ第2のもの(41)が縁部での物体視野点(22)に属する2つの放射線部分束(40、41)が、該2つの物体視野点を含む子午断面(xy)内で最大で30%だけ重なり合う構成要素であることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記コンデンサー群(15)の前記変位可能構成要素(FLG3,FLG4,FLG5)は、450mmよりも短いその焦点距離の絶対値を有することを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記対物光学素子群(18)の前記変位可能構成要素(REMA1,REMA2,REMA3)は、450mmよりも短く、特に、400mmよりも短いその焦点距離の絶対値を有することを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記コンデンサー群(15)は、前記有効光の束(4)を誘導する11個よりも多くない構成要素(FLG1からFLG6)を含み、該構成要素(FLG1からFLG6)のうちの少なくとも1つ(FLG4;FLG5)かつ2つよりも多くないもの(FLG、FLG5)が変位可能であることを特徴とする請求項1から請求項15のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記対物光学素子群(18)は、前記有効光の束(4)を誘導する17個よりも多くない構成要素(REMA1からREMA9)を含み、該構成要素(REMA1からREMA9)のうちの少なくとも1つ(REMA1;REMA2)かつ2つよりも多くないもの(REMA1、REMA2)が変位可能であることを特徴とする請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 光源(3)と、
請求項1から請求項17のいずれか1項に記載の照明光学系(5)と、
を含むことを特徴とする照明系。 - 照明環境を定めるための調節デバイス(8)を含むことを特徴とする請求項18に記載の照明系。
- 請求項18又は請求19に記載の照明系と、
物体視野(14)を像視野(14a)内に結像するための投影対物系(11)と、
を含むことを特徴とする投影露光装置(1)。 - 構造化構成要素を生成する方法であって、
少なくとも一部に感光材料の層が付加されたウェーハ(13)を準備する段階と、
結像される構造を有するレチクル(7)を準備する段階と、
請求項20に記載の投影露光装置(1)を準備する段階と、
前記投影露光装置(1)を用いて前記レチクル(7)の少なくとも一部を前記ウェーハ(13)上の前記層の領域に投影する段階と、
を含むことを特徴とする方法。
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US2534408P | 2008-02-01 | 2008-02-01 | |
| DE102008007449.7 | 2008-02-01 | ||
| US61/025,344 | 2008-02-01 | ||
| DE102008007449A DE102008007449A1 (de) | 2008-02-01 | 2008-02-01 | Beleuchtungsoptik zur Beleuchtung eines Objektfeldes einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie |
| PCT/EP2008/009914 WO2009095052A1 (en) | 2008-02-01 | 2008-11-22 | Illumination optics and projection exposure apparatus |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2011517843A JP2011517843A (ja) | 2011-06-16 |
| JP2011517843A5 JP2011517843A5 (ja) | 2012-01-12 |
| JP5319706B2 true JP5319706B2 (ja) | 2013-10-16 |
Family
ID=40847171
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2010544588A Expired - Fee Related JP5319706B2 (ja) | 2008-02-01 | 2008-11-22 | 照明光学系及び投影露光装置 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US8705000B2 (ja) |
| JP (1) | JP5319706B2 (ja) |
| KR (1) | KR101541563B1 (ja) |
| CN (1) | CN101932975B (ja) |
| DE (1) | DE102008007449A1 (ja) |
| WO (1) | WO2009095052A1 (ja) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008007449A1 (de) | 2008-02-01 | 2009-08-13 | Carl Zeiss Smt Ag | Beleuchtungsoptik zur Beleuchtung eines Objektfeldes einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie |
| DE102010029765A1 (de) | 2010-06-08 | 2011-12-08 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Beleuchtungsoptik für die EUV-Projektionslithografie |
| DE102011003928B4 (de) | 2011-02-10 | 2012-10-31 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Beleuchtungsoptik für die Projektionslithographie |
| DE102011076145B4 (de) * | 2011-05-19 | 2013-04-11 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Verfahren zum Zuordnen einer Pupillenfacette eines Pupillenfacettenspiegels einer Beleuchtungsoptik einer Projektionsbelichtungsanlage zu einer Feldfacette eines Feldfacettenspiegels der Beleuchtungsoptik |
| DE102012209132A1 (de) | 2012-05-31 | 2013-12-05 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Beleuchtungsoptik für die Projektionslithographie |
| DE102012213937A1 (de) | 2012-08-07 | 2013-05-08 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Spiegel-Austauscharray |
| DE102012218074A1 (de) | 2012-10-04 | 2013-08-14 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Blenden-Vorrichtung |
| DE102014204388A1 (de) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Beleuchtungsoptik für die Projektionslithographie |
| JP6453251B2 (ja) | 2013-03-14 | 2019-01-16 | カール・ツァイス・エスエムティー・ゲーエムベーハー | 投影リソグラフィのための照明光学ユニット |
| WO2014139814A1 (en) | 2013-03-14 | 2014-09-18 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Illumination optical unit for projection lithography |
| DE102013223808A1 (de) | 2013-11-21 | 2014-12-11 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Optische Spiegeleinrichtung zur Reflexion eines Bündels von EUV-Licht |
| DE102016222033A1 (de) | 2016-11-10 | 2016-12-29 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Verfahren zur Zuordnung von Feldfacetten zu Pupillenfacetten zur Schaffung von Beleuchtungslicht-Ausleuchtungskanälen in einem Be-leuchtungssystem in einer EUV-Projektionsbelichtungsanlage |
| DE102017200663A1 (de) | 2017-01-17 | 2017-03-02 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Verfahren zur Zuordnung von Ausgangs-Kippwinkeln von kippbaren Feldfacetten eines Feldfacettenspiegels für eine Projektionsbelich-tungsanlage für die Projektionslithografie |
| DE102017209440A1 (de) * | 2017-06-02 | 2018-12-06 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Projektionsbelichtungsverfahren und Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithografie |
| DE102020210829A1 (de) | 2020-08-27 | 2022-03-03 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Pupillenfacettenspiegel für eine Beleuchtungsoptik einer Projektionsbelichtungsanlage |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19548805A1 (de) * | 1995-12-27 | 1997-07-03 | Zeiss Carl Fa | REMA-Objektiv für Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlagen |
| JPH10275771A (ja) * | 1997-02-03 | 1998-10-13 | Nikon Corp | 照明光学装置 |
| DE19809395A1 (de) * | 1998-03-05 | 1999-09-09 | Zeiss Carl Fa | Beleuchtungssystem und REMA-Objektiv mit Linsenverschiebung und Betriebsverfahren dafür |
| EP0989434B1 (en) * | 1998-07-29 | 2006-11-15 | Carl Zeiss SMT AG | Catadioptric optical system and exposure apparatus having the same |
| US6281967B1 (en) | 2000-03-15 | 2001-08-28 | Nikon Corporation | Illumination apparatus, exposure apparatus and exposure method |
| JP3599629B2 (ja) * | 2000-03-06 | 2004-12-08 | キヤノン株式会社 | 照明光学系及び前記照明光学系を用いた露光装置 |
| JP4888819B2 (ja) * | 2000-04-12 | 2012-02-29 | 株式会社ニコン | 露光装置、露光方法、露光装置の製造方法及びマイクロデバイスの製造方法 |
| KR20020046932A (ko) * | 2000-12-14 | 2002-06-21 | 시마무라 테루오 | 콘덴서 광학계, 및 그 광학계를 구비한 조명 광학 장치그리고 노광 장치 |
| JP2004335575A (ja) * | 2003-05-01 | 2004-11-25 | Canon Inc | 露光装置 |
| JP4366163B2 (ja) * | 2003-09-25 | 2009-11-18 | キヤノン株式会社 | 照明装置及び露光装置 |
| JP2005114922A (ja) * | 2003-10-06 | 2005-04-28 | Canon Inc | 照明光学系及びそれを用いた露光装置 |
| JP4684563B2 (ja) * | 2004-02-26 | 2011-05-18 | キヤノン株式会社 | 露光装置及び方法 |
| JP4599936B2 (ja) | 2004-08-17 | 2010-12-15 | 株式会社ニコン | 照明光学装置、照明光学装置の調整方法、露光装置、および露光方法 |
| DE102006025025A1 (de) * | 2006-05-26 | 2007-11-29 | Carl Zeiss Smt Ag | Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage und Projektionsbelichtungsverfahren |
| WO2008007633A1 (fr) * | 2006-07-12 | 2008-01-17 | Nikon Corporation | Appareil optique d'éclairage, appareil d'exposition, et procédé de fabrication du dispositif |
| DE102008007449A1 (de) | 2008-02-01 | 2009-08-13 | Carl Zeiss Smt Ag | Beleuchtungsoptik zur Beleuchtung eines Objektfeldes einer Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie |
-
2008
- 2008-02-01 DE DE102008007449A patent/DE102008007449A1/de not_active Ceased
- 2008-11-22 JP JP2010544588A patent/JP5319706B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2008-11-22 CN CN2008801259209A patent/CN101932975B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-11-22 WO PCT/EP2008/009914 patent/WO2009095052A1/en active Application Filing
- 2008-11-22 KR KR1020107017402A patent/KR101541563B1/ko active IP Right Grant
-
2010
- 2010-07-29 US US12/846,470 patent/US8705000B2/en active Active
-
2014
- 2014-03-07 US US14/200,199 patent/US9588431B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR101541563B1 (ko) | 2015-08-03 |
| US20110019172A1 (en) | 2011-01-27 |
| CN101932975A (zh) | 2010-12-29 |
| US20140185027A1 (en) | 2014-07-03 |
| US9588431B2 (en) | 2017-03-07 |
| JP2011517843A (ja) | 2011-06-16 |
| CN101932975B (zh) | 2013-04-10 |
| WO2009095052A1 (en) | 2009-08-06 |
| KR20100119543A (ko) | 2010-11-09 |
| US8705000B2 (en) | 2014-04-22 |
| DE102008007449A1 (de) | 2009-08-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5319706B2 (ja) | 照明光学系及び投影露光装置 | |
| JP5726396B2 (ja) | 結像光学系 | |
| JP5876516B2 (ja) | マイクロリソグラフィのための投影対物系、投影露光装置、投影露光方法、及び光学補正プレート | |
| US10191386B2 (en) | Imaging optical unit for EUV projection lithography | |
| JP6249449B2 (ja) | マイクロリソグラフィのための投影対物系 | |
| JP5842302B2 (ja) | マイクロリソグラフィのための投影光学系 | |
| JP2016525720A (ja) | 物体視野を像視野内に結像するための投影光学ユニット及びそのような投影光学ユニットを含む投影露光装置 | |
| JPH08179204A (ja) | 投影光学系及び投影露光装置 | |
| EP1875292A2 (en) | Illumination system for a microlithgraphic exposure apparatus | |
| JP2001343582A (ja) | 投影光学系、当該投影光学系を備えた露光装置、及び当該露光装置を用いたマイクロデバイスの製造方法 | |
| JP5431345B2 (ja) | 結像光学系、この種の結像光学系を含むマイクロリソグラフィのための投影露光装置、及びこの種の投影露光装置を用いて微細構造構成要素を生成する方法 | |
| US20070285644A1 (en) | Microlithographic Projection Exposure Apparatus | |
| KR20120005463A (ko) | 이미징 광학 기기 및 이 유형의 이미징 광학 기기를 갖는 마이크로리소그래피용 투영 노광 장치 | |
| JP2008186912A (ja) | 収差評価方法、調整方法、露光装置、露光方法、およびデバイス製造方法 | |
| CN117546098A (zh) | 用于半导体光刻的投射曝光设备 | |
| WO2002021187A1 (fr) | Systeme d'objectif, dispositif d'observation equipe du systeme d'objectif et systeme d'exposition equipe du dispositif d'observation | |
| JP2002202449A (ja) | 対物光学系の製造方法、検査装置及びその製造方法、観察装置、露光装置、並びにマイクロデバイスの製造方法 | |
| JP2021511546A (ja) | 投影リソグラフィ用の照明光学デバイス |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111117 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20111117 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20121206 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20121220 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130319 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130605 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20130705 |
|
| A602 | Written permission of extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602 Effective date: 20130716 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130711 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5319706 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |