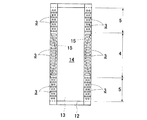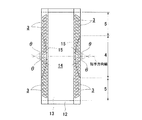JP5065836B2 - 使い捨て紙おむつ - Google Patents
使い捨て紙おむつ Download PDFInfo
- Publication number
- JP5065836B2 JP5065836B2 JP2007254898A JP2007254898A JP5065836B2 JP 5065836 B2 JP5065836 B2 JP 5065836B2 JP 2007254898 A JP2007254898 A JP 2007254898A JP 2007254898 A JP2007254898 A JP 2007254898A JP 5065836 B2 JP5065836 B2 JP 5065836B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sheet
- absorbent body
- leak
- surface side
- opening
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 120
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 120
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims description 74
- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 claims description 36
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 30
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 7
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 4
- 210000001124 body fluid Anatomy 0.000 description 70
- 239000010839 body fluid Substances 0.000 description 61
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 description 12
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 9
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 6
- 238000004049 embossing Methods 0.000 description 6
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 6
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 6
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 5
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 5
- 239000004831 Hot glue Substances 0.000 description 4
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 4
- 230000027939 micturition Effects 0.000 description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 4
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 4
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 4
- 210000002700 urine Anatomy 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 3
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 3
- 229920000247 superabsorbent polymer Polymers 0.000 description 3
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 3
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 description 3
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 2
- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 2
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 2
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 2
- 239000002964 rayon Substances 0.000 description 2
- 239000005871 repellent Substances 0.000 description 2
- 238000010008 shearing Methods 0.000 description 2
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000037303 wrinkles Effects 0.000 description 2
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 125000002066 L-histidyl group Chemical group [H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H] 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 239000002174 Styrene-butadiene Substances 0.000 description 1
- 229920006311 Urethane elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000003187 abdominal effect Effects 0.000 description 1
- 239000002313 adhesive film Substances 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 1
- MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N butadiene-styrene rubber Chemical compound C=CC=C.C=CC1=CC=CC=C1 MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 210000004013 groin Anatomy 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012943 hotmelt Substances 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011256 inorganic filler Substances 0.000 description 1
- 229910003475 inorganic filler Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004898 kneading Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N olefin Natural products CCCCCCCC=C JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 229920006149 polyester-amide block copolymer Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920005672 polyolefin resin Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000002940 repellent Effects 0.000 description 1
- 239000011115 styrene butadiene Substances 0.000 description 1
- 229920003048 styrene butadiene rubber Polymers 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Description
前記吸収体の長手方向両側部において、不透液性の被覆シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の裏面側から表面側まで延在して固定され、
前記被覆シートの表面側延在部分に沿って複数の開孔が設けられるとともに、前記開孔は長孔とされ、かつこの長孔の長手方向外方端側が吸収体中央の短手方向線側に傾斜するとともに、前記長孔の長手方向線と吸収体の短手方向線との交差角θが30°<θ<60°の範囲となるように配置されていることを特徴とする使い捨て紙おむつ
が提供される。
前記吸収体の長手方向両側部において、前記防漏シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の表面側まで延在して固定され、前記防漏シートの表面側延在部分に前記複数の開孔が設けられている請求項1記載の使い捨て紙おむつが提供される。
これによって、前記ポケット部分に体液の液溜まりが形成されず、横漏れ及び前後漏れ防止効果に優れ、吸収体表面の体液吸収効率が向上するようになる。
先ず最初に、吸収性本体10の構造の一例について図2及び図3に基づいて詳述する。
次に外装シート20の構造について、図4及び図5に基づいて詳述する。外装シート20は、上層不織布20A及び下層不織布20Bが、ホットメルト接着剤などにより接着された2層構造の不織布シートとされ、前記上層不織布20Aと下層不織布20Bとの間に各種弾性伸縮部材がホットメルト接着剤などにより接着され、伸縮性が付与されている。平面形状は、中間両側部に夫々脚部開口を形成するための凹状の脚回りカットライン29により、全体として擬似砂時計形状を成している。
本発明では、前記防漏シート12の表面側延在部分に複数の開孔3、3…が設けられるようになっている。これにより、表面側両側部での体液吸収が図られるとともに、吸収体13に吸収された体液の滲み出し防止が図られている。
(1)上記形態例では、パンツ型使い捨て紙おむつを例に採り本発明を説明したが、本発明はテープ式使い捨て紙おむつに対しても同様に適用が可能である。
Claims (10)
- 吸収体と、前記吸収体の少なくとも表面側を覆う透液性の表面シートと、前記吸収体の少なくとも裏面側を覆う不透液性の防漏シートとを含み、表面がわ両側部に立体ギャザーが形成された使い捨て紙おむつにおいて、
前記吸収体の長手方向両側部において、不透液性の被覆シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の裏面側から表面側まで延在して固定され、
前記被覆シートの表面側延在部分に沿って複数の開孔が設けられるとともに、前記開孔は長孔とされ、かつこの長孔の長手方向外方端側が吸収体中央の短手方向線側に傾斜するとともに、前記長孔の長手方向線と吸収体の短手方向線との交差角θが30°<θ<60°の範囲となるように配置されていることを特徴とする使い捨て紙おむつ。 - 前記被覆シートが前記防漏シートによって構成され、
前記吸収体の長手方向両側部において、前記防漏シートが吸収体側縁部を巻き込んで吸収体の表面側まで延在して固定され、前記防漏シートの表面側延在部分に前記複数の開孔が設けられている請求項1記載の使い捨て紙おむつ。 - 前記吸収体の長手方向両側部において、前記表面シートが前記被覆シート又は防漏シートによって巻き込まれた吸収体側縁部をさらに上側から巻き込んで吸収体の裏面側まで延在して固定され、かつ前記立体ギャザーを形成するためのギャザー不織布が前記表面シートによって巻き込まれた吸収体側縁部をさらに上側から巻き込んで吸収体の裏面側まで延在して固定されている請求項1、2いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に対応する前記表面シートに開孔が設けられている請求項1〜3いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、装着時に股間部に相当する部位とそれ以外の前後端部とで開孔率を異なるようにしてある請求項1〜4いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、装着時に股間部に相当する部位とそれ以外の前後端部とで開孔の形状及び/又は大きさを異なるようにしてある請求項1〜4いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、装着時に股間部に相当する部位以外の前後端部に、股間部から前後端部に向かって漸次小さくなるようにしてある請求項1〜4いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、前記吸収体の長手方向長さLに対して、吸収体の長手方向両端から最大L/6の範囲には形成しないようにしてある請求項1〜4いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、装着時に股間部に相当する部位に設けられる開孔群と、それ以外の前後端部に設けられる開孔群との間に離隔部を形成してある請求項1〜4いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
- 前記被覆シート又は防漏シートの表面側延在部分に設けられる開孔は、前記被覆シート又は防漏シートの厚み方向に対し、表面側が広く裏面側が狭くなるように形成されている請求項1〜9いずれかに記載の使い捨て紙おむつ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007254898A JP5065836B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 使い捨て紙おむつ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007254898A JP5065836B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 使い捨て紙おむつ |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2009082358A JP2009082358A (ja) | 2009-04-23 |
| JP2009082358A5 JP2009082358A5 (ja) | 2010-11-11 |
| JP5065836B2 true JP5065836B2 (ja) | 2012-11-07 |
Family
ID=40656644
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007254898A Expired - Fee Related JP5065836B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 使い捨て紙おむつ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5065836B2 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009285196A (ja) * | 2008-05-29 | 2009-12-10 | Uni Charm Corp | 吸収性物品 |
| JP6278434B2 (ja) * | 2013-03-28 | 2018-02-14 | 大王製紙株式会社 | 使い捨ておむつ |
| JP5964389B2 (ja) | 2014-10-24 | 2016-08-03 | 大王製紙株式会社 | パンツタイプ使い捨ておむつ |
| JP6446082B2 (ja) | 2017-03-17 | 2018-12-26 | 大王製紙株式会社 | 吸収性物品 |
| JP6939671B2 (ja) * | 2018-03-22 | 2021-09-22 | 王子ホールディングス株式会社 | 吸収性物品 |
| JP7311132B2 (ja) * | 2018-05-16 | 2023-07-19 | 第一衛材株式会社 | 衛生吸収具 |
| KR102445786B1 (ko) * | 2020-03-20 | 2022-09-21 | 주식회사 디알컴퍼니 | 요실금 팬티 |
| JP2023000880A (ja) * | 2021-06-18 | 2023-01-04 | 花王株式会社 | 吸収性物品 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4423088B2 (ja) * | 2004-03-31 | 2010-03-03 | 大王製紙株式会社 | 吸収性物品及びその製造方法 |
| JP4522281B2 (ja) * | 2005-02-10 | 2010-08-11 | 株式会社リブドゥコーポレーション | 使い捨ておむつ |
| BRPI0520752A2 (pt) * | 2005-12-16 | 2009-05-26 | Sca Hygiene Prod Ab | produto absorvente |
-
2007
- 2007-09-28 JP JP2007254898A patent/JP5065836B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2009082358A (ja) | 2009-04-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3919023B1 (ja) | 使い捨ておむつ | |
| JP5065836B2 (ja) | 使い捨て紙おむつ | |
| JP4990070B2 (ja) | 使い捨ておむつ | |
| JP5074734B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP6399306B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| ES2962376T3 (es) | Artículo absorbente con flacidez reducida | |
| KR20120112419A (ko) | 흡수성 물품 | |
| JP5281977B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP2013192848A (ja) | 使い捨て紙おむつ | |
| JP5517682B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| KR20120104550A (ko) | 흡수성 물품 | |
| ES2962377T3 (es) | Artículo absorbente con una disposición de sellado que tiene una anchura constante | |
| JP4814835B2 (ja) | 体液吸収性物品 | |
| JP7151844B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP5319365B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP5942764B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| ES2932214T3 (es) | Artículo absorbente con sellados de canal y método de fabricación del artículo absorbente | |
| JP5090975B2 (ja) | 使い捨ておむつ | |
| JP5536545B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP6575656B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP5319366B2 (ja) | 吸収性物品 | |
| JP2008284167A (ja) | 吸収性物品 | |
| JP2011250878A5 (ja) | ||
| JP2017217257A (ja) | 吸収性物品 | |
| JP2021083694A (ja) | パンツ型吸収性物品 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100922 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100922 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120112 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120116 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120312 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120725 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120810 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5065836 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150817 Year of fee payment: 3 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150817 Year of fee payment: 3 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |