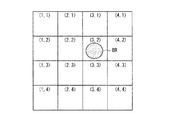JP5984482B2 - 投射型プロジェクタ - Google Patents
投射型プロジェクタ Download PDFInfo
- Publication number
- JP5984482B2 JP5984482B2 JP2012101145A JP2012101145A JP5984482B2 JP 5984482 B2 JP5984482 B2 JP 5984482B2 JP 2012101145 A JP2012101145 A JP 2012101145A JP 2012101145 A JP2012101145 A JP 2012101145A JP 5984482 B2 JP5984482 B2 JP 5984482B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light source
- coefficient
- signal
- sum
- blue light
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/12—Picture reproducers
- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
- H04N9/3141—Constructional details thereof
- H04N9/315—Modulator illumination systems
- H04N9/3155—Modulator illumination systems for controlling the light source
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/20—Lamp housings
- G03B21/2053—Intensity control of illuminating light
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
- G03B21/14—Details
- G03B21/20—Lamp housings
- G03B21/2086—Security or safety means in lamp houses
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/12—Picture reproducers
- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
- H04N9/3141—Constructional details thereof
- H04N9/315—Modulator illumination systems
- H04N9/3158—Modulator illumination systems for controlling the spectrum
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/12—Picture reproducers
- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
- H04N9/3179—Video signal processing therefor
- H04N9/3182—Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/3406—Control of illumination source
- G09G3/3413—Details of control of colour illumination sources
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/12—Picture reproducers
- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
- H04N9/3191—Testing thereof
- H04N9/3194—Testing thereof including sensor feedback
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/64—Circuits for processing colour signals
- H04N9/643—Hue control means, e.g. flesh tone control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/64—Circuits for processing colour signals
- H04N9/68—Circuits for processing colour signals for controlling the amplitude of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/79—Processing of colour television signals in connection with recording
- H04N9/793—Processing of colour television signals in connection with recording for controlling the level of the chrominance signal, e.g. by means of automatic chroma control circuits
- H04N9/7933—Processing of colour television signals in connection with recording for controlling the level of the chrominance signal, e.g. by means of automatic chroma control circuits the level control being frequency-dependent
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
- Projection Apparatus (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
Description
パーソナルコンピュータやDVDレコーダ等のビデオ機器など、映像信号を出力する機器から映像信号を受け、その映像をスクリーンに投射する投射型プロジェクタにおいては、代表的な構成として以下の2種類が挙げられる。
図2は、本発明に係る実施の形態1の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部501、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図である。なお、青色光影響軽減部501は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
図3は、本発明に係る実施の形態2の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部502、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図2に示した青色光影響軽減部501と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部502は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
図5は、本発明に係る実施の形態3の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部503、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図3に示した青色光影響軽減部502と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部503は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
以上説明した実施の形態2、3においては、レーザ光のような単波長の光源を備えた投射型プロジェクタを前提として説明したが、本発明に係る実施の形態4では、例えば図6に示すような、単波長ではなく所定の波長幅を持ったLED等を光源とする構成を前提とする。
以上説明した実施の形態1〜4においては、総和算出器1〜3が、赤色信号R、緑色信号Gおよび青色信号Bのそれぞれについて映像信号1フレーム分の赤色信号総和ΣR、緑色信号総和ΣGおよび青色信号総和ΣBを算出するものとして説明した。実施の形態5の投射型プロジェクタにおいては、総和算出器1〜3が、投射映像1フレームをN分割した場合のある領域を構成する複数の画素(液晶パネル31の画素)における赤色信号、緑色信号、青色信号の総和を算出するという点で異なっている。
以上説明した実施の形態1〜4においては、総和算出器1〜3は、赤色信号R、緑色信号Gおよび青色信号Bを受け、それぞれについて映像信号1フレーム分の全画素(液晶パネル31の全画素)について各色信号の総和を算出する構成を採り、実施の形態5においては、投射映像1フレームをN分割した場合のある領域を構成する複数の全画素について各色信号の総和を算出する構成を採ったが、実施の形態6の投射型プロジェクタにおいては、総和を算出する対象を全画素とせず、所定の画素間隔で間引いた画素についての総和を算出することを特徴とする。
以上説明した実施の形態6においては、総和算出器1〜3では、赤色信号、緑色信号、青色信号を所定の画素間隔で間引いた画素について総和を算出する構成を採っていた。そのため、画素間隔をM画素間隔とすると、1画素目、(M+1)画素目、(2M+1)画素目、(3M+1)画素目、・・・の画素について赤色信号、緑色信号、青色信号を用いることになる。この場合、全てのフレームにおいて総和を算出する対象となる画素は同じものとなる。
図8は、本発明に係る実施の形態8の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部504、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図2に示した青色光影響軽減部501と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部504は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
図9は、本発明に係る実施の形態9の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部505、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図2に示した青色光影響軽減部501と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部505は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
図10は、本発明に係る実施の形態10の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部506、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図2に示した青色光影響軽減部501と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部506は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
図11は、本発明に係る実施の形態11の投射型プロジェクタの青色光影響軽減部507、光源部20および出射光変調部30の構成を示すブロック図であり、図2に示した青色光影響軽減部501と同一の構成については同一の符号を付し、重複する説明は省略する。なお、青色光影響軽減部507は、図1に示した映像信号処理部50に含まれる構成である。
Claims (12)
- 光源部で発生された光を変調する光変調部と、
入力された映像信号を処理する映像信号処理部と、
前記光変調部で変調された光を外部の投射対象に投射して投射映像を得る投射光学系とを備えた投射型プロジェクタであって、
前記映像信号処理部は、青色光による網膜への影響を軽減する青色光影響軽減部を有し、
前記青色光影響軽減部は、
映像信号に含まれる赤色信号、緑色信号および青色信号のうち、前記青色信号の割合だけが多い場合には、前記光源部を制御して前記投射映像の明るさを全体的に下げる青色光影響軽減信号を生成することを特徴とする、投射型プロジェクタ。 - 前記青色光影響軽減部は、
1フレームの映像信号の個々の画素における前記赤色信号、前記緑色信号および前記青色信号の総和をそれぞれ算出する第1、第2および第3の総和算出器と
前記第1の総和算出器および前記第2の総和算出器の出力値を加算する第1の加算器と、
前記第1の加算器の出力値と前記第3の総和算出器の出力値とを加算する第2の加算器と、
前記第1の加算器の出力値を前記第2の加算器の出力値で除算する除算器と、
前記除算器の出力値が規定値未満の場合は第1の係数を、前記規定値以上の場合は前記第1の係数よりも大きな第2の係数を青色光影響軽減信号として出力する係数算出器と、を備え、
前記光源部は、
赤色光源、緑色光源および青色光源と、
前記赤色光源を駆動する第1の駆動電流を出力する第1の光源制御ドライバ、前記緑色光源を駆動する第2の駆動電流を出力する第2の光源制御ドライバおよび前記青色光源を駆動する第3の駆動電流を出力する第3の光源制御ドライバを備え、
前記青色光影響軽減信号は、前記第1〜第3の光源制御ドライバに与えられ、
前記第1〜第3の光源制御ドライバのそれぞれは、
前記青色光影響軽減信号に基づいて、前記第1または第2の係数に対応するデューティ比で前記第1〜第3の駆動電流を出力する、請求項1記載の投射型プロジェクタ。 - 前記青色光影響軽減部は、
1フレームの映像信号の個々の画素における前記赤色信号、前記緑色信号および前記青色信号の総和をそれぞれ算出する第1、第2および第3の総和算出器と、
前記第1、第2および第3の総和算出器の出力値に、光の3原色に対応した赤色光の波長の比視感度、緑色光の波長の比視感度および青色光の波長の比視感度を、それぞれ1から減じた値を係数として乗じる、第1、第2および第3の乗算器と、
前記第1の乗算器および前記第2の乗算器の出力値を加算する第1の加算器と、
前記第1の加算器の出力値と前記第3の乗算器の出力値とを加算する第2の加算器と、
前記第1の加算器の出力値を前記第2の加算器の出力値で除算する除算器と、
前記除算器の出力値が規定値未満の場合は第1の係数を、前記規定値以上の場合は前記第1の係数よりも大きな第2の係数を出力する係数算出器と、を備え、
前記光源部は、
赤色光源、緑色光源および青色光源と、
前記赤色光源を駆動する第1の駆動電流を出力する第1の光源制御ドライバ、前記緑色光源を駆動する第2の駆動電流を出力する第2の光源制御ドライバおよび前記青色光源を駆動する第3の駆動電流を出力する第3の光源制御ドライバを備え、
前記青色光影響軽減信号は、前記第1〜第3の光源制御ドライバに与えられ、
前記第1〜第3の光源制御ドライバのそれぞれは、
前記青色光影響軽減信号に基づいて、前記第1または第2の係数に対応するデューティ比で前記第1〜第3の駆動電流を出力する、請求項1記載の投射型プロジェクタ。 - 前記青色光影響軽減部は、
1フレームの映像信号の個々の画素における前記赤色信号、前記緑色信号および前記青色信号の総和をそれぞれ算出する第1、第2および第3の総和算出器と、
前記第1、第2および第3の総和算出器の出力値に、光の3原色に対応した赤色光の波長の比視感度の逆数、緑色光の波長の比視感度の逆数および青色光の波長の比視感度の逆数を、それぞれ係数として乗じる、第1、第2および第3の乗算器と、
前記第1の乗算器および前記第2の乗算器の出力値を加算する第1の加算器と、
前記第1の加算器の出力値と前記第3の乗算器の出力値とを加算する第2の加算器と、
前記第1の加算器の出力値を前記第2の加算器の出力値で除算する除算器と、
前記除算器の出力値が規定値未満の場合は第1の係数を、前記規定値以上の場合は前記第1の係数よりも大きな第2の係数を出力する係数算出器と、を備え、
前記光源部は、
赤色光源、緑色光源および青色光源と、
前記赤色光源を駆動する第1の駆動電流を出力する第1の光源制御ドライバ、前記緑色光源を駆動する第2の駆動電流を出力する第2の光源制御ドライバおよび前記青色光源を駆動する第3の駆動電流を出力する第3の光源制御ドライバを備え、
前記青色光影響軽減信号は、前記第1〜第3の光源制御ドライバに与えられ、
前記第1〜第3の光源制御ドライバのそれぞれは、
前記青色光影響軽減信号に基づいて、前記第1または第2の係数に対応するデューティ比で前記第1〜第3の駆動電流を出力する、請求項1記載の投射型プロジェクタ。 - 前記光源部は、
一定の波長範囲を有する光を発生し、
前記映像信号処理部は、
各色光の分光分布の波長範囲内の各波長における相対エネルギーに、それぞれの波長での比視感度を乗じ、その値が最大となる波長を代表波長として、前記赤色光の波長の比視感度、前記緑色光の波長の比視感度および前記青色光の波長の比視感度を決定する、請求項3または請求項4記載の投射型プロジェクタ。 - 前記第1、第2および第3の総和算出器は、
1フレームの前記投射映像を複数の領域に分割した場合の各領域を構成する個々の画素における前記赤色信号、前記緑色信号および前記青色信号の総和をそれぞれ領域ごとに算出し、
前記係数算出器は、
何れかの領域における前記除算器の出力値が前記規定値未満の場合は前記第1の係数を、前記規定値以上の場合は前記第2の係数を出力し、
前記複数の領域のうち、何れか1つの領域でも前記第1の係数が出力される場合には、前記青色光影響軽減信号として前記第1の係数を出力する、請求項2〜請求項5の何れか1項に記載の投射型プロジェクタ。 - 前記第1、第2および第3の総和算出器は、
前記1フレームの映像信号の前記個々の画素のうち所定の画素間隔で間引いた画素についての総和を算出する、請求項2〜請求項6の何れか1項に記載の投射型プロジェクタ。 - 前記第1、第2および第3の総和算出器は、
前記1フレームの映像信号の前記個々の画素のうち、最初に信号を取り込む画素の位置をフレームごとに変えることで、総和を算出する対象となる画素をフレームごとに変える、請求項7記載の投射型プロジェクタ。 - 前記除算器と前記係数算出器との間に設けられ、
所定フレーム数について前記除算器の出力値の総和を取る第4の総和算出器と、
0を超え1未満の特定の値から1まで段階的に大きくした係数を記憶する係数記憶器とを備え、
前記係数算出器は、
前記第4の総和算出器の出力値が、前記規定値未満の場合は、現在の値より1段階小さい係数を前記係数記憶器から読み出して前記第1の係数とし、
前記第4の総和算出器の出力値が、前記規定値以上の場合は、現在の値より1段階大きい係数を前記係数記憶器から読み出して前記第2の係数とする、請求項2〜請求項8の何れか1項に記載の投射型プロジェクタ。 - 前記第4の総和算出器は、
前記映像信号が、パーソナルコンピュータからの映像信号であるか、ビデオ機器からの映像信号であるかに基づいて前記所定フレーム数の個数を設定する、請求項9記載の投射型プロジェクタ。 - 前記投射対象までの距離を測定する測距器と、
前記投射光学系に含まれるズームレンズの回転位置を検出する回転位置検出器と、
前記距離と前記ズームレンズの前記回転位置を入力とし、前記投射映像の推定面積を算出して出力する投射映像面積推定器とをさらに備え、
前記係数算出器は、
前記推定面積に基づいて前記第1の係数および前記第2の係数を可変して出力する、請求項2〜請求項10の何れか1項に記載の投射型プロジェクタ。 - 周囲の明るさを測定して、その照度を出力する測光器をさらに備え、
前記係数算出器は、
前記照度に基づいて前記第1の係数および前記第2の係数を可変して出力する、請求項2〜請求項10の何れか1項に記載の投射型プロジェクタ。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012101145A JP5984482B2 (ja) | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 投射型プロジェクタ |
| US13/686,705 US9039199B2 (en) | 2012-04-26 | 2012-11-27 | Projector having blue light alleviating part |
| EP12195076.0A EP2658264B1 (en) | 2012-04-26 | 2012-11-30 | Projector |
| TW101146333A TWI476502B (zh) | 2012-04-26 | 2012-12-10 | 投射型投影機 |
| CN201310052205.XA CN103379345B (zh) | 2012-04-26 | 2013-02-18 | 投射型投影仪 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012101145A JP5984482B2 (ja) | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 投射型プロジェクタ |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2013229791A JP2013229791A (ja) | 2013-11-07 |
| JP2013229791A5 JP2013229791A5 (ja) | 2015-04-02 |
| JP5984482B2 true JP5984482B2 (ja) | 2016-09-06 |
Family
ID=47325904
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012101145A Expired - Fee Related JP5984482B2 (ja) | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 投射型プロジェクタ |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9039199B2 (ja) |
| EP (1) | EP2658264B1 (ja) |
| JP (1) | JP5984482B2 (ja) |
| CN (1) | CN103379345B (ja) |
| TW (1) | TWI476502B (ja) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10347163B1 (en) | 2008-11-13 | 2019-07-09 | F.lux Software LLC | Adaptive color in illuminative devices |
| JP6613640B2 (ja) * | 2014-06-16 | 2019-12-04 | 大日本印刷株式会社 | 画像処理装置、表示装置並びに画像処理方法及び画像処理用プログラム |
| JP2016126110A (ja) * | 2014-12-26 | 2016-07-11 | 船井電機株式会社 | 表示装置 |
| JP6502195B2 (ja) * | 2015-06-30 | 2019-04-17 | 日置電機株式会社 | 測定装置および測定方法 |
| US10255880B1 (en) | 2015-09-14 | 2019-04-09 | F.lux Software LLC | Coordinated adjustment of display brightness |
| TWI654475B (zh) | 2017-09-19 | 2019-03-21 | 明基電通股份有限公司 | 投影機 |
| CN109884848B (zh) * | 2017-12-06 | 2023-09-01 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 投影设备 |
| CN109884846B (zh) * | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 投影设备 |
| CN109884850B (zh) * | 2017-12-06 | 2021-08-24 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 投影设备 |
| CN109884845B (zh) * | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 投影设备 |
| US10469813B2 (en) | 2017-12-21 | 2019-11-05 | Stmicroelectronics S.R.L. | Light source response compensation for light projection system using a graphics processing unit |
| WO2019217966A1 (en) | 2018-05-11 | 2019-11-14 | F.lux Software LLC | Coordinated lighting adjustment for groups |
| WO2020210740A1 (en) * | 2019-04-11 | 2020-10-15 | PixelDisplay Inc. | Method and apparatus of a multi-modal illumination and display for improved color rendering, power efficiency, health and eye-safety |
| CN112118433B (zh) * | 2019-06-20 | 2022-01-04 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 图像显示方法及激光投影设备 |
| WO2021009104A1 (en) * | 2019-07-15 | 2021-01-21 | Interdigital Ce Patent Holdings, Sas | Device and method for controlling output levels of content |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2752309B2 (ja) * | 1993-01-19 | 1998-05-18 | 松下電器産業株式会社 | 表示装置 |
| KR0147214B1 (ko) | 1994-09-23 | 1998-09-15 | 이헌조 | 프로젝터의 광량제어장치 |
| US6075525A (en) * | 1998-05-05 | 2000-06-13 | Hsieh; Kuan-Hong | Method for preventing the injury of eyesight during operating a device with a display |
| US6078309A (en) * | 1998-05-22 | 2000-06-20 | Way Tech Development, Inc. | System and method for visually measuring color characteristics of a display |
| JP3692321B2 (ja) * | 2000-10-31 | 2005-09-07 | ヒューレット・パッカード・カンパニー | 照明付きディスプレイ及びその使用方法 |
| US7595811B2 (en) | 2001-07-26 | 2009-09-29 | Seiko Epson Corporation | Environment-complaint image display system, projector, and program |
| CN100424547C (zh) | 2002-12-26 | 2008-10-08 | 三洋电机株式会社 | 投影式视频显示器 |
| DE10361661A1 (de) * | 2003-07-14 | 2005-03-17 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | Licht emittierendes Bauelement mit einem Lumineszenz-Konversionselement |
| US20060152525A1 (en) * | 2005-01-13 | 2006-07-13 | Woog Kenneth M | Viewing screen color limiting device and method |
| JP4432818B2 (ja) | 2005-04-01 | 2010-03-17 | セイコーエプソン株式会社 | 画像表示装置、画像表示方法、および画像表示プログラム |
| JP2006330447A (ja) | 2005-05-27 | 2006-12-07 | Mitsubishi Electric Corp | フロントプロジェクタ装置 |
| US7967452B2 (en) * | 2005-08-26 | 2011-06-28 | Panasonic Corporation | Projection type display apparatus |
| KR100985860B1 (ko) * | 2005-11-08 | 2010-10-08 | 삼성전자주식회사 | 발광장치 및 그 제어방법 |
| ES2289957B1 (es) * | 2007-02-07 | 2008-12-01 | Universidad Complutense De Madrid | Fuente de iluminacion con emision reducida de longitudes de onda corta para la proteccion de ojos. |
| JP2008311532A (ja) | 2007-06-15 | 2008-12-25 | Rohm Co Ltd | 白色発光装置及び白色発光装置の形成方法 |
| JP5382849B2 (ja) * | 2008-12-19 | 2014-01-08 | パナソニック株式会社 | 光源装置 |
| JP5527058B2 (ja) * | 2010-07-06 | 2014-06-18 | セイコーエプソン株式会社 | 光源装置及びプロジェクター |
| JP5445379B2 (ja) * | 2010-07-30 | 2014-03-19 | セイコーエプソン株式会社 | プロジェクター |
| CN102375314B (zh) * | 2010-08-09 | 2013-12-04 | 台达电子工业股份有限公司 | 光源系统及其适用的投影机 |
| TWM410899U (en) * | 2011-01-27 | 2011-09-01 | Optoma Corp | Projection system and power failure protection apparatus |
| TWM409438U (en) | 2011-03-09 | 2011-08-11 | Bin Shyh Entpr Co Ltd | Lens structure for blocking blue light |
| JP5999959B2 (ja) * | 2012-04-05 | 2016-09-28 | 三菱電機株式会社 | 投射型プロジェクタ |
-
2012
- 2012-04-26 JP JP2012101145A patent/JP5984482B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-27 US US13/686,705 patent/US9039199B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-30 EP EP12195076.0A patent/EP2658264B1/en not_active Not-in-force
- 2012-12-10 TW TW101146333A patent/TWI476502B/zh not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-02-18 CN CN201310052205.XA patent/CN103379345B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TWI476502B (zh) | 2015-03-11 |
| CN103379345B (zh) | 2015-11-18 |
| EP2658264A1 (en) | 2013-10-30 |
| EP2658264B1 (en) | 2016-11-23 |
| JP2013229791A (ja) | 2013-11-07 |
| US9039199B2 (en) | 2015-05-26 |
| TW201344331A (zh) | 2013-11-01 |
| CN103379345A (zh) | 2013-10-30 |
| US20130286052A1 (en) | 2013-10-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5984482B2 (ja) | 投射型プロジェクタ | |
| JP5999959B2 (ja) | 投射型プロジェクタ | |
| JP4956932B2 (ja) | 画像表示装置、及び画像表示方法 | |
| JP4904792B2 (ja) | 画像表示方法、画像表示装置およびプロジェクタ | |
| JP2003339056A (ja) | 画像処理システム、プロジェクタ、画像処理方法、プログラムおよび情報記憶媒体 | |
| JP4701851B2 (ja) | 画像表示装置とその制御方法 | |
| JP2008020887A (ja) | 映像表示装置及び映像表示方法 | |
| KR100756708B1 (ko) | 화상 표시 방법 및 장치와 프로젝터 | |
| JP5092207B2 (ja) | 画像表示装置及び画像表示方法 | |
| JP6057397B2 (ja) | プロジェクタ、色補正装置および投写方法 | |
| JP6232796B2 (ja) | 画像表示装置および画像表示方法 | |
| JP2007121541A (ja) | 画像表示装置、及び画像表示方法 | |
| KR20090023275A (ko) | 화상 표시 장치 | |
| JP5353990B2 (ja) | 画像表示装置、及び画像表示方法 | |
| JP2011095402A (ja) | 投写型表示装置 | |
| JP2005266462A (ja) | プロジェクタ装置及びプロジェクタ装置における色補正方法 | |
| JP5605038B2 (ja) | 画像処理装置、画像表示装置、及び画像処理方法 | |
| JP2009098627A (ja) | 投写型映像表示装置 | |
| JP2015129781A (ja) | 前面投射型プロジェクタ | |
| WO2011092807A1 (ja) | 投写型表示装置、および投写型表示装置の制御方法 | |
| WO2010089937A1 (ja) | 画像表示制御装置、及び、画像表示制御方法 | |
| JP2005227577A (ja) | 液晶プロジェクタ | |
| JP2019169867A (ja) | 投影システム、情報処理装置及びその制御方法及びプログラム、並びに、投影装置 | |
| JP2009186546A (ja) | プロジェクタおよび投写方法 | |
| JP2011150110A (ja) | 画像処理装置、画像表示システム、画像処理方法及びむら補正値生成方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150213 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150213 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20151130 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20151208 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160129 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160705 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160802 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5984482 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |