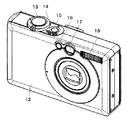JP5094485B2 - レンズ鏡筒および撮影装置 - Google Patents
レンズ鏡筒および撮影装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5094485B2 JP5094485B2 JP2008061148A JP2008061148A JP5094485B2 JP 5094485 B2 JP5094485 B2 JP 5094485B2 JP 2008061148 A JP2008061148 A JP 2008061148A JP 2008061148 A JP2008061148 A JP 2008061148A JP 5094485 B2 JP5094485 B2 JP 5094485B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- rectilinear
- optical axis
- lens
- cylindrical portion
- lens barrel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
- G02B7/02—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
- G02B7/04—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
- G02B7/10—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens
- G02B7/102—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens controlled by a microcomputer
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lens Barrels (AREA)
Description
1a フォロワ部
1b 第3直進規制部
2 第2レンズ部
4 直進規制部材
6 第2直進規制部材
6a 直進規制部
6b 第2直進規制部
6r リブ
7 第2円筒部
7c 被第3直進規制部
8 第3円筒部
71 撮影レンズ鏡筒
Claims (5)
- フォロア部と直進規制部が設けられたレンズ部を保持し、光軸方向に移動するレンズ鏡筒であって、
前記レンズ部に設けられたフォロア部を追従させるカム部が外周に形成され、回転することにより前記レンズ部を前記光軸方向に移動させる円筒部と、
前記レンズ部の移動を光軸方向に規制する直進規制部材と、
前記円筒部とバヨネット結合され、バヨネット結合された前記円筒部が光軸周りに回転しても、光軸周りに回転しないように光軸周りの回転が規制されており、かつ前記レンズ部が光軸周りに回転すると、前記レンズ部に設けられた直進規制部と非当接状態から当接状態へ移行する被直進規制部が設けられた第2円筒部と、
前記直進規制部材および前記第2円筒部の光軸回りの回転を規制する第2直進規制部材と、
前記第2円筒部の外周に配置され、前記円筒部および前記第2円筒部を前記光軸方向に移動させる第3円筒部とを有し、
前記第2直進規制部材は、円環部と、前記円環部から前記光軸方向に突出して設けられ、前記直進規制部材および前記第2円筒部とそれぞれ嵌合し、前記直進規制部材および前記第2円筒部の移動を直進に規制する複数の第2直進規制部と、前記第2直進規制部の両側の前記円環部に形成され、前記第3円筒部と回転自在に結合する結合部とを有することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 前記第2直進規制部材は、前記第2直進規制部の接線方向における両側の前記円環部に形成され、前記第2直進規制部の変形を防止する変形防止保持部を有することを特徴とする請求項1記載のレンズ鏡筒。
- 前記変形防止保持部は、その両側に配置された前記複数の第2直進規制部を保持することを特徴とする請求項2記載のレンズ鏡筒。
- 前記結合部は、前記変形防止保持部を兼ねており、前記第3円筒部の後端部にバヨネット結合することを特徴とする請求項2記載のレンズ鏡筒。
- 請求項1乃至4のいずれかの1項に記載のレンズ鏡筒を備えた撮影装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008061148A JP5094485B2 (ja) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | レンズ鏡筒および撮影装置 |
| EP09154765A EP2101206B1 (en) | 2008-03-11 | 2009-03-10 | Lens barrel |
| US12/401,615 US7936985B2 (en) | 2008-03-11 | 2009-03-10 | Lens barrel and image pickup apparatus |
| CN2009101187692A CN101533144B (zh) | 2008-03-11 | 2009-03-11 | 镜头镜筒和摄像设备 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2008061148A JP5094485B2 (ja) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | レンズ鏡筒および撮影装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2009217013A JP2009217013A (ja) | 2009-09-24 |
| JP2009217013A5 JP2009217013A5 (ja) | 2011-04-28 |
| JP5094485B2 true JP5094485B2 (ja) | 2012-12-12 |
Family
ID=40532517
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2008061148A Expired - Fee Related JP5094485B2 (ja) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | レンズ鏡筒および撮影装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7936985B2 (ja) |
| EP (1) | EP2101206B1 (ja) |
| JP (1) | JP5094485B2 (ja) |
| CN (1) | CN101533144B (ja) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101599881B1 (ko) * | 2009-06-30 | 2016-03-04 | 삼성전자주식회사 | 화각 미리 보기 기능을 갖는 디지털 영상 신호 처리 장치, 이의 제어 방법 및 상기 방법을 기록한 기록 매체 |
| US8520328B2 (en) * | 2010-02-05 | 2013-08-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Lens barrel and imaging apparatus |
| JP5882625B2 (ja) * | 2010-08-18 | 2016-03-09 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒及び撮像装置 |
| JP6136791B2 (ja) * | 2013-09-11 | 2017-05-31 | ソニー株式会社 | レンズ鏡筒及び撮像装置 |
| CN109669268A (zh) | 2019-02-25 | 2019-04-23 | 京东方科技集团股份有限公司 | 虚拟现实镜筒组件和虚拟现实设备 |
| CN110658622A (zh) * | 2019-08-19 | 2020-01-07 | 深圳市矽赫科技有限公司 | 一种自动调节的微显示器光学目镜及其调整方法 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH08160277A (ja) * | 1994-12-01 | 1996-06-21 | Canon Inc | ズームレンズ |
| JP2000066081A (ja) | 1998-08-20 | 2000-03-03 | Canon Inc | レンズ鏡筒 |
| JP3679683B2 (ja) * | 2000-05-16 | 2005-08-03 | キヤノン株式会社 | 撮像装置 |
| US6934096B1 (en) * | 2000-05-16 | 2005-08-23 | Canon Kabushiki Kaisha | Optical device |
| JP2003021776A (ja) | 2001-07-10 | 2003-01-24 | Olympus Optical Co Ltd | ズーム鏡枠およびズームカメラ |
| JP3655865B2 (ja) * | 2001-10-31 | 2005-06-02 | ペンタックス株式会社 | レンズ鏡筒 |
| JP3689379B2 (ja) * | 2002-03-20 | 2005-08-31 | 株式会社タムロン | 高倍率ズームレンズ |
| JP4763342B2 (ja) * | 2005-05-13 | 2011-08-31 | 株式会社Suwaオプトロニクス | レンズ鏡筒及び撮像装置 |
| JP4817877B2 (ja) * | 2006-02-20 | 2011-11-16 | キヤノン株式会社 | レンズ装置および撮像装置 |
-
2008
- 2008-03-11 JP JP2008061148A patent/JP5094485B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-03-10 EP EP09154765A patent/EP2101206B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-10 US US12/401,615 patent/US7936985B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-03-11 CN CN2009101187692A patent/CN101533144B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2101206A3 (en) | 2009-10-28 |
| CN101533144A (zh) | 2009-09-16 |
| EP2101206A2 (en) | 2009-09-16 |
| EP2101206B1 (en) | 2013-02-13 |
| US20090232484A1 (en) | 2009-09-17 |
| US7936985B2 (en) | 2011-05-03 |
| JP2009217013A (ja) | 2009-09-24 |
| CN101533144B (zh) | 2011-11-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4750723B2 (ja) | レンズ装置及び撮像装置 | |
| JP5328181B2 (ja) | レンズ鏡筒および撮影装置 | |
| JP5094485B2 (ja) | レンズ鏡筒および撮影装置 | |
| JP5274058B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |
| US7729060B2 (en) | Lens barrel and image pickup apparatus | |
| JP5335410B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮影装置 | |
| JP6270370B2 (ja) | レンズ鏡筒および撮像装置 | |
| JP4883276B2 (ja) | レンズ鏡胴及び撮像装置 | |
| JP5430258B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |
| JP5566163B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |
| JP5538763B2 (ja) | 光学機器 | |
| JP5566164B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |
| JP2008046200A (ja) | レンズ鏡胴及び撮像装置 | |
| JP2009217014A (ja) | レンズ鏡筒および撮影装置 | |
| JP5414471B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |
| JP4542111B2 (ja) | 鏡筒及び撮影装置 | |
| JP5489567B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |
| JP5570264B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |
| JP5039518B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮影装置 | |
| JP4542109B2 (ja) | 鏡筒及び撮影装置 | |
| JP5037802B2 (ja) | 組立て鏡筒 | |
| JP2007024997A (ja) | カメラ装置 | |
| JP4508707B2 (ja) | 鏡筒、および撮像装置 | |
| JP6271996B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮影装置 | |
| JP2006047392A (ja) | 光学機器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110311 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110314 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20111221 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120110 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120312 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120821 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120918 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150928 Year of fee payment: 3 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |