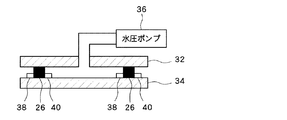JP4965213B2 - 変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 - Google Patents
変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4965213B2 JP4965213B2 JP2006267352A JP2006267352A JP4965213B2 JP 4965213 B2 JP4965213 B2 JP 4965213B2 JP 2006267352 A JP2006267352 A JP 2006267352A JP 2006267352 A JP2006267352 A JP 2006267352A JP 4965213 B2 JP4965213 B2 JP 4965213B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- modified polytetrafluoroethylene
- welding
- polytetrafluoroethylene molded
- molded body
- thermal
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 title claims description 60
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 title claims description 60
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims description 30
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 title claims description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 22
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 8
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 8
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 16
- 229920002943 EPDM rubber Polymers 0.000 description 10
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 10
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 8
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 8
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 8
- BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N tetrafluoroethene Chemical group FC(F)=C(F)F BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 229920001774 Perfluoroether Polymers 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 230000037303 wrinkles Effects 0.000 description 3
- QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N Vinyl ether Chemical compound C=COC=C QYKIQEUNHZKYBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 2
- 238000004073 vulcanization Methods 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000004925 denaturation Methods 0.000 description 1
- 230000036425 denaturation Effects 0.000 description 1
- BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N edrophonium chloride Chemical compound [Cl-].CC[N+](C)(C)C1=CC=CC(O)=C1 BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N ethene;prop-1-ene Chemical group C=C.CC=C HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001153 fluoro group Chemical group F* 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 1
- 239000009719 polyimide resin Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/70—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
- B29C66/71—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the composition of the plastics material of the parts to be joined
Landscapes
- Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
Description
上記変性PTFEテープの溶着個所(接合面)を含むようにマイクロダンベル型により打ち抜き、得られたマイクロダンベルを200mm/分の速度で引っ張って引張強度と伸びを測定した。なお本試験には、電子計測制御式万能材料試験機(オリオンテック社製テンシロンUTM−10T)を使用した。
上記変性PTFEテープの溶着個所の段差を、JIS B0601−1982に準じて表面粗さ計(東京精密社製SURFCOM130A)にて測定した。試験結果は、Rmaxとして30μm以下であった。
溶着個所の外観を目視により観察した。
上記溶着した変性PTFEテープから溶着部を中心にして全長約10cmに切り出し、シール試験用テープサンプルとした。シール試験用テープサンプルの表面に対して、金属ナトリウムによりフッ素原子を引き抜き、ラジカルを生じさせる処理を行った後、市販のEPDMゴム(エチレン・プロピレンゴム)をリング状に予備成型した成形体と加硫接着し、シール試験用のサンプルを作製した。
Claims (3)
- シート状の変性ポリ四フッ化エチレン成形体に形成された接合面を互いに対向し接触させて配置してなる、接合体とし、
前記接合面が接触して前記接合体に形成された接合線及びその近傍を、前記変性ポリ四フッ化エチレンの溶融温度以上の耐熱性を有する耐熱性剥離フィルムにより覆い、
前記接合線及びその近傍を、前記接合体の表裏両面から熱型により押圧しながら前記変性ポリ四フッ化エチレンの溶融温度以上の温度に加熱し、前記熱型は、一方が他方より前記接合線に対して直行方向の幅が幅広に形成されている、
ことを特徴とする変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法。 - 請求項1記載の変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法において、前記幅が狭い熱型とシート状の変性ポリ四フッ化エチレン成形体との間には、金属製の板部材が介在し、
前記板部材は、前記変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶融温度以上の温度に加熱しながら加圧される際に前記幅が狭い熱型と接するように介在し、
当該板部材の前記接合線に対して直行方向の幅は、前記幅が狭い熱型よりも広く形成されている、
ことを特徴とする変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法。 - 請求項2記載の変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法において、前記接合線及びその近傍の加熱終了後、前記接合体の表裏両面から冷却型により加圧しながら冷却することを特徴とする変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2006267352A JP4965213B2 (ja) | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2006267352A JP4965213B2 (ja) | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2008087183A JP2008087183A (ja) | 2008-04-17 |
| JP2008087183A5 JP2008087183A5 (ja) | 2009-03-26 |
| JP4965213B2 true JP4965213B2 (ja) | 2012-07-04 |
Family
ID=39371852
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2006267352A Active JP4965213B2 (ja) | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4965213B2 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4990261B2 (ja) | 2008-12-25 | 2012-08-01 | 日東電工株式会社 | シート部材の接合方法 |
| JP5378556B2 (ja) * | 2012-02-10 | 2013-12-25 | 日東電工株式会社 | シート部材の接合方法 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62183331A (ja) * | 1986-02-07 | 1987-08-11 | Ogawa Tento Kk | 膜状体接合方法 |
| JPH0634091Y2 (ja) * | 1990-08-02 | 1994-09-07 | 三ツ星ベルト株式会社 | 熱可塑性樹脂ベルト用ジョイントプレス |
| JPH06831A (ja) * | 1992-06-18 | 1994-01-11 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 積層板の製造方法 |
| JP3316230B2 (ja) * | 1992-07-02 | 2002-08-19 | バンドー化学株式会社 | 樹脂ベルトのエンドレス施工方法 |
| JPH08118473A (ja) * | 1994-10-21 | 1996-05-14 | Tokyo Nisshin Jiyabara Kk | 薄膜状樹脂半製品の溶着装置における溶着部の構造 |
| JPH10175256A (ja) * | 1996-12-19 | 1998-06-30 | Ricoh Co Ltd | フィルムの接合方法及び該接合方法により形成される転写ベルト及び該転写ベルトを備える画像形成装置 |
| JP2001018293A (ja) * | 1999-07-09 | 2001-01-23 | Bridgestone Corp | Evaシートの接合方法 |
| JP2001280504A (ja) * | 2000-03-31 | 2001-10-10 | Nichias Corp | ゴムガスケット構造およびその製造方法 |
| JP4063049B2 (ja) * | 2001-12-14 | 2008-03-19 | 旭硝子株式会社 | フィルムの接合方法、その方法を用いた広幅フィルムの製造方法 |
-
2006
- 2006-09-29 JP JP2006267352A patent/JP4965213B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2008087183A (ja) | 2008-04-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10093069B2 (en) | Method of forming large diameter thermoplastic seal | |
| JP5345696B2 (ja) | 大直径の熱可塑性シールの形成方法 | |
| US11826964B2 (en) | Method of bonding thermoplastic resin and metal | |
| JP2012508299A (ja) | 大直径熱可塑性シール | |
| US4990296A (en) | Welding of filled sintered polytetrafluoroethylene | |
| JP2021098229A (ja) | 二重壁式チタニウム管材及びその管材を製造する方法 | |
| US6228204B1 (en) | Method and apparatus for welding together fluoropolymer pipe liners | |
| JP4965213B2 (ja) | 変性ポリ四フッ化エチレン成形体の溶着方法 | |
| WO2020054425A1 (ja) | 銅管とアルミニウム管の接合体およびその接合方法 | |
| JPS6056611B2 (ja) | ポリテトラフルオルエチレンよりなる成形体を接合する方法 | |
| JP3910567B2 (ja) | 管状端を有する熱可塑性樹脂成形品の溶着方法 | |
| JP2005161735A (ja) | 樹脂製チューブの曲げ加工方法及び曲げ加工装置 | |
| CN104999658B (zh) | 一种超高分子量聚乙烯板材无缝焊接的方法 | |
| JP6948832B2 (ja) | 真空装置用伝熱板及びその製造方法 | |
| GB2528713A (en) | Bi-metallic mechanically lined pipe | |
| JP4106287B2 (ja) | 熱融着性管状体の接合方法 | |
| JP7081828B2 (ja) | 金属体-フッ素樹脂体接合体の製造方法 | |
| KR101271668B1 (ko) | 마찰교반용접방법 | |
| JPS58167089A (ja) | クラツドパイプ製作法 | |
| JP5297621B2 (ja) | 変性ptfe枠形状成形品及びその製造方法。 | |
| JP2008087183A5 (ja) | ||
| Shibayanagi et al. | Development of Disc Friction Joining and its Application to Dissimilar Butt Joining of Aluminum and Resin Plates | |
| JP2004189939A (ja) | 溶接被覆材、接合構造体、溶接施工方法、溶接施工品及び複合物品 | |
| JP2004301197A (ja) | 熱融着性管状体の接合体 | |
| JP2004268069A (ja) | 超音波圧接方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090209 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20090209 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110726 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110802 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111003 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120321 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120329 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 4965213 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150406 Year of fee payment: 3 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |