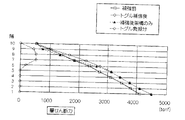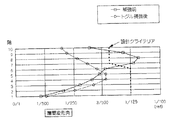JP2005290774A - 耐震補強構造 - Google Patents
耐震補強構造 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2005290774A JP2005290774A JP2004105776A JP2004105776A JP2005290774A JP 2005290774 A JP2005290774 A JP 2005290774A JP 2004105776 A JP2004105776 A JP 2004105776A JP 2004105776 A JP2004105776 A JP 2004105776A JP 2005290774 A JP2005290774 A JP 2005290774A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- frame
- control device
- existing building
- vibration control
- seismic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 title claims abstract description 25
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 claims description 13
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 10
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 8
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 8
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 3
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000009418 renovation Methods 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000009420 retrofitting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Transmission Devices (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
Abstract
【解決手段】 建物10と隣接して柱20が立設され、この柱20に梁22を掛け渡して架構24を構成している。この架構24と既設建物は連結部材と連結されている。この架構24内には、制震装置34が配置され、架構24を通じて既設建物が制震されるが、全ての架構24に制震装置34は配置されていない。すなわち、層間変形角から耐震補強が必要な階層を割り出して、その階層に連結された架構24に制震装置34を配置し、既設建物全階の層間変形角が所定値以下となるようにする。層間変形角から耐震補強が必要な階層を割り出して制震装置34を設置することで、制震装置34の設置個数が削減して施工コストが削減される。また、建物10の見栄えも良くなる。
【選択図】 図1
Description
22 梁
26 連結スラブ(連結部材)
34 制震装置
38 第1アーム
42 第2アーム
44 回転ヒンジ(連結部材)
46 油圧ダンパー
Claims (4)
- 多層階の既設建物と隣接して立設された複数本の支柱と、前記支柱に掛け渡され架構を構成する梁と、前記既設建物と前記架構とを連結する連結部材と、前記架構内に設けられ、前記連結部材を介して既設建物の振動を抑える制震装置と、を有し、前記既設建物が建てられた地盤に想定地震波を入力したとき、該既設建物全階の層間変形角が所定値以下となるように、前記架構内に前記制震装置を配置したことを特徴とする耐震補強構造。
- 前記既設建物が、鉄骨鉄筋コンクリート構造と鉄筋コンクリート構造で構築されており、耐震性能が劣る鉄筋コンクリート構造部分と連結された架構に制震装置を配置することを特徴とする請求項1に記載の耐震補強構造。
- 前記架構が、既設建物に設けられた共同廊下側に設けられたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の耐震補強構造。
- 前記制震装置が、架構の上側梁に一端が回転可能に取付けられた第1アームと、架構の下側梁に一端が回転可能に取付けられた第2アームと、第1アームと第2アームの自由端を所定の角度を持って回転可能に連結する連結部材と、一端が連結部材に回転可能に連結され、他端が下側梁に回転可能に連結されて、連結部材の移動により伸縮して振動エネルギーを吸収するダンパーと、で構成されていることを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の耐震補強構造。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004105776A JP2005290774A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 耐震補強構造 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004105776A JP2005290774A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 耐震補強構造 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2005290774A true JP2005290774A (ja) | 2005-10-20 |
Family
ID=35324023
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2004105776A Pending JP2005290774A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 耐震補強構造 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2005290774A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007132015A (ja) * | 2005-11-08 | 2007-05-31 | Univ Nihon | トグル制震装置 |
| JP2008002165A (ja) * | 2006-06-22 | 2008-01-10 | Tatsuji Ishimaru | 回転慣性質量付きトグル型制震装置 |
| CN105868477A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-17 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 基于层间位移角约束的结构抗震敏感性优化方法 |
| CN106709199A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-05-24 | 沈阳工业大学 | 基于层间位移的抗震鲁棒性方法 |
-
2004
- 2004-03-31 JP JP2004105776A patent/JP2005290774A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007132015A (ja) * | 2005-11-08 | 2007-05-31 | Univ Nihon | トグル制震装置 |
| JP2008002165A (ja) * | 2006-06-22 | 2008-01-10 | Tatsuji Ishimaru | 回転慣性質量付きトグル型制震装置 |
| CN105868477A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-08-17 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 基于层间位移角约束的结构抗震敏感性优化方法 |
| CN105868477B (zh) * | 2016-03-31 | 2019-05-31 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 基于层间位移角约束的结构抗震敏感性优化方法 |
| CN106709199A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-05-24 | 沈阳工业大学 | 基于层间位移的抗震鲁棒性方法 |
| CN106709199B (zh) * | 2017-01-04 | 2019-11-15 | 沈阳工业大学 | 基于层间位移的抗震鲁棒性方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6437685B1 (ja) | 既存建物用耐震補強装置 | |
| JP4038472B2 (ja) | 既存建物用制震補強架構及びそれを用いた制震構造物 | |
| JP4579615B2 (ja) | 連層コアウオール型制震超高層集合住宅建物 | |
| KR20090025496A (ko) | 내진성능 보강구조체 | |
| JP4597660B2 (ja) | 耐震補強構造を有する建物および建物の耐震補強方法 | |
| JP5406587B2 (ja) | 制振構造、制振構造を有する建物 | |
| JP2005290774A (ja) | 耐震補強構造 | |
| JP5059687B2 (ja) | 建物の連結制震構造 | |
| JP2010047933A (ja) | 制振補強フレーム | |
| JP4837145B1 (ja) | 制震補強架構付き構造物 | |
| JPH11229631A (ja) | 既存建物外殻の制震補強方法 | |
| JP2008025113A (ja) | 制震構造 | |
| JP4010981B2 (ja) | 既存建物の上部増築工法 | |
| JP5946165B2 (ja) | 耐震補強構造 | |
| JP6833292B2 (ja) | 屋根耐震構造 | |
| JP2007077698A (ja) | 免震・制震機能を有する構造物 | |
| JP2000145162A (ja) | 耐震補強構造 | |
| JP2012233374A5 (ja) | ||
| JP5060842B2 (ja) | 制振構造物 | |
| JP5503200B2 (ja) | ユニット建物 | |
| JP2008297727A (ja) | 既存建物の耐震補強構造 | |
| JP4825087B2 (ja) | 既存建物の耐震補強構造 | |
| JP6275314B1 (ja) | 橋梁の耐震補強構造 | |
| JPH11229632A (ja) | 既存建物外殻の制震補強方法 | |
| JP3925868B2 (ja) | 制震補強架構及びそれを用いた制震構造物 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070111 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Effective date: 20070807 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Effective date: 20080115 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080306 |
|
| A911 | Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |
Effective date: 20080321 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 |
|
| A912 | Removal of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |
Effective date: 20080620 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 |