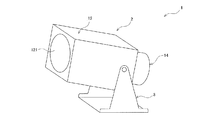JP6631798B2 - 投光装置 - Google Patents
投光装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6631798B2 JP6631798B2 JP2016130719A JP2016130719A JP6631798B2 JP 6631798 B2 JP6631798 B2 JP 6631798B2 JP 2016130719 A JP2016130719 A JP 2016130719A JP 2016130719 A JP2016130719 A JP 2016130719A JP 6631798 B2 JP6631798 B2 JP 6631798B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- optical system
- incident
- fluorescent element
- lens
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 145
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 5
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 4
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 4
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Microscoopes, Condenser (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Semiconductor Lasers (AREA)
Description
Claims (4)
- レーザ光を出射する発光素子と、
前記発光素子から出射された光が入射され、該光の少なくとも一部を蛍光に変換して出力する蛍光素子と、
前記蛍光素子から出力された光が入射される第1光学系と、
前記第1光学系から出射された光が入射され、該光を平行光にして装置の外部に向けて出射する第2光学系と、を備え、
前記第1光学系は、前記蛍光素子から出力された光が最初に入射されるレンズを含み、
前記第2光学系に入射される光の発散角は、前記第1光学系に入射される光の発散角よりも大きい、投光装置。 - 前記第1光学系は、入射された光を集束光にして出射する集光光学系であり、
前記第2光学系は、前記第1光学系から出射された光が入射される際に発散光となるように、前記第1光学系から離間して配置される、請求項1に記載の投光装置。 - 前記蛍光素子から出力された光のうち、前記第1光学系を通過することなく前記第2光学系に向かう光を遮蔽すべく、該光を遮蔽する遮光体を、さらに備え、
前記遮光体は、前記第1光学系から出射された光が前記第2光学系に入射するために通過するための光路部を備える、請求項2に記載の投光装置。 - 前記光路部は、前記第1光学系の焦点の位置に配置され、
前記光路部の領域は、前記蛍光素子の光出力領域よりも、大きい、請求項3に記載の投光装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016130719A JP6631798B2 (ja) | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 投光装置 |
| US16/312,442 US10760766B2 (en) | 2016-06-30 | 2017-06-05 | Floodlight device with two optical systems that condense and collimate laser light |
| PCT/JP2017/020766 WO2018003409A1 (ja) | 2016-06-30 | 2017-06-05 | 投光装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016130719A JP6631798B2 (ja) | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 投光装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2018006133A JP2018006133A (ja) | 2018-01-11 |
| JP2018006133A5 JP2018006133A5 (ja) | 2019-12-05 |
| JP6631798B2 true JP6631798B2 (ja) | 2020-01-15 |
Family
ID=60948014
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2016130719A Active JP6631798B2 (ja) | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 投光装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6631798B2 (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019161127A (ja) * | 2018-03-15 | 2019-09-19 | 豊田合成株式会社 | 発光装置 |
| WO2019209090A1 (ko) * | 2018-04-27 | 2019-10-31 | 주식회사 인포웍스 | 코히런트 방식을 이용한 fmcw 라이다 시스템 |
| JP2021128273A (ja) | 2020-02-14 | 2021-09-02 | キヤノン株式会社 | 光源装置、およびこれを備える画像投写装置 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010080364A (ja) * | 2008-09-29 | 2010-04-08 | Stanley Electric Co Ltd | 照明装置 |
| JP6424336B2 (ja) * | 2013-07-04 | 2018-11-21 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 投光装置 |
| JP2015210890A (ja) * | 2014-04-24 | 2015-11-24 | シャープ株式会社 | 光源装置および車両 |
| EP3514447B1 (de) * | 2018-01-17 | 2023-12-27 | ZKW Group GmbH | Kraftfahrzeugscheinwerfer |
-
2016
- 2016-06-30 JP JP2016130719A patent/JP6631798B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2018006133A (ja) | 2018-01-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6342279B2 (ja) | 発光装置 | |
| US20170016586A1 (en) | Light source module and vehicle lamp | |
| KR101825537B1 (ko) | 발광 장치 및 프로젝션 시스템 | |
| JP6111805B2 (ja) | 車両用灯具 | |
| JP6539665B2 (ja) | スポーツ照明器具 | |
| JP6621631B2 (ja) | 光源モジュール | |
| JP6631798B2 (ja) | 投光装置 | |
| JP2012013459A5 (ja) | ||
| JP5891858B2 (ja) | 発光装置及び車両用灯具 | |
| WO2018003409A1 (ja) | 投光装置 | |
| JP6765238B2 (ja) | 光学装置及び照明装置 | |
| KR101830045B1 (ko) | 조명 장치 | |
| JP5883114B2 (ja) | 発光装置、車両用前照灯および照明装置 | |
| JP2018006136A (ja) | 投光装置 | |
| JP6248573B2 (ja) | 導光用光学素子、及び光源装置 | |
| JP2017069110A (ja) | 照明装置 | |
| JPWO2015174312A1 (ja) | 光源モジュールおよび車両用灯具 | |
| JP2019186139A (ja) | 照明装置 | |
| JP2019169251A (ja) | 照明装置、及びレーザダイオード | |
| KR101515370B1 (ko) | 협각 빔 조사를 위한 멀티칩 엘이디 광학시스템 | |
| JP5539768B2 (ja) | 照明装置 | |
| JP6560582B2 (ja) | ルーバー、及び投光器 | |
| JP2018085167A (ja) | 光源装置 | |
| JP6204140B2 (ja) | 照明装置 | |
| KR101800634B1 (ko) | 청색 레이저다이오드와 형광체를 이용한 산업용 조명장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190312 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191023 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191113 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191126 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6631798 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |