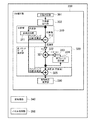JP6478774B2 - 撮像装置、撮像方法及びプログラム - Google Patents
撮像装置、撮像方法及びプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP6478774B2 JP6478774B2 JP2015079394A JP2015079394A JP6478774B2 JP 6478774 B2 JP6478774 B2 JP 6478774B2 JP 2015079394 A JP2015079394 A JP 2015079394A JP 2015079394 A JP2015079394 A JP 2015079394A JP 6478774 B2 JP6478774 B2 JP 6478774B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- frames
- frequency component
- data
- component
- offset
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims description 120
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 63
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 28
- 238000009795 derivation Methods 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 description 30
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 18
- 230000008569 process Effects 0.000 description 17
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 8
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 6
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002591 computed tomography Methods 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 229910021417 amorphous silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M caesium iodide Chemical compound [I-].[Cs+] XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
Description
OBrec(N)=αOBnew+(1−α)OBrec(N−1) …(式1)
ここで、分割部310により得られた、対象フレームの高周波成分をOBnew、前フレームの高周波成分をOBrec(N−1)、更新により得られた対象フレームの高周波成分をOBrec(N)とする。αは、再帰係数である。再帰係数は任意の値であり、再帰係数を変化させることにより、前フレームの情報の重み付け量を調整することができる。ここで、αは、対象フレームの高周波成分の利用比率の一例である。(式1)により得られた高周波成分は、次のフレームの処理において、OBrec(N−1)の値として使用すべく、前フレーム保存部324に記録される。
OBlow(N)=βOBlow_new+(1−β)OBlow(N−1)
…(式2)
ここで、分割部310により得られた低周波成分をOBlow_new、前フレームの低周波成分をOBlow(N−1)、更新により得られた高周波成分をOBlow(N)とする。また、βは、再帰係数である。再帰係数は任意の値であり、再帰係数を変化させることにより、前フレームの情報の重み付け量を調整することができる。ここで、βは、対象フレームの低周波成分の利用比率の一例である。
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そして、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
110 撮像装置
111 パネル
112 画像処理装置
300 OB補正部
310 分割部
320 オフセットデータ生成部
Claims (10)
- 行方向と列方向に複数の有効画素が配置された第1の領域と、該有効画素の領域の行又は列に共通のオフセット成分を補正するために利用される画素が配置された第2の領域と、を含む複数の領域から複数のフレームの画像を取得するための撮像装置であって、
取得されたフレームの前記画素から得られたデータを空間的な高周波成分と低周波成分とに分割する分割手段と、
第1の数のフレームの前記低周波成分と、前記第1の数に比べて多い第2の数のフレームの前記高周波成分と、に基づいて、前記有効画素の行又は列に共通のオフセット成分を補正するためのデータを生成する生成手段と
を有することを特徴とする撮像装置。 - 前記生成手段は、前記第1の数のフレームの前記低周波成分に基づいて、前記オフセット成分を補正するためのデータの低周波成分を生成し、前記第1の数に比べて多い第2の数のフレームの前記高周波成分に基づいて、前記オフセット成分を補正するためのデータの高周波成分を生成し、前記オフセット成分を補正するためのデータの前記高周波成分と前記低周波成分とを加算することにより、前記オフセット成分を補正するためのデータを生成することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 前記生成手段は、補正対象の対象フレーム及び前記対象フレームよりも前に得られた前フレームそれぞれの前記高周波成分と、前記対象フレームの前記低周波成分と、に基づいて前記オフセット成分を補正するためのデータを生成することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像装置。
- 行方向と列方向に複数の有効画素が配置された第1の領域と、該有効画素の領域の行又は列に共通のオフセット成分を補正するために利用される画素が配置された第2の領域と、を含む複数の領域から複数のフレームの画像を取得するための撮像装置であって、
取得されたフレームの前記画素から得られたデータを空間的な高周波成分と低周波成分とに分割する分割手段と、
複数のフレームの前記低周波成分に対する、補正対象の対象フレームの低周波成分の利用比率を第1の利用比率として、前記対象フレームを含む前記複数のフレームの前記低周波成分に基づいて、前記有効画素の行又は列に共通のオフセット成分を補正するためのデータの低周波成分を生成する第1の生成手段と、
前記複数のフレームの前記高周波成分に対する、補正対象の対象フレームの高周波成分の利用比率を、前記第1の利用比率に比べて低い第2の利用比率として、前記複数のフレームの前記高周波成分に基づいて、前記オフセット成分を補正するためのデータの高周波成分を生成する第2の生成手段と、
前記オフセット成分を補正するためのデータの前記高周波成分と前記低周波成分とを加算することにより、前記オフセット成分を補正するためのデータを生成する第3の生成手段と
を有することを特徴とする撮像装置。 - 前記撮像装置の受光量の変化量に基づいて、前記第1の利用比率を決定する決定手段をさらに有することを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。
- 各列の前記画素から得られたデータの代表値の近似曲線を求める曲線導出手段をさらに有し、
前記分割手段は、前記近似曲線に基づいて、前記画素から得られたデータを、前記高周波成分と前記低周波成分に分割することを特徴とする請求項1乃至5何れか1項に記載の撮像装置。 - 前記分割手段は、空間的帯域通過フィルタを有することを特徴とする請求項1乃至5何れか1項に記載の撮像装置。
- 行方向と列方向に複数の有効画素が配置された第1の領域と、該有効画素の領域の行又は列に共通のオフセット成分を補正するために利用される画素が配置された第2の領域と、を含む複数の領域から複数のフレームの画像を取得するための撮像装置が実行する撮像方法であって、
取得されたフレームの前記画素から得られたデータを空間的な高周波成分と低周波成分とに分割する分割ステップと、
第1の数のフレームの前記低周波成分と、前記第1の数に比べて多い第2の数のフレームの前記高周波成分と、に基づいて、前記有効画素の行又は列に共通のオフセット成分を補正するためのデータを生成するオフセットデータ生成ステップと
を含むことを特徴とする撮像方法。 - 行方向と列方向に複数の有効画素が配置された第1の領域と、該有効画素の領域の行又は列に共通のオフセット成分を補正するために利用される画素が配置された第2の領域と、を含む複数の領域から複数のフレームの画像を取得するための撮像装置が実行する撮像方法であって、
取得されたフレームの前記画素から得られたデータを空間的な高周波成分と低周波成分とに分割する分割ステップと、
複数のフレームの前記低周波成分に対する、補正対象の対象フレームの低周波成分の利用比率を第1の利用比率として、前記対象フレームを含む前記複数のフレームの前記低周波成分に基づいて、前記有効画素の行又は列に共通のオフセット成分を補正するためのデータの低周波成分を生成する第1の生成ステップと、
前記複数のフレームの前記高周波成分に対する、補正対象の対象フレームの高周波成分の利用比率を、前記第1の利用比率に比べて低い第2の利用比率として、前記複数のフレームの前記高周波成分に基づいて、前記オフセット成分を補正するためのデータの高周波成分を生成する第2の生成ステップと、
前記オフセット成分を補正するためのデータの前記高周波成分と前記低周波成分とを加算することにより、前記オフセット成分を補正するためのデータを生成する第3の生成ステップと
を含むことを特徴とする撮像方法。 - 請求項8又は9に記載の撮像方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015079394A JP6478774B2 (ja) | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 撮像装置、撮像方法及びプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015079394A JP6478774B2 (ja) | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 撮像装置、撮像方法及びプログラム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2016201634A JP2016201634A (ja) | 2016-12-01 |
| JP2016201634A5 JP2016201634A5 (ja) | 2018-04-26 |
| JP6478774B2 true JP6478774B2 (ja) | 2019-03-06 |
Family
ID=57424587
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2015079394A Active JP6478774B2 (ja) | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 撮像装置、撮像方法及びプログラム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6478774B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111633651B (zh) * | 2020-05-28 | 2021-01-29 | 杭州键嘉机器人有限公司 | 一种中空管状工具的tcp标定方法 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7313800B2 (ja) * | 2018-05-11 | 2023-07-25 | キヤノン株式会社 | 放射線撮影装置、放射線撮影装置の制御装置及び制御方法、並びに、プログラム |
| JP7118798B2 (ja) * | 2018-08-06 | 2022-08-16 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | X線コンピュータ断層撮影装置 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5129650B2 (ja) * | 2008-05-23 | 2013-01-30 | キヤノン株式会社 | 撮像装置 |
| JP2010166479A (ja) * | 2009-01-19 | 2010-07-29 | Fujifilm Corp | 撮像装置及び撮像画像の補正方法 |
-
2015
- 2015-04-08 JP JP2015079394A patent/JP6478774B2/ja active Active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111633651B (zh) * | 2020-05-28 | 2021-01-29 | 杭州键嘉机器人有限公司 | 一种中空管状工具的tcp标定方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2016201634A (ja) | 2016-12-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5374217B2 (ja) | 画像処理装置およびその方法 | |
| KR101367747B1 (ko) | 방사선 촬영장치 및 그 제어 방법 | |
| US9014461B2 (en) | Image processing apparatus, image processing method and storage medium | |
| US8710447B2 (en) | Control device for radiation imaging apparatus and control method therefor | |
| JP2003190126A (ja) | X線画像処理装置 | |
| JPH02237277A (ja) | X線診断装置 | |
| JP6491545B2 (ja) | 画像処理装置、放射線撮影装置、画像処理方法、プログラム、および記憶媒体 | |
| US20150243027A1 (en) | Image processing device, image processing method, and program | |
| JP6478774B2 (ja) | 撮像装置、撮像方法及びプログラム | |
| JP6383186B2 (ja) | 画像処理装置および画像処理方法、画像処理システム | |
| JP3880117B2 (ja) | 画像読取方法及び装置 | |
| JP6202855B2 (ja) | 画像処理装置、画像処理装置の制御方法、及びプログラム | |
| CN109709597B (zh) | 平板探测器的增益校正方法 | |
| US9369639B2 (en) | Image processing apparatus, image processing method and storage medium | |
| JP7368948B2 (ja) | 画像処理装置、放射線撮影装置および画像処理方法 | |
| JP5547548B2 (ja) | 電子増倍率の測定方法 | |
| US20130322596A1 (en) | Image capturing apparatus, image capturing system, method of controlling image capturing apparatus, and storage medium | |
| JP6305080B2 (ja) | 情報処理装置、放射線撮影システム、情報処理方法、及びプログラム | |
| JP6976699B2 (ja) | X線診断装置 | |
| WO2015059886A1 (ja) | 放射線撮影装置およびその制御方法、放射線画像処理装置および方法、並びに、プログラムおよびコンピュータ可読記憶媒体 | |
| JP2017028583A (ja) | 画像処理装置、撮像装置、画像処理方法、画像処理プログラム、および、記憶媒体 | |
| JP7313800B2 (ja) | 放射線撮影装置、放射線撮影装置の制御装置及び制御方法、並びに、プログラム | |
| JP5631153B2 (ja) | 画像処理装置、制御方法、及びプログラム | |
| JP3279083B2 (ja) | X線撮影装置 | |
| JP2022191914A (ja) | 放射線撮影システム、画像処理装置、画像処理方法及びプログラム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180314 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180314 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20181221 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190108 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190205 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6478774 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |