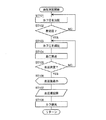JP5944727B2 - 血圧計およびポンプ駆動システム - Google Patents
血圧計およびポンプ駆動システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP5944727B2 JP5944727B2 JP2012095287A JP2012095287A JP5944727B2 JP 5944727 B2 JP5944727 B2 JP 5944727B2 JP 2012095287 A JP2012095287 A JP 2012095287A JP 2012095287 A JP2012095287 A JP 2012095287A JP 5944727 B2 JP5944727 B2 JP 5944727B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- voltage
- pump
- switching elements
- control
- series circuit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B45/00—Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids
- F04B45/04—Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having plate-like flexible members, e.g. diaphragms
- F04B45/047—Pumps having electric drive
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/02141—Details of apparatus construction, e.g. pump units or housings therefor, cuff pressurising systems, arrangements of fluid conduits or circuits
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/02225—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers using the oscillometric method
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0225—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0225—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
- A61B5/02255—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds the pressure being controlled by plethysmographic signals, e.g. derived from optical sensors
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/024—Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physiology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
Description
血圧測定用カフへ流体を送るポンプと、
上記ポンプを駆動するためのポンプ駆動回路と、
血圧測定のために上記ポンプ駆動回路を制御する制御部とを少なくとも備え、
上記ポンプ駆動回路は、
電源からの第1のDC電圧を昇圧して第2のDC電圧として出力する昇圧部と、
上記第2のDC電圧に対応する高電位とこの高電位よりも低い基準電位との間に、直列に接続された2個のスイッチング素子をそれぞれ含む第1、第2の直列回路を有するHブリッジ部とを備え、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、それぞれオン、オフ制御され、
上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第1の接続点と、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第2の接続点との間に生じる電圧が、上記ポンプを駆動するための駆動電圧として用いられることを特徴とする。
上記制御部からの昇圧制御信号はPWM信号であり、
上記昇圧部としての昇圧レギュレータは、上記PWM信号のパルス幅に応じて、上記第2のDC電圧を可変して出力することを特徴とする。
上記ポンプは圧電ポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子は相補的にオン、オフ制御されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相で相補的にオン、オフ制御されることを特徴とする。
上記ポンプはロータリポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のうち上記高電位側のスイッチング素子はオン、オフ制御され、上記基準電位側のスイッチング素子はオフ状態に維持されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子のうち上記高電位側のスイッチング素子はオフ状態に維持され、上記基準電位側のスイッチング素子は上記第1の直列回路の上記高電位側のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相でオン、オフ制御されることを特徴とする。
ポンプと、
上記ポンプを駆動するためのポンプ駆動回路と、
上記ポンプ駆動回路を制御する制御部とを少なくとも備え、
上記ポンプ駆動回路は、
電源からの第1のDC電圧を昇圧して第2のDC電圧として出力する昇圧部と、
上記第2のDC電圧に対応する高電位とこの高電位よりも低い基準電位との間に、直列に接続された2個のスイッチング素子をそれぞれ含む第1、第2の直列回路を有するHブリッジ部とを備え、
上記制御部からの昇圧制御信号はPWM信号であり、上記昇圧部は、抵抗とFETとを有する上記PWM信号のパルス幅に応じて抵抗値を可変させる第1の抵抗部と、第2の抵抗部とを備え、上記第2のDC電圧を、上記第1の抵抗部と上記第2の抵抗部とで分圧して帰還させることで、上記第2のDC電圧の可変出力が可能な昇圧レギュレータであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1、第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子はオン、オフ制御され、
上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第1の接続点と、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第2の接続点との間に生じる電圧が、上記ポンプを駆動するための駆動電圧として用いられることを特徴とする。
上記ポンプは圧電ポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子は相補的にオン、オフ制御されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相で相補的にオン、オフ制御されることを特徴とする。
20 血圧測定用カフ
62 昇圧レギュレータ
63 Hブリッジ回路
100 CPU
320 ポンプ駆動回路
Claims (11)
- 血圧測定用カフへ流体を送るポンプと、
上記ポンプを駆動するためのポンプ駆動回路と、
血圧測定のために上記ポンプ駆動回路を制御する制御部とを少なくとも備え、
上記ポンプ駆動回路は、
電源からの第1のDC電圧を昇圧して第2のDC電圧として出力する昇圧部と、
上記第2のDC電圧に対応する高電位とこの高電位よりも低い基準電位との間に、直列に接続された2個のスイッチング素子をそれぞれ含む第1、第2の直列回路を有するHブリッジ部とを備え、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、それぞれオン、オフ制御され、
上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第1の接続点と、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第2の接続点との間に生じる電圧が、上記ポンプを駆動するための駆動電圧として用いられることを特徴とする血圧計。 - 請求項1に記載の血圧計において、
上記昇圧部は、上記制御部からの昇圧制御信号に応じて、上記第2のDC電圧を可変して出力する昇圧レギュレータであることを特徴とする血圧計。 - 請求項2に記載の血圧計において、
上記制御部からの昇圧制御信号はPWM信号であり、
上記昇圧部としての昇圧レギュレータは、上記PWM信号のパルス幅に応じて、上記第2のDC電圧を可変して出力することを特徴とする血圧計。 - 請求項1から3までのいずれか一つに記載の血圧計において、
上記ポンプは圧電ポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子は相補的にオン、オフ制御されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相で相補的にオン、オフ制御されることを特徴とする血圧計。 - 請求項4に記載の血圧計において、
上記制御部は、上記第1、第2の直列回路の或るスイッチング素子のオン期間とこのオン期間に続く別のスイッチング素子のオン期間との間に、いずれのスイッチング素子もオフしている休止期間を設定する制御を行うことを特徴とする血圧計。 - 請求項4または5に記載の血圧計において、
上記制御部は、上記第1、第2の直列回路の各スイッチング素子を、オフ状態からオン状態へ、またオン状態からオフ状態へ、それぞれ有限の遷移期間をかけて遷移させる制御を行うことを特徴とする血圧計。 - 請求項1に記載の血圧計において、
上記ポンプはロータリポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のうち上記高電位側のスイッチング素子はオン、オフ制御され、上記基準電位側のスイッチング素子はオフ状態に維持されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子のうち上記高電位側のスイッチング素子はオフ状態に維持され、上記基準電位側のスイッチング素子は上記第1の直列回路の上記高電位側のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相でオン、オフ制御されることを特徴とする血圧計。 - ポンプと、
上記ポンプを駆動するためのポンプ駆動回路と、
上記ポンプ駆動回路を制御する制御部とを少なくとも備え、
上記ポンプ駆動回路は、
電源からの第1のDC電圧を昇圧して第2のDC電圧として出力する昇圧部と、
上記第2のDC電圧に対応する高電位とこの高電位よりも低い基準電位との間に、直列に接続された2個のスイッチング素子をそれぞれ含む第1、第2の直列回路を有するHブリッジ部とを備え、
上記制御部からの昇圧制御信号はPWM信号であり、上記昇圧部は、抵抗とFETとを有する上記PWM信号のパルス幅に応じて抵抗値を可変させる第1の抵抗部と、第2の抵抗部とを備え、上記第2のDC電圧を、上記第1の抵抗部と上記第2の抵抗部とで分圧して帰還させることで、上記第2のDC電圧の可変出力が可能な昇圧レギュレータであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1、第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子はオン、オフ制御され、
上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第1の接続点と、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子の間の第2の接続点との間に生じる電圧が、上記ポンプを駆動するための駆動電圧として用いられることを特徴とするポンプ駆動システム。 - 請求項8に記載のポンプ駆動システムにおいて、
上記ポンプは圧電ポンプであり、
上記制御部からのブリッジ制御信号によって、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子は相補的にオン、オフ制御されるとともに、上記第2の直列回路の上記2個のスイッチング素子は、上記第1の直列回路の上記2個のスイッチング素子のオン、オフ制御とは逆の位相で相補的にオン、オフ制御されることを特徴とするポンプ駆動システム。 - 請求項9に記載のポンプ駆動システムにおいて、
上記制御部は、上記第1、第2の直列回路の或るスイッチング素子のオン期間とこのオン期間に続く別のスイッチング素子のオン期間との間に、いずれのスイッチング素子もオフしている休止期間を設定する制御を行うことを特徴とするポンプ駆動システム。 - 請求項9または10に記載のポンプ駆動システムにおいて、
上記制御部は、上記第1、第2の直列回路の各スイッチング素子を、オフ状態からオン状態へ、またオン状態からオフ状態へ、それぞれ有限の遷移期間をかけて遷移させる制御を行うことを特徴とするポンプ駆動システム。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012095287A JP5944727B2 (ja) | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 血圧計およびポンプ駆動システム |
| PCT/JP2013/060231 WO2013157394A1 (ja) | 2012-04-19 | 2013-04-03 | 血圧計およびポンプ駆動システム |
| CN201380020501.XA CN104254276B (zh) | 2012-04-19 | 2013-04-03 | 血压计以及泵驱动系统 |
| DE112013002130.7T DE112013002130T5 (de) | 2012-04-19 | 2013-04-03 | Blutdruckmesser und Pumpenantriebssystem |
| US14/516,777 US9775526B2 (en) | 2012-04-19 | 2014-10-17 | Blood pressure meter and pump driving system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012095287A JP5944727B2 (ja) | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 血圧計およびポンプ駆動システム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2013220288A JP2013220288A (ja) | 2013-10-28 |
| JP2013220288A5 JP2013220288A5 (ja) | 2015-06-11 |
| JP5944727B2 true JP5944727B2 (ja) | 2016-07-05 |
Family
ID=49383359
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012095287A Active JP5944727B2 (ja) | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 血圧計およびポンプ駆動システム |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9775526B2 (ja) |
| JP (1) | JP5944727B2 (ja) |
| CN (1) | CN104254276B (ja) |
| DE (1) | DE112013002130T5 (ja) |
| WO (1) | WO2013157394A1 (ja) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWI670046B (zh) * | 2016-03-29 | 2019-09-01 | 豪展醫療科技股份有限公司 | 兼具情緒壓力指數檢測與血壓檢測之量測裝置與方法 |
| JP6673505B2 (ja) * | 2017-01-20 | 2020-03-25 | 株式会社村田製作所 | 流体制御装置および血圧計 |
| WO2018168379A1 (ja) * | 2017-03-16 | 2018-09-20 | 株式会社村田製作所 | 流体制御装置および血圧計 |
| CN107536605B (zh) * | 2017-09-05 | 2020-05-05 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 一种pwm电路占空比调节方法、控制器和血压测量装置 |
| CN107748589A (zh) * | 2017-10-18 | 2018-03-02 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种输出电压可调电路及其电压调整方法和显示装置 |
| JP7055659B2 (ja) * | 2018-02-15 | 2022-04-18 | 東芝テック株式会社 | 液体循環装置、及び液体吐出装置 |
| GB2583226B (en) * | 2018-02-16 | 2022-11-16 | Murata Manufacturing Co | Fluid control apparatus |
| TWI720876B (zh) * | 2020-04-24 | 2021-03-01 | 研能科技股份有限公司 | 驅動壓電式泵浦的驅動電路系統 |
| CN113143234B (zh) * | 2021-04-13 | 2023-04-14 | 研和智能科技(杭州)有限公司 | 一种血压测量装置和控制方法 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2770295B2 (ja) * | 1989-12-05 | 1998-06-25 | 株式会社産機 | 振動式搬送装置 |
| JP3622539B2 (ja) | 1998-12-04 | 2005-02-23 | 松下電工株式会社 | 圧電ダイアフラムポンプを用いた血圧測定装置 |
| JP3595808B2 (ja) | 2002-07-11 | 2004-12-02 | コニカミノルタホールディングス株式会社 | 電圧発生回路及び該回路を備えた駆動装置 |
| US7862514B2 (en) * | 2006-02-06 | 2011-01-04 | Welch Allyn, Inc. | Blood pressure measurement |
| JP2007259911A (ja) * | 2006-03-27 | 2007-10-11 | Omron Healthcare Co Ltd | 血圧測定装置 |
| JP5151310B2 (ja) | 2007-08-15 | 2013-02-27 | ソニー株式会社 | 圧電素子の駆動回路およびポンプ装置 |
| JP5596567B2 (ja) | 2008-02-28 | 2014-09-24 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | 圧電セラミックダイアフラム装置を使用する自動化された非磁性医用モニタ |
| JP2009240151A (ja) * | 2008-03-07 | 2009-10-15 | Seiko Epson Corp | 駆動信号供給制御用半導体装置 |
| JP5028400B2 (ja) * | 2008-12-22 | 2012-09-19 | 三洋電機株式会社 | 電圧出力ドライバーおよび圧電ポンプ |
| JP2010142783A (ja) | 2008-12-22 | 2010-07-01 | Sanyo Electric Co Ltd | 電圧出力ドライバー |
| JP5740879B2 (ja) * | 2009-09-18 | 2015-07-01 | 株式会社村田製作所 | 圧電アクチュエーター駆動回路 |
| US8371829B2 (en) * | 2010-02-03 | 2013-02-12 | Kci Licensing, Inc. | Fluid disc pump with square-wave driver |
| JP2012029793A (ja) * | 2010-07-29 | 2012-02-16 | Omron Healthcare Co Ltd | 電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計 |
-
2012
- 2012-04-19 JP JP2012095287A patent/JP5944727B2/ja active Active
-
2013
- 2013-04-03 CN CN201380020501.XA patent/CN104254276B/zh active Active
- 2013-04-03 WO PCT/JP2013/060231 patent/WO2013157394A1/ja active Application Filing
- 2013-04-03 DE DE112013002130.7T patent/DE112013002130T5/de active Pending
-
2014
- 2014-10-17 US US14/516,777 patent/US9775526B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20150038858A1 (en) | 2015-02-05 |
| DE112013002130T5 (de) | 2015-01-29 |
| CN104254276A (zh) | 2014-12-31 |
| CN104254276B (zh) | 2016-06-08 |
| WO2013157394A1 (ja) | 2013-10-24 |
| US9775526B2 (en) | 2017-10-03 |
| JP2013220288A (ja) | 2013-10-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5944727B2 (ja) | 血圧計およびポンプ駆動システム | |
| JP5884496B2 (ja) | 血圧測定装置、および、血圧測定装置の制御方法 | |
| JP5998486B2 (ja) | 血圧測定装置、および、血圧測定装置の制御方法 | |
| CA2739852C (en) | A method and apparatus for supplying energy to a medical device | |
| US20090168475A1 (en) | Converter power supply circuit and converter power supply driving method | |
| KR102012743B1 (ko) | 전원 공급 장치 및 부하에 전원을 공급하는 방법 | |
| GB2577710A (en) | Methods and devices for driving a piezoelectric pump | |
| WO2013157399A1 (ja) | 血圧測定装置、血圧測定装置における制御装置、および、血圧測定装置の制御方法 | |
| WO2018142975A1 (ja) | 流体制御装置および血圧計 | |
| US11773835B2 (en) | Fluid control device and sphygmomanometer | |
| TW201223095A (en) | Switching power converter | |
| TW201526497A (zh) | 正負電壓產生電路、液晶顯示模組驅動系統及網路電話機 | |
| JP2014014556A (ja) | 電子血圧計および血圧測定方法 | |
| JP6908137B2 (ja) | 駆動装置、および、流体制御装置 | |
| JP5212494B2 (ja) | 複数電圧出力型電源装置 | |
| JP2010011606A (ja) | 圧電トランスを用いた電源回路 | |
| JP2013252188A (ja) | 血圧計および駆動装置 | |
| JP5771769B2 (ja) | 点灯装置、照明器具、照明システム | |
| JP2000300662A (ja) | 電動式低圧持続吸引器 | |
| JP2017115792A (ja) | 圧電ポンプ駆動装置及びそれを備えた血圧計 | |
| JP2013220320A (ja) | 圧電ポンプ制御装置、圧電ポンプ制御方法、圧電ポンプ制御プログラム、および、血圧測定装置 | |
| JP2015015983A (ja) | 経絡測定装置 | |
| CN110213990A (zh) | 流体控制装置以及血压计 | |
| AU2017201947B2 (en) | A method and apparatus for supplying energy to a medical device | |
| JP5046518B2 (ja) | 圧電素子の駆動回路 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150408 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150408 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160510 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160526 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5944727 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |