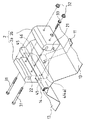JP3633918B2 - 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 - Google Patents
二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 Download PDFInfo
- Publication number
- JP3633918B2 JP3633918B2 JP2002317875A JP2002317875A JP3633918B2 JP 3633918 B2 JP3633918 B2 JP 3633918B2 JP 2002317875 A JP2002317875 A JP 2002317875A JP 2002317875 A JP2002317875 A JP 2002317875A JP 3633918 B2 JP3633918 B2 JP 3633918B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- saddle
- lower side
- folded
- roof
- roofing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000000725 suspension Substances 0.000 title claims description 27
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 26
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 claims description 24
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims description 3
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04D—ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
- E04D13/00—Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
- E04D13/16—Insulating devices or arrangements in so far as the roof covering is concerned, e.g. characterised by the material or composition of the roof insulating material or its integration in the roof structure
- E04D13/1606—Insulation of the roof covering characterised by its integration in the roof structure
- E04D13/1643—Insulation of the roof covering characterised by its integration in the roof structure the roof structure being formed by load bearing corrugated sheets, e.g. profiled sheet metal roofs
- E04D13/165—Double skin roofs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属製の折板屋根を用いた屋根葺き構造に関し、さらに詳しくは、下葺き折板屋根の上に上葺き折板屋根を葺設して形成される、いわゆる二重葺き折板屋根の屋根葺き構造に関する。
【0002】
【従来の技術】
金属製の折板屋根材をはぜ継ぎして葺設される折板屋根において、特に高い断熱・防音効果を得るため、折板屋根材を二重葺きし、下葺き屋根と上葺き屋根との間にグラスウール等の断熱防音材を配置するという屋根葺き構造が採用されている(例えば、特許文献1及び2参照。)。かかる二重葺き折板屋根の基本的な屋根葺き構造を図3〜図4に示す。
【0003】
この屋根葺き構造は、タイトフレーム11の頂部に取り付けた下葺き側の吊子12を介して、まず下葺き側の屋根材13,13をはぜ継ぎし、この下葺き側はぜ継ぎ部14に図示のようなサドル2を適宜間隔で取り付け、下葺き側の屋根材13の表面に断熱防音材15を敷設した後、サドル2の上部に挟み込んだ上葺き側の吊子16を介して、上葺き側の屋根材17,17をはぜ継ぎする、というものである。
【0004】
サドル2は、合成樹脂等により形成された左右一対のブロック2a,2bからなる部材で、これら両ブロック2a,2bの分割面を挟む同位置にボルト貫通孔が形成され、このボルト貫通孔に締結ボルト31を挿通してナット32を螺着することにより連結される。
【0005】
サドル2の分割面の下部には断面略T字状をなす下側溝部21が形成され、この下側溝部21に下葺き側はぜ継ぎ部14が挟持されて、側方から打込まれるタッピングビス(セルフタッピングスクリュー)33により、サドル2と下葺き側はぜ継ぎ部14とが固定される。
【0006】
そして、特許文献1記載の屋根葺き構造においては、図示のように、サドル2の分割面の上部に断面逆T字状をなす上側溝部22が形成され、この上側溝部22に上葺き側の吊子16が挟み込まれて、溝方向に摺動しうるように保持される。
【0007】
また、特許文献2記載の屋根葺き構造においては、サドル2の分割面の上部に縦長の上側溝部が形成され、この上側溝部に上葺き側の吊子が挟み込まれて、サドル2を貫通する吊子固定ボルトにより保持される。
【0008】
【特許文献1】
特開平9−328869号公報 (図1−図3)
【特許文献2】
特開2001−132172号公報 (図1−図4)
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
前記のような二重葺き折板屋根においては、屋根全体の強度を確保するために、下葺き側はぜ継ぎ部14とサドル2とをタッピングビス33で固定する必要があるが、この固定作業に際して以下2点の問題がある。
【0010】
第1は、下葺き側屋根材13,13がはぜ継ぎされると、下葺き側の吊子12が下葺き側はぜ継ぎ部14に隠れて見えなくなってしまうので、サドル2の位置決めが困難になるという点である。下葺き屋根の上に適宜間隔で配置される多数のサドル2のうち少なくとも半分程度は、屋根強度の安定のため、下葺き側の吊子12の直上に配置して吊子12と一体に固定するのが望ましい。しかしながら、サドル2の配置に際して下葺き側の吊子12が見えないことにより、吊子12の位置を確認する作業に手間がかかって施工性が低下することになる。
【0011】
第2は、下葺き側はぜ継ぎ部14にタッピングビス33を打込む作業が容易ではないという点である。下葺き側はぜ継ぎ部14におけるタッピングビス33の貫通部分は、吊子12と2枚の屋根材13を重ね合わせた厚みがあるが、下葺き側の吊子12が例えばステンレス鋼のような硬質材料で形成されていると、下穴なしでタッピングビス33を貫通させるのは困難である。そのため、タッピングビス33を打込む前に、ハンドドリル等を用いて下葺き側はぜ継ぎ部14に下穴を開ける作業が必要となり、この点でも施工性の改善が望まれている。
【0012】
本発明は前記のような事情に鑑みてなされたもので、下葺き側はぜ継ぎ部に用いられる下葺き側の吊子を改良することにより、サドルの位置決めとタッピングビスの打込みを容易に行うことができる二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を提供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため、本発明の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造は、下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺き側はぜ継ぎ部に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方からタッピングビスを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込んだ上葺き側の吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造において、下葺き側の吊子には、下葺き側の屋根材に挟み込まれる部分の側面または上面に2箇所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、下葺き側の吊子におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴とする。
【0014】
また、本発明の吊子は、前記のような二重葺き折板屋根の屋根葺き構造に用いられる下葺き側の吊子であって、屋根の構造体に固定される基部と、基部から立ち上がる首部と、首部の上端に形成されたはぜ受部とを備え、前記首部の側面またははぜ受け部の上面に2箇所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、前記首部におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴とする。
【0015】
これらの発明によれば、下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎしたときに、吊子に形成された位置決め用突起によって下葺き側はぜ締め部の側面または上面に小さな膨らみが生じるので、これを手掛かりにして吊子の位置を容易に確認することができる。位置決め用突起は、サドルの長さに相当する距離を隔てて2箇所に形成されているので、これらの突起の間にサドルを当てがうことにより、サドルを下葺き側の吊子の直上に正しく位置決めすることができる。
【0016】
さらに、下葺き側の吊子には、タッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されているので、前記のようにして位置決めされたサドルに側方からタッピングビスを打込めば、下穴の案内によって、容易に下葺き側はぜ継ぎ部を貫通させることができる。
【0017】
これらの作用により、下葺き側はぜ継ぎ部にサドルを配置してビス固定する作業の施工性が大幅に改善される。下葺き側の吊子には2箇所の位置決め用突起と下穴を形成するだけでよいので、加工も簡単で経済的である。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【0019】
図1(a)及び(b)は、本発明の屋根葺き構造に用いられる下葺き側の吊子4(4a,4b)の斜視図であり、図2は、図1(a)に示す吊子4(4a)を用いた屋根葺き構造の要部を示す部分斜視図である。この実施の形態は、図3及び図4に示した従来の屋根葺き構造と比較したとき、下葺き側の吊子だけが相違し、それ以外の構成は共通している。したがって、前記従来の屋根葺き構造と共通の部位や部材には共通の符号を付して、詳細な説明を省略する。
【0020】
下葺き側の吊子4は、図1(a)及び(b)に示すように、タイトフレーム11、またはこれに類する適宜の屋根構造体に固定される基部41と、基部41から略垂直に立ち上がる首部42と、首部42の上端に折曲形成されたはぜ受部43とを備えている。例示の形態に係る吊子4は、タイトフレーム11に予め固着した固定ボルトを挿通させるための長穴44が基部41に形成されているが、基部41の形状や固定方法は、タイトフレーム11その他の屋根構造体の形状に合わせて適宜に設計される。同様に、首部42及びはぜ受部43の断面形状も、下葺き側はぜ締め部14の断面形状に合わせて適宜に設計される。
【0021】
本発明の特徴として、吊子4の首部42及びはぜ受け部43は、長さ方向(はぜ締め部の延長方向)の寸法が、少なくともサドル2の長さを上回るように形成されている。さらに、図1(a)の吊子4aにおいては首部42の側面(詳細には、かぶせ側の屋根材に相対する側面)に、また図1(b)の吊子4bにおいてははぜ受部43の上面に、それぞれ2箇所の位置決め用突起45,45が形成されている。そして、これら両突起45,45の離隔距離が、ちょうどサドル2の長さに相当している。
【0022】
このような吊子4に下葺き側の屋根材13,13を重ねてシーマ等ではぜ締めすると、下葺き側はぜ継ぎ部14におけるかぶせ側の屋根材13の表面が、位置決め用突起45の形状に合わせて若干膨出する。これらの膨出痕が吊子4の位置を示す目印となるので、図2に示すように、両膨出痕に合わせてサドル2の両端を位置決めすることが可能になる。
【0023】
位置決め用突起45の突出高さは、下葺き側屋根材13の厚みと同程度ないしその倍寸程度とするのが好ましい。突出高さが小さすぎると膨出痕が目立たなくなり、突出高さが大きすぎると、はぜ締めが甘くなったり、反対に屋根材13を突き破ったりするおそれがあるからである。
【0024】
なお、例示の形態に係る位置決め用突起45は、吊子4を構成する金属板をポンチングするなどして略円錐形に突出させたものであるが、位置決め用突起45の形状は、サドル2の両端面に沿うような直線状の突条であってもよい。
【0025】
また、本発明の吊子4においては、首部42の略中央に1箇所、タッピングビス33を打込むための下穴46が形成されている。この下穴46は、図2のようにして位置決めされるサドル2のビス固定穴23と穴中心を一致させるように形成されている。したがって、吊子4に形成された2箇所の位置決め用突起45,45に合わせてサドル2を位置決めすると、サドル2の側方から打込まれるタッピングビス33が、この下穴46に案内されて、容易に吊子4を貫通することとなる。
【0026】
こうして、サドル2が下葺き側はぜ継ぎ部14に取り付けられ、下葺き側はぜ継ぎ部14に打込まれるタッピングビス33と、サドル2の両ブロック2a,2bを連結する締結用ボルト31・ナット32とによって固定される。これに続いて、図3及び図4に示したように、サドル2の上部に上葺き側の吊子16が挟み込まれ、これを介して上葺き側の屋根材17,17がはぜ継ぎされる。この工程は従来と同様であり、上葺き側の吊子16や上葺き側のはぜ継ぎ部の構成は特に図示の形態に限定されるものではない。
【0027】
【発明の効果】
本発明によれば、下葺き側の吊子に形成された2箇所の位置決め用突起によって下葺き側はぜ締め部の側面または上面に小さな膨らみが生じるので、これを手掛かりにして、サドルを下葺き側の吊子の直上に正しく位置決めすることができる。
【0028】
また、下葺き側の吊子にはタッピングビスの貫通予定位置に下穴が形成されているので、タッピングビスを下葺き側はぜ継ぎ部に対して容易に貫通させることができる。
【0029】
こうして、二重葺き折板屋根の葺設作業を格段に効率化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係る下葺き側の吊子の斜視図である。
【図2】図1(a)の吊子を用いた屋根葺き構造の要部を示す部分斜視図である。
【図3】従来の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を示す断面図である。
【図4】同じく、従来の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を示す部分斜視図である。
【符号の説明】
13 下葺き側の屋根材
14 下葺き側のはぜ継ぎ部
16 上葺き側の吊子
17 上葺き側の屋根材
2 サドル
2a ブロック
2b ブロック
31 締結ボルト
32 ナット
33 タッピングビス
4 下葺き側の吊子
41 基部
42 首部
43 はぜ受部
45 位置決め用突起
46 下穴
Claims (2)
- 下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺き側はぜ継ぎ部に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方からタッピングビスを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込んだ上葺き側の吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造において、
下葺き側の吊子には、下葺き側の屋根材に挟み込まれる部分の側面または上面に2箇所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、下葺き側の吊子におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴とする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造。 - 下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺き側はぜ継ぎ部に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方からタッピングビスを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込んだ上葺き側の吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造に用いられる下葺き側の吊子であって、
屋根の構造体に固定される基部と、基部から立ち上がる首部と、首部の上端に形成されたはぜ受部とを備え、前記首部の側面またははぜ受け部の上面に2箇所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、前記首部におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴とする吊子。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002317875A JP3633918B2 (ja) | 2002-10-31 | 2002-10-31 | 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002317875A JP3633918B2 (ja) | 2002-10-31 | 2002-10-31 | 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2004150174A JP2004150174A (ja) | 2004-05-27 |
| JP3633918B2 true JP3633918B2 (ja) | 2005-03-30 |
Family
ID=32461159
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2002317875A Expired - Fee Related JP3633918B2 (ja) | 2002-10-31 | 2002-10-31 | 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3633918B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109190321B (zh) * | 2018-11-05 | 2023-09-12 | 湖南远大工程设计有限公司 | 构件吊件设置信息确定方法、装置、存储介质及设备 |
-
2002
- 2002-10-31 JP JP2002317875A patent/JP3633918B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2004150174A (ja) | 2004-05-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4398812B2 (ja) | 受金具 | |
| JP3633918B2 (ja) | 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造及び吊子 | |
| JP4955639B2 (ja) | 外装材用取付部材、その取付構造、その取付方法、及び外装構造の施工方法 | |
| JP4663439B2 (ja) | 野縁受及び野縁の連結補強具並びに天井下地補強施工方法 | |
| CN214302583U (zh) | 板体连接构件 | |
| JP2003301567A (ja) | 立平葺き屋根構造 | |
| JP4543997B2 (ja) | 母材と連結材の接合構造 | |
| KR20050109427A (ko) | 조립식 건축용 지붕체의 연결부재 | |
| JP2909810B2 (ja) | 屋根葺替え用c型鋼材固定金具 | |
| JPS5830805Y2 (ja) | レ−ル用継手 | |
| JP3597094B2 (ja) | 二重葺き折板屋根の屋根葺き構造 | |
| JP2001032370A (ja) | 鋼管柱と鉄骨梁との継手構造とその接合方法 | |
| JPH0416826Y2 (ja) | ||
| JP2648085B2 (ja) | 鉄筋コンクリート建造物用の鉄筋ジョイント | |
| JP2589661B2 (ja) | はぜ継ぎルーフ材のケラバ施工金具組立体及びその施工方法 | |
| JP2905968B2 (ja) | 屋根板取付装置 | |
| CN214243402U (zh) | 一种围裙板连接角形件 | |
| JP3059898U (ja) | ケ―ブル支持具 | |
| JPH0754428Y2 (ja) | 吊 子 | |
| JP3032005U (ja) | フレ−ムの接合構造 | |
| KR20250049811A (ko) | 샌드위치패널 고정볼트 | |
| JP2912854B2 (ja) | 木造建築の柱と梁の結合装置 | |
| JP2754156B2 (ja) | 嵌合式の屋根板接合構造 | |
| JP6174907B2 (ja) | 外装材の取付構造 | |
| JPH0747555Y2 (ja) | 笠木付き手摺用笠木アンカー |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20041129 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20041207 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20041221 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110107 Year of fee payment: 6 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110107 Year of fee payment: 6 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110107 Year of fee payment: 6 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120107 Year of fee payment: 7 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |