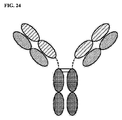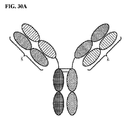JP2020529410A - Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 - Google Patents
Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2020529410A JP2020529410A JP2020505208A JP2020505208A JP2020529410A JP 2020529410 A JP2020529410 A JP 2020529410A JP 2020505208 A JP2020505208 A JP 2020505208A JP 2020505208 A JP2020505208 A JP 2020505208A JP 2020529410 A JP2020529410 A JP 2020529410A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- seq
- chain variable
- variable domain
- binding site
- antigen binding
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 102100020718 Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 Human genes 0.000 title claims abstract description 92
- 101000917858 Homo sapiens Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A Proteins 0.000 title claims abstract description 29
- 101000917839 Homo sapiens Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B Proteins 0.000 title claims abstract description 29
- 102100029185 Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B Human genes 0.000 title claims abstract description 22
- 101000932478 Homo sapiens Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 Proteins 0.000 title claims abstract 7
- 101001109501 Homo sapiens NKG2-D type II integral membrane protein Proteins 0.000 title claims description 129
- 102100022680 NKG2-D type II integral membrane protein Human genes 0.000 title claims description 119
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 title claims description 98
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 title claims description 98
- 239000000427 antigen Substances 0.000 claims abstract description 122
- 108091007433 antigens Proteins 0.000 claims abstract description 122
- 102000036639 antigens Human genes 0.000 claims abstract description 122
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 claims abstract description 82
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 claims abstract description 56
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000027455 binding Effects 0.000 claims description 237
- 125000003275 alpha amino acid group Chemical group 0.000 claims description 145
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 claims description 112
- 210000000822 natural killer cell Anatomy 0.000 claims description 77
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 claims description 64
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 claims description 59
- 229920001184 polypeptide Polymers 0.000 claims description 57
- 241000282414 Homo sapiens Species 0.000 claims description 51
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 50
- 238000009472 formulation Methods 0.000 claims description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 27
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 claims description 19
- 210000004881 tumor cell Anatomy 0.000 claims description 16
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 13
- 208000031261 Acute myeloid leukaemia Diseases 0.000 claims description 11
- 208000033776 Myeloid Acute Leukemia Diseases 0.000 claims description 10
- 239000001608 potassium adipate Substances 0.000 claims description 10
- 208000032839 leukemia Diseases 0.000 claims description 9
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 claims description 9
- 102000044042 human KLRK1 Human genes 0.000 claims description 8
- 208000010839 B-cell chronic lymphocytic leukemia Diseases 0.000 claims description 6
- 208000031422 Lymphocytic Chronic B-Cell Leukemia Diseases 0.000 claims description 6
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims description 6
- 208000024893 Acute lymphoblastic leukemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000014697 Acute lymphocytic leukaemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000032791 BCR-ABL1 positive chronic myelogenous leukemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000010833 Chronic myeloid leukaemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000033761 Myelogenous Chronic BCR-ABL Positive Leukemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000006664 Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma Diseases 0.000 claims description 5
- 108010003723 Single-Domain Antibodies Proteins 0.000 claims description 5
- 208000000389 T-cell leukemia Diseases 0.000 claims description 5
- 208000028530 T-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma Diseases 0.000 claims description 5
- 208000032852 chronic lymphocytic leukemia Diseases 0.000 claims description 5
- 201000009277 hairy cell leukemia Diseases 0.000 claims description 4
- 239000001601 sodium adipate Substances 0.000 claims description 4
- 230000030833 cell death Effects 0.000 claims description 3
- 239000003937 drug carrier Substances 0.000 claims description 3
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 claims description 2
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 claims description 2
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 claims 1
- 108091008324 binding proteins Proteins 0.000 abstract description 41
- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract description 12
- 239000008194 pharmaceutical composition Substances 0.000 abstract description 11
- 108010001657 NK Cell Lectin-Like Receptor Subfamily K Proteins 0.000 abstract description 3
- 102000000812 NK Cell Lectin-Like Receptor Subfamily K Human genes 0.000 abstract description 3
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 abstract description 3
- 102000023732 binding proteins Human genes 0.000 abstract 1
- 108010003374 fms-Like Tyrosine Kinase 3 Proteins 0.000 description 84
- 235000018102 proteins Nutrition 0.000 description 59
- 230000037396 body weight Effects 0.000 description 48
- 102000014914 Carrier Proteins Human genes 0.000 description 40
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 34
- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 24
- 230000035772 mutation Effects 0.000 description 24
- 241000699666 Mus <mouse, genus> Species 0.000 description 21
- 239000000833 heterodimer Substances 0.000 description 21
- 108010074328 Interferon-gamma Proteins 0.000 description 20
- 102100037850 Interferon gamma Human genes 0.000 description 19
- 238000005734 heterodimerization reaction Methods 0.000 description 18
- 208000009956 adenocarcinoma Diseases 0.000 description 17
- -1 NCR Proteins 0.000 description 16
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 16
- 239000012669 liquid formulation Substances 0.000 description 16
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 15
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 101001023379 Homo sapiens Lysosome-associated membrane glycoprotein 1 Proteins 0.000 description 14
- 102100035133 Lysosome-associated membrane glycoprotein 1 Human genes 0.000 description 14
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 14
- 102000006496 Immunoglobulin Heavy Chains Human genes 0.000 description 13
- 108010019476 Immunoglobulin Heavy Chains Proteins 0.000 description 13
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 13
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 13
- 102000013463 Immunoglobulin Light Chains Human genes 0.000 description 12
- 108010065825 Immunoglobulin Light Chains Proteins 0.000 description 12
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 12
- 239000013641 positive control Substances 0.000 description 12
- 229940024606 amino acid Drugs 0.000 description 11
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 11
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 11
- 238000000684 flow cytometry Methods 0.000 description 11
- 102000005962 receptors Human genes 0.000 description 11
- 108020003175 receptors Proteins 0.000 description 11
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 11
- 239000002585 base Substances 0.000 description 10
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 10
- 210000003819 peripheral blood mononuclear cell Anatomy 0.000 description 10
- 108050005493 CD3 protein, epsilon/gamma/delta subunit Proteins 0.000 description 9
- 229960002685 biotin Drugs 0.000 description 9
- 239000011616 biotin Substances 0.000 description 9
- 238000001990 intravenous administration Methods 0.000 description 9
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 9
- 239000003755 preservative agent Substances 0.000 description 9
- FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N D-Mannitol Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N 0.000 description 8
- 206010025323 Lymphomas Diseases 0.000 description 8
- 229930195725 Mannitol Natural products 0.000 description 8
- 238000003556 assay Methods 0.000 description 8
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 8
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 8
- 239000000594 mannitol Substances 0.000 description 8
- 235000010355 mannitol Nutrition 0.000 description 8
- 230000008685 targeting Effects 0.000 description 8
- 101100355609 Caenorhabditis elegans rae-1 gene Proteins 0.000 description 7
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 101100404853 Mus musculus Klrk1 gene Proteins 0.000 description 7
- 230000006051 NK cell activation Effects 0.000 description 7
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 7
- 230000001472 cytotoxic effect Effects 0.000 description 7
- 230000006240 deamidation Effects 0.000 description 7
- 239000003446 ligand Substances 0.000 description 7
- 235000010482 polyoxyethylene sorbitan monooleate Nutrition 0.000 description 7
- 229920000053 polysorbate 80 Polymers 0.000 description 7
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 7
- 108060003951 Immunoglobulin Proteins 0.000 description 6
- 108010002350 Interleukin-2 Proteins 0.000 description 6
- 102000000588 Interleukin-2 Human genes 0.000 description 6
- 108091028043 Nucleic acid sequence Proteins 0.000 description 6
- 239000008365 aqueous carrier Substances 0.000 description 6
- 239000008228 bacteriostatic water for injection Substances 0.000 description 6
- 239000007853 buffer solution Substances 0.000 description 6
- 230000009089 cytolysis Effects 0.000 description 6
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 description 6
- 102000018358 immunoglobulin Human genes 0.000 description 6
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 6
- 201000001441 melanoma Diseases 0.000 description 6
- 239000002953 phosphate buffered saline Substances 0.000 description 6
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 6
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 6
- 230000009870 specific binding Effects 0.000 description 6
- KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N succinimide Chemical compound O=C1CCC(=O)N1 KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 6
- 101710145634 Antigen 1 Proteins 0.000 description 5
- 101000581981 Homo sapiens Neural cell adhesion molecule 1 Proteins 0.000 description 5
- 108020003285 Isocitrate lyase Proteins 0.000 description 5
- 102100030301 MHC class I polypeptide-related sequence A Human genes 0.000 description 5
- 102100027347 Neural cell adhesion molecule 1 Human genes 0.000 description 5
- 206010039491 Sarcoma Diseases 0.000 description 5
- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 description 5
- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 description 5
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 5
- 239000004067 bulking agent Substances 0.000 description 5
- 238000002648 combination therapy Methods 0.000 description 5
- 231100000433 cytotoxic Toxicity 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 239000003599 detergent Substances 0.000 description 5
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 5
- 239000013604 expression vector Substances 0.000 description 5
- 102000037865 fusion proteins Human genes 0.000 description 5
- 108020001507 fusion proteins Proteins 0.000 description 5
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 description 5
- 239000012931 lyophilized formulation Substances 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 230000001404 mediated effect Effects 0.000 description 5
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 5
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000047 product Substances 0.000 description 5
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 5
- 239000005720 sucrose Substances 0.000 description 5
- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 5
- OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N 1-[(4-fluorophenyl)methyl]piperazine Chemical compound C1=CC(F)=CC=C1CN1CCNCC1 OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- OWEGMIWEEQEYGQ-UHFFFAOYSA-N 100676-05-9 Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCC1C(O)C(O)C(O)C(OC2C(OC(O)C(O)C2O)CO)O1 OWEGMIWEEQEYGQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 4
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 4
- 241000282567 Macaca fascicularis Species 0.000 description 4
- GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N Maltose Natural products O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]1[C@@H](CO)OC(O)[C@H](O)[C@H]1O GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N 0.000 description 4
- 208000015914 Non-Hodgkin lymphomas Diseases 0.000 description 4
- MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N Oxalic acid Chemical compound OC(=O)C(O)=O MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 206010042971 T-cell lymphoma Diseases 0.000 description 4
- 208000027585 T-cell non-Hodgkin lymphoma Diseases 0.000 description 4
- 210000001744 T-lymphocyte Anatomy 0.000 description 4
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 4
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 4
- GUBGYTABKSRVRQ-QUYVBRFLSA-N beta-maltose Chemical compound OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O GUBGYTABKSRVRQ-QUYVBRFLSA-N 0.000 description 4
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 4
- 230000003013 cytotoxicity Effects 0.000 description 4
- 231100000135 cytotoxicity Toxicity 0.000 description 4
- LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I dipotassium trisodium dihydrogen phosphate hydrogen phosphate dichloride Chemical compound P(=O)(O)(O)[O-].[K+].P(=O)(O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Cl-].[K+].[Cl-].[Na+] LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 239000000710 homodimer Substances 0.000 description 4
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 4
- 230000009871 nonspecific binding Effects 0.000 description 4
- 239000000244 polyoxyethylene sorbitan monooleate Substances 0.000 description 4
- 229940068968 polysorbate 80 Drugs 0.000 description 4
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001509 sodium citrate Substances 0.000 description 4
- NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K sodium citrate Chemical compound O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 4
- 235000011083 sodium citrates Nutrition 0.000 description 4
- 229940074545 sodium dihydrogen phosphate dihydrate Drugs 0.000 description 4
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 4
- VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N trans-butenedioic acid Natural products OC(=O)C=CC(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- MZOFCQQQCNRIBI-VMXHOPILSA-N (3s)-4-[[(2s)-1-[[(2s)-1-[[(1s)-1-carboxy-2-hydroxyethyl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-[[2-[[(2s)-2,6-diaminohexanoyl]amino]acetyl]amino]-4-oxobutanoic acid Chemical compound OC[C@@H](C(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCCN MZOFCQQQCNRIBI-VMXHOPILSA-N 0.000 description 3
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 108091003079 Bovine Serum Albumin Proteins 0.000 description 3
- 108010019670 Chimeric Antigen Receptors Proteins 0.000 description 3
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K Citrate Chemical compound [O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 3
- 206010009944 Colon cancer Diseases 0.000 description 3
- 102000004127 Cytokines Human genes 0.000 description 3
- 108090000695 Cytokines Proteins 0.000 description 3
- 238000012286 ELISA Assay Methods 0.000 description 3
- VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N Fumaric acid Chemical compound OC(=O)\C=C\C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N 0.000 description 3
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Chemical compound OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 3
- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 108010001336 Horseradish Peroxidase Proteins 0.000 description 3
- DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N L-asparagine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N 0.000 description 3
- ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N L-leucine Chemical compound CC(C)C[C@H](N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 3
- ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N Leucine Natural products CC(C)CC(N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N Methanesulfonic acid Chemical compound CS(O)(=O)=O AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229930191564 Monensin Natural products 0.000 description 3
- GAOZTHIDHYLHMS-UHFFFAOYSA-N Monensin A Natural products O1C(CC)(C2C(CC(O2)C2C(CC(C)C(O)(CO)O2)C)C)CCC1C(O1)(C)CCC21CC(O)C(C)C(C(C)C(OC)C(C)C(O)=O)O2 GAOZTHIDHYLHMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Propanedioic acid Natural products OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 208000015634 Rectal Neoplasms Diseases 0.000 description 3
- 208000000453 Skin Neoplasms Diseases 0.000 description 3
- 108060008682 Tumor Necrosis Factor Proteins 0.000 description 3
- 102000000852 Tumor Necrosis Factor-alpha Human genes 0.000 description 3
- 125000000539 amino acid group Chemical group 0.000 description 3
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 229940098773 bovine serum albumin Drugs 0.000 description 3
- 239000008366 buffered solution Substances 0.000 description 3
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 3
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 3
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 3
- 238000000432 density-gradient centrifugation Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 239000000539 dimer Substances 0.000 description 3
- 150000002016 disaccharides Chemical class 0.000 description 3
- 231100000673 dose–response relationship Toxicity 0.000 description 3
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 3
- 206010073071 hepatocellular carcinoma Diseases 0.000 description 3
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 3
- 229940072221 immunoglobulins Drugs 0.000 description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 229960005358 monensin Drugs 0.000 description 3
- GAOZTHIDHYLHMS-KEOBGNEYSA-N monensin A Chemical compound C([C@@](O1)(C)[C@H]2CC[C@@](O2)(CC)[C@H]2[C@H](C[C@@H](O2)[C@@H]2[C@H](C[C@@H](C)[C@](O)(CO)O2)C)C)C[C@@]21C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H]([C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C(O)=O)O2 GAOZTHIDHYLHMS-KEOBGNEYSA-N 0.000 description 3
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 3
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 3
- 210000005259 peripheral blood Anatomy 0.000 description 3
- 239000011886 peripheral blood Substances 0.000 description 3
- 230000003389 potentiating effect Effects 0.000 description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3
- 206010038038 rectal cancer Diseases 0.000 description 3
- 201000001275 rectum cancer Diseases 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- 201000000849 skin cancer Diseases 0.000 description 3
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 3
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 3
- 210000000130 stem cell Anatomy 0.000 description 3
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 229960002317 succinimide Drugs 0.000 description 3
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 3
- UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine Chemical compound CC1=C(N)C(C)=CC(C=2C=C(C)C(N)=C(C)C=2)=C1 UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonia chloride Chemical compound [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000003950 B-cell lymphoma Diseases 0.000 description 2
- 206010005003 Bladder cancer Diseases 0.000 description 2
- 206010006187 Breast cancer Diseases 0.000 description 2
- 208000026310 Breast neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 101100506090 Caenorhabditis elegans hil-2 gene Proteins 0.000 description 2
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 201000009030 Carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 206010008342 Cervix carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 208000005243 Chondrosarcoma Diseases 0.000 description 2
- YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N Citric acid monohydrate Chemical compound O.OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N Cladribine Chemical compound C1=NC=2C(N)=NC(Cl)=NC=2N1[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N 0.000 description 2
- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 description 2
- FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N D-glucitol Chemical compound OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N 0.000 description 2
- 108010009540 DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 1 Proteins 0.000 description 2
- 102100036279 DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 Human genes 0.000 description 2
- FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N Dextrotartaric acid Chemical compound OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N 0.000 description 2
- AOJJSUZBOXZQNB-TZSSRYMLSA-N Doxorubicin Chemical compound O([C@H]1C[C@@](O)(CC=2C(O)=C3C(=O)C=4C=CC=C(C=4C(=O)C3=C(O)C=21)OC)C(=O)CO)[C@H]1C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O1 AOJJSUZBOXZQNB-TZSSRYMLSA-N 0.000 description 2
- 206010014733 Endometrial cancer Diseases 0.000 description 2
- 206010014759 Endometrial neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 208000000461 Esophageal Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 229910052693 Europium Inorganic materials 0.000 description 2
- 108010087819 Fc receptors Proteins 0.000 description 2
- 102000009109 Fc receptors Human genes 0.000 description 2
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N Glycolic acid Chemical compound OCC(O)=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101001002657 Homo sapiens Interleukin-2 Proteins 0.000 description 2
- 229940076838 Immune checkpoint inhibitor Drugs 0.000 description 2
- 102000037984 Inhibitory immune checkpoint proteins Human genes 0.000 description 2
- 108091008026 Inhibitory immune checkpoint proteins Proteins 0.000 description 2
- 208000005016 Intestinal Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 102000002698 KIR Receptors Human genes 0.000 description 2
- 108010043610 KIR Receptors Proteins 0.000 description 2
- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 2
- 208000003445 Mouth Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 208000034578 Multiple myelomas Diseases 0.000 description 2
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 2
- 206010030155 Oesophageal carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 206010033128 Ovarian cancer Diseases 0.000 description 2
- 206010061535 Ovarian neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 206010061336 Pelvic neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 208000027190 Peripheral T-cell lymphomas Diseases 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010035226 Plasma cell myeloma Diseases 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N Progesterone Chemical compound C1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H]2[C@@H]1[C@@H]1CC[C@H](C(=O)C)[C@@]1(C)CC2 RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N 0.000 description 2
- 102100040678 Programmed cell death protein 1 Human genes 0.000 description 2
- 101710089372 Programmed cell death protein 1 Proteins 0.000 description 2
- 241000283984 Rodentia Species 0.000 description 2
- 208000005718 Stomach Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000031672 T-Cell Peripheral Lymphoma Diseases 0.000 description 2
- 208000007097 Urinary Bladder Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 208000006593 Urologic Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 208000006105 Uterine Cervical Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 208000002495 Uterine Neoplasms Diseases 0.000 description 2
- 150000001242 acetic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 2
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 2
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 2
- 239000013011 aqueous formulation Substances 0.000 description 2
- SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N benzenesulfonic acid Chemical compound OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N benzoic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1 WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 201000006491 bone marrow cancer Diseases 0.000 description 2
- KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N brefeldin A Chemical compound O[C@@H]1\C=C\C(=O)O[C@@H](C)CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]21 KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N 0.000 description 2
- 239000006172 buffering agent Substances 0.000 description 2
- 238000002619 cancer immunotherapy Methods 0.000 description 2
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 2
- 230000006037 cell lysis Effects 0.000 description 2
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 2
- 201000010881 cervical cancer Diseases 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 208000006990 cholangiocarcinoma Diseases 0.000 description 2
- 239000007979 citrate buffer Substances 0.000 description 2
- 150000001860 citric acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 208000029742 colonic neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 2
- 239000012228 culture supernatant Substances 0.000 description 2
- 208000035250 cutaneous malignant susceptibility to 1 melanoma Diseases 0.000 description 2
- 210000001151 cytotoxic T lymphocyte Anatomy 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 230000002357 endometrial effect Effects 0.000 description 2
- 201000004101 esophageal cancer Diseases 0.000 description 2
- CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M ethanesulfonate Chemical compound CCS([O-])(=O)=O CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N etoposide Chemical compound COC1=C(O)C(OC)=CC([C@@H]2C3=CC=4OCOC=4C=C3[C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O[C@H](C)OC[C@H]4O3)O)[C@@H]3[C@@H]2C(OC3)=O)=C1 VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N 0.000 description 2
- 229960005420 etoposide Drugs 0.000 description 2
- OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N europium atom Chemical compound [Eu] OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010017758 gastric cancer Diseases 0.000 description 2
- 230000002496 gastric effect Effects 0.000 description 2
- 210000004392 genitalia Anatomy 0.000 description 2
- 150000004679 hydroxides Chemical class 0.000 description 2
- 210000000987 immune system Anatomy 0.000 description 2
- 239000012274 immune-checkpoint protein inhibitor Substances 0.000 description 2
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 201000002313 intestinal cancer Diseases 0.000 description 2
- 230000003834 intracellular effect Effects 0.000 description 2
- 239000007951 isotonicity adjuster Substances 0.000 description 2
- 238000002372 labelling Methods 0.000 description 2
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 210000000265 leukocyte Anatomy 0.000 description 2
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 description 2
- 208000012987 lip and oral cavity carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 229940124302 mTOR inhibitor Drugs 0.000 description 2
- VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N maleic acid Chemical compound OC(=O)\C=C/C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N 0.000 description 2
- 239000003628 mammalian target of rapamycin inhibitor Substances 0.000 description 2
- 208000020968 mature T-cell and NK-cell non-Hodgkin lymphoma Diseases 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N methanoic acid Natural products OC=O BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N perchloric acid Chemical compound OCl(=O)(=O)=O VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000008363 phosphate buffer Substances 0.000 description 2
- 229920000136 polysorbate Polymers 0.000 description 2
- 229950008882 polysorbate Drugs 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 2
- YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N salicylic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1O YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000020989 salivary duct carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 2
- 230000019491 signal transduction Effects 0.000 description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 2
- 208000000649 small cell carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 description 2
- 201000011549 stomach cancer Diseases 0.000 description 2
- 150000003890 succinate salts Chemical class 0.000 description 2
- 229940095064 tartrate Drugs 0.000 description 2
- JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N toluene-4-sulfonic acid Chemical compound CC1=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C1 JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001890 transfection Methods 0.000 description 2
- 229940121358 tyrosine kinase inhibitor Drugs 0.000 description 2
- 239000005483 tyrosine kinase inhibitor Substances 0.000 description 2
- 201000005112 urinary bladder cancer Diseases 0.000 description 2
- 206010046766 uterine cancer Diseases 0.000 description 2
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 2
- OGWKCGZFUXNPDA-XQKSVPLYSA-N vincristine Chemical compound C([N@]1C[C@@H](C[C@]2(C(=O)OC)C=3C(=CC4=C([C@]56[C@H]([C@@]([C@H](OC(C)=O)[C@]7(CC)C=CCN([C@H]67)CC5)(O)C(=O)OC)N4C=O)C=3)OC)C[C@@](C1)(O)CC)CC1=C2NC2=CC=CC=C12 OGWKCGZFUXNPDA-XQKSVPLYSA-N 0.000 description 2
- 229960004528 vincristine Drugs 0.000 description 2
- OGWKCGZFUXNPDA-UHFFFAOYSA-N vincristine Natural products C1C(CC)(O)CC(CC2(C(=O)OC)C=3C(=CC4=C(C56C(C(C(OC(C)=O)C7(CC)C=CCN(C67)CC5)(O)C(=O)OC)N4C=O)C=3)OC)CN1CCC1=C2NC2=CC=CC=C12 OGWKCGZFUXNPDA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 2
- HDTRYLNUVZCQOY-UHFFFAOYSA-N α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside Natural products OC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC1C(O)C(O)C(O)C(CO)O1 HDTRYLNUVZCQOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FPVKHBSQESCIEP-UHFFFAOYSA-N (8S)-3-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol Natural products C1C(O)C(CO)OC1N1C(NC=NCC2O)=C2N=C1 FPVKHBSQESCIEP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LKJPYSCBVHEWIU-KRWDZBQOSA-N (R)-bicalutamide Chemical compound C([C@@](O)(C)C(=O)NC=1C=C(C(C#N)=CC=1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1 LKJPYSCBVHEWIU-KRWDZBQOSA-N 0.000 description 1
- DKZYXHCYPUVGAF-UHFFFAOYSA-N 1-[6-(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]cyclohexyl]amino]-1,5-naphthyridin-3-yl]ethanone Chemical compound CN(C)CC1CCC(CC1)Nc1c(cnc2ccc(nc12)-c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)C(C)=O DKZYXHCYPUVGAF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NFGXHKASABOEEW-UHFFFAOYSA-N 1-methylethyl 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate Chemical compound COC(C)(C)CCCC(C)CC=CC(C)=CC(=O)OC(C)C NFGXHKASABOEEW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FFRUQSUMDFNBLG-UHFFFAOYSA-N 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)ethyl 2,2,2-trichloroacetate Chemical compound ClC1=CC(Cl)=C(OCCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl)C=C1Cl FFRUQSUMDFNBLG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N 2-[[(3,4-dimethoxyphenyl)-oxomethyl]amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide Chemical compound C1=C(OC)C(OC)=CC=C1C(=O)NC1=C(C(N)=O)C(CCCC2)=C2S1 FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940080296 2-naphthalenesulfonate Drugs 0.000 description 1
- BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 3-azaniumyl-2-hydroxypropanoate Chemical compound NCC(O)C(O)=O BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N 3-cyclopentylpropionic acid Chemical compound OC(=O)CCC1CCCC1 ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 4-(3-methoxyphenyl)aniline Chemical compound COC1=CC=CC(C=2C=CC(N)=CC=2)=C1 OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FWMNVWWHGCHHJJ-SKKKGAJSSA-N 4-amino-1-[(2r)-6-amino-2-[[(2r)-2-[[(2r)-2-[[(2r)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]hexanoyl]piperidine-4-carboxylic acid Chemical compound C([C@H](C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O)NC(=O)[C@H](N)CC=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 FWMNVWWHGCHHJJ-SKKKGAJSSA-N 0.000 description 1
- STQGQHZAVUOBTE-UHFFFAOYSA-N 7-Cyan-hept-2t-en-4,6-diinsaeure Natural products C1=2C(O)=C3C(=O)C=4C(OC)=CC=CC=4C(=O)C3=C(O)C=2CC(O)(C(C)=O)CC1OC1CC(N)C(O)C(C)O1 STQGQHZAVUOBTE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010061424 Anal cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000003076 Angiosarcoma Diseases 0.000 description 1
- 208000007860 Anus Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 239000004475 Arginine Substances 0.000 description 1
- DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYSA-N Asparagine Natural products OC(=O)C(N)CC(N)=O DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000036170 B-Cell Marginal Zone Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 229940124290 BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 208000005440 Basal Cell Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 206010004146 Basal cell carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 206010061692 Benign muscle neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000005711 Benzoic acid Substances 0.000 description 1
- 206010004593 Bile duct cancer Diseases 0.000 description 1
- 206010005949 Bone cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000018084 Bone neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1
- 241000282817 Bovidae Species 0.000 description 1
- 208000003174 Brain Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- ULHIRVIYRFKCEC-UHFFFAOYSA-N CC1CC(C)(C2)C2C1 Chemical compound CC1CC(C)(C2)C2C1 ULHIRVIYRFKCEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100038077 CD226 antigen Human genes 0.000 description 1
- 102100027207 CD27 antigen Human genes 0.000 description 1
- 102000017420 CD3 protein, epsilon/gamma/delta subunit Human genes 0.000 description 1
- 229940124294 CD33 monoclonal antibody Drugs 0.000 description 1
- 101150013553 CD40 gene Proteins 0.000 description 1
- 229940126074 CDK kinase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 239000012275 CTLA-4 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229940045513 CTLA4 antagonist Drugs 0.000 description 1
- 241000282832 Camelidae Species 0.000 description 1
- 241000282836 Camelus dromedarius Species 0.000 description 1
- 241000282465 Canis Species 0.000 description 1
- AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N Carmofur Chemical compound CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100034744 Cell division cycle 7-related protein kinase Human genes 0.000 description 1
- 241000282693 Cercopithecidae Species 0.000 description 1
- 102000019034 Chemokines Human genes 0.000 description 1
- 108010012236 Chemokines Proteins 0.000 description 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 208000001333 Colorectal Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 108010047041 Complementarity Determining Regions Proteins 0.000 description 1
- OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L Copper gluconate Chemical class [Cu+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L 0.000 description 1
- 102100034770 Cyclin-dependent kinase inhibitor 3 Human genes 0.000 description 1
- 229940124087 DNA topoisomerase II inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 229940126289 DNA-PK inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 108010049207 Death Domain Receptors Proteins 0.000 description 1
- 102000009058 Death Domain Receptors Human genes 0.000 description 1
- 208000002699 Digestive System Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 108010052167 Dihydroorotate Dehydrogenase Proteins 0.000 description 1
- 102100032823 Dihydroorotate dehydrogenase (quinone), mitochondrial Human genes 0.000 description 1
- 206010061825 Duodenal neoplasm Diseases 0.000 description 1
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002965 ELISA Methods 0.000 description 1
- 208000002460 Enteropathy-Associated T-Cell Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- OBMLHUPNRURLOK-XGRAFVIBSA-N Epitiostanol Chemical compound C1[C@@H]2S[C@@H]2C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@](C)([C@H](CC4)O)[C@@H]4[C@@H]3CC[C@H]21 OBMLHUPNRURLOK-XGRAFVIBSA-N 0.000 description 1
- 241000283086 Equidae Species 0.000 description 1
- 241000283073 Equus caballus Species 0.000 description 1
- CTKXFMQHOOWWEB-UHFFFAOYSA-N Ethylene oxide/propylene oxide copolymer Chemical compound CCCOC(C)COCCO CTKXFMQHOOWWEB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000006168 Ewing Sarcoma Diseases 0.000 description 1
- 102000010834 Extracellular Matrix Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010037362 Extracellular Matrix Proteins Proteins 0.000 description 1
- 241000282324 Felis Species 0.000 description 1
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1
- 206010018404 Glucagonoma Diseases 0.000 description 1
- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 1
- 102000003886 Glycoproteins Human genes 0.000 description 1
- 108090000288 Glycoproteins Proteins 0.000 description 1
- 244000060234 Gmelina philippensis Species 0.000 description 1
- 108010017080 Granulocyte Colony-Stimulating Factor Proteins 0.000 description 1
- 102000004269 Granulocyte Colony-Stimulating Factor Human genes 0.000 description 1
- 102000004457 Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Human genes 0.000 description 1
- 108010017213 Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Proteins 0.000 description 1
- 102000001398 Granzyme Human genes 0.000 description 1
- 108060005986 Granzyme Proteins 0.000 description 1
- 208000001258 Hemangiosarcoma Diseases 0.000 description 1
- 102100034458 Hepatitis A virus cellular receptor 2 Human genes 0.000 description 1
- 206010073073 Hepatobiliary cancer Diseases 0.000 description 1
- 229920000209 Hexadimethrine bromide Polymers 0.000 description 1
- 208000017604 Hodgkin disease Diseases 0.000 description 1
- 208000010747 Hodgkins lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 101000884298 Homo sapiens CD226 antigen Proteins 0.000 description 1
- 101000914511 Homo sapiens CD27 antigen Proteins 0.000 description 1
- 101000945740 Homo sapiens Cell division cycle 7-related protein kinase Proteins 0.000 description 1
- 101000945639 Homo sapiens Cyclin-dependent kinase inhibitor 3 Proteins 0.000 description 1
- 101001068133 Homo sapiens Hepatitis A virus cellular receptor 2 Proteins 0.000 description 1
- 101001137987 Homo sapiens Lymphocyte activation gene 3 protein Proteins 0.000 description 1
- 101000934338 Homo sapiens Myeloid cell surface antigen CD33 Proteins 0.000 description 1
- 101000744394 Homo sapiens Oxidized purine nucleoside triphosphate hydrolase Proteins 0.000 description 1
- 101001117317 Homo sapiens Programmed cell death 1 ligand 1 Proteins 0.000 description 1
- 101100101727 Homo sapiens RAET1L gene Proteins 0.000 description 1
- 101000777293 Homo sapiens Serine/threonine-protein kinase Chk1 Proteins 0.000 description 1
- 101000801234 Homo sapiens Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18 Proteins 0.000 description 1
- 101000679903 Homo sapiens Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25 Proteins 0.000 description 1
- 101000851370 Homo sapiens Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 Proteins 0.000 description 1
- 101000621390 Homo sapiens Wee1-like protein kinase Proteins 0.000 description 1
- CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N Hydrogen bromide Chemical class Br CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010020649 Hyperkeratosis Diseases 0.000 description 1
- 108010021625 Immunoglobulin Fragments Proteins 0.000 description 1
- 102000008394 Immunoglobulin Fragments Human genes 0.000 description 1
- 102100040061 Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 Human genes 0.000 description 1
- 102000006992 Interferon-alpha Human genes 0.000 description 1
- 108010047761 Interferon-alpha Proteins 0.000 description 1
- 102000003996 Interferon-beta Human genes 0.000 description 1
- 108090000467 Interferon-beta Proteins 0.000 description 1
- 102000008070 Interferon-gamma Human genes 0.000 description 1
- 102000013462 Interleukin-12 Human genes 0.000 description 1
- 108010065805 Interleukin-12 Proteins 0.000 description 1
- 102000003812 Interleukin-15 Human genes 0.000 description 1
- 108090000172 Interleukin-15 Proteins 0.000 description 1
- SHGAZHPCJJPHSC-NUEINMDLSA-N Isotretinoin Chemical compound OC(=O)C=C(C)/C=C/C=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C SHGAZHPCJJPHSC-NUEINMDLSA-N 0.000 description 1
- 229940122245 Janus kinase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 208000001126 Keratosis Diseases 0.000 description 1
- 208000008839 Kidney Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N L-alanine Chemical compound C[C@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N L-aspartic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N L-histidine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1 HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1
- FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N L-methotrexate Chemical compound C=1N=C2N=C(N)N=C(N)C2=NC=1CN(C)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)C=C1 FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N 0.000 description 1
- COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N L-phenylalanine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1 COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N L-tryptophane Chemical compound C1=CC=C2C(C[C@H](N)C(O)=O)=CNC2=C1 QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N L-tyrosine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N L-valine Chemical compound CC(C)[C@H](N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- 102000017578 LAG3 Human genes 0.000 description 1
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M Lactate Chemical compound CC(O)C([O-])=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 208000031671 Large B-Cell Diffuse Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 206010023825 Laryngeal cancer Diseases 0.000 description 1
- HLFSDGLLUJUHTE-SNVBAGLBSA-N Levamisole Chemical compound C1([C@H]2CN3CCSC3=N2)=CC=CC=C1 HLFSDGLLUJUHTE-SNVBAGLBSA-N 0.000 description 1
- 206010058467 Lung neoplasm malignant Diseases 0.000 description 1
- 201000003791 MALT lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 229940124647 MEK inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 229940124787 MELK inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 101100404851 Macaca fascicularis KLRK1 gene Proteins 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000025205 Mantle-Cell Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 108010061593 Member 14 Tumor Necrosis Factor Receptors Proteins 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- VFKZTMPDYBFSTM-KVTDHHQDSA-N Mitobronitol Chemical compound BrC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr VFKZTMPDYBFSTM-KVTDHHQDSA-N 0.000 description 1
- 229930192392 Mitomycin Natural products 0.000 description 1
- 101100174574 Mus musculus Pikfyve gene Proteins 0.000 description 1
- 208000002231 Muscle Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 102100025243 Myeloid cell surface antigen CD33 Human genes 0.000 description 1
- 201000004458 Myoma Diseases 0.000 description 1
- NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N Mytomycin Chemical compound C1N2C(C(C(C)=C(N)C3=O)=O)=C3[C@@H](COC(N)=O)[C@@]2(OC)[C@@H]2[C@H]1N2 NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N 0.000 description 1
- OVRNDRQMDRJTHS-UHFFFAOYSA-N N-acelyl-D-glucosamine Natural products CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O OVRNDRQMDRJTHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OVRNDRQMDRJTHS-FMDGEEDCSA-N N-acetyl-beta-D-glucosamine Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O OVRNDRQMDRJTHS-FMDGEEDCSA-N 0.000 description 1
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 206010029260 Neuroblastoma Diseases 0.000 description 1
- PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N Niacin Chemical compound OC(=O)C1=CC=CN=C1 PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010029461 Nodal marginal zone B-cell lymphomas Diseases 0.000 description 1
- 206010029488 Nodular melanoma Diseases 0.000 description 1
- 241000283973 Oryctolagus cuniculus Species 0.000 description 1
- 102100039792 Oxidized purine nucleoside triphosphate hydrolase Human genes 0.000 description 1
- 239000012661 PARP inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 206010061902 Pancreatic neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 208000002471 Penile Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 206010034299 Penile cancer Diseases 0.000 description 1
- KHGNFPUMBJSZSM-UHFFFAOYSA-N Perforine Natural products COC1=C2CCC(O)C(CCC(C)(C)O)(OC)C2=NC2=C1C=CO2 KHGNFPUMBJSZSM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000009328 Perro Species 0.000 description 1
- 208000009565 Pharyngeal Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 206010034811 Pharyngeal cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000007452 Plasmacytoma Diseases 0.000 description 1
- RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N Poloxamer Chemical compound C1CO1.CC1CO1 RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108010064218 Poly (ADP-Ribose) Polymerase-1 Proteins 0.000 description 1
- 229940121906 Poly ADP ribose polymerase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 102100023712 Poly [ADP-ribose] polymerase 1 Human genes 0.000 description 1
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1
- 229920001213 Polysorbate 20 Polymers 0.000 description 1
- 208000009052 Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 102100024216 Programmed cell death 1 ligand 1 Human genes 0.000 description 1
- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M Propionate Chemical compound CCC([O-])=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229940079156 Proteasome inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 102000004022 Protein-Tyrosine Kinases Human genes 0.000 description 1
- 108090000412 Protein-Tyrosine Kinases Proteins 0.000 description 1
- 206010051807 Pseudosarcoma Diseases 0.000 description 1
- 201000008183 Pulmonary blastoma Diseases 0.000 description 1
- 101710151245 Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 Proteins 0.000 description 1
- 108020004511 Recombinant DNA Proteins 0.000 description 1
- 206010038389 Renal cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000006265 Renal cell carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 1
- 206010070834 Sensitisation Diseases 0.000 description 1
- MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N Serine Natural products OCC(N)C(O)=O MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100031081 Serine/threonine-protein kinase Chk1 Human genes 0.000 description 1
- 108010071390 Serum Albumin Proteins 0.000 description 1
- 102000007562 Serum Albumin Human genes 0.000 description 1
- 206010054184 Small intestine carcinoma Diseases 0.000 description 1
- VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M Sodium acetate Chemical compound [Na+].CC([O-])=O VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 208000032383 Soft tissue cancer Diseases 0.000 description 1
- 102000005157 Somatostatin Human genes 0.000 description 1
- 108010056088 Somatostatin Proteins 0.000 description 1
- 108010090804 Streptavidin Proteins 0.000 description 1
- 208000010502 Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma Diseases 0.000 description 1
- KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N Succinic acid Natural products OC(=O)CCC(O)=O KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 208000031673 T-Cell Cutaneous Lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 208000029052 T-cell acute lymphoblastic leukemia Diseases 0.000 description 1
- 208000024313 Testicular Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- 206010057644 Testis cancer Diseases 0.000 description 1
- ZMZDMBWJUHKJPS-UHFFFAOYSA-M Thiocyanate anion Chemical compound [S-]C#N ZMZDMBWJUHKJPS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N Threonine Natural products CC(O)C(N)C(O)=O AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004473 Threonine Substances 0.000 description 1
- 208000024770 Thyroid neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 206010062129 Tongue neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000000317 Topoisomerase II Inhibitor Substances 0.000 description 1
- HDTRYLNUVZCQOY-WSWWMNSNSA-N Trehalose Natural products O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1 HDTRYLNUVZCQOY-WSWWMNSNSA-N 0.000 description 1
- QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N Tryptophan Natural products C1=CC=C2C(CC(N)C(O)=O)=CNC2=C1 QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100028785 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 Human genes 0.000 description 1
- 102100033728 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18 Human genes 0.000 description 1
- 102100022203 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25 Human genes 0.000 description 1
- 102100022153 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 Human genes 0.000 description 1
- 101710165473 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 Proteins 0.000 description 1
- 102100040245 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 Human genes 0.000 description 1
- 102100036856 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 Human genes 0.000 description 1
- 102100040013 UL16-binding protein 6 Human genes 0.000 description 1
- 101150013568 US16 gene Proteins 0.000 description 1
- 108091008605 VEGF receptors Proteins 0.000 description 1
- 208000009311 VIPoma Diseases 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N Valine Natural products CC(C)C(N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100033177 Vascular endothelial growth factor receptor 2 Human genes 0.000 description 1
- ZVNYJIZDIRKMBF-UHFFFAOYSA-N Vesnarinone Chemical compound C1=C(OC)C(OC)=CC=C1C(=O)N1CCN(C=2C=C3CCC(=O)NC3=CC=2)CC1 ZVNYJIZDIRKMBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 102100023037 Wee1-like protein kinase Human genes 0.000 description 1
- 208000008383 Wilms tumor Diseases 0.000 description 1
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 1
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 201000011186 acute T cell leukemia Diseases 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N adipic acid Chemical class OC(=O)CCCCC(O)=O WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002671 adjuvant Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000001261 affinity purification Methods 0.000 description 1
- 239000000556 agonist Substances 0.000 description 1
- 235000004279 alanine Nutrition 0.000 description 1
- 235000010443 alginic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229920000615 alginic acid Polymers 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 1
- SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N all-trans-retinoic acid Chemical compound OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N 0.000 description 1
- 230000000735 allogeneic effect Effects 0.000 description 1
- HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N alpha,alpha-trehalose Chemical compound O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N 0.000 description 1
- AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N alpha-glycerophosphate Natural products OCC(O)COP(O)(O)=O AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004178 amaranth Substances 0.000 description 1
- 229960003437 aminoglutethimide Drugs 0.000 description 1
- ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N aminoglutethimide Chemical compound C=1C=C(N)C=CC=1C1(CC)CCC(=O)NC1=O ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019270 ammonium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 229960001220 amsacrine Drugs 0.000 description 1
- XCPGHVQEEXUHNC-UHFFFAOYSA-N amsacrine Chemical compound COC1=CC(NS(C)(=O)=O)=CC=C1NC1=C(C=CC=C2)C2=NC2=CC=CC=C12 XCPGHVQEEXUHNC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- 239000005557 antagonist Substances 0.000 description 1
- 239000002246 antineoplastic agent Substances 0.000 description 1
- 201000011165 anus cancer Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N arginine Natural products OC(=O)C(N)CCCNC(N)=N ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000009582 asparagine Nutrition 0.000 description 1
- 229960001230 asparagine Drugs 0.000 description 1
- 235000003704 aspartic acid Nutrition 0.000 description 1
- KLNFSAOEKUDMFA-UHFFFAOYSA-N azanide;2-hydroxyacetic acid;platinum(2+) Chemical compound [NH2-].[NH2-].[Pt+2].OCC(O)=O KLNFSAOEKUDMFA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VSRXQHXAPYXROS-UHFFFAOYSA-N azanide;cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid;platinum(2+) Chemical compound [NH2-].[NH2-].[Pt+2].OC(=O)C1(C(O)=O)CCC1 VSRXQHXAPYXROS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 229940092714 benzenesulfonic acid Drugs 0.000 description 1
- 235000010233 benzoic acid Nutrition 0.000 description 1
- 150000001558 benzoic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N beta-carboxyaspartic acid Natural products OC(=O)C(N)C(C(O)=O)C(O)=O OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960000997 bicalutamide Drugs 0.000 description 1
- 208000026900 bile duct neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 210000003445 biliary tract Anatomy 0.000 description 1
- 201000009036 biliary tract cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000020790 biliary tract neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-M bisulphate group Chemical group S([O-])(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 201000000053 blastoma Diseases 0.000 description 1
- 230000036765 blood level Effects 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 210000001124 body fluid Anatomy 0.000 description 1
- 239000010839 body fluid Substances 0.000 description 1
- JUMGSHROWPPKFX-UHFFFAOYSA-N brefeldin-A Natural products CC1CCCC=CC2(C)CC(O)CC2(C)C(O)C=CC(=O)O1 JUMGSHROWPPKFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KDYFGRWQOYBRFD-NUQCWPJISA-N butanedioic acid Chemical compound O[14C](=O)CC[14C](O)=O KDYFGRWQOYBRFD-NUQCWPJISA-N 0.000 description 1
- 150000004648 butanoic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 229960004562 carboplatin Drugs 0.000 description 1
- 229960003261 carmofur Drugs 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 238000013354 cell banking Methods 0.000 description 1
- 238000000423 cell based assay Methods 0.000 description 1
- 230000005779 cell damage Effects 0.000 description 1
- 208000037887 cell injury Diseases 0.000 description 1
- 239000006285 cell suspension Substances 0.000 description 1
- 210000003169 central nervous system Anatomy 0.000 description 1
- SBNPWPIBESPSIF-MHWMIDJBSA-N cetrorelix Chemical compound C([C@@H](C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@H](C)C(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC=1C=NC=CC=1)NC(=O)[C@@H](CC=1C=CC(Cl)=CC=1)NC(=O)[C@@H](CC=1C=C2C=CC=CC2=CC=1)NC(C)=O)C1=CC=C(O)C=C1 SBNPWPIBESPSIF-MHWMIDJBSA-N 0.000 description 1
- 229960003230 cetrorelix Drugs 0.000 description 1
- 108700008462 cetrorelix Proteins 0.000 description 1
- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 1
- 229960002436 cladribine Drugs 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 239000002299 complementary DNA Substances 0.000 description 1
- 238000011970 concomitant therapy Methods 0.000 description 1
- 201000010918 connective tissue cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000009260 cross reactivity Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 201000007241 cutaneous T cell lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 239000002875 cyclin dependent kinase inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229940043378 cyclin-dependent kinase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 208000002445 cystadenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 230000016396 cytokine production Effects 0.000 description 1
- 230000001461 cytolytic effect Effects 0.000 description 1
- 229940127089 cytotoxic agent Drugs 0.000 description 1
- 239000002254 cytotoxic agent Substances 0.000 description 1
- STQGQHZAVUOBTE-VGBVRHCVSA-N daunorubicin Chemical compound O([C@H]1C[C@@](O)(CC=2C(O)=C3C(=O)C=4C=CC=C(C=4C(=O)C3=C(O)C=21)OC)C(C)=O)[C@H]1C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O1 STQGQHZAVUOBTE-VGBVRHCVSA-N 0.000 description 1
- 229960000975 daunorubicin Drugs 0.000 description 1
- 230000009615 deamination Effects 0.000 description 1
- 238000006481 deamination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000000113 differential scanning calorimetry Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 206010012818 diffuse large B-cell lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 208000024558 digestive system cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 1
- 239000001177 diphosphate Substances 0.000 description 1
- XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-J diphosphate(4-) Chemical compound [O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 1
- 235000011180 diphosphates Nutrition 0.000 description 1
- UJASNKJSHULBIQ-UHFFFAOYSA-L disodium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate dihydrate Chemical compound O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(C([O-])=O)CC([O-])=O UJASNKJSHULBIQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L disodium hydrogenphosphate dihydrate Chemical compound O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N dodecyl hydrogen sulfate Chemical compound CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940043264 dodecyl sulfate Drugs 0.000 description 1
- 229960004679 doxorubicin Drugs 0.000 description 1
- 239000013583 drug formulation Substances 0.000 description 1
- 229940088679 drug related substance Drugs 0.000 description 1
- 201000000312 duodenum cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000012636 effector Substances 0.000 description 1
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 201000008184 embryoma Diseases 0.000 description 1
- 210000000750 endocrine system Anatomy 0.000 description 1
- 201000003908 endometrial adenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 201000003914 endometrial carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 201000000330 endometrial stromal sarcoma Diseases 0.000 description 1
- 208000029179 endometrioid stromal sarcoma Diseases 0.000 description 1
- 208000029382 endometrium adenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 210000002889 endothelial cell Anatomy 0.000 description 1
- 230000003511 endothelial effect Effects 0.000 description 1
- 210000003979 eosinophil Anatomy 0.000 description 1
- 210000002919 epithelial cell Anatomy 0.000 description 1
- 208000010932 epithelial neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 229950002973 epitiostanol Drugs 0.000 description 1
- 210000003743 erythrocyte Anatomy 0.000 description 1
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 210000002744 extracellular matrix Anatomy 0.000 description 1
- 208000024519 eye neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 1
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000001943 fluorescence-activated cell sorting Methods 0.000 description 1
- MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N flutamide Chemical compound CC(C)C(=O)NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1 MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960002074 flutamide Drugs 0.000 description 1
- 210000000285 follicular dendritic cell Anatomy 0.000 description 1
- 201000003444 follicular lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 229960004421 formestane Drugs 0.000 description 1
- OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N formestane Chemical compound O=C1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@](C)(C(CC4)=O)[C@@H]4[C@@H]3CCC2=C1O OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N 0.000 description 1
- 235000019253 formic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000001530 fumaric acid Substances 0.000 description 1
- 230000005714 functional activity Effects 0.000 description 1
- 150000002270 gangliosides Chemical class 0.000 description 1
- 208000015419 gastrin-producing neuroendocrine tumor Diseases 0.000 description 1
- 201000000052 gastrinoma Diseases 0.000 description 1
- 201000010231 gastrointestinal system cancer Diseases 0.000 description 1
- 238000002523 gelfiltration Methods 0.000 description 1
- SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N gemcitabine Chemical compound O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]1C(F)(F)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N 0.000 description 1
- 229960005277 gemcitabine Drugs 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 230000003394 haemopoietic effect Effects 0.000 description 1
- 210000002768 hair cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000005802 health problem Effects 0.000 description 1
- 201000010235 heart cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000024348 heart neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 201000002222 hemangioblastoma Diseases 0.000 description 1
- 230000002489 hematologic effect Effects 0.000 description 1
- 210000000777 hematopoietic system Anatomy 0.000 description 1
- 231100000844 hepatocellular carcinoma Toxicity 0.000 description 1
- MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N heptanoic acid Chemical compound CCCCCCC(O)=O MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940022353 herceptin Drugs 0.000 description 1
- 210000003630 histaminocyte Anatomy 0.000 description 1
- HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N histidine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CN=CN1 HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940121372 histone deacetylase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 239000003276 histone deacetylase inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N hydrogen iodide Chemical compound I XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZMZDMBWJUHKJPS-UHFFFAOYSA-N hydrogen thiocyanate Natural products SC#N ZMZDMBWJUHKJPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 206010020718 hyperplasia Diseases 0.000 description 1
- HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N ifosfamide Chemical compound ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960001101 ifosfamide Drugs 0.000 description 1
- 201000002312 ileal neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 210000002865 immune cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002757 inflammatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000001802 infusion Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 108091008042 inhibitory receptors Proteins 0.000 description 1
- 210000005007 innate immune system Anatomy 0.000 description 1
- 206010022498 insulinoma Diseases 0.000 description 1
- 229960003130 interferon gamma Drugs 0.000 description 1
- 229960001388 interferon-beta Drugs 0.000 description 1
- 238000001361 intraarterial administration Methods 0.000 description 1
- 238000010212 intracellular staining Methods 0.000 description 1
- 208000014899 intrahepatic bile duct cancer Diseases 0.000 description 1
- 238000007918 intramuscular administration Methods 0.000 description 1
- 238000007912 intraperitoneal administration Methods 0.000 description 1
- 238000007913 intrathecal administration Methods 0.000 description 1
- 238000004255 ion exchange chromatography Methods 0.000 description 1
- 229960005386 ipilimumab Drugs 0.000 description 1
- SUMDYPCJJOFFON-UHFFFAOYSA-N isethionic acid Chemical compound OCCS(O)(=O)=O SUMDYPCJJOFFON-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960005280 isotretinoin Drugs 0.000 description 1
- 201000010982 kidney cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000002147 killing effect Effects 0.000 description 1
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 description 1
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 description 1
- 206010023841 laryngeal neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 229960001614 levamisole Drugs 0.000 description 1
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 201000007270 liver cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000014018 liver neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 description 1
- 201000005249 lung adenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 201000005202 lung cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000020816 lung neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 210000004698 lymphocyte Anatomy 0.000 description 1
- 201000007919 lymphoplasmacytic lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 239000008176 lyophilized powder Substances 0.000 description 1
- 239000012139 lysis buffer Substances 0.000 description 1
- 210000002540 macrophage Anatomy 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 201000005831 male reproductive organ cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000011976 maleic acid Substances 0.000 description 1
- 230000003211 malignant effect Effects 0.000 description 1
- 208000015486 malignant pancreatic neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 208000016847 malignant urinary system neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 210000004962 mammalian cell Anatomy 0.000 description 1
- 201000007924 marginal zone B-cell lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 208000021937 marginal zone lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 1
- 208000037819 metastatic cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000011575 metastatic malignant neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 229940098779 methanesulfonic acid Drugs 0.000 description 1
- 229960000485 methotrexate Drugs 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 238000000386 microscopy Methods 0.000 description 1
- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 1
- 229960005485 mitobronitol Drugs 0.000 description 1
- 239000002829 mitogen activated protein kinase inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229960004857 mitomycin Drugs 0.000 description 1
- 238000012434 mixed-mode chromatography Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 150000002772 monosaccharides Chemical class 0.000 description 1
- 201000002077 muscle cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000005962 mycosis fungoides Diseases 0.000 description 1
- 229950006780 n-acetylglucosamine Drugs 0.000 description 1
- KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-M naphthalene-2-sulfonate Chemical compound C1=CC=CC2=CC(S(=O)(=O)[O-])=CC=C21 KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N naphthalene-2-sulfonic acid Chemical compound C1=CC=CC2=CC(S(=O)(=O)O)=CC=C21 KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229950007221 nedaplatin Drugs 0.000 description 1
- 201000008026 nephroblastoma Diseases 0.000 description 1
- 210000005036 nerve Anatomy 0.000 description 1
- 210000000653 nervous system Anatomy 0.000 description 1
- 210000000440 neutrophil Anatomy 0.000 description 1
- 235000001968 nicotinic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000011664 nicotinic acid Substances 0.000 description 1
- VFEDRRNHLBGPNN-UHFFFAOYSA-N nimustine Chemical compound CC1=NC=C(CNC(=O)N(CCCl)N=O)C(N)=N1 VFEDRRNHLBGPNN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000000032 nodular malignant melanoma Diseases 0.000 description 1
- 231100000065 noncytotoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002020 noncytotoxic effect Effects 0.000 description 1
- 229920002113 octoxynol Polymers 0.000 description 1
- 201000008106 ocular cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000000890 orbital cancer Diseases 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- 201000008968 osteosarcoma Diseases 0.000 description 1
- 235000006408 oxalic acid Nutrition 0.000 description 1
- 101710135378 pH 6 antigen Proteins 0.000 description 1
- 201000002528 pancreatic cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000008443 pancreatic carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 208000021255 pancreatic insulinoma Diseases 0.000 description 1
- FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N papa-hydroxy-benzoic acid Natural products OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000005163 papillary serous adenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 208000024641 papillary serous cystadenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 208000003154 papilloma Diseases 0.000 description 1
- 230000037361 pathway Effects 0.000 description 1
- 229960002340 pentostatin Drugs 0.000 description 1
- FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N pentostatin Chemical compound C1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C(N=CNC[C@H]2O)=C2N=C1 FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N 0.000 description 1
- 229930192851 perforin Natural products 0.000 description 1
- 230000010412 perfusion Effects 0.000 description 1
- JRKICGRDRMAZLK-UHFFFAOYSA-L peroxydisulfate Chemical compound [O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O JRKICGRDRMAZLK-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000002823 phage display Methods 0.000 description 1
- 239000000546 pharmaceutical excipient Substances 0.000 description 1
- 230000002974 pharmacogenomic effect Effects 0.000 description 1
- DYUMLJSJISTVPV-UHFFFAOYSA-N phenyl propanoate Chemical compound CCC(=O)OC1=CC=CC=C1 DYUMLJSJISTVPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N phenylalanine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1 COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000002935 phosphatidylinositol 3 kinase inhibitor Substances 0.000 description 1
- 229940043441 phosphoinositide 3-kinase inhibitor Drugs 0.000 description 1
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229950010765 pivalate Drugs 0.000 description 1
- IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N pivalic acid Chemical compound CC(C)(C)C(O)=O IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960000502 poloxamer Drugs 0.000 description 1
- 229920001983 poloxamer Polymers 0.000 description 1
- 229920001993 poloxamer 188 Polymers 0.000 description 1
- 229940044519 poloxamer 188 Drugs 0.000 description 1
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 239000000256 polyoxyethylene sorbitan monolaurate Substances 0.000 description 1
- 235000010486 polyoxyethylene sorbitan monolaurate Nutrition 0.000 description 1
- 229940068977 polysorbate 20 Drugs 0.000 description 1
- 235000015497 potassium bicarbonate Nutrition 0.000 description 1
- 229910000028 potassium bicarbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011736 potassium bicarbonate Substances 0.000 description 1
- TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M potassium hydrogencarbonate Chemical compound [K+].OC([O-])=O TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 208000025638 primary cutaneous T-cell non-Hodgkin lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 201000006037 primary mediastinal B-cell lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 239000000186 progesterone Substances 0.000 description 1
- 229960003387 progesterone Drugs 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003207 proteasome inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000011002 quantification Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N razoxane Chemical compound C1C(=O)NC(=O)CN1C(C)CN1CC(=O)NC(=O)C1 BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960000460 razoxane Drugs 0.000 description 1
- 108091008598 receptor tyrosine kinases Proteins 0.000 description 1
- 102000027426 receptor tyrosine kinases Human genes 0.000 description 1
- 230000007115 recruitment Effects 0.000 description 1
- 239000003488 releasing hormone Substances 0.000 description 1
- 238000007634 remodeling Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 201000007048 respiratory system cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000006845 reticulosarcoma Diseases 0.000 description 1
- 208000029922 reticulum cell sarcoma Diseases 0.000 description 1
- 230000002207 retinal effect Effects 0.000 description 1
- 230000001177 retroviral effect Effects 0.000 description 1
- 229960004889 salicylic acid Drugs 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000013341 scale-up Methods 0.000 description 1
- 230000003248 secreting effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000008313 sensitization Effects 0.000 description 1
- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1
- 230000001568 sexual effect Effects 0.000 description 1
- 208000037968 sinus cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000000267 smooth muscle cancer Diseases 0.000 description 1
- AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N sn-glycerol 3-phosphate Chemical compound OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N 0.000 description 1
- 239000001632 sodium acetate Substances 0.000 description 1
- 235000017281 sodium acetate Nutrition 0.000 description 1
- 239000008354 sodium chloride injection Substances 0.000 description 1
- 229940074404 sodium succinate Drugs 0.000 description 1
- ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L sodium succinate (anhydrous) Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- WZWGGYFEOBVNLA-UHFFFAOYSA-N sodium;dihydrate Chemical compound O.O.[Na] WZWGGYFEOBVNLA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M sodium;dihydrogen phosphate;dihydrate Chemical compound O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- NHXLMOGPVYXJNR-ATOGVRKGSA-N somatostatin Chemical compound C([C@H]1C(=O)N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC=2C=CC=CC=2)C(=O)N[C@@H](CC=2C=CC=CC=2)C(=O)N[C@@H](CC=2C3=CC=CC=C3NC=2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@H](C(=O)N1)[C@@H](C)O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)N)C(O)=O)=O)[C@H](O)C)C1=CC=CC=C1 NHXLMOGPVYXJNR-ATOGVRKGSA-N 0.000 description 1
- 229960000553 somatostatin Drugs 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 201000011096 spinal cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000014618 spinal cord cancer Diseases 0.000 description 1
- 210000000952 spleen Anatomy 0.000 description 1
- 210000004989 spleen cell Anatomy 0.000 description 1
- 206010062113 splenic marginal zone lymphoma Diseases 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- 206010041823 squamous cell carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 210000004500 stellate cell Anatomy 0.000 description 1
- 239000008227 sterile water for injection Substances 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N streptozocin Chemical compound O=NN(C)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N 0.000 description 1
- 229960001052 streptozocin Drugs 0.000 description 1
- 238000007920 subcutaneous administration Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-L succinate(2-) Chemical compound [O-]C(=O)CCC([O-])=O KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- WFWLQNSHRPWKFK-ZCFIWIBFSA-N tegafur Chemical compound O=C1NC(=O)C(F)=CN1[C@@H]1OCCC1 WFWLQNSHRPWKFK-ZCFIWIBFSA-N 0.000 description 1
- 229960001674 tegafur Drugs 0.000 description 1
- NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N teniposide Chemical compound COC1=C(O)C(OC)=CC([C@@H]2C3=CC=4OCOC=4C=C3[C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O[C@@H](OC[C@H]4O3)C=3SC=CC=3)O)[C@@H]3[C@@H]2C(OC3)=O)=C1 NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N 0.000 description 1
- 229960001278 teniposide Drugs 0.000 description 1
- 201000003120 testicular cancer Diseases 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000011287 therapeutic dose Methods 0.000 description 1
- 230000004797 therapeutic response Effects 0.000 description 1
- 201000002510 thyroid cancer Diseases 0.000 description 1
- 201000006134 tongue cancer Diseases 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002054 transplantation Methods 0.000 description 1
- 229960001727 tretinoin Drugs 0.000 description 1
- 230000006433 tumor necrosis factor production Effects 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N tyrosine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004917 tyrosine kinase inhibitor derivatives Chemical class 0.000 description 1
- ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N undecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCC(O)=O ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001430294 unidentified retrovirus Species 0.000 description 1
- 201000004435 urinary system cancer Diseases 0.000 description 1
- 210000004291 uterus Anatomy 0.000 description 1
- 206010046885 vaginal cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000013139 vaginal neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000004474 valine Substances 0.000 description 1
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 1
- 229950005577 vesnarinone Drugs 0.000 description 1
- GBABOYUKABKIAF-GHYRFKGUSA-N vinorelbine Chemical compound C1N(CC=2C3=CC=CC=C3NC=22)CC(CC)=C[C@H]1C[C@]2(C(=O)OC)C1=CC([C@]23[C@H]([C@]([C@H](OC(C)=O)[C@]4(CC)C=CCN([C@H]34)CC2)(O)C(=O)OC)N2C)=C2C=C1OC GBABOYUKABKIAF-GHYRFKGUSA-N 0.000 description 1
- 239000008215 water for injection Substances 0.000 description 1
- 239000000080 wetting agent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
- C07K16/2863—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against receptors for growth factors, growth regulators
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K39/00—Medicinal preparations containing antigens or antibodies
- A61K39/395—Antibodies; Immunoglobulins; Immune serum, e.g. antilymphocytic serum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
- A61P35/02—Antineoplastic agents specific for leukemia
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
- C07K16/2803—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the immunoglobulin superfamily
- C07K16/283—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the immunoglobulin superfamily against Fc-receptors, e.g. CD16, CD32, CD64
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
- C07K16/2851—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the lectin superfamily, e.g. CD23, CD72
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
- C07K16/2896—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against molecules with a "CD"-designation, not provided for elsewhere
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans
- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
- C07K16/30—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants from tumour cells
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/46—Hybrid immunoglobulins
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
- C07K16/46—Hybrid immunoglobulins
- C07K16/468—Immunoglobulins having two or more different antigen binding sites, e.g. multifunctional antibodies
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K39/00—Medicinal preparations containing antigens or antibodies
- A61K2039/505—Medicinal preparations containing antigens or antibodies comprising antibodies
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/20—Immunoglobulins specific features characterized by taxonomic origin
- C07K2317/21—Immunoglobulins specific features characterized by taxonomic origin from primates, e.g. man
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/30—Immunoglobulins specific features characterized by aspects of specificity or valency
- C07K2317/31—Immunoglobulins specific features characterized by aspects of specificity or valency multispecific
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/50—Immunoglobulins specific features characterized by immunoglobulin fragments
- C07K2317/52—Constant or Fc region; Isotype
- C07K2317/524—CH2 domain
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/50—Immunoglobulins specific features characterized by immunoglobulin fragments
- C07K2317/52—Constant or Fc region; Isotype
- C07K2317/53—Hinge
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/50—Immunoglobulins specific features characterized by immunoglobulin fragments
- C07K2317/56—Immunoglobulins specific features characterized by immunoglobulin fragments variable (Fv) region, i.e. VH and/or VL
- C07K2317/569—Single domain, e.g. dAb, sdAb, VHH, VNAR or nanobody®
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/60—Immunoglobulins specific features characterized by non-natural combinations of immunoglobulin fragments
- C07K2317/62—Immunoglobulins specific features characterized by non-natural combinations of immunoglobulin fragments comprising only variable region components
- C07K2317/622—Single chain antibody (scFv)
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/70—Immunoglobulins specific features characterized by effect upon binding to a cell or to an antigen
- C07K2317/75—Agonist effect on antigen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07K—PEPTIDES
- C07K2317/00—Immunoglobulins specific features
- C07K2317/90—Immunoglobulins specific features characterized by (pharmaco)kinetic aspects or by stability of the immunoglobulin
- C07K2317/92—Affinity (KD), association rate (Ka), dissociation rate (Kd) or EC50 value
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Oncology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Mycology (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
Abstract
Description
本出願は、2017年7月31日出願の米国特許仮出願第62/539,421号明細書の利益及びその優先権を主張し、その内容全体が、あらゆる目的のために参照によって本明細書に組み込まれる。
本出願は、ASCII形式で電子的に提出された配列表を含有し、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。2018年7月30日に作成されたASCIIコピーは、DFY−027WO_SL.txtという名称であり、103,731バイトのサイズである。
本発明は、ナチュラルキラー細胞上のNKG2D受容体及びCD16受容体、ならびに腫瘍関連抗原FLT3に結合する多重特異性結合タンパク質を提供する。多重特異性結合タンパク質は、本明細書に記載される医薬組成物及び治療方法に有用である。多重特異性結合タンパク質と、ナチュラルキラー細胞上のNKG2D受容体及びCD16受容体との結合は、FLT3を発現する腫瘍細胞の破壊に対するナチュラルキラー細胞の活性を増強する。多重特異性結合タンパク質とFLT3発現細胞との結合は、がん細胞をナチュラルキラー細胞に近接させ、これにより、ナチュラルキラー細胞による直接的かつ間接的ながん細胞の破壊が促進される。いくつかの例示的な多重特異性結合タンパク質のさらなる記載が以下に提供される。
本明細書に記載される多重特異性タンパク質は、NKG2D結合部位、CD16結合部位、及びFLT3結合部位を含む。いくつかの実施形態では、多重特異性タンパク質は、NK細胞などの、NKG2D及び/またはCD16を発現する細胞、ならびにFLT3を発現する腫瘍細胞に同時に結合する。多重特異性結合タンパク質とNK細胞との結合は、腫瘍細胞の破壊に対するNK細胞の活性を増強し得る。
本発明は、本明細書に記載される多重特異性結合タンパク質及び/または本明細書に記載される医薬組成物を使用して、がんを処置する方法を提供する。本方法は、FLT3を発現する様々ながんを処置するために使用されてよい。いくつかの実施形態では、がんは白血病、例えば、急性骨髄性白血病、T細胞白血病、急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、または有毛細胞白血病である。
本発明の別の態様は、併用療法をもたらす。本明細書に記載される多重特異性結合タンパク質は、がんを処置するために追加の治療剤と組み合わせて使用され得る。
本開示はまた、治療有効量の本明細書に記載されるタンパク質を含有する医薬組成物を特徴とする。組成物は、様々な薬物送達システムで使用するために製剤化され得る。1つ以上の生理学的に許容される賦形剤または担体も、適切な製剤化のために組成物に含まれ得る。本開示での使用に好適な製剤は、Remington’s Pharmaceutical Sciences,Mack Publishing Company,Philadelphia,Pa.,17th ed.,1985に見出される。薬剤送達の方法の簡単な概説については、例えば、Langer(Science 249:1527−1533,1990)を参照のこと。
NKG2D結合ドメインは、精製した組換えNKG2Dに結合する
ヒト、マウスまたはカニクイザルNKG2Dエクトドメインの核酸配列を、ヒトIgG1Fcドメインをコードする核酸配列と融合し、発現される哺乳動物細胞内に導入した。精製後、NKG2D−Fc融合タンパク質をマイクロプレートのウェルに吸着させた。非特異的結合を防止するためにウシ血清アルブミンでウェルをブロックした後、NKG2D結合ドメインを滴定し、NKG2D−Fc融合タンパク質を予め吸着させたウェルに添加した。一次抗体の結合を、西洋ワサビペルオキシダーゼと複合化させた、Fc交差反応を回避するためにヒトカッパ軽鎖を特異的に認識する二次抗体を使用して検出した。3,3’,5,5’−テトラメチルベンジジン(TMB)、すなわち、西洋ワサビペルオキシダーゼの基質をウェルに添加して結合シグナルを可視化し、その吸光度を450nMで測定して540nMで補正した。NKG2D結合ドメインクローン、アイソタイプ対照または陽性対照(配列番号:101〜104から選択される重鎖及び軽鎖可変ドメインを含む、もしくはeBioscienceで入手可能な抗マウスNKG2DクローンのMI−6及びCX−5)を各ウェルに添加した。
EL4マウスリンパ腫細胞株を操作して、ヒトまたはマウスNKG2D−CD3ゼータシグナル伝達ドメインキメラ抗原受容体を発現させた。NKG2D結合クローン、アイソタイプ対照または陽性対照を100nMの濃度で使用して、EL4細胞上に発現した細胞外NKG2Dを染色した。抗体結合を、フルオロフォア複合化抗ヒトIgG二次抗体を使用して検出した。細胞をフローサイトメトリーによって分析し、バックグラウンドに対する倍率(FOB)を、親EL4細胞と比較したNKG2D発現細胞の平均蛍光強度(MFI)を使用して算出した。
ULBP−6との競合
組換えヒトNKG2D−Fcタンパク質をマイクロプレートのウェルに吸着させ、非特異的結合を減少させるためにウシ血清アルブミンでウェルをブロックした。飽和濃度のULBP−6−His−ビオチンをウェルに添加し、続いてNKG2D結合ドメインクローンを添加した。2時間のインキュベーション後、ウェルを洗浄し、NKG2D−Fcでコーティングしたウェルに結合したままであったULBP−6−His−ビオチンを、西洋ワサビペルオキシダーゼと複合化したストレプトアビジン及びTMB基質によって検出した。吸光度を450nMで測定し、540nMで補正した。バックグラウンドを差し引いた後、NKG2D−Fcタンパク質に対するNKG2D結合ドメインの特異的結合を、ウェル中でNKG2D−Fcタンパク質に対する結合からブロックされたULBP−6−His−ビオチンのパーセンテージから算出した。陽性対照抗体(配列番号:101〜104から選択される重鎖及び軽鎖可変ドメインを含む)ならびに様々なNKG2D結合ドメインが、NKG2Dに結合するULBP−6をブロックした一方で、アイソタイプ対照は、ULBP−6との競合をほとんど示さなかった(図8)。
組換えヒトMICA−Fcタンパク質をマイクロプレートのウェルに吸着させ、非特異的結合を減少させるためにウシ血清アルブミンでウェルをブロックした。NKG2D−Fc−ビオチンをウェルに添加し、続いてNKG2D結合ドメインを添加した。インキュベーション及び洗浄後、MICA−Fcでコーティングしたウェルに結合したままであったNKG2D−Fc−ビオチンを、ストレプトアビジン−HRP及びTMB基質を使用して検出した。吸光度を450nMで測定し、540nMで補正した。バックグラウンドを差し引いた後、NKG2D−Fcタンパク質に対するNKG2D結合ドメインの特異的結合を、MICA−Fcでコーティングしたウェルに対する結合からブロックされたNKG2D−Fc−ビオチンのパーセンテージから算出した。陽性対照抗体(配列番号:101〜104から選択される重鎖及び軽鎖可変ドメインを含む)ならびに様々なNKG2D結合ドメインが、NKG2Dに結合するMICAをブロックした一方で、アイソタイプ対照は、MICAとの競合をほとんど示さなかった(図9)。
組換えマウスRae−1デルタ−Fc(R&D Systemsから購入した)をマイクロプレートのウェルに吸着させ、非特異的結合を減少させるためにウシ血清アルブミンでウェルをブロックした。マウスNKG2D−Fc−ビオチンをウェルに添加し、続いてNKG2D結合ドメインを添加した。インキュベーション及び洗浄後、Rae−1デルタ−Fcでコーティングしたウェルに結合したままであったNKG2D−Fc−ビオチンを、ストレプトアビジン−HRP及びTMB基質を使用して検出した。吸光度を450nMで測定し、540nMで補正した。バックグラウンドを差し引いた後、NKG2D−Fcタンパク質に対するNKG2D結合ドメインの特異的結合を、Rae−1デルタ−Fcでコーティングしたウェルに対する結合からブロックされたNKG2D−Fc−ビオチンのパーセンテージから算出した。陽性対照(配列番号:101〜104から選択される重鎖及び軽鎖可変ドメインを含む、またはeBioscienceで入手可能な抗マウスNKG2DクローンのMI−6及びCX−5)ならびに様々なNKG2D結合ドメインクローンが、マウスNKG2Dに結合するRae−1デルタをブロックした一方で、アイソタイプ対照抗体は、Rae−1デルタとの競合をほとんど示さなかった(図10)。
ヒト及びマウスNKG2Dの核酸配列を、CD3ゼータシグナル伝達ドメインをコードする核酸配列に融合し、キメラ抗原受容体(CAR)構築物を得た。次いで、NKG2D−CAR構築物を、ギブソンアセンブリを使用してレトロウイルスベクターにクローニングし、レトロウイルス産生のためにexpi293細胞にトランスフェクトした。EL4細胞を、8μg/mLのポリブレンと共にNKG2D−CARを含有するウイルスに感染させた。感染から24時間後、EL4細胞中のNKG2D−CARの発現レベルをフローサイトメトリーによって分析し、細胞表面上で高レベルのNKG2D−CARを発現するクローンを選択した。
初代ヒトNK細胞
末梢血単核細胞(PBMC)を、密度勾配遠心分離法を使用して、ヒト末梢血バフィーコートから単離した。NK細胞(CD3−CD56+)を、磁気ビーズを用いたネガティブセレクションを使用してPBMCから単離し、単離したNK細胞の純度は通常、>95%であった。次いで、単離したNK細胞を、100ng/mLのIL−2を含有する培地中で24〜48時間培養してから、それらを、NKG2D結合ドメインを吸着させたマイクロプレートのウェルに移し、フルオロフォア複合化抗CD107a抗体、ブレフェルジン−A、及びモネンシンを含有する培地中で培養した。培養後、NK細胞を、フローサイトメトリーによってCD3、CD56及びIFN−γに対するフルオロフォア複合化抗体を使用してアッセイした。CD107a及びIFN−γ染色を、CD3−CD56+細胞中で分析し、NK細胞活性化を評価した。CD107a/IFN−γ二重陽性細胞の増加は、1つの受容体ではなく、2つの活性化受容体の結合による良好なNK細胞活性化を示している。NKG2D結合ドメインならびに陽性対照(例えば、配列番号:101または配列番号:103で表される重鎖可変ドメイン、及び配列番号:102または配列番号:104で表される軽鎖可変ドメイン)は、アイソタイプ対照よりも高いパーセンテージの、CD107a+及びIFN−γ+となるNK細胞を示した(図13及び図14は、2つの独立した実験からのデータを表し、各々でNK細胞調製のために異なるドナーのPBMCを使用した)。
脾臓をC57Bl/6マウスから入手し、70μmのセルストレーナーによって破砕して単一の細胞懸濁液を得た。細胞をペレットにし、ACK溶解緩衝液(Thermo Fisher Scientificから購入した#A1049201、155mMの塩化アンモニウム、10mMの重炭酸カリウム、0.01mMのEDTA)中に再懸濁して赤血球を除去した。残存する細胞を100ng/mLのhIL−2と共に72時間培養してから、採取してNK細胞単離のために調製した。次いで、NK細胞(CD3−NK1.1+)を、磁気ビーズを用いたネガティブ除去技術を使用して脾臓細胞から単離し、通常は>90%の純度であった。精製したNK細胞を、100ng/mLのmIL−15を含有する培地中で48時間培養してから、それらを、NKG2D結合ドメインを吸着させたマイクロプレートのウェルに移し、フルオロフォア複合化抗CD107a抗体、ブレフェルジン−A、及びモネンシンを含有する培地中で培養した。NKG2D結合ドメインでコーティングしたウェル中での培養後、NK細胞を、フローサイトメトリーによってCD3、NK1.1及びIFN−γに対するフルオロフォア複合化抗体を使用してアッセイした。CD107a及びIFN−γ染色を、CD3−NK1.1+細胞中で分析し、NK細胞活性化を評価した。CD107a/IFN−γ二重陽性細胞の増加は、1つの受容体ではなく、2つの活性化受容体の結合による良好なNK細胞活性化を示している。NKG2D結合ドメインならびに陽性対照(eBioscienceで入手可能な抗マウスNKG2DクローンのMI−6及びCX−5から選択される)は、アイソタイプ対照よりも高いパーセンテージの、CD107a+及びIFN−γ+となるNK細胞を示した(図15及び図16は、2つの独立した実験からのデータを表し、各々でNK細胞調製のために異なるマウスを使用した)。
ヒト及びマウス初代NK細胞活性化アッセイは、NKG2D結合ドメインとのインキュベーション後における、NK細胞上での細胞傷害性マーカーの増加を実証した。このことが腫瘍細胞溶解の増加につながるかを確認するために、細胞に基づくアッセイを利用し、各NKG2D結合ドメインを単一特異性抗体とした。Fc領域を1つの標的化アームとして使用した一方で、Fab領域(NKG2D結合ドメイン)は、NK細胞を活性化させるための別の標的化アームとして機能した。THP−1細胞はヒト起源であり、高レベルのFc受容体を発現し、これらを腫瘍標的として使用して、Perkin Elmer DELFIA細胞傷害性キットを使用した。THP−1細胞をBATDA試薬で標識し、105/mLで培養培地中に再懸濁させた。次いで、標識したTHP−1細胞をNKG2D抗体と組み合わせ、マウスNK細胞をマイクロタイタープレートのウェル中において37℃で3時間単離した。インキュベーション後、20μLの培養上清を除去し、200μLのユウロピウム溶液と混合して15分間暗所で振盪しながらインキュベートした。蛍光を、時間分解蛍光モジュールを備えたPheraStarプレートリーダーによって経時的に測定し(励起337nm、発光620nm)、特異的溶解をキットの説明書に従って算出した。
NKG2D結合ドメインの融解温度を、示差走査蛍光定量法を使用してアッセイした。外挿した見かけの融解温度は、典型的なIgG1抗体と比較して高い(図18)。
初代ヒトNK細胞活性化アッセイ
末梢血単核細胞(PBMC)を、密度勾配遠心分離法を使用して、ヒト末梢血バフィーコートから単離した。NK細胞を、ネガティブ磁気ビーズ(StemCell#17955)を使用してPBMCから精製した。NK細胞は、フローサイトメトリーによって決定した場合、>90%のCD3−CD56+であった。次いで、細胞を、活性化アッセイでの使用前に100ng/mLのhIL−2(Peprotech#200−02)を含有する培地中で48時間増殖させた。抗体を96ウェル平底プレート上に、2μg/mL(抗CD16、Biolegend#302013)及び5μg/mL(抗NKG2D、R&D#MAB139)の濃度で、100μLの滅菌PBS中において一晩4℃でコーティングし、続いてウェルを完全に洗浄して過剰な抗体を除去した。脱顆粒の評価のために、IL−2活性化NK細胞を5×105細胞/mLで、100ng/mLのヒトIL−2(hIL2)及び1μg/mLのAPC複合化抗CD107a mAb(Biolegend#328619)を補充した培養培地中に再懸濁させた。次いで、1×105細胞/ウェルを抗体でコーティングしたプレート上に添加した。タンパク質輸送阻害剤のブレフェルジンA(BFA、Biolegend#420601)及びモネンシン(Biolegend#420701)を、それぞれ1:1000及び1:270の最終希釈で添加した。播種した細胞を、4時間37℃で5%CO2中においてインキュベートした。IFN−γの細胞内染色のために、NK細胞を抗CD3(Biolegend#300452)及び抗CD56mAb(Biolegend#318328)で標識し、その後、固定して透過処理し、抗IFN−γ mAb(Biolegend#506507)で標識した。生CD56+CD3−細胞上でゲーティングした後、NK細胞を、CD107a及びIFN−γの発現についてフローサイトメトリーによって分析した。
EL4マウスリンパ腫細胞株を操作して、ヒトNKG2Dを発現させた。多重特異性結合タンパク質、例えば、三重特異性結合タンパク質(TriNKET)は、その各々がNKG2D結合ドメイン、FLT3結合ドメイン、及びCD16に結合するFcドメインを含有し、EL4細胞上に発現した細胞外NKG2Dに結合するそれらの親和性について試験した。TriNKETを20μg/mLに希釈し、次いで段階的に希釈した。TriNKETとNKG2Dとの結合を、フルオロフォア複合化抗ヒトIgG二次抗体を使用して検出した。次いで、細胞をフローサイトメトリーによって分析し、平均蛍光強度(MFI)を、二次抗体対照を基準として正規化してバックグラウンドに対する倍率(FOB)値を得た。
FLT3を発現するヒトAML細胞株(Molm−13及びEOL−1)を使用して、FLT3標的化TriNKETと腫瘍関連抗原との結合をアッセイした。TriNKETを細胞と共にインキュベートし、結合を、フルオロフォア複合化抗ヒトIgG二次抗体を使用して検出した。細胞をフローサイトメトリーによって分析し、平均蛍光強度(MFI)を、二次抗体対照を基準として正規化してバックグラウンドに対する倍率(FOB)値を得た。
ヒトAML細胞株のMolm−13及びEOL−1を使用して、細胞表面上に発現したFLT3に結合した後のFLT3標的化TriNKETの内在化を評価した。TriNKETまたはモノクローナル抗体のリンツズマブを20μg/mLに希釈し、これを使用して細胞を染色した。染色後、試料の3分の2を37℃で一晩置いて内在化を促進させ、試料の残り3分の1を、フルオロフォア複合化抗ヒトIgG二次抗体を使用して検出し、ベースラインMFIを得た。37℃での2時間及び20時間のインキュベーション後、試料をインキュベーターから取り出し、細胞の表面上にある結合した抗体を、フルオロフォア複合化抗ヒトIgG二次抗体を使用して検出し、試料MFIを得た。内在化を算出した:%内在化=(1−(試料MFI/ベースラインMFI))*100%。
FLT3標的化TriNKETの存在下においてFLT3発現がん細胞を溶解させるヒトNK細胞の能力を試験するために、末梢血単核細胞(PBMC)を単離し、NK細胞単離のために調製した。PBMCを、密度勾配遠心分離法を使用して、ヒト末梢血バフィーコートから単離した。単離したPBMCを洗浄し、NK細胞単離のために調製した。NK細胞を、磁気ビーズを用いたネガティブセレクション技術を使用して単離し、単離したNK細胞の純度は通常、>90%のCD3−CD56+であった。単離したNK細胞を、100ng/mLのIL−2を含有する培地中で培養したか、またはサイトカインを入れずに一晩置いた。IL−2活性化または置いたNK細胞を、細胞傷害性アッセイで翌日使用した。
本明細書で言及される特許文献及び科学論文の各々の開示全体は、あらゆる目的のために参照によって組み込まれる。
本発明は、その趣旨または本質的特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化されてよい。したがって、前述の実施形態は、本明細書に記載される本発明を限定するのではなく、あらゆる点において例示的であると見なされるべきである。したがって、本発明の範囲は、前述の記載によってではなく、添付の特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と等価の意味及び範囲内に入る全ての変更が、本明細書に包含されること意図する。
Claims (38)
- タンパク質であって、
(a)NKG2Dと結合する第1抗原結合部位と、
(b)FLT3と結合する第2抗原結合部位と、
(c)抗体FcドメインもしくはCD16と結合するのに十分なその一部分、またはCD16と結合する第3抗原結合部位とを含む、前記タンパク質。 - 前記第1抗原結合部位が、ヒトのNKG2Dに結合する、請求項1に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、重鎖可変ドメイン及び軽鎖可変ドメインを含む、請求項1または2に記載のタンパク質。
- 前記重鎖可変ドメイン及び前記軽鎖可変ドメインが、同じポリペプチド上に存在する、請求項3に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位が、重鎖可変ドメイン及び軽鎖可変ドメインを含む、請求項3または4に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位の前記重鎖可変ドメイン及び前記軽鎖可変ドメインが、同じポリペプチド上に存在する、請求項5に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位の前記軽鎖可変ドメインが、前記第2抗原結合部位の前記軽鎖可変ドメインのアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を有する、請求項5または6に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:1、配列番号:41、配列番号:49、配列番号:57、配列番号:59、配列番号:61、配列番号:69、配列番号:77、配列番号:85、及び配列番号:93から選択されるアミノ酸配列と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメインを含む、先行請求項のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:41と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:42と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:49と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:50と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:57と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:58と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:59と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:60と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:61と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:62と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:69と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:70と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:77と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:78と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:85と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:86と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:93と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:94と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:101と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:102と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、配列番号:103と少なくとも90%同一の重鎖可変ドメイン及び配列番号:104と少なくとも90%同一の軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第1抗原結合部位が、単一ドメイン抗体である、請求項1または2に記載のタンパク質。
- 前記単一ドメイン抗体が、VHH断片またはVNAR断片である、請求項20に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位が、重鎖可変ドメイン及び軽鎖可変ドメインを含む、請求項1〜2または20〜21のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位の前記重鎖可変ドメイン及び前記軽鎖可変ドメインが、同じポリペプチド上に存在する、請求項22に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位がFLT3と結合し、前記第2抗原結合部位の前記重鎖可変ドメインが、配列番号:109と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含み、前記第2抗原結合部位の前記軽鎖可変ドメインが、配列番号:113と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含む、請求項1〜23のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位がFLT3と結合し、前記第2抗原結合部位の前記重鎖可変ドメインが、配列番号:117と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含み、前記第2抗原結合部位の前記軽鎖可変ドメインが、配列番号:121と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含む、請求項1〜23のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位がFLT3と結合し、前記第2抗原結合部位の前記重鎖可変ドメインが、配列番号:125と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含み、前記第2抗原結合部位の前記軽鎖可変ドメインが、配列番号:129と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含む、請求項1〜23のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位が、単一ドメイン抗体である、請求項1〜4または8〜21のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記第2抗原結合部位が、VHH断片またはVNAR断片である、請求項27に記載のタンパク質。
- 前記タンパク質が、CD16と結合するのに十分な抗体Fcドメインの一部分を含み、前記抗体Fcドメインがヒンジ及びCH2ドメインを含む、先行請求項のいずれか1項に記載のタンパク質。
- 前記抗体Fcドメインが、ヒトIgG1抗体のヒンジ及びCH2ドメインを含む、請求項29に記載のタンパク質。
- 前記Fcドメインが、ヒトIgG1抗体のアミノ酸234〜332と少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含む、請求項29または30に記載のタンパク質。
- 前記Fcドメインが、ヒトIgG1の前記Fcドメインと少なくとも90%同一のアミノ酸配列を含み、Q347、Y349、L351、S354、E356、E357、K360、Q362、S364、T366、L368、K370、N390、K392、T394、D399、S400、D401、F405、Y407、K409、T411、K439からなる群から選択される1つ以上の位置で異なる、請求項31に記載のタンパク質。
- 先行請求項のいずれか1項に記載のタンパク質と、薬学的に許容される担体とを含む、製剤。
- 請求項1〜32のいずれか1項に記載のタンパク質を発現する1つ以上の核酸を含む、細胞。
- 腫瘍細胞死の増強方法であって、腫瘍細胞及びナチュラルキラー細胞を、有効量の請求項1〜32のいずれか1項に記載の前記タンパク質に曝露することを含み、前記腫瘍細胞がFLT3を発現する、前記方法。
- がんの処置方法であって、前記方法が、有効量の請求項1〜32のいずれか1項に記載の前記タンパク質または請求項33に記載の前記製剤を患者に投与することを含む、前記方法。
- 前記がんが白血病である、請求項36に記載の方法。
- 前記白血病が、急性骨髄性白血病、T細胞白血病、急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、及び有毛細胞白血病からなる群から選択される、請求項37に記載のがんの処置方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2023075458A JP2023106433A (ja) | 2017-07-31 | 2023-05-01 | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201762539421P | 2017-07-31 | 2017-07-31 | |
| US62/539,421 | 2017-07-31 | ||
| PCT/US2018/044610 WO2019028027A1 (en) | 2017-07-31 | 2018-07-31 | PROTEINS BINDING TO NKG2D, CD16 AND FLT3 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2023075458A Division JP2023106433A (ja) | 2017-07-31 | 2023-05-01 | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2020529410A true JP2020529410A (ja) | 2020-10-08 |
| JP2020529410A5 JP2020529410A5 (ja) | 2021-09-24 |
Family
ID=65233032
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2020505208A Pending JP2020529410A (ja) | 2017-07-31 | 2018-07-31 | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 |
| JP2023075458A Pending JP2023106433A (ja) | 2017-07-31 | 2023-05-01 | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2023075458A Pending JP2023106433A (ja) | 2017-07-31 | 2023-05-01 | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20200165344A1 (ja) |
| EP (1) | EP3661554A4 (ja) |
| JP (2) | JP2020529410A (ja) |
| KR (1) | KR20200033302A (ja) |
| CN (1) | CN111132698A (ja) |
| AU (1) | AU2018309712A1 (ja) |
| BR (1) | BR112020001972A2 (ja) |
| CA (1) | CA3070986A1 (ja) |
| CO (1) | CO2020001981A2 (ja) |
| EA (1) | EA202090387A1 (ja) |
| IL (1) | IL272374A (ja) |
| MA (1) | MA49769A (ja) |
| MX (1) | MX2020001257A (ja) |
| SG (1) | SG11202000632QA (ja) |
| WO (1) | WO2019028027A1 (ja) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA3221995A1 (en) | 2017-02-08 | 2018-08-16 | Dragonfly Therapeutics, Inc. | Multi-specific binding proteins for activation of natural killer cells and therapeutic uses thereof to treat cancer |
| US11884732B2 (en) | 2017-02-20 | 2024-01-30 | Dragonfly Therapeutics, Inc. | Proteins binding HER2, NKG2D and CD16 |
| JP2021512630A (ja) | 2018-02-08 | 2021-05-20 | ドラゴンフライ セラピューティクス, インコーポレイテッド | Nkg2d受容体を標的とする抗体可変ドメイン |
| TW202128759A (zh) * | 2019-10-15 | 2021-08-01 | 美商蜻蜓醫療公司 | 結合nkg2d、cd及flt3之蛋白質 |
| CN117580865A (zh) * | 2021-06-29 | 2024-02-20 | 山东先声生物制药有限公司 | Cd16抗体及其应用 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011506406A (ja) * | 2007-12-14 | 2011-03-03 | ノボ・ノルデイスク・エー/エス | ヒトnkg2dに対する抗体とその使用 |
| JP2011521647A (ja) * | 2008-05-30 | 2011-07-28 | イムクローン・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 抗flt3抗体 |
| JP2013500721A (ja) * | 2009-07-29 | 2013-01-10 | アボット・ラボラトリーズ | 二重可変ドメイン免疫グロブリンおよびその使用 |
| JP2013515472A (ja) * | 2009-12-23 | 2013-05-09 | シュニムネ ゲーエムベーハー | 抗flt3抗体及びその使用方法 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| UY33492A (es) * | 2010-07-09 | 2012-01-31 | Abbott Lab | Inmunoglobulinas con dominio variable dual y usos de las mismas |
| JP6441079B2 (ja) * | 2011-12-19 | 2018-12-19 | シンイミューン ゲーエムベーハー | 二重特異性抗体分子 |
| WO2013187495A1 (ja) * | 2012-06-14 | 2013-12-19 | 中外製薬株式会社 | 改変されたFc領域を含む抗原結合分子 |
| EP3126384B1 (en) * | 2014-04-01 | 2020-12-02 | Adimab, LLC | Multispecific antibody analogs comprising a common light chain, and methods of their preparation and use |
| WO2016166139A1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-10-20 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Bispecific fusion proteins for enhancing immune responses of lymphocytes against tumor cells |
-
2018
- 2018-07-31 AU AU2018309712A patent/AU2018309712A1/en active Pending
- 2018-07-31 WO PCT/US2018/044610 patent/WO2019028027A1/en active Application Filing
- 2018-07-31 CA CA3070986A patent/CA3070986A1/en active Pending
- 2018-07-31 CN CN201880062880.1A patent/CN111132698A/zh active Pending
- 2018-07-31 JP JP2020505208A patent/JP2020529410A/ja active Pending
- 2018-07-31 SG SG11202000632QA patent/SG11202000632QA/en unknown
- 2018-07-31 BR BR112020001972-0A patent/BR112020001972A2/pt unknown
- 2018-07-31 EA EA202090387A patent/EA202090387A1/ru unknown
- 2018-07-31 KR KR1020207005238A patent/KR20200033302A/ko not_active Application Discontinuation
- 2018-07-31 EP EP18840650.8A patent/EP3661554A4/en active Pending
- 2018-07-31 MX MX2020001257A patent/MX2020001257A/es unknown
- 2018-07-31 US US16/635,079 patent/US20200165344A1/en active Pending
- 2018-07-31 MA MA049769A patent/MA49769A/fr unknown
-
2020
- 2020-01-30 IL IL272374A patent/IL272374A/en unknown
- 2020-02-25 CO CONC2020/0001981A patent/CO2020001981A2/es unknown
-
2023
- 2023-05-01 JP JP2023075458A patent/JP2023106433A/ja active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011506406A (ja) * | 2007-12-14 | 2011-03-03 | ノボ・ノルデイスク・エー/エス | ヒトnkg2dに対する抗体とその使用 |
| JP2011521647A (ja) * | 2008-05-30 | 2011-07-28 | イムクローン・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 抗flt3抗体 |
| JP2013500721A (ja) * | 2009-07-29 | 2013-01-10 | アボット・ラボラトリーズ | 二重可変ドメイン免疫グロブリンおよびその使用 |
| JP2013515472A (ja) * | 2009-12-23 | 2013-05-09 | シュニムネ ゲーエムベーハー | 抗flt3抗体及びその使用方法 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, vol. 12, no. 11, JPN6021051696, 2016, pages 2790 - 2796, ISSN: 0004959289 * |
| ファルマシア, vol. 51, no. 5, JPN6021051695, 2015, pages 424 - 428, ISSN: 0004959290 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA202090387A1 (ru) | 2020-05-21 |
| US20200165344A1 (en) | 2020-05-28 |
| IL272374A (en) | 2020-03-31 |
| CN111132698A (zh) | 2020-05-08 |
| MA49769A (fr) | 2021-04-21 |
| EP3661554A4 (en) | 2021-04-21 |
| SG11202000632QA (en) | 2020-02-27 |
| BR112020001972A2 (pt) | 2020-08-04 |
| MX2020001257A (es) | 2020-08-17 |
| JP2023106433A (ja) | 2023-08-01 |
| AU2018309712A1 (en) | 2020-02-13 |
| WO2019028027A1 (en) | 2019-02-07 |
| CO2020001981A2 (es) | 2020-05-29 |
| CA3070986A1 (en) | 2019-02-07 |
| EP3661554A1 (en) | 2020-06-10 |
| KR20200033302A (ko) | 2020-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20210261668A1 (en) | Proteins binding nkg2d, cd16, and egfr, ccr4, or pd-l1 | |
| JP7431392B2 (ja) | NKG2D、CD16およびNectin4に結合するタンパク質 | |
| JP7257323B2 (ja) | Bcma、nkg2d及びcd16と結合するタンパク質 | |
| US20200157174A1 (en) | Proteins binding nkg2d, cd16 and ror1 or ror2 | |
| US20200277384A1 (en) | Proteins binding nkg2d, cd16, and c-type lectin-like molecule-1 (cll-1) | |
| JP2020508997A (ja) | Her2、NKG2DおよびCD16に結合するタンパク質 | |
| JP2023052214A (ja) | Cd33、nkg2d及びcd16と結合するタンパク質 | |
| JP2024012297A (ja) | Nkg2d、cd16、および腫瘍関連抗原に結合するタンパク質 | |
| JP2020529410A (ja) | Nkg2d、cd16及びflt3と結合するタンパク質 | |
| US20240018266A1 (en) | Proteins binding cd123, nkg2d and cd16 | |
| JP2023030174A (ja) | Nkg2d、cd16、および腫瘍関連抗原に結合するタンパク質 | |
| JP2022105121A (ja) | Psma、nkg2dおよびcd16に結合するタンパク質 | |
| JP2020510644A (ja) | Gd2、nkg2dおよびcd16に結合するタンパク質 | |
| JP2021523140A (ja) | Nkg2d、cd16、及び腫瘍関連抗原に結合するタンパク質 | |
| KR20240078657A (ko) | Bcma, nkg2d 및 cd16에 결합하는 단백질 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200701 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210729 |
|
| A524 | Written submission of copy of amendment under article 19 pct |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A524 Effective date: 20210729 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210729 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220608 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220621 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20220916 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220926 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20230110 |