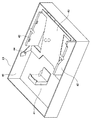JP6637685B2 - 画像形成装置 - Google Patents
画像形成装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6637685B2 JP6637685B2 JP2015129205A JP2015129205A JP6637685B2 JP 6637685 B2 JP6637685 B2 JP 6637685B2 JP 2015129205 A JP2015129205 A JP 2015129205A JP 2015129205 A JP2015129205 A JP 2015129205A JP 6637685 B2 JP6637685 B2 JP 6637685B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sheet
- unit
- sheets
- loading
- overload
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
筐体と、
シートが積載される積載手段と、
前記筐体からの前記積載手段の抜き挿しを検知する抜挿検知手段と、
前記積載手段に積載された前記シートを搬送する搬送手段と、
前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから搬送路の所定位置に前記シートが到着するまでの搬送時間を計時する計時手段と、
前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知してから、前記計時手段によって最初に計時された前記シートの搬送時間が過積載閾値を超えている場合、前記積載手段にシートが過積載されていると判定する過積載判定手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置が提供される。
[画像形成装置の構成]
図1を用いて画像形成装置100について説明する。本実施例での画像形成装置100は電子写真方式のプリンタであるが、本発明を適用可能な画像形成装置はインクジェット方式、熱転写方式など、他の画像形成方式を採用していてもよい。画像形成装置100は複写機や複合機、ファクシミリ装置として実現されてもよい。画像形成装置100は4つの画像形成部(ステーション)を有しており、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)のトナー画像を形成する。図1においては、4つの画像形成部にはそれぞれ色にちなんだ参照符号であるY、M、C、Kが付与されている。感光ドラム1は、感光体であり、かつ、像担持体であり、時計方向に所定の周速度(プロセススピード)で回転する。帯電ローラ2は感光ドラム1の表面を一様に帯電させる。光学走査装置9は画像信号に応じた光ビームを出力する。光ビームは感光ドラム1の表面に照射され、静電潜像を形成する。現像ローラ6はトナーを付着させて静電潜像を現像し、トナー画像を形成する。YMCKの各トナー画像は一次転写ローラ11によって中間転写ベルト12に重畳的に転写され、多色画像となる。
図2を用いてコントローラ50の機能について説明する。CPU51や記憶装置55に記憶されている制御プログラムを実行することで画像形成装置100の全体を統括的に制御する。記憶装置55はROMやRAMなどのメモリを有している。コントローラ50は操作部59から指定された画像形成モードにしたがって画像形成条件を設定する。画像形成条件とは、たとえば、シートSの搬送速度や定着装置18の定着温度などである。画像形成モードには、たとえば、普通紙に画像を形成する普通紙モード、厚紙に画像を形成する厚紙モード、封筒に文字を形成する封筒モードなどが含まれうる。コントローラ50は、各画像形成モードごとの画像形成条件を記憶装置55に保持しており、指定された画像形成モードに対応する画像形成条件を読み出す。
図6ないし図8を用いて給紙カセット23の構成について説明する。上述したように、給紙カセット23は、画像形成装置100の筐体101に対して抜挿自在である。図6に示すように、給紙カセット23はカセット桶40を有している。カセット桶40の内側にある底面には、シートSの搬送方向とその反対方向との両方向(前後方向と呼ばれてもよい)に移動自在な後端規制板41が設けられている。操作者はシートSのサイズに応じて後端規制板41を移動させる。後端規制板41はシートSの後端の位置を規制して揃える規制手段の一例である。これにより、複数のシートSがほぼ同じ位置から搬送を開始されるようになる。後端規制板41の位置は上述した位置センサ54によって検知される。カセット桶40の底面には、シートSの搬送方向に直交した方向(左右方向や幅方向と呼ばれてもよい)に移動自在な二つのサイド規制板42が設けられている。二つのサイド規制板42は、シートSの両端の位置を規制して揃える。中板43は給紙カセット23に設けられ、シートSが積載されるプレート部材であり、支点44を中心に回動する。
給紙カセット23にシートSが過積載された状態を詳しく説明する。ここでは、係止爪47の上にシートSが積載された過積載ケースと、係止爪47の下にシートSが無理やり積載された過積載ケースについて説明する
(係止爪47の上に積載されたケース)
図9に示すように、設計上の上限値を超えた高さまで多数のシートSを積載すると、一部のシートSは係止爪47の上に乗り上げてしまう。なお、上限値に相当する上限枚数はシートSの厚みによって変化する。この係止爪47の上に乗り上げてしまったいくつかのシートSは後端規制板41によって搬送方向の位置を規制されないため、搬送方向の上流側(つまり、搬送方向に対して逆方向)にずれてしまう。
給紙カセット23における過積載を判定する手順について詳しく説明する。上述したように過積載されたシートSaの搬送時間Tは正常に積載されたシートSの搬送時間Tよりも長くなってしまうが、遅延閾値Tmを超えるほどではない。そこで、図13に示すように、過積載閾値Tkを定義する。過積載閾値Tkは、許容範囲Xの上限値以上であり、かつ、遅延閾値Tm未満である。CPU51はシートセンサ52を用いて検知したシートSの搬送時間Tと過積載閾値Tkを比較することで過積載の有無を判定する。つまり、CPU51はシートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えると、当該シートSは過積載されたシートであると判定する。また、CPU51はシートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えていなければ、当該シートSは正常に積載されたシートであると判定する。このように搬送遅延と判定するほどは遅延していないようなシートSを過積載されたシートとしてCPU51は検知できるようになる。なお、CPU51は、画像形成ジョブを開始してから二枚目以降に搬送されるシートSの搬送時間Tが遅延閾値Tmを超えると、搬送遅延と判定するとともに、過積載と判定する。
(1)CPU51は常に過積載判定を実行せずに、実行条件が満たされたときに過積載判定を実行してもよい。実行条件はいくつ考えられる。操作者は給紙カセット23にシートSを積載するためには、画像形成装置100の筐体から給紙カセット23を抜き挿しする必要がある。よって、CPU51はカセットセンサ61が給紙カセット23の抜き挿しを検知した後で、最初に給紙されるシートSについて過積載判定を実行する。つまり、実行条件は、シートSが給紙カセット23の抜き挿しを検知した後で給紙される一枚目のシートSであることである。これは、シートSが過積載されている場合、必ず一枚目のシートSで過積載が検知され、一枚目のシートSで過積載が検知されないのに二枚目以降のシートSで初めて過積載が検知されることはないからである。このように、給紙カセット23を挿入した後の一枚目のシートSのみに過積載判定を適用することで過積載の判定精度が向上しよう。たとえば、常時、過積載判定を実行する制御では別の要因で搬送遅延が引き起こされたにもかかわらず過積載が誤検知されてしまうかもしれない。よって、実行条件が満たされたときにのみ過積載判定が実行されれば、より高い精度で過積載を検知できるようになろう。
本実施例の画像形成装置では、ローラ(接触部材)が搬送遅延を引き起こすほど摩耗してくると過積載していない場合でも500枚(本実施例では1カセット)の中でシートSの搬送時間が1回でも過積載閾値Tkを超えるという事象が、5回以上連続で発生するようになってくる。
図15は過積載判定を示すフローチャートである。操作部59またはホストコンピュータから画像形成の指示が入力されると、CPU51は以下の処理を実行する。
過積載に関するメッセージは操作部59に出力されてもよいが、通信装置58を介してネットワーク上のコンピュータ(保守会社のサーバなど)に送信されてもよい。たとえば、CPU51は、過積載が発生したことを示す過積載メッセージを、画像形成装置100について保守契約を結んでいる保守担当者(保守会社)のアドレスに電子メールとして送信してもよい。なお、電子メール以外の通信プロトコルを用いて過積載メッセージが保守会社のサーバに送信されてもよい。なお、過積載に関するメッセージが保守会社に送信される場合、操作部59には出力されなくてもよい。保守会社は、保守契約の一環として画像形成装置100のユーザーに対して過積載が発生したことを電子メールまたは口頭で伝えてもよい。また、保守会社は、シートSの上限積載量や正しい積載方法、封筒印刷の注意点などについてアドバイスしてもよい。
CPU51は過積載状態が解消すると、過積載メッセージの出力を停止または消去する。過積載メッセージの出力を停止または消去する条件を解消条件と呼ぶことにする。あるいは、CPU51は過積載状態が解消したことを示す解消メッセージを操作部59に表示したり、通信装置58を介して送信したりする。解消条件としては、給紙カセット23の抜き挿しが実行されたことをカセットセンサ61が検知したことであってもよい。また、図16に示すように、過積載メッセージ(過積載情報)が出力されている状態で、シートSの搬送時間Tが過積載閾値Tk以下になると、CPU51は過積載メッセージの出力を停止してもよい。過積載の程度は、シートSを搬送するたびに低下して行く。よって、シートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを下回ったのであれば、過積載状態が解消した可能性は高い。このように、シートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを下回ったことを解消条件として採用してもよい。
実施例1によれば搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えると、CPU51は過積載が発生したと判定する。ところで、係止爪47の下にシートSが積載されていても過積載となることがある。図17(A)が示すように、上限枚数を超えた枚数のシートSを係止爪47の下に無理やり押し込めると、係止爪47によってシートSの後端部は強く押さえつけられる。そのため、シートSに働く搬送抵抗は、過積載されていないシートSに働く搬送抵抗と比較して大きくなる。とりわけ、ピックアップローラ35がシートSを搬送できなくなるほど、搬送抵抗が大きくなることがある。CPU51は、給紙を開始してからの経過時間がジャム閾値Tjを超えてもシートSの先端がシートセンサ52により検知されないと、ジャムが発生したと判定する。
図18のフローチャートを用いて実施例2の過積載判定方法について説明する。図15と比較して、図18では、S2とS3との間にS10とS11が挿入されている。
図19(A)が示すように、過積載されたシートSの少なくとも一部が係止爪47の上に乗り上げてしまい、しかも搬送方向とは逆方向に大きくずれていることがある。図19(B)が示すように、ピックアップローラ35は最上位のシートSaに接していないため、シートSbがピックアップローラ35によって給紙されてしまう。図19(C)が示すように、シートSbとともにシートSaも搬送されてしまい、シートSaがピックアップローラ35の給紙位置に到達する。この時点でシートSbはすでにフィードローラ24のニップ部に到達している。よって、図19(D)が示すように、シートSaとシートSbはその後も搬送され続ける。この現象は連れ重送と呼ばれる。CPU51によって計時される搬送時間Tは、給紙を開始したタイミングからフラグ49にシートSbが到達しタイミングまでの時間である。したがって、この搬送時間Tが許容範囲X内の時間となってしまうことがある。なぜなら、シートSbは正規の位置から搬送されているからである。よって、連れ重送が発生するケースでは、搬送時間Tに基づいて正確に過積載を判定できなくなってしまう。
CPU51は、予め指定されたサイズとシートセンサ52を用いて実測されたサイズとが異なっているときに連れ重送が発生していることを判別できる。そこで、CPU51は、位置センサ54によって検知された後端規制板41の位置に対応するサイズに対して、シートセンサ52を用いて取得されたシートSのサイズが大きいときに、過積載が発生していると判定する。
図21(B)が示すように、後端規制板41がシートSの後端よりも後方にずれて位置決めされてしまうと、シートセンサ52を用いて求めたシートサイズLaと位置センサ54を用いて求めたシートサイズLbとが一致してしまうことがある。この場合、CPU51は、シートサイズLa、Lbから過積載を検知できなくなってしまう。
図22を用いてCPU51の機能を説明する。図4やS2を用いて説明したように、計時部70はモータ57やピックアップローラ35がシートSの搬送を開始してから搬送路の所定位置にシートSが到着するまでの搬送時間Tを計時する。S4などで説明したように判定部62はカセットセンサ61が給紙カセット23の抜き挿しを検知してから最初に搬送されるシートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えているかどうかを判定してもよい。判定部62は搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えているかどうかに基づき給紙カセット23にシートSが過積載されているかどうかを判定する。画像形成制御部63は、搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えていなければ画像形成部を制御して当該シートSに画像を形成する。画像形成制御部63は、シートSの搬送時間Tが過積載閾値Tkを超えていれば画像形成部を制御して当該シートSに画像を形成しない。このようにシートSの束の高さを計測するセンサを用いずに、シートの搬送時間に着目することでシートの過積載を従来よりも精度よく検知することが可能となる。
Claims (25)
- 筐体と、
シートが積載される積載手段と、
前記筐体からの前記積載手段の抜き挿しを検知する抜挿検知手段と、
前記積載手段に積載された前記シートを搬送する搬送手段と、
前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから搬送路の所定位置に前記シートが到着するまでの搬送時間を計時する計時手段と、
前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知してから、前記計時手段によって最初に計時された前記シートの搬送時間が過積載閾値を超えている場合、前記積載手段にシートが過積載されていると判定する過積載判定手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。 - 前記シートの搬送時間が、画像形成を停止して前記シートを排出するための搬送遅延閾値を超えているかどうかに基づいて前記シートに搬送遅延が発生したことを検知する検知手段をさらに有し、
前記過積載閾値は前記搬送遅延閾値と同じであることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 筐体と、
シートが積載される積載手段と、
前記筐体からの前記積載手段の抜き挿しを検知する抜挿検知手段と、
前記積載手段に積載された前記シートを搬送する搬送手段と、
前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから搬送路の所定位置に前記シートが到着するまでの搬送時間を計時する計時手段と、
前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知してから、前記計時手段によって最初に計時された前記シートの搬送時間が過積載閾値を超えている場合、前記積載手段にシートが過積載されていると判定する過積載判定手段と、を有し、正常な動作を保証する最大の積載高さまたは積載枚数が規定されている画像形成装置において、
前記積載手段に積載されているシートの積載度合判定手段を有し、
前記積載度合判定手段で判定された積載度合が前記積載高さまたは積載枚数に対して所定の範囲内にある積載容量であると判定された場合、前記過積載判定手段によって前記積載手段にシートが過積載されているかの判定を実行することを特徴とする画像形成装置。 - 前記積載高さまたは積載枚数に対して所定の範囲内とは、前記積載度合判定手段が前記積載高さまたは積載枚数を判定でき得る精度のばらつき範囲内である
ことを特徴とする請求項3記載の画像形成装置。 - 前記積載手段に設けられ、前記シートが積載されるプレート部材と、
前記プレート部材に積載されたシートが前記搬送手段に接触するよう、前記プレート部材を上昇させる上昇手段と、
前記プレート部材の上昇に要する上昇時間を測定する測定手段と、
を有し、
前記プレート部材は、前記積載手段が前記画像形成装置の外に抜き出されると最低部まで下降するものであり、
前記積載度合判定手段は、前記上昇時間が上昇閾値未満であるときに、積載度合が前記積載高さまたは積載枚数に対して所定の範囲内にある積載容量であると判定して、前記過積載判定手段によって前記積載手段にシートが過積載されているかどうかを判定することを特徴とする請求項3ないし4のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 前記プレート部材に積載されたシートの表面が前記上昇手段によって所定の高さへ上昇したかどうかを検知する面検知手段をさらに有し、
前記上昇手段は、前記プレート部材に積載されたシートの表面が前記所定の高さへ上昇すると、前記プレート部材の上昇を停止させることを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。 - 前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから前記計時手段が所定の時間を計時し終えるまでの間に前記シートが搬送路の前記所定位置に到着しないと、前記搬送時間に前記過積載閾値よりも大きな値を代入することで、前記積載手段にシートが過積載されていると前記過積載判定手段に判定させる代入手段をさらに有することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 筐体と、
シートが積載される積載手段と、
前記筐体からの前記積載手段の抜き挿しを検知する抜挿検知手段と、
前記積載手段に積載された前記シートを搬送する搬送手段と、
前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから搬送路の所定位置に前記シートが到着するまでの搬送時間を計時する計時手段と、
前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知してから、前記計時手段によって最初に計時された前記シートの搬送時間が過積載閾値を超えている場合、前記積載手段にシートが過積載されていると判定する過積載判定手段と、
前記積載手段に積載されるシートの搬送方向に移動自在であり、当該搬送方向におけるシートの後端の位置を規制する規制手段と、
前記規制手段の位置を検知する位置検知手段と、
を有し、
前記過積載判定手段は、前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置が前記積載手段に積載されたシートのサイズに対応していれば、前記過積載判定手段によって前記積載手段にシートが過積載されているかどうかを判定し、前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置が前記積載手段に積載されたシートのサイズに対応していなければ、前記過積載判定手段による前記積載手段にシートが過積載されているかどうかの判定を行わないことを特徴とする画像形成装置。 - 前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置をシートのサイズに変換する変換手段をさらに有し、
前記過積載判定手段は、前記搬送手段により搬送されるシートのサイズと前記規制手段の位置から求められたシートのサイズとが一致しているときに前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置が前記積載手段に積載されたシートのサイズに対応している判定し、前記搬送手段により搬送されるシートのサイズと前記規制手段の位置から求められたシートのサイズとが一致していないときに前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置が前記積載手段に積載されたシートのサイズに対応していないと判定することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。 - 前記搬送手段により搬送されるシートのサイズを計測する計測手段をさらに有し、
前記過積載判定手段は前記計測手段により計測されたシートのサイズと前記規制手段の位置から求められたシートのサイズとを比較することを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。 - 前記搬送手段により搬送されるシートのサイズを入力する入力手段をさらに有し、
前記過積載判定手段は前記入力手段により入力されたシートのサイズと前記規制手段の位置から求められたシートのサイズとを比較することを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。 - 前記積載手段に積載されるシートの搬送方向に移動自在であり、当該搬送方向におけるシートの後端の位置を規制する規制手段と、
前記規制手段の位置を検知する位置検知手段と、
前記位置検知手段により検知された前記規制手段の位置をシートのサイズに変換する変換手段と、
をさらに有し、
前記過積載判定手段は、前記搬送手段により搬送されるシートのサイズが前記規制手段の位置から前記変換手段によって求められたシートのサイズより大きいときには、前記搬送時間が前記過積載閾値を超えていなくても、前記積載手段にシートが過積載されていると判定することを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 前記搬送手段により搬送されるシートのサイズを計測する計測手段、
をさらに有し、
前記過積載判定手段は、前記計測手段により計測されたシートのサイズが前記規制手段の位置から前記変換手段により求められたシートのサイズより大きいときには、前記搬送時間が前記過積載閾値を超えていなくても、前記積載手段にシートが過積載されていると判定することを特徴とする請求項12に記載の画像形成装置。 - 前記規制手段にはシート束の高さを規制する係止爪が設けられていることを特徴とする請求項8ないし13のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記搬送手段が劣化しているかどうかを判別する判別手段をさらに有し、
前記過積載判定手段は、前記搬送手段が劣化していなければ前記積載手段にシートが過積載されているかどうかを判定し、前記搬送手段が劣化していれば前記積載手段にシートが過積載されているかどうかを判定しないことを特徴とする請求項1ないし14のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 前記判別手段は、第一の所定枚数の中で、搬送時間が一回でも前記過積載閾値を超えたものが発生する事象が、所定回数連続で発生した場合、前記搬送手段が劣化していると判定することを特徴とする請求項15に記載の画像形成装置。
- 前記過積載判定手段は、前記判別手段によって前記搬送手段が劣化していると判定された後に、搬送時間が第二の所定枚数以上にわたり連続で前記過積載閾値を超えていない場合は、前記積載手段にシートが過積載されているかどうかの判定を再開することを特徴とする請求項15または16に記載の画像形成装置。
- 前記過積載判定手段が前記積載手段にシートが過積載されていると判定すると、シートが過積載されていることを示す過積載情報を出力する出力手段をさらに有することを特徴とする請求項1ないし17のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記過積載判定手段が前記積載手段にシートが過積載されていると判定した後で前記積載手段におけるシートの過積載が解消したと判定すると、前記出力手段は、前記過積載情報の出力を停止するように構成されていることを特徴とする請求項18に記載の画像形成装置。
- 前記過積載判定手段が前記積載手段にシートが過積載されていると判定した後で前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知すると、前記出力手段は、前記過積載情報の出力を停止するように構成されていることを特徴とする請求項18に記載の画像形成装置。
- 前記過積載判定手段が前記積載手段にシートが過積載されていると判定した後で、前記搬送時間が前記過積載閾値を超えなくなると、前記出力手段は、前記過積載情報の出力を停止するように構成されていることを特徴とする請求項18に記載の画像形成装置。
- 前記出力手段は、前記過積載情報を表示する表示手段であることを特徴とする請求項18ないし21のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記出力手段は、前記過積載情報を含むメッセージを送信する送信手段であることを特徴とする請求項18ないし21のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記送信手段は、前記画像形成装置の保守担当者のアドレスに前記メッセージを送信するように構成されていることを特徴とする請求項23に記載の画像形成装置。
- 筐体と、
シートが積載される積載手段と、
前記筐体からの前記積載手段の抜き挿しを検知する抜挿検知手段と、
前記積載手段に積載された前記シートを搬送する搬送手段と、
前記搬送手段が前記シートの搬送を開始してから搬送路の所定位置に前記シートが到着するまでの搬送時間を計時する計時手段と、
前記積載手段にシートが過積載されていることを示す情報を出力する出力手段と、前記抜挿検知手段が前記積載手段の抜き挿しを検知してから、前記計時手段によって最初に計時された前記シートの搬送時間が第一閾値を超えると、前記出力手段に前記情報を出力させ、かつ、前記搬送手段による前記シートの搬送を継続させ、前記シートの搬送時間が前記第一閾値よりも大きな第二閾値を超えると、画像形成を停止させ前記搬送手段によって前記シートを排出させるか、または前記搬送手段による前記シートの搬送を停止させる制御手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015129205A JP6637685B2 (ja) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 画像形成装置 |
| US15/184,026 US9802778B2 (en) | 2015-06-26 | 2016-06-16 | Image forming apparatus for forming image on sheet |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015129205A JP6637685B2 (ja) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 画像形成装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2017013910A JP2017013910A (ja) | 2017-01-19 |
| JP2017013910A5 JP2017013910A5 (ja) | 2018-07-26 |
| JP6637685B2 true JP6637685B2 (ja) | 2020-01-29 |
Family
ID=57829818
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2015129205A Active JP6637685B2 (ja) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 画像形成装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6637685B2 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7100520B2 (ja) * | 2018-07-18 | 2022-07-13 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| CN113401686A (zh) * | 2020-03-17 | 2021-09-17 | 柯尼卡美能达株式会社 | 给纸装置以及图像形成装置 |
-
2015
- 2015-06-26 JP JP2015129205A patent/JP6637685B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2017013910A (ja) | 2017-01-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8960668B2 (en) | Sheet-discharge apparatus, sheet processing apparatus, and image forming apparatus | |
| US11016429B2 (en) | Image forming device that selects feeding mode according to type of insertion sheet | |
| JP5377684B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP5928532B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6493289B2 (ja) | シート積載装置及びそれを備えたシート後処理装置並びに画像形成装置 | |
| US10308452B2 (en) | Image forming apparatus | |
| US11186104B2 (en) | Image forming system | |
| US9296581B2 (en) | Document feeder and image forming apparatus | |
| JP6637685B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| US11142418B2 (en) | Image forming device, paper feeding mechanism deterioration determining method and non-transitory recording medium | |
| US10077164B2 (en) | Sheet discharge device and image forming apparatus | |
| US9802778B2 (en) | Image forming apparatus for forming image on sheet | |
| JP2018100181A (ja) | 画像形成装置 | |
| US9708149B2 (en) | Sheet processing apparatus including stacking tray on which sheets are stacked, and image forming system | |
| JP5982413B2 (ja) | 後処理装置、画像形成装置および画像形成システム | |
| JP2011235985A (ja) | 画像形成装置 | |
| US10924619B2 (en) | Image forming system | |
| JP7334451B2 (ja) | 用紙積載装置及び画像形成システム | |
| US20200310319A1 (en) | Image forming system | |
| JP7222208B2 (ja) | 画像形成装置、給紙装置及びプログラム | |
| JP6565817B2 (ja) | シート給送装置、画像形成装置及びシート給送方法 | |
| JP7134736B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6660108B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2017165498A (ja) | 自動原稿送り装置及び画像形成装置 | |
| JP6659153B2 (ja) | 画像形成装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180613 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180613 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20190320 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190408 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190604 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191122 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191223 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6637685 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |