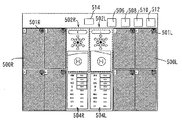JP5870866B2 - 角膜内皮細胞撮影装置 - Google Patents
角膜内皮細胞撮影装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5870866B2 JP5870866B2 JP2012156474A JP2012156474A JP5870866B2 JP 5870866 B2 JP5870866 B2 JP 5870866B2 JP 2012156474 A JP2012156474 A JP 2012156474A JP 2012156474 A JP2012156474 A JP 2012156474A JP 5870866 B2 JP5870866 B2 JP 5870866B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- image
- endothelial
- cornea
- fixation
- eye
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims description 146
- 210000000399 corneal endothelial cell Anatomy 0.000 title claims description 23
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 186
- 210000004087 cornea Anatomy 0.000 claims description 119
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 69
- 210000002889 endothelial cell Anatomy 0.000 claims description 61
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims description 49
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 claims description 37
- 210000003038 endothelium Anatomy 0.000 claims description 37
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 26
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000003511 endothelial effect Effects 0.000 description 203
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 55
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 19
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 description 12
- 238000012351 Integrated analysis Methods 0.000 description 10
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 10
- 230000008859 change Effects 0.000 description 8
- 101000581402 Homo sapiens Melanin-concentrating hormone receptor 1 Proteins 0.000 description 7
- 102000037055 SLC1 Human genes 0.000 description 7
- 102000037062 SLC2 Human genes 0.000 description 6
- 108091006209 SLC2 Proteins 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 4
- 210000000871 endothelium corneal Anatomy 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 206010062621 Corneal endotheliitis Diseases 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000004397 blinking Effects 0.000 description 1
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 1
- 210000000981 epithelium Anatomy 0.000 description 1
- 210000003560 epithelium corneal Anatomy 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/0016—Operational features thereof
- A61B3/0041—Operational features thereof characterised by display arrangements
- A61B3/0058—Operational features thereof characterised by display arrangements for multiple images
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/14—Arrangements specially adapted for eye photography
Description
被検眼の角膜に向けて照明光を照射する照明光学系と、角膜内皮細胞を含む前記角膜からの反射光を受光する光検出器を有する受光光学系と、を有し、被検眼角膜の内皮細胞を撮影する角膜内皮細胞撮影装置であって、
被検眼角膜上における内皮細胞の撮影位置を上下左右方向に関して変更するための撮影位置変更手段と、
内皮細胞画像を処理して被検眼の内皮細胞に関する解析結果を取得する画像処理手段と、
被検眼角膜上の異なる位置にて撮影された複数の内皮細胞画像をモニタ上に同時に表示すると共に、前記画像処理手段によって取得された前記モニタ上の各内皮細胞画像に関する解析結果を同一画面上に表示する表示制御手段と、を備え、
前記表示制御手段は、前記モニタに表示された少なくとも2つの内皮細胞画像に基づく変動係数の平均、六角形細胞出現率の平均、最大面積、最小面積の少なくともいずれかをモニタ上に表示することを特徴とする。
(2)
被検眼の角膜に向けて照明光を照射する照明光学系と、角膜内皮細胞を含む前記角膜からの反射光を受光する光検出器を有する受光光学系と、を有し、被検眼角膜の内皮細胞を撮影する角膜内皮細胞撮影装置であって、
前記照明光学系及び前記受光光学系を有する撮影部との相対的な位置を調整するための駆動手段、又は被検眼の視線方向を変更するための固視光学系、の少なくともいずれかと、
内皮細胞画像を処理して被検眼の内皮細胞に関する解析結果を取得する画像処理手段と、
被検眼角膜上の異なる位置にて撮影された複数の内皮細胞画像をモニタ上に同時に表示すると共に、前記モニタに表示された少なくとも2つの内皮細胞画像に基づく変動係数の平均、六角形細胞出現率の平均、最大面積、最小面積の少なくともいずれかを、前記画像処理手段の解析結果に基づいて前記モニタ上に表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする。
本発明の本実施形態に係る装置100は、被検者眼Eの角膜部位の画像を撮影する装置に関し、照明光束を角膜に向けて照射する照明光学系10、角膜からの反射光束を光検出器により受光する受光光学系30を有し、眼の角膜部位を非接触にて撮影するための光学系を備える。このような光学系は、撮影部(装置本体)4内に配置される。
撮影部は、被検眼の固視方向を誘導するための固視光学系70、75を有する。固視光学系70は、撮影部の内部に配置される内部固視光学系である。内部固視光学系は、装置本体内に設けられた複数の固視灯を持ち、被検眼の固視方向を誘導する。固視光学系75は、撮影部4の被検者側筐体面に設けられる外部固視光学系である。
本装置は、眼Eに対する撮影部のアライメント状態を検出するためのアライメント検出センサ(80、85)を有する。アライメント検出センサは、眼Eに対するX、Y、Z方向の少なくともいずれかのアライメント状態を検出する。
演算制御器(以下、制御部)90は、装置の各構成の制御処理、画像処理、演算処理、等を行う。例えば、制御部90は、照明光学系、受光光学系、固視光学系、アライメント検出センサ、モニタに接続されている。
制御部90は、アライメント検出センサ(80、85)の検出結果がアライメント許容範囲から外れているとき、アライメント適正位置へ撮影部を移動させるように駆動部6を制御する(自動アライメント)。また、制御部90は、アライメント検出センサ(80、85)の検出結果がアライメント許容範囲から外れたとき、アライメント適正位置へ撮影部4を復帰させるように駆動部6を制御する(自動トラッキング)。制御部90は、XY方向のアライメント検出センサ(80)の検出結果に基づいて駆動部を制御し、眼Eに対して撮影部をXY方向に移動する。また、制御部90は、Z方向のアライメント検出センサ(80、85)の検出結果に基づいて駆動部6を制御し、眼Eに対して撮影部6をZ方向に移動する。
制御部90は、取得された少なくとも1つの内皮画像をモニタ95に表示する。解析処理を行うための所定のスイッチからの操作信号に基づいて、制御部90は、取得された内皮画像に基づいて眼Eの内皮細胞を解析する。例えば、制御部90は、撮像画像を形成する部分画像において内皮細胞の密度、細胞のサイズ、サイズのバラツキ、六角形細胞の数の少なくともいずれかを算出する。
統合表示として、制御部(表示制御部として機能する)90は、被検眼角膜上の異なる位置にて撮影された複数の内皮画像(内皮細胞画像)610a〜610iを、角膜中心部で撮影された内皮細胞画像を基準位置としてモニタ95上に同時に表示する(図14参照)。また、制御部90は、モニタ95上の各内皮細胞画像に関する解析結果630a、630bを同一画面上に表示する(図14参照)。
以下、複数の固視灯を用いて複数の撮影位置での内皮画像を連続的に取得するための連続撮影モードの流れについて説明する。
図10は固視位置設定画面の一例を示す図である。固視位置設定画面において、連続撮影モードにおける固視灯の点灯位置、点灯順が予め設定され、制御部90は、設定された固視灯の点灯位置及び点灯順に基づいて連続撮影モードでの固視位置を制御する。
制御部90は、照明光学系10及び受光光学系30を制御して、予め設定された第1の固視位置にて内皮画像を取得する。制御部90は、第1の固視位置にて取得された内皮画像の適否の判定結果に応じて、第2の固視位置に対応する固視灯を点灯させると共に第2の固視位置での画像取得を許可し、照明光学系10及び受光光学系30を制御して第2の固視位置にて内皮画像を取得する。内皮画像の適否の判定結果は、検者による入力、又は制御部90による画像判定によって得られる。
制御部90は、トリガ信号が発せられると、照明光源12を連続的に点灯させ、可視照明光による角膜内皮細胞像を二次元撮像素子44にて取得する。このとき、制御部90は、上皮反射光が検出され、内皮反射光が検出されない程度の光量にて光源12を発光させるのが好ましい。その後、制御部90は、光源12を点灯させると共に、駆動部6の駆動を制御して、撮影部4を眼Eに向かって前進させていく。この撮影部4のZ方向への移動中において、制御部90は、XY方向における自動アライメントの作動(撮像素子84を用いた追尾制御)を継続する。
制御部90は、撮像素子44からの出力画像を検出し、検出結果に基づいて光源12及び駆動部6を制御する。図6は撮像素子44からの出力画像に基づいて角膜画像の受光状態を判定する際の一例を示す図である。図6において、中央の白い矩形領域は、撮像素子44より前方に配置されたマスク35の開口部に対応し、左右の黒いハッチングは、マスク35の遮光部に対応する。
<連続撮影モード>
以下、連続撮影モードにおいて、複数の固視灯を用いて各位置での内皮細胞を連続的に取得する際の流れについて説明する。
以下に、撮影画像の判定結果に基づいて固視位置を切換える場合の例について説明する。制御部90は、取得された内皮画像の画質が所定範囲内か否かを画像処理により判定する。制御部90は、内皮画像の画質が所定範囲内であると判定された場合、固視光学系を制御し、固視灯の点灯位置を切換え、次の固視位置での内皮画像を取得する。一方、制御部90は、内皮画像の画質が所定範囲内でないと判定された場合、固視灯の点灯位置を切り換えず、内皮画像を再度取得する。制御部90は、例えば、内皮画像における輝度値の合計、内皮画像におけるエッジの数等を、内皮画像の画質を評価するための評価値として用いる。制御部90は、評価値が所定範囲内か否かを判定する。
シングル表示の画面では、内皮画像500R、500L、撮影眼表示502R、502L、解析値504R、504L、削除ボタン506、印刷ボタン508、撮影ボタン510が表示される。
マルチ表示では、左右眼毎にそれぞれ複数の内皮画像が表示され、解析値を表示するデータが選択される。なお、特段の説明がない限り、上記シングル表示での装置構成と同様である。
図13Bの撮影結果画面において統合表示ボタン514が押されると、統合表示画面(図14参照)に移行される。統合表示画面には、統合画像表示領域610、解析結果表示領域630、拡大画像表示領域640が形成されている。統合表示画面には、左右眼のいずれかに関連する内皮画像及び解析結果が出力され、左右眼切換ボタン650によって出力データが切り換えられる。
統合画像表示領域610には、角膜中心部での第1内皮画像610aが表示されている。角膜中心部とは異なる位置で撮影された複数の第2内皮画像610b〜610iが第1内皮画像610aを基準として配列されている。第2内皮画像610b〜610iは、例えば、角膜中心部の近傍領域における複数の位置にて撮影された第2内皮画像である。第1内皮画像610a、及び第2内皮画像610b〜610iは、例えば、図14に示すように、それぞれが離間されたレイアウトにてモニタ95上に表示される。これは、各内皮画像における細胞の状態を検者が把握しやするためである。なお、図15は、角膜中心部C、角膜中心部の近傍領域PAR、角膜周辺領域PERの角膜上の位置関係の一例を示す図であり、ハッチング部分が撮影領域に相当する。
解析結果表示領域630には、モニタ95上に表示された内皮画像の解析結果が表示される。解析結果の内訳は、例えば、図14に示すように、細胞数NUM、内皮細胞密度CD、変動係数CV、六角形細胞出現率HEXである。もちろん上記に限定されるものではなく、角膜内皮解析に用いられるパラメータであってもよい。パラメータとしては、細胞数NUM、内皮細胞密度CD、平均内皮面積AVG、標準偏差SD、変動係数CV、最大面積MAX、最小面積MIN、六角形細胞出現率HEX、などが考えられる。
6 駆動部
10 照明光学系
12 照明光源
30 撮像光学系
44 撮像素子
80 前眼部観察光学系
85 Zアライメント検出光学系
85a 投光光学系
85b 受光光学系
90 制御部
95 モニタ
Claims (2)
- 被検眼の角膜に向けて照明光を照射する照明光学系と、角膜内皮細胞を含む前記角膜からの反射光を受光する光検出器を有する受光光学系と、を有し、被検眼角膜の内皮細胞を撮影する角膜内皮細胞撮影装置であって、
被検眼角膜上における内皮細胞の撮影位置を上下左右方向に関して変更するための撮影位置変更手段と、
内皮細胞画像を処理して被検眼の内皮細胞に関する解析結果を取得する画像処理手段と、
被検眼角膜上の異なる位置にて撮影された複数の内皮細胞画像をモニタ上に同時に表示すると共に、前記画像処理手段によって取得された前記モニタ上の各内皮細胞画像に関する解析結果を同一画面上に表示する表示制御手段と、を備え、
前記表示制御手段は、前記モニタに表示された少なくとも2つの内皮細胞画像に基づく変動係数の平均、六角形細胞出現率の平均、最大面積、最小面積の少なくともいずれかをモニタ上に表示することを特徴とする角膜内皮細胞撮影装置。 - 被検眼の角膜に向けて照明光を照射する照明光学系と、角膜内皮細胞を含む前記角膜からの反射光を受光する光検出器を有する受光光学系と、を有し、被検眼角膜の内皮細胞を撮影する角膜内皮細胞撮影装置であって、
前記照明光学系及び前記受光光学系を有する撮影部との相対的な位置を調整するための駆動手段、又は被検眼の視線方向を変更するための固視光学系、の少なくともいずれかと、
内皮細胞画像を処理して被検眼の内皮細胞に関する解析結果を取得する画像処理手段と、
被検眼角膜上の異なる位置にて撮影された複数の内皮細胞画像をモニタ上に同時に表示すると共に、前記モニタに表示された少なくとも2つの内皮細胞画像に基づく変動係数の平均、六角形細胞出現率の平均、最大面積、最小面積の少なくともいずれかを、前記画像処理手段の解析結果に基づいて前記モニタ上に表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする角膜内皮細胞撮影装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012156474A JP5870866B2 (ja) | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 角膜内皮細胞撮影装置 |
| US13/940,431 US9049990B2 (en) | 2012-07-12 | 2013-07-12 | Corneal endothelial cell photographing apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012156474A JP5870866B2 (ja) | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 角膜内皮細胞撮影装置 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2015018925A Division JP5807727B2 (ja) | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 角膜内皮細胞撮影装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014018226A JP2014018226A (ja) | 2014-02-03 |
| JP2014018226A5 JP2014018226A5 (ja) | 2015-03-26 |
| JP5870866B2 true JP5870866B2 (ja) | 2016-03-01 |
Family
ID=49913739
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012156474A Active JP5870866B2 (ja) | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 角膜内皮細胞撮影装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9049990B2 (ja) |
| JP (1) | JP5870866B2 (ja) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6464569B2 (ja) | 2014-05-19 | 2019-02-06 | 株式会社ニデック | 角膜内皮細胞解析プログラム |
| JP2016083240A (ja) * | 2014-10-27 | 2016-05-19 | 株式会社トーメーコーポレーション | 眼科装置 |
| JP6636188B2 (ja) * | 2019-01-09 | 2020-01-29 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及び、コンピュータプログラム |
| JP7186888B2 (ja) * | 2019-09-11 | 2022-12-09 | 株式会社トプコン | 角膜内皮細胞撮影装置、その制御方法、及びプログラム |
| JP6732093B2 (ja) * | 2019-12-18 | 2020-07-29 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及び、コンピュータプログラム |
| JP7422403B2 (ja) | 2020-12-28 | 2024-01-26 | 株式会社コーナン・メディカル | 眼科用撮影装置 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2675962B2 (ja) * | 1993-04-28 | 1997-11-12 | 株式会社トプコン | 眼科装置 |
| JP2580467B2 (ja) * | 1993-05-26 | 1997-02-12 | 株式会社トプコン | 角膜内皮細胞撮影装置 |
| JP3897864B2 (ja) * | 1997-08-29 | 2007-03-28 | 株式会社トプコン | 眼科装置 |
| JP3469872B2 (ja) * | 2000-12-27 | 2003-11-25 | 株式会社コーナン・メディカル | 角膜内皮細胞解析システム |
| JP5643000B2 (ja) | 2010-05-28 | 2014-12-17 | 株式会社ニデック | 眼科装置 |
| JP5845608B2 (ja) * | 2011-03-31 | 2016-01-20 | 株式会社ニデック | 眼科撮影装置 |
| US9039176B2 (en) * | 2011-03-31 | 2015-05-26 | Nidek Co., Ltd. | Corneal endothelial cell photographing apparatus |
-
2012
- 2012-07-12 JP JP2012156474A patent/JP5870866B2/ja active Active
-
2013
- 2013-07-12 US US13/940,431 patent/US9049990B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20140016094A1 (en) | 2014-01-16 |
| JP2014018226A (ja) | 2014-02-03 |
| US9049990B2 (en) | 2015-06-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3784247B2 (ja) | 眼底カメラ | |
| US7695139B2 (en) | Alignment method for ophthalmic measurement apparatus and alignment device of the same | |
| JP5870866B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5772117B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |
| JP5776609B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5892409B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5862142B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP4916917B2 (ja) | 眼底カメラ | |
| JP5879825B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP2016158721A (ja) | 眼科装置 | |
| JP6008023B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5690190B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5628078B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP4774305B2 (ja) | 眼底カメラ | |
| JP4469205B2 (ja) | 眼科装置 | |
| JP5807727B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| CN104224110A (zh) | 眼科设备和眼科设备的控制方法 | |
| JP5643000B2 (ja) | 眼科装置 | |
| JP5871089B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP5317049B2 (ja) | 眼底カメラ | |
| JP5842477B2 (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 | |
| JP6098094B2 (ja) | 眼科装置 | |
| JP7429435B2 (ja) | 角膜内皮撮像装置 | |
| JP5587480B2 (ja) | 眼底カメラ | |
| JP2014079378A (ja) | 角膜内皮細胞撮影装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150205 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150205 |
|
| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20150205 |
|
| A975 | Report on accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20150303 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150310 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150511 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150804 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151005 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20151215 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20151228 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5870866 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |