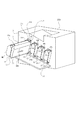JP5528092B2 - プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 - Google Patents
プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5528092B2 JP5528092B2 JP2009290111A JP2009290111A JP5528092B2 JP 5528092 B2 JP5528092 B2 JP 5528092B2 JP 2009290111 A JP2009290111 A JP 2009290111A JP 2009290111 A JP2009290111 A JP 2009290111A JP 5528092 B2 JP5528092 B2 JP 5528092B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- main body
- process cartridge
- cartridge
- unit
- image forming
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Electrophotography Configuration And Component (AREA)
Description
本発明の目的は、プロセスカートリッジを装置本体へ安定した状態で装着することのできるプロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置を提供することにある。
〔第1実施形態〕
本発明の第1実施形態に係るプロセスカートリッジ(以下「カートリッジ」という)及びカラー電子写真画像形成装置(以下「画像形成装置」という)の実施形態について、図を用いて説明する。
まず画像形成装置の全体構成について、図2及び図4を用いて説明する。図2は本実施例における画像形成装置の概略図、図4はカートリッジ7の装置本体100aへの装着前の状態を説明する斜視図である。図2に示す画像形成装置100は、水平方向に対して傾斜して並設した4個のカートリッジを備えている。各カートリッジは独立に画像形成装置100の装置本体100aに着脱可能である。ここで、装置本体100aとは、画像形成装置100の構成からカートリッジを除いた構成である。図4に示すように、装置本体100aはカートリッジの装着手段である装着部22を有する。そして、前記装着部22に装着されたカートリッジ7(7a〜7d)は、夫々1個の感光体ドラム1(1a〜1d)を備えている。
次に本実施形態のカートリッジについて、図3を用いて説明する。図3はトナーtを収納したカートリッジ7の主断面である。尚、イエロー色のトナーtを収納したカートリッジ7a、マゼンタ色のトナーtを収納したカートリッジ7b、シアン色のトナーtを収納したカートリッジ7c、ブラック色のトナーtを収納したカートリッジ7dは同一構成である。
次に本実施形態のカートリッジ7を装置本体100aへ取り外し可能に装着する構成について図4から図7を用いて説明する。
次に本実施形態のカートリッジの装置本体への位置決め構成及び押圧機構について図1と図8及び図9を用いて説明する。
図7に示すように、本体100aには装着方向下流側に側板82、上流側に側板92がそれぞれ備えられている。側板92にはカートリッジ7を取り外し可能に装着する装着部22が設けられている。カートリッジ7はこの装着部22を通して本体100aに挿入される。そして、前述した上側装着ガイド80、下側装着ガイド81に沿って矢印F方向に装着される。
次に、カートリッジを画像形成装置本体に対して着脱〜位置決めされるまでの動作について図10から図16を用いて説明する。
カートリッジ7を更に挿入させていくと、装着方向下流側においては、図13(a)、図14(a)に示すように、カートリッジ7の下流側の軸受40に設けられた押し退け部40cの傾斜面40eが、被押し退け部83cの傾斜面83eに当接する(待機位置)。そしてカートリッジ7の挿入に従って押圧部材83は除々に押し下げられ、図13(b)のように、押し退け部40cの凸部40dと被押し退け部83cの凸部83dとが当接する。これによって、押圧部材83は矢印X方向に移動して退避する(退避位置)。
装着方向上流側も前述した下流側と同様に、カートリッジを挿入させていく。すると、図15(a)、図16(a)に示すように、カートリッジ7の上流側の軸受50に設けられた押し退け部50cの傾斜面50eが、被押し退け部93cの傾斜面93eに当接する(待機位置)。そして、カートリッジ7の挿入に従って引き上げ部材93は除々に押し下げられる。そして、図15(b)に示すように、押し退け部50cの凸部50dと被押し退け部93cの凸部93dとが当接することによって、引き上げ部材93は矢印Y方向に移動して退避する(退避位置)。
7 カートリッジ
22 装着部
22a 装着部に設けられた突起形状部(第三本体ガイドである)
29 第一被ガイド部
30 第二被ガイド部
31 現像枠体
31b 被押圧部
33 規制部(第三被ガイド部)
40、50 軸受
80 装着上ガイド(第一本体ガイド部)
81 装着下ガイド(第二本体ガイド部)
90 現像離間ガイド
100 画像形成装置
Claims (6)
- 画像形成装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジにおいて、
感光体ドラムと、
前記感光体ドラムを回転可能に支持する第一ユニットと、
現像ローラと、
前記現像ローラを回転可能に支持する第二ユニットであって、前記現像ローラが前記感光体ドラムに当接する画像形成位置と、前記現像ローラを前記感光体ドラムから離間する非画像形成位置を取り得るよう前記第一ユニットに対して移動可能に支持された第二ユニットと、
前記プロセスカートリッジを前記感光体ドラムの軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記装置本体に設けられた現像離間ガイドと当接して前記第二ユニットを前記画像形成位置から前記非画像形成位置に移動させる力を受ける、前記第二ユニットに設けられた被押圧部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記装置本体に設けられた前記プロセスカートリッジの装着方向に沿って延びる第一本体ガイドにガイドされる、前記第一ユニットに設けられた第一被ガイド部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記装置本体に設けられた前記装着方向に沿って延びる第二本体ガイドにガイドされる、前記第一ユニットに設けられた第二被ガイド部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する途中では、前記装着方向において前記装置本体の上流側に設けられた第三本体ガイドにガイドされ、前記プロセスカートリッジが前記装置本体へ装着が完了した装着完了位置では、前記第三本体ガイドによる規制が解除される第三被ガイド部であって、前記プロセスカートリッジを装着する途中において前記被押圧部が前記現像離間ガイドと当接することによって前記第二ユニットが前記画像形成位置から前記非画像形成位置へ向けて移動する際も、前記第三本体ガイドによってガイドされることが可能な第三被ガイド部と、
を有するプロセスカートリッジ。 - 前記第一被ガイド部及び前記第三被ガイド部は、前記プロセスカートリッジを前記装置本体に装着した状態において前記プロセスカートリッジの上方に設けられ、前記第二被ガイド部及び前記被押圧部は、前記プロセスカートリッジを前記装置本体に装着した状態において前記プロセスカートリッジの下方に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のプロセスカートリッジ。
- 前記第三被ガイド部は、前記装着方向の下流側から上流側に向かうに従って、前記第二被ガイド部からの前記プロセスカートリッジを前記装置本体に装着した状態における鉛直方向における高さが高くなり、且つ、前記第二被ガイド部からの水平方向における距離が短くなる領域を有することを特徴とする請求項1又は2に記載のプロセスカートリッジ。
- 前記領域の前記軸線方向における長さは、前記被押圧部が前記現像離間ガイドと当接する前記軸線方向における長さと同じであることを特徴とする請求項3に記載のプロセスカートリッジ。
- 前記第一被ガイド部は、前記第一ユニットの前記装着方向において下流側に設けられ、前記第二被ガイド部は、前記第一ユニットの前記装着方向において上流側から下流側にわたって設けられていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のプロセスカートリッジ。
- プロセスカートリッジを着脱可能な、記録媒体に画像を形成する画像形成装置において、
(a)前記プロセスカートリッジの装着方向に沿って延びる第一本体ガイドと、
(b)前記装着方向に沿って延びる第二本体ガイドと、
(c)前記装着方向において前記画像形成装置の装置本体の上流側に設けられた第三本体ガイドと、
(d)現像離間ガイドと、
(e)感光体ドラムと、
前記感光体ドラムを回転可能に支持する第一ユニットと、
現像ローラと、
前記現像ローラを回転可能に支持する第二ユニットであって、前記現像ローラが前記感光体ドラムに当接する画像形成位置と、前記現像ローラを前記感光体ドラムから離間する非画像形成位置を取り得るよう前記第一ユニットに対して移動可能に支持された第二ユニットと、
前記プロセスカートリッジを前記感光体ドラムの軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記現像離間ガイドと当接して前記第二ユニットを前記画像形成位置から前記非画像形成位置に移動させる力を受ける、前記第二ユニットに設けられた被押圧部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記第一本体ガイドにガイドされる、前記第一ユニットに設けられた第一被ガイド部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する際に、前記第二本体ガイドにガイドされる、前記第一ユニットに設けられた第二被ガイド部と、
前記プロセスカートリッジを前記軸線方向に沿って前記装置本体へ装着する途中では、前記第三本体ガイドにガイドされ、前記プロセスカートリッジが前記装置本体へ装着が完了した装着完了位置では、前記第三本体ガイドによる規制が解除される第三被ガイド部であって、前記プロセスカートリッジを装着する途中において前記被押圧部が前記現像離間ガイドと当接することによって前記第二ユニットが前記画像形成位置から前記非画像形成位置へ向けて移動する際も、前記第三本体ガイドによってガイドされることが可能な第三被ガイド部と、
を有するプロセスカートリッジを取り外し可能に装着する為の装着部と、
(f)前記記録媒体を搬送する搬送手段と、
を有する画像形成装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009290111A JP5528092B2 (ja) | 2009-12-22 | 2009-12-22 | プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009290111A JP5528092B2 (ja) | 2009-12-22 | 2009-12-22 | プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2011133517A JP2011133517A (ja) | 2011-07-07 |
| JP2011133517A5 JP2011133517A5 (ja) | 2013-02-14 |
| JP5528092B2 true JP5528092B2 (ja) | 2014-06-25 |
Family
ID=44346360
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2009290111A Expired - Fee Related JP5528092B2 (ja) | 2009-12-22 | 2009-12-22 | プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5528092B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7226297B2 (ja) * | 2019-12-23 | 2023-02-21 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4709029B2 (ja) * | 2006-02-17 | 2011-06-22 | キヤノン株式会社 | 現像剤供給容器、プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 |
| JP4241865B2 (ja) * | 2006-12-08 | 2009-03-18 | キヤノン株式会社 | プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置 |
| JP5288769B2 (ja) * | 2006-12-11 | 2013-09-11 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |
| JP5024080B2 (ja) * | 2008-01-31 | 2012-09-12 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |
| JP4630932B2 (ja) * | 2008-05-27 | 2011-02-09 | キヤノン株式会社 | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |
-
2009
- 2009-12-22 JP JP2009290111A patent/JP5528092B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2011133517A (ja) | 2011-07-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4630932B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |
| JP4701266B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置 | |
| JP4148530B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置 | |
| JP4241865B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置 | |
| JP4971832B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| RU2442205C2 (ru) | Технологический картридж и устройство формирования изображения | |
| JP4095649B1 (ja) | 電子写真画像形成装置、プロセスカートリッジ、及び移動部材 | |
| KR101494500B1 (ko) | 화상 형성 장치 및 카트리지 | |
| JP5121573B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |
| JP5768530B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP6990822B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジおよび画像形成装置 | |
| JP5111238B2 (ja) | プロセスカートリッジ | |
| JP5528092B2 (ja) | プロセスカートリッジ、及び画像形成装置 | |
| US9164476B2 (en) | Toner cartridge having structure for minimizing deformation when gripped | |
| JP5084946B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP4685197B2 (ja) | 電子写真画像形成装置およびプロセスカートリッジ | |
| US20190302687A1 (en) | Image forming apparatus | |
| JP5171488B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP5247924B2 (ja) | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |
| CN110941167B (zh) | 成像设备和显影盒 | |
| JP6821350B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2009288335A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2022032445A (ja) | 画像形成装置 | |
| JP2020184008A (ja) | 画像形成装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121225 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121225 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131031 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131105 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140106 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140318 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140415 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 5528092 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |