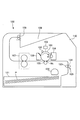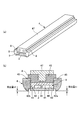JP2019128564A - 像加熱装置及びその製造方法 - Google Patents
像加熱装置及びその製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019128564A JP2019128564A JP2018012095A JP2018012095A JP2019128564A JP 2019128564 A JP2019128564 A JP 2019128564A JP 2018012095 A JP2018012095 A JP 2018012095A JP 2018012095 A JP2018012095 A JP 2018012095A JP 2019128564 A JP2019128564 A JP 2019128564A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heater
- protrusion
- flexible member
- support member
- disposed
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Fixing For Electrophotography (AREA)
Abstract
【課題】ヒータを支持する支持部材の突起部からヒータ面までの高さの精度を向上することのできる像加熱装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】支持部材4が、ヒータ3の可撓性部材と接触する面であるヒータ面31と交差する方向において回転体2側に突出した突起部42a、42bを有する像加熱装置107は、支持部材4は、ヒータ面31と交差する方向においてヒータ31に対し回転体2とは反対側にヒータ3と離隔して配置された基礎部43を有し、ヒータ面31と交差する方向におけるヒータ3と基礎部43との間に、支持部材4とは別部材である樹脂部材8が配置されて、ヒータ面31と交差する方向における突起部42a、42bの回転体2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている構成とする。
【選択図】図7
【解決手段】支持部材4が、ヒータ3の可撓性部材と接触する面であるヒータ面31と交差する方向において回転体2側に突出した突起部42a、42bを有する像加熱装置107は、支持部材4は、ヒータ面31と交差する方向においてヒータ31に対し回転体2とは反対側にヒータ3と離隔して配置された基礎部43を有し、ヒータ面31と交差する方向におけるヒータ3と基礎部43との間に、支持部材4とは別部材である樹脂部材8が配置されて、ヒータ面31と交差する方向における突起部42a、42bの回転体2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている構成とする。
【選択図】図7
Description
本発明は、電子写真方式や静電記録方式を用いたプリンタ、複写機、ファクシミリ装置などの画像形成装置にて用いられる像加熱装置、及びその像加熱装置の製造方法に関するものである。
従来、電子写真方式などを用いた画像形成装置では、画像を担持した記録材を加熱する像加熱装置として、例えば記録材上の未定着のトナー像を記録材に定着させる定着装置が用いられている。また、この定着装置として、オンデマンド性に優れたフィルム加熱方式の定着装置がある。
フィルム加熱方式の定着装置は、加熱源としてのヒータと、ヒータを支持する支持部材と、耐熱性の加熱フィルムと、加圧ローラと、を有する。支持部材に支持されたヒータと加圧ローラとで加熱フィルムが挟まれることで、加圧ローラと加熱フィルムとが接触するニップ部が形成される。そして、フィルム加熱方式の定着装置は、このニップ部で記録材を挟持して搬送することで、記録材上の未定着のトナー像を加熱及び加圧して記録材に定着させる。
特許文献1には、フィルム加熱方式の定着装置において、ニップ部における記録材搬送方向の下流側に突起部を設けることが開示されている。この突起部は、回転する加熱フィルムの内面がヒータのエッジとの接触で摩耗することを防止する役割を持っている。具体的には、加熱フィルムの内面がヒータのエッジに接触する前に突起部で加熱フィルムの内面をガイドしている。
しかしながら、上述のように支持部材に突起部を設ける場合、支持部材の突起部から、ヒータの加熱フィルムと接触する面であるヒータ面までの高さに、ばらつきが生じることがある。図15は、定着装置の一例におけるニップ部の近傍の記録材搬送方向の断面図である。突起部からヒータ面までの高さのばらつきは、突起部から、支持部材のヒータを支持する面であるヒータ支持面までの高さの公差と、ヒータの厚みの公差と、を足し合わせたものである。
上述のような突起部からヒータ面までの高さのばらつきが大きいと、特に、定着装置の高寿命化の観点から問題となることがある。具体的には、定着装置の高寿命化を実現する場合には、加熱フィルムの表面が記録材との摩擦力により徐々に摩耗することを抑える必要があるため、突起部による記録材に与える圧力のピークを低くすることが求められる。一方で、圧力のピークを低くするために突起部の高さを低くし過ぎると、加熱フィルムの内面がヒータのエッジと接触して摩耗してしまう。
このように、例えば、定着装置の高寿命化を実現するために、突起部からヒータ面までの高さの精度を向上することが求められる。しかし、突起部からヒータ支持面までの高さの精度とヒータの厚みの精度とを厳しく管理して、突起部からヒータ面までの高さの精度を向上することには限界がある。
したがって、本発明の目的は、ヒータを支持する支持部材の突起部からヒータ面までの高さの精度を向上することのできる像加熱装置及びその製造方法を提供することである。
上記目的は本発明に係る像加熱装置及びその製造方法にて達成される。要約すれば、本発明は、無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置において、前記支持部材は、前記ヒータ面と交差する方向において前記ヒータに対し前記回転体とは反対側に前記ヒータと離隔して配置された基礎部を有し、前記ヒータ面と交差する方向における前記ヒータと前記基礎部との間に、前記支持部材とは別部材である樹脂部材が配置されて、前記ヒータ面と交差する方向における前記突起部の前記回転体側の先端と前記ヒータ面との間の距離が決められていることを特徴とする像加熱装置である。
本発明の他の態様によると、無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータを覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置する工程と、前記ヒータと前記支持部材との間に樹脂材料を充填する工程と、を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法が提供される。
本発明の他の態様によると、無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、前記ヒータの前記ヒータ面とは反対側の側面であるヒータ上面に樹脂材料を塗布する工程と、前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータを覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置し、前記支持部材と前記ヒータとの間で前記樹脂材料を挟み込む工程と、を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法が提供される。
本発明の他の態様によると、無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、前記ヒータの前記ヒータ面とは反対側の面であるヒータ上面にスペーサ部材を配置する工程と、前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータ及び前記スペーサ部材を覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置する工程と、前記ヒータと前記スペーサ部材との間に樹脂材料を充填する工程と、を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法が提供される。
以上説明したように、本発明によれば、ヒータを支持する支持部材の突起部からヒータ面までの高さの精度を向上することができる。
以下、本発明に係る像加熱装置及びその製造方法を図面に則して更に詳しく説明する。
[実施例1]
1.画像形成装置の全体的な構成及び動作
図1は、本実施例の像加熱装置としての定着装置107を備えた画像形成装置100の概略断面図である。本実施例では、画像形成装置100は、電子写真方式を用いたレーザビームプリンタである。
1.画像形成装置の全体的な構成及び動作
図1は、本実施例の像加熱装置としての定着装置107を備えた画像形成装置100の概略断面図である。本実施例では、画像形成装置100は、電子写真方式を用いたレーザビームプリンタである。
画像形成装置100は、トナー像を担持する像担持体としての、回転可能なドラム型(円筒形)の感光体(電子写真感光体)である感光ドラム101を有する。感光ドラム101は、図中矢印R1方向(時計回り)に回転駆動される。回転する感光ドラム101の表面は、帯電手段としてのローラ型の帯電部材(接触帯電部材)である帯電ローラ102によって、所定の極性(本実施例では負極性)の所定の電位に帯電処理される。帯電処理された感光ドラム101の表面は、露光手段としての露光装置(レーザスキャナ)103によって、画像情報に基づいてレーザービームが照射されて走査露光され、感光ドラム101上に静電像(静電潜像)が形成される。感光ドラム101上に形成された静電像は、現像手段としての現像装置104によって現像剤としてのトナーが供給されて現像(可視化)され、感光ドラム101上にトナー像が形成される。
感光ドラム101に対向して、転写手段としてのローラ型の転写部材である転写ローラ105が配置されている。転写ローラ105は、感光ドラム101に向けて押圧され、感光ドラム101と転写ローラ105とが接触する転写部(転写ニップ部)Ntを形成する。感光ドラム101上に形成されたトナー像は、転写部Ntにおいて、感光ドラム101と転写ローラ105とに挟持されて搬送される紙などの記録材P上に転写される。記録材Pは、カセット121内に積載されており、給送ローラ122によって最上位の記録材Pから1枚ずつピックアップされ、レジストローラ123とレジストコロ124とで形成されるレジスト部125へと送られる。記録材Pは、レジスト部125で搬送方向を揃えられた後、感光ドラム101上のトナー像とタイミングが合わされて転写部Ntへと搬送される。転写工程において記録材Pに転写されずに感光ドラム101上に残留したトナー(転写残トナー)は、クリーニング手段としてのクリーニング装置106によって感光ドラム101上から除去されて回収される。
トナー像が転写された記録材Pは、像加熱装置としての定着装置107へと搬送される。定着装置107は、未定着のトナー像を担持した記録材Pを加熱及び加圧することで、トナー像を記録材Pに定着(溶融、固着)させる。定着装置107については、後述して更に詳しく説明する。定着装置107を通過してトナー像が定着された記録材Pは、排出ローラ対108によって、画像形成装置100の装置本体110の上部に設けられた記録材積載部109上に排出(出力)される。
2.定着装置の概略構成
次に、本実施例の定着装置107について説明する。なお、以下の説明において、定着装置107及び定着装置107を構成する部材に関して、「長手方向」とは、記録材Pの搬送方向(「記録材搬送方向」)と略直交する方向である。図2(a)は、定着装置107の記録材搬送方向の断面図であり、図2(b)は、定着装置107のニップ部の近傍の記録材搬送方向の拡大断面図である。また、図3は、定着装置107の長手方向の断面図である。
次に、本実施例の定着装置107について説明する。なお、以下の説明において、定着装置107及び定着装置107を構成する部材に関して、「長手方向」とは、記録材Pの搬送方向(「記録材搬送方向」)と略直交する方向である。図2(a)は、定着装置107の記録材搬送方向の断面図であり、図2(b)は、定着装置107のニップ部の近傍の記録材搬送方向の拡大断面図である。また、図3は、定着装置107の長手方向の断面図である。
本実施例の定着装置107は、加熱回転体としての無端状(筒状)の可撓性部材で構成された加熱フィルム1と、加圧回転体としての加圧ローラ2と、加熱体としてのヒータ3と、支持部材としてのヒータホルダ4と、を有する。加圧ローラ2は、軸部(心金)2aの外周に耐熱性弾性体層2bが形成されて構成されている。本実施例の定着装置107は、加圧ローラ2を回転駆動して加熱フィルム1を加圧ローラ2の搬送力により回転させる、加圧ローラ駆動方式・フィルム加熱方式の像加熱装置である。
ヒータ3は、ヒータホルダ4によって支持されている。ヒータホルダ4は、その長手方向の両端部が、装置フレーム(図示せず)に保持されている。また、ヒータホルダ4の加圧ローラ2側とは反対側の側面に当接するように、加圧ローラ2に対して加圧力を伝達する加圧ステー5が配置されている。加熱フィルム1は、ヒータホルダ4、ヒータ3、及び加圧ステー5の外側に外嵌されている。加熱フィルム1の長手方向の両端部には、加熱フィルム1の長手方向への移動を規制する規制部材としての定着フランジ6が配置されている。加圧ステー5は、その長手方向の両端部が、加圧手段としての加圧バネ7により、定着フランジ6を介して、加圧ローラ2の回転軸線に向けて付勢されている。これによって、ヒータ3と加熱フィルム1との間に、記録材搬送方向の幅が所定幅の内面ニップ部N2が形成される。また、これによって、加熱フィルム1と加圧ローラ2との間に、記録材搬送方向における幅が所定幅の定着ニップ部N1が形成される。トナー像Tの定着に必要な熱は、内面ニップ部N2でヒータ3から加熱フィルム1に伝えられ、定着ニップ部N1で加熱フィルム1から記録材Pに伝えられる。
加圧ローラ2は、駆動源(図示せず)から駆動ギアGを介して駆動力が伝達されることで回転駆動され、加熱フィルム1は加圧ローラ2の回転に伴って従動回転する。定着ニップ部N1に導入されるトナー像Tを担持した記録材Pは、加熱フィルム1と加圧ローラ2とに挟持されて搬送される。その搬送過程において、記録材Pには、ヒータ3により加熱されている加熱フィルム1の熱と、定着ニップ部N1の圧力と、が加えられる。これにより、トナー像Tが記録材P上に定着される。
ヒータホルダ4は、加圧ローラ2側の側面に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、凹形状の溝41を有する。そして、詳しくは後述するように、この溝41に対応する位置にヒータ3が配置される。また、ヒータホルダ4は、記録材搬送方向においてヒータ3の上流側に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、上流突起部42aを有する。上流突起部42aは、ヒータ3の加熱フィルム1と接触(摺擦)する面であるヒータ面(摺動面)31と略直交する方向においてヒータ面31よりも加圧ローラ2側に突出しており、加熱フィルム1の内周面と接触する。また、ヒータホルダ4は、記録材搬送方向においてヒータ3の下流側に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、下流突起部42bを有する。下流突起部42bは、ヒータ面31と略直交する方向においてヒータ面31よりも加圧ローラ2側に突出しており、加熱フィルム1の内周面と接触する。加熱フィルム1は、ヒータ3並びにヒータホルダ4の上流突起部42a及び下流突起部42bと、加圧ローラ2と、の間に挟持されて、定着ニップ部N1を形成する。
また、本実施例では、ヒータホルダ4は、ヒータ面31と略直交する方向においてヒータ3に対し加圧ローラ2とは反対側にヒータ3と離隔して配置された、ヒータ3の位置を決める基礎となる基礎部としての支持面43を有する。本実施例では、この支持面43は、ヒータホルダ4の溝41の底部(あるいは天井)で構成される。そして、ヒータ面31と略直交する方向におけるヒータ3と支持面43との間に、ヒータホルダ4とは別部材である樹脂部材8が配置されている。これにより、ヒータ面31と略直交する方向における、上流突起部42a、下流突起部42bのそれぞれの加圧ローラ2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている。本実施例では、樹脂部材8は、ヒータ3とヒータホルダ4との間に、これら両方と接触するように充填されて配置されている。
なお、本実施例では、ヒータホルダ4は、耐熱性樹脂である液晶ポリマー(LCP)で形成されている。また、本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向に沿ってヒータ3と加圧ローラ2とが加熱フィルム1を介して互いに加圧されるが、ヒータ面31に対して角度を有してヒータ3と加圧ローラ2とが加熱フィルム1を介して互いに加圧されてもよい。そして、例えば、そのようにヒータ面31に対して角度を有してヒータ3と加圧ローラ2とが互いに加圧される場合などには、本実施例においてヒータ面31と略直交する方向として説明する方向は、該角度を有してヒータ面31と交差する方向であってよい。
ここでは、ヒータ面31と略直交する方向における上流突起部42a、下流突起部42bのそれぞれの先端とヒータ面31との間の距離を、「突起部からヒータ面までの高さ」、あるいは「突出量」ともいう。この上流突起部42a、下流突起部42bからヒータ面31までの高さ、及び定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)については、以下で更に詳しく説明する。
3.突起部からヒータ面までの高さ
次に、本実施例におけるヒータホルダ4の上流突起部42a、下流突起部42bからヒータ面31までの高さ(突出量)について詳細に説明する。図2(b)に示すように、上流突起部42a、下流突起部42bは、ヒータ面31と略直交する方向においてヒータ面31よりも加圧ローラ2側にそれぞれ突出量h1、h2だけ突出している。なお、これに限定されるものではないが、突出量h1、h2は、例えば0.1mm〜3mm程度とされる。上流突起部42a、下流突起部42bがそれぞれヒータ面31よりも突出していることで、加熱フィルム1の内面がヒータ3のエッジとの接触で摩耗することを抑制することができる。しかし、上流突起部42a、下流突起部42bによる記録材Pに与える圧力のピークが高いほど、加熱フィルム1の表面と記録材Pとの摩擦力が大きくなるため、加熱フィルム1の表面の摩耗が進行しやすくなる。したがって、上流突起部42a、下流突起部42bによる記録材Pに与える圧力のピークを低くすることが求められるが、上流突起部42a、下流突起部42bの高さを低くし過ぎると、加熱フィルム1の内面がヒータ3のエッジと接触して摩耗してしまう。
次に、本実施例におけるヒータホルダ4の上流突起部42a、下流突起部42bからヒータ面31までの高さ(突出量)について詳細に説明する。図2(b)に示すように、上流突起部42a、下流突起部42bは、ヒータ面31と略直交する方向においてヒータ面31よりも加圧ローラ2側にそれぞれ突出量h1、h2だけ突出している。なお、これに限定されるものではないが、突出量h1、h2は、例えば0.1mm〜3mm程度とされる。上流突起部42a、下流突起部42bがそれぞれヒータ面31よりも突出していることで、加熱フィルム1の内面がヒータ3のエッジとの接触で摩耗することを抑制することができる。しかし、上流突起部42a、下流突起部42bによる記録材Pに与える圧力のピークが高いほど、加熱フィルム1の表面と記録材Pとの摩擦力が大きくなるため、加熱フィルム1の表面の摩耗が進行しやすくなる。したがって、上流突起部42a、下流突起部42bによる記録材Pに与える圧力のピークを低くすることが求められるが、上流突起部42a、下流突起部42bの高さを低くし過ぎると、加熱フィルム1の内面がヒータ3のエッジと接触して摩耗してしまう。
そのため、定着装置107の高寿命化を実現するためには、突起部42a、42bからヒータ面31までの高さを所望の高さとする精度を向上することが求められる。しかし、前述のように、突起部42a、42bからヒータホルダ4のヒータ支持面までの高さの精度とヒータ3の厚みの精度とを厳しく管理して、突起部42a、42bからヒータ面31までの高さの精度を向上することには限界がある。
そこで、本実施例では、ヒータ3と、ヒータホルダ4の支持面43との間に、ヒータホルダ4とは別部材である樹脂部材8が配置されて、高精度に所望の突出量h1、h2を得ることが可能な構成とされている。
4.ヒータとヒータホルダとの位置決め方法
次に、本実施例における定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)について説明する。
次に、本実施例における定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)について説明する。
図4(a)、(b)は、本実施例におけるヒータホルダ4の外観斜視図であり、図4(a)は加圧ローラ2側に配置される側とは反対側から見た様子、図4(b)は加圧ローラ2側に配置される側から見た様子を示す。本実施例では、ヒータホルダ4には、溝41からヒータホルダ4の加圧ローラ2側とは反対側の側面である上面44を貫通する貫通穴45が設けられている。本実施例では、貫通穴45は、ヒータホルダ4の長手方向に沿って複数(本実施例では4個)設けられている。ただし、貫通穴45は1つでもよい。また、本実施例では、貫通穴45は、平面視略円形とされている。ただし、貫通穴45の形状は平面視略円形に限定されるものではなく、例えば、平面視略矩形などの他の任意の形状であってよい。また、本実施例では、溝41の底部に相当する支持面43は、ヒータ3(より詳細には、ヒータ3のヒータ面31とは反対側の側面であるヒータ上面32)との間に隙間を有するように意図的にヒータホルダ4の上面44側にオフセットされている。なお、ヒータ面31と略直交する方向におけるこの隙間の幅は、これに限定されるものではないが、0.5mm〜3mm程度であれば十分であることが多い。
図5は、本実施例におけるヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法の手順を示す。以下、図5(a)〜(d)に示す各工程について順次説明する。
(a)ヒータ配置工程
図5(a)に示すように、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めには、位置決め台10を使用する。本実施例では、位置決め台10は、金属で形成されている。位置決め台10は、ヒータホルダ4の長手方向の長さと同等の長手方向の長さを有する。そして、位置決め台10は、長手方向と略直交する短手方向の中央部に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、第1配置部として、凸部であるヒータ配置部11を有する。典型的には、位置決め台10は、略水平な設置面上に設置される。このように位置決め台10が略水平に設置された状態で、ヒータ配置部11は略水平な平面とされている。ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めを行う際には、ヒータ配置部11にヒータ面31を接触させるようにして、ヒータ3を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、ヒータ3をヒータ配置部11に接触させ、ヒータ3を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。
図5(a)に示すように、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めには、位置決め台10を使用する。本実施例では、位置決め台10は、金属で形成されている。位置決め台10は、ヒータホルダ4の長手方向の長さと同等の長手方向の長さを有する。そして、位置決め台10は、長手方向と略直交する短手方向の中央部に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、第1配置部として、凸部であるヒータ配置部11を有する。典型的には、位置決め台10は、略水平な設置面上に設置される。このように位置決め台10が略水平に設置された状態で、ヒータ配置部11は略水平な平面とされている。ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めを行う際には、ヒータ配置部11にヒータ面31を接触させるようにして、ヒータ3を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、ヒータ3をヒータ配置部11に接触させ、ヒータ3を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。
(b)ヒータホルダ配置工程
図5(b)に示すように、位置決め台10は、短手方向におけるヒータ配置部11の両側に、第2配置部として、ヒータ配置部11とは高さが異なる上流突起配置部12a、下流突起配置部12bを有する。本実施例では、位置決め台10が略水平に設置された場合に、重力方向における上流突起配置部12a及び下流突起配置部12bの高さは、ヒータ配置部11の高さよりも低い。上述のように位置決め台10が略水平に設置された状態で、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bは、それぞれ略水平な平面とされている。ヒータ3を位置決め台10に配置した後、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bにそれぞれ上流突起部42a、下流突起部42bを接触させると共に、ヒータ3を覆うようにして、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、上流突起部42a、下流突起部42bをそれぞれ上流突起配置部12a、下流突起配置部12bに接触させ、ヒータホルダ4を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。ここで、上流突起配置部12aからヒータ配置部11までの高さ(段差)、下流突起配置部12bからヒータ配置部11までの高さ(段差)は、それぞれ設計上必要な突出量h1、h2と同じ高さになっている。そして、ヒータホルダ4は、前述のように位置決め台10に配置された状態で、ヒータ3と、ヒータホルダ4の溝41の底部に相当する支持面43と、が接触せず、これらの間に空間(隙間)46ができるように構成されている。なお、本実施例では、位置決め台10の形状は長手方向の全域で略同一であり、ヒータ3及びヒータホルダ4はそれぞれ長手方向の全域で均一に位置決め台10に接触し、固定される。
図5(b)に示すように、位置決め台10は、短手方向におけるヒータ配置部11の両側に、第2配置部として、ヒータ配置部11とは高さが異なる上流突起配置部12a、下流突起配置部12bを有する。本実施例では、位置決め台10が略水平に設置された場合に、重力方向における上流突起配置部12a及び下流突起配置部12bの高さは、ヒータ配置部11の高さよりも低い。上述のように位置決め台10が略水平に設置された状態で、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bは、それぞれ略水平な平面とされている。ヒータ3を位置決め台10に配置した後、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bにそれぞれ上流突起部42a、下流突起部42bを接触させると共に、ヒータ3を覆うようにして、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、上流突起部42a、下流突起部42bをそれぞれ上流突起配置部12a、下流突起配置部12bに接触させ、ヒータホルダ4を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。ここで、上流突起配置部12aからヒータ配置部11までの高さ(段差)、下流突起配置部12bからヒータ配置部11までの高さ(段差)は、それぞれ設計上必要な突出量h1、h2と同じ高さになっている。そして、ヒータホルダ4は、前述のように位置決め台10に配置された状態で、ヒータ3と、ヒータホルダ4の溝41の底部に相当する支持面43と、が接触せず、これらの間に空間(隙間)46ができるように構成されている。なお、本実施例では、位置決め台10の形状は長手方向の全域で略同一であり、ヒータ3及びヒータホルダ4はそれぞれ長手方向の全域で均一に位置決め台10に接触し、固定される。
(c)樹脂充填工程
図5(c)に示すように、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置した後、ヒータホルダ4の貫通穴45に対応して樹脂注入部材20をヒータホルダ4の上面44に固定する。本実施例では、ヒータホルダ4に設けられた4個の貫通穴45のそれぞれに対して樹脂注入部材20を固定する。樹脂注入部材20は、溶融した耐熱性樹脂Aを送り出す装置(図示せず)と繋がっている。そして、樹脂部材8を構成する樹脂材料としての溶融した耐熱性樹脂Aを、樹脂注入部材20から射出し、貫通穴45を通して空間46に注入して、その耐熱性樹脂Aで空間46を埋めるように、その耐熱性樹脂Aを空間46に充填する。なお、本実施例では耐熱性樹脂Aは熱硬化型であるが、光硬化型や湿度硬化型等、樹脂を硬化させられれば良い。
図5(c)に示すように、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置した後、ヒータホルダ4の貫通穴45に対応して樹脂注入部材20をヒータホルダ4の上面44に固定する。本実施例では、ヒータホルダ4に設けられた4個の貫通穴45のそれぞれに対して樹脂注入部材20を固定する。樹脂注入部材20は、溶融した耐熱性樹脂Aを送り出す装置(図示せず)と繋がっている。そして、樹脂部材8を構成する樹脂材料としての溶融した耐熱性樹脂Aを、樹脂注入部材20から射出し、貫通穴45を通して空間46に注入して、その耐熱性樹脂Aで空間46を埋めるように、その耐熱性樹脂Aを空間46に充填する。なお、本実施例では耐熱性樹脂Aは熱硬化型であるが、光硬化型や湿度硬化型等、樹脂を硬化させられれば良い。
(d)保持工程
図5(d)に示すように、耐熱性樹脂Aが冷却した後に、樹脂注入部材20をヒータホルダ4から移動させる。空間46に充填された耐熱性樹脂Aは、樹脂部材8としてヒータ3とヒータホルダ4との間に介在する。したがって、上述の突出量h1、h2を維持してヒータ3とヒータホルダ4とが位置決めされる。また、樹脂部材8は、ヒータホルダ4に対してアンカーのような形状をしており、組立中にヒータホルダ4から脱落しないようになっている。つまり、本実施例では、樹脂注入部材20は、図5(c)に示すように、空間46を埋める樹脂部材8、貫通穴45を埋める連結部8a、及びヒータホルダ4の上面44上に配置される平面視略円形の係止部8bを形成するように構成されている。この係止部8bの直径は、貫通穴45の直径よりも大きい。これら樹脂部材8、連結部8a及び係止部8bは、樹脂注入部材20から射出された耐熱性樹脂Aで一体的に成形されることになる。このような樹脂部材8の樹脂注入部材20側の端部、つまり本実施例ではアンカー状の係止部8bには、樹脂注入部材20からの射出跡が残っている。
図5(d)に示すように、耐熱性樹脂Aが冷却した後に、樹脂注入部材20をヒータホルダ4から移動させる。空間46に充填された耐熱性樹脂Aは、樹脂部材8としてヒータ3とヒータホルダ4との間に介在する。したがって、上述の突出量h1、h2を維持してヒータ3とヒータホルダ4とが位置決めされる。また、樹脂部材8は、ヒータホルダ4に対してアンカーのような形状をしており、組立中にヒータホルダ4から脱落しないようになっている。つまり、本実施例では、樹脂注入部材20は、図5(c)に示すように、空間46を埋める樹脂部材8、貫通穴45を埋める連結部8a、及びヒータホルダ4の上面44上に配置される平面視略円形の係止部8bを形成するように構成されている。この係止部8bの直径は、貫通穴45の直径よりも大きい。これら樹脂部材8、連結部8a及び係止部8bは、樹脂注入部材20から射出された耐熱性樹脂Aで一体的に成形されることになる。このような樹脂部材8の樹脂注入部材20側の端部、つまり本実施例ではアンカー状の係止部8bには、樹脂注入部材20からの射出跡が残っている。
5.本実施例の効果
図6(a)、(b)は、本実施例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の外観斜視図であり、図6(a)は加圧ローラ2側に配置される側とは反対側から見た様子、図6(b)は加圧ローラ2側に配置される側から見た様子を示す。また、図7(a)は、本実施例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の記録材搬送方向の断面図であり、図7(b)は、その長手方向の断面図である。
図6(a)、(b)は、本実施例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の外観斜視図であり、図6(a)は加圧ローラ2側に配置される側とは反対側から見た様子、図6(b)は加圧ローラ2側に配置される側から見た様子を示す。また、図7(a)は、本実施例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の記録材搬送方向の断面図であり、図7(b)は、その長手方向の断面図である。
上述のように、本実施例の定着装置107は、無端状の可撓性部材1と、可撓性部材1の内周面側に配置され可撓性部材を加熱するヒータ3と、を有する。また、この定着装置107は、可撓性部材1の内周面側に配置されヒータ3を支持する支持部材4と、可撓性部材1を介して支持部材4及びヒータ3に押圧されてニップ部N1を形成する回転体2と、を有する。また、支持部材4は、ヒータ3の可撓性部材1と接触する面であるヒータ面31と交差する方向において回転体側に突出した突起部42a、42bを有する。特に、本実施例では、突起部42a、42bの先端は、ヒータ面31と交差する方向においてヒータ面31に対し回転体2側に位置する。つまり、本実施例では、加圧ローラ2に対してヒータ面31よりも上流突起部42a、下流突起部42bの方が高い。また、支持部材4は、ヒータ面31と交差する方向においてヒータ3に対し回転体2とは反対側にヒータ3と離隔して配置された基礎部(支持面)43を有する。そして、ヒータ面31と交差する方向におけるヒータ3と基礎部43との間に、支持部材4とは別部材である樹脂部材8が配置されて、ヒータ面31と交差する方向における突起部42a、42bの回転体2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている。また、本実施例では、樹脂部材8は、ヒータ3と支持部材4との間の空間46を埋めるように充填されている。また、本実施例では、支持部材4は、樹脂部材8によって埋められた、樹脂部材8を構成する樹脂材料を注入するための貫通孔45を有する。
本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向において、ヒータ3とヒータホルダ4の支持面43とは接触していない。そして、本実施例では、このヒータ3と支持面43との間に樹脂部材8が介在し、ヒータホルダ4からの加圧力は樹脂部材8を介してヒータ3に加えられる。
これは、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めが、図5(b)に示す手順において、ヒータ面31と、上流突起部42a、下流突起部42bと、を基準にして行われるためである。したがって、突出量h1、h2は、実質的に位置決め台10の段差のみで管理することができ、ヒータ3とヒータホルダ4とを従来よりも高精度に位置決めすることが可能となる。これにより、加熱フィルム1の表面の摩耗速度の抑制を高水準で達成することができる。
なお、本実施例では、樹脂部材8の材料として耐熱性樹脂を用いているが、樹脂部材8の材料として熱硬化型、光硬化型、湿度硬化型等の耐熱性接着材を用いてもよく、貫通穴45を通して空間46を埋めることが可能な材料であればよい。
また、本実施例では、貫通穴45から樹脂材料を注入することで樹脂部材8を形成したが、これに限定されるものではない。図8(a)は、本実施例の変形例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の外観斜視図であり、図8(b)はその長手方向の断面図である。この変形例では、ヒータホルダ4の長手方向の端部から樹脂材料を注入することで樹脂部材8を形成する。このような構成によっても、本実施例と同様の効果を得ることができる。なお、この変形例では、樹脂部材8の長手方向の端部(連結部8a、係止部8b)をヒータホルダ4の上面44にアンカーとして引っかけることで、ヒータホルダ4から樹脂部材8が脱落しないようにすることができる。
[実施例2]
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
1.ヒータとヒータホルダとの位置決め方法
本実施例における定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)について説明する。
本実施例における定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)について説明する。
図9(a)、(b)は、本実施例におけるヒータホルダ4の外観斜視図であり、図9(a)は加圧ローラ2側に配置される側とは反対側から見た様子、図9(b)は加圧ローラ2側に配置される側から見た様子を示す。本実施例では、ヒータホルダ4は、実施例1と同様に、加圧ローラ2側の側面に、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、凹形状の溝41を有する。ただし、本実施例では、この溝41は2段階の深さを有し、記録材搬送方向の両端部に配置されたより浅い第1の溝部41a、41aと、記録材搬送方向の中央部に配置されたより深い第2の溝部41bと、を有する。そして、詳しくは後述するように、この溝41に対応する位置にヒータ3が配置される。また、本実施例では、ヒータ3の位置を決める基礎となる基礎部としての支持面43を構成する第1の溝部41a、41aは、実施例1と同様に、ヒータ3との間に隙間を有するように意図的にヒータホルダ4の上面44側にオフセットされている。
図10は、本実施例におけるヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法の手順を示す。以下、図10(a)〜(c)に示す各工程について順次説明する。
(a)ヒータ配置工程
図10(a)に示すように、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めには、位置決め台10を使用する。位置決め台10は、実施例1で説明したものと実質的に同じである。ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めを行う際には、ヒータ配置部11にヒータ面31を接触させるようにして、ヒータ3を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、ヒータ3をヒータ配置部11に接触させ、ヒータ3を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。
図10(a)に示すように、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めには、位置決め台10を使用する。位置決め台10は、実施例1で説明したものと実質的に同じである。ヒータ3とヒータホルダ4との位置決めを行う際には、ヒータ配置部11にヒータ面31を接触させるようにして、ヒータ3を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、ヒータ3をヒータ配置部11に接触させ、ヒータ3を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。
(b)樹脂塗布工程
図10(b)に示すように、ヒータ3を位置決め台10に配置した後、ヒータ3のヒータ面31とは反対側の面であるヒータ上面32に、樹脂部材8を構成する樹脂材料としての未硬化状態の耐熱性接着部材Bを塗布する。この耐熱性接着部材Bを塗布する個所は、ヒータホルダ4の支持面43を構成する第1の溝部41a、41aに対応する箇所である。つまり、ヒータ上面32の記録材搬送方向の両端部に、ヒータ上面32の長手方向に沿って、ヒータ3の略全長に渡り耐熱性接着部材Bを塗布する。
図10(b)に示すように、ヒータ3を位置決め台10に配置した後、ヒータ3のヒータ面31とは反対側の面であるヒータ上面32に、樹脂部材8を構成する樹脂材料としての未硬化状態の耐熱性接着部材Bを塗布する。この耐熱性接着部材Bを塗布する個所は、ヒータホルダ4の支持面43を構成する第1の溝部41a、41aに対応する箇所である。つまり、ヒータ上面32の記録材搬送方向の両端部に、ヒータ上面32の長手方向に沿って、ヒータ3の略全長に渡り耐熱性接着部材Bを塗布する。
(c)ヒータホルダ配置工程
図10(c)に示すように、耐熱性接着部材Bが未硬化状態の間に、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bにそれぞれ上流突起部42a、下流突起部42bを接触させると共に、ヒータ3を覆うようにして、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、上流突起部42a、下流突起部42bをそれぞれ上流突起配置部12a、下流突起配置部12bに接触させ、ヒータホルダ4を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。これによって、ヒータホルダ4の第1の溝部41a、41aとヒータ上面32との間で耐熱性接着材Bが押しつぶされる。ここで、本実施例では、実施例1と同様に、上流突起配置部12aからヒータ配置部11までの高さ(段差)、下流突起配置部12bからヒータ配置部11までの高さ(段差)は、それぞれ設計上必要な突出量h1、h2と同じ高さになっている。したがって、耐熱性接着部材Bが硬化することで、耐熱性接着剤Bが樹脂部材8としてヒータ3とヒータホルダ4との間に介在し、上述の突出量h1、h2を維持してヒータ3とヒータホルダ4とが位置決めされ、かつ、固定される。
図10(c)に示すように、耐熱性接着部材Bが未硬化状態の間に、上流突起配置部12a、下流突起配置部12bにそれぞれ上流突起部42a、下流突起部42bを接触させると共に、ヒータ3を覆うようにして、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置する。このとき、本実施例では、上流突起部42a、下流突起部42bをそれぞれ上流突起配置部12a、下流突起配置部12bに接触させ、ヒータホルダ4を位置決め台10上の所定位置に保持するように位置決め台10に固定する。これによって、ヒータホルダ4の第1の溝部41a、41aとヒータ上面32との間で耐熱性接着材Bが押しつぶされる。ここで、本実施例では、実施例1と同様に、上流突起配置部12aからヒータ配置部11までの高さ(段差)、下流突起配置部12bからヒータ配置部11までの高さ(段差)は、それぞれ設計上必要な突出量h1、h2と同じ高さになっている。したがって、耐熱性接着部材Bが硬化することで、耐熱性接着剤Bが樹脂部材8としてヒータ3とヒータホルダ4との間に介在し、上述の突出量h1、h2を維持してヒータ3とヒータホルダ4とが位置決めされ、かつ、固定される。
2.本実施例の効果
本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向において、ヒータ3とヒータホルダ4の支持面43とは接触していない。そして、本実施例では、このヒータ3と支持面43との間に樹脂部材8が介在し、ヒータホルダ4からの加圧力は樹脂部材8を介してヒータ3に加えられる。
本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向において、ヒータ3とヒータホルダ4の支持面43とは接触していない。そして、本実施例では、このヒータ3と支持面43との間に樹脂部材8が介在し、ヒータホルダ4からの加圧力は樹脂部材8を介してヒータ3に加えられる。
また、本実施例では、ヒータ3とヒータホルダ4の第2の溝部41bとの間に空間48を形成することができる。つまり、本実施例では、樹脂部材8は、ヒータ3と支持部材4との間の一部に配置されており、ヒータ3と支持部材4との間に空間48が形成されている。そのため、本実施例では、このヒータ3とヒータホルダ4との間に形成される空間48によって断熱効果を生み出し、熱エネルギーをより効率的に記録材Pに与えることが可能となる。
また、本実施例では、耐熱性接着部材Bを用いることで、ヒータ3とヒータホルダ4とが固定されるため、組立性が向上する。
なお、本実施例では、樹脂部材8の材料として耐熱性接着部材Bを用いているが、これに限定されるものではない。この材料は、該材料がヒータ3に配置された後にヒータホルダ4が位置決め台10に配置された状態で変形し、その後硬化するものであればよい。例えば、耐熱性接着部材Bの代わりに、熱硬化型樹脂をヒータ3に配置し、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置した後に該熱硬化型樹脂を加熱して硬化させても、本実施例と同様の効果が得られる。
[実施例3]
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
図11(a)は、本実施例におけるヒータ3が取り付けられたヒータホルダ4の外観斜視図であり、図11(b)は、その記録材搬送方向の断面図である。本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向におけるヒータ3とヒータホルダ4の支持面43との間に、ヒータホルダ4とは別部材であるスペーサ部材9が配置されている。そして、本実施例では、樹脂部材8は、ヒータ面31と略直交する方向におけるスペーサ部材9とヒータホルダ4の支持面43との間に配置される。これにより、ヒータ面31と略直交する方向における、上流突起部42a、下流突起部42bのそれぞれの加圧ローラ2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている。
図12(a)は、本実施例におけるヒータホルダ4及びスペーサ部材9の外観斜視図であり、図12(b)は、その記録材搬送方向の断面図である。本実施例では、ヒータホルダ4には、上面44を貫通する貫通穴45が設けられている。本実施例では、貫通穴45は、ヒータホルダ4の長手方向に沿って、記録材搬送方向において2個設けられている。また、本実施例では、ヒータホルダ4には、ヒータ面31と略直交する方向において上面44から加圧ローラ2側とは反対側に突出して補強部47が設けられている。補強部47は、図12(b)に示すように断面略T字形状を有し、記録材搬送方向に伸びる部分が貫通穴45と対向する。本実施例では、この補強部47の貫通穴45と対向する面が、ヒータ3の位置を決める基礎となる基礎部としての支持面43を構成する。また、本実施例では、スペーサ部材9は、ヒータ3側の側面に、長手方向に沿って、凹形状のスペーサ溝91を有する。そして、スペーサ部材9は、このスペーサ溝91の記録材搬送方向の両側の、長手方向に沿って伸びる当接部(座面)92、92でヒータ上面32に当接する。スペーサ部材9は、ヒータ3とヒータホルダ4の支持面43との間に配置されるように、ヒータホルダ4の凹形状の溝41内に篏合されて配置される。そして、このスペーサ部材9とヒータホルダ4の支持面43との間に樹脂部材8が配置される。
このように、本実施例では、ヒータ面31と交差する方向におけるヒータ3と基礎部(支持面)43との間に、支持部材4とは別部材であるスペーサ部材9が配置されている。そして、樹脂部材8が、ヒータ面31と交差する方向におけるスペーサ部材9と基礎部43との間に配置されて、ヒータ面31と交差する方向における突起部42a、42bの回転体2側の先端とヒータ面31との間の距離が決められている。また、本実施例では、樹脂部材8は、スペーサ部材9と支持部材4との間の空間を埋めるように充填されている。また、本実施例では、ヒータ3はスペーサ部材9の一部と接触し、ヒータ3とスペーサ部材9との間に空間48が形成されている。
本実施例における定着装置107の製造方法(特に、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法)は、図5を参照して説明した実施例1における方法と概略同様である。ただし、本実施例では、図5(a)に示すヒータ配置工程において、ヒータ3を位置決め台10上に配置すると共に、スペーサ部材9をヒータ3上に配置する。また、本実施例では、図5(b)に示すヒータホルダ配置工程において、突起配置部12a、12bに突起部42a、42bを接触させると共に、ヒータ3及びスペーサ部材9を覆うようにして、ヒータホルダ4を位置決め台10に配置する。また、本実施例では、図5(c)に示す樹脂充填工程において、貫通穴45から樹脂部材8を構成する樹脂材料としての耐熱性樹脂Aを注入して、スペーサ部材9とヒータホルダ4の補強部47の支持面43との間に樹脂部材8を介在させる。
上述のようにしてスペーサ部材9とヒータホルダ4の支持面43との間に樹脂部材8を介在させることで、ヒータ3とヒータホルダ4とを位置決めすることができる。図11(b)に示すように、本実施例では、ヒータ面31と略直交する方向において、スペーサ部材9とヒータホルダ4の補強部47の支持面43とは接触していない。そして、本実施例では、このスペーサ部材9と支持面43との間に樹脂部材8が介在し、ヒータ3からの加圧力の反力を最終的に補強部47の支持面43で受けるようにしている。これによって、貫通穴45上の加圧方向の強度を高めることが可能となり、加圧時の位置精度の信頼性が向上する。
また、本実施例では、スペーサ部材9にスペーサ溝91が設けられており、ヒータ3との間に空間48が形成される。ここで、実施例2では、ヒータ3とヒータホルダ4との間の空間48の体積は、耐熱性接着部材Bの形状によって決まる。そして、実施例2では、位置決め台10上で所定の突出量h1、h2を得る際に耐熱性接着部材Bの厚さが変化して、上記空間48の体積も変化する。そのため、実施例2では、空間48による断熱効果にばらつきが生じる可能性がある。これに対し、本実施例では、スペーサ溝91の形状を予め設定すれば、ヒータ3とスペーサ部材9との間の空間48が実施例2のように製造過程で変化することはない。これによって、断熱効果のばらつきを抑え、記録材Pに熱を与える効率性の信頼性を向上させることができる。
なお、本実施例では、貫通穴45を用いて樹脂部材8の材料を充填しているが、実施例1にて説明したのと同様に、ヒータホルダ4の長手方向の端部から樹脂部材8の材料を充填しても同様の効果が得られる。また、樹脂部材8の材料は、耐熱性樹脂であっても、耐熱性接着材であってもよい。
[実施例4]
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置、定着装置の基本的な構成及び動作は、実施例1のものと同じである。したがって、本実施例の画像形成装置、定着装置において、実施例1の画像形成装置、定着装置のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、実施例1と同一符号を付して、詳しい説明は省略する。
図13は、本実施例の定着装置107のニップ部の近傍の記録材搬送方向の断面図である。本実施例では、実施例1と同様、支持部材4は、ヒータ3の可撓性部材1と接触する面であるヒータ面31と交差する方向において回転体2側に突出した突起部42a、42bを有する。ただし、本実施例では、突起部42a、42bの先端は、ヒータ面31と交差する方向においてヒータ面31に対し回転体2とは反対側に位置する。つまり、本実施例では、加圧ローラ2に対してヒータ面31よりも上流突起部42a、下流突起部42bの方が低い。
具体的には、本実施例では、ヒータ3の表面にはガラスの摺動層49が設けられており、この摺動層49の加圧ローラ2側の面がヒータ面31を構成している。摺動層49には、ヒータ3の加熱フィルム1との摺動性を上げる効果があるため、加熱フィルム1の内面の摩耗をさらに抑えることができる。さらに、摺動層49の厚みによってヒータ3のエッジと加熱フィルム1との距離が離れるため、ヒータ3のエッジと加熱フィルム1とが接触しない程度まで上流突起部42a、下流突起部42bの高さを低くすることができる。これにより、本実施例では、加圧ローラ2に対してヒータ面31よりも上流突起部42a、下流突起部42bの方が低いニップ構成を実現している。本実施例では、加圧ローラ2に対してヒータ面31よりも上流突起部42a、下流突起部42bの方が低いため、上流突起部42a、下流突起部42bによる圧力のピークを下げることができる。したがって、加熱フィルム1と記録材Pとの摩擦力による加熱フィルム1の表層の摩耗をさらに抑えることができる。
図14は、本実施例におけるヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法の手順を示す。図14(a)〜(d)に示す各工程は、それぞれ実施例1における図5(a)〜(d)に示す各工程と同様である。ただし、本実施例では、位置決め台10の形状が実施例1とは異なる。具体的には、本実施例では、位置決め台10が略水平に設置された場合に、重力方向における上流突起配置部12a及び下流突起配置部12bの高さは、ヒータ配置部11の高さよりも高い。これにより、図14(b)に示すヒータホルダ配置工程では、ヒータホルダ4を位置決め台10に固定することで、加圧ローラ2に対してヒータ面31よりも上流突起部42a、下流突起部42bを高精度に低く位置決めすることが可能となる。
なお、本実施例では、実施例1と同様の構成の定着装置107において、上流突起部42a、下流突起部42bをヒータ面31よりも加圧ローラ2とは反対側に退避させたニップ構成とした場合について説明した。実施例2、実施例3と同様の構成の定着装置107においても、本実施例と同様に上流突起部42a、下流突起部42bをヒータ面31よりも加圧ローラ2とは反対側に退避させたニップ構成とすることができる。この場合も、ヒータ3とヒータホルダ4との位置決め方法においては、位置決め台10のヒータ配置部11と上流突起配置部12a、下流突起配置部12bとの高さ関係を、実施例2、3における関係から本実施例と同様の関係に変更すればよい。
[その他]
以上、本発明を具体的な実施例に即して説明したが、本発明は上述の実施例に限定されるものではない。
以上、本発明を具体的な実施例に即して説明したが、本発明は上述の実施例に限定されるものではない。
例えば、画像を担持した記録材を加熱する像加熱装置は、典型的には未定着のトナー像を記録材に定着させる定着装置であるが、例えばトナー像が定着された記録材を再加熱して光沢を制御する装置などであってもよい。
また、上述の実施例ではモノクロ画像形成装置を例として説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明は、例えばイエロー、マゼンダ、シアン、ブラックの4色などの複数色のトナー像を重ねて印字するカラー画像形成装置にて用いられる像加熱装置に関しても適用することも可能であり、上述の実施例と同様の作用効果を得ることができる。
1 加熱フィルム
2 加圧ローラ
3 ヒータ
4 支持部材
8 樹脂部材
9 スペーサ部材
10 位置決め台
20 樹脂注入部材
31 ヒータ面
43 支持面(基礎部)
45 貫通穴
A 耐熱性樹脂
B 耐熱性接着部材
2 加圧ローラ
3 ヒータ
4 支持部材
8 樹脂部材
9 スペーサ部材
10 位置決め台
20 樹脂注入部材
31 ヒータ面
43 支持面(基礎部)
45 貫通穴
A 耐熱性樹脂
B 耐熱性接着部材
Claims (12)
- 無端状の可撓性部材と、
前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、
前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、
前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、
を有し、
前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置において、
前記支持部材は、前記ヒータ面と交差する方向において前記ヒータに対し前記回転体とは反対側に前記ヒータと離隔して配置された基礎部を有し、
前記ヒータ面と交差する方向における前記ヒータと前記基礎部との間に、前記支持部材とは別部材である樹脂部材が配置されて、前記ヒータ面と交差する方向における前記突起部の前記回転体側の先端と前記ヒータ面との間の距離が決められていることを特徴とする像加熱装置。 - 前記樹脂部材は、前記ヒータと前記支持部材との間の空間を埋めるように充填されていることを特徴とする請求項1に記載の像加熱装置。
- 前記樹脂部材は、前記ヒータと前記支持部材との間の一部に配置されており、前記ヒータと前記支持部材との間に空間が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の像加熱装置。
- 前記ヒータ面と交差する方向における前記ヒータと前記基礎部との間に、前記支持部材とは別部材であるスペーサ部材が配置されており、前記樹脂部材が、前記ヒータ面と交差する方向における前記スペーサ部材と前記基礎部との間に配置されて、前記ヒータ面と交差する方向における前記突起部の前記回転体側の先端と前記ヒータ面との間の距離が決められていることを特徴とする請求項1に記載の像加熱装置。
- 前記樹脂部材は、前記スペーサ部材と前記支持部材との間の空間を埋めるように充填されていることを特徴とする請求項4に記載の像加熱装置。
- 前記ヒータは前記スペーサ部材の一部と接触し、前記ヒータと前記スペーサ部材との間に空間が形成されていることを特徴とする請求項4又は5に記載の像加熱装置。
- 前記支持部材は、前記樹脂部材によって埋められた、前記樹脂部材を構成する樹脂材料を注入するための貫通孔を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の像加熱装置。
- 前記ヒータ面と交差する方向において、前記突起部の前記回転体側の先端は、前記ヒータ面に対し前記回転体側、又は前記回転体とは反対側に位置することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の像加熱装置。
- 無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、
前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、
前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータを覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置する工程と、
前記ヒータと前記支持部材との間に樹脂材料を充填する工程と、
を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法。 - 無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、
前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、
前記ヒータの前記ヒータ面とは反対側の側面であるヒータ上面に樹脂材料を塗布する工程と、
前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータを覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置し、前記支持部材と前記ヒータとの間で前記樹脂材料を挟み込む工程と、
を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法。 - 無端状の可撓性部材と、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記可撓性部材を加熱するヒータと、前記可撓性部材の内周面側に配置され前記ヒータを支持する支持部材と、前記可撓性部材を介して前記支持部材及び前記ヒータに押圧されてニップ部を形成する回転体と、を有し、前記支持部材は、前記ヒータの前記可撓性部材と接触する面であるヒータ面と交差する方向において前記回転体側に突出した突起部を有する像加熱装置の製造方法において、
前記ヒータが配置される第1配置部と、前記突起部が配置される第2配置部と、を有する位置決め台の前記第1配置部に前記ヒータ面を接触させるようにして前記ヒータを前記位置決め台に配置する工程と、
前記ヒータの前記ヒータ面とは反対側の面であるヒータ上面にスペーサ部材を配置する工程と、
前記第2配置部に前記突起部を接触させると共に、前記ヒータ及び前記スペーサ部材を覆うようにして前記支持部材を前記位置決め台に配置する工程と、
前記ヒータと前記スペーサ部材との間に樹脂材料を充填する工程と、
を有することを特徴とする像加熱装置の製造方法。 - 前記第2配置部の高さは、前記第1配置部の高さよりも低い又は高いことを特徴とする請求項9乃至11のいずれか1項に記載の像加熱装置の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2018012095A JP2019128564A (ja) | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 像加熱装置及びその製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2018012095A JP2019128564A (ja) | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 像加熱装置及びその製造方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2019128564A true JP2019128564A (ja) | 2019-08-01 |
Family
ID=67472309
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2018012095A Pending JP2019128564A (ja) | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 像加熱装置及びその製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2019128564A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12061429B2 (en) | 2021-10-11 | 2024-08-13 | Canon Kabushiki Kaisha | Heater, heating device, and image forming apparatus |
-
2018
- 2018-01-26 JP JP2018012095A patent/JP2019128564A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12061429B2 (en) | 2021-10-11 | 2024-08-13 | Canon Kabushiki Kaisha | Heater, heating device, and image forming apparatus |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6347163B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |
| US10928767B2 (en) | Heating device with a guide having convex and recess portions and a connector with a conduction terminal | |
| US20180203384A1 (en) | Fixing device and image forming apparatus | |
| JP6365039B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |
| US9791813B2 (en) | Fixing device and image forming apparatus | |
| US11994815B2 (en) | Heating apparatus and image forming apparatus | |
| JP2013221975A (ja) | 現像ユニット、プロセスカートリッジ、及び電子写真画像形成装置 | |
| JP6376841B2 (ja) | カートリッジ及び画像形成装置 | |
| JP2015084082A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |
| JP6884540B2 (ja) | 定着装置 | |
| US10353327B2 (en) | Fixing device for fixing an image on a recording material and having a nip plate with a projection that projects towards a roller | |
| US9195182B2 (en) | Image heating apparatus, lubricant application system, lubricant application method, and lubricant container-applicator | |
| JP2019128564A (ja) | 像加熱装置及びその製造方法 | |
| JP6190761B2 (ja) | 画像形成装置 | |
| KR100708161B1 (ko) | 화상 형성장치의 가변 장력 벨트 정착기 및 그 구동방법 | |
| JP2015079082A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |
| JP2005158639A (ja) | 加熱装置および画像形成装置 | |
| JP2010247435A (ja) | 光源ユニット、光源装置、光走査装置、及び画像形成装置 | |
| JP2019204067A (ja) | 像加熱装置及びその製造方法 | |
| JP6129383B2 (ja) | 現像ユニット、プロセスカートリッジ、及び電子写真画像形成装置 | |
| JP7127496B2 (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |
| US20250355389A1 (en) | Fixing device and image forming apparatus incorporating same | |
| JP2020134885A (ja) | 剥離シート、定着装置及び剥離シートの製造方法 | |
| KR102022326B1 (ko) | 정착 장치 및 화상 형성 장치 | |
| JP2011112673A (ja) | 画像形成方法及びこれを用いる画像形成装置 |