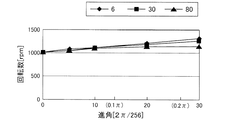JP5510493B2 - 電気機械装置 - Google Patents
電気機械装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5510493B2 JP5510493B2 JP2012109721A JP2012109721A JP5510493B2 JP 5510493 B2 JP5510493 B2 JP 5510493B2 JP 2012109721 A JP2012109721 A JP 2012109721A JP 2012109721 A JP2012109721 A JP 2012109721A JP 5510493 B2 JP5510493 B2 JP 5510493B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- control
- phase
- value
- signal
- motor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 91
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims description 15
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims description 15
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 27
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 21
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 15
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 9
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 7
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 3
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000000881 depressing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 239000012811 non-conductive material Substances 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2200/00—Type of vehicles
- B60L2200/26—Rail vehicles
Landscapes
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Description
本発明の一形態によれば、電気機械装置が提供される。この電気機械装置は、独立結線された複数相の電磁コイルと、前記電磁コイルにPWM駆動信号を供給するためのPWM駆動回路と、前記PWM駆動回路を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電磁コイルに前記PWM駆動信号を供給する区間としての励磁区間を設定する第1の制御と、前記PWM駆動信号のデューティ比を変更する第2の制御と、を実行し、前記制御部は、前記第1の制御において、前記励磁区間の中心の位相を、前記電磁コイルに生じる逆起電力の最大値が生じる位相の値よりも早める進角制御を行うとともに、前記第2の制御において、第2の制御による変更後のPWM駆動信号のデューティ比を、正弦波を模擬するPWM駆動波形のデューティ比、で割った値であるゲインが100%を越えるように前記デューティ比を増大させる。この形態によれば、効率のよい位相で駆動するように励磁区間を進角し、かつ、その励磁区間において、ゲインを飽和させて100%を越えるゲインとするので、電気機械装置を効率的に制御することが可能となる。
電気機械装置であって、独立結線された複数相の電磁コイルと、前記電磁コイルにPWM駆動信号を供給するためのPWM駆動回路と、前記PWM駆動回路を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電磁コイルに前記PWM駆動信号を供給する区間としての励磁区間を設定する第1の制御と、前記PWM駆動信号のデューティ比を変更する第2の制御と、を実行し、前記制御部は、前記第1の制御において、前記励磁区間の中心の位相を、前記電磁コイルに生じる逆起電力の最大値が生じる位相の値よりも早める進角制御を行うとともに、前記第2の制御において、正弦波を模擬するPWM駆動信号を生成する際のゲインを100%としたときに、100%を越えるゲインを実現するように前記デューティ比を増大させる、電気機械装置。
この実施例によれば、効率のよい位相で駆動するように励磁区間を進角し、かつ、その励磁区間において、ゲインを飽和させて100%を越えるゲインとするので、電気機械装置を効率的に制御することが可能となる。
[適用例2]
適用例1に記載の電気機械装置において、
前記PWM駆動回路は3相駆動回路である、電気機械装置。
適用例1または2に記載の電気機械装置において、前記進角制御における進角の大きさは、前記励磁区間の長さが短いほど大きく設定されている、電気機械装置。
本実施例によれば、励磁区間の長さが短いほど、進角を大きくしているので、効率がよく、高回転が可能である。
適用例1から適用例3までのいずれか一つの適用例に記載の電気機械装置において、さらに、前記制御部は、前記第1の制御において、前記電気機械装置が高速で動作するほど、前記励磁区間を狭める制御を行う、電気機械装置。
一般に、高速動作のときは、大きなトルクよりも高回転が要求される。この適用例によれば、励磁区間を狭める制御を行うことにより、低トルク、高回転が可能となる。
適用例1から適用例4までのいずれか一つの適用例に記載の電気機械装置において、前記制御部は、前記電気機械装置の減速時には、減速度が大きいほど前記第1の制御において前記励磁区間を広める制御を行いつつ、エネルギーの回生を行う、電気機械装置。
この適用例によれば、減速度が大きいほど、より多くのエネルギーの回生が可能となる。
図1は、第1の実施例のモーターを示す説明図である。 モーター10は、略円筒状のステーター15が外側に配置され、略円筒状のローター20が内側に配置されたラジアルギャップ構造のインナーローター型モーターである。ステーター15は、ケーシング110の内周に沿って配列された複数の電磁コイル100を有している。ステーター15には、さらに、ローター20の位相を検出する位置センサーとしての磁気センサー300が、配置されている。磁気センサー300は、回路基板310の上に固定されており、回路基板310は、ケーシング110に固定されている。また、回路基板310は、コネクタ320により外部の制御回路と接続されている。
図28は、第2の実施例を示す説明図である。第2の実施例では、モーター10(図示せず)からの回生制御を行う。第2の実施例では、回生制御部700と、U相充電切替部710u〜710wと、蓄電部800と、を備える。回生制御部700は、U相回生制御回路700u〜W相回生制御回路700wを含んでいる。U相回生制御回路700u〜W相回生制御回路700wの構成は同じであるので、U相回生制御回路700uを例にとり説明する。U相回生制御回路700uは、U相電磁コイル100uに対して駆動回路690uと並列に接続されている。U回生制御部700uは、インバーター回路720uと、バッファー回路730uと、ダイオードで構成される整流回路740u〜743uと、スイッチングトランジスタ750u、760uと、抵抗752u、762uと、を備えている。
[変形例]
本発明によるモーターは、移動体やロボット用のモーターとしても利用可能である。図29は、本発明の変形例によるモーターを利用した鉄道車両を示す説明図である。この鉄道車両1500は、モーター1510と、車輪1520とを有している。このモーター1510は、車輪1520を駆動する。さらに、モーター1510は、鉄道車両1500の制動時には発電機として利用され、電力が回生される。このモーター1510としては、上述した各種のブラシレスモーターを利用することができる。
15…ステーター
20…ローター
100、100u〜100w…電磁コイル
110…ケーシング
200…永久磁石
230…回転軸
260…コイルバネ
300…磁気センサー
310…回路基板
320…コネクタ
405…CPU
410…基本クロック生成回路
420…分周器
440…正逆方向指示値レジスタ
450…乗算器
452…乗算器
454…乗算器
460…符号化部
462…符号化部
464…符号化部
480…電圧指令値レジスタ
492…電子可変抵抗器
494…第1の電圧比較器
496…第2の電圧比較器
521〜523…駆動波形形成部
585…電圧比較器
590…励磁区間設定部
592…制御部
594…第1カウンタ部
596…第2カウンタ部
598…カウンタ値記憶部
600…第1の演算値記憶部
602…第2の演算値記憶部
604…第1の乗算回路
605…第2の乗算回路
606…演算回路
608…第1の演算結果記憶部
610…第2の演算結果記憶部
612…比較回路
690…三相駆動回路
690u…駆動回路
695u…レベルシフト回路
700…回生制御部
720u…インバーター回路
730u…バッファー回路
740u…整流回路
750u…スイッチングトランジスタ
752u…抵抗
760u…スイッチングトランジスタ
800…蓄電部
810…トルク変換操作レバー
820…アクセルペダル
830…ブレーキペダル
840…制御テーブル
1500…鉄道車両
1510…モーター
1520…車輪
A1〜A3…トランジスタ
CM1…カウント値
DRVA1〜DRVA4…駆動信号
EP…励磁区間
Eu…励磁区間信号
Iu1…符号
Iu2…符号
Mu…乗算値
NEP…非励磁区間
PCL…クロック信号
Pu…正負符号信号
RI…正逆方向指示値
Rv…可変抵抗値
S1、S2…出力
SDC…クロック信号
Sn…出力
Sp…出力信号
SSU…センサー出力
u1…端子
V1,V2…電圧
VS…電源電位
Xu…センサー出力値
Yu…電圧指令値
Claims (5)
- 電気機械装置であって、
独立結線された複数相の電磁コイルと、
前記電磁コイルにPWM駆動信号を供給するためのPWM駆動回路と、
前記PWM駆動回路を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、
前記電磁コイルに前記PWM駆動信号を供給する区間としての励磁区間を設定する第1の制御と、
前記PWM駆動信号のデューティ比を変更する第2の制御と、
を実行し、
前記制御部は、前記第1の制御において、前記励磁区間の中心の位相を、前記電磁コイルに生じる逆起電力の最大値が生じる位相の値よりも早める進角制御を行うとともに、前記第2の制御において、第2の制御による変更後のPWM駆動信号のデューティ比を、正弦波を模擬するPWM駆動波形のデューティ比、で割った値であるゲインが100%を越えるように前記デューティ比を増大させる、電気機械装置。 - 請求項1に記載の電気機械装置において、
前記PWM駆動回路は3相駆動回路である、電気機械装置。 - 請求項1または2に記載の電気機械装置において、
前記進角制御における進角の大きさは、前記励磁区間の長さが短いほど大きく設定されている、電気機械装置。 - 請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の電気機械装置において、さらに、
前記制御部は、前記第1の制御において、前記電気機械装置が高速で動作するほど、前記励磁区間を狭める制御を行う、電気機械装置。 - 請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の電気機械装置において、
前記制御部は、前記電気機械装置の減速時には、減速度が大きいほど前記第1の制御において前記励磁区間を広める制御を行いつつ、エネルギーの回生を行う、電気機械装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012109721A JP5510493B2 (ja) | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 電気機械装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012109721A JP5510493B2 (ja) | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 電気機械装置 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2010120303A Division JP5077389B2 (ja) | 2010-05-26 | 2010-05-26 | 電気機械装置 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2012147675A JP2012147675A (ja) | 2012-08-02 |
| JP2012147675A5 JP2012147675A5 (ja) | 2012-10-25 |
| JP5510493B2 true JP5510493B2 (ja) | 2014-06-04 |
Family
ID=46790628
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2012109721A Active JP5510493B2 (ja) | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 電気機械装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5510493B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20200198697A1 (en) * | 2017-07-26 | 2020-06-25 | Nidec Corporation | Power conversion device, motor module, electric power steering device |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004058800A (ja) * | 2002-07-26 | 2004-02-26 | Koyo Seiko Co Ltd | 電動パワーステアリング装置 |
| JP2004180410A (ja) * | 2002-11-26 | 2004-06-24 | Sony Corp | サーボ・モータ |
| JP4835996B2 (ja) * | 2006-11-17 | 2011-12-14 | セイコーエプソン株式会社 | Pwm制御システム |
| JP5359021B2 (ja) * | 2007-06-28 | 2013-12-04 | セイコーエプソン株式会社 | 電動機の駆動制御回路 |
| JP2009178016A (ja) * | 2007-07-03 | 2009-08-06 | Seiko Epson Corp | 電動機の駆動制御回路 |
| JP5359015B2 (ja) * | 2007-08-06 | 2013-12-04 | セイコーエプソン株式会社 | モータの制御装置、制御方法、ロボット及び移動体 |
| JP5468215B2 (ja) * | 2008-06-09 | 2014-04-09 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機及び空気調和機の製造方法 |
| JP2009303298A (ja) * | 2008-06-10 | 2009-12-24 | Denso Corp | 交流モータ装置 |
-
2012
- 2012-05-11 JP JP2012109721A patent/JP5510493B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2012147675A (ja) | 2012-08-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7948141B2 (en) | Electric motor device | |
| JP5016674B2 (ja) | モータ制御回路、モータシステム、モータ制御方法 | |
| JP5077389B2 (ja) | 電気機械装置 | |
| JP5151486B2 (ja) | ブラシレス電気機械、装置、移動体、及び、ロボット | |
| US8106548B2 (en) | Electric motor device | |
| US8258734B2 (en) | Energy converter and electromechanical apparatus | |
| JP2012170307A (ja) | 電気機械装置、移動体、及びロボット | |
| US8080953B2 (en) | Motor control method and device | |
| EP2020736A2 (en) | Brushless motor | |
| US8766574B2 (en) | Method and control device for operating a three-phase brushless direct current motor | |
| JP5266746B2 (ja) | ブラシレスモータ、装置、及び、ロボット | |
| JP2008092789A (ja) | ブラシレス発電機 | |
| JP2009189225A (ja) | 電動機の駆動制御回路 | |
| JP5771857B1 (ja) | モータ及びモータ制御方法 | |
| JP5510493B2 (ja) | 電気機械装置 | |
| JP5498910B2 (ja) | 電動機の駆動制御方法 | |
| JP6060296B1 (ja) | 定電流制御によるスイッチドリラクタンスモータ装置 | |
| Wahyu et al. | PWM Control Strategy of Regenerative Braking to Maximize The Charging Current into The Battery in SRM Drive | |
| Lee et al. | Evaluation of slotless permanent synchronous motor with toroidal winding | |
| JP5359015B2 (ja) | モータの制御装置、制御方法、ロボット及び移動体 | |
| Awari et al. | Speed control and electrical braking of axial flux BLDC motor | |
| Dewi et al. | The Impact of SRM Rotor Speed on Regenerative Braking to Optimize the Performance | |
| Chandran et al. | Simulation of Stepper Motor using Quasi Square Wave Input | |
| Rezal et al. | Rotating analysis of 18-slot/16-pole permanent magnet synchronous motor for light electric vehicle using FEM | |
| Gladyshev et al. | Hardware and Software Technology in Design Electrical DC and AC Machines with Wireless Rotor |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120903 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120903 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131016 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131022 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131210 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140225 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140310 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5510493 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| S131 | Request for trust registration of transfer of right |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313135 |
|
| SZ02 | Written request for trust registration |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313Z02 |
|
| S131 | Request for trust registration of transfer of right |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313135 |
|
| SZ02 | Written request for trust registration |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313Z02 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
| SZ03 | Written request for cancellation of trust registration |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313Z03 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |