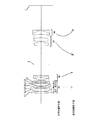JP2005292345A - 防振機能を有するマクロレンズ - Google Patents
防振機能を有するマクロレンズ Download PDFInfo
- Publication number
- JP2005292345A JP2005292345A JP2004105429A JP2004105429A JP2005292345A JP 2005292345 A JP2005292345 A JP 2005292345A JP 2004105429 A JP2004105429 A JP 2004105429A JP 2004105429 A JP2004105429 A JP 2004105429A JP 2005292345 A JP2005292345 A JP 2005292345A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- lens
- lens group
- object side
- group
- positive
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Landscapes
- Lenses (AREA)
- Adjustment Of Camera Lenses (AREA)
Abstract
【課題】 フィルム又は固体撮像素子を用いる一眼レフカメラに適し、絶対値が0.5倍より大きい撮影倍率と10度以上の半画角を有し、諸収差を良好に補正可能でオートフォーカスに適した、防振機能を有するマクロレンズを提供する。
【解決方法】正の第1群G1を最も物体側に有し、第1群G1の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、遠距離から近距離へのフォーカシングに際し第1群G1は光軸方向に固定されており前記少なくとも2つのレンズ群は移動し、第1群G1は物体側から順に正の第1−1群G11と正の第1−2群G12と負の第1−3群G13とからなり、第1−2群G12を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面I上の像ぶれを補正し、所定の条件式を満足する。
【選択図】図1
【解決方法】正の第1群G1を最も物体側に有し、第1群G1の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、遠距離から近距離へのフォーカシングに際し第1群G1は光軸方向に固定されており前記少なくとも2つのレンズ群は移動し、第1群G1は物体側から順に正の第1−1群G11と正の第1−2群G12と負の第1−3群G13とからなり、第1−2群G12を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面I上の像ぶれを補正し、所定の条件式を満足する。
【選択図】図1
Description
本発明は、フィルム又は固体撮像素子を用いる一眼レフカメラ用の撮影レンズに関し、特に、光学系の一部を光軸と直交する方向に移動させることによって画像のぶれを補正する防振機能を有するマクロレンズに関する。
従来、防振機能を有するマクロレンズが提案されている(例えば、特許文献1,2,3,4参照。)。
特開平9−218349号公報
特開平7−261127号公報
特開平7−261126号公報
特開2003-322797号公報
しかしながら、上記特許文献1,3に開示されているレンズは、質量が大きくなりがちな最も物体側のレンズ群をフォーカシングに際して移動する構成である。このため、オートフォーカスの際のレンズの駆動速度を高速化することが困難であるという問題がある。また、上記特許文献1に開示されているレンズは、フォーカシングに際して、合焦レンズ群と共に防振機構も移動させなければならない構成である。このため、オートフォーカスの際のレンズの駆動速度を高速化することがより困難であるという問題がある。
また、上記特許文献2に開示されているレンズは、半画角が小さく、後述する本発明の目的である10°以上の画角を得ることができないという問題がある。
また、上記特許文献4に開示されているレンズは、フォーカシングに際して、最も物体側のレンズ群が固定であり、合焦レンズ群と共に防振機構を移動させることも不要の構成である。しかしながら、半画角が小さく、本発明の目的である10°以上の画角を得ることができないという問題がある。また、当該レンズにおいて大きな画角を得ようとすれば、偏心収差を十分に補正することができなくなってしまうという問題がある。
また、上記特許文献2に開示されているレンズは、半画角が小さく、後述する本発明の目的である10°以上の画角を得ることができないという問題がある。
また、上記特許文献4に開示されているレンズは、フォーカシングに際して、最も物体側のレンズ群が固定であり、合焦レンズ群と共に防振機構を移動させることも不要の構成である。しかしながら、半画角が小さく、本発明の目的である10°以上の画角を得ることができないという問題がある。また、当該レンズにおいて大きな画角を得ようとすれば、偏心収差を十分に補正することができなくなってしまうという問題がある。
そこで本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、フィルム又は固体撮像素子を用いる一眼レフカメラに適し、絶対値が0.5倍より大きい撮影倍率と10度以上の半画角を有し、諸収差を良好に補正可能でオートフォーカスに適した、防振機能を有するマクロレンズを提供することを目的とする。
上記課題を解決するために本発明は、
正の屈折力を有する第1レンズ群を最も物体側に有し、前記第1レンズ群の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記少なくとも2つのレンズ群は移動し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式(1),(2)を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズを提供する。
(1)0.5<|M| (M<0)
(2)10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
正の屈折力を有する第1レンズ群を最も物体側に有し、前記第1レンズ群の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記少なくとも2つのレンズ群は移動し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式(1),(2)を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズを提供する。
(1)0.5<|M| (M<0)
(2)10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
また本発明は、
物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とを有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔が減少し、前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が増大し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式(1),(2)を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズを提供する。
(1)0.5<|M| (M<0)
(2)10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とを有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔が減少し、前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が増大し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式(1),(2)を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズを提供する。
(1)0.5<|M| (M<0)
(2)10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
本発明によれば、フィルム又は固体撮像素子を用いる一眼レフカメラに適し、絶対値が0.5倍より大きい撮影倍率と10度以上の半画角を有し、諸収差を良好に補正可能でオートフォーカスに適した、防振機能を有するマクロレンズを提供することができる。
本発明の防振機能を有するマクロレンズは、正の屈折力を有する第1レンズ群を最も物体側に有し、前記第1レンズ群の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記少なくとも2つのレンズ群が移動するように構成されている。
このように最も物体側の第1レンズ群を固定とすることによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズはオートフォーカシングの高速化を実現することが可能である。また、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群は光軸方向に固定されており、少なくとも2つのレンズ群が移動することによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズは無限遠撮影状態から最近接撮影状態までの全範囲において良好な結像性能を達成することができる。
このように最も物体側の第1レンズ群を固定とすることによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズはオートフォーカシングの高速化を実現することが可能である。また、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群は光軸方向に固定されており、少なくとも2つのレンズ群が移動することによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズは無限遠撮影状態から最近接撮影状態までの全範囲において良好な結像性能を達成することができる。
又は、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とを有し、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔が減少し、前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が増大するように構成されている。
このように最も物体側の第1レンズ群を固定とすることによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズはオートフォーカシングの高速化を実現することが可能である。また、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群は光軸方向に固定されており、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が増大し、第2レンズ群と第3レンズ群との間隔が減少し、第3レンズ群と第4レンズ群との間隔が増大することによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズは無限遠撮影状態から最近接撮影状態までの全範囲において良好な結像性能を達成することができる。
このように最も物体側の第1レンズ群を固定とすることによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズはオートフォーカシングの高速化を実現することが可能である。また、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群は光軸方向に固定されており、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が増大し、第2レンズ群と第3レンズ群との間隔が減少し、第3レンズ群と第4レンズ群との間隔が増大することによって、本発明の防振機能を有するマクロレンズは無限遠撮影状態から最近接撮影状態までの全範囲において良好な結像性能を達成することができる。
さらに、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、前記第1レンズ群が、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、以下の条件式(1),(2)を満足するように構成されている。
(1) 0.5<|M| (M<0)
(2) 10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
(1) 0.5<|M| (M<0)
(2) 10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度)
フォーカシングに際して固定の第1レンズ群中に、ぶれ補正用のレンズ群を設けることによって、フォーカシングの際にぶれ補正機構を移動させることが不要となるため、レンズ全体の小型化と簡素化を効果的に図ることができる。また、第1レンズ群を正・正・負の3つのレンズ群に分割し、中央の第1−2レンズ群のみをぶれ補正用のレンズ群とすることによって、該ぶれ補正用のレンズ群の軽量化を図ることができ、ぶれ補正機構の負荷を効果的に軽減させることができる。さらに、上述のような屈折力配分により、防振係数(ぶれ補正時のぶれ補正用のレンズ群の移動量に対する結像面における像の移動量の比)を適正に保ちつつ、ぶれ補正のために補正用のレンズ群が偏心したときの結像性能の劣化を軽減することが可能となる。
上記条件式(1)は、本発明の防振機能を有するマクロレンズの最近接撮影状態における撮影倍率を規定する条件式である。条件式(1)の下限値を下回ると、撮影倍率の絶対値が小さくなるため、マクロレンズとして不十分な撮影倍率となってしまう。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(1)の下限値を0.75にすることが望ましい。
上記条件式(2)は、本発明の防振機能を有するマクロレンズの無限遠撮影状態における半画角を規定する条件式である。条件式(2)の下限値を下回ると、画角が小さくなり、汎用のマクロレンズとしての使い勝手が悪くなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(2)の下限値を11にすることが望ましい。
上記条件式(2)は、本発明の防振機能を有するマクロレンズの無限遠撮影状態における半画角を規定する条件式である。条件式(2)の下限値を下回ると、画角が小さくなり、汎用のマクロレンズとしての使い勝手が悪くなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(2)の下限値を11にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、以下の条件式(3),(4),(5),(6)を満足することが望ましい。
(3) 0.45<f1/f<0.65
(4) −0.55<f2/f<−0.30
(5) 0.35<f3/f<0.55
(6) −1.30<f4/f<−0.85
ただし、
f :無限遠合焦状態における前記マクロレンズ全系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f2:前記第2レンズ群の焦点距離
f3:前記第3レンズ群の焦点距離
f4:前記第4レンズ群の焦点距離
(3) 0.45<f1/f<0.65
(4) −0.55<f2/f<−0.30
(5) 0.35<f3/f<0.55
(6) −1.30<f4/f<−0.85
ただし、
f :無限遠合焦状態における前記マクロレンズ全系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f2:前記第2レンズ群の焦点距離
f3:前記第3レンズ群の焦点距離
f4:前記第4レンズ群の焦点距離
上記条件式(3),(4),(5),(6)は、一眼レフカメラ用のマクロレンズとして十分なバックフォーカス、十分な最大撮影倍率(撮影倍率Mの絶対値が最大となる)、及び無限遠撮影状態から最近接撮影状態までの良好な結像性能を実現しつつ、レンズを小型に構成するために、各レンズ群の焦点距離を規定する条件式である。
条件式(3),(4),(5),(6)のいずれかの上限値又は下限値を越えると、前述の特徴を達成することが困難となってしまうため好ましくない。
なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(3)の上限値を0.62にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(3)の下限値を0.50にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(4)の上限値を−0.34にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(4)の下限値を−0.50にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(5)の上限値を0.51にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(5)の下限値を0.39にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(6)の上限値を−0.88にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(6)の下限値を−1.10にすることが望ましい。
条件式(3),(4),(5),(6)のいずれかの上限値又は下限値を越えると、前述の特徴を達成することが困難となってしまうため好ましくない。
なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(3)の上限値を0.62にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(3)の下限値を0.50にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(4)の上限値を−0.34にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(4)の下限値を−0.50にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(5)の上限値を0.51にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(5)の下限値を0.39にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(6)の上限値を−0.88にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(6)の下限値を−1.10にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、以下の条件式(7),(8),(9)を満足することが望ましい。
(7) 1.30<f1−1/f1<1.90
(8)1.30<f1−2/f1<1.70
(9) −6.00<f1−3/f1<−2.50
ただし、
f1 :前記第1レンズ群の焦点距離
f1−1:前記第1−1レンズ群の焦点距離
f1−2:前記第1−2レンズ群の焦点距離
f1−3:前記第1−3レンズ群の焦点距離
(7) 1.30<f1−1/f1<1.90
(8)1.30<f1−2/f1<1.70
(9) −6.00<f1−3/f1<−2.50
ただし、
f1 :前記第1レンズ群の焦点距離
f1−1:前記第1−1レンズ群の焦点距離
f1−2:前記第1−2レンズ群の焦点距離
f1−3:前記第1−3レンズ群の焦点距離
上記条件式(7),(8),(9)は、正の屈折力を有する第1−2レンズ群(ぶれ補正用のレンズ群)を光軸と直交する方向に移動(偏心移動)させることによって防振を行う際に、防振係数を適正に保つための条件式である。防振係数の絶対値の適切な範囲は、0.7〜2.5程度である。防振係数の絶対値が0.7より小さい場合、ぶれ補正時のぶれ補正用のレンズ群の移動量を大きくしなければならない。このため、ぶれ補正のためのレンズ駆動機構の大型化を招くこととなってしまうため好ましくない。一方、防振係数の絶対値が2.5より大きい場合、ぶれ補正時のレンズ駆動誤差の像面に及ぼす影響が大きくなってしまうため好ましくない。
条件式(7),(8)のいずれかの上限値又は下限値を越えると、防振係数の絶対値を前述の適切な範囲に設定することが困難となってしまうため好ましくない。
なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(7)の上限値を1.80にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(7)の下限値を1.40にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(8)の上限値を1.60にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(8)の下限値を1.40にすることが望ましい。
条件式(9)は、正の屈折力を有する第1−2レンズ群を光軸と直交する方向に移動させることによって防振を行う際に、レンズ偏心時の結像性能の劣化を抑えるための条件式である。負の屈折力を有する第1−3レンズ群は、ぶれ補正用の第1−2レンズ群が偏心することによって生じる収差(偏心収差)を打ち消す作用を担うレンズ群であり、条件式(9)の上限値又は下限値を越えると、第1−2レンズ群の偏心収差を第1−3レンズ群で打ち消すように収差のバランスをとることが困難となってしまう。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(9)の上限値を−2.70にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(9)の下限値を−5.80にすることが望ましい。
なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(7)の上限値を1.80にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(7)の下限値を1.40にすることが望ましい。
また、本発明の効果を確実にするために、条件式(8)の上限値を1.60にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(8)の下限値を1.40にすることが望ましい。
条件式(9)は、正の屈折力を有する第1−2レンズ群を光軸と直交する方向に移動させることによって防振を行う際に、レンズ偏心時の結像性能の劣化を抑えるための条件式である。負の屈折力を有する第1−3レンズ群は、ぶれ補正用の第1−2レンズ群が偏心することによって生じる収差(偏心収差)を打ち消す作用を担うレンズ群であり、条件式(9)の上限値又は下限値を越えると、第1−2レンズ群の偏心収差を第1−3レンズ群で打ち消すように収差のバランスをとることが困難となってしまう。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(9)の上限値を−2.70にすることが望ましい。また、本発明の効果を確実にするために、条件式(9)の下限値を−5.80にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、前記第1−2レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、物体側に凸面を向けた正レンズとからなり、以下の条件式(10)を満足することが望ましい。
(10) 15<ν12p−ν12n
ただし、
ν12p:前記第1−2レンズ群における前記正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n:前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
(10) 15<ν12p−ν12n
ただし、
ν12p:前記第1−2レンズ群における前記正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n:前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
上記条件式(10)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生しやすい回転非対称な倍率色収差を軽減するための条件式である。条件式(10)の下限値を下回ると、偏心による倍率色収差の発生が増加することとなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(10)の下限値を17にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、前記第1−3レンズ群中の最も物体側のレンズ面が凹面であることが望ましい。これにより、第1−2レンズ群が偏心した際の偏心収差の発生を効果的に抑制することができる。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、前記第1−3レンズ群は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと物体側に凹面を向けた負レンズとの接合レンズからなり、以下の条件式(11),(12)を満足することが望ましい。
(11) 0.25<N13n−N13p
(12) 25<ν13p−ν13n
ただし、
N13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
N13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
ν13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
(11) 0.25<N13n−N13p
(12) 25<ν13p−ν13n
ただし、
N13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
N13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
ν13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
前述のように、第1−3レンズ群を、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと物体側に凹面を向けた負レンズとの接合レンズで構成することにより、第1−2レンズ群が偏心した際の偏心収差の発生を効果的に抑制することができる。
上記条件式(11)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生する偏心収差のうち、回転非対称な非点収差及び像面の傾きを軽減するための条件式である。条件式(11)の下限値を下回ると、偏心時の非点収差及び像面の傾きの発生が大きくなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(11)の下限値を0.27にすることが望ましい。
上記条件式(12)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生する偏心収差のうち、回転非対称な倍率色収差を軽減するための条件式である。条件式(12)の下限値を下回ると、偏心時の倍率色収差の発生が大きくなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(12)の下限値を30にすることが望ましい。
上記条件式(11)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生する偏心収差のうち、回転非対称な非点収差及び像面の傾きを軽減するための条件式である。条件式(11)の下限値を下回ると、偏心時の非点収差及び像面の傾きの発生が大きくなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(11)の下限値を0.27にすることが望ましい。
上記条件式(12)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生する偏心収差のうち、回転非対称な倍率色収差を軽減するための条件式である。条件式(12)の下限値を下回ると、偏心時の倍率色収差の発生が大きくなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(12)の下限値を30にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズにおいて、前記第1−2レンズ群は、物体側から順に、第1正レンズと、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、物体側に凸面を向けた第2正レンズとからなり、以下の条件式(13)を満足することが望ましい。
(13) 15<ν12p2−ν12n
ただし、
ν12p2:前記第1−2レンズ群における前記第2正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n :前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
(13) 15<ν12p2−ν12n
ただし、
ν12p2:前記第1−2レンズ群における前記第2正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n :前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
上記条件式(13)は、第1−2レンズ群が偏心した際に発生しやすい回転非対称な倍率色収差を軽減するための条件式である。条件式(13)の下限値を下回ると、偏心時の倍率色収差の発生が大きくなってしまうため好ましくない。なお、本発明の効果を確実にするために、条件式(13)の下限値を20にすることが望ましい。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズは、前記第1−3レンズ群中の最も物体側のレンズ面が凹面であることが望ましい。これにより、第1−2レンズ群が偏心した際の偏心収差の発生を効果的に抑制することができる。
本発明の好ましい態様によれば、本発明の防振機能を有するマクロレンズにおいて、前記第1−1レンズ群は、物体側から順に、2枚の両凸形状の正レンズと、両凹形状の負レンズとからなることが望ましい。これにより、無限遠撮影状態から近接撮影状態までの全域で諸収差を効果的に補正し、第1−2レンズ群がぶれ補正のために偏心した際の偏心収差の発生を効果的に軽減することができる。
本発明の防振機能を有するマクロレンズにおいて、第4レンズ群を正の屈折力を有するレンズ群で構成することもできる。尚、第4レンズ群を正の屈折力を有するレンズ群で構成するよりも負の屈折力を有するレンズ群で構成する方が、レンズ全長を短くすることができるため、レンズの小型化を図る上でより好ましい。
以下、添付図面に基づき本発明の各実施例に係る防振機能を有するマクロレンズについて詳細に説明する。
(第1実施例)
図1は、本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図1に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシング(無限遠撮影状態から最近接撮影状態へのフォーカシング)に際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
(第1実施例)
図1は、本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図1に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシング(無限遠撮影状態から最近接撮影状態へのフォーカシング)に際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群G11と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群G12と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群G13とからなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL6と両凹形状の負レンズL7との接合レンズからなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL6と両凹形状の負レンズL7との接合レンズからなる。
第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、両凹形状の負レンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの接合レンズとからなる。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
以下の表1に、本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの諸元の値を掲げる。
(全体諸元)において、fは焦点距離、FNOはFナンバー、ωは半画角をそれぞれ示す。
(レンズデータ)において、第1カラムの面番号は物体側からのレンズ面の順序、第2カラムのrはレンズ面の曲率半径、第3カラムのdはレンズ面の間隔、第4カラムのνはd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数、第5カラムのnはd線(λ=587.6nm)に対する屈折率をそれぞれ示す。また、∞は平面、B.f.はバックフォーカスをそれぞれ示し、空気の屈折率1.0000はその記載を省略している。
(全体諸元)において、fは焦点距離、FNOはFナンバー、ωは半画角をそれぞれ示す。
(レンズデータ)において、第1カラムの面番号は物体側からのレンズ面の順序、第2カラムのrはレンズ面の曲率半径、第3カラムのdはレンズ面の間隔、第4カラムのνはd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数、第5カラムのnはd線(λ=587.6nm)に対する屈折率をそれぞれ示す。また、∞は平面、B.f.はバックフォーカスをそれぞれ示し、空気の屈折率1.0000はその記載を省略している。
(フォーカシングデータ)には、無限遠撮影状態、中間距離撮影状態、及び最近接撮影状態における焦点距離f又は撮影倍率M、及び可変間隔の値を示す。D0は物体から第1レンズ面までの距離、Rは物体から像面Iまでの距離、B.f.はバックフォーカスの値をそれぞれ示す。
ここで、以下の各実施例の全ての諸元値において掲載されている焦点距離f、曲率半径r、その他長さの単位は一般に「mm」が使われる。しかし光学系は、比例拡大または比例縮小しても同等の光学性能が得られるため、単位は「mm」に限られるものではない。
なお、以下の全実施例の諸元値においても、本実施例と同様の符号を用いる。
ここで、以下の各実施例の全ての諸元値において掲載されている焦点距離f、曲率半径r、その他長さの単位は一般に「mm」が使われる。しかし光学系は、比例拡大または比例縮小しても同等の光学性能が得られるため、単位は「mm」に限られるものではない。
なお、以下の全実施例の諸元値においても、本実施例と同様の符号を用いる。
[表1]
(全体諸元)
f =104.827
FNO= 2.85
ω = 11.70°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 140.5916 4.3340 46.58 1.804000
2 -304.6651 0.1500
3 54.5339 7.0903 81.61 1.497000
4 -141.0659 1.4000 34.96 1.801000
5 178.5483 1.5000
6 87.9941 1.4000 25.68 1.784720
7 40.9414 0.3802
8 42.5295 5.2680 46.58 1.804000
9 -324.5205 1.5000
10 -274.0591 2.1413 81.61 1.497000
11 -88.0305 1.4000 42.24 1.799520
12 2141.7521 (d12)
13 1611.2683 1.4000 46.58 1.804000
14 33.2052 3.2301
15 -127.8824 1.4000 44.89 1.639300
16 29.3525 3.5793 23.78 1.846660
17 267.1938 (d17)
18 ∞ (d18) 開口絞りS
19 274.8906 3.3516 53.22 1.693500
20 -61.4091 5.2348
21 109.5104 5.0407 46.58 1.804000
22 -41.5391 1.6000 23.78 1.846660
23 -302.2037 (d23)
24 -51.6011 3.1074 23.78 1.846660
25 -30.9388 1.6000 35.30 1.592700
26 247.6195 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.82690 -0.50000 -0.97000
D0 ∞ 239.4083 149.0777
d12 1.60000 10.97819 20.78241
d17 21.28241 11.90423 2.10000
d18 20.81507 10.08499 4.10180
d23 5.00000 16.49996 32.90816
B.f. 53.19468 52.42478 41.99975
R ∞ 397.40811 307.07749
(全体諸元)
f =104.827
FNO= 2.85
ω = 11.70°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 140.5916 4.3340 46.58 1.804000
2 -304.6651 0.1500
3 54.5339 7.0903 81.61 1.497000
4 -141.0659 1.4000 34.96 1.801000
5 178.5483 1.5000
6 87.9941 1.4000 25.68 1.784720
7 40.9414 0.3802
8 42.5295 5.2680 46.58 1.804000
9 -324.5205 1.5000
10 -274.0591 2.1413 81.61 1.497000
11 -88.0305 1.4000 42.24 1.799520
12 2141.7521 (d12)
13 1611.2683 1.4000 46.58 1.804000
14 33.2052 3.2301
15 -127.8824 1.4000 44.89 1.639300
16 29.3525 3.5793 23.78 1.846660
17 267.1938 (d17)
18 ∞ (d18) 開口絞りS
19 274.8906 3.3516 53.22 1.693500
20 -61.4091 5.2348
21 109.5104 5.0407 46.58 1.804000
22 -41.5391 1.6000 23.78 1.846660
23 -302.2037 (d23)
24 -51.6011 3.1074 23.78 1.846660
25 -30.9388 1.6000 35.30 1.592700
26 247.6195 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.82690 -0.50000 -0.97000
D0 ∞ 239.4083 149.0777
d12 1.60000 10.97819 20.78241
d17 21.28241 11.90423 2.10000
d18 20.81507 10.08499 4.10180
d23 5.00000 16.49996 32.90816
B.f. 53.19468 52.42478 41.99975
R ∞ 397.40811 307.07749
図2(a),(b)は、それぞれ本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの無限遠撮影状態における諸収差図、無限遠撮影状態において0.3°の回転ぶれに対するぶれ補正を行ったときのメリディオナル横収差図である。
なお、レンズ全系の焦点距離がfで防振係数がKのレンズによって角度θの回転ぶれを補正するためには、ぶれ補正用の移動レンズ群を(f・tanθ)/Kだけ光軸と直交する方向に移動させればよい。本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は104.827mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.549mmとなる。
図3(a),(b)は、それぞれ本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
なお、レンズ全系の焦点距離がfで防振係数がKのレンズによって角度θの回転ぶれを補正するためには、ぶれ補正用の移動レンズ群を(f・tanθ)/Kだけ光軸と直交する方向に移動させればよい。本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は104.827mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.549mmとなる。
図3(a),(b)は、それぞれ本発明の第1実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
各収差図において、FNOはFナンバー、NAは開口数、Yは像高、ωは半画角をそれぞれ示す。尚、球面収差図では最大口径に対応するFナンバーの値又は開口数の最大値を示し、非点収差図及び歪曲収差図では像高の最大値をそれぞれ示し、コマ収差図では各像高の値又は半画角の最大値を示す。また、各収差図において、dはd線(λ=587.6nm)、gはg線(λ=435.8nm)、CはC線(λ=656.3nm)、FはF(λ=486.1nm)の収差曲線をそれぞれ示す。さらに、非点収差図において、実線はサジタル像面、破線はメリディオナル像面をそれぞれ示す。
尚、以下に示す各実施例の諸収差図において、本実施例と同様の符号を用いる。
尚、以下に示す各実施例の諸収差図において、本実施例と同様の符号を用いる。
各諸収差図より本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、諸収差を良好に補正し、優れた結像性能を有していることがわかる。
(第2実施例)
図4は、本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図4に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するよう第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
図4は、本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図4に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するよう第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群G11と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群G12と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群G13とからなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL6と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7との接合レンズからなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL6と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7との接合レンズからなる。
第2レンズ群G2は、物体側から順に、両凹形状の負レンズと、両凹形状の負レンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの接合レンズとからなる。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
以下の表2に、本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの諸元の値を掲げる。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
以下の表2に、本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの諸元の値を掲げる。
[表2]
(全体諸元)
f =105.000
FNO= 2.85
ω = 11.52°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 160.9098 3.2362 46.58 1.804000
2 -287.7316 0.1500
3 65.4186 5.4325 81.61 1.497000
4 -136.0738 1.4000 34.96 1.801000
5 277.8526 1.5000
6 101.9973 1.4000 28.46 1.728250
7 37.4467 0.5916
8 41.0414 5.0321 46.58 1.804000
9 -234.2370 1.5000
10 -214.7813 1.4025 70.24 1.487490
11 -117.6717 1.4000 34.96 1.801000
12 -1063.9287 (d12)
13 -321.8144 1.4000 43.73 1.605620
14 32.4637 3.6142
15 -136.7087 1.4000 59.78 1.522490
16 32.7427 3.1300 23.78 1.846660
17 127.8432 (d17)
18 ∞ (d18) 開口絞りS
19 279.3120 5.5835 46.58 1.804000
20 -67.9776 2.2265
21 105.4067 7.0801 46.58 1.804000
22 -43.3608 1.4000 23.78 1.846660
23 650.5805 (d23)
24 -91.6307 6.7960 25.43 1.805180
25 -29.1696 1.4000 34.96 1.801000
26 630.9231 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.99987 -0.50000 -0.97000
D0 ∞ 229.8760 134.8999
d12 1.60000 10.95681 21.43967
d17 21.93967 12.58286 2.10000
d18 36.76024 21.92349 14.63106
d23 5.00000 14.84868 32.75400
B.f. 47.62396 52.61194 41.99870
R ∞ 399.87506 304.89861
(全体諸元)
f =105.000
FNO= 2.85
ω = 11.52°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 160.9098 3.2362 46.58 1.804000
2 -287.7316 0.1500
3 65.4186 5.4325 81.61 1.497000
4 -136.0738 1.4000 34.96 1.801000
5 277.8526 1.5000
6 101.9973 1.4000 28.46 1.728250
7 37.4467 0.5916
8 41.0414 5.0321 46.58 1.804000
9 -234.2370 1.5000
10 -214.7813 1.4025 70.24 1.487490
11 -117.6717 1.4000 34.96 1.801000
12 -1063.9287 (d12)
13 -321.8144 1.4000 43.73 1.605620
14 32.4637 3.6142
15 -136.7087 1.4000 59.78 1.522490
16 32.7427 3.1300 23.78 1.846660
17 127.8432 (d17)
18 ∞ (d18) 開口絞りS
19 279.3120 5.5835 46.58 1.804000
20 -67.9776 2.2265
21 105.4067 7.0801 46.58 1.804000
22 -43.3608 1.4000 23.78 1.846660
23 650.5805 (d23)
24 -91.6307 6.7960 25.43 1.805180
25 -29.1696 1.4000 34.96 1.801000
26 630.9231 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.99987 -0.50000 -0.97000
D0 ∞ 229.8760 134.8999
d12 1.60000 10.95681 21.43967
d17 21.93967 12.58286 2.10000
d18 36.76024 21.92349 14.63106
d23 5.00000 14.84868 32.75400
B.f. 47.62396 52.61194 41.99870
R ∞ 399.87506 304.89861
図5(a),(b)は、それぞれ本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの無限遠撮影状態における諸収差図、無限遠撮影状態において0.3°の回転ぶれに対するぶれ補正を行ったときのメリディオナル横収差図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は105.000mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.550mmとなる。
図6(a),(b)は、それぞれ本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
各諸収差図より本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、諸収差を良好に補正し、優れた結像性能を有していることがわかる。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は105.000mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.550mmとなる。
図6(a),(b)は、それぞれ本発明の第2実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
各諸収差図より本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、諸収差を良好に補正し、優れた結像性能を有していることがわかる。
(第3実施例)
図7は、本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図7に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
図7は、本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズのレンズ構成を示す図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、図7に示すように、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、開口絞りSと、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そして、遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、第1レンズ群G1は固定であり、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、及び第4レンズ群G4が光軸方向へ移動する。また、開口絞りSは、フォーカシングに際して固定である。
第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群G11と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群G12と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群G13とからなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ(第1正レンズ)L4と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL5と、両凸形状の正レンズ(物体側に凸面を向けた第2正レンズ)L6とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7からなる。
第1−1レンズ群G11は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL1と、両凸形状の正レンズL2と両凹形状の負レンズL3との接合レンズとからなる。
第1−2レンズ群G12は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ(第1正レンズ)L4と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL5と、両凸形状の正レンズ(物体側に凸面を向けた第2正レンズ)L6とからなる。
第1−3レンズ群G13は、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7からなる。
第2レンズ群G2は、物体側から順に、両凹形状の負レンズと、両凹形状の負レンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの接合レンズとからなる。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
以下の表3に、本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの諸元の値を掲げる。
第3レンズ群G3は、物体側から順に、両凸形状の正レンズと、両凸形状の正レンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズとからなる。
第4レンズ群G4は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと両凹形状の負レンズとの接合レンズからなる。
そして、本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、第1−2レンズ群G12を光軸と直交する方向に移動させることによって像面I上の像ぶれを補正する。
以下の表3に、本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの諸元の値を掲げる。
[表3]
(全体諸元)
f =105.000
FNO= 2.85
ω = 11.66°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 147.7879 3.9184 46.58 1.804000
2 -296.1048 0.1500
3 58.5075 6.8986 81.61 1.497000
4 -124.7556 1.4000 39.59 1.804400
5 149.8247 1.5002
6 139.5959 1.6138 81.61 1.497000
7 243.1340 0.1500
8 52.9576 1.4000 29.23 1.721510
9 36.7443 0.5685
10 39.6374 5.5744 81.61 1.497000
11 -164.1215 1.5000
12 -144.5245 1.4000 46.58 1.804000
13 -311.0961 (d13)
14 -276.6564 1.4000 43.73 1.605620
15 29.3712 3.6395
16 -122.5927 1.4000 59.78 1.522490
17 30.4280 2.9973 23.78 1.846660
18 102.9754 (d18)
19 ∞ (d19) 開口絞りS
20 265.2287 5.9186 46.58 1.804000
21 -68.0413 0.1500
22 83.5879 6.6671 46.58 1.804000
23 -47.1455 1.9966 23.78 1.846660
24 312.6115 (d24)
25 -130.3529 6.9050 25.43 1.805180
26 -30.2822 2.2929 34.96 1.801000
27 198.3576 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.99984 -0.50000 -0.96999
D0 ∞ 234.8315 149.3573
d13 1.60000 12.32979 23.47702
d18 23.97702 13.24724 2.10000
d19 26.84396 18.00242 11.51048
d24 6.78573 18.81333 31.47179
B.f. 51.35180 48.16557 41.99865
R ∞ 404.83055 319.35595
(全体諸元)
f =105.000
FNO= 2.85
ω = 11.66°
(レンズデータ)
面番号 r d ν n
1 147.7879 3.9184 46.58 1.804000
2 -296.1048 0.1500
3 58.5075 6.8986 81.61 1.497000
4 -124.7556 1.4000 39.59 1.804400
5 149.8247 1.5002
6 139.5959 1.6138 81.61 1.497000
7 243.1340 0.1500
8 52.9576 1.4000 29.23 1.721510
9 36.7443 0.5685
10 39.6374 5.5744 81.61 1.497000
11 -164.1215 1.5000
12 -144.5245 1.4000 46.58 1.804000
13 -311.0961 (d13)
14 -276.6564 1.4000 43.73 1.605620
15 29.3712 3.6395
16 -122.5927 1.4000 59.78 1.522490
17 30.4280 2.9973 23.78 1.846660
18 102.9754 (d18)
19 ∞ (d19) 開口絞りS
20 265.2287 5.9186 46.58 1.804000
21 -68.0413 0.1500
22 83.5879 6.6671 46.58 1.804000
23 -47.1455 1.9966 23.78 1.846660
24 312.6115 (d24)
25 -130.3529 6.9050 25.43 1.805180
26 -30.2822 2.2929 34.96 1.801000
27 198.3576 (B.f.)
(フォーカシングデータ)
無限遠撮影状態 中間距離撮影状態 最近接撮影状態
f/M 104.99984 -0.50000 -0.96999
D0 ∞ 234.8315 149.3573
d13 1.60000 12.32979 23.47702
d18 23.97702 13.24724 2.10000
d19 26.84396 18.00242 11.51048
d24 6.78573 18.81333 31.47179
B.f. 51.35180 48.16557 41.99865
R ∞ 404.83055 319.35595
以下の表4に、上記各実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの条件式対応値を掲げる。
[表4]
(条件式対応値)
第1実施例 第2実施例 第3実施例
(1) 0.97 0.97 0.97
(2) 11.70 11.52 11.66
(3) 0.572 0.571 0.571
(4) -0.383 -0.449 -0.381
(5) 0.433 0.478 0.452
(6) -0.913 -0.956 -0.934
(7) 1.468 1.582 1.767
(8) 1.496 1.545 1.510
(9) -2.958 -3.985 -5.616
(10) 20.90 18.12 ---
(11) 0.30252 0.31351 ---
(12) 39.37 35.28 ---
(13) --- --- 52.38
[表4]
(条件式対応値)
第1実施例 第2実施例 第3実施例
(1) 0.97 0.97 0.97
(2) 11.70 11.52 11.66
(3) 0.572 0.571 0.571
(4) -0.383 -0.449 -0.381
(5) 0.433 0.478 0.452
(6) -0.913 -0.956 -0.934
(7) 1.468 1.582 1.767
(8) 1.496 1.545 1.510
(9) -2.958 -3.985 -5.616
(10) 20.90 18.12 ---
(11) 0.30252 0.31351 ---
(12) 39.37 35.28 ---
(13) --- --- 52.38
図8(a),(b)は、それぞれ本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの無限遠撮影状態における諸収差図、無限遠撮影状態において0.3°の回転ぶれに対するぶれ補正を行ったときのメリディオナル横収差図である。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は105.000mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.550mmとなる。
図9(a),(b)は、それぞれ本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
各諸収差図より本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、諸収差を良好に補正し、優れた結像性能を有していることがわかる。
本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズにおいては、第1−2レンズ群G12の防振係数を1.00としており、レンズ全系の焦点距離は105.000mmであるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第1−2レンズ群G12の移動量は、0.550mmとなる。
図9(a),(b)は、それぞれ本発明の第3実施例に係る防振機能を有するマクロレンズの中間距離撮影撮影状態(撮影倍率-0.5倍)における諸収差図、最近接撮影状態(撮影倍率-0.97倍)における諸収差図である。
各諸収差図より本実施例に係る防振機能を有するマクロレンズは、諸収差を良好に補正し、優れた結像性能を有していることがわかる。
上記各実施例によれば、フィルム又は固体撮像素子を用いる一眼レフカメラに適し、絶対値が0.5倍より大きい撮影倍率と10度以上の半画角を有し、フォーカシングに際して最も物体側のレンズ群が固定でオートフォーカスに適し、諸収差を良好に補正可能で、光学系の一部を光軸と直交する方向に移動させることによって画像のぶれを補正する防振機能を有するマクロレンズを実現できる。
G1 第1レンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
G11 第1−1レンズ群
G12 第1−2レンズ群
G13 第1−3レンズ群
S 開口絞り
I 像面
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
G11 第1−1レンズ群
G12 第1−2レンズ群
G13 第1−3レンズ群
S 開口絞り
I 像面
Claims (10)
- 正の屈折力を有する第1レンズ群を最も物体側に有し、前記第1レンズ群の像側に少なくとも2つのレンズ群を有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記少なくとも2つのレンズ群は移動し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズ。
0.5<|M| (M<0)
10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度) - 物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とを有し、
遠距離から近距離へのフォーカシングに際して、前記第1レンズ群は光軸方向に固定されており、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔が減少し、前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が増大し、
前記第1レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1−1レンズ群と、正の屈折力を有する第1−2レンズ群と、負の屈折力を有する第1−3レンズ群とからなり、
前記第1−2レンズ群を光軸と直交する方向へ移動させることによって像面上の像ぶれを補正し、
以下の条件式を満足することを特徴とする防振機能を有するマクロレンズ。
0.5<|M| (M<0)
10<ω
ただし、
M:最近接撮影状態における撮影倍率
ω:無限遠撮影状態における半画角(単位は度) - 以下の条件式を満足することを特徴とする請求項2に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
0.45<f1/f<0.65
−0.55<f2/f<−0.30
0.35<f3/f<0.55
−1.30<f4/f<−0.85
ただし、
f :無限遠合焦状態における前記マクロレンズ全系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f2:前記第2レンズ群の焦点距離
f3:前記第3レンズ群の焦点距離
f4:前記第4レンズ群の焦点距離 - 以下の条件式を満足することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
1.30<f1−1/f1<1.90
1.30<f1−2/f1<1.70
−6.00<f1−3/f1<−2.50
ただし、
f1 :前記第1レンズ群の焦点距離
f1−1:前記第1−1レンズ群の焦点距離
f1−2:前記第1−2レンズ群の焦点距離
f1−3:前記第1−3レンズ群の焦点距離 - 前記第1−2レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、物体側に凸面を向けた正レンズとからなり、
以下の条件式を満足することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
15<ν12p−ν12n
ただし、
ν12p:前記第1−2レンズ群における前記正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n:前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数 - 前記第1−3レンズ群中の最も物体側のレンズ面が凹面であることを特徴とする請求項5に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
- 前記第1−3レンズ群は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと物体側に凹面を向けた負レンズとの接合レンズからなり、
以下の条件式を満足することを特徴とする請求項6に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
0.25<N13n−N13p
25<ν13p−ν13n
ただし、
N13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
N13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対する屈折率
ν13p:前記第1−3レンズ群における前記正メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν13n:前記第1−3レンズ群における前記負レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数 - 前記第1−2レンズ群は、物体側から順に、第1正レンズと、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、物体側に凸面を向けた第2正レンズとからなり、
以下の条件式を満足することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
15<ν12p2−ν12n
ただし、
ν12p2:前記第1−2レンズ群における前記第2正レンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数
ν12n :前記第1−2レンズ群における前記負メニスカスレンズの硝材のd線(λ=587.6nm)に対するアッベ数 - 前記第1−3レンズ群中の最も物体側のレンズ面が凹面であることを特徴とする請求項8に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
- 前記第1−1レンズ群は、物体側から順に、2枚の両凸形状の正レンズと、両凹形状の負レンズとからなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の防振機能を有するマクロレンズ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004105429A JP2005292345A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 防振機能を有するマクロレンズ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2004105429A JP2005292345A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 防振機能を有するマクロレンズ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2005292345A true JP2005292345A (ja) | 2005-10-20 |
Family
ID=35325357
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2004105429A Withdrawn JP2005292345A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 防振機能を有するマクロレンズ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2005292345A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8681435B2 (en) | 2009-10-28 | 2014-03-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Macro lens system and pickup device including the same |
| KR101431539B1 (ko) * | 2008-01-11 | 2014-08-19 | 삼성전자주식회사 | 줌 렌즈 시스템 |
| JP2015215391A (ja) * | 2014-05-08 | 2015-12-03 | キヤノン株式会社 | 光学系及びそれを有する撮像装置 |
| US9417430B2 (en) | 2012-07-20 | 2016-08-16 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Inner focus lens system, interchangeable lens apparatus and camera system |
-
2004
- 2004-03-31 JP JP2004105429A patent/JP2005292345A/ja not_active Withdrawn
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101431539B1 (ko) * | 2008-01-11 | 2014-08-19 | 삼성전자주식회사 | 줌 렌즈 시스템 |
| US8681435B2 (en) | 2009-10-28 | 2014-03-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Macro lens system and pickup device including the same |
| US9417430B2 (en) | 2012-07-20 | 2016-08-16 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Inner focus lens system, interchangeable lens apparatus and camera system |
| JP2015215391A (ja) * | 2014-05-08 | 2015-12-03 | キヤノン株式会社 | 光学系及びそれを有する撮像装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4857576B2 (ja) | ズームレンズ | |
| JP5475401B2 (ja) | 防振機能を有する大口径望遠ズームレンズ | |
| JP5648907B2 (ja) | 変倍光学系、及び、光学機器 | |
| JP5176410B2 (ja) | 変倍光学系、光学装置、変倍光学系の変倍方法 | |
| JP4356040B2 (ja) | 防振機能を備えたバックフォーカスの長いズームレンズ | |
| JP2013097212A (ja) | インナーフォーカス式望遠レンズ | |
| JP3858305B2 (ja) | 像位置補正光学系 | |
| JP2009014766A (ja) | 変倍光学系、光学装置、変倍光学系の変倍方法 | |
| JP4635688B2 (ja) | 防振機能を有するズームレンズ | |
| WO2013146758A1 (ja) | 変倍光学系、光学装置、および変倍光学系の製造方法 | |
| JP4120647B2 (ja) | 防振機能を有するズームレンズ | |
| JP2018097101A (ja) | 撮像レンズおよび撮像装置 | |
| JP5544926B2 (ja) | 撮影レンズ、この撮影レンズを有する光学機器、及び、撮影レンズの製造方法 | |
| JP5157295B2 (ja) | 光学系、撮像装置、光学系の結像方法 | |
| JP5648900B2 (ja) | 変倍光学系、及び、この変倍光学系を有する光学機器 | |
| JP6152641B2 (ja) | ズームレンズ系及びこれを備えた電子撮像装置 | |
| JP2014098794A (ja) | 変倍光学系、光学装置、変倍光学系の製造方法 | |
| JP2015215557A (ja) | 光学系、光学装置、光学系の製造方法 | |
| JPH0727975A (ja) | 防振機能を備えたリアコンバージョンレンズ | |
| JP2005292338A (ja) | ズームレンズ | |
| JP5958018B2 (ja) | ズームレンズ、撮像装置 | |
| JP2020086159A (ja) | 光学系、光学機器及び光学系の製造方法 | |
| WO2014077120A1 (ja) | 変倍光学系、光学装置、変倍光学系の製造方法 | |
| JP4905429B2 (ja) | ズームレンズ | |
| JP2005292345A (ja) | 防振機能を有するマクロレンズ |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20070605 |