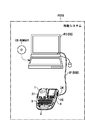JP2004013463A - メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 - Google Patents
メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2004013463A JP2004013463A JP2002165137A JP2002165137A JP2004013463A JP 2004013463 A JP2004013463 A JP 2004013463A JP 2002165137 A JP2002165137 A JP 2002165137A JP 2002165137 A JP2002165137 A JP 2002165137A JP 2004013463 A JP2004013463 A JP 2004013463A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- communication
- program
- copy
- storage area
- rewriting
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Landscapes
- Stored Programmes (AREA)
Abstract
【課題】RAMのアドレス範囲用の通信プログラムを利用して、指定可能アドレス範囲を広げることなく、その通信プログラム自体やそれを指定する通信割込ベクタを記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書込可能で、かつ、通信中に書き換えても正常に通信できるメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体を提供する。
【解決手段】書換可能ROMの通信コア情報の書換モードを設定し、通信コア情報のコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアをRAM内に設定して、通信コア情報のコピーであるコピーコア情報をコピー記憶エリアに記憶させ、コア記憶エリアとコピー記憶エリアとのメモリアクセスを、書換モードの設定の有無に従って相互に切り換え、書換モード時の通信プログラムの指定アドレスとして、書換モードでないときのコピー記憶エリアのアドレスを指定する。
【選択図】 図6
【解決手段】書換可能ROMの通信コア情報の書換モードを設定し、通信コア情報のコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアをRAM内に設定して、通信コア情報のコピーであるコピーコア情報をコピー記憶エリアに記憶させ、コア記憶エリアとコピー記憶エリアとのメモリアクセスを、書換モードの設定の有無に従って相互に切り換え、書換モード時の通信プログラムの指定アドレスとして、書換モードでないときのコピー記憶エリアのアドレスを指定する。
【選択図】 図6
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信割込に応じて起動される通信プログラムに従って通信先から新規データを受信し、その新規データによりメモリを書き換えるメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】
パソコンやワープロ等を初めとして、小型のテープ印刷装置や印章作成装置等を含む情報処理装置では、一般的に、各種の割込発生に応じて起動される割込処理プログラムやそれらの起動のために割込発生時に参照される割込ベクタ(ベクタテーブル等)などが、書換不可能ROM(マスクROM等)や外部から書換可能な書換可能ROM(フラッシュROM等)等に記憶されて用意される。ここで、後者の書換可能ROMは、仕様変更や論理的不具合(バグ)対策や機種毎のカスタマイズ等に対応しやすく、かつ近年の低価格化もあって、多用される傾向にある。また、通信機能を有する装置では、通信要求の割込(通信割込)に応じて起動された通信プログラムに従って通信が行われるが、この通信機能を利用して通信先より受信した新規データ(新規受信データ)により書換可能であることが要望されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、アドレス空間上、RAMに割り当てられたアドレスのエリアを指定して、その指定エリアに新規受信データを書き込むための通信プログラムが既存の場合、原理的には、指定可能なエリアのアドレスの範囲を、アドレス空間上の書換可能ROMのエリアにまで広げれば、その通信プログラムを利用して、書換可能ROMを書き換えることができる。
【0004】
ただし、通信割込用の割込ベクタ(通信割込ベクタ)や通信プログラムを記憶する書換可能ROMの場合、それらを通信中に書き換えてしまうと、その通信中に複数回の通信割込が必要なときに通信割込ベクタの内容(指定アドレス)が異なって通信プログラムの正常起動ができなくなったり、通信プログラムの処理フローが途中で途切れて正常動作しないなどの不具合が発生する可能性がある。かといって、通信割込ベクタや通信プログラムの記憶エリアへの書き込みを禁止したのでは、新規受信データにより書き換えたい旨の要望に答えられない。
【0005】
本発明は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、その通信プログラム自体やそれを指定する通信割込ベクタを記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができ、かつ、その通信プログラム自体や通信割込ベクタ自体を通信中に書き換えても正常に通信できるメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項1のメモリ書換装置は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMと、前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定手段と、前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー手段と、前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換手段と、前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定手段と、を備えたことを特徴とする。
【0007】
また、請求項13のメモリ書換方法は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、前記通信プログラムを利用して、前記通信先から受信された新規データを書き込むことにより、前記書換可能ROMを書き換えるメモリ書換方法であって、前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定工程と、前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー工程と、前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換工程と、前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定工程と、を備えたことを特徴とする。
【0008】
このメモリ書換装置およびメモリ書換方法では、通信プログラムとそれを通信割込に応じて起動するための通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、通信先から受信された新規データを書き込んで書き換える。この場合、書換可能ROMの少なくとも通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定し、書換可能ROM内の通信コア情報の記憶エリア(コア記憶エリア)に対応するコピー記憶エリアをRAM内に設定し、通信コア情報のコピーであるコピーコア情報をコピー記憶エリアに記憶させる。このため、この時点では、コア記憶エリアの内容とコピー記憶エリアの内容は同一となる。すなわち、コピー記憶エリアにもコア記憶エリアと同様の通信コア情報が記憶される。一方、アドレス空間におけるコア記憶エリアに対するメモリアクセスとコピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、書換モードの設定の有無に従って相互に切り換える。すなわち、書換モードの設定の有無に従って、アドレス空間上、コア記憶エリアとコピー記憶エリアを入れ換えることになるが、内容は同一なので、書換モードの設定の有無に拘わらず、通信プログラムや通信割込ベクタとして正常に参照される。ここで、通信プログラムは、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定するものではあるが、コピー記憶エリアのアドレスは、対象アドレスの範囲内なので指定することができる。すなわち、書換モードが設定されているときに、通信プログラムの指定アドレスとして、書換モードが設定されていないときのコピー記憶エリアのアドレスを指定することができ、それにより、その指定アドレスに通信先から受信された新規データを書き込むことができるが、実際には、書換モードが設定されているときには、その指定アドレスへのメモリアクセスは、書換可能ROMのコア記憶エリアへのアクセスとなるので、コア記憶エリアに対する書込みとなる。また、この書込みが実行されているときには、RAMのコピー記憶エリアにコピーされた通信コア情報が参照されているので、通信中に書換可能ROMへの書込みがあっても、正常に通信できる。したがって、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、その通信プログラム自体やそれを指定する通信割込ベクタを記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができ、かつ、その通信プログラム自体や通信割込ベクタ自体を通信中に書き換えても正常に通信できる。
【0009】
また、請求項1のメモリ書換装置において、前記書換可能ROMはフラッシュROMであることが好ましい。
【0010】
このメモリ書換装置では、書換可能ROMはフラッシュROMなので、割込処理プログラムや割込ベクタ等を記憶するためには、RAMより安定した記憶ができてる一方、近年の低価格化等の傾向にも適合している。
【0011】
また、請求項1または2のメモリ書換装置において、前記通信コア情報には、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの双方が含まれ、前記通信割込ベクタは相対アドレスに基づいており、前記通信コア情報コピー手段は、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの相対関係を保つように前記通信コア情報を前記RAMにコピーして、前記コピーコア情報として記憶させることが好ましい。
【0012】
このメモリ書換装置では、通信コア情報には、通信割込ベクタと通信プログラムとの双方が含まれ、通信割込ベクタは相対アドレスに基づいていて、通信割込ベクタと通信プログラムとの相対関係を保つように通信コア情報をRAMにコピーして、コピーコア情報として記憶させるので、通信割込ベクタをコピーした後に、その指定アドレスをコピープログラムの格納アドレスに合うように調整する必要がない。
【0013】
また、請求項1ないし3のいずれかのメモリ書換装置において、前記RAM内の先頭と前記コピー記憶エリアの相対関係が、前記書換可能ROM内の先頭とコア記憶エリアとの相対関係に一致し、前記メモリアクセス切換手段は、前記書換可能ROMと前記RAMとのメモリ切換手段を有することが好ましい。
【0014】
このメモリ書換装置では、RAM内の先頭と前記コピー記憶エリアの相対関係が、前記書換可能ROM内の先頭とコア記憶エリアとの相対関係に一致するので、書換可能ROMとRAMとのメモリ切換をしてから、コピー記憶エリアへの書込みを行えば、コア記憶エリアへの書込みとなる。このため、RAM用のアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができる。また、通信中に通信コア情報の書換があっても、書換可能ROMとRAMとのメモリ切換をした状態では、コア記録エリアからの通信コア情報の読出しの代わりに、コピー記憶エリアのコピーコア情報が読み出され、これは元の(書換前の)通信コア情報と同一内容なので、正常に通信できる。
【0015】
また、請求項4のメモリ書換装置において、前記書換可能ROMと前記RAMは、それぞれ1チップで構成され、前記メモリ切換手段は、チップセレクトによって各チップを切り換える手段であることが好ましい。
【0016】
このメモリ書換装置では、書換可能ROMと前記RAMは、それぞれ1チップで構成され、それぞれ1チップで構成されるので、チップセレクトによって各チップを切り換えることにより、メモリ切換ができる。
【0017】
また、請求項1ないし5のいずれかのメモリ書換装置において、前記通信プログラムによる通信は、RS−232C、USB、IEEE1394またはセントロニクスの規格に従ったものであることが好ましい。
【0018】
このメモリ書換装置では、通信プログラムによる通信は、RS−232C、USB、IEEE1394またはセントロニクスの規格に従ったものなので、その規格に従って通信して受信した新規データにより書換可能ROMを書き換えることができる。
【0019】
また、請求項7の情報処理装置は、請求項1ないし6のいずれか1項に記載の各手段と、前記書換可能ROMに記憶されたプログラムに従って処理を行うプログラム処理手段と、を備えたことを特徴とする。
【0020】
この情報処理装置は、上述したメモリ書換装置(の各手段)を備え、書換対象メモリに記憶されたプログラムに従って処理を行うので、各種処理が可能なほか、通信プログラムに従った通信により各種プログラムを新規データとして受信して格納できるので、アップデートしやすい情報処理装置となる。
【0021】
また、請求項7の情報処理装置において、所定の印刷対象物に印刷を行う印刷手段をさらに備え、前記複数の割込プログラムには、前記印刷手段に前記印刷を行わせるプログラムが含まれることが好ましい。
【0022】
この情報処理装置は、所定の印刷対象物に印刷を行う印刷手段をさらに備え、複数の割込プログラムには、印刷手段に印刷を行わせるプログラムが含まれるので、印刷装置に適用できる。
【0023】
また、請求項8の情報処理装置において、前記印刷対象物は、テープであることが好ましい。
【0024】
この情報処理装置は、印刷対象物は、テープなので、テープ印刷装置に適用できる。
【0025】
また、請求項10の情報処理システムは、請求項7ないし9のいずれかに記載の情報処理装置と、前記通信先として前記新規データを送信する供給装置と、を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【0026】
この情報処理システムでは、7ないし9のいずれかに記載の情報処理装置と、通信先として新規データを送信する供給装置と、を備えるので、供給装置側に格納する新規データを変更したり追加したりすることにより、情報処理装置側に送信する新規データを種々変更できる。
【0027】
また、請求項10の情報処理システムにおいて、前記供給装置は、前記新規データおよびそれを送信するためのプログラムを記憶した記憶媒体を装着可能な装着手段と、装着された前記記憶媒体内に記憶された前記プログラムに従って前記新規データを送信するプログラム実行手段と、を有することが好ましい。
【0028】
この情報処理システムでは、供給装置は、新規データおよびそれを送信するためのプログラムを記憶した記憶媒体を装着し、その記憶媒体内に記憶されたプログラムに従って新規データを送信することができるので、各種の新規データを記憶したその種の記憶媒体を装着するだけで、プログラムを実行して情報処理装置に新規データを送信でき、それによるアップデートができる。
【0029】
また、請求項10または11の情報処理システムにおいて、前記供給装置は、所定のネットワークを介して他の装置と接続され、前記他の装置から前記新規データを受信する上位通信手段を有することが好ましい。
【0030】
この情報処理システムでは、供給装置は、所定のネットワークを介して他の装置と接続され、他の装置から新規データを受信できるので、種々の新規データを受信して、情報処理装置側に送信することにより、情報処理装置を種々アップデートできる。
【0031】
また、請求項14の記憶媒体は、請求項1ないし9のいずれか1項に記載の各手段の機能を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする。
【0032】
また、請求項15の記憶媒体は、請求項13に記載のメモリ書換方法を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする。
【0033】
これらの記憶媒体に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、通信プログラムに従って通信先から受信した新規データを書き込むことができ、書換可能ROMの内容を書き換えることができる。
【0034】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係るテープ印刷装置について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【0035】
図1に示すように、まず、本実施形態のテープ印刷装置(情報処理装置)1は、データサーバDSとインタフェースIFを介して接続され、全体として印刷システム(情報処理システム)PSYSを構成している。データサーバDSは、テープ印刷装置1に対して、メモリ書換用の新規データ(ダウンロードデータ)を供給するものである。同図は単純な構成の例を示していて(後述の図10参照)、スタンドアロンのパソコンPCをデータサーバDSとし、そのパソコンPCとテープ印刷装置1とを、USB等のインタフェースIFで接続するだけで、印刷システムPSYSを構成する。
【0036】
ここで、テープ印刷装置1は、同図に示すように、装置ケース2により外殻が形成され、装置ケース2の前部上面には各種入力キーから成るキーボード3を備えている。後部上面には、その左部に開閉蓋21が取り付けられ、その右部にディスプレイ4が配設され、その側面には、図外の内部電源部に接続するACアダプタ接続口24(アダプタ省略)の他、(USBケーブルによる)インタフェースIFが接続されるUSBコネクタ25が配置されている。
【0037】
この場合、例えば図2に示すように、メモリに書き込むための新規データとしてパソコンPCに記憶されたデータをダウンロードする構成となる。もちろん、これらの場合、新規データを外部からコンパクトディスク(CD、CD−ROM)501等により供給することもできる。なお、インタフェースIFとしては、シリアルデータ通信(RS−232C、USB、IEEE1394等)でも、パラレルデータ通信(セントロニクス等)でも良い。また、これらは有線通信の規格であるが、無線通信を利用することも可能である。
【0038】
テープ印刷装置1は、メモリに関連する構成として、図3に示すように、各種制御の中枢となるCPU10と、インタフェースIFからUSBコネクタ25を介してデータサーバDSとCPU10との通信を司るUSBドライバ用のIC等から成るUSBインタフェースドライバ(USBドライバ)IFDと、メモリとして書換可能なフラッシュROM(本実施形態では16Mバイトを想定:以下単に「ROM」)20と、スタティックRAM(SRAM:以下単に「RAM」)30と、ROM20とRAM30との役割(メモリアクセス)を切り換えるメモリアクセス切換回路40と、を備えている。
【0039】
メモリアクセス切換回路40は、図4(a)に示すように、論理回路として構成され、メモリ切換情報記憶回路401と、各論理ゲートU1〜U8と、を有して、いわゆる選択回路(セレクタ)として構成されている。メモリ切換情報記憶回路401は、ROM30を書き換える書換モードか否かを記憶する回路であり、具体的には1ビットのフリップフロップやレジスタ内の1ビット等で構成でき、いわゆるフラグ等と呼ばれる回路で構成される。
【0040】
以下では、これを単に「書換モードフラグ」とし、書換モードフラグCF(の出力)=1のときに「書換モード」、0のときに「通常モード」とする。この書換モードフラグは、図6で後述のアドレスマップ上、I/Oマップ等と同様にアドレスが割り振られ、書換モードフラグCFへの例えば「1」の書込(セット)または「0」の書込(リセット)は、オペレーティングシステム(OS)上、その指定アドレスへの「1」または「0」の書込として扱われる。同図のチップセレクト信号CSSはその書込等の時に有効(イネーブル)となる信号である。
【0041】
この場合、同図のメモリアクセス切換回路40は、4個のアンド(AND)ゲートU1〜U4、2個のオア(OR)ゲートU5〜U6、2個のノット(NOT)ゲートU7〜U8により、図5に示すように、書換モードフラグCF=0の通常モードのときには、CPU10からのチップセレクト信号CS0がCSA(CS0→CSA)、チップセレクト信号CS1がCSB(CS1→CSB)となるように、チップセレクト信号(すなわちメモリアクセス)を切り換え、書換モードフラグCF=1の書換モードのときには、CS0→CSB、CS1→CSAとなるように、切り換える。
【0042】
なお、図4(b)は同一論理を実現する別の構成例を示し、同様のメモリ切換情報記憶回路401(書換モードフラグCF)と、ナンド(NAND)ゲートU1s〜U7sとアンド(AND)ゲートU8sを有する。ここで、アンドゲートU8sは論理上は省略可能であり、また、ナンドゲートU7sとアンドゲートU8sの代わりに、これらを合わせた論理のアンドナンドゲートU9sを使用しても良い。
【0043】
図3に示すように、テープ印刷装置1のメモリは、ROM20+RAM30により構成され、図2および図6に示すように、アドレス空間(アドレスマップ)上、プログラム等や制御用のデータを記憶する制御メモリエリア201と、ワーク用のワークメモリエリア301とに分けて使用される。
【0044】
図3〜図5で前述のCPU10からのチップセレクト信号CS0は、制御メモリエリア201へのメモリアクセス時にイネーブルとなる信号であり、チップセレクト信号CS1は、ワークメモリエリア301へのメモリアクセス時にイネーブルとなる信号である。また、メモリアクセス切換回路40から出力されるチップセレクト信号CSAは、ROM20へのメモリアクセスをイネーブルにする信号であり、チップセレクト信号CSBは、RAM30へのメモリアクセスをイネーブルにする信号である。
【0045】
通常モード時には、前述のように、CS0→CSA、CS1→CSBとなるので(図5参照)、ROM20が制御メモリエリア201を、RAM30がワークメモリエリア301を担当する。
【0046】
これらのうち、通信により書き込まれる対象エリアは、RAM30が担当するワークメモリエリア301側であり、図2に示すように、パソコンPC(すなわちデータDS)では、例えば書換用の新規データを記憶したCD−ROM501を装着(挿入)し、ダウンロード用の専用アプリケーション502を駆動して、テープ印刷装置1のワークメモリエリア301内の指定アドレスにより指定されたダウンロードデータ領域に新規データ(ダウンロードデータ)をダウンロードする。
【0047】
ところで、テープ印刷装置1では、図7に示すように、電源キーを押すこと(電源オン)等により処理が開始すると、まず、前回の電源オフ時の状態に戻すために、退避していた各制御フラグを復旧するなどの初期設定を行い(S1)、次に、前回の表示画面を初期画面として表示する(S2)。
【0048】
図7のその後の処理、すなわちキー入力か否かの判断分岐(S3)および各種割込処理(S4)は、概念的に示した処理である。実際には、テープ印刷装置1では、初期画面表示(S2)が終了すると、キー入力割込を許可し、キー入力割込が発生するまでは、そのままの状態を維持し(S3:No)、何らかのキー入力割込が発生すると(S3:Yes)、それぞれの割込処理に移行して(S4)、その割込処理が終了すると、再度、その状態を維持する(S3:No)。
【0049】
すなわち、テープ印刷装置1では、主な処理を割込処理により行う。例えば印刷画像作成などの準備ができていれば、ユーザが任意の時点で印刷キーを押すことにより、印刷処理割込が発生して、印刷処理が起動され、印刷画像データに基づいて印刷画像の印刷ができる。
【0050】
そして、図6に示すように、これら各種の割込の発生に応じて起動される割込処理プログラムおよびそれらの起動のために割込発生時に参照される割込ベクタ(ベクタテーブル等)V20などは、通常モード時にROM20が担当する制御メモリエリア201側に記憶されている。
【0051】
例えば図2で前述のダウンロード用の専用アプリケーションからの通信要求等は、図3で前述のUSBドライバIFDを介して通信割込としてCPU10の端子INTに入力され、CPU10では、その入力(割込要求)を受けて、割込ベクタV20を参照し、該当する通信プログラムP20の先頭アドレスを検出して、それを起動する。
【0052】
テープ印刷装置1では、大きなデータをダウンロードする場合、例えば64Kバイト毎程度に分割して送受信するので、一回(まとまった1個のデータ)の通信の間にも複数回の通信割込が発生し、通信プログラムP20が起動される。
【0053】
ところで、本実施形態のテープ印刷装置1では、通常はRAM30用に使用される上記のダウンロードにより、ROM20を書き換えることができるので、以下、この点について説明する。
【0054】
テープ印刷装置1のキーボード3は、ROM20を書き換える書換モードをセット(設定)するための書換モードキーを有し、この書換モードキーが押下されると、書換モード設定割込が発生して、図8に示すように、書換モード設定処理(S10)が起動され、まず、割込ベクタV20のコピーを行う(S11)。すなわち、図6に示す通常モード時において、制御メモリエリア201内にある割込ベクタV20を、ワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピーベクタV30とする(S11)。
【0055】
割込ベクタV20のコピー(S10)が終了すると、次に、必要プログラムのコピーを行う(S12)。ここでは、図6に示す通常モード時において制御メモリエリア201内にあり且つ通信中に起動させる必要のあるプログラム、例えば前述の通信プログラムP20などのプログラムを、ワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピープログラムP30とする(S12)。ここでは、説明の都合上、単に通信プログラムP20のみコピーしてコピープログラムP30とする。
【0056】
必要プログラムのコピー(S12)が終了すると、次に、書換モードをセットして(S13)、書換モード設定処理(S10)を終了する(S14)。具体的には、アドレス空間上、所定アドレスに設定された書換モードフラグCFへの「1」の書込(書換モードフラグCF←1)を行って(S13)、処理(S10)を終了する(S14)。
【0057】
書換モードが設定されると、すなわち書換モード時には、前述のように、CS0→CSB、CS1→CSAとなるので(図5参照)、図6に示すように、RAM30が制御メモリエリア201を、ROM20がワークメモリエリア301を担当する。
【0058】
これらのうち、通信により書き込まれる対象エリアは、ワークメモリエリア301側、すなわちROM20が担当する側であり、図2で前述のダウンロードは、テープ印刷装置1のワークメモリエリア301内の指定アドレスにより指定されたダウンロードデータ領域に新規データをダウンロードする。
【0059】
この場合、テープ印刷装置1側で起動される通信プログラムは、図6の書換モード時に制御メモリエリア内にあり且つ通信プログラムP20と同内容のコピープログラムP30であり、それを起動する割込ベクタは、同じく図6の書換モード時に制御メモリエリア内にあり且つ割込ベクタV20と同内容のコピーベクタV30である。
【0060】
すなわち、通常モード時にRAM30内にダウンロードして新規データで書き換えることができたのと同様に、書換モード時には、ワークメモリエリア301として割り当てられたアドレスを指定して、ROM20内にダウンロードして新規データで書き換えることができる。また、これらが通信中に書き換えられても、この通信中は書換モード時であり、コピーベクタV30およびコピープログラムP30に従って通信が行われるので、正常に通信できる。
【0061】
上述のように、本実施形態のテープ印刷装置1では、書換モードキーの押下によりROM20を書き換える書換モードをセット(設定)でき、これにより、ROM20とRAM30へのメモリアクセスを相互に切り換えられるので、RAM30のエリア(ワークメモリエリア)を対象エリアとしてダウンロードするための専用アプリケーションなどのデータベースDS側の書込プログラムと、それに応答して通信を行うテープ印刷装置1側の通信プログラムP20とを利用して、ROM20への書込みができる。
【0062】
また、この場合、データサーバDSからの通信に応答する通信プログラムP20やそれを起動するための通信割込ベクタを含む割込ベクタV20は、書換モード設定時の通信割込(および通信プログラムの起動)以前に、ROM20からRAM30へコピーされ、書換モード時の通信では、メモリアクセスの交換によりRAM30内のコピー側(コピープログラムP30、コピーベクタV30)が参照されるので、その通信中にROM20内の通信プログラムP20や割込ベクタV20等が書き換えられても、正常に通信できる。
【0063】
また、この場合、通信プログラムP20で対象エリアとしていたワークエリア301のアドレスの範囲への書込みなので、書込のために指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、通信プログラムP20を利用できる。また、この場合、受信した新規データを一時格納するワーク用のエリア等を要しないので、一時格納用のエリア等を確保したり、一旦格納した新規データを元来の通信割込ベクタ等のエリアに移し替えるための余分なメモリ容量や余分な処理時間は必要としない。
【0064】
なお、上述のダウンロードが終了した時点、すなわち通信プログラムP20のコピーであるコピープログラムP30が通信終了を検出した時点で、書換モードをリセット(書換モードフラグCF←0)しても良いし、書換モードキー以外に例えば書換モード解除キー等を設けて、そのキーの押下により書換モードをリセットしても良い。また、例えば同一の書換モードキーを押す毎に、書換モードと通常モードを交互に切り換えるように、すなわち押す毎に、書換モードフラグのセットとリセットを交互に繰り返すようにしても良い。
【0065】
この場合、書換モードキーを押す毎に、例えば書換モード切換割込が発生し、例えば図9に示すように、書換モード切換処理(S20)が起動され、まず、そのときのモードが書換モード(書換モードフラグCF=1)か否かを判別し(S21)、通常モードのときには(S21:No)、図8で前述の書換モード設定処理(S10)と同様の書換モード設定処理を行って(S22)、処理(S20)を終了する(S23)。ただし、この場合、通信中にも本処理(S20:本割込処理プログラム)を起動するので、書換モード設定処理(S22)におけるコピープログラムには本プログラムを含める。
【0066】
そして、次に書換モードキーが押されて書換モード切換割込が発生し、書換モード切換処理(S20)が起動されると、このときには書換モードなので(S21:Yes)、書換モードをリセット(書換モードフラグCF←0)して(S24)、処理(S20)を終了する(S23)。これらにより、同一の書換モードキーを押す毎に、書換モードと通常モードを交互に切り換えることができる。
【0067】
なお、上述の実施形態では、書換モードキーの押下後、書換モードを設定する前に、割込ベクタV20と通信プログラムP20とを、制御メモリエリア201内からワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピーベクタV30とコピープログラムP30にするので、コピーベクタV30とコピープログラムP30の相対関係は、割込ベクタV20と通信プログラムP20の相対関係と一致する(図6参照)。このため、割込ベクタV20により参照される通信プログラムP20のアドレスを相対アドレスとしておくことにより、コピー後に、コピーベクタV30による指定(参照)アドレス(相対アドレス)を、コピープログラムP30の格納アドレスに合うように調整する必要がない。
【0068】
ただし、逆に、コピーベクタV30による指定アドレスを、コピー後に、コピープログラムP30の格納アドレスに合うように調整するようにしておいて、コピープログラムP30の格納アドレス、すなわち通信プログラムP20をコピーするアドレスを任意にできる。例えば図10に示すように、コンパクトに隣接してコピーした後、コピープログラムP30の格納アドレスに合わせて、コピーベクタV30による指定アドレスを調整できる。
【0069】
また、図11に示すように、ROM20やRAM30以外のメモリとして例えばROM25を用意して、通信プログラムP25を記憶させておき、割込ベクタV20による通信プログラムP25を指定する指定アドレスを、一般的な絶対アドレスとすることもできる。この場合、割込ベクタV20を任意のアドレスにコピーしても、指定アドレスの調整を要しない。また、書込対象とならないので、通信に際して通信プログラムP25のコピーは必要としない。
【0070】
また、図12に示すように、コピーベクタV30とコピープログラムP30を別々のRAM30とRAM35にコピーして、コピーベクタV30による指定アドレスを調整しても良い。また、この場合、コピーベクタV30のサイズは予め確定できるので、図13に示すように、メモリアクセス切換回路40とともに1チップに組み込んで、専用IC50としても良い。また、図14に示すように、コピーして使うためのコピー通信プログラムP20sを予め用意しておき、それをコピーしてコピープログラムP30とした後、コピーベクタV30による指定アドレスを調整しても良い。なお、この場合のコピー先は、図6や図10と同様にコピーベクタV30とともにRAM30でも良いし、図12と同様に別のRAM35でも良く、この場合のROM30は、専用IC50でも良い。
【0071】
また、上述の実施形態では、RAM30内の先頭アドレスとコピーベクタV30との相対関係は、ROM20内の先頭アドレスと割込ベクタV20との相対関係に一致する。
【0072】
このため、書換モードの設定の有無に従って、ROM20とRAM30とのメモリ切換を行うだけで、書換モードが設定されていないときの割込ベクタV20へのアクセスと、設定されているときのコピーベクタV30へのアクセスが、アドレス空間上、互いに同一アドレスへのアクセスとなるように、メモリアクセスを切り換えることができる。さらに、ROM20とRAM30はそれぞれ1チップなので、チップセレクトによって各チップを切り換えることにより、メモリ切換、すなわちメモリアクセスの切換えができる。なお、この場合のチップセレクトには、図4や図5等で前述の純然たるチップセレクト信号ばかりでなく、ROM20やRAM30に配られるアドレスの一部を、書換モードか否かによりアドレス変換するなど、結果としてチップ選択となるものも含む。
【0073】
なお、上述の実施形態では、上記のように、書換モード設定により、ROM20とRAM30に対するメモリアクセスを、チップ単位で(チップセレクトにより)切り換えた(交換した)が、上述の割込ベクタV20や通信プログラムP20などのように、通信時にも必要で且つ通信により書き換えられる可能性のある情報(通信コア情報)のみを対象として、書換モードの設定の有無により、通信コア情報の本体とそのコピーに関するメモリアクセスのみを切り換えて、交換するようにしても良い。
【0074】
また、上述の実施形態では、書換可能なROM20としてフラッシュROMの例を挙げたが、プログラム等をスタティックに記憶可能な書換対象メモリとしては、このほか、EEPROM(electrically eraseable programmableROM)、不揮発性RAM、FRAM(ferric RAM)などでも良い。
【0075】
また、上述の実施形態では、より単純な構成として、データサーバDSを、スタンドアロンタイプの装置(PC)としたが、データサーバDSは、例えば図15に示すように、ネットワークNWを中心に、端末となる複数のワークステーションWS(パソコンPC等)1〜3やターミナルアダプタ(ルータ、リピータ、ハブ等を含む)TA等を接続して構成し、これらの端末のいずれかからインタフェースIFを介してテープ印刷装置1を接続しても良い。すなわち、同図の構成では、データサーバDS内の各装置(WS1〜3、TA等)に記憶された新規データをダウンロードする構成となる。
【0076】
また、この場合のネットワークNWとしては、IEEE標準LAN準拠の通信プロトコルに従ったもの、例えばいわゆるインターネットや各種のローカルエリアネットワーク(LAN:イーサネット(登録商標)、10/100ベース(Base)等)が採用できる。なお、これらは有線通信の規格であるが、無線通信を利用することも可能である。
【0077】
また、上述の実施形態では、図1で前述のパソコンPC(データサーバDS)に、新規データを記憶したCD−ROM501を挿入し、ダウンロード用の専用アプリケーション502を駆動したが、この専用アプリケーション502は、パソコンPC内に元から準備しておいても良いし、このアプリケーションプログラム自体も新規データと共にCD−ROM501内に記憶しておき、それを起動できるようにしても良い。前者の場合、CD−ROMを入れ替えるだけで種々の新規データに変更できる。また、後者の場合、一般的なオペレーションシステム(OS)で実行可能なアプリケーションにしておけば、そのOSを有するパソコン等に、各種の新規データを記憶したその種のCD−ROMを装着するだけで、プログラムを実行してダウンロードにより新規データを送信でき、テープ印刷装置1を種々アップデートできる。
【0078】
なお、上述の実施形態では、CD−ROMを例に挙げたが、FD、MO、DVD等、その他の記憶媒体を利用しても良い。また、図1の構成でなく、図10のようにネットワークを利用する場合には、テープ印刷装置1の上位機(図示の例ではPC1またはTA)を介して、そのネットワークに接続された各種の他の装置(図示の例ではWS2やWS3等)から新規データを受信できるので、種々の新規データをダウンロードして、ROM20の内容を種々変更して、テープ印刷装置1をアップデートできる。
【0079】
また、上述の実施形態では、テープ印刷装置の例を挙げたが、通信機能を利用して新規データを受信して書換可能ROMを書き換えるものであれば、印刷対象物がテープではない他のタイプの印刷装置にも適用できるし、印刷装置以外の情報処理装置にも適用できる。また、上述の新規データのダウンロード等を実行するプログラムをCD等を初めとする記憶媒体に記憶しておけば、それを実行可能な任意の印刷装置あるいは情報処理装置に実装(装着)して、記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、受信した新規データによる書換可能ROMの書換えが容易にできる。もちろん、その他、種々の形態を採用でき、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更も可能である。
【0080】
【発明の効果】
上述のように、本発明のメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体によれば、通信割込ベクタにより指定された通信プログラムに従って新規データを受信し、その新規データにより通信割込ベクタ自体を書換可能で、かつ、通信中に書き換えても正常に通信できる、などの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係るテープ印刷装置を構成要素とする印刷システムの構成の一例を示す説明図である。
【図2】図1の印刷システムにおけるテープ印刷装置のメモリマップイメージおよびパソコンからのダウンロードイメージを示す説明図である。
【図3】図1のテープ印刷装置1のメモリ関連の概略構成を示すブロック図である。
【図4】図3のメモリアクセス切換回路の回路構成の例を示す説明図である。
【図5】図3のメモリアクセス切換回路の各モード時における切換イメージを示す説明図である。
【図6】図5に対応して、各モード時におけるアドレス空間と担当メモリと記憶内容の説明図である。
【図7】テープ印刷装置の制御全体の概略処理を示すフローチャートである。
【図8】書換モード設定処理を示すフローチャートである。
【図9】同一の書換モードキーの押下毎に書換モードのセットとリセットを交互に繰り返す例における書換モード切換処理を示すフローチャートである。
【図10】割込ベクタ、通信プログラム、コピーベクタおよびコピープログラムの格納イメージの図6とは別の一例を示す説明図である。
【図11】コピープログラムが不要な場合の、割込ベクタ、通信プログラムおよびコピーベクタの格納イメージの一例を示す説明図である。
【図12】コピーベクタとコピープログラムを別メモリに格納する別の一例の示す、図10と同様の説明図である。
【図13】メモリアクセス切換回路をRAMとともに1チップ化した専用ICのイメージを示す説明図である。
【図14】通信プログラム以外にコピーのためのコピー通信プログラムを用意したさらに別の一例の示す、図10と同様の説明図である。
【図15】他の構成の一例を示す、図1と同様の説明図である。
【符号の説明】
1 …… テープ印刷装置
10 …… CPU
20 …… ROM(書換可能ROM、フラッシュROM)
30 …… RAM(スタティックRAM)
40 …… メモリアクセス切換回路
201 …… 制御メモリエリア
301 …… ワークメモリエリア
501 …… CD−ROM
CF …… 書換モードフラグ
CS0、CS1、CSA、CSB、CSS …… チップセレクト信号
DS …… データサーバ
IF …… インタフェース
IFD …… USBドライバ
NW …… ネットワーク
P20 …… 通信プログラム(通信コア情報)
P30 …… コピープログラム(コピーコア情報)
PC …… パソコン
PSYS …… 印刷システム
TA …… ターミナルアダプタ
V20 …… 割込ベクタ(通信コア情報)
V30 …… コピーベクタ(コピーコア情報)
WS1〜WS3 …… ワークステーション
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信割込に応じて起動される通信プログラムに従って通信先から新規データを受信し、その新規データによりメモリを書き換えるメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】
パソコンやワープロ等を初めとして、小型のテープ印刷装置や印章作成装置等を含む情報処理装置では、一般的に、各種の割込発生に応じて起動される割込処理プログラムやそれらの起動のために割込発生時に参照される割込ベクタ(ベクタテーブル等)などが、書換不可能ROM(マスクROM等)や外部から書換可能な書換可能ROM(フラッシュROM等)等に記憶されて用意される。ここで、後者の書換可能ROMは、仕様変更や論理的不具合(バグ)対策や機種毎のカスタマイズ等に対応しやすく、かつ近年の低価格化もあって、多用される傾向にある。また、通信機能を有する装置では、通信要求の割込(通信割込)に応じて起動された通信プログラムに従って通信が行われるが、この通信機能を利用して通信先より受信した新規データ(新規受信データ)により書換可能であることが要望されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、アドレス空間上、RAMに割り当てられたアドレスのエリアを指定して、その指定エリアに新規受信データを書き込むための通信プログラムが既存の場合、原理的には、指定可能なエリアのアドレスの範囲を、アドレス空間上の書換可能ROMのエリアにまで広げれば、その通信プログラムを利用して、書換可能ROMを書き換えることができる。
【0004】
ただし、通信割込用の割込ベクタ(通信割込ベクタ)や通信プログラムを記憶する書換可能ROMの場合、それらを通信中に書き換えてしまうと、その通信中に複数回の通信割込が必要なときに通信割込ベクタの内容(指定アドレス)が異なって通信プログラムの正常起動ができなくなったり、通信プログラムの処理フローが途中で途切れて正常動作しないなどの不具合が発生する可能性がある。かといって、通信割込ベクタや通信プログラムの記憶エリアへの書き込みを禁止したのでは、新規受信データにより書き換えたい旨の要望に答えられない。
【0005】
本発明は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、その通信プログラム自体やそれを指定する通信割込ベクタを記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができ、かつ、その通信プログラム自体や通信割込ベクタ自体を通信中に書き換えても正常に通信できるメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項1のメモリ書換装置は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMと、前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定手段と、前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー手段と、前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換手段と、前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定手段と、を備えたことを特徴とする。
【0007】
また、請求項13のメモリ書換方法は、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、前記通信プログラムを利用して、前記通信先から受信された新規データを書き込むことにより、前記書換可能ROMを書き換えるメモリ書換方法であって、前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定工程と、前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー工程と、前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換工程と、前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定工程と、を備えたことを特徴とする。
【0008】
このメモリ書換装置およびメモリ書換方法では、通信プログラムとそれを通信割込に応じて起動するための通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、通信先から受信された新規データを書き込んで書き換える。この場合、書換可能ROMの少なくとも通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定し、書換可能ROM内の通信コア情報の記憶エリア(コア記憶エリア)に対応するコピー記憶エリアをRAM内に設定し、通信コア情報のコピーであるコピーコア情報をコピー記憶エリアに記憶させる。このため、この時点では、コア記憶エリアの内容とコピー記憶エリアの内容は同一となる。すなわち、コピー記憶エリアにもコア記憶エリアと同様の通信コア情報が記憶される。一方、アドレス空間におけるコア記憶エリアに対するメモリアクセスとコピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、書換モードの設定の有無に従って相互に切り換える。すなわち、書換モードの設定の有無に従って、アドレス空間上、コア記憶エリアとコピー記憶エリアを入れ換えることになるが、内容は同一なので、書換モードの設定の有無に拘わらず、通信プログラムや通信割込ベクタとして正常に参照される。ここで、通信プログラムは、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定するものではあるが、コピー記憶エリアのアドレスは、対象アドレスの範囲内なので指定することができる。すなわち、書換モードが設定されているときに、通信プログラムの指定アドレスとして、書換モードが設定されていないときのコピー記憶エリアのアドレスを指定することができ、それにより、その指定アドレスに通信先から受信された新規データを書き込むことができるが、実際には、書換モードが設定されているときには、その指定アドレスへのメモリアクセスは、書換可能ROMのコア記憶エリアへのアクセスとなるので、コア記憶エリアに対する書込みとなる。また、この書込みが実行されているときには、RAMのコピー記憶エリアにコピーされた通信コア情報が参照されているので、通信中に書換可能ROMへの書込みがあっても、正常に通信できる。したがって、アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、その通信プログラム自体やそれを指定する通信割込ベクタを記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができ、かつ、その通信プログラム自体や通信割込ベクタ自体を通信中に書き換えても正常に通信できる。
【0009】
また、請求項1のメモリ書換装置において、前記書換可能ROMはフラッシュROMであることが好ましい。
【0010】
このメモリ書換装置では、書換可能ROMはフラッシュROMなので、割込処理プログラムや割込ベクタ等を記憶するためには、RAMより安定した記憶ができてる一方、近年の低価格化等の傾向にも適合している。
【0011】
また、請求項1または2のメモリ書換装置において、前記通信コア情報には、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの双方が含まれ、前記通信割込ベクタは相対アドレスに基づいており、前記通信コア情報コピー手段は、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの相対関係を保つように前記通信コア情報を前記RAMにコピーして、前記コピーコア情報として記憶させることが好ましい。
【0012】
このメモリ書換装置では、通信コア情報には、通信割込ベクタと通信プログラムとの双方が含まれ、通信割込ベクタは相対アドレスに基づいていて、通信割込ベクタと通信プログラムとの相対関係を保つように通信コア情報をRAMにコピーして、コピーコア情報として記憶させるので、通信割込ベクタをコピーした後に、その指定アドレスをコピープログラムの格納アドレスに合うように調整する必要がない。
【0013】
また、請求項1ないし3のいずれかのメモリ書換装置において、前記RAM内の先頭と前記コピー記憶エリアの相対関係が、前記書換可能ROM内の先頭とコア記憶エリアとの相対関係に一致し、前記メモリアクセス切換手段は、前記書換可能ROMと前記RAMとのメモリ切換手段を有することが好ましい。
【0014】
このメモリ書換装置では、RAM内の先頭と前記コピー記憶エリアの相対関係が、前記書換可能ROM内の先頭とコア記憶エリアとの相対関係に一致するので、書換可能ROMとRAMとのメモリ切換をしてから、コピー記憶エリアへの書込みを行えば、コア記憶エリアへの書込みとなる。このため、RAM用のアドレスの範囲を指定して新規受信データを書き込む通信プログラムを利用して、指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、新規受信データを書き込みことができる。また、通信中に通信コア情報の書換があっても、書換可能ROMとRAMとのメモリ切換をした状態では、コア記録エリアからの通信コア情報の読出しの代わりに、コピー記憶エリアのコピーコア情報が読み出され、これは元の(書換前の)通信コア情報と同一内容なので、正常に通信できる。
【0015】
また、請求項4のメモリ書換装置において、前記書換可能ROMと前記RAMは、それぞれ1チップで構成され、前記メモリ切換手段は、チップセレクトによって各チップを切り換える手段であることが好ましい。
【0016】
このメモリ書換装置では、書換可能ROMと前記RAMは、それぞれ1チップで構成され、それぞれ1チップで構成されるので、チップセレクトによって各チップを切り換えることにより、メモリ切換ができる。
【0017】
また、請求項1ないし5のいずれかのメモリ書換装置において、前記通信プログラムによる通信は、RS−232C、USB、IEEE1394またはセントロニクスの規格に従ったものであることが好ましい。
【0018】
このメモリ書換装置では、通信プログラムによる通信は、RS−232C、USB、IEEE1394またはセントロニクスの規格に従ったものなので、その規格に従って通信して受信した新規データにより書換可能ROMを書き換えることができる。
【0019】
また、請求項7の情報処理装置は、請求項1ないし6のいずれか1項に記載の各手段と、前記書換可能ROMに記憶されたプログラムに従って処理を行うプログラム処理手段と、を備えたことを特徴とする。
【0020】
この情報処理装置は、上述したメモリ書換装置(の各手段)を備え、書換対象メモリに記憶されたプログラムに従って処理を行うので、各種処理が可能なほか、通信プログラムに従った通信により各種プログラムを新規データとして受信して格納できるので、アップデートしやすい情報処理装置となる。
【0021】
また、請求項7の情報処理装置において、所定の印刷対象物に印刷を行う印刷手段をさらに備え、前記複数の割込プログラムには、前記印刷手段に前記印刷を行わせるプログラムが含まれることが好ましい。
【0022】
この情報処理装置は、所定の印刷対象物に印刷を行う印刷手段をさらに備え、複数の割込プログラムには、印刷手段に印刷を行わせるプログラムが含まれるので、印刷装置に適用できる。
【0023】
また、請求項8の情報処理装置において、前記印刷対象物は、テープであることが好ましい。
【0024】
この情報処理装置は、印刷対象物は、テープなので、テープ印刷装置に適用できる。
【0025】
また、請求項10の情報処理システムは、請求項7ないし9のいずれかに記載の情報処理装置と、前記通信先として前記新規データを送信する供給装置と、を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【0026】
この情報処理システムでは、7ないし9のいずれかに記載の情報処理装置と、通信先として新規データを送信する供給装置と、を備えるので、供給装置側に格納する新規データを変更したり追加したりすることにより、情報処理装置側に送信する新規データを種々変更できる。
【0027】
また、請求項10の情報処理システムにおいて、前記供給装置は、前記新規データおよびそれを送信するためのプログラムを記憶した記憶媒体を装着可能な装着手段と、装着された前記記憶媒体内に記憶された前記プログラムに従って前記新規データを送信するプログラム実行手段と、を有することが好ましい。
【0028】
この情報処理システムでは、供給装置は、新規データおよびそれを送信するためのプログラムを記憶した記憶媒体を装着し、その記憶媒体内に記憶されたプログラムに従って新規データを送信することができるので、各種の新規データを記憶したその種の記憶媒体を装着するだけで、プログラムを実行して情報処理装置に新規データを送信でき、それによるアップデートができる。
【0029】
また、請求項10または11の情報処理システムにおいて、前記供給装置は、所定のネットワークを介して他の装置と接続され、前記他の装置から前記新規データを受信する上位通信手段を有することが好ましい。
【0030】
この情報処理システムでは、供給装置は、所定のネットワークを介して他の装置と接続され、他の装置から新規データを受信できるので、種々の新規データを受信して、情報処理装置側に送信することにより、情報処理装置を種々アップデートできる。
【0031】
また、請求項14の記憶媒体は、請求項1ないし9のいずれか1項に記載の各手段の機能を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする。
【0032】
また、請求項15の記憶媒体は、請求項13に記載のメモリ書換方法を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする。
【0033】
これらの記憶媒体に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、通信プログラムに従って通信先から受信した新規データを書き込むことができ、書換可能ROMの内容を書き換えることができる。
【0034】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係るテープ印刷装置について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【0035】
図1に示すように、まず、本実施形態のテープ印刷装置(情報処理装置)1は、データサーバDSとインタフェースIFを介して接続され、全体として印刷システム(情報処理システム)PSYSを構成している。データサーバDSは、テープ印刷装置1に対して、メモリ書換用の新規データ(ダウンロードデータ)を供給するものである。同図は単純な構成の例を示していて(後述の図10参照)、スタンドアロンのパソコンPCをデータサーバDSとし、そのパソコンPCとテープ印刷装置1とを、USB等のインタフェースIFで接続するだけで、印刷システムPSYSを構成する。
【0036】
ここで、テープ印刷装置1は、同図に示すように、装置ケース2により外殻が形成され、装置ケース2の前部上面には各種入力キーから成るキーボード3を備えている。後部上面には、その左部に開閉蓋21が取り付けられ、その右部にディスプレイ4が配設され、その側面には、図外の内部電源部に接続するACアダプタ接続口24(アダプタ省略)の他、(USBケーブルによる)インタフェースIFが接続されるUSBコネクタ25が配置されている。
【0037】
この場合、例えば図2に示すように、メモリに書き込むための新規データとしてパソコンPCに記憶されたデータをダウンロードする構成となる。もちろん、これらの場合、新規データを外部からコンパクトディスク(CD、CD−ROM)501等により供給することもできる。なお、インタフェースIFとしては、シリアルデータ通信(RS−232C、USB、IEEE1394等)でも、パラレルデータ通信(セントロニクス等)でも良い。また、これらは有線通信の規格であるが、無線通信を利用することも可能である。
【0038】
テープ印刷装置1は、メモリに関連する構成として、図3に示すように、各種制御の中枢となるCPU10と、インタフェースIFからUSBコネクタ25を介してデータサーバDSとCPU10との通信を司るUSBドライバ用のIC等から成るUSBインタフェースドライバ(USBドライバ)IFDと、メモリとして書換可能なフラッシュROM(本実施形態では16Mバイトを想定:以下単に「ROM」)20と、スタティックRAM(SRAM:以下単に「RAM」)30と、ROM20とRAM30との役割(メモリアクセス)を切り換えるメモリアクセス切換回路40と、を備えている。
【0039】
メモリアクセス切換回路40は、図4(a)に示すように、論理回路として構成され、メモリ切換情報記憶回路401と、各論理ゲートU1〜U8と、を有して、いわゆる選択回路(セレクタ)として構成されている。メモリ切換情報記憶回路401は、ROM30を書き換える書換モードか否かを記憶する回路であり、具体的には1ビットのフリップフロップやレジスタ内の1ビット等で構成でき、いわゆるフラグ等と呼ばれる回路で構成される。
【0040】
以下では、これを単に「書換モードフラグ」とし、書換モードフラグCF(の出力)=1のときに「書換モード」、0のときに「通常モード」とする。この書換モードフラグは、図6で後述のアドレスマップ上、I/Oマップ等と同様にアドレスが割り振られ、書換モードフラグCFへの例えば「1」の書込(セット)または「0」の書込(リセット)は、オペレーティングシステム(OS)上、その指定アドレスへの「1」または「0」の書込として扱われる。同図のチップセレクト信号CSSはその書込等の時に有効(イネーブル)となる信号である。
【0041】
この場合、同図のメモリアクセス切換回路40は、4個のアンド(AND)ゲートU1〜U4、2個のオア(OR)ゲートU5〜U6、2個のノット(NOT)ゲートU7〜U8により、図5に示すように、書換モードフラグCF=0の通常モードのときには、CPU10からのチップセレクト信号CS0がCSA(CS0→CSA)、チップセレクト信号CS1がCSB(CS1→CSB)となるように、チップセレクト信号(すなわちメモリアクセス)を切り換え、書換モードフラグCF=1の書換モードのときには、CS0→CSB、CS1→CSAとなるように、切り換える。
【0042】
なお、図4(b)は同一論理を実現する別の構成例を示し、同様のメモリ切換情報記憶回路401(書換モードフラグCF)と、ナンド(NAND)ゲートU1s〜U7sとアンド(AND)ゲートU8sを有する。ここで、アンドゲートU8sは論理上は省略可能であり、また、ナンドゲートU7sとアンドゲートU8sの代わりに、これらを合わせた論理のアンドナンドゲートU9sを使用しても良い。
【0043】
図3に示すように、テープ印刷装置1のメモリは、ROM20+RAM30により構成され、図2および図6に示すように、アドレス空間(アドレスマップ)上、プログラム等や制御用のデータを記憶する制御メモリエリア201と、ワーク用のワークメモリエリア301とに分けて使用される。
【0044】
図3〜図5で前述のCPU10からのチップセレクト信号CS0は、制御メモリエリア201へのメモリアクセス時にイネーブルとなる信号であり、チップセレクト信号CS1は、ワークメモリエリア301へのメモリアクセス時にイネーブルとなる信号である。また、メモリアクセス切換回路40から出力されるチップセレクト信号CSAは、ROM20へのメモリアクセスをイネーブルにする信号であり、チップセレクト信号CSBは、RAM30へのメモリアクセスをイネーブルにする信号である。
【0045】
通常モード時には、前述のように、CS0→CSA、CS1→CSBとなるので(図5参照)、ROM20が制御メモリエリア201を、RAM30がワークメモリエリア301を担当する。
【0046】
これらのうち、通信により書き込まれる対象エリアは、RAM30が担当するワークメモリエリア301側であり、図2に示すように、パソコンPC(すなわちデータDS)では、例えば書換用の新規データを記憶したCD−ROM501を装着(挿入)し、ダウンロード用の専用アプリケーション502を駆動して、テープ印刷装置1のワークメモリエリア301内の指定アドレスにより指定されたダウンロードデータ領域に新規データ(ダウンロードデータ)をダウンロードする。
【0047】
ところで、テープ印刷装置1では、図7に示すように、電源キーを押すこと(電源オン)等により処理が開始すると、まず、前回の電源オフ時の状態に戻すために、退避していた各制御フラグを復旧するなどの初期設定を行い(S1)、次に、前回の表示画面を初期画面として表示する(S2)。
【0048】
図7のその後の処理、すなわちキー入力か否かの判断分岐(S3)および各種割込処理(S4)は、概念的に示した処理である。実際には、テープ印刷装置1では、初期画面表示(S2)が終了すると、キー入力割込を許可し、キー入力割込が発生するまでは、そのままの状態を維持し(S3:No)、何らかのキー入力割込が発生すると(S3:Yes)、それぞれの割込処理に移行して(S4)、その割込処理が終了すると、再度、その状態を維持する(S3:No)。
【0049】
すなわち、テープ印刷装置1では、主な処理を割込処理により行う。例えば印刷画像作成などの準備ができていれば、ユーザが任意の時点で印刷キーを押すことにより、印刷処理割込が発生して、印刷処理が起動され、印刷画像データに基づいて印刷画像の印刷ができる。
【0050】
そして、図6に示すように、これら各種の割込の発生に応じて起動される割込処理プログラムおよびそれらの起動のために割込発生時に参照される割込ベクタ(ベクタテーブル等)V20などは、通常モード時にROM20が担当する制御メモリエリア201側に記憶されている。
【0051】
例えば図2で前述のダウンロード用の専用アプリケーションからの通信要求等は、図3で前述のUSBドライバIFDを介して通信割込としてCPU10の端子INTに入力され、CPU10では、その入力(割込要求)を受けて、割込ベクタV20を参照し、該当する通信プログラムP20の先頭アドレスを検出して、それを起動する。
【0052】
テープ印刷装置1では、大きなデータをダウンロードする場合、例えば64Kバイト毎程度に分割して送受信するので、一回(まとまった1個のデータ)の通信の間にも複数回の通信割込が発生し、通信プログラムP20が起動される。
【0053】
ところで、本実施形態のテープ印刷装置1では、通常はRAM30用に使用される上記のダウンロードにより、ROM20を書き換えることができるので、以下、この点について説明する。
【0054】
テープ印刷装置1のキーボード3は、ROM20を書き換える書換モードをセット(設定)するための書換モードキーを有し、この書換モードキーが押下されると、書換モード設定割込が発生して、図8に示すように、書換モード設定処理(S10)が起動され、まず、割込ベクタV20のコピーを行う(S11)。すなわち、図6に示す通常モード時において、制御メモリエリア201内にある割込ベクタV20を、ワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピーベクタV30とする(S11)。
【0055】
割込ベクタV20のコピー(S10)が終了すると、次に、必要プログラムのコピーを行う(S12)。ここでは、図6に示す通常モード時において制御メモリエリア201内にあり且つ通信中に起動させる必要のあるプログラム、例えば前述の通信プログラムP20などのプログラムを、ワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピープログラムP30とする(S12)。ここでは、説明の都合上、単に通信プログラムP20のみコピーしてコピープログラムP30とする。
【0056】
必要プログラムのコピー(S12)が終了すると、次に、書換モードをセットして(S13)、書換モード設定処理(S10)を終了する(S14)。具体的には、アドレス空間上、所定アドレスに設定された書換モードフラグCFへの「1」の書込(書換モードフラグCF←1)を行って(S13)、処理(S10)を終了する(S14)。
【0057】
書換モードが設定されると、すなわち書換モード時には、前述のように、CS0→CSB、CS1→CSAとなるので(図5参照)、図6に示すように、RAM30が制御メモリエリア201を、ROM20がワークメモリエリア301を担当する。
【0058】
これらのうち、通信により書き込まれる対象エリアは、ワークメモリエリア301側、すなわちROM20が担当する側であり、図2で前述のダウンロードは、テープ印刷装置1のワークメモリエリア301内の指定アドレスにより指定されたダウンロードデータ領域に新規データをダウンロードする。
【0059】
この場合、テープ印刷装置1側で起動される通信プログラムは、図6の書換モード時に制御メモリエリア内にあり且つ通信プログラムP20と同内容のコピープログラムP30であり、それを起動する割込ベクタは、同じく図6の書換モード時に制御メモリエリア内にあり且つ割込ベクタV20と同内容のコピーベクタV30である。
【0060】
すなわち、通常モード時にRAM30内にダウンロードして新規データで書き換えることができたのと同様に、書換モード時には、ワークメモリエリア301として割り当てられたアドレスを指定して、ROM20内にダウンロードして新規データで書き換えることができる。また、これらが通信中に書き換えられても、この通信中は書換モード時であり、コピーベクタV30およびコピープログラムP30に従って通信が行われるので、正常に通信できる。
【0061】
上述のように、本実施形態のテープ印刷装置1では、書換モードキーの押下によりROM20を書き換える書換モードをセット(設定)でき、これにより、ROM20とRAM30へのメモリアクセスを相互に切り換えられるので、RAM30のエリア(ワークメモリエリア)を対象エリアとしてダウンロードするための専用アプリケーションなどのデータベースDS側の書込プログラムと、それに応答して通信を行うテープ印刷装置1側の通信プログラムP20とを利用して、ROM20への書込みができる。
【0062】
また、この場合、データサーバDSからの通信に応答する通信プログラムP20やそれを起動するための通信割込ベクタを含む割込ベクタV20は、書換モード設定時の通信割込(および通信プログラムの起動)以前に、ROM20からRAM30へコピーされ、書換モード時の通信では、メモリアクセスの交換によりRAM30内のコピー側(コピープログラムP30、コピーベクタV30)が参照されるので、その通信中にROM20内の通信プログラムP20や割込ベクタV20等が書き換えられても、正常に通信できる。
【0063】
また、この場合、通信プログラムP20で対象エリアとしていたワークエリア301のアドレスの範囲への書込みなので、書込のために指定可能なアドレスの範囲を広げることなく、通信プログラムP20を利用できる。また、この場合、受信した新規データを一時格納するワーク用のエリア等を要しないので、一時格納用のエリア等を確保したり、一旦格納した新規データを元来の通信割込ベクタ等のエリアに移し替えるための余分なメモリ容量や余分な処理時間は必要としない。
【0064】
なお、上述のダウンロードが終了した時点、すなわち通信プログラムP20のコピーであるコピープログラムP30が通信終了を検出した時点で、書換モードをリセット(書換モードフラグCF←0)しても良いし、書換モードキー以外に例えば書換モード解除キー等を設けて、そのキーの押下により書換モードをリセットしても良い。また、例えば同一の書換モードキーを押す毎に、書換モードと通常モードを交互に切り換えるように、すなわち押す毎に、書換モードフラグのセットとリセットを交互に繰り返すようにしても良い。
【0065】
この場合、書換モードキーを押す毎に、例えば書換モード切換割込が発生し、例えば図9に示すように、書換モード切換処理(S20)が起動され、まず、そのときのモードが書換モード(書換モードフラグCF=1)か否かを判別し(S21)、通常モードのときには(S21:No)、図8で前述の書換モード設定処理(S10)と同様の書換モード設定処理を行って(S22)、処理(S20)を終了する(S23)。ただし、この場合、通信中にも本処理(S20:本割込処理プログラム)を起動するので、書換モード設定処理(S22)におけるコピープログラムには本プログラムを含める。
【0066】
そして、次に書換モードキーが押されて書換モード切換割込が発生し、書換モード切換処理(S20)が起動されると、このときには書換モードなので(S21:Yes)、書換モードをリセット(書換モードフラグCF←0)して(S24)、処理(S20)を終了する(S23)。これらにより、同一の書換モードキーを押す毎に、書換モードと通常モードを交互に切り換えることができる。
【0067】
なお、上述の実施形態では、書換モードキーの押下後、書換モードを設定する前に、割込ベクタV20と通信プログラムP20とを、制御メモリエリア201内からワークメモリエリア301内の対応アドレスにコピーして、コピーベクタV30とコピープログラムP30にするので、コピーベクタV30とコピープログラムP30の相対関係は、割込ベクタV20と通信プログラムP20の相対関係と一致する(図6参照)。このため、割込ベクタV20により参照される通信プログラムP20のアドレスを相対アドレスとしておくことにより、コピー後に、コピーベクタV30による指定(参照)アドレス(相対アドレス)を、コピープログラムP30の格納アドレスに合うように調整する必要がない。
【0068】
ただし、逆に、コピーベクタV30による指定アドレスを、コピー後に、コピープログラムP30の格納アドレスに合うように調整するようにしておいて、コピープログラムP30の格納アドレス、すなわち通信プログラムP20をコピーするアドレスを任意にできる。例えば図10に示すように、コンパクトに隣接してコピーした後、コピープログラムP30の格納アドレスに合わせて、コピーベクタV30による指定アドレスを調整できる。
【0069】
また、図11に示すように、ROM20やRAM30以外のメモリとして例えばROM25を用意して、通信プログラムP25を記憶させておき、割込ベクタV20による通信プログラムP25を指定する指定アドレスを、一般的な絶対アドレスとすることもできる。この場合、割込ベクタV20を任意のアドレスにコピーしても、指定アドレスの調整を要しない。また、書込対象とならないので、通信に際して通信プログラムP25のコピーは必要としない。
【0070】
また、図12に示すように、コピーベクタV30とコピープログラムP30を別々のRAM30とRAM35にコピーして、コピーベクタV30による指定アドレスを調整しても良い。また、この場合、コピーベクタV30のサイズは予め確定できるので、図13に示すように、メモリアクセス切換回路40とともに1チップに組み込んで、専用IC50としても良い。また、図14に示すように、コピーして使うためのコピー通信プログラムP20sを予め用意しておき、それをコピーしてコピープログラムP30とした後、コピーベクタV30による指定アドレスを調整しても良い。なお、この場合のコピー先は、図6や図10と同様にコピーベクタV30とともにRAM30でも良いし、図12と同様に別のRAM35でも良く、この場合のROM30は、専用IC50でも良い。
【0071】
また、上述の実施形態では、RAM30内の先頭アドレスとコピーベクタV30との相対関係は、ROM20内の先頭アドレスと割込ベクタV20との相対関係に一致する。
【0072】
このため、書換モードの設定の有無に従って、ROM20とRAM30とのメモリ切換を行うだけで、書換モードが設定されていないときの割込ベクタV20へのアクセスと、設定されているときのコピーベクタV30へのアクセスが、アドレス空間上、互いに同一アドレスへのアクセスとなるように、メモリアクセスを切り換えることができる。さらに、ROM20とRAM30はそれぞれ1チップなので、チップセレクトによって各チップを切り換えることにより、メモリ切換、すなわちメモリアクセスの切換えができる。なお、この場合のチップセレクトには、図4や図5等で前述の純然たるチップセレクト信号ばかりでなく、ROM20やRAM30に配られるアドレスの一部を、書換モードか否かによりアドレス変換するなど、結果としてチップ選択となるものも含む。
【0073】
なお、上述の実施形態では、上記のように、書換モード設定により、ROM20とRAM30に対するメモリアクセスを、チップ単位で(チップセレクトにより)切り換えた(交換した)が、上述の割込ベクタV20や通信プログラムP20などのように、通信時にも必要で且つ通信により書き換えられる可能性のある情報(通信コア情報)のみを対象として、書換モードの設定の有無により、通信コア情報の本体とそのコピーに関するメモリアクセスのみを切り換えて、交換するようにしても良い。
【0074】
また、上述の実施形態では、書換可能なROM20としてフラッシュROMの例を挙げたが、プログラム等をスタティックに記憶可能な書換対象メモリとしては、このほか、EEPROM(electrically eraseable programmableROM)、不揮発性RAM、FRAM(ferric RAM)などでも良い。
【0075】
また、上述の実施形態では、より単純な構成として、データサーバDSを、スタンドアロンタイプの装置(PC)としたが、データサーバDSは、例えば図15に示すように、ネットワークNWを中心に、端末となる複数のワークステーションWS(パソコンPC等)1〜3やターミナルアダプタ(ルータ、リピータ、ハブ等を含む)TA等を接続して構成し、これらの端末のいずれかからインタフェースIFを介してテープ印刷装置1を接続しても良い。すなわち、同図の構成では、データサーバDS内の各装置(WS1〜3、TA等)に記憶された新規データをダウンロードする構成となる。
【0076】
また、この場合のネットワークNWとしては、IEEE標準LAN準拠の通信プロトコルに従ったもの、例えばいわゆるインターネットや各種のローカルエリアネットワーク(LAN:イーサネット(登録商標)、10/100ベース(Base)等)が採用できる。なお、これらは有線通信の規格であるが、無線通信を利用することも可能である。
【0077】
また、上述の実施形態では、図1で前述のパソコンPC(データサーバDS)に、新規データを記憶したCD−ROM501を挿入し、ダウンロード用の専用アプリケーション502を駆動したが、この専用アプリケーション502は、パソコンPC内に元から準備しておいても良いし、このアプリケーションプログラム自体も新規データと共にCD−ROM501内に記憶しておき、それを起動できるようにしても良い。前者の場合、CD−ROMを入れ替えるだけで種々の新規データに変更できる。また、後者の場合、一般的なオペレーションシステム(OS)で実行可能なアプリケーションにしておけば、そのOSを有するパソコン等に、各種の新規データを記憶したその種のCD−ROMを装着するだけで、プログラムを実行してダウンロードにより新規データを送信でき、テープ印刷装置1を種々アップデートできる。
【0078】
なお、上述の実施形態では、CD−ROMを例に挙げたが、FD、MO、DVD等、その他の記憶媒体を利用しても良い。また、図1の構成でなく、図10のようにネットワークを利用する場合には、テープ印刷装置1の上位機(図示の例ではPC1またはTA)を介して、そのネットワークに接続された各種の他の装置(図示の例ではWS2やWS3等)から新規データを受信できるので、種々の新規データをダウンロードして、ROM20の内容を種々変更して、テープ印刷装置1をアップデートできる。
【0079】
また、上述の実施形態では、テープ印刷装置の例を挙げたが、通信機能を利用して新規データを受信して書換可能ROMを書き換えるものであれば、印刷対象物がテープではない他のタイプの印刷装置にも適用できるし、印刷装置以外の情報処理装置にも適用できる。また、上述の新規データのダウンロード等を実行するプログラムをCD等を初めとする記憶媒体に記憶しておけば、それを実行可能な任意の印刷装置あるいは情報処理装置に実装(装着)して、記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、受信した新規データによる書換可能ROMの書換えが容易にできる。もちろん、その他、種々の形態を採用でき、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更も可能である。
【0080】
【発明の効果】
上述のように、本発明のメモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体によれば、通信割込ベクタにより指定された通信プログラムに従って新規データを受信し、その新規データにより通信割込ベクタ自体を書換可能で、かつ、通信中に書き換えても正常に通信できる、などの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係るテープ印刷装置を構成要素とする印刷システムの構成の一例を示す説明図である。
【図2】図1の印刷システムにおけるテープ印刷装置のメモリマップイメージおよびパソコンからのダウンロードイメージを示す説明図である。
【図3】図1のテープ印刷装置1のメモリ関連の概略構成を示すブロック図である。
【図4】図3のメモリアクセス切換回路の回路構成の例を示す説明図である。
【図5】図3のメモリアクセス切換回路の各モード時における切換イメージを示す説明図である。
【図6】図5に対応して、各モード時におけるアドレス空間と担当メモリと記憶内容の説明図である。
【図7】テープ印刷装置の制御全体の概略処理を示すフローチャートである。
【図8】書換モード設定処理を示すフローチャートである。
【図9】同一の書換モードキーの押下毎に書換モードのセットとリセットを交互に繰り返す例における書換モード切換処理を示すフローチャートである。
【図10】割込ベクタ、通信プログラム、コピーベクタおよびコピープログラムの格納イメージの図6とは別の一例を示す説明図である。
【図11】コピープログラムが不要な場合の、割込ベクタ、通信プログラムおよびコピーベクタの格納イメージの一例を示す説明図である。
【図12】コピーベクタとコピープログラムを別メモリに格納する別の一例の示す、図10と同様の説明図である。
【図13】メモリアクセス切換回路をRAMとともに1チップ化した専用ICのイメージを示す説明図である。
【図14】通信プログラム以外にコピーのためのコピー通信プログラムを用意したさらに別の一例の示す、図10と同様の説明図である。
【図15】他の構成の一例を示す、図1と同様の説明図である。
【符号の説明】
1 …… テープ印刷装置
10 …… CPU
20 …… ROM(書換可能ROM、フラッシュROM)
30 …… RAM(スタティックRAM)
40 …… メモリアクセス切換回路
201 …… 制御メモリエリア
301 …… ワークメモリエリア
501 …… CD−ROM
CF …… 書換モードフラグ
CS0、CS1、CSA、CSB、CSS …… チップセレクト信号
DS …… データサーバ
IF …… インタフェース
IFD …… USBドライバ
NW …… ネットワーク
P20 …… 通信プログラム(通信コア情報)
P30 …… コピープログラム(コピーコア情報)
PC …… パソコン
PSYS …… 印刷システム
TA …… ターミナルアダプタ
V20 …… 割込ベクタ(通信コア情報)
V30 …… コピーベクタ(コピーコア情報)
WS1〜WS3 …… ワークステーション
Claims (15)
- アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMと、
前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定手段と、
前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー手段と、
前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換手段と、
前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定手段と、
を備えたことを特徴とするメモリ書換装置。 - 前記書換可能ROMはフラッシュROMであることを特徴とする、請求項1に記載のメモリ書換装置。
- 前記通信コア情報には、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの双方が含まれ、
前記通信割込ベクタは相対アドレスに基づいており、
前記通信コア情報コピー手段は、前記通信割込ベクタと前記通信プログラムとの相対関係を保つように前記通信コア情報を前記RAMにコピーして、前記コピーコア情報として記憶させることを特徴とする、請求項1または2に記載のメモリ書換装置。 - 前記RAM内の先頭と前記コピー記憶エリアの相対関係が、前記書換可能ROM内の先頭とコア記憶エリアとの相対関係に一致し、
前記メモリアクセス切換手段は、前記書換可能ROMと前記RAMとのメモリ切換手段を有することを特徴とする、請求項1ないし3のいずれかに記載のメモリ書換装置。 - 前記書換可能ROMと前記RAMは、それぞれ1チップで構成され、
前記メモリ切換手段は、チップセレクトによって各チップを切り換える手段であることを特徴とする、請求項4に記載のメモリ書換装置。 - 前記通信プログラムによる通信は、RS−232C、USB、IEEE1394またはセントロニクスの規格に従ったものであることを特徴とする、請求項1ないし5のいずれかに記載のメモリ書換装置。
- 請求項1ないし6のいずれか1項に記載の各手段と、
前記書換可能ROMに記憶されたプログラムに従って処理を行うプログラム処理手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。 - 所定の印刷対象物に印刷を行う印刷手段をさらに備え、
前記複数の割込プログラムには、前記印刷手段に前記印刷を行わせるプログラムが含まれることを特徴とする、請求項7に記載の情報処理装置。 - 前記印刷対象物は、テープであることを特徴とする、請求項7に記載の情報処理装置。
- 請求項7ないし9のいずれかに記載の情報処理装置と、
前記通信先として前記新規データを送信する供給装置と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。 - 前記供給装置は、
前記新規データおよびそれを送信するためのプログラムを記憶した記憶媒体を装着可能な装着手段と、
装着された前記記憶媒体内に記憶された前記プログラムに従って前記新規データを送信するプログラム実行手段と、
を有することを特徴とする、請求項10に記載の情報処理システム。 - 前記供給装置は、所定のネットワークを介して他の装置と接続され、前記他の装置から前記新規データを受信する上位通信手段を有することを特徴とする、請求項10または11に記載の情報処理システム。
- アドレス空間におけるRAMに割り当てられたアドレスの範囲内を指定して通信先から受信された新規データを書き込むための通信プログラムとその通信プログラムを通信割込に応じて起動するために参照される通信割込ベクタとの少なくとも一方を含む通信コア情報を記憶する書換可能ROMに、前記通信プログラムを利用して、前記通信先から受信された新規データを書き込むことにより、前記書換可能ROMを書き換えるメモリ書換方法であって、
前記書換可能ROMの少なくとも前記通信コア情報を書き換えるための書換モードを設定する書換モード設定工程と、
前記書換可能ROM内の前記通信コア情報の記憶エリアであるコア記憶エリアに対応するコピー記憶エリアを前記RAM内に設定して、前記通信コア情報のコピーであるコピーコア情報を前記コピー記憶エリアに記憶させる通信コア情報コピー工程と、
前記アドレス空間における前記コア記憶エリアに対するメモリアクセスと前記コピー記憶エリアに対するメモリアクセスとを、前記書換モードの設定の有無に従って相互に切り換えるメモリアクセス切換工程と、
前記書換モードが設定されているときに、前記通信プログラムの指定アドレスとして、前記書換モードが設定されていないときの前記コピー記憶エリアのアドレスを指定する書換時エリア指定工程と、
を備えたことを特徴とするメモリ書換方法。 - 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の各手段の機能を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体。
- 請求項13に記載のメモリ書換方法を実行可能なプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002165137A JP2004013463A (ja) | 2002-06-06 | 2002-06-06 | メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2002165137A JP2004013463A (ja) | 2002-06-06 | 2002-06-06 | メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2004013463A true JP2004013463A (ja) | 2004-01-15 |
| JP2004013463A5 JP2004013463A5 (ja) | 2005-10-13 |
Family
ID=30433046
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2002165137A Withdrawn JP2004013463A (ja) | 2002-06-06 | 2002-06-06 | メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2004013463A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10804549B2 (en) * | 2013-02-06 | 2020-10-13 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Power generation system and method for operating power generation system |
| CN113127383A (zh) * | 2021-04-21 | 2021-07-16 | 广州众诺电子技术有限公司 | 一种芯片改写方法、装置和设备 |
| CN114741137A (zh) * | 2022-05-09 | 2022-07-12 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种基于多核微控制器的软件启动方法、装置、设备及存储介质 |
-
2002
- 2002-06-06 JP JP2002165137A patent/JP2004013463A/ja not_active Withdrawn
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10804549B2 (en) * | 2013-02-06 | 2020-10-13 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Power generation system and method for operating power generation system |
| CN113127383A (zh) * | 2021-04-21 | 2021-07-16 | 广州众诺电子技术有限公司 | 一种芯片改写方法、装置和设备 |
| CN113127383B (zh) * | 2021-04-21 | 2023-11-10 | 广州众诺微电子有限公司 | 一种芯片改写方法、装置和设备 |
| CN114741137A (zh) * | 2022-05-09 | 2022-07-12 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种基于多核微控制器的软件启动方法、装置、设备及存储介质 |
| CN114741137B (zh) * | 2022-05-09 | 2024-02-20 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种基于多核微控制器的软件启动方法、装置、设备及存储介质 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TWI261254B (en) | Memory card and semiconductor device | |
| JP4900760B2 (ja) | Osイメージのデプロイメントマシン及び方法 | |
| JP2000148465A (ja) | ファ―ムウェア変更方法 | |
| WO2018054261A1 (zh) | 存储介质、数据处理方法及采用该方法的盒芯片 | |
| CN106843943A (zh) | 一种stm32微处理器程序架构设计方法 | |
| CN101025711B (zh) | 控制闪存的设备和方法 | |
| US8179554B2 (en) | Printer, control method of a printer and computer-readable recording medium | |
| JP2004013463A (ja) | メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 | |
| JP5062687B2 (ja) | 情報処理装置 | |
| JP2007011944A (ja) | 画像処理装置およびファームバージョンアップ方法 | |
| JP2004013462A (ja) | メモリ書換装置、メモリ書換方法、情報処理装置、情報処理システム並びに記憶媒体 | |
| JP2004220575A (ja) | カード型メモリのインターフェース回路、その回路を搭載したasic、及びそのasicを搭載した画像形成装置 | |
| KR20040018869A (ko) | 화상형성장치 | |
| TW522311B (en) | Auxiliary processor manages firmware personalities while borrowing host system resources | |
| JP4900805B2 (ja) | Osイメージのデプロイメントマシン及び方法 | |
| JP2002007152A (ja) | ダウンロード方法および装置 | |
| JP4182928B2 (ja) | 情報処理装置、メモリ管理プログラムおよびメモリ管理方法 | |
| EP1804166A2 (en) | Memory device and information processing apparatus | |
| JP2004118937A (ja) | 不揮発性メモリおよびこれを有したデータ記憶装置 | |
| JP2018022283A (ja) | 情報処理システム、情報処理システムにおける方法、及びプログラム | |
| JP2004013463A5 (ja) | ||
| JP5350077B2 (ja) | 情報処理装置及びこれを備えた画像形成装置 | |
| TW201804316A (zh) | 系統參數存取的設定方法及其伺服器 | |
| JP2812285B2 (ja) | プリンタ用ネットワークインタフェースカード | |
| JP2004017624A (ja) | 印刷装置、印刷システム及び記録媒体 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Effective date: 20050603 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Effective date: 20050603 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Effective date: 20070904 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |
|
| A761 | Written withdrawal of application |
Effective date: 20071005 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761 |