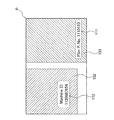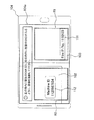JP6917618B2 - 装置管理システム - Google Patents
装置管理システム Download PDFInfo
- Publication number
- JP6917618B2 JP6917618B2 JP2017159724A JP2017159724A JP6917618B2 JP 6917618 B2 JP6917618 B2 JP 6917618B2 JP 2017159724 A JP2017159724 A JP 2017159724A JP 2017159724 A JP2017159724 A JP 2017159724A JP 6917618 B2 JP6917618 B2 JP 6917618B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- product processing
- symbol
- unique symbol
- processing device
- management system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65B—MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
- B65B57/00—Automatic control, checking, warning, or safety devices
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q50/00—Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
- G06Q50/04—Manufacturing
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding
- G06V10/10—Image acquisition
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding
- G06V10/98—Detection or correction of errors, e.g. by rescanning the pattern or by human intervention; Evaluation of the quality of the acquired patterns
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/30—Computing systems specially adapted for manufacturing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Economics (AREA)
- Primary Health Care (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- Marketing (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- Tourism & Hospitality (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Character Input (AREA)
- Character Discrimination (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Description
本発明に係る装置管理システムは、商品を包装材で覆う商品処理を行う商品処理装置を管理する。この装置管理システムは、商品処理装置の運転開始前のセットアップ確認作業を自動化する機能を有する。セットアップ確認作業とは、商品処理の対象である商品に合った種類の包装材が商品処理装置にセットされているか否かを確認するための作業である。
商品処理装置102は、例えば、商品の包装または箱詰めを行う装置である。次に、商品処理装置102の一例である製袋包装機について説明する。製袋包装機は、食品等の被包装物をフィルムで包装して袋詰めするための装置である。
撮影装置104は、画像を撮影するためのカメラ等を有する。本実施形態では、撮影装置104は、カメラ付きのスマートフォン、または、カメラ付きのスマートグラスであるとする。撮影装置104は、無線によりネットワーク108に接続されている。撮影装置104は、撮影した画像を解析装置106に送信する機能を有する。撮影装置104は、主として、撮影部121と、送信部122とを有する。これらは、撮影装置104の記憶装置に記憶され実行されるプログラムである。
解析装置106は、例えば、LANケーブルを介して各商品処理装置102と接続されているパソコン(サーバ)である。解析装置106は、主として、読み取り部123と、記憶部124と、制御部125とを有する。これらは、解析装置106の記憶装置に記憶され実行されるプログラムである。
次に、装置管理システム100の運用の手順について説明する。図5は、装置管理システム100の運用の手順を表すフローチャートである。ステップS1〜S3は、事前準備に関し、任意の順番で実行可能である。ステップS4〜S8は、セットアップ確認作業に関する。図5の処理の開始時点では、商品処理装置102の運転開始は禁止されているものとする。また、商品処理装置102にセットされている包装材103には、第1固有記号111が予め付与されている。
本実施形態では、装置管理システム100の使用者は、撮影装置104を用いて、商品処理装置102にセットされている包装材103に付されている第1固有記号111と、商品処理装置102に付されている第2固有記号112とを同時に撮影して認証用画像を取得する。解析装置106は、認証用画像から読み取った第1・第2固有記号111,112である第1・第2読み取り済み記号に基づいて、商品処理装置102の運転開始前のセットアップ確認作業を行う。具体的には、解析装置106は、第1読み取り済み記号と第2読み取り済み記号との組み合わせが解析装置106に登録されている場合、第2読み取り済み記号が付されている商品処理装置102に適切な包装材103がセットされていると判定する。この場合、商品処理装置102は、解析装置106の判定結果に基づいて、自身の運転開始ボタン等を使用者が押せる状態にする。従って、装置管理システム100は、商品処理装置102の運転開始前のセットアップ確認作業を自動で行うことができる。
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、本発明には、次に説明する変形例の少なくとも1つを適用することができる。
図6は、本変形例における、装置管理システム100の全体構成を表す図である。図6に示されるように、各商品処理装置102は、登録部126をさらに有してもよい。登録部126は、商品処理装置102の商品処理に関する設定である処理設定を登録するためのプログラムである。処理設定とは、例えば、商品処理装置102による商品処理の対象である商品の種類、および、商品処理装置102による商品処理の能力に関する設定である。商品処理装置102に登録されている処理設定は、その商品処理装置102が現在使用している処理設定である。
装置管理システム100では、商品処理装置102は、包装材103をロックするための機構をさらに有してもよい。包装材103がロックされている場合、商品処理装置102にセットされている包装材103を取り外すことができない。そのため、包装材103がロックされている場合、商品処理装置102にセットされている包装材103を、別の種類の包装材103に交換することができない。商品処理装置102が商品処理を行っていない間は、包装材103のロックを解除することができる。
実施形態の装置管理システム100では、解析装置106は、認証用画像を解析して、第1読み取り済み記号および第2読み取り済み記号を取得する。その後、解析装置106は、第1読み取り済み記号と第2読み取り済み記号との組み合わせが、記憶部124の照合情報に含まれているか否かを判定する認証処理を行う。
装置管理システム100では、撮影装置104は、認証用画像の所定の領域に第1・第2固有記号111,112が収まるようにナビゲーションする機能を有してもよい。例えば、撮影装置104がスマートフォンである場合、撮影装置104のディスプレイに、第1固有記号111が収まるための第1撮影領域と、第2固有記号112が収まるための第2撮影領域を表示してもよい。図8は、スマートフォンである撮影装置104のディスプレイ104aに表示される第1撮影領域R1および第2撮影領域R2の一例である。図8に示されるディスプレイ104aには、撮影装置104の操作者に対する指示が表示されている。第1撮影領域R1および第2撮影領域R2は、認証用画像全体の一部分の矩形領域であり、かつ、互いに重なり合わない。図8では、第1撮影領域R1は、ディスプレイ104aの画面右側に位置する矩形領域であり、第2撮影領域R2は、ディスプレイ104aの画面左側に位置する矩形領域である。また、撮影装置104がスマートグラスである場合、例えば、拡張現実(AR)の機能を用いて、透過型ディスプレイに第1撮影領域および第2撮影領域を表示してもよい。
実施形態では、商品処理装置102の一例として、食品等の被包装物をフィルムで包装して袋詰めするための製袋包装機1について説明した。しかし、商品処理装置102は、製袋包装機1以外の装置でもよい。例えば、商品処理装置102は、食品が包装された袋をダンボール箱に詰めるための箱詰め装置であってもよい。この場合、第1固有記号111は、包装材103であるダンボール箱に付されている。
実施形態の装置管理システム100では、解析装置106の読み取り部123は、撮影装置104が取得した認証用画像を解析して第1・第2読み取り済み記号を取得する。そして、解析装置106の制御部125は、認証用画像から取得した第1読み取り済み記号と第2読み取り済み記号との組み合わせが、解析装置106の記憶部124に記憶されている照合情報に含まれているか否かを判定する認証処理を行う。すなわち、解析装置106は、読み取り部123と、記憶部124と、制御部125とを有する。
102 商品処理装置
103 包装材
106 解析装置(管理装置)
108 ネットワーク
111 第1固有記号
112 第2固有記号
121 撮影部
122 送信部
123 読み取り部
124 記憶部
125 制御部
126 登録部
Claims (7)
- 商品を包装材で覆う商品処理を行う商品処理装置を管理するシステムであって、
前記包装材に付与されている第1固有記号と、前記商品処理装置に付与されている第2固有記号とを撮影する撮影部と、
前記撮影部が撮影した前記第1固有記号および前記第2固有記号を読み取る読み取り部と、
前記読み取り部が読み取った前記第1固有記号である第1読み取り済み記号、および、前記読み取り部が読み取った前記第2固有記号である第2読み取り済み記号に基づいて、前記商品処理装置を管理する制御部と、
を備え、
前記撮影部は、前記第1固有記号および前記第2固有記号が同一の画面に収まるように、前記第1固有記号および前記第2固有記号を撮影し、
前記第1固有記号と前記第2固有記号との組合せを含む照合情報を記憶する記憶部をさらに備え、
前記制御部は、前記第1読み取り済み記号と前記第2読み取り済み記号との組合せが、前記記憶部に記憶されている前記照合情報に含まれている場合に、前記第2読み取り済み記号が付与されている前記商品処理装置の前記商品処理を許可する、
装置管理システム。 - 前記商品処理装置の前記商品処理に関する処理設定を登録するための登録部をさらに備え、
前記記憶部は、前記第1固有記号と前記第2固有記号と前記処理設定との組合せを含む前記照合情報を記憶し、
前記制御部は、前記第1読み取り済み記号と、前記第2読み取り済み記号と、前記登録部に登録されている前記処理設定との組合せが、前記記憶部に記憶されている前記照合情報に含まれている場合に、前記第2読み取り済み記号が付与されている前記商品処理装置の前記商品処理を許可する、
請求項1に記載の装置管理システム。 - 前記商品処理装置は、前記包装材をロックするための機構を有し、
前記制御部は、さらに、前記包装材がロックされている場合に、前記商品処理装置の前記商品処理を許可する、
請求項1または2に記載の装置管理システム。 - 前記制御部は、さらに、前記商品処理装置の前記商品処理を許可した後に前記包装材のロックが解除された場合に、前記商品処理装置の前記商品処理を禁止する、
請求項3に記載の装置管理システム。 - 前記読み取り部は、前記画面内の第1領域から前記第1固有記号を読み取り、前記画面内の第2領域から前記第2固有記号を読み取る、
請求項1から4のいずれか1項に記載の装置管理システム。 - 前記読み取り部および前記制御部は、前記商品処理装置とは異なる管理装置に備えられている、
請求項1から5のいずれか1項に記載の装置管理システム。 - 前記管理装置は、前記商品処理装置とネットワークを介して接続され、
前記撮影部が撮影した前記第1固有記号および前記第2固有記号を前記管理装置に送信する送信部をさらに備える、
請求項6に記載の装置管理システム。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017159724A JP6917618B2 (ja) | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 装置管理システム |
| PCT/JP2018/021852 WO2019039039A1 (ja) | 2017-08-22 | 2018-06-07 | 装置管理システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017159724A JP6917618B2 (ja) | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 装置管理システム |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2019038550A JP2019038550A (ja) | 2019-03-14 |
| JP6917618B2 true JP6917618B2 (ja) | 2021-08-11 |
Family
ID=65438532
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2017159724A Expired - Fee Related JP6917618B2 (ja) | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 装置管理システム |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6917618B2 (ja) |
| WO (1) | WO2019039039A1 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115817939B (zh) * | 2022-09-16 | 2023-11-17 | 锋聚睿(苏州)科技有限公司 | 包装设备的控制方法、装置、计算机设备及存储介质 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0532404Y2 (ja) * | 1988-07-27 | 1993-08-19 | ||
| JP2000006926A (ja) * | 1998-06-24 | 2000-01-11 | Ricoh Logistics Kk | 梱包管理システムおよび管理方法 |
| JP4411023B2 (ja) * | 2003-07-02 | 2010-02-10 | 株式会社川島製作所 | 包装用印刷検査システム |
| JP4738951B2 (ja) * | 2005-09-20 | 2011-08-03 | 株式会社イシダ | 中継装置および中継装置を含む通信システム |
-
2017
- 2017-08-22 JP JP2017159724A patent/JP6917618B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-06-07 WO PCT/JP2018/021852 patent/WO2019039039A1/ja not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2019038550A (ja) | 2019-03-14 |
| WO2019039039A1 (ja) | 2019-02-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6938169B2 (ja) | ラベル生成装置及びプログラム | |
| JP5808353B2 (ja) | 薬剤混合調製管理装置、制御プログラム及び薬剤混合調整管理システム | |
| CN102567909A (zh) | 图像数据销售系统及其方法、照相机、服务器装置 | |
| JP7238295B2 (ja) | 製品の製造方法、製品の製造装置、判定装置およびプログラム | |
| JP5940382B2 (ja) | 引越荷物管理システム及び引越荷物管理方法 | |
| US9288358B2 (en) | Document management system, document management device, and non-transitory computer readable medium | |
| JP6668702B2 (ja) | 顔画像配信システム | |
| JP6917618B2 (ja) | 装置管理システム | |
| JP7363148B2 (ja) | 画像データ販売システム | |
| TWM511082U (zh) | 行動列印系統 | |
| JP7560942B2 (ja) | 情報処理装置および情報処理方法 | |
| JP6497076B2 (ja) | 会計システム、情報処理方法、及び、プリンター | |
| JP7276032B2 (ja) | 撮影システム | |
| JP6508521B2 (ja) | 船荷写真公開システム | |
| JP7650306B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | |
| JP7053694B2 (ja) | プログラム、端末及び管理システム | |
| JP6492964B2 (ja) | Idカード作成装置及びidカード作成システム | |
| JP2019175384A (ja) | 情報処理システム、および情報処理方法 | |
| CN118229373A (zh) | 瑕疵照拍摄方法、装置、设备和存储介质 | |
| JP6881126B2 (ja) | 印画物作成システム | |
| JP4260040B2 (ja) | プリント注文システム,プリント注文受付装置,および画像データ送信装置ならびにそれらの制御方法 | |
| JP2019064639A (ja) | 装置管理システム | |
| JP2006243880A (ja) | 薬情作成システムおよび薬情 | |
| JP7059844B2 (ja) | 画像管理装置及び画像管理方法 | |
| US7668408B2 (en) | Support apparatus for optical characteristic measurement, and program product used for same |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200616 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210525 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210621 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210706 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210713 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6917618 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |