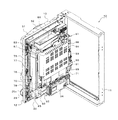以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機(以下、「パチンコ機」という)の一実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図1はパチンコ機10の正面図、図2はパチンコ機10の斜視図、図3はパチンコ機10の前扉枠13を開いた状態の斜視図、図4はパチンコ機10の本体枠12を開いた状態の斜視図である。なお、図1〜図3では便宜上、パチンコ機10の遊技領域内の構成を空白としている。
図1〜図4に示すように、パチンコ機10は、取付対象としての外枠11を備えており、該外枠11の一側部には、本体枠12が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチンコ機10の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸心にして本体枠12が前方に開放できるようになっている。なお、外枠11に代わる構成として設置枠体を遊技ホール側に予め設けておき、遊技ホールへのパチンコ機10の設置に際しては本体枠12を前記設置枠体に組み付ける構成とすることも可能である。
本体枠12の前面側には、本体枠12を覆うようにして前面扉としての前扉枠13が設けられている。前扉枠13は、本体枠12に対して開閉可能に取り付けられており、本体枠12と同様、パチンコ機10の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にして前方に開放できるようになっている。前扉枠13には、その中央部に略円形状の窓部14が形成されている。本体枠12には、窓部14と対応する位置に、遊技盤15が着脱可能に装着されている。そして、遊技盤15の前面部の略中央部分だけが前扉枠13の窓部14を通じて視認可能な状態となっている。本実施の形態では、これら本体枠12、前扉枠13、遊技盤15等により遊技機本体が構成されている。
前扉枠13には、手前側へ膨出した第1膨出部16が窓部14の下方に設けられており、その第1膨出部16内側には、上方に開口した上皿17が設けられている。上皿17は、第1払出口18より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら下流側(本実施の形態では右側)へ導くための球受皿である。第1膨出部16には、上皿17の下流側に球抜きスイッチ19が設けられるとともに、上皿17の前方に貸球操作部20が配設されている。球抜きスイッチ19は、上皿17に貯留された遊技球を排出するために操作されるものである。貸球操作部20には、球貸しボタン21と、返却ボタン22と、度数表示部23とが設けられている。球貸しボタン21は、カード等(記録媒体)に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が払い出される。返却ボタン22は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部23は、カード等の残額情報を表示するものである。また、第1膨出部16の前面側中央部には、遊技者により操作可能なプッシュ式の選択スイッチ24が設けられている。選択スイッチ24には図示しないランプが内蔵されており、選択操作が有効とされる状況下ではランプが点灯表示され、選択操作が無効とされる状況下ではランプが消灯表示されるようになっている。そして、当該ランプが点灯表示されている状況下で選択スイッチ24を操作された場合、図柄表示装置41の表示モードが変更されるようになっている。
前扉枠13の下部位置には、手前側へ膨出した第2膨出部25が設けられており、その第2膨出部25内側には、上方に開口した下皿26が設けられている。下皿26は、第2払出口27より払い出された遊技球を一旦貯留するための球受皿である。下皿26には、例えば球抜きレバー19を操作された場合、上皿17に貯留された遊技球が第2払出口27より排出されるようになっている。第2膨出部25前面側には、下皿26に貯留された遊技球を下方に排出するための球抜きレバー28が設けられている。また、第2膨出部25の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射操作部29が設けられている。遊技球発射操作部29は、上皿17に貯留された遊技球を発射させる場合に操作される操作部である。遊技球発射操作部29は、図2に示すように、略半球状の操作部29aを有しており、操作部29aには、上縁部から右縁部にかけて切欠部29bが形成されている。切欠部29bには、遊技者の接触操作を検知する検知部材29cが設けられている。また、遊技球発射操作部29の左下部には、遊技球の発射を停止させるための止め打ちスイッチ29dが設けられている。
検知部材29cの構成及び作用について簡単に説明する。検知部材29cは、絶縁体が2つの板状部材によって挟持された構成となっている。各板状部材には、対応する板状部材の一端から他端に延びる複数の電極が、平行に、且つ、他方の板状部材に配置された電極と直交して配置されている。このため、各板状部材の電極間に電圧をかけた場合には、一方の板状部材の電極と他方の板状部材の電極との各交点においてコンデンサが形成されることとなる。つまり、検知部材29cには、格子状にコンデンサが形成されることとなる。そして、例えば遊技者が検知部材29cに触れた場合には、その接触位置のコンデンサに蓄えられた電荷が減少するため、各コンデンサの静電容量の変化を通じて検知部材29cのどの位置に遊技者が触れたかを検知することができる。
遊技球発射操作部29(より詳しくは検知部材29c及び止め打ちスイッチ29d)は、本体枠12の背面側に設けられた電源・発射制御装置92(図4参照)と接続されており、電源・発射制御装置92には、遊技球を発射させるための遊技球発射装置30(図4参照)が接続されている。このため、上皿17に貯留された遊技球は、遊技者が遊技球発射操作部29の検知部材29cに触れたことに基づいて、遊技盤15に形成された遊技領域に向けて発射される。
次に、遊技盤15の構成を図5に基づいて説明する。遊技盤15には、遊技球発射装置30より発射された遊技球を遊技盤15上部に案内する内レール31と外レール32が設けられている。内レール31は右上方の約1/2ほどを除いて略半円環状に形成され、外レール32は内レール31の上方開放領域を囲むようにかつ内レール31の左側部と並行するように略半円環状に形成されている。本実施の形態では、遊技盤15のうち内レール31と外レール32によって囲まれた領域が、遊技球の流下可能な遊技領域となっている。
遊技盤15には、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。遊技盤15の表面には、各開口部と対応する位置に、一般入賞口33、可変入賞装置34、作動口装置35、スルーゲート36及び可変表示ユニット37等がそれぞれ取り付けられている。作動口装置35には、上側作動口35aと下側作動口35bとが設けられ、更に下側作動口35bには左右一対の可動片よりなる電動役物が設けられている。本実施の形態では、可変表示ユニット37が遊技盤15の略中央に配置され、その下方に作動口装置35が配置され、さらにその下方に可変入賞装置34が配置されている。また、可変表示ユニット37の左右両側にスルーゲート36が配置され、遊技盤15の下部両側に一般入賞口33がそれぞれ複数配置されている。
前記一般入賞口33、可変入賞装置34及び作動口35a,35bに遊技球が入賞すると、遊技盤15の背面側に設けられた検出スイッチにより検出され、その検出結果に基づいて上皿17(場合によっては下皿26)に対し所定数の賞球が払い出される。また、上側作動口35aと下側作動口35bでは、遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数が相違するようになっており、上側作動口35aに入賞した場合には3個の賞球が払い出され、下側作動口35bに入賞した場合には5個の賞球が払い出されるようになっている。
その他に、遊技盤15の最下部にはアウト口38が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口38を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技盤15には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されていると共に、風車39等の各種部材(役物)が配設されている。
可変表示ユニット37には、作動口35a,35bへの入賞をトリガとして図柄を変動表示する図柄表示装置41が設けられている。可変表示ユニット37には、図柄表示装置41を囲むようにしてセンターフレーム42が配設されている。センターフレーム42の右上部には、所定の識別情報を表示するための第1特定ランプ部43aと第2特定ランプ部43bが横並びの状態で設けられている。センターフレーム42の左上部には、役物ランプ部44と、該役物ランプ部44に対応した役物保留ランプ45が設けられている。遊技球がスルーゲート36を通過した回数は最大4回まで保留され、役物保留ランプ45の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。また、センターフレーム42の左下部には、第1特定ランプ部43a及び図柄表示装置41に対応した第1保留ランプ46aが設けられており、センターフレーム42の右下部には、第2特定ランプ部43b及び図柄表示装置41に対応した第2保留ランプ46bが設けられている。遊技球が作動口35a,35bに入賞した個数はそれぞれ最大4個まで保留され、対応する保留ランプ46a,46bの点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。すなわち、上側作動口35aに遊技球が入賞した場合には第1保留ランプ46aが点灯され、下側作動口35bに遊技球が入賞した場合には第2保留ランプ46bが点灯されるようになっている。
図柄表示装置41は液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置62により表示内容が制御される。図柄表示装置41には、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が左右方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の図柄の組み合わせが停止表示された場合には、大当たり発生としてそれ以降の遊技状態が特別遊技状態としての大当たり状態に移行する。また、図柄表示装置41には、各作動口35a,35bに遊技球が入賞した順序を把握可能に各保留個数が表示されるようになっている。なお、図柄表示装置41は、液晶表示装置の他に、CRT,ドットマトリックス,7セグメント等その他のタイプにより表示画面を構成したものであってもよい。
第1特定ランプ部43a及び第2特定ランプ部43bには、その内側に赤、緑、青の3色発光タイプのLEDが配設されている。各特定ランプ部43a,43bは、対応する作動口35a,35bへの入賞をトリガとして、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。第1特定ランプ部43aを例として具体的に説明すると、上側作動口35aへの入賞をトリガとして、赤色光が点灯され、その状態で所定時間が経過すると緑色光に発光色が切り替えられる。そして、緑色光が点灯された状態で前記所定時間が経過すると青色光に発光色が切り替えられる。その後、発光色の切り替え停止時期がくるまで、赤色、緑色、青色という順序で発光色の切り替えが繰り返し行われる。これにより、第1特定ランプ部43aには、赤色、緑色、青色が、この順序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止表示された場合には、大当たり発生としてそれ以降の遊技状態が大当たり状態に移行し、青色が停止表示された場合には、大当たり発生とならず大当たり状態に移行しない。第2特定ランプ部43bについても同様であり、下側作動口35bへの入賞をトリガとして、赤色、緑色、青色が、この順序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止表示された場合には、大当たり発生としてそれ以降の遊技状態が大当たり状態に移行し、青色が停止表示された場合には、大当たり発生とならず大当たり状態に移行しない。
役物ランプ部44には、その内側に赤、緑の2色発光タイプのLEDが配設されている。この役物ランプ部44は、スルーゲート36の通過をトリガとして、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。具体的には、遊技球がスルーゲート36を通過すると、赤色光の点灯と緑色光の点灯とが交互に行われる。これにより、役物ランプ部44には、赤色、緑色が交互に表示されることとなる。そして、赤色が停止表示された場合には、下側作動口35bに設けられた電動役物が開放状態に切り替えられるようになっている。電動役物は、予め定めた閉鎖条件が成立するまで開放状態が継続されるようになっている。
可変入賞装置34は、通常状態において遊技球が入賞できない閉鎖状態になっており、大当たり状態に移行すると遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り替えられるようになっている。より詳しくは、可変入賞装置34が開放状態となると、可変入賞装置34の大入賞口に遊技球が入賞し易い状態となる。そして、可変入賞装置34は、開放時間(例えば29.5秒)の経過又は所定数(例えば9個)の遊技球が入賞した場合に閉鎖状態に切り替えられる。大当たり状態は、可変入賞装置34が開閉されたことを1ラウンドとして、15ラウンドの開閉が行われるまで継続する。なお、可変入賞装置34の閉鎖状態を、遊技球が入賞できない状態ではなく遊技球が入賞し難い状態としてもよい。
前扉枠13の説明に戻り、前扉枠13にはその周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり状態下や所定のリーチ演出時等において点灯、点滅のように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。例えば、窓部14の上部周縁に沿ってLED等の発光手段を内蔵した電飾部51が設けられ、電飾部51の中央であってパチンコ機10の最上部にはLED等の発光手段を内蔵した中央電飾部52が設けられている。本パチンコ機10では、中央電飾部52が大当たりランプとして機能し、大当たり状態下で点灯や点滅を行うことにより大当たり状態に移行していることを報知する。また、第1膨出部16にも、同じくLED等の発光手段を内蔵した上皿電飾部53が設けられている。さらに、前扉枠13には、電飾部51を挟むようにして左右一対のスピーカカバー部54が形成されており、当該スピーカカバー部54の後方に設置されたスピーカ55の出力音がスピーカカバー部54を通じて前方に発せられるようになっている。
次に、パチンコ機10の背面の構成を説明する。図6は遊技盤15の背面図、図7はパチンコ機10の背面図である。なお、理解を容易なものとするため、先ず遊技盤15の背面の構成を説明する。
遊技盤15の背面側には、可変表示ユニット37及び図柄表示装置41を覆うようにして合成樹脂製のフレームカバー61が設けられており、そのフレームカバー61の後端(図6においては手前側)には、図柄表示装置41と前後に重なるようにして表示制御装置62が着脱可能に取り付けられている。また、フレームカバー61には、表示制御装置62を覆うようにしてサブ制御装置ユニット63が取り付けられている。サブ制御装置ユニット63は、取付台64を有し、該取付台64にサブ制御装置65が搭載されている。サブ制御装置65は、後述する主制御装置71からの指令に基づいて、表示制御装置62や電飾部51等の制御を行う。サブ制御装置ユニット63は、何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に支軸部を設けて遊技盤15の裏面に対して展開できる構成となっている。これは、サブ制御装置ユニット63によって覆われることとなる表示制御装置62等を容易に確認することを可能とするための工夫である。具体的に説明すると、サブ制御装置ユニット63には遊技盤15の背面から見て右端部に支軸部66が設けられ、その支軸部66による軸線を中心にサブ制御装置ユニット63が回動可能となっている。また、サブ制御装置ユニット63には、支軸部66の反対側となる開放端側に、ナイラッチ(登録商標)等よりなる締結部67が設けられており、この締結部67によってサブ制御装置ユニット63が遊技盤15(フレームカバー61)の裏面に沿った状態で保持されるようになっている。
遊技盤15の裏面であって可変表示ユニット37の下方には、集合板ユニット68が設けられている。集合板ユニット68には、各種入賞口に入賞した遊技球やアウト口38を通過した遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための入賞検知機構などが設けられている。
入賞検知機構について簡単に説明すると、集合板ユニット68には、遊技盤15表側の一般入賞口33と対応する位置に入賞口スイッチが設けられ、可変入賞装置34と対応する位置にカウントスイッチが設けられている。カウントスイッチは、可変入賞装置34に入賞した遊技球の数をカウントするスイッチである。また、作動口装置35の上側作動口35aと対応する位置には当該上側作動口35aへの遊技球の入賞を検知する上側作動口スイッチが設けられ、下側作動口35bと対応する位置には当該下側作動口35bへの遊技球の入賞を検知する下側作動口スイッチが設けられている。さらに、スルーゲート36と対応する位置にはスルーゲート36の遊技球の通過を検知するゲートスイッチが設けられている。入賞口スイッチ、ゲートスイッチ及びカウントスイッチは、図示しない中継基板を介して後述する主制御装置71に接続されており、上側作動口スイッチと下側作動口スイッチは、中継基板を介することなく直接主制御装置71に接続されている。
上記入賞検知機構にて各々検出された検出結果は主制御装置71に取り込まれ、該主制御装置71よりその都度の入賞状況に応じた払出指令(遊技球の払出個数)が払出制御装置94に送信される。そして、払出制御装置94の出力により所定数の遊技球の払出が実行されるようになっている。
集合板ユニット68の裏面には、主制御装置ユニット69が取り付けられている。主制御装置ユニット69は、主制御取付台70を有し、該主制御取付台70に主制御装置71が搭載されている。主制御装置71は、遊技に関わる主たる制御を行う。主制御装置ユニット69は、何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に支軸部を設けて遊技盤15の裏面に対して展開できる構成となっている。具体的に説明すると、主制御装置ユニット69には遊技盤15の背面から見て左端部に支軸部72が設けられ、その支軸部72による軸線を中心に主制御装置ユニット69が回動可能となっている。また、主制御装置ユニット69には、その右端部すなわち支軸部72の反対側となる開放端側に、ナイラッチ等よりなる締結部73が設けられており、この締結部73によって主制御装置ユニット69が遊技盤15(集合板ユニット68)の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。
本体枠12には、上述した遊技盤15が裏面側より設置され、本体枠12に設けられた複数の係止固定具によって後方へ脱落しないように固定されている。また、例えば図4等に示すように、本体枠12の開放端側には、施錠装置75が設けられている。施錠装置75は、上下方向に延び本体枠12に固定された基枠76と、その基枠76に対して上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆77とを備え、基枠76の下部にシリンダ錠78が一体化されている。当該施錠装置75は、シリンダ錠78だけが本体枠12の前方に突出するとともにパチンコ機10前面に露出するように、本体枠12に設けられている。シリンダ錠78は、本体枠12の施解錠と前扉枠13の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵穴に差し込んだキーを一方に回すと外枠11に対する本体枠12の施錠が解除され、キーを他方に回すと本体枠12に対する前扉枠13の施錠が解除されるようになっている。本体枠12には、施錠装置75側の下部に、遊技球発射装置30が設けられている。
本体枠12の背面側には、当該本体枠12を覆うようにして裏セット機構81が取り付けられている。裏セット機構81は、何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に支軸部を設けて本体枠12の裏面に対して展開できる構成となっている。具体的に説明すると、裏セット機構81には本体枠12の背面から見て右端部に支軸部82が設けられ、その支軸部82による軸線を中心に裏セット機構81が回動可能となっている。また、裏セット機構81には、支軸部82の反対側となる開放端側に、ナイラッチ等よりなる締結部83が設けられるとともに、本体枠12には、上端部及び下端部にそれぞれ回動式の係止部が設けられており、これら締結部83及び係止部によって裏セット機構81が本体枠12の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。
裏セット機構81には、遊技盤16の背面側を覆うようにして、より具体的には、サブ制御装置ユニット63と主制御装置ユニット69の一部とを覆うようにして、透明樹脂材料にて成形された防護カバー84が設けられている。
また、裏セット機構81には、防護カバー84を迂回するようにして払出機構部85が配設されている。すなわち、裏セット機構81の最上部には上方に開口した貯留タンク86が設けられており、貯留タンク86には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。貯留タンク86の下方には、例えば横方向2列(2条)の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール87が連結され、タンクレール87の下流側には、上下方向に延びるケースレール88が連結されている。ケースレール88の下流側には、払出装置89が設けられている。払出装置89は、遊技球を下流側に払い出すための払出モータ、払出モータの回転を検出する払出回転センサ、払い出される遊技球数をカウントする払出カウントスイッチ等を有する。当該払出装置89は、払出制御装置94からの払出指令により払出モータを駆動し、必要個数の遊技球の払出を適宜行う。払出装置89より払い出された遊技球は、図示しない払出通路等を通じて上皿17又は下皿26に供給される。払出装置89の下方には、裏セット中継基板90が設けられている。裏セット中継基板90は、払出制御装置94から払出装置89への払出指令信号を中継する機能と、外部より例えば交流24ボルトの主電源を取り込む機能とを有する。裏セット中継基板90には電源スイッチ91が設けられており、当該電源スイッチ91を切替操作することで電源ONと電源OFFとを切り替えることができる。
裏セット機構81には、防護カバー84の下方に電源・発射制御装置92が設けられている。電源・発射制御装置92は、裏セット機構81が本体枠12の裏面に沿った状態で保持された場合に、主制御装置71の下方に位置するように設けられている。電源・発射制御装置92は、各種制御装置等で要する所定の電源を生成して出力するとともに、遊技球発射操作部29が操作された場合に遊技球の打ち出しの制御を行う。また、電源・発射制御装置92には、RAM消去スイッチ93が設けられている。本パチンコ機10は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰(復電)の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。しかしながら、RAM消去スイッチ93を押しながら電源を投入した場合には、RAMデータが初期化されるようになっている。電源・発射制御装置92の背面側には、当該電源・発射制御装置92と前後に重なるようにして払出制御装置94が設けられている。払出制御装置94は、賞球や貸出球を払い出す制御を行う。
次に、本パチンコ機10の電気的構成について、図8のブロック図に基づいて説明する。図8では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
主制御装置71に設けられた主制御基板71aには、演算装置である1チップマイコンとしてのCPU101が搭載されている。CPU101には、該CPU101により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM102と、そのROM102内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM103と、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。
RAM103は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源・発射制御装置92に設けられた電源・発射制御基板92aからデータ記憶保持用電源(データ記憶保持用電圧)が供給されてデータが保持される構成となっている。詳細には、電源・発射制御基板92aには、データ記憶保持用コンデンサが設けられており、当該コンデンサからデータ記憶保持用電源が供給される。
主制御基板71aのCPU101には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。主制御基板71aの入力側には、主制御装置71に設けられた電源監視基板71b、払出制御装置94に設けられた払出制御基板94a及びその他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、電源監視基板71bには電源・発射制御基板92aが接続されており、主制御基板71aには電源監視基板71bを介して電源が供給される。
一方、主制御基板71aの出力側には、電源監視基板71b、払出制御基板94a及び中継端子板95が接続されている。払出制御基板94aには、賞球コマンドなどといった各種コマンドが出力される。かかる場合に、当該各種コマンドは、ハーネスを介して一方向通信によって出力される(すなわち、コマンドを入力した旨の情報が払出制御基板94aから主制御基板71aに対して出力されない)。また、中継端子板95を介して主制御基板71aからサブ制御装置65に設けられたサブ制御基板65aに対して各種コマンドなどが出力される。加えて、主制御基板71aの出力側には、各特定ランプ部43a,43bに配設されたLEDのスイッチや役物ランプ部44に配設されたLEDのスイッチも接続されている。つまり、各特定ランプ部43a,43bと役物ランプ部44は、主制御基板71aにより直接的に制御されている。なお、図示は省略したが、主制御基板71aの出力側には、可変表示ユニット37の役物保留ランプ45,第1保留ランプ46a及び第2保留ランプ46bのそれぞれに配設されたランプスイッチも接続されている。
電源監視基板71bは、主制御基板71aと電源・発射制御基板92aとを中継し、また電源・発射制御基板92aから出力される最大電源である直流安定24ボルトの電源を監視する。
払出制御基板94aは、払出装置89を駆動させて賞球や貸し球の払出制御を行うものである。演算装置であるCPU111は、そのCPU111により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM112と、ワークメモリ等として使用されるRAM113とを備えている。
払出制御基板94aのRAM113は、主制御基板71aのRAM103と同様に、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源・発射制御基板92aからデータ記憶保持用電源が供給されてデータを保持できる構成となっている。また、RAM113における各種のカウンタ等が記憶される作業エリアには、コマンド入力フラグ格納エリアなどといった各種フラグ格納エリアと共に、主制御基板71aから出力されたコマンドが記憶されるコマンドバッファ113aが設けられている。
コマンドバッファ113aは、主制御基板71aから出力されるコマンドを一時的に記憶するリングバッファで構成されている。リングバッファは所定の記憶領域を有しており、その記憶領域の始端から終端に至るまで規則性をもってコマンドが記憶され、全ての記憶領域にコマンドが記憶された場合には、記憶領域の始端に戻りコマンドが更新されるよう構成されている。よって、コマンドが記憶された場合及びコマンドが読み出された場合に、コマンドバッファ113aにおける記憶ポインタ及び読出ポインタが更新され、その各ポインタに基づきコマンドの記憶と読み出しとが行われる。
払出制御基板94aのCPU111には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板94aの入力側には、主制御基板71a、電源・発射制御基板92a、及び裏セット中継基板90が接続されている。また、払出制御基板94aの出力側には、主制御基板71aと裏セット中継基板90が接続されている。この場合に、裏セット中継基板90を介して払出装置89などを含む払出機構部85が接続されている。
電源・発射制御基板92aは、演算装置であるCPU121と、そのCPU121により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM122と、ワークメモリ等として使用されるRAM123とを備えており、電源部としての機能と、発射制御部としての機能とを備えている。
電源部は、二重線矢印で示す経路を通じて、主制御基板71aや払出制御基板94a等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては、電源部は、裏セット中継基板90を介して供給される交流24ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための+12V電源、ロジック用の+5V電源、RAMのデータ記憶保持用電源などを生成し、これら+12V電源、+5V電源及びデータ記憶保持用電源を主制御基板71aや払出制御基板94a等に対して供給する。なお、データ記憶保持用電源を生成するとは、データ記憶保持用コンデンサの充電を行うことをいう。
また、電源部には、RAM消去スイッチ回路が設けられている。電源部は、RAM消去スイッチ93のスイッチ信号を読み込み、当該スイッチ93の読み込み状態に応じて、主制御基板71aのRAM103に記憶されたデータをクリアするためのRAM消去信号を出力する。すなわち、RAM消去スイッチ93が押された場合、RAM消去スイッチ回路は主制御基板71aに対してRAM消去信号を出力する。これにより、RAM消去スイッチ93が押された状態でパチンコ機10の電源が投入されると、主制御基板71aにおいてRAM103のデータがクリアされる。また、この際、主制御基板71aから払出制御基板94aに対して払出初期化コマンドが出力され、払出制御基板94aにおいてもRAM113のデータがクリアされる。
発射制御部は、遊技者による遊技球発射操作部29の操作に基づいて遊技球発射装置30の発射制御を担うものである。電源・発射制御基板92aの入力側には、遊技球発射操作部29の検知部材29c及び止め打ちスイッチ29dが接続されており、出力側には、変換器124を介して遊技球発射装置30が接続されている。電源・発射制御基板92aは、検知部材29c及び止め打ちスイッチ29dからの信号入力状況に基づいて、遊技球を発射させるか否かや遊技球を発射させる際の発射強度等を制御する。なお、発射制御の詳細については後述することとする。
サブ制御基板65aは、表示制御装置62やスピーカ55、電飾部65の制御を行うものである。サブ制御基板65aは、CPU、ROM及びRAM等を備えており、CPUにはアドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。サブ制御基板65aの入力側には、中継端子板95を介して主制御基板71aが接続されるとともに、選択スイッチ24が接続されている。サブ制御基板65aは、主制御基板71aから出力される各種コマンドや遊技者による選択スイッチ24の操作に基づいて、表示制御装置62に対して各種コマンドを出力するとともに、スピーカ55、電飾部65の駆動制御を行う。表示制御装置62は、サブ制御基板65aから出力される各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41における図柄の変動表示や各保留個数の表示等を制御する。なお、サブ制御基板65aが表示制御装置62を介することなく図柄表示装置41を直接制御する構成としても良いし、主制御基板71aからの各種コマンドが表示制御装置62に直接入力される構成としても良い。或いは、サブ制御装置65及び表示制御装置62に代えて、前記サブ制御装置の機能と前記表示制御装置の機能とを有する制御装置を設ける構成としても良い。
ここで、電源監視基板71bは、上述したように、電源・発射制御基板92aから出力される最大電源である直流安定24ボルトの電源を監視する。より詳しくは、電源監視基板71bは、電源が22ボルト未満になると停電(電源遮断)の発生と判断し、主制御基板71aのCPU101に設けられたNMI端子(ノンマスカブル割込端子)に停電信号SG1を出力する。停電信号SG1が入力された場合、主制御基板71aは、停電の発生を認識してNMI割込み処理を即座に実行し、さらにこれに基づいて後述する停電時処理を実行する。なお、NMI端子とは、割込禁止設定をできない割込端子のことをいう。
また、主制御基板71aは、停電時処理において、払出制御基板94aのCPU111に設けられたNMI端子(ノンマスカブル割込端子)へ停電信号SG2を出力する。停電信号SG2が入力された場合、払出制御基板94aは、停電の発生を認識してNMI割込み処理を即座に実行し、さらにこれに基づいて停電時処理を実行する。すなわち、本パチンコ機10の場合、払出制御基板94aは、電源監視基板71bから停電信号が直接入力されるのではなく、主制御基板71aを介して停電信号が入力される。さらにいうと、停電信号SG2は払出制御基板94aのNMI端子に入力される構成であるため、停電信号SG2を伝送するための信号線は、賞球コマンドなどといったコマンド信号を伝送するための信号線とは別個に設けられている。
なお、電源・発射制御基板92aは、直流安定24ボルトの電源が22ボルト未満になった後においても、停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電源である5ボルトの出力を正常値に維持するように構成されている。詳細には、電源及び発射制御基板92aには、上述したデータ記憶保持用コンデンサとは異なる停電時処理用コンデンサが設けられており、当該コンデンサからの放電により5ボルト電源が維持されるようになっている。このため、主制御基板71aと払出制御基板94aは、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
次に、遊技球の発射に関わる各制御処理を、図9〜図12のフローチャートを参照しながら説明する。本パチンコ機10では、主制御装置71と、電源・発射制御装置92と、が各種処理を実行することによって遊技球が発射されるようになっている。
先ず、主制御装置71内のCPU101により実行される第1処理及び発射許可処理を説明する。かかるCPU101の処理としては、大別して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に(本実施の形態では2msec周期で)起動されるタイマ割込み処理と、NMI端子(ノンマスカブル端子)への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理とがある。第1処理は、タイマ割込み処理において行われ、発射許可処理は、メイン処理において行われる。
第1処理では、図9のフローチャートに示すように、ステップS101において要求信号が入力されているか否かを判定する。詳細は後述するが、要求信号とは、電源・発射制御装置92から主制御装置71に対して出力される信号である。要求信号が入力されている場合には、ステップS102にて要求フラグをセットした後にステップS105に進む。要求信号が入力されていない場合には、ステップS103にて要求フラグがセットされているか否かを判定する。要求フラグがセットされている場合には、ステップS104にて要求フラグをクリアした後にステップS105に進み、要求フラグがセットされていない場合には、そのままステップS105に進む。ステップS105では、CPU101のRAM103に設けられたタイマカウンタtcの値が0か否かを判定し、0である場合にはそのまま本処理を終了する。一方、タイマカウンタtcの値が0でない場合には、ステップS106にてタイマカウンタtcの値を1減算し、本処理を終了する。
発射許可処理では、図10のフローチャートに示すように、ステップS201において要求フラグがセットされているか否かを判定する。要求フラグがセットされている場合には、ステップS202に進み、タイマカウンタtcの値が0か否かを判定する。タイマカウンタtcの値が0である場合には、ステップS203に進み、電源・発射制御装置92に対して許可コマンドを送信する。その後、ステップS204にてタイマカウンタtcに300をセットし、本処理を終了する。一方、要求フラグがセットされていない場合、及びタイマカウンタの値が0でない場合には、許可コマンドを送信することなく本処理を終了する。
このように、主制御装置71は、電源・発射制御装置92からの要求信号が入力されていることと、タイマカウンタtcの値が0であることと、を条件として、電源・発射制御装置92に対して許可コマンドを送信する。また、タイマカウンタtcの値は、許可コマンドの送信後に300がセットされ、第1処理のステップS106において1減算される。第1処理は2msec周期で起動されるタイマ割込み処理において行われるため、タイマカウンタtcの値は、許可コマンドが送信されてから600msec経過した後に0となる。したがって、主制御装置71は、要求信号が継続して入力されている場合、許可コマンドを600msec周期で電源・発射制御装置92に送信する。
次に、電源・発射制御装置92内のCPU121によりにより実行される第2処理及び発射処理を説明する。かかるCPU121の処理としては、大別すると、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に(本実施の形態では2msec周期で)起動されるタイマ割込み処理とがある。第2処理は、タイマ割込み処理において行われ、発射処理は、メイン処理において行われる。
第2処理では、図11のフローチャートに示すように、ステップS301において検知部材監視処理を行う。検知部材監視処理では、検知部材29cに形成された各コンデンサの静電容量が変化したか否かを監視する。より具体的には、検知部材29cの電極に供給される電流を監視する。ステップS302では、検知部材監視処理の処理結果に基づいて、検知部材29cに遊技者が触れたか否かを判定する。上述したとおり、遊技者が検知部材29cに触れた場合には、その接触位置のコンデンサに蓄えられた電荷が減少するため、これに伴って対応する電極に供給される電流が変化することとなる。そこで、ステップS302では、検知部材29cの電極に供給される電流が変化した場合、遊技者が検知部材29cに触れたと判定し、検知部材29cの電極に供給される電流が変化していない場合、遊技者が検知部材29cに触れていないと判定する。
遊技者が検知部材29cに触れた場合には、ステップS303に進み、検知部材29cのどの位置に遊技者が触れたかを特定する。具体的には、検知部材29cの各板状部材において電流に変化が生じた電極をそれぞれ特定する。そして、一方の板状部材において特定した電極と、他方の板状部材において特定した電極と、の交点を接触位置と特定する。続くステップS304では、補正処理を行う。遊技球発射操作部29の操作部29aには上縁部から右縁部にかけて検知部材29cが設けられているため、例えば遊技者が操作部29aをパチンコ機10前方から覆うようにして掴んだ場合には、検知部材29cに遊技者の指が複数接触する可能性がある。また、1本の指のみが検知部材29cに接触した場合であっても、指の向きによって接触位置が複数特定される可能性がある。そこで、補正処理では、ステップS303にて複数の接触位置を特定した場合に、接触位置を限定する処理を行う。具体的には、検知部材29cの左端を始点位置とし、複数の接触位置のうち左右方向において始点位置に最も近い接触位置を特定する。その後、ステップS305では、接触位置を示す位置情報を、RAM123に設けられた位置情報記憶エリアに記憶する。ステップS302にて遊技者が検知部材29cに触れていないと判定した場合には、ステップS306に進み、位置情報が位置情報記憶エリアに記憶されているか否かを判定する。位置情報が記憶されていない場合には、そのままステップS308に進み、位置情報が記憶されている場合には、ステップS307にて位置情報をクリアした後にステップS308に進む。
ステップS308では、止め打ち操作がなされているか否かを判定する。具体的には、止め打ちスイッチ29dからの信号入力状況を確認し、止め打ち信号が入力されている場合には止め打ち操作がなされていると判定し、止め打ち信号が入力されていない場合には止め打ち操作がなされていないと判定する。止め打ち操作がなされている場合には、ステップS309にて止め打ちフラグをセットした後、ステップS312に進む。止め打ち操作がなされていない場合には、ステップS310にて止め打ちフラグがセットされているか否かを判定する。止め打ちフラグがセットされていない場合には、そのままステップS312に進み、止め打ちフラグがセットされている場合には、ステップS311にて止め打ちフラグをクリアした後にステップS312に進む。
ステップS312では、主制御装置71から許可コマンドを受信しているか否かを判定する。許可コマンドを受信していない場合には、そのまま本処理を終了し、許可コマンドを受信している場合には、ステップS313にて許可フラグをセットした後に本処理を終了する。
次に、発射処理を、図12のフローチャートに基づいて説明する。
発射処理では、ステップS401にて位置情報記憶エリアに位置情報が記憶されているか否かを判定する。位置情報が記憶されている場合には、ステップS402にて止め打ちフラグがセットされていないか否かを判定する。位置情報が記憶されているとともに止め打ちフラグがセットされていない場合には、遊技者が止め打ちスイッチ29dを操作することなく検知部材29cに触れていること、すなわち遊技者が遊技球を発射させるべく遊技球発射操作部29を操作していることを意味する。かかる場合には、ステップS403に進み、主制御装置71に対して要求信号を出力中であるか否かを判定する。要求信号を出力中である場合には、そのままステップS405に進み、要求信号を出力中でない場合には、ステップS404にて要求信号を出力状態に切り替えた後にステップS405に進む。
ステップS405では、許可フラグがセットされているか否かを判定し、許可フラグがセットされていない場合には、そのまま本処理を終了する。一方、許可フラグがセットされている場合には、主制御装置71からの許可信号が入力されたことを意味する。そこで、ステップS406〜ステップS410では、遊技球発射装置30を駆動制御するための駆動制御処理を行う。駆動制御処理では、先ずステップS406にて位置情報記憶エリアに記憶された位置情報を読み込む。続くステップS407では、RAM123に記憶された発射強度テーブルを参照する。発射強度テーブルとは、位置情報と、遊技球発射装置30(より詳しくは遊技球を遊技領域に向けて発射させるための発射ソレノイド)の発射強度と、の対応関係を定めたテーブルである。発射強度テーブルには、位置情報の示す接触位置が始点位置から遠いほど発射強度が強くなるように、位置情報と発射強度との対応関係が設定されている。ステップS408では、読み込んだ位置情報と対応する発射強度を発射強度テーブルから取得する。例えば、遊技者が検知部材29cの左端部に触れたことを示す位置情報を読み込んだ場合には、遊技球が遊技領域まで飛翔しない発射強度、すなわち所謂ファール球となる発射強度を取得し、遊技者が検知部材29cの右端部に触れたことを示す位置情報を読み込んだ場合には、遊技球が遊技領域の右上端部まで飛翔する発射強度、すなわち所謂ゴム打ちの発射強度を取得する。ステップS409では、取得した発射強度と対応する駆動信号を変換器124に出力する。変換器124は、駆動信号が入力された場合、駆動信号を、遊技球発射装置30に設けられた発射ソレノイドを励磁するための励磁信号に変換し、遊技球発射装置30に出力する。これにより、遊技球発射装置30の発射ソレノイドが励磁され、1個の遊技球が遊技領域に向けて発射される。駆動信号を出力した場合には、ステップS410にて許可フラグをクリアし、本処理を終了する。
一方、ステップS401にて位置情報が記憶されていないと判定した場合には、遊技者が検知部材29cに触れていないことを意味し、ステップS402にて止め打ちフラグがセットされていると判定した場合には、遊技者が検知部材29cに触れている一方で止め打ちスイッチ29dを操作していることを意味する。すなわち、遊技者が遊技球を発射させるべく遊技球発射操作部29を操作していないことを意味する。そこで、ステップS411では、要求信号を出力中であるか否かを判定する。要求信号を出力中でない場合には、そのまま本処理を終了し、要求信号を出力中である場合には、要求信号を非出力状態に切り替えた後に本処理を終了する。
このように、電源・発射制御装置92は、検知部材29cに遊技者が触れていることと、止め打ちスイッチ29dが操作されていないことと、を条件として、主制御装置71に対して要求信号を出力する。そして、要求信号を出力している状況下で許可コマンドを受信した場合には、遊技者が検知部材29cに触れている接触位置に応じた発射強度を決定し、駆動信号を出力する。したがって、遊技者が遊技球を発射させるべく遊技球発射操作部29を操作している場合には、許可コマンドを受信する毎に遊技球発射装置30の発射ソレノイドが励磁され、1個の遊技球が遊技領域に向けて発射される。
以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
遊技球発射操作部29に検知部材29cを設け、遊技者が検知部材29cに触れた場合には、当該結果に基づいて発射強度を決定する構成とした。かかる構成においては、所定方向に可動するとともに発射強度を決定すべく遊技者に操作される可動部が不要となり、異物を用いて遊技球発射操作部29が固定されることを防止することが可能となる。故に、遊技球発射操作部29に過度の負担が生じることを防止することが可能となり、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。また、遊技者は検知部材29cに触れることで発射強度を調整することが可能なため、遊技者が疲労を感じる機会を低減させることが可能となる。以上の結果、遊技者が疲労を感じる機会を低減させつつ、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。
遊技者が検知部材29cに触れた場合、その接触位置を特定し、当該特定結果に基づいて発射強度を決定する構成とした。かかる構成とすることにより、可動部を非具備とした場合であっても、遊技者の操作に基づいて発射強度を決定することが可能となる。
接触位置を特定した場合には、補正処理を行って接触位置を限定する構成とした。かかる構成とすることにより、検知部材29cに複数の指が接触した場合や、検知部材29cに形成された複数のコンデンサに指が接触した場合等であっても、好適な形で発射強度を決定することが可能となる。さらにいうと、かかる補正処理を行う構成とすることにより、検知部材29cの各板状部材に電極をより多く設けることが可能となり、検知部材29cに触れたか否かを判定する際や接触位置を特定する際の解析能力を高めることが可能となる。この結果、遊技者が検知部材29cに触れたにもかかわらず当該結果が検知されず、遊技球が発射されないという不具合の発生を回避することが可能となる。
補正処理では、検知部材29cの左端を始点位置とし、複数の接触位置のうち左右方向において始点位置に最も近い接触位置を特定する構成とした。かかる構成とすることにより、遊技者が疲労を感じる機会を低減させることが可能となる。すなわち、例えば従来のパチンコ機に慣れ親しんだ遊技者は、遊技球発射操作部29を前方から覆うようにして掴むものと考えられる。かかる場合、検知部材29cに例えば人差し指と中指等の複数の指が接触することが考えられ、例えば複数の接触位置のうち左右方向において始点位置に最も遠い接触位置を特定する構成とした場合、人差し指が検知部材29cに接触しないように遊技球発射操作部29を掴む必要が生じ、遊技を長時間行った場合に遊技者が疲労を感じる可能性が懸念されるからである。
電源・発射制御装置92のRAM123には、位置情報と、遊技球発射装置30の発射強度と、の対応関係を定めた発射強度テーブルを予め記憶した。かかる構成とすることにより、遊技球発射装置30を駆動制御するための駆動制御処理において比較的速やかに発射強度を決定することが可能となる。
発射強度テーブルには、位置情報の示す接触位置が始点位置から遠いほど発射強度が強くなるように、位置情報と発射強度との対応関係を設定し、検知部材29cの始点位置を検知部材29cの左端とした。かかる構成とすることにより、遊技者が発射強度を調整する際の操作を容易なものとすることが可能となる。遊技球発射装置30により発射された遊技球は、遊技領域の左端部から視認可能となる。そして、遊技球は、発射強度が強くなるほど左右方向において右方に飛翔するようになる。このため、検知部材29cの始点位置を検知部材29cの左端とし、接触位置が始点位置から遠いほど発射強度が強くなる構成とすることにより、遊技者が遊技球の飛翔度合いを確認した上で発射強度を調整する場合に、当該遊技者は遊技球を飛翔させたい向きと同じ向きに検知部材29cに触れている指等を移動させれば良いからである。
なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
(1)上記実施の形態では、遊技球発射操作部29の操作部29aに、上縁部から右縁部にかけて検知部材29cを設ける構成としたが、かかる構成に限定されるものではなく、右縁部から下縁部にかけて検知部材29cを設ける構成としても良いし、操作部29aの周縁部全てに検知部材29cを設ける構成としても良い。すなわち、検知部材29cを設ける位置や検知部材29cの左右方向の長さは任意である。
(2)上記実施の形態では、検知部材29cの左端を始点位置とし、補正処理において左右方向における始点位置に最も近い接触位置を特定する構成としたが、検知部材29cの右端を始点位置とし、補正処理において左右方向における始点位置に最も遠い接触位置を特定する構成としても良い。かかる構成とした場合であっても、上記実施の形態と同様の作用効果を奏することは明らかである。
(3)上記実施の形態における補正処理では、左右方向において始点位置に最も近い接触位置を特定する構成としたが、始点位置から最も遠い接触位置を特定する構成としても良い。また、始点位置に最も近い接触位置と最も遠い接触位置を特定し、これらの中間位置を発射強度の決定に用いる構成としても良い。
(4)上記実施の形態における補正処理では、左右方向において接触位置を限定する構成としたが、前後方向において接触位置を限定する構成としても良い。また、検知部材を上下方向に延びるように設けた場合には、上下方向において接触位置を限定する構成とすれば良い。
(5)上記実施の形態では、検知部材29cの左端を始点位置としたが、検知部材29cの右端を始点位置としても良いし、検知部材29cの中央を始点位置としても良い。つまり、基準となる初期位置が予め定められている構成であれば良い。
(6)上記実施の形態における発射強度テーブルには、位置情報の示す接触位置が始点位置から遠いほど発射強度が強くなるように、位置情報と発射強度との対応関係を設定したが、位置情報の示す接触位置が始点位置から遠いほど発射強度が弱くなるように、位置情報と発射強度との対応関係を設定しても良い。
(7)上記実施の形態では、左右方向における始点位置から接触位置までの距離に基づいて発射強度を決定する構成としたが、かかる構成を変更する。具体的には、遊技者が検知部材29cに触れた場合、その接触位置を特定する。そして、遊技者が接触位置に触れている指を検知部材29cに触れた状態でスライド移動させた場合には、前記接触位置からの移動距離を算出し、当該移動距離に基づいて発射強度を決定する。かかる構成とした場合であっても、所定方向に可動するとともに発射強度を決定すべく遊技者に操作される可動部が不要となり、異物を用いて遊技球発射操作部29が固定されることを防止することが可能となる。故に、遊技球発射操作部29に過度の負担が生じることを防止することが可能となり、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。また、遊技者は検知部材29cに触れることで発射強度を調整することが可能なため、遊技者が疲労を感じる機会を低減させることが可能となる。以上の結果、遊技者が疲労を感じる機会を低減させつつ、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。
また、かかる構成においては、最初に特定した接触位置が始点位置となるため、始点位置を予め定めておかずとも発射強度を決定することができる。
(8)上記実施の形態では、遊技球発射操作部29の操作部29aを半円球状に形成したが、かかる構成に限定されるものではなく任意である。例えば、操作部を矩形のボックス形状とし、一側面に検知部材を設ける構成としても良い。
(9)上記実施の形態では、検知部材29cにコンデンサが格子状に形成される構成としたが、左右方向における始点位置と接触位置の距離に基づいて発射強度を決定する構成においては、少なくとも左右方向にコンデンサが複数形成される構成であれば良い。
(10)上記実施の形態では、発射強度を電源・発射制御装置92が決定する構成としたが、主制御装置71や遊技球発射装置30が決定する構成としても良いことは言うまでもない。
(11)上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等に適用しても良いことは言うまでもない。例えば、作動口を遊技球が通過したことを契機として第1抽選を行い、この第1抽選に当選すると特別装置が所定の開放状態となり、特別装置の特定領域に遊技球が入ると大当たり発生となるタイプのパチンコ機に適用しても良い。また、遊技者に払い出すべき賞球を仮想遊技媒体として貯留記憶する貯留記憶手段を備えたパチンコ機に適用しても良い。
以下、本発明の遊技機を、必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。
遊技機1.遊技球が飛翔する遊技球飛翔領域(遊技領域)を備えた遊技機本体(遊技盤15を含む本体枠12)と、
遊技球を前記遊技球飛翔領域に飛翔させるべく操作される操作手段(遊技球発射操作部29)と、
前記操作手段が操作されたことに基づいて遊技球を前記遊技球飛翔領域に向けて発射させる遊技球発射手段(遊技球発射装置20)と
を備えた遊技機において、
前記操作手段に設けられ、遊技者が接触したことを検知する接触検知手段(検知部材29c)と、
前記接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、当該検知結果に基づいて前記遊技球発射手段が遊技球を発射させる際の発射強度を決定する発射強度決定手段(電源・発射制御装置92の発射強度決定処理機能S406〜S408)と
を備え、
所定方向に可動するとともに前記発射強度を決定すべく遊技者に操作される可動手段を非具備としたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、所定方向に可動するとともに発射強度を決定すべく遊技者に操作される可動手段を備えておらず、接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、当該検知結果に基づいて遊技球発射手段が遊技球を発射させる際の発射強度が決定される。かかる構成とすることにより、異物を用いて操作手段が固定されることを防止することが可能となり、操作手段に過度の負担が生じることを防止することが可能となる。故に、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。また、遊技者は接触検知手段に触れることで発射強度を調整することが可能なため、遊技者が疲労を感じる機会を低減させることが可能となる。以上の結果、遊技者が疲労を感じる機会を低減させつつ、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。
遊技機2.上記遊技機1において、前記接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、遊技者が接触した接触位置を特定する接触位置特定手段(電源・発射制御装置92の接触位置特定処理機能S303)を備え、前記発射強度決定手段は、前記接触位置特定手段の特定結果に基づいて前記発射強度を決定することを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、遊技者の接触した接触位置が特定され、当該特定結果に基づいて発射強度が決定される。かかる構成とすることにより、可動手段を非具備とした場合であっても、遊技者の操作に基づいて発射強度を決定することが可能となる。
遊技機3.上記遊技機2において、前記接触位置特定手段が前記接触位置を複数特定した場合、前記複数の接触位置から前記発射強度決定手段が前記発射強度を決定する際に用いる接触位置を決定する決定手段(電源・発射制御装置92の補正処理機能S304)を備えたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触位置特定手段が接触位置を複数特定した場合、複数の接触位置から発射強度決定手段が発射強度を決定する際に用いる接触位置が決定される。かかる構成とすることにより、例えば遊技者の複数の指が接触検知手段に接触した場合であっても、好適な形で発射強度を決定することが可能となる。
遊技機4.上記遊技機2又は遊技機3において、前記接触位置と前記発射強度との対応関係を予め定めた対応関係情報群(発射強度テーブル)を備えたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触位置と発射強度との対応関係が予め定められているため、接触位置を特定した場合に比較的速やかに発射強度を決定することが可能となる。
遊技機5.上記遊技機2又は遊技機3において、予め定めた初期位置を記憶する初期位置記憶手段(電源・発射制御装置92のROM122)を備え、前記接触位置特定手段は、前記接触位置として前記初期位置からの距離を特定することを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、予め初期位置が定められており、遊技者が接触検知手段に接触した場合、接触位置として初期位置からの距離が特定される。かかる構成とすることにより、接触位置を用いて発射強度を決定することが可能となる。
遊技機6.上記遊技機5において、前記初期位置から前記接触位置までの距離が長くなるほど前記発射強度が強くなるように、前記接触位置と前記発射強度との対応関係を予め定めた対応関係情報群(発射強度テーブル)を備えたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触位置と発射強度との対応関係が予め定められているため、接触位置を特定した場合に比較的速やかに発射強度を決定することが可能となる。また、初期位置から接触位置までの距離が長くなるほど発射強度が強くなる構成とすることにより、遊技者が発射強度を調整する際の操作を容易なものとすることが可能となる。
遊技機7.上記遊技機6において、前記遊技球飛翔領域を、前記遊技球発射手段により発射された遊技球が前記遊技球飛翔領域の左端部から視認可能となる構成とし、前記初期位置を、前記接触検知手段の左端部としたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、遊技球は遊技球飛翔領域の左端部から視認可能となり、初期位置は接触検知手段の左端部とされている。かかる構成においては、遊技者が遊技球の飛翔度合いを確認した上で発射強度を調整する場合に、当該遊技者は遊技球を飛翔させたい向きと同じ向きに接触検知手段に触れている指等を移動させれば良い。故に、遊技者が発射強度を調整する際の操作を容易なものとすることが可能となる。
遊技機8.上記遊技機1乃至遊技機7のいずれかにおいて、前記接触検出手段は、遊技者が接触可能な位置に複数のコンデンサを備えることを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触検出手段は遊技者が接触可能な位置に複数のコンデンサを備えているため、各コンデンサの静電容量の変化を通じて遊技者が接触したか否かを検知することが可能となる。また、複数のコンデンサを遊技者が接触可能な位置に設けることにより、接触検出手段のどの位置に遊技者が触れたかを検知することが可能となる。
遊技機9.遊技球が飛翔する遊技球飛翔領域(遊技領域)を備えた遊技機本体(遊技盤15を含む本体枠12)と、
遊技球を前記遊技球飛翔領域に飛翔させるべく操作される操作手段(遊技球発射操作部29)と、
前記操作手段が操作されたことに基づいて遊技球を前記遊技球飛翔領域に向けて発射させる遊技球発射手段(遊技球発射装置20)と
を備えた遊技機において、
前記操作手段に設けられ、遊技者が接触したことを検知する接触検知手段(検知部材29c)と、
前記接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、遊技者が接触した接触位置を特定する接触位置特定手段(電源・発射制御装置92の接触位置特定処理機能S303)と、
前記接触位置特定手段の特定結果に基づいて前記遊技球発射手段が遊技球を発射させる際の発射強度を決定する発射強度決定手段(電源・発射制御装置92の発射強度決定処理機能S406〜S408)と
を備えたことを特徴とする遊技機。
本遊技機によれば、接触検知手段が遊技者の接触を検知した場合、遊技者の接触した接触位置が特定され、当該特定結果に基づいて遊技球発射手段が遊技球を発射させる際の発射強度が決定される。かかる構成においては、所定方向に可動するとともに発射強度を決定すべく遊技者に操作される可動手段が不要となり、異物を用いて操作手段が固定されることを防止することが可能となる。故に、操作手段に過度の負担が生じることを防止することが可能となり、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。また、遊技者は接触検知手段に触れることで発射強度を調整することが可能なため、遊技者が疲労を感じる機会を低減させることが可能となる。以上の結果、遊技者が疲労を感じる機会を低減させつつ、遊技場等が不利益を被ることを抑制することが可能となる。
10…遊技機としてのパチンコ機、11…外枠、12…本体枠、13…前扉枠、15…遊技盤、29…遊技球発射操作部、29a…操作部、29c…接触検知手段としての検知部材、29d…止め打ちスイッチ、30…遊技球発射手段としての遊技球発射装置、34…可変入球装置としての可変入賞装置、35…作動口装置、35a…第1作動口としての上側作動口、35b…第2作動口としての下側作動口、37…可変表示ユニット、41…絵柄表示装置及び保留状況表示手段としての図柄表示装置、43a…第1識別情報表示手段としての第1特定ランプ部、43b…第2識別情報表示手段としての第2特定ランプ部、44…役物ランプ部、71…主制御装置、92…電源・発射制御装置。