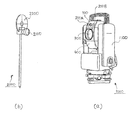JP3731021B2 - 位置検出測量機 - Google Patents
位置検出測量機 Download PDFInfo
- Publication number
- JP3731021B2 JP3731021B2 JP03321797A JP3321797A JP3731021B2 JP 3731021 B2 JP3731021 B2 JP 3731021B2 JP 03321797 A JP03321797 A JP 03321797A JP 3321797 A JP3321797 A JP 3321797A JP 3731021 B2 JP3731021 B2 JP 3731021B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- target
- surveying instrument
- light receiving
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C15/00—Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
- G01C15/002—Active optical surveying means
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Measurement Of Optical Distance (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、ターゲットの位置を検出するための位置検出測量機に係わり、特に、自動測量装置に最適であり、高価な音響光学素子を使用することなく、省電力、小型化が可能な位置検出測量機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、ターゲットの位置を検出することのできる自動測量装置が開発され、測量のワンマン化が進んでいる。この自動測量装置は、走査部や、測距部、測角部等を備えており、本体を水平方向に回転させるための駆動手段や、鏡筒を垂直回転させるための駆動手段等から構成されていた。
【0003】
ターゲットに設けられているプリズムの検出には、走査部からターゲットに向けて射出された光の反射光を利用しており、受光された反射光を受光部で、受光信号に変換し、回転手段や駆動手段にフィードバック制御することにより、自動測量装置をターゲットの方向に向ける構成となっている。
【0004】
走査部から射出されたレーザー光は、音響光学素子により、水平方向、及び垂直方向に偏向され、射出方向の特定の部分を例えば、リサージュ走査する様になっている。
【0005】
ここで、図15に基づいて、音響光学素子を利用した偏向手段について説明する。
【0006】
レーザーダイオード21は、走査光として赤外レーザー光を出射し、コリメータレンズにより平行光束に変換される。水平偏向素子23と垂直偏向素子24とが、音響光学素子であり、水平偏向素子23は赤外レーザーを水平方向Hに偏向させ、垂直偏向素子24は、赤外レーザー光を垂直方向Vに偏向させる様になっている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記音響光学素子を利用した偏向手段は、非常に高価でコストアップの原因となる上、発熱を伴うので、消費電力が増大し、小型電池による駆動が事実上困難となるという問題点があった。
【0008】
従って、ライン電源や、大型のバッテリーパックを持参する必要があり、携帯性に劣る上、測量の作業効率も低下するという深刻な問題点があった。
【0009】
更に音響光学素子は、偏向角に限界があり、走査範囲を広げるためには、鏡筒を鉛直方向に回転させる必要があるという問題点があった。
【0010】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題に鑑み案出されたもので、装置本体を水平回転させ鏡筒を垂直回転させてターゲットの位置を検出するための位置検出測量機において、前記鏡筒は、光波距離計と、前記ターゲットに向けて上下方向に扇状光を照射するための発光部と、前記ターゲットからの反射光を検出する受光部とを備え、この受光部が前記ターゲットからの反射光を検出することにより、前記装置本体の水平回転を前記ターゲットに向けて停止させ、前記光波距離計が前記ターゲットからの反射光を検出することにより、前記鏡筒の垂直回転を前記ターゲットに向けて停止させるための演算処理手段とからなる位置検出測量機。
【0011】
また本発明の受光部は、発光部を挟んで水平方向に一対の受光部が配置され、装置本体の水平回転方向と一対の受光部のどちらが先に受光されたかによって、ターゲットであるか、不要反射体であるかを識別する構成にすることもできる。
【0012】
更に本発明の発光部の扇状光は、ポインタービームに切り替え可能であって、水平回転と垂直回転を、ターゲットに向けて停止させた後、扇状光からポインタービームに切り替えて、前記ターゲットに向けてポインタービームを投射する構成にすることもできる。
【0016】
【発明の実施の形態】
以上の様に構成された本発明は、装置本体を水平回転させ鏡筒を垂直回転させてターゲットの位置を検出するための位置検出測量機であって、発光部が、ターゲットに向けて上下方向に扇状光を照射させ、受光部が、ターゲットからの反射光を検出する様になっており、演算処理手段が、受光部がターゲットからの反射光を検出することにより、装置本体の水平回転をターゲットに向けて停止させ、光波距離計がターゲットからの反射光を検出することにより、鏡筒の垂直回転をターゲットに向けて停止させることができる。
【0017】
また本発明の受光部は、発光部を挟んで水平方向に一対の受光部が配置され、装置本体の水平回転方向と一対の受光部のどちらが先に受光されたかによって、ターゲットであるか、不要反射体であるかを識別することもできる。
【0018】
更に本発明の発光部の扇状光は、ポインタービームに切り替え可能であって、水平回転と垂直回転を、ターゲットに向けて停止させた後、扇状光からポインタービームに切り替えて、ターゲットに向けてポインタービームを投射することもできる。
【0021】
【実施例】
【0022】
「原理」
【0023】
まず、本発明の「上下方向に扇状となる光」を照射させる発光手段100の原理を図13(a)及び図13(b)に基づいて説明する。
【0024】
発光手段100は、図13(a)及び図13(b)に示す様に、光源110と、コリメートレンズ120と、シリンドリカルレンズ130とから構成されている。
【0025】
光源110はレーザー光源を発生させるもので、本実施例では、レーザーダイオードが採用されている。
【0026】
コリメートレンズ120は、光源110からのレーザー光を平行光束に変換するためのものである。
【0027】
シリンドリカルレンズ130は、図13(a)に示す様に、側面から見ると1面が凸レンズとなっているものか、或いは、図13(b)に示す様に側面から見ると、1面が凹レンズとなっているものを使用することができる。
【0028】
従って、図13(a)に示す様に、シリンドリカルレンズ130に平行光束を入射させると、焦点距離Fで集光されるが、焦点距離Fより離れた位置では、上下方向に扇状となる光となる。
【0029】
また、図13(b)に示す様に、シリンドリカルレンズ130に平行光束を入射させると、上下方向に扇状となる光が射出される。
【0030】
「第1実施例」
【0031】
本発明の第1実施例を図面に基づいて説明する。
【0032】
図1(a)は、本第1実施例の自動測量機1000を示す斜視図であり、自動測量機1000は、自動測量機本体1100と、発光手段100と、受光手段200と、光波距離計300と、鏡筒400とから構成されている。
【0033】
本第1実施例では、光波距離計300と視準望遠鏡が同軸に構成されている。
【0034】
発光手段100は、図1(b)に示すターゲット2000のプリズム2100を検知するために照射するものである。本実施例の発光手段100は、上述した「原理」で説明した様に、「上下方向に扇状となる光」を照射させるものであれば、何れのものを使用することができる。
【0035】
受光手段200は、ターゲット2000のプリズム2100で反射された反射光を受光するためのものである。反射光を電気信号に変換することのできる素子であれば、何れの素子を利用することができる。
【0036】
光波距離計300は、ターゲット2000までの距離を測定するための距離測定手段に該当するものである。例えば、本実施例の光波距離計300は、位相差測定方式又はパルス測定方式を利用した距離計等を使用することができる。
【0037】
ここで図14に基づいて、光波距離計300の一例を説明する。
【0038】
光波距離計300は、測距光を出射方向に向けて反射させるためのプリズム2100と、測距光を発光させるための発光部310と、プリズム2100からの反射光を受光するための受光部320と、発光部310からの測距光をプリズム2100に向けて反射させると共に、プリズム2100からの反射光を受光部320に向けるためのミラー330と、測距光をコリメートして反射光を受光部320に合焦させるための対物レンズ340とを備えている。
【0039】
光波距離計300は、位相差測定による距離測定装置であり、発光部310と受光部320とを備えている。そして受光部は、受光部からの光量を捕らえることは容易に行うことができる。
【0040】
鏡筒400は、鉛直方向に回動可能に構成されており、発光手段100と受光手段200と光波距離計300とが取り付けられている。
【0041】
次に図4に基づいて、本第1実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する。
【0042】
本第1実施例の自動測量機1000は、レーザーダイオード110と、レーザーダイオード駆動部111と、受光部200と、光波距離計300と、同期検出回路500と、クロック回路600と、信号処理部700と、制御部800と、回転駆動部900とから構成されている。
【0043】
レーザーダイオード110とレーザーダイオード駆動部111とは、発光手段100を構成するもので、レーザーダイオード駆動部111が、クロック回路600のクロック信号に基づき、レーザーダイオード110を駆動し、レーザー光を発生する様になっている。
【0044】
同期検出回路500は、クロック回路600のクロック信号に基づき、受光部200の受光信号から反射レーザー光の受光信号を検出するための同期検波のための回路である。
【0045】
クロック回路600は、同期検出回路500が同期検波するためのタイミング及びレーザーダイオード駆動部111を駆動するタイミングを決定するクロック信号を形成するためのものである。
【0046】
信号処理部700は、波形整形等の信号処理を行うためのものである。
【0047】
制御手段800は、演算処理手段に該当するもので、CPUを含み、全体の制御を司ると共に、角度の決定等の各種演算等を行うためのものである。
【0048】
信号処理部700からの処理信号に基づいて制御手段800は演算を行い、自動測量機本体1100をプリズム2100に向ける様にフィードバック制御を行う。
【0049】
回転駆動部900は、自動測量機本体1100を水平方向に回転させるための制御を行うためのものである。
【0050】
ここで、図5に基づいて、自動測量機本体1100を水平方向及び鉛直方向に回転させるための機構を説明する。なお、この機構が回動手段に該当するものである。
【0051】
この自動測量機1000は、図5に示す様に、固定台4と、この固定台4に取り付けられた基台5とを備えている。基台5はその平面5aと固定台4の平面4aとのなす角度がレベリングスクリューS、S、Sによって調整できる様になっている。
【0052】
基台5には、鉛直方向に延びた軸受部6を有する軸受部材7が固定され、この軸受部材7には鉛直方向に延びた回転軸8が回転自在に取り付けられている。回転軸8には測量機本体1100が取り付けられていて、回転軸8と共に測量機本体1100が基台5に対して水平方向に回転可能に構成されている。測量機本体1100には、高低角を微調整するための調整ノブと水平角を調整するための調整ノブが設けられている。
【0053】
測量機本体1100は、両方から上方へ膨出した2つの膨出部51、52が形成されており、この膨出部51、52の間の凹部53には鏡筒400が配置されている。この鏡筒400の側板61、62には水平方向に延びた水平軸63、64が設けられており、この水平軸63、64が膨出部61、62の側板65、66に軸受67、68を介して回転可能に保持されていて鏡筒部400が鉛直方向に回転できる様に構成されている。
【0054】
測量機本体1100の回転は、測量機本体1100内に設けたモータ70によって行なうもので、このモータ70は測量機本体1100の側板71に取り付けられている。モータ70の駆動軸72にはギア73が設けられており、ギア73は軸受部6に固定された平歯車74に噛合している。平歯車74は回転軸8と同心状となっている。これにより、モータ70の駆動によって平歯車74の回りをギア73が回転移動していき、測量機本体1100が回転軸8と共に回転することになる。
【0055】
回転軸8の上部には水平角目盛用目盛板75が取り付けられており、その水平角目盛を読む水平角読取エンコーダ76が平歯車74に設けられている。水平角読取エンコーダ76は水平角目盛用目盛板75が微小角回転する毎にパルスを発生させるためのものである。
【0056】
鏡筒部400の回転は、膨出部52に設けたモータ80によって行うもので、このモータ80の駆動軸81にはギア82が設けられており、ギア82は水平軸64に固定した平歯車83に噛合している。これにより、モータ80の駆動によって、平歯車83が回転して水平軸63、64が鏡筒部400と共に回転する。
【0057】
水平軸63には、高低角目盛用目盛板84が取り付けられており、高低角目盛を読む高低角読取用エンコーダ85が膨出部51に設けられている。高低角読取用エンコーダ85は、高低角目盛用目盛板84が微小角回転する毎にパルスを発生させるためのものである。
【0058】
次に本第1実施例の動作を図6に基づいて具体的に説明する。
【0059】
初めに、図7に示す様に、自動測量機1000を三脚上に配置する。
【0060】
まずステップ1(以下S1と略する。)で、電源を投入し、測定を開始する。S2では、レーザーダイオード駆動部111が、クロック回路600のタイミング信号に基づき、レーザーダイオード110を駆動し、シリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出される。
【0061】
そしてS3では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ70を回転させて測量機本体1100を水平方向に回転させる。
【0062】
次にS4では、制御手段800が、ターゲット2000からの反射光が、受光部200で検出されるかを判断する。シリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出されているので、ターゲット2000のプリズム2100と相対する位置になった場合には、プリズム2100に入射した光が反射され、反射光が、受光部200に入射される。
【0063】
受光部200に反射光が入射されると、受光信号は、信号処理部700で波形整形等の信号処理が施された後、制御手段800に入力される。そして制御手段800が、反射光の入力を認識した場合には、S5に進み、S5では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ70の回転を停止させて測量機本体1100の回転を中止させ、水平角を決定する。
【0064】
またS4で、制御手段800が、受光部200に反射光の入射を認識しない場合には、S3に戻り、測量機本体1100の水平方向の回転を継続させる。
【0065】
S5で、測量機本体1100の回転を中止させた後、S6に進む。S6では、制御手段800が光波距離計300を駆動させる。そしてS7では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ80を回転させて鏡筒400を鉛直方向に回転させる。
【0066】
次にS8では、制御手段800が、光波距離計300で反射光検出が行われたか否かを判断する。そしてS8で反射光の検出を認識した場合には、S9に進み、S9では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ80の回転を停止させて鏡筒400の回転を中止させる。
【0067】
そして、図9に示す様に、光波距離計300の反射光量とエンコーダ85に基づく角度位置から重心を演算し、この重心位置から高度角を検出する。
【0068】
なおS8で、光波距離計300の反射光検出が認められない場合には、S7に戻り、鏡筒400の鉛直方向の回転を継続させる。
【0069】
S5で水平角を、S9で鉛直角を決定した後、S10に進み、シリンドリカルレンズ130を切り替えて外し、ポインタービームを出力させる。そしてS11で、光波距離計300による測距を行う。
【0070】
ポインタービームは、ターゲット2000のターゲット板2200の中心に投射され、測量機本体1100がプリズム2100に相対したことが判る。
【0071】
以上の様に構成された本第1実施例は、自動的に自動測量機1000をターゲット2000のプリズム2100に向けるて位置決めすることができる。
【0072】
なお、光波距離計300は、自動測量機1000に初めから装備されていてもよいが、従来の光波距離計300に対して、本第1実施例の構成を付加させるタイプのものであってもよい。
【0073】
また本第1実施例は、本発明の位置検出装置を自動測量機1000に応用したものであるが、自動測量機1000に限ることなく、何れの測量装置に応用することができる。
【0074】
更に、光波距離計300の光ビームは、5分から7分程度の広がりを有するので、更に、光波距離計300の光ビームを利用して、上述した原理により、正確な位置決めを行うこともできる。
【0075】
「第2実施例」
【0076】
本発明の第2実施例を図面に基づいて説明する。
【0077】
図2(a)は、本第2実施例の自動測量機1000を示す斜視図であり、自動測量機1000は、自動測量機本体1100と、発光手段100と、第1の受光部200Aと、第2の受光部200Bと、光波距離計300と、鏡筒400とから構成されている。
【0078】
本第2実施例では、光波距離計300と視準望遠鏡が同軸に構成されている。
【0079】
発光手段100は、図2(b)に示すターゲット2000のプリズム2100に向けて光を照射させるためのものである。本実施例の発光手段100は、上述した「原理」で説明した様に、「上下方向に扇状となる光」を照射させるものであれば、何れのものを使用することができる。
【0080】
受光手段200は、ターゲット2000のプリズム2100で反射された反射光を受光するためのものである。反射光を電気信号に変換することのできる素子であれば、何れの素子を利用することができる。
【0081】
本第2実施例の受光手段200は、図3(a)及び図3(b)に示す様に、発光手段100を挟んで1対配置されている。即ち、受光手段200は、第1の受光部200Aと第2の受光部200Bとから構成されている。
【0082】
ここで、図3(a)に示す様に、自動測量機本体1100が反時計回りに回転した場合のプリズム2100からの受光状態を示し、図3(b)は同様に反時計回りした場合の不要反射面からの受光状態を示している。
【0083】
再帰反射部材であるプリズム2100で反射された反射光は、第2の受光手段200Bより先に第1の受光手段200Aに入射する。
【0084】
図3(b)の様な不要反射面、例えば、相対するミラー等で反射された場合には、先に第2の受光手段200Bに入射する。
【0085】
自動測量機本体1000が時計回りをした場合、プリズム2100で反射された反射光は、先に第2の受光部200Bに入射し、不要反射面で反射された反射光は、先に第1の受光部200Aに入射する。
【0086】
従って反射光が、第1の受光部200A及び第2の受光部200Bのどちらが先に入射したことを認識することにより、不要反射を識別することができる。
【0087】
次に図9に基づいて、本第2実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する。
【0088】
本第2実施例の自動測量機1000は、レーザーダイオード110と、レーザーダイオード駆動部111と、第1の受光部200Aと第2の受光部200Bと、光波距離計300と、同期検出回路500と、クロック回路600と、信号処理部700と、制御部800と、回転駆動部900とから構成されている。
【0089】
レーザーダイオード110とレーザーダイオード駆動部111とは、発光手段100を構成するもので、レーザーダイオード駆動部111が、クロック回路600のクロック信号に基づき、レーザーダイオード110を駆動し、レーザー光を発生する様になっている。
【0090】
同期検出回路500は、クロック回路600のクロック信号に基づき、第1の受光部200Aと第2の受光部200Bの受光信号から反射レーザー光の受光信号を検出するための同期検波のための回路である。
【0091】
クロック回路600は、同期検出回路500が同期検波するためのタイミング及びレーザーダイオード駆動部111を駆動するタイミングを決定するクロック信号を形成するためのものである。
【0092】
信号処理部700は、第1の受光部200Aと第2の受光部200Bの差を取ると共に、波形整形等の信号処理を行うためのものである。
【0093】
制御手段800は、演算処理手段に該当するもので、CPUを含み、全体の制御を司ると共に、角度の決定等の各種演算等を行うためのものである。
【0094】
信号処理部700からの処理信号に基づいて制御手段800は演算を行い、自動測量機本体1100をプリズム2100に向ける様にフィードバック制御を行う。
【0095】
回転駆動部900は、自動測量機本体1100を水平方向に回転させるための制御を行うためのものである。
【0096】
次に本第2実施例の動作を図10に基づいて具体的に説明する。
【0097】
初めに、図7に示す様に、自動測量機1000を三脚上に配置する。
【0098】
まずステップ1(以下S1と略する。)で、電源を投入し、測定を開始する。S2では、レーザーダイオード駆動部111が、クロック回路600のタイミング信号に基づき、レーザーダイオード110を駆動し、シリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出される。
【0099】
そしてS3では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ70を回転させて測量機本体1100を水平方向に回転させる。
【0100】
次にS4では、制御手段800が、ターゲット2000からの反射光が、第1の受光部200Aか又は第2の受光部200Bで検出されるかを判断する。シリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出されているので、ターゲット2000のプリズム2100と相対する位置になるまでフィードバック制御される。
【0101】
第1の受光部200Aか又は第2の受光部200Bに反射光が入射されると、受光信号は、信号処理部700で波形整形等の信号処理が施された後、制御手段800に入力される。そして制御手段800が、反射光の入力をターゲットからの反射光であると認識した場合には、S5に進み、S5では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ70の回転を停止させて測量機本体1100の回転を中止させ、水平角を決定する。なお、不要反射であると判断した場合には、S5に進まず回転を継続する。
【0102】
またS4で、制御手段800が、反射光の入射を認識しない場合には、S3に戻り、測量機本体1100の水平方向の回転を継続させる。
【0103】
S5で、測量機本体1100の回転を中止させた後、S6に進む。S6では、制御手段800が光波距離計300を駆動させる。そしてS7では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ80を回転させて鏡筒400を鉛直方向に回転させる。
【0104】
次にS8では、制御手段800が、光波距離計300で反射光検出が行われたか否かを判断する。そしてS8で反射光の検出を認識した場合には、S9に進み、S9では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ80の回転を停止させて鏡筒400の回転を中止させる。
【0105】
そして、図8に示す様に、光波距離計300の反射光量とエンコーダ85に基づく角度位置から重心を演算し、この重心位置から高度角を検出する。
【0106】
なおS8で、光波距離計300の反射光検出が認められない場合には、S7に戻り、鏡筒400の鉛直方向の回転を継続させる。
【0107】
S5で水平角を、S9で鉛直角を決定した後、S10に進み、シリンドリカルレンズ130を切り替えて外し、ポインタービームを出力させる。そしてS11で、光波距離計300による測距を行う。
【0108】
ポインタービームは、ターゲット2000のターゲット板2200の中心に投射され、測量機本体1100がプリズム2100に相対したことが判る。
【0109】
以上の様に構成された本第2実施例は、自動的に自動測量機1000をターゲット2000のプリズム2100に向けて位置決めすることができる。
【0110】
なお、本第2実施例のその他の構成、作用は、第1実施例と同様であるから説明を省略する。
【0111】
「第3実施例」
【0112】
本発明の第3実施例を説明する。
【0113】
上述の第1実施例又は第2実施例は、「上下方向に扇状となる光」をターゲット2000に向けて照射し、この反射光から水平角を決定し、鉛直角は、光波距離計の光を利用し、光波距離計の反射光の重心位置を利用して鉛直角を求めていた。
【0114】
本第3実施例は、光波距離計の光を利用せず、第1実施例及び第2実施例の水平角を決定する方法を鉛直角に応用したものである。
【0115】
次に図11に基づいて、本第3実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する。
【0116】
本第3実施例は、第1レーザーダイオード110と、第2のレーザーダイオード115と、第1のレーザーダイオード駆動部111と、第2のレーザーダイオード駆動部116と、第1の受光部200Aと第2の受光部200Bと、第3の受光部200Cと第4の受光部200Dと、光波距離計300と、同期検出回路500と、クロック回路600と、信号処理部700と、制御部800と、回転駆動部900とから構成されている。
【0117】
第1レーザーダイオード110は、第1の実施例と同様に、「上下方向に扇状となる光」を照射させる第1の発光手段100の構成の一つであって、第1のシリンドリカルレンズ130により、「上下方向に扇状となる光」を射出する様に構成されている。
【0118】
第2レーザーダイオード115は、「水平方向に扇状となる光」を照射させる第2の発光手段119の構成の一つであって、第2のシリンドリカルレンズ139により、「水平方向に扇状となる光」を射出する様に構成されている。
【0119】
即ち第2の発光手段119は、第1の発光手段100を90度回転させて配置し、「水平方向に扇状となる光」を射出させるものである。
【0120】
第1の受光部200Aと第2の受光部200Bは、第1の実施例と同様に、第1の発光手段100の第1レーザーダイオード110から射出された「上下方向に扇状となる光」の反射光を受光するためのものである。
【0121】
第3の受光部200Cと第4の受光部200Dは、第2の発光手段109の第2レーザーダイオード115から射出された「水平方向に扇状となる光」の反射光を受光するためのものである。
【0122】
第1のレーザーダイオード駆動部111は、第1実施例と同様に、第1レーザーダイオード110を駆動して、「上下方向に扇状となる光」を射出させるためのものである。
【0123】
第2のレーザーダイオード駆動部116は、第2レーザーダイオード115を駆動して、「水平方向に扇状となる光」を射出させるためのものである。
【0124】
以上の様に構成された第3実施例の自動測量機1000の動作を図12に基づいて具体的に説明する。
【0125】
まずステップ1(以下S1と略する。)で、電源を投入し、測定を開始する。S2では、第1のレーザーダイオード駆動部111が、クロック回路600のタイミング信号に基づき、第1レーザーダイオード110を駆動し、第1のシリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出される。
【0126】
そしてS3では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ70を回転させて測量機本体1100を水平方向に回転させる。
【0127】
次にS4では、制御手段800が、ターゲット2000からの反射光が、第1の受光部200Aか又は第2の受光部200Bで検出されるかを判断する。第1のシリンドリカルレンズ130から上下方向に扇状となる光(上下ファンビーム)が射出されているので、ターゲット2000のプリズム2100と相対する位置になるまでフィードバック制御される。
【0128】
第1の受光部200Aか又は第2の受光部200Bに反射光が入射されると、受光信号は、信号処理部700で波形整形等の信号処理が施された後、制御手段800に入力される。そして制御手段800が、反射光の入力をターゲット2000からの反射光であると認識した場合には、S5に進み、S5では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ70の回転を停止させて測量機本体1100の回転を中止させ、水平角を決定する。なお、第2の受光部200Bに反射光が入射された場合には、不要反射であると判断し、S5に進まず回転を継続する。
【0129】
またS4で、制御手段800が、反射光の入射を認識しない場合には、S3に戻り、測量機本体1100の水平方向の回転を継続させる。
【0130】
S5で、測量機本体1100の回転を中止させた後、S6に進む。S6では、第2のレーザーダイオード駆動部116が、クロック回路600のタイミング信号に基づき、第2レーザーダイオード115を駆動し、第2のシリンドリカルレンズ139から水平方向に扇状となる光(水平ファンビーム)が射出される。
【0131】
そしてS7では、制御手段800が回転駆動部900を制御駆動し、モータ80を回転させて鏡筒400を鉛直方向に回転させる。
【0132】
次にS8では、制御手段800が、ターゲット2000からの反射光が、第3の受光部200Cか又は第4の受光部200Dで検出されるかを判断する。第2のシリンドリカルレンズ139から水平方向に扇状となる光(水平ファンビーム)が射出されているので、ターゲット2000のプリズム2100と相対する位置になるまでフィードバック制御する。
【0133】
第3の受光部200Cか又は第4の受光部200Dに反射光が入射されると、受光信号は、信号処理部700で波形整形等の信号処理が施された後、制御手段800に入力される。そして制御手段800が、反射光の入力をターゲット2000からの反射光であると認識した場合には、S9に進み、S9では、制御手段800が回転駆動部900を制御し、モータ80の回転を停止させて鏡筒400の鉛直方向の回転を中止させ、高度角を決定する。不要反射であると判断した場合には、S9に進まず回転を継続する。
【0134】
またS8で、制御手段800が、反射光の入射を認識しない場合には、S7に戻り、鏡筒400の鉛直方向の回転を継続させる。
【0135】
S5で水平角を、S9で鉛直角を決定した後、S10に進み、シリンドリカルレンズ130を切り替えて外し、ポインタービームを出力させる。そしてS11で、光波距離計300による測距を行う。
【0136】
ポインタービームは、ターゲット2000のターゲット板2200の中心に投射され、測量機本体1100がプリズム2100に相対したことが判る。
【0137】
以上の様に構成された本第3実施例は、自動的に自動測量機1000をターゲット2000のプリズム2100に向けて位置決めすることができる。
【0138】
なお本第3実施例のその他の構成、作用等は、第1実施例及び第2実施例と同様であるから、説明を省略する。
【0139】
また、第2レーザーダイオード115を使用する代わりに、シリンドリカルレンズ130を機械的に90度回転する、又は、シリンドリカルレンズ130を切り換えて、水平方向に扇状となる光を構成しても同様である。
【0140】
【効果】
以上の様に構成された本発明は、音響光学素子に比べ、扇状となる光によってターゲットを走査するため、広範囲の走査を迅速に行うことができると共に、発熱量が少なく省電力化を図ることができる上、高価な音響光学素子を使用しないので、コストダウンが可能となるという効果がある。
【0141】
更に音響光学素子を使用しないので、偏向角に限界がなく、容易に走査範囲を広げることができるという卓越した効果がある。
【0142】
そして、光波距離計を有する測量機と組み合わせた場合には、よりコストダウンをした安価で精度の高い自動測量機が提供できる。
【0143】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例の自動測量機1000とターゲット2000を示す斜視図である。
【図2】本発明の第2実施例の自動測量機1000とターゲット2000を示す斜視図である。
【図3(a)】受光手段200を説明する図である。
【図3(b)】受光手段200を説明する図である。
【図4】本第1実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する図である。
【図5】本第1実施例の回動手段を説明する図である。
【図6】本第1実施例の動作を説明する図である。
【図7】自動測量機1000とターゲット2000との位置関係を説明する図である。
【図8】光波距離計300の反射光量の重心を演算し、この重心位置から高度角を検出することを説明する図である。
【図9】本第2実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する図である。
【図10】本第2実施例の動作を説明する図である。
【図11】本第3実施例の自動測量機1000の電気的構成を説明する図である。
【図12】本第3実施例の動作を説明する図である。
【図13(a)】本発明の原理を説明する図である。
【図13(b)】本発明の原理を説明する図である。
【図14】光波距離計を説明する図である。
【図15】従来技術を説明する図である。
【符号の説明】
1000 第1実施例の自動測量機
1100 自動測量機本体
1000 第2実施例の自動測量機
1000 第3実施例の自動測量機
2000 ターゲット
2100 プリズム
2200 ターゲット板
100 発光手段
110 レーザーダイオード
115 第2レーザーダイオード
111 レーザーダイオード駆動部
116 第2のレーザーダイオード駆動部
119 第2の発光手段
120 コリメートレンズ
130 シリンドリカルレンズ
139 第2のシリンドリカルレンズ
200 受光手段
200A 第1の受光部
200B 第2の受光部
200C 第3の受光部
200D 第4の受光部
300 光波距離計
400 鏡筒
500 同期検出回路
600 クロック回路
700 信号処理部
800 制御部
900 回転駆動部
Claims (3)
- 装置本体を水平回転させ鏡筒を垂直回転させてターゲットの位置を検出するための位置検出測量機において、前記鏡筒は、光波距離計と、前記ターゲットに向けて上下方向に扇状光を照射するための発光部と、前記ターゲットからの反射光を検出する受光部とを備え、この受光部が前記ターゲットからの反射光を検出することにより、前記装置本体の水平回転を前記ターゲットに向けて停止させ、前記光波距離計が前記ターゲットからの反射光を検出することにより、前記鏡筒の垂直回転を前記ターゲットに向けて停止させるための演算処理手段とからなる位置検出測量機。
- 受光部は、発光部を挟んで水平方向に一対の受光部が配置され、装置本体の水平回転方向と一対の受光部のどちらが先に受光されたかによって、ターゲットであるか、不要反射体であるかを識別する請求項1記載の位置検出測量機。
- 発光部の扇状光は、ポインタービームに切り替え可能であって、水平回転と垂直回転を、ターゲットに向けて停止させた後、扇状光からポインタービームに切り替えて、前記ターゲットに向けてポインタービームを投射する請求項1記載の位置検出測量機。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP03321797A JP3731021B2 (ja) | 1997-01-31 | 1997-01-31 | 位置検出測量機 |
| EP98101537A EP0856718B1 (en) | 1997-01-31 | 1998-01-29 | Automatic surveying apparatus |
| DE69837456T DE69837456T2 (de) | 1997-01-31 | 1998-01-29 | Automatishe Vermessungsvorrichtung |
| US09/015,449 US6046800A (en) | 1997-01-31 | 1998-01-29 | Position detection surveying device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP03321797A JP3731021B2 (ja) | 1997-01-31 | 1997-01-31 | 位置検出測量機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10221073A JPH10221073A (ja) | 1998-08-21 |
| JP3731021B2 true JP3731021B2 (ja) | 2006-01-05 |
Family
ID=12380290
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP03321797A Expired - Fee Related JP3731021B2 (ja) | 1997-01-31 | 1997-01-31 | 位置検出測量機 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6046800A (ja) |
| EP (1) | EP0856718B1 (ja) |
| JP (1) | JP3731021B2 (ja) |
| DE (1) | DE69837456T2 (ja) |
Families Citing this family (70)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3965593B2 (ja) * | 1998-07-08 | 2007-08-29 | 株式会社トプコン | 測量機の求心位置測定装置及び測量機 |
| JP2000097703A (ja) * | 1998-09-21 | 2000-04-07 | Topcon Corp | 3次元測定方法と、これを利用した測量機 |
| EP1024344B1 (de) * | 1999-01-27 | 2002-11-13 | Leica Geosystems AG | Vermessungsgerät mit einer Höhenmesseinrichtung |
| JP4210792B2 (ja) * | 1999-06-15 | 2009-01-21 | 株式会社トプコン | 位置検出装置 |
| US8412377B2 (en) | 2000-01-24 | 2013-04-02 | Irobot Corporation | Obstacle following sensor scheme for a mobile robot |
| US8788092B2 (en) | 2000-01-24 | 2014-07-22 | Irobot Corporation | Obstacle following sensor scheme for a mobile robot |
| US6956348B2 (en) | 2004-01-28 | 2005-10-18 | Irobot Corporation | Debris sensor for cleaning apparatus |
| DE10066379B4 (de) * | 2000-05-20 | 2008-07-10 | Trimble Jena Gmbh | Verfahren und Einrichtung zur Realisierung eines Informations- und Datenflusses für geodätische Geräte |
| US6656700B2 (en) * | 2000-05-26 | 2003-12-02 | Amersham Plc | Isoforms of human pregnancy-associated protein-E |
| US6686188B2 (en) * | 2000-05-26 | 2004-02-03 | Amersham Plc | Polynucleotide encoding a human myosin-like polypeptide expressed predominantly in heart and muscle |
| US6381006B1 (en) * | 2000-07-12 | 2002-04-30 | Spectra Precision Ab | Spatial positioning |
| US20020123474A1 (en) * | 2000-10-04 | 2002-09-05 | Shannon Mark E. | Human GTP-Rho binding protein2 |
| US6690134B1 (en) | 2001-01-24 | 2004-02-10 | Irobot Corporation | Method and system for robot localization and confinement |
| US7571511B2 (en) | 2002-01-03 | 2009-08-11 | Irobot Corporation | Autonomous floor-cleaning robot |
| US8396592B2 (en) | 2001-06-12 | 2013-03-12 | Irobot Corporation | Method and system for multi-mode coverage for an autonomous robot |
| US7663333B2 (en) | 2001-06-12 | 2010-02-16 | Irobot Corporation | Method and system for multi-mode coverage for an autonomous robot |
| US20040078837A1 (en) * | 2001-08-02 | 2004-04-22 | Shannon Mark E. | Four human zinc-finger-containing proteins: MDZ3, MDZ4, MDZ7 and MDZ12 |
| EP1329690A1 (de) | 2002-01-22 | 2003-07-23 | Leica Geosystems AG | Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Auffinden von Zielmarken |
| US9128486B2 (en) | 2002-01-24 | 2015-09-08 | Irobot Corporation | Navigational control system for a robotic device |
| US8386081B2 (en) | 2002-09-13 | 2013-02-26 | Irobot Corporation | Navigational control system for a robotic device |
| US8428778B2 (en) | 2002-09-13 | 2013-04-23 | Irobot Corporation | Navigational control system for a robotic device |
| JP2004144629A (ja) * | 2002-10-25 | 2004-05-20 | Pentax Precision Co Ltd | 測量機 |
| US7332890B2 (en) | 2004-01-21 | 2008-02-19 | Irobot Corporation | Autonomous robot auto-docking and energy management systems and methods |
| FR2869112B1 (fr) * | 2004-04-20 | 2007-03-09 | Airbus France Sas | Systeme de mesure a trois dimensions |
| KR101142564B1 (ko) | 2004-06-24 | 2012-05-24 | 아이로보트 코퍼레이션 | 자동 로봇 장치용의 원격 제어 스케줄러 및 방법 |
| US7706917B1 (en) | 2004-07-07 | 2010-04-27 | Irobot Corporation | Celestial navigation system for an autonomous robot |
| US8972052B2 (en) | 2004-07-07 | 2015-03-03 | Irobot Corporation | Celestial navigation system for an autonomous vehicle |
| EP1619468A1 (de) * | 2004-07-22 | 2006-01-25 | Leica Geosystems AG | Geodätisches Messgerät mit Piezo-Antrieb |
| JP4446850B2 (ja) | 2004-09-27 | 2010-04-07 | 株式会社トプコン | 測量装置用ターゲット |
| US7620476B2 (en) | 2005-02-18 | 2009-11-17 | Irobot Corporation | Autonomous surface cleaning robot for dry cleaning |
| DE602006014364D1 (de) | 2005-02-18 | 2010-07-01 | Irobot Corp | Autonomer oberflächenreinigungsroboter für nass- und trockenreinigung |
| US8392021B2 (en) | 2005-02-18 | 2013-03-05 | Irobot Corporation | Autonomous surface cleaning robot for wet cleaning |
| US8930023B2 (en) | 2009-11-06 | 2015-01-06 | Irobot Corporation | Localization by learning of wave-signal distributions |
| KR101074937B1 (ko) | 2005-12-02 | 2011-10-19 | 아이로보트 코퍼레이션 | 모듈형 로봇 |
| ES2706729T3 (es) | 2005-12-02 | 2019-04-01 | Irobot Corp | Sistema de robot |
| ES2378138T3 (es) | 2005-12-02 | 2012-04-09 | Irobot Corporation | Movilidad de robot de cubrimiento |
| EP2466411B1 (en) | 2005-12-02 | 2018-10-17 | iRobot Corporation | Robot system |
| EP2816434A3 (en) | 2005-12-02 | 2015-01-28 | iRobot Corporation | Autonomous coverage robot |
| EP3031377B1 (en) | 2006-05-19 | 2018-08-01 | iRobot Corporation | Removing debris from cleaning robots |
| US8417383B2 (en) | 2006-05-31 | 2013-04-09 | Irobot Corporation | Detecting robot stasis |
| US8060344B2 (en) * | 2006-06-28 | 2011-11-15 | Sam Stathis | Method and system for automatically performing a study of a multidimensional space |
| EP2574265B1 (en) | 2007-05-09 | 2015-10-14 | iRobot Corporation | Compact autonomous coverage robot |
| JP5166087B2 (ja) * | 2008-03-21 | 2013-03-21 | 株式会社トプコン | 測量装置及び測量システム |
| JP5285974B2 (ja) * | 2008-06-23 | 2013-09-11 | 株式会社ミツトヨ | 測定装置 |
| CN104127156B (zh) | 2010-02-16 | 2017-01-11 | 艾罗伯特公司 | 真空吸尘器毛刷 |
| US9222771B2 (en) | 2011-10-17 | 2015-12-29 | Kla-Tencor Corp. | Acquisition of information for a construction site |
| US8836922B1 (en) * | 2013-08-20 | 2014-09-16 | Google Inc. | Devices and methods for a rotating LIDAR platform with a shared transmit/receive path |
| JP6209021B2 (ja) * | 2013-08-23 | 2017-10-04 | 株式会社トプコン | 測量機 |
| JP6227324B2 (ja) * | 2013-08-23 | 2017-11-08 | 株式会社トプコン | 測量機及び測量作業システム |
| US10184794B2 (en) | 2015-07-01 | 2019-01-22 | Makita Corporation | Laser marker |
| US9720415B2 (en) | 2015-11-04 | 2017-08-01 | Zoox, Inc. | Sensor-based object-detection optimization for autonomous vehicles |
| JP6697888B2 (ja) * | 2016-01-18 | 2020-05-27 | 株式会社トプコン | 測量装置 |
| EP3199913B1 (de) | 2016-01-28 | 2019-04-03 | Leica Geosystems AG | Vorrichtung zum automatischen auffinden eines beweglichen geodätischen zielobjekts |
| US10830878B2 (en) | 2016-12-30 | 2020-11-10 | Panosense Inc. | LIDAR system |
| US10122416B2 (en) | 2016-12-30 | 2018-11-06 | Panosense Inc. | Interface for transferring power and data between a non-rotating body and a rotating body |
| US10359507B2 (en) | 2016-12-30 | 2019-07-23 | Panosense Inc. | Lidar sensor assembly calibration based on reference surface |
| US10742088B2 (en) | 2016-12-30 | 2020-08-11 | Panosense Inc. | Support assembly for rotating body |
| US10295660B1 (en) | 2016-12-30 | 2019-05-21 | Panosense Inc. | Aligning optical components in LIDAR systems |
| US10048358B2 (en) | 2016-12-30 | 2018-08-14 | Panosense Inc. | Laser power calibration and correction |
| US10591740B2 (en) | 2016-12-30 | 2020-03-17 | Panosense Inc. | Lens assembly for a LIDAR system |
| US10109183B1 (en) | 2016-12-30 | 2018-10-23 | Panosense Inc. | Interface for transferring data between a non-rotating body and a rotating body |
| US10338594B2 (en) * | 2017-03-13 | 2019-07-02 | Nio Usa, Inc. | Navigation of autonomous vehicles to enhance safety under one or more fault conditions |
| US10556585B1 (en) | 2017-04-13 | 2020-02-11 | Panosense Inc. | Surface normal determination for LIDAR range samples by detecting probe pulse stretching |
| US10423162B2 (en) | 2017-05-08 | 2019-09-24 | Nio Usa, Inc. | Autonomous vehicle logic to identify permissioned parking relative to multiple classes of restricted parking |
| US10369974B2 (en) | 2017-07-14 | 2019-08-06 | Nio Usa, Inc. | Control and coordination of driverless fuel replenishment for autonomous vehicles |
| US10710633B2 (en) | 2017-07-14 | 2020-07-14 | Nio Usa, Inc. | Control of complex parking maneuvers and autonomous fuel replenishment of driverless vehicles |
| US11022971B2 (en) | 2018-01-16 | 2021-06-01 | Nio Usa, Inc. | Event data recordation to identify and resolve anomalies associated with control of driverless vehicles |
| CN108387221A (zh) * | 2018-01-17 | 2018-08-10 | 西安理工大学 | 一种隧道开挖快速放样装置和放样方法 |
| CN113646608A (zh) | 2019-04-10 | 2021-11-12 | 米沃奇电动工具公司 | 光学激光靶 |
| USD974205S1 (en) | 2020-09-17 | 2023-01-03 | Milwaukee Electric Tool Corporation | Laser target |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3897151A (en) * | 1973-01-29 | 1975-07-29 | James F Lecroy | Laser miss distance indicator |
| US4401886A (en) * | 1981-03-23 | 1983-08-30 | The Boeing Company | Electromagnetic beam acquisition and tracking system |
| US4721385A (en) * | 1985-02-11 | 1988-01-26 | Raytheon Company | FM-CW laser radar system |
| FR2677834B1 (fr) * | 1986-09-16 | 1993-12-31 | Thomson Csf | Systeme d'imagerie laser a barrette detectrice. |
| JP2521754B2 (ja) * | 1987-05-13 | 1996-08-07 | 株式会社トプコン | 測量装置 |
| DE3808972A1 (de) * | 1988-03-17 | 1989-10-05 | Hipp Johann F | Vorrichtung zur kontinuierlichen verfolgung und positionsmessung eines objektes |
| JPH0778533B2 (ja) * | 1988-05-02 | 1995-08-23 | 株式会社日立製作所 | レーザレーダ |
| US5098185A (en) * | 1988-06-15 | 1992-03-24 | Japan Industrial Land Development Co., Ltd. | Automatic tracking type measuring apparatus |
| CH676042A5 (en) * | 1988-07-22 | 1990-11-30 | Wild Leitz Ag | Surveying unit with theodolite and range finder - determines coordinates of target point includes light pulse transmitter and receiver |
| EP0464263A3 (en) * | 1990-06-27 | 1992-06-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Device for obstacle detection for pilots of low flying aircrafts |
-
1997
- 1997-01-31 JP JP03321797A patent/JP3731021B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-01-29 EP EP98101537A patent/EP0856718B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-01-29 US US09/015,449 patent/US6046800A/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-01-29 DE DE69837456T patent/DE69837456T2/de not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH10221073A (ja) | 1998-08-21 |
| DE69837456T2 (de) | 2007-12-13 |
| DE69837456D1 (de) | 2007-05-16 |
| US6046800A (en) | 2000-04-04 |
| EP0856718A2 (en) | 1998-08-05 |
| EP0856718B1 (en) | 2007-04-04 |
| EP0856718A3 (en) | 2000-04-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3731021B2 (ja) | 位置検出測量機 | |
| JP4088906B2 (ja) | 測量機の受光装置 | |
| EP0374265B1 (en) | Automatic tracking type surveying apparatus | |
| WO1997016703A1 (fr) | Systeme laser rotatif | |
| JP5732956B2 (ja) | 距離測定装置 | |
| JP2000193454A (ja) | 回転レ―ザ装置 | |
| JP3288454B2 (ja) | 回転レーザ装置 | |
| JP3937268B2 (ja) | レーザー装置 | |
| JP3351374B2 (ja) | レーザ式測距装置 | |
| JP2696240B2 (ja) | 測量装置 | |
| US20190331911A1 (en) | Mirror assemblies for imaging devices | |
| JPH11145536A (ja) | レーザー装置 | |
| JPH0921872A (ja) | 走査型距離測定装置 | |
| JPH11166832A (ja) | レーザ測量システム | |
| JPH11230747A (ja) | レーザ照射装置 | |
| JP3978737B2 (ja) | レーザーレベル装置 | |
| JP4074967B2 (ja) | レーザー照射装置 | |
| JP3418903B2 (ja) | 光走査装置 | |
| JP3330917B2 (ja) | 回転レーザ装置 | |
| JPS581120A (ja) | テレセントリツク光線を発生する装置および物体の寸法または位置を測定する方法 | |
| JP5197527B2 (ja) | レーザ測距装置 | |
| JP2003207580A (ja) | レーザ式積雪深計 | |
| JPH07117414B2 (ja) | 自動視準式光波距離計 | |
| KR20070015267A (ko) | 변위 측정 장치 | |
| JP2840951B2 (ja) | 自動視準装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040126 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040126 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20050421 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050531 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050728 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050823 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050914 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091021 Year of fee payment: 4 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101021 Year of fee payment: 5 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111021 Year of fee payment: 6 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121021 Year of fee payment: 7 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121021 Year of fee payment: 7 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131021 Year of fee payment: 8 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |