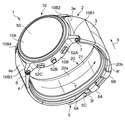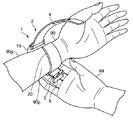JP6734773B2 - 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム - Google Patents
血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP6734773B2 JP6734773B2 JP2016256035A JP2016256035A JP6734773B2 JP 6734773 B2 JP6734773 B2 JP 6734773B2 JP 2016256035 A JP2016256035 A JP 2016256035A JP 2016256035 A JP2016256035 A JP 2016256035A JP 6734773 B2 JP6734773 B2 JP 6734773B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- blood pressure
- risk
- related information
- diastolic
- systolic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/74—Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
- A61B5/742—Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means using visual displays
- A61B5/7425—Displaying combinations of multiple images regardless of image source, e.g. displaying a reference anatomical image with a live image
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
- A61B5/6802—Sensor mounted on worn items
- A61B5/681—Wristwatch-type devices
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/72—Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
- A61B5/7271—Specific aspects of physiological measurement analysis
- A61B5/7275—Determining trends in physiological measurement data; Predicting development of a medical condition based on physiological measurements, e.g. determining a risk factor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/02233—Occluders specially adapted therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/74—Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
- A61B5/746—Alarms related to a physiological condition, e.g. details of setting alarm thresholds or avoiding false alarms
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16H—HEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
- G16H50/00—ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics
- G16H50/30—ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics for calculating health indices; for individual health risk assessment
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Public Health (AREA)
- Pathology (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Physiology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Psychiatry (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Description
被験者の血圧に関連する情報を表示画面に表示する血圧関連情報表示装置であって、
上記被験者について、収縮期血圧と拡張期血圧とを含む血圧データを取得するデータ取得部と、
予め定められた血圧基準に基づいて、上記取得された収縮期血圧に応じたリスクを表す収縮期リスク値と、上記取得された拡張期血圧に応じたリスクを表す拡張期リスク値とを求めるリスク値算出部と、
上記表示画面内に定められた、1次元のリスク座標をなす湾曲した又はストレートの細長い表示領域に、上記収縮期リスク値から上記拡張期リスク値までのリスク範囲を表示する処理を行う表示処理部と
を備えたことを特徴とする。
上記表示領域は上記血圧基準に応じて複数のリスク段階に区分され、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲を、上記リスク段階に応じて色分けして表示することを特徴とする。
上記表示領域は上記血圧基準に応じて3つ以上のリスク段階に区分され、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲が3つ以上のリスク段階にまたがるとき、上記リスク範囲のうち中間のリスク段階に相当する中間範囲について、上記リスク範囲のうち最も高いリスク段階に応じた色と同じ色を付することを特徴とする。
上記表示領域は上記表示画面の周縁部に沿った円弧状領域であり、
上記表示画面のうち上記円弧状領域で囲まれた内部領域に、上記取得された収縮期血圧のデジタル表示、上記取得された拡張期血圧のデジタル表示がなされることを特徴とする。
被験者の血圧に関連する情報を表示画面に表示する血圧関連情報表示方法であって、
上記被験者について、収縮期血圧と拡張期血圧とを含む血圧データを取得し、
予め定められた血圧基準に基づいて、上記取得された収縮期血圧に応じたリスクを表す収縮期リスク値と、上記取得された拡張期血圧に応じたリスクを表す拡張期リスク値とを求め、
上記表示画面内に定められた、1次元のリスク座標をなす湾曲した又はストレートの細長い表示領域に、上記収縮期リスク値から上記拡張期リスク値までのリスク範囲を表示する処理を行うことを特徴とする。
図1は、この発明の血圧関連情報表示装置が適用された一実施形態の血圧計(全体を符号1で示す。)の外観を、ベルト2が締結された状態で斜めから見たところ示している。また、図2は、血圧計1の外観を、ベルト2が開放された状態で斜めから見たところ示している。
図4は、ユーザが被験者となって血圧計1によって血圧測定を行う際の動作フローを示している。
図11は、表示器50の表示画面500の構成を例示している。この例では、表示画面500は円状の輪郭を有している。表示画面500の内部領域500a(環状の周縁部500pを除く)には、上段から下段へ向かって順に、現在の月日時(この例では、1月6日、午前8時38分を表す「JAN6 8:38AM」)を表示する現在日時表示領域501と、収縮期血圧(最高血圧;SYS)をmmHg単位でデジタル表示する収縮期血圧表示領域502と、拡張期血圧(最低血圧)をmmHg単位でデジタル表示する拡張期血圧表示領域503と、脈拍(PULSE)を毎分の回数(/min)単位でデジタル表示する脈拍表示領域504と、表示画面500の標題(この例では、「blood pressure」)を表す標題表示領域505とが設けられている。収縮期血圧表示領域502の左半分、拡張期血圧表示領域503の左半分、脈拍表示領域504の左半分には、それぞれ表示内容の意味を示す文字列「SYS mmHg」、「DIA mmHg」、「PULSE /min」が表示されている。この例では、収縮期血圧表示領域502の右半分、拡張期血圧表示領域503の右半分、脈拍表示領域504の右半分には、それぞれ「110」、「78」、「70」というデジタル値が表示されている。内部領域500aの地色BKは、この例では白色または黒色になっている。
図8は、一実施形態の血圧関連情報表示方法として、表示器50の表示画面500に測定結果を表示する処理のフローを示している。
上述の図11〜図16の例では、それぞれリスク範囲X1〜X6を連続した帯状の領域として表示したが、これに限られるものではない。例えば、図17に示すように、リスク範囲X7を、収縮期リスク値を表すマークX7jと、拡張期リスク値を表すマークX7iとの、互いに離間した2つのマークで表示してもよい。詳しくは、この例では、図12の例と同様に、図8のステップS31で、取得された収縮期血圧SYSが121mmHgであり、また、取得された拡張期血圧DIAが78mmHgであったとする。この場合、図8のステップS32では、収縮期リスク値はRSYS7=2.0となり、また、拡張期リスク値はRDIA7=1.8となる。つまり、RDIA7<RSYS7になっている。このとき、図8のステップS33では、図16中に示すように、収縮期リスク値RSYS7から拡張期リスク値RDIA7までのリスク範囲X7を示すために、円弧状領域510の内周側に、収縮期リスク値を表す▽印のマークX7jと、拡張期リスク値を表す○印のマークX7iとが表示される。したがって、ユーザは、円弧状領域510におけるリスク範囲X7を直感的に認識できる。また、この例では、収縮期リスク値RSYS7は第2のリスク段階512に属し、また、拡張期リスク値RDIA7は第1のリスク段階511に属する。それに応じて、収縮期リスク値を表す▽印のマークX7jには黄色Yが付され、また、拡張期リスク値を表す○印のマークX7iには緑色Gが付されている。したがって、ユーザは、血圧のリスク段階を直感的に認識できる。
上述の図11〜図17の例では、表示画面500は円状で、環状の周縁部500pに沿った円弧状領域510にリスク範囲X1〜X7を表示したが、これに限られるものではない。例えば、図18に示すように、表示画面600は矩形状で、その1辺(この例では、右辺)の縁部600pに沿って、1次元のリスク座標をなすストレートの細長い表示領域として、コラム領域610を設けてもよい。この例では、コラム領域610の左側には、表示画面600の大部分を占めて、収縮期血圧表示領域602と、拡張期血圧表示領域603と、脈拍表示領域604とが設けられている。これらの収縮期血圧表示領域602、拡張期血圧表示領域603、脈拍表示領域604は、それぞれ図11〜図17中の収縮期血圧表示領域502、拡張期血圧表示領域503、脈拍表示領域504に相当する。
2 ベルト
3 第1ベルト部
4 第2ベルト部
10 本体
20 カフ構造体
21 センシングカフ
22 背板
23 押圧カフ
24 カーラ
30 ポンプ
31 第1圧力センサ
32 第2圧力センサ
33 開閉弁
50 表示器
500,600 表示画面
502,602 収縮期血圧表示領域
503,603 拡張期血圧表示領域
504,604 脈拍表示領域
510 円弧状領域
610 コラム領域
RDIA1,RDIA2,…,RDIA8 拡張期リスク値
RSYS1,RSYS2,…,RSYS8 収縮期リスク値
X1,X2,…,X8 リスク範囲
Claims (11)
- 被験者の血圧に関連する情報を表示画面に表示する血圧関連情報表示装置であって、
上記被験者について、収縮期血圧と拡張期血圧とを含む血圧データを取得するデータ取得部と、
予め定められた血圧基準に基づいて、上記取得された収縮期血圧に応じたリスクを表す収縮期リスク値と、上記取得された拡張期血圧に応じたリスクを表す拡張期リスク値とを求めるリスク値算出部と、
上記表示画面内に定められた、1次元のリスク座標をなす湾曲した又はストレートの細長い表示領域に、上記収縮期リスク値から上記拡張期リスク値までのリスク範囲を表示する処理を行う表示処理部と
を備えたことを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項1に記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲を、連続した帯状の領域として表示することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項2に記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示領域は上記血圧基準に応じて複数のリスク段階に区分され、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲を、上記リスク段階に応じて色分けして表示することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項3に記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示領域は上記血圧基準に応じて3つ以上のリスク段階に区分され、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲が3つ以上のリスク段階にまたがるとき、上記リスク範囲のうち中間のリスク段階に相当する中間範囲について、上記リスク範囲のうち最も高いリスク段階に応じた色と同じ色を付することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項1から4までのいずれか一つに記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示処理部は、上記表示領域における上記リスク範囲を、上記表示領域における上記リスク範囲以外の範囲に比して強調表示することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項1から5までのいずれか一つに記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示処理部は、上記表示画面内に、上記取得された収縮期血圧と上記取得された拡張期血圧をそれぞれデジタル表示することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項6に記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示領域は上記表示画面の周縁部に沿った円弧状領域であり、
上記表示画面のうち上記円弧状領域で囲まれた内部領域に、上記取得された収縮期血圧のデジタル表示、上記取得された拡張期血圧のデジタル表示がなされることを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項6または7に記載の血圧関連情報表示装置において、
上記表示処理部は、上記取得された収縮期血圧のデジタル表示、上記取得された拡張期血圧のデジタル表示に、それぞれ上記収縮期リスク値、上記拡張期リスク値が属するリスク段階に応じた色を付することを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 請求項1から8までのいずれか一つに記載の血圧関連情報表示装置において、
上記データ取得部、上記リスク値算出部、および、上記表示処理部は、上記表示画面を有する本体に一体に搭載されていることを特徴とする血圧関連情報表示装置。 - 被験者の血圧に関連する情報を表示画面に表示する血圧関連情報表示方法であって、
上記被験者について、収縮期血圧と拡張期血圧とを含む血圧データを取得し、
予め定められた血圧基準に基づいて、上記取得された収縮期血圧に応じたリスクを表す収縮期リスク値と、上記取得された拡張期血圧に応じたリスクを表す拡張期リスク値とを求め、
上記表示画面内に定められた、1次元のリスク座標をなす湾曲した又はストレートの細長い表示領域に、上記収縮期リスク値から上記拡張期リスク値までのリスク範囲を表示する処理を行うことを特徴とする血圧関連情報表示方法。 - 請求項10に記載の血圧関連情報表示方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016256035A JP6734773B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム |
| DE112017006626.3T DE112017006626T5 (de) | 2016-12-28 | 2017-11-27 | Einrichtung für das anzeigen blutdruckbezogener information, verfahren für das anzeigen blutdruckbezogener information und programm |
| CN201780080642.9A CN110113993B (zh) | 2016-12-28 | 2017-11-27 | 血压关联信息显示装置、血压关联信息显示方法以及程序 |
| PCT/JP2017/042371 WO2018123386A1 (ja) | 2016-12-28 | 2017-11-27 | 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム |
| US16/454,745 US11647965B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-06-27 | Blood-pressure-related information display device, blood-pressure-related information display method, and non-transitory computer readable medium |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016256035A JP6734773B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2018102873A JP2018102873A (ja) | 2018-07-05 |
| JP2018102873A5 JP2018102873A5 (ja) | 2020-01-16 |
| JP6734773B2 true JP6734773B2 (ja) | 2020-08-05 |
Family
ID=62708161
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2016256035A Active JP6734773B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11647965B2 (ja) |
| JP (1) | JP6734773B2 (ja) |
| CN (1) | CN110113993B (ja) |
| DE (1) | DE112017006626T5 (ja) |
| WO (1) | WO2018123386A1 (ja) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102407094B1 (ko) * | 2017-07-25 | 2022-06-08 | 삼성전자주식회사 | 생체정보 측정 장치 및 방법 |
| US10966664B2 (en) * | 2018-07-10 | 2021-04-06 | Kayden Beibei Fu | Dynamically calibrated blood pressure reference value electronic sphygmomanometer |
| JP7202886B2 (ja) * | 2018-12-27 | 2023-01-12 | オムロンヘルスケア株式会社 | 血圧測定装置 |
| CN115137327A (zh) * | 2021-03-31 | 2022-10-04 | 华为技术有限公司 | 一种血压测量方法及装置 |
| WO2023073827A1 (ja) * | 2021-10-27 | 2023-05-04 | オムロンヘルスケア株式会社 | 血圧関連情報表示装置 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62197304U (ja) * | 1987-06-11 | 1987-12-15 | ||
| JPS6419406U (ja) | 1987-07-21 | 1989-01-31 | ||
| JP2006122144A (ja) * | 2004-10-26 | 2006-05-18 | Matsushita Electric Works Ltd | 血圧測定装置 |
| CN101317755A (zh) * | 2007-06-08 | 2008-12-10 | 曹德森 | 柯氏音听诊法血压测量装置及其数据处理方法 |
| JP2009219829A (ja) * | 2008-03-19 | 2009-10-01 | Terumo Corp | バイタルデータの表示装置及び制御方法 |
| CN101554322B (zh) * | 2008-04-09 | 2012-07-04 | 陈敦金 | 产科危重症患者病情评估系统 |
| JP2010119446A (ja) * | 2008-11-17 | 2010-06-03 | Omron Healthcare Co Ltd | 血圧測定装置 |
| US9778079B1 (en) * | 2011-10-27 | 2017-10-03 | Masimo Corporation | Physiological monitor gauge panel |
| US9480435B2 (en) * | 2012-02-09 | 2016-11-01 | Masimo Corporation | Configurable patient monitoring system |
| US9232894B2 (en) * | 2012-08-27 | 2016-01-12 | Koninklijke Philips N.V. | Remote patient management system |
| US10580173B2 (en) * | 2013-11-15 | 2020-03-03 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Graphical display of physiological parameters on patient monitors |
| US9875560B2 (en) * | 2013-11-15 | 2018-01-23 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Graphical display of physiological parameters on patient monitors |
| JP6331384B2 (ja) * | 2013-12-26 | 2018-05-30 | オムロンヘルスケア株式会社 | 活動量関連情報表示装置 |
| CN104970778A (zh) * | 2014-04-13 | 2015-10-14 | 唐伟钊 | 一种具有预警癌症和疾病功能的电子仪器 |
| EP3261526B1 (en) * | 2015-02-24 | 2020-11-25 | Koninklijke Philips N.V. | Apparatus and method for providing a control signal for a blood pressure measurement device |
| EP3334334A1 (en) * | 2015-08-11 | 2018-06-20 | Masimo Corporation | Medical monitoring analysis and replay including indicia responsive to light attenuated by body tissue |
-
2016
- 2016-12-28 JP JP2016256035A patent/JP6734773B2/ja active Active
-
2017
- 2017-11-27 WO PCT/JP2017/042371 patent/WO2018123386A1/ja active Application Filing
- 2017-11-27 DE DE112017006626.3T patent/DE112017006626T5/de active Pending
- 2017-11-27 CN CN201780080642.9A patent/CN110113993B/zh active Active
-
2019
- 2019-06-27 US US16/454,745 patent/US11647965B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN110113993A (zh) | 2019-08-09 |
| WO2018123386A1 (ja) | 2018-07-05 |
| DE112017006626T5 (de) | 2019-10-10 |
| US11647965B2 (en) | 2023-05-16 |
| JP2018102873A (ja) | 2018-07-05 |
| CN110113993B (zh) | 2022-08-02 |
| US20190313982A1 (en) | 2019-10-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6734773B2 (ja) | 血圧関連情報表示装置、血圧関連情報表示方法およびプログラム | |
| US11918327B2 (en) | Sphygmomanometer, blood pressure measurement method, and device | |
| US11850031B2 (en) | Sphygmomanometer, blood pressure measurement method, and device | |
| JP6761338B2 (ja) | 血圧計および血圧測定方法並びに機器 | |
| US10765366B2 (en) | Appliance | |
| JP6772058B2 (ja) | 血圧計および血圧測定方法並びに機器 | |
| KR101945960B1 (ko) | 손목 혈압계 | |
| US20180310835A1 (en) | Instrument | |
| KR20160092250A (ko) | 손목 혈압계 | |
| KR20150092465A (ko) | 손목시계형 혈압계 | |
| KR101680197B1 (ko) | 손목 혈압계 | |
| CN108378838A (zh) | 电子血压计及电子血压计的控制方法 | |
| KR20200054863A (ko) | 손목 혈압계 | |
| EP4054507B1 (en) | Apparatus, system and method for reducing stress | |
| KR101916309B1 (ko) | 혈압계용 커프 | |
| JP6830353B2 (ja) | 血圧計および血圧測定方法並びに機器 | |
| US20240041337A1 (en) | Blood pressure measurement device | |
| JP4674107B2 (ja) | 血圧測定装置用耳掛け部 | |
| KR20200030952A (ko) | 웨어러블유닛을 이용한 스마트 바이오 센싱시스템과 스마트 바이오 센싱방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191125 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20191125 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200630 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200710 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6734773 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |