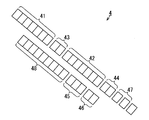以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係る遊技機1について説明する。
[遊技機1の概略構成例]
まず、図1〜図7を参照しつつ、遊技機1の概略構成について説明する。図1は、遊技機1の概略正面図である。図1に例示されるように、遊技機1は、入賞や判定に関する役物等が設けられた遊技盤2と、遊技盤2を支持固定する枠部材3とを備えている。枠部材3は、遊技盤2と所定の間隔を隔てて平行配置された透明なガラス板を支持しており、このガラス板と遊技盤2とによって、遊技球が流下可能な遊技領域10が形成されている。
遊技者がハンドル20を握ってレバー21を時計回りに回転させると、上皿28に溜められた遊技球が発射装置(不図示)へと案内され、ハンドル20の回転角度に応じた打球力で遊技領域10へと発射される。この遊技領域10には、不図示の遊技クギや風車等が設けられており、発射された遊技球は、遊技領域10における上部位置へと案内され、遊技クギや風車等に接触することでその移動方向を変化させながら遊技盤2に沿って落下する。なお、遊技球の発射は、遊技者が停止ボタン22を操作することによって一時的に停止される。
上皿28は、発射装置へ供給される遊技球及び賞球を溜めるものである。この上皿28の下方には、賞球を溜める下皿29が設けられている。この下皿29と近接配置された取り出しボタン23を遊技者が操作すると、下皿29の下面の一部が開口されて、下皿29に溜まった遊技球が下皿29の下方に配置された不図示の箱に落下する。
遊技者がハンドル20を小さい回転角で回転させた状態を維持するいわゆる「左打ち」を行うと、遊技球が相対的に弱い打球力で打ち出される。この場合、遊技球は、矢印31に例示されるように遊技領域10における左側領域を流下する。一方、遊技者がハンドル20を大きい回転角で回転させた状態を維持するいわゆる「右打ち」を行うと、遊技球が相対的に強い打球力で打ち出される。この場合、遊技球は、矢印32に例示されるように遊技領域10における右側領域を流下する。
左打ちされた遊技球の通過経路には、入賞や判定に関する役物として、第1始動口11、3つの普通入賞口14が設けられている。また、右打ちされた遊技球の通過経路には、入賞や判定に関する役物として、第2始動口12、大入賞口13、普通入賞口14、ゲート16、電動チューリップ17、及び小入賞口19が設けられている。遊技者が左打ちを行った場合、基本的には第2始動口12に遊技球が入賞することはなく、遊技者が右打ちを行った場合、基本的には第1始動口11に遊技球が入賞することはない。
遊技領域10に打ち出された遊技球は、遊技盤2に沿って流下する過程で、第1始動口11、第2始動口12、大入賞口13、普通入賞口14、及び小入賞口19のいずれかに入球して入賞し得る。これらに入賞した場合、入賞した箇所に応じた所定数の賞球が上皿28又は下皿29に払い出される。なお、入賞しなかった遊技球は、排出口18を介して遊技領域10から排出される。
第1始動口11は、常時開放されている始動口である。第2始動口12は、普通電動役物としての電動チューリップ17が作動しているときだけ開放される始動口である。電動チューリップ17は、第2始動口12に近接配置されており、一対の羽根部材を有している。この電動チューリップ17は、一対の羽根部材が第2始動口12を閉塞する閉姿勢(図1の実線を参照)と、第2始動口12を開放する開姿勢(図1の破線を参照)とに姿勢変化可能に構成されている。電動チューリップ17は、開姿勢になることによって右打ちされた遊技球を第2始動口12に寄せ集める。
本実施形態の第2始動口12は、通常は閉姿勢の電動チューリップ17によって閉塞されている。遊技球がゲート16を通過すると、賞球の払い出しは行われないものの、第2始動口12を開放するか否かが判定される。以下の説明では、ゲート16に対する遊技球の通過を条件として実行される判定を「普通図柄判定」と呼ぶ。普通図柄判定が行われると、普通図柄表示器45(図4参照)において普通図柄が変動表示されてから普通図柄判定の判定結果を示す普通図柄が停止表示される。普通図柄判定の判定結果を示す普通図柄には、第2始動口12を開放することを示す普通図柄と、第2始動口12を開放しないことを示す普通図柄とがある。第2始動口12を開放することを示す普通図柄が停止表示された場合、電動チューリップ17の一対の羽根部材が規定時間開姿勢を維持した後に閉姿勢に戻る動作が規定回数行われる。一方、第2始動口12を開放しないことを示す普通図柄が停止表示された場合、電動チューリップ17は開姿勢にならず閉姿勢のままである。
普通図柄判定で第2始動口12を開放すると判定される確率には、時短状態(例えば、1/1)と、時短状態よりも確率が低い非時短状態(例えば、1/256)とがある。本実施形態における普通図柄の変動時間は、時短状態であるか非時短状態であるかに関わらず同じである(例えば0.4秒間)。電動チューリップ17が開姿勢に制御される時間(すなわち、第2始動口12の開放時間)は、時短状態の方が非時短状態よりも長い。具体的には、例えば、時短状態のときに第2始動口12を開放することを示す普通図柄が停止表示された場合、第2始動口12が5秒間だけ1回開放される。本実施形態では、時短状態のときに遊技者が右打ちしていれば、容易に第2始動口12に遊技球が入賞する。非時短状態のときに第2始動口12を開放することを示す普通図柄が停止表示された場合、第2始動口12が0.2秒間だけ1回開放される。本実施形態では、非時短状態のときに遊技者が右打ちを継続していても、第2始動口12は、仮に開姿勢になったとしてもすぐに閉姿勢になる。このため、非時短状態のときは基本的には第2始動口12に遊技球を入球できない。よって、非時短状態のときに第2始動口12を狙うのはあまり現実的ではなく、遊技者は、非時短状態のときは第1始動口11を狙った左打ちを行う。また、時短状態のときは第2始動口12を狙った右打ちを行う。なお、時短状態の場合よりも非時短状態の場合の方が普通図柄の変動時間を短くしてもよい。例えば、時短状態の場合における普通図柄の変動時間は0.4秒間であり、非時短状態の場合における普通図柄の変動時間は25秒間でもよい。
遊技機1では、遊技球が第1始動口11を通過して入賞した場合、又は遊技球が第2始動口12を通過して入賞した場合、遊技者に有利な大当たり遊技(特別遊技)を実行するか否かが判定される。以下の説明では、第1始動口11への遊技球の入賞を条件として実行される判定を「第1特別図柄判定」と呼び、第2始動口12への遊技球の入賞を条件として実行される判定を「第2特別図柄判定」と呼ぶ。また、これらの判定を総称して「特別図柄判定」と呼ぶ。第1特別図柄判定が行われると、第1特別図柄表示器41(図3参照)において第1特別図柄が変動表示されてから判定結果を示す第1特別図柄が停止表示される。第2特別図柄判定が行われると、第2特別図柄表示器42(図3参照)において第2特別図柄が変動表示されてから判定結果を示す第2特別図柄が停止表示される。
第1特別図柄判定の判定結果を示す第1特別図柄として、大当たりを示す大当たり図柄A〜C、及びハズレを示すハズレ図柄が予め用意されている。また、第2特別図柄判定の判定結果を示す第2特別図柄として、大当たり図柄D〜F、小当たりを示す小当たり図柄1〜3、及びハズレ図柄が予め用意されている。なお、第1特別図柄には第2特別図柄と異なり小当たり図柄がない(すなわち小当たり確率0%)。特別図柄判定で大当たりと判定される確率は、入賞した始動口および遊技状態に関わらず同じである(例えば約1/319、図5(A)及び(B)参照)。
大当たりを示す大当たり図柄A〜Fのうちの何れかが停止表示された場合、この停止表示に続いて大当たり遊技が行われる。大当たり遊技では、大入賞口13を閉塞するプレートが作動される。これにより、通常は閉塞されている大入賞口13が開放される。遊技者は、大当たり遊技中に大入賞口13に遊技球を入賞させることで、大当たり遊技が行われていないときに比べてより多くの賞球を得ることができる。
大入賞口13の開放パターンは予め複数用意されており、大入賞口13が何れの開放パターンで開放されるかは、停止表示された大当たり図柄の種類によって一義的に決まる。本実施形態では、大当たり図柄A〜Fが停止表示された場合、所定の条件(本実施形態では、大入賞口13への遊技球の入賞数が10個に達すること、又は、大入賞口13が開放されてから29.5秒が経過すること)を満たすまで大入賞口13が開放されるラウンド遊技が複数回行われる。大当たり図柄A〜Fが停止表示された場合、1回のラウンド遊技(以下、「1R」と呼ぶ。)中の大入賞口13の開放時間は、遊技者が10個の遊技球を大入賞口13に入賞させるのに十分な時間である。なお、大当たり図柄A〜Fが停止表示された場合の1R中の大入賞口13の開放時間は、上述した時間に限らず予め定められた任意の時間(具体的には、29.5秒以下であって1.8秒を超える時間)でよい。
大当たり図柄Cは7Rの大当たりである。本実施形態の遊技機1では、遊技者は、基本的には第1特別図柄判定によって初当たりを引き当てる。初当たりとは、遊技を開始してから1回目に発生した大当たり遊技をいう。図5(C)の「第1特別図柄」の行に例示するように、第1特別図柄判定の大当たりのうち大当たり図柄Cの割合が85%を占める。このため、初当たりのほとんどは大当たり図柄Cとなる。
ここで、本実施形態の遊技機1は、初期的には非時短状態に設定される。そして、大当たり遊技(なお、遊技状態としては非時短状態)が実行されると、その終了時に時短状態に設定される。大当たり遊技が実行されなければ時短状態に設定されず、非時短状態のままである。大当たり遊技終了時に時短状態に設定されると、その大当たり遊技の契機となった大当たり図柄に対応した回数の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(C)参照)。本実施形態の遊技機1では、時短状態用に複数の演出モードが予め用意されている。各演出モードは、互いに異なる演出が実行される。本実施形態では、遊技者の好みに応じた演出にて小当たりを狙えるように、大当たり遊技終了後の演出モードを遊技者が選択できる構成を採用している。
大当たり図柄Cの場合、大当たり遊技直後に夜モード又は新章モード(なお、遊技状態としては時短状態)に移行し、3回の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(C)及び図8(A)参照)。夜モード及び新章モードは、3回の第2特別図柄判定と、4回の第2特別図柄判定の保留との合計7回の第2特別図柄判定によって小当たりを狙う演出モードである。大当たり図柄Cに係る大当たり遊技直後には、夜モード、及び新章モードのうち、この大当たり遊技中に遊技者が選択した演出モードに移行する。
大当たり図柄Bは7Rの大当たりであり、大当たり図柄Eは8Rの大当たりであり、大当たり図柄Fは5Rの大当たりである。大当たり図柄B、E、又はFの場合、大当たり遊技直後にバトルモード又はストーリーモード(なお、遊技状態としては時短状態)に移行し、13回の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(C)及び図8(A)参照)。バトルモード及びストーリーモードは、13回の第2特別図柄判定と、4回の第2特別図柄判定の保留との合計17回の第2特別図柄判定によって小当たりを狙う演出モードである。大当たり図柄B、E、及びFに係る大当たり遊技直後には、バトルモード、及びストーリーモードのうち、この大当たり遊技中に遊技者が選択した演出モードに移行する。以下の説明では、バトルモード、及びストーリーモードを総称して「少女ラッシュ」と呼ぶ。
大当たり図柄A及びDは、10Rの大当たりであり、本実施形態においては遊技者が最も賞球を得られる大当たりである。大当たり図柄A又はDの停止表示を契機に大当たり遊技が実行された場合、大当たり遊技直後に神ラッシュ又は悪魔ラッシュ(なお、遊技状態としては時短状態)に移行し、100回の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(C)及び図8(A)参照)。神ラッシュ及び悪魔ラッシュは、100回の第2特別図柄判定と、4回の第2特別図柄判定の保留との合計104回の第2特別図柄判定によって小当たりを狙う演出モードである。
神ラッシュは、夜モード及びバトルモードと互いに演出内容が関連するグループAの演出モードである。グループAの演出は、例えば地上波で放送されたテレビアニメをもとに作られている。悪魔ラッシュは、新章モード及びストーリーモードと互いに演出内容が関連するグループBの演出モードである。グループBの演出は、例えば上記テレビアニメの劇場版アニメをもとに作られている。本実施形態では、神ラッシュ及び悪魔ラッシュに特別感を与えるために、神ラッシュ及び悪魔ラッシュだけは遊技者が選べず、前回の時短状態のときの演出モードと同じグループの演出モードに自動的に決定される構成を採用している。後に詳述するが、本実施形態では、演出モードが決定される度に何れの演出モードに決定されたかの情報が演出制御基板130のサブRAM133(後述する)に記憶される。この情報に基づいて、神ラッシュ及び悪魔ラッシュのうち何れの演出モードで演出が実行されるかが決定される。なお、初当たりのときは神ラッシュとなる。
特別図柄判定の判定結果としてハズレ図柄または小当たりを示す小当たり図柄が停止表示された場合、この停止表示に続いて大当たり遊技が行われない。具体的には、ハズレ図柄が停止表示された場合、この停止表示後には次の特別図柄判定が行われる。小当たり図柄1〜3のうちの何れかが表示器4に停止表示された場合、この停止表示に続いて小当たり遊技が実行される(図5(D)参照)。小当たり遊技では、小入賞口19を閉塞するプレートが作動される。これにより、通常は閉塞されている小入賞口19が開放される。
小入賞口19を閉塞するプレートには「V」との文字が表記されている(図1参照)。この文字は、小入賞口19の内部に設けられたV入賞口スイッチ116bの位置を示唆する。ここで、小入賞口19の周囲は透明な合成樹脂材で形成されている。このため、小入賞口19の開閉に関わらず遊技者は小入賞口19の内部を視認可能である。具体的には、小入賞口19の内部には小入賞口スイッチ116a、V入賞口スイッチ116b、ハズレ入賞口スイッチ116c、及びこれらのスイッチを開閉するプレート(不図示)が設けられており、何れも視認可能である(図4参照)。本実施形態では、小当たり遊技が行われていない場合、上記プレートにより、V入賞口スイッチ116bは遊技球が通過不可能に閉塞され、ハズレ入賞口スイッチ116cは遊技球が通過可能に開放されている。本実施形態の小当たり遊技中は、上記プレートにより、V入賞口スイッチ116bは遊技球が通過可能に開放され、ハズレ入賞口スイッチ116cは遊技球が通過不可能に閉塞される。
小当たり遊技において小入賞口19が開放される時間は、大当たり遊技における大入賞口13の1回の開放期間(以下、「1R」と呼ぶ。)よりも短く、1.8秒以下の予め定められた任意の時間(例えば1.8秒間)である。なお、小当たり遊技中における小入賞口19の開放時間の合計時間が1.8秒以下であれば、小入賞口19は小当たり遊技中に複数回開放されてもよい。小当たり遊技中に小入賞口19に入賞できる遊技球数は、大当たり遊技中に大入賞口13に入賞可能な遊技球数(例えば平均10個)に比べると少ない。遊技者は、小当たり遊技中に、小入賞口19に平均3個の遊技球を入賞させることが可能であり、例えば30個ほどの賞球を得ることができる。この賞球は、1Rの大当たり遊技で得られる賞球よりも少ない。すなわち、小当たり遊技で得られる賞球は1Rの大当たり遊技で得られる賞球に満たない。
小入賞口19に入賞した遊技球は、まず小入賞口スイッチ116aを通過する。この遊技球は、V入賞口スイッチ116bおよびハズレ入賞口スイッチ116cのうちの何れかを通過して遊技領域10から排出される。本実施形態では、小当たり遊技中に遊技者が右打ちしていれば、容易にV入賞口スイッチ116bを遊技球が通過(以下、「V入賞」と呼ぶ。)する。V入賞した場合、小当たり遊技の終了に続いて、大入賞口13を開放する大当たり遊技が開始される(図5(D)参照)。小当たり遊技が行われてもV入賞しなかった場合(具体的には、ハズレ入賞口スイッチ116cしか遊技球が通過しなかった場合)、小当たり遊技の終了に続いて大当たり遊技が開始されず、次の特別図柄判定が行われる。
なお、小当たり遊技では、小入賞口19に代えて大入賞口13が開放されてもよい。この場合の大入賞口13の内部には、V入賞口スイッチと、このスイッチを開閉するプレートと、ハズレ入賞口スイッチとが設けられる。そして、小当たり遊技が行われていない場合、上記プレートにより、V入賞口スイッチは遊技球が通過不可能に閉塞され、ハズレ入賞口スイッチは遊技球が通過可能に開放される。また、小当たり遊技中は、上記プレートが作動されることにより、V入賞口スイッチは遊技球が通過可能に開放され、ハズレ入賞口スイッチは遊技球が通過不可能に閉塞される。V入賞口スイッチを遊技球が通過した場合、小当たり遊技の終了に続いて、引き続き大入賞口13を開放する大当たり遊技が開始される。ハズレ入賞口スイッチを遊技球が通過した場合、小当たり遊技の終了に続いて大当たり遊技が開始されず、次の特別図柄判定が行われる。
小当たり遊技における小入賞口19の開放パターン、及びこの小当たり遊技終了直後の大当たり遊技における大入賞口13の開放パターンは、何れも停止表示された小当たり図柄の種類によって一義的に決まる。小当たり遊技終了直後の大当たり遊技が終了すると時短状態で制御される(図5(D)参照)。時短状態には、小当たり図柄によって定められた回数の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで制御される。
小当たり図柄1が停止表示されると、V入賞を条件に10Rの大当たり遊技が行われる。小当たり図柄1の停止表示に基づいて大当たり遊技が実行された場合、神ラッシュ又は悪魔ラッシュ(なお、遊技状態としては時短状態)に移行し、100回の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(D)及び図8(A)参照)。小当たり図柄1によって、大当たり図柄A又はDの場合と同様に、100回の第2特別図柄判定と、4回の第2特別図柄判定の保留との合計104回の第2特別図柄判定で小当たりを狙える。小当たり図柄1によって神ラッシュ及び悪魔ラッシュのうち何れの演出モードに移行するかは、大当たり図柄A又はDが停止表示された場合と同様に遊技者が選択できない。本実施形態では、小当たり図柄1を初当たりで引き当てることが基本的にはない。このため、小当たり図柄1が停止表示されると、基本的には神ラッシュ及び悪魔ラッシュのうち前回の時短状態のときの演出モードと同じグループの演出モードに移行する。
小当たり図柄2が停止表示されると、V入賞を条件に8Rの大当たり遊技が行われる。また、小当たり図柄3が停止表示されると、V入賞を条件に5Rの大当たり遊技が行われる。小当たり図柄2又は3の場合、バトルモード又はストーリーモード(なお、遊技状態としては時短状態)に移行し、13回の第2特別図柄判定に係る変動表示が終了するまで時短状態で制御される(図5(D)及び図8(A)参照)。小当たり図柄2又は3によって、大当たり図柄B、E、又はFの場合と同様に、13回の第2特別図柄判定と、4回の第2特別図柄判定の保留との合計17回の第2特別図柄判定で小当たりを狙える。小当たり図柄2又は3の停止表示を契機とする大当たり遊技直後には、バトルモード、及びストーリーモードのうち遊技者が選択した演出モードに移行する。
大当たり遊技終了時に時短状態に設定され、上述した回数の特別図柄判定が行われても1度も大当たり遊技が実行されなかった場合、上記回数目の特別図柄の停止表示に伴って非時短状態に設定される。演出モードとしては、上記回数目の特別図柄の停止表示直前に、時短状態のときの演出モードから通常モードに転落する。本実施形態の遊技機1では、例えば、大当たり遊技中を除き、非時短状態で遊技が制御されているときには通常モードで演出が行われる。通常モードは、グループA及びBの何れにも関連しない演出モードである。
上述したように、本実施形態では、第2始動口12に対し時短状態のときに遊技球を容易に入賞可能であり、非時短状態のときに遊技球を入賞不可能である。本実施形態では、第2特別図柄判定が行われると相対的に高い確率(例えば約1/10)で小当たり遊技が行われる(図5(B)参照)。本実施形態では小当たり遊技中に基本的にV入賞するため、時短状態のときは比較的容易に小当たり遊技を介して大当たり遊技が実行される。
普通入賞口14は、第1始動口11及び第2始動口12と同様に常時開放されており、遊技球の入賞によって所定個数の賞球が払い出される入賞口である。なお、第1始動口11等とは異なり、普通入賞口14に遊技球が入賞しても判定が行われることはない。
[遊技機1の演出手段の構成例]
図1に例示されるように、遊技機1には、各種の演出を行うものとして、液晶表示装置、演出役物7、スピーカ24、盤ランプ25、演出ボタン26、及び、枠ランプ37が設けられている。
液晶表示装置(EL表示装置等でもよい)の表示画面(以下、「液晶画面5」と呼ぶ。)は、各種演出画像を表示する画像表示装置である。液晶表示装置は遊技盤2よりも遊技機1の背面側(すなわち後方側)に設けられ、遊技盤2に形成された開口を通して視認できる。図1に示すように、液晶画面5は遊技者によって視認され易い位置に設けられている。液晶画面5には、装飾図柄55、小図柄56、第4図柄57、CG又はアニメのキャラクタなどが表示される。
装飾図柄55、小図柄56、及び第4図柄57は、特別図柄の変動表示に同期して変動表示される画像である。装飾図柄55は、1〜9のうちの何れかの数字を表す図柄である。本実施形態では特別図柄の変動表示の開始に伴って3つの装飾図柄55(及び3つの小図柄56)が横並びで変動表示を開始し、特別図柄の停止表示の開始に伴って3つの装飾図柄55(及び3つの小図柄56)が横並びで停止表示する(「本停止」と呼ぶ。)。3つの数字の組み合わせによって、特別図柄判定の判定結果が報知される。停止表示する装飾図柄55の組み合わせは小図柄56の組み合わせと同じである。
具体的には、大当たり図柄A、D、又は小当たり図柄1の停止表示の開始に伴って、装飾図柄55として「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄が3つ停止表示される(図5(E)、図31(C)参照)。また、大当たり図柄B、E、又は小当たり図柄2の停止表示の開始に伴って、装飾図柄55として「神」との文字を重畳表示しない7図柄が3つ停止表示される。また、大当たり図柄C、F、又は小当たり図柄3の停止表示に伴って、装飾図柄55として1〜6、8、又は9図柄のうち何れかが3つ停止表示される。
本実施形態では、大当たり図柄B、E、又は小当たり図柄2が停止表示されるのに先立って、装飾図柄55(及び小図柄56)が、1〜9図柄のうち何れかが3つ仮停止表示される。また、大当たり図柄C、F、又は小当たり図柄3が停止表示されるのに先立って、装飾図柄55(及び小図柄56)が、1〜6、8、又は9図柄のうち何れかが3つ仮停止表示される。本実施形態では、このように仮停止表示された装飾図柄55(及び小図柄56)を再び高速で変動表示(以下、「再変動」と呼ぶ。)させて、「神」との文字を重畳表示しない7図柄に変化することを期待させる再抽選演出を実行する。本実施形態では、再抽選演出の開始に伴って、3つの装飾図柄55を図柄揃いの態様で同期したまま、図柄揃いの態様が保持されていることを認識可能な態様で再変動させる(例えば、222→333→444とゆっくり変化させる。)。また、本実施形態では、再抽選演出の開始に伴って、3つの小図柄56を個々の図柄を認識不可能なスピードで再変動させる。
本実施形態では、大当たり図柄B、E、又は小当たり図柄2が停止表示される場合、再抽選演出によって1〜6、8、又は9図柄が再変動して「神」との文字を重畳表示しない7図柄に変化(以下、このような変化を「昇格」と呼ぶ。)する。再抽選演出によって昇格することにより、遊技者に対して、大当たり図柄B、E、又は小当たり図柄2であることを示唆することが可能である。大当たり図柄C、F、又は小当たり図柄3が停止表示される場合、再抽選演出によって昇格せず、装飾図柄55は再抽選演出前と同じ組み合わせで仮停止表示する。小図柄56は、装飾図柄55が再抽選演出後に仮停止表示されるのと同時に、装飾図柄55と同じ組み合わせで仮停止表示する。その後、装飾図柄55の停止表示に伴って、小図柄56が装飾図柄55と同じ組み合わせで停止表示する。
ここで、本実施形態では、装飾図柄55が昇格する(具体的には、小当たり図柄2である)ことを示唆するために、再抽選演出中に群演出が実行される場合がある。群演出は、大量のキャラCがキャラC用の武器(本実施形態ではモリ)に乗って液晶画面5の右下隅から左上隅に向かって横切る演出である(図15(C)参照)。再抽選演出中の群演出は、再抽選演出によって装飾図柄55及び小図柄56が再変動を開始したときから装飾図柄55及び小図柄56が仮停止表示するまでの間に実行される。再抽選演出中の群演出は、小当たり図柄2である場合に実行され、他の特別図柄である場合に実行されない。再抽選演出中の群演出は、遊技制御基板100(後述する)から変動開始コマンド(後述する)を受信したときに演出制御基板130(後述する)による乱数抽選により実行の有無が決定される。ここで、図6は、再抽選演出中の群演出の実行割合について説明するための説明図である。本実施形態では、小当たり図柄2である場合、再抽選演出中に群演出が実行される割合は20%であり、再抽選演出中に群演出が実行されない割合は80%である(図6参照)。すなわち、装飾図柄55は、再抽選演出中に群演出が実行されたか否かに関わらず昇格可能である。小当たり図柄1又は3である場合、再抽選演出中に群演出が実行されることがなく、再抽選演出中に群演出が実行されない割合は100%である。本実施形態では、ハズレ又は大当たりである場合、再抽選演出中に群演出が実行されない。
なお、再抽選演出中の群演出は、大当たり図柄B又はEであることを報知するために実行されてもよい。このような場合、再抽選演出中の群演出は、大当たり図柄B又はEである場合に実行され、他の特別図柄である場合に実行されない。
第4図柄57は色で表現されるものであり、装飾図柄55(及び特別図柄)と同期して変動表示した後、装飾図柄55(及び特別図柄)と同時に停止表示される。本実施形態では、第4図柄57は、「赤」、「青」、「緑」、「黄」、「白」、及び、「紫」の第4図柄57が、この順で同じ位置に一定の時間(例えば0.2秒間)ずつ繰り返し表示されることにより変動表示する。なお、第4図柄57の変動表示は、所定色(例えば青)の第4図柄57を一定の時間毎(例えば0.2秒毎)に表示と非表示とに切り替えて点滅させることにより実現されてもよい。
停止表示される装飾図柄55(及び小図柄56)と、停止表示される第4図柄57の色との組み合わせは、特別図柄毎に異なるように予め定められている(図5(E)参照)。これにより、装飾図柄55(及び小図柄56)と第4図柄57との組み合わせにより、停止表示された特別図柄が示す内容と同じ内容を報知できる。例えば、装飾図柄55として「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄が3つ停止表示されると共に、第4図柄57として「赤」の図柄が停止表示されることは、大当たり図柄Aと同じ内容を報知する。また、例えば、装飾図柄55として2図柄が3つ停止表示されると共に、第4図柄57として「青」の図柄が停止表示されることは、大当たり図柄Cと同じ内容を報知する。
第4図柄57は、液晶画面5の端の方に小さく表示される画像であり、装飾図柄55(及び小図柄56)に比べて目立たない画像である。このため、装飾図柄55と第4図柄57との組み合わせによって大当たりの種類を報知していても、遊技者に気付かれ難い。なお、第4図柄57は、液晶表示装置5の右側近傍に設けられた発光素子(例えばフルカラーLED)で実現されてもよい。この発光素子を、装飾図柄55の停止表示と同時に予め定められた色で点灯させることにより第4図柄57として用いて、特別図柄判定の判定結果を一義的に報知してもよい。
図面では、見易くする目的で変動表示中の第4図柄の図示を省略し、停止表示中の第4図柄だけ図示している。しかしながら、小図柄56および第4図柄57は、大当たり遊技中以外は常に、演出役物7で隠れない位置において他の画像よりも手前側に表示される。このため、見えなくなることも視認性が低下することもない。これに対し、装飾図柄55は他の画像の後ろ側に重畳表示されて見えなくなったり、演出役物7で隠れたりする場合がある。また、装飾図柄55は、特別図柄が変動表示しているか否かに関わらず一部または全部が非表示となることがある。
本実施形態の演出役物7は、遊技盤2の前面とガラス板との間に設けられ、液晶画面5の上方中央に配置されている。本実施形態の演出役物7は、動作していないときは液晶画面5上方の初期位置に配される。演出役物7を動作させるタイミングとなると、演出役物7は、演出役物用モータ71の駆動力により初期位置から液晶画面5の中央に向かって回転しながら下方向に移動し、液晶画面5の前面に配される。演出役物7は、初期位置と進出位置との間で動作させることによって各種の演出に用いられる。
演出役物7は透光性のある合成樹脂材で形成される。演出役物7は、内蔵された複数の発光素子(盤ランプ25の1種)を複数色または単色で発光させることによって各種の演出に用いられる。例えば、演出役物7に内蔵された各発光素子を7つの色(具体的には、赤色、橙色、黄色、緑色、水色、青色、及び紫色)で同時に発光させることにより全体として虹色で発光させる。演出役物7は、その位置に関わらず遊技者が視認可能である。このため、演出役物7に施された装飾および演出役物7の発光により、動作の有無に関わらず演出効果を高めることが可能である。
なお、演出役物7は、例えば遊技盤2と液晶画面5との間に設けられ、初期位置では遊技者が視認困難でもよい。また、演出役物7は、上下左右に移動可能でもよいし振動可能でもよい。
スピーカ24は、液晶画面5で行われる画像を表示する演出と同期するように或いは非同期に、楽曲や音声、効果音等を出力して音による演出を行う。
盤ランプ25は、遊技盤2に設けられた複数の発光素子(例えばフルカラーLED)の総称である。枠ランプ37は、枠部材3に設けられた複数の発光素子(例えばフルカラーLED)の総称である。枠ランプ37は、例えば、枠部材3の左側に設けられた左サイドランプと、枠部材3の右側に設けられた右サイドランプと、2つのスピーカ24の間に設けられたセンターランプと、遊技者によって操作可能な演出ボタン26(図2参照)に内蔵されたボタンランプとによって構成される。
図2は、演出ボタン26の一例について説明するための説明図である。本実施形態の演出ボタン26は枠部材3に設けられており、遊技者は操作(例えば押下)することによって操作情報を入力可能である。遊技機1では、演出ボタン26の操作に応じた演出が行われる場合がある。演出ボタン26は、その上面が枠部材3の上面と略同じ高さにある通常状態と、その上面が枠部材3の上面に対して所定の高さ(例えば10センチ)だけ上方に突出した突出状態との間でその高さを変更する制御が可能に構成されている。なお、演出ボタン26は、通常状態と突出状態との間におけるどの高さに制御されていても操作が可能である。
また、本実施形態の枠部材3は、遊技者が選択操作またはカーソル移動を行うために演出キー27が設けられている(図2参照)。演出キー27はいわゆる十字キーであり、上キー、下キー、左キー、及び右キーを有して構成されている。演出キー27は、液晶画面5、盤ランプ25、及び枠ランプ37の光量調整に用いられたり、スピーカ24の音量調整に用いられたりする。
[表示器4の構成例]
図3は、図1における表示器4の拡大図である。表示器4は、主に特別図柄判定や普通図柄判定に関する情報を表示するものであり、図3に例示されるように、第1特別図柄表示器41、第2特別図柄表示器42、第1特別図柄保留表示器43、第2特別図柄保留表示器44、普通図柄表示器45、普通図柄保留表示器46、遊技状態表示器47、ラウンド表示器48等を有して構成されている。
第1特別図柄表示器41は、第1特別図柄判定が行われると、特別図柄を変動表示してから第1特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示することによって第1特別図柄判定の判定結果を報知する。第2特別図柄表示器42は、第2特別図柄判定が行われると、特別図柄を変動表示してから第2特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示することによって第2特別図柄判定の判定結果を報知する。
第1特別図柄保留表示器43は、第1特別図柄判定の保留数(以下、「特1保留数」と呼ぶ。)を表示する。第2特別図柄保留表示器44は、第2特別図柄判定の保留数(以下、「特2保留数」と呼ぶ。)を表示する。なお、本実施形態では遊技者が保留数を分かり易いように、液晶画面5に保留アイコン54及び保留数字(不図示)が表示される。保留アイコン54は、保留の数(本実施形態では最大4つ)だけ保留された順に並んで表示される。
本実施形態では、保留アイコン54の表示態様が演出モードによって異なる。バトルモード及びストーリーモードの場合、保留アイコン54は基本的には白色で表示される(図31(A)参照)。ここで、本実施形態では、青色、緑色、赤色、及び虹色が大当たり又は小当たりとなる可能性(以下、「信頼度」という)の高低を示唆する色として用いられる。各色は上述した順に、大当たりの場合に用いられ易くハズレの場合に用いられ難い。虹色は、信頼度が100%であり、大当たりである場合にのみ用いられ、ハズレである場合には用いられない。バトルモード及びストーリーモードの場合、大当たりの場合やハズレであって特別図柄の変動時間が相対的に長い場合には、保留アイコン54は信頼度の高低を示唆する色のうちの何れかで表示され易い。以下の説明では、白色の保留アイコン54を通常態様の保留アイコン54と呼び、白色以外の上記の色の保留アイコン54を特別態様の保留アイコン54と呼ぶ。
夜モード及び新章モードにおける保留アイコン54は、液晶画面5の端に表示される。また、夜モード及び新章モードにおける保留アイコン54は、小さく目立たない表示態様で基本的には保留数だけを報知し、特別態様で表示されない(図13(A)参照)。本実施形態では、保留内で小当たりとなる場合にのみ、保留アイコン54をわずかに異なる表示態様(例えば、明度が高い表示態様)で表示可能である。ここで、本実施形態では、新章モードにおける保留アイコン54は、1回転目および2回転目の第2特別図柄の変動表示中においてのみ表示可能である。新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中においては、後述するキャラストック演出によってキャラクタを表すパネル画像を表示することにより、保留内で小当たりとなる可能性を示唆する。このため、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示開始時から変動表示終了時まで、キャラストック演出と同じような内容を示唆する保留アイコン54は表示されない。
神ラッシュ及び悪魔ラッシュにおいては、1/10の確率の小当たりを100回の第2特別図柄判定で引き当てればよいため、小当たりを引き当てるのが比較的容易である。このため、神ラッシュ及び悪魔ラッシュにおいては、個々の特別図柄判定よりも大当たり遊技が連続することを強調するために、保留アイコン54を表示しない構成を採用している。なお、神ラッシュ及び悪魔ラッシュにおいて、保留アイコン54を表示してもよい。この場合、例えば、夜モード及び新章モードにおける保留アイコン54と同様に、液晶画面5の端に小さく表示するなど目立たない表示態様で保留アイコン54を表示するのが好ましい。
保留数字は、第1特別図柄判定の保留数および第2特別図柄判定の保留数に同期して、大当たりか否かに関わらず同じ態様で液晶画面5の左端に小さく表示される0〜4の数字である。保留数字には、第1特別図柄保留表示器43の表示と同期して保留数を0〜4の数字で示す第1保留数字と、第2特別図柄保留表示器44の表示と同期して保留数を0〜4の数字で示す第2保留数字とがある。例えば、第1特別図柄判定の保留が1つ増えると第1保留数字が1加算された数字で表示され、第2特別図柄判定の保留が1つ増えると第2保留数字が1加算された数字で表示される。ここで、保留アイコン54は装飾図柄55と同様に非表示にされたり他の画像で見えなくなったり表示されなかったりする。これに対して、保留数字は小図柄56と同様に、演出モードに関わらず常に他の画像よりも手前側に表示されるので、他の画像によって見えなくなることも視認性が低下することもない。
普通図柄表示器45は、普通図柄判定が行われると、普通図柄を変動表示してから普通図柄判定の判定結果を示す普通図柄を停止表示することによって普通図柄判定の判定結果を報知する。普通図柄保留表示器46は、普通図柄判定の保留数を表示する。遊技状態表示器47は、遊技機1の電源投入時点における遊技状態を表示する。ラウンド表示器48は、基本的には消灯しており、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に大当たり図柄が停止表示されたことに応じて、大当たり遊技のラウンド数を表示する。ラウンド表示器48は、ハズレ図柄または小当たり図柄が停止表示されたことに応じては点灯せず消灯したままである。
[遊技機1の制御装置の構成、及び、遊技機1で行われる各種判定の概要]
図4〜図7を参照しつつ、遊技機1が備える制御装置の構成例、及び、遊技機1で行われる各種判定の概要について説明する。図4は、遊技機1が備える制御装置の構成例を示すブロック図である。図5は、特別図柄判定について説明するための説明図である。図7は、メインRAM103の構成例及びメインRAM103に格納される各種情報を示すブロック図である。
遊技盤2の裏面側には、上皿28又は下皿29へと送り出される遊技球を溜めておく球タンクの他に、遊技機1の動作を制御する制御装置が設けられている。図4に例示されるように、遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種ランプや演出役物7による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されている。なお、制御装置の構成はこれに限定されるものではなく、例えば演出制御基板130、画像音響制御基板140、及びランプ制御基板150が1つの基板で構成されていてもよい。
[遊技制御基板100の構成例]
図4に例示されるように、遊技制御基板100は、メインCPU101、メインROM102、メインRAM103、及び乱数回路104を備えている。メインCPU101は、メインROM102に記憶されたプログラム等に基づいて、判定や払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う。メインRAM103は、メインCPU101が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。乱数回路104は、例えば、大当たりかハズレか小当たりかの決定に用いる大当たり乱数を生成する。
遊技制御基板100には、第1始動口スイッチ111、第2始動口スイッチ112、電動チューリップ制御部113、ゲートスイッチ114、大入賞口スイッチ115、小入賞口スイッチ116a、V入賞口スイッチ116b、ハズレ入賞口116c、大入賞口制御部117、小入賞口制御部118、普通入賞口スイッチ119、及び表示器4を構成する各表示器41〜48が接続されている。また、普通入賞口スイッチ119についても実際は4つ備えているが、図4においては、普通入賞口スイッチ119を1つだけ表記している。
第1始動口スイッチ111は、第1始動口11に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。第2始動口スイッチ112は、第2始動口12に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。電動チューリップ制御部113は、遊技制御基板100からの制御信号に応じて、電動チューリップ17の一対の羽根部材に駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、第2始動口12を開閉する。ゲートスイッチ114は、遊技球がゲート16を通過したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。大入賞口スイッチ115は、大入賞口13に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。小入賞口スイッチ116aは、小入賞口19に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。V入賞口スイッチ116bは、V入賞を検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。ハズレ入賞口スイッチ116cは、遊技球がハズレ入賞口スイッチで検知されたことを示す検知信号を遊技制御基板100に出力する。大入賞口制御部117は、遊技制御基板100からの制御信号に基づいて、大入賞口13を閉塞するプレートに駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、大入賞口13を開閉する。小入賞口制御部118は、遊技制御基板100からの制御信号に基づいて、小入賞口19を閉塞するプレートに駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、小入賞口19を開閉する。また、小入賞口制御部118は、遊技制御基板100からの制御信号に基づいて、V入賞口スイッチ116bとハズレ入賞口スイッチ116cとを開閉するプレートに駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動させることによって、これらのスイッチを開閉する。普通入賞口スイッチ119は、遊技球が普通入賞口14に入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板100に出力する。
遊技制御基板100のメインCPU101は、第1始動口スイッチ111、第2始動口スイッチ112、大入賞口スイッチ115、小入賞口スイッチ116a、又は普通入賞口スイッチ119からの検知信号が入力されると、遊技球が入賞した場所に応じた所定数の賞球の払い出しを払出制御基板(不図示)に指示し、払出制御基板からの情報に基づいて、払い出す賞球の個数を管理する。詳細な説明は省略するが、払出制御基板は、球タンクから遊技球を送り出す駆動モータを制御することによって、上皿28又は下皿29に遊技球を供給する。
メインCPU101は、第1始動口スイッチ111からの検知信号が入力されたタイミングで取得情報としての「特別図柄判定用の各種乱数」を取得し、取得した各種乱数を用いて第1特別図柄判定を実行する。また、第2始動口スイッチ112からの検知信号が入力されたタイミングで特別図柄判定用の各種乱数を取得し、取得した各種乱数を用いて第2特別図柄判定を実行する。
本実施形態では、「特別図柄判定用の各種乱数」として、例えば、大当たり乱数、図柄乱数、変動パターン乱数、及びリーチ乱数が用いられる。大当たり乱数は、大当たりかハズレか小当たりかを判定するための乱数である。図柄乱数は、大当たりと判定した場合に大当たり図柄の種類を決定し、小当たりと判定した場合に小当たり図柄の種類を決定するための乱数である。本実施形態では、大当たり遊技のラウンド数と大当たり遊技終了直後の遊技状態との組み合わせが大当たり図柄(及び小当たり図柄)毎に異なる(図5(C)及び(D)参照)。このため、図柄乱数は大当たり遊技の種類および大当たり遊技終了直後の遊技状態を決定するための乱数といえる。変動パターン乱数は、特別図柄が変動表示を開始してから特別図柄判定の判定結果を示す態様で停止表示するまでの変動時間を決定するための乱数である。本実施形態では特別図柄が変動表示されるパターン(以下、「変動パターン」と呼ぶ。)が変動時間毎に異なるので、変動パターン乱数は、変動パターンを決定するための乱数といえる。リーチ乱数は、ハズレと判定した場合の変動パターンを決定する際に、特定秒数(例えば13.5秒)を超えるハズレ用変動パターン群と、当該変動パターン群以外(すなわち、特定秒数以下のハズレ用変動パターン群)とのうちの何れから変動パターンを決定するかを選択するための乱数である。
また、メインCPU101は、ゲートスイッチ114からの検知信号が入力されたタイミングで普通図柄乱数を取得し、取得した普通図柄乱数を用いて普通図柄判定を実行する。普通図柄乱数は、第2始動口12を開放するか否かを決定するための乱数であり、例えば、メインRAM103に設けられたランダムカウンタを用いて生成される乱数である。メインCPU101は、普通図柄乱数を取得すると、取得した普通図柄乱数が、普通図柄乱数と比較される判定値として第2始動口12を開放するとの判定結果に割り当てられた判定値と一致するか否かに基づいて第2始動口12を開放するか否かを判定する。
なお、本実施形態では、大当たり乱数は乱数回路104を用いて生成され、大当たり乱数以外の特別図柄判定用の各種乱数はメインRAM103に設けたランダムカウンタを用いてソフトウェアにより生成される。なお、本実施形態では、遊技制御基板100が1つの乱数回路104を備える場合を説明するが、遊技制御基板100が複数の乱数回路を備え、この乱数回路によって大当たり乱数以外の特別図柄判定用の各種乱数が生成されてもよい。例えば、遊技制御基板100は、大当たり乱数を生成するための16ビットの乱数回路と、図柄乱数を生成するための8ビットの乱数回路と、変動パターン乱数を生成するための8ビットの乱数回路と、リーチ乱数を生成するための8ビットの乱数回路と、を備えてもよい。16ビットの乱数回路は、0〜65535の数値範囲のハードウェア乱数を、8ビットの乱数回路は、0〜255の数値範囲のハードウェア乱数を、それぞれ独立して更新する。
メインROM102には、特別図柄判定用の各種乱数と比較するための各種判定値が予め記憶されている。例えば、メインROM102には、大当たり乱数と比較される判定値が「大当たり」、「小当たり」、及び「ハズレ」のうちの何れかに予め割り当てられた大当たり判定テーブル(不図示)が予め記憶されている。例えば、メインCPU101は、取得した大当たり乱数と、大当たり判定テーブルとを用いて、大当たり判定(図43参照)の判定結果を大当たり、小当たり、及びハズレのうちの何れとするかを、特別図柄判定の判定結果が報知される以前に決定する。大当たり乱数が大当たりに対して割り当てられた判定値と一致した場合、メインCPU101は大当たりと判定する。
具体的には、本実施形態では、「0〜65535」が大当たり乱数と比較される判定値として設定されている。例えば、第1特別図柄判定に使用される大当たり判定テーブルでは、「大当たり」に対して「0〜204」が割り当てられており、「ハズレ」に対して「205〜65335」が割り当てられている(すなわち大当たり確率約1/319。図5(A)参照)。なお、第1特別図柄判定の場合、遊技状態に関わらず「小当たり」となることがない。
第2特別図柄判定に使用される大当たり判定テーブルでは、「大当たり」に対して「0〜204」が割り当てられており、「ハズレ」に対して「205〜58981」が割り当てられており、「小当たり」に対して「58982〜65535」が割り当てられている(すなわち大当たり確率約1/319。図5(B)参照))。第2特別図柄判定が行われると、遊技状態に関わらず同じ確率(例えば約1/10)で「小当たり」となる。
また、例えば、メインROM102には、大当たりと判定した場合に用いるテーブルとして、「図柄決定テーブル」(不図示)と「大当たり用変動パターンテーブル」(不図示)とが予め記憶されている。「図柄決定テーブル」は、図柄乱数と比較される判定値が複数の大当たり図柄のうちの何れかに予め割り当てられたテーブルである。例えば、メインCPU101は、大当たりと判定したのに続いて、取得した図柄乱数が何れの大当たり図柄に割り当てられた判定値と一致するかに基づいて大当たり図柄の種類を決定する。
具体的には、本実施形態では、「0〜99」が図柄乱数と比較される判定値として設定されている(図5(C)参照)。第1特別図柄判定に使用される図柄決定テーブル(第1始動口用図柄決定テーブル)では、大当たり図柄Aに対して「0」が割り当てられており(決定割合1%)、大当たり図柄Bに対して「1〜14」が割り当てられており(決定割合14%)、大当たり図柄Cに対して「15〜99」が割り当てられている(決定割合85%)。また、第2特別図柄判定に使用される図柄決定テーブル(第2始動口用図柄決定テーブル)では、大当たり図柄Dに対して「0」が割り当てられており(決定割合1%)、大当たり図柄Eに対して「1〜14」が割り当てられており(決定割合14%)、大当たり図柄Fに対して「15〜99」が割り当てられている(決定割合85%)。
本実施形態では、小当たりと判定した場合に用いるテーブルとして、「小当たり図柄決定テーブル」(不図示)と「小当たり用変動パターンテーブル」(不図示)とが予め記憶されている。小当たり図柄を決定する場合、メインCPU101は、大当たり図柄を決定する場合と同様に、「小当たり図柄決定テーブル」を参照して図柄乱数と比較される判定値が割り当てられた小当たり図柄に決定する。具体的には、小当たり図柄決定テーブルでは、小当たり図柄1に対して「0〜9」が割り当てられており(決定割合10%)、小当たり図柄2に対して「10〜64」が割り当てられており(決定割合55%)、小当たり図柄3に対して「65〜99」が割り当てられている(決定割合35%)。
また、ハズレと判定した場合に用いるテーブルとして、「リーチ判定テーブル」(不図示)と「ハズレ用変動パターンテーブル」(不図示)とが予め記憶されている。「大当たり用変動パターンテーブル」、「小当たり用変動パターンテーブル」、及び「ハズレ用変動パターンテーブル」は、取得した変動パターン乱数が、変動パターン乱数と比較される判定値のうちの何れと一致するかに基づいて、複数の変動パターンから1つの変動パターンを決定するためのテーブルである。
「リーチ判定テーブル」は、特定秒数(例えば13.5秒)を超えるハズレ用変動パターン群から変動パターンを選択するか否かを決定するためのテーブルである。取得したリーチ乱数が、リーチ判定テーブルに含まれる判定値の何れと一致するかに基づいて、特定秒数(例えば13.5秒)を超えるハズレ用変動パターン群から変動パターンを選択するか否かが決定される。本実施形態では、特別図柄判定実行時の保留数が多い程、特定秒数を超えるハズレ用変動パターン群から変動パターンを選択する割合(以下、「リーチ割合」と呼ぶ。)が小さくなるように予め設定されている(図5(F)参照)。
具体的には、例えば、「0〜99」がリーチ乱数と比較するための判定値として予め設定される場合、特別図柄判定実行時の特別図柄判定の保留数が0〜1の場合(以下、「保留0〜1」とも呼ぶ。)、特定秒数を超えるハズレ用変動パターン群から決定するとの判定結果に対して「0〜14」が割り当てられている。また、上記変動パターン群以外から決定するとの判定結果に対して「15〜99」が割り当てられている(すなわちリーチ割合15%、図5(D)参照)。また、特別図柄判定実行時の特別図柄判定の保留数が2以上の場合のリーチ割合は5%である。なお、リーチ割合は遊技状態に関わらず同じでもよいし、遊技状態に応じて(例えば、非時短状態であるか時短状態であるかによって)異なってもよい。
また、詳細な説明は省略するが、本実施形態では非時短状態用の第1特別図柄の変動パターンは、時短状態用の第1特別図柄の変動パターンよりも長い。また、時短状態用の第2特別図柄の変動パターンは、非時短状態用の第2特別図柄の変動パターンよりも短い。時短状態用の第2特別図柄の変動パターンは、時短状態用の第1特別図柄の変動パターンよりも長い。しかしながら、第2特別図柄判定でしか小当たりに当選しないため、遊技者は、時短状態のときは第1始動口11ではなく第2始動口12を狙う。
詳細な説明は省略するが、本実施形態では何れの遊技状態であっても、大当たり用変動パターンテーブル及び小当たり用変動パターンテーブルにおいては特別図柄の変動時間が長い変動パターンほど、変動パターン乱数と比較される判定値が多く割り当てられている。このため、大当たり又は小当たりの場合は、特別図柄の変動時間が相対的に長い変動パターンに決定され易い。また、ハズレ用変動パターンテーブルにおいては特別図柄の変動時間が短い変動パターンほど、変動パターン乱数と比較される判定値が多く割り当てられている。このため、ハズレの場合は、特別図柄の変動時間が相対的に短い変動パターンに決定され易く、特別図柄の変動時間が相対的に長い変動パターンに決定され難い。
本実施形態では、メインCPU101によって決定された変動パターンに対応した変動演出パターンが演出制御基板130のサブCPU131によって決定される。変動演出パターンは、「変動演出」の構成のおおもと(シナリオ)となる。ここで、「変動演出」とは、特別図柄判定の結果に基づく演出であって、特別図柄が変動表示を開始したときから当該特別図柄が停止表示するまでに実行される演出の総称である。
(メインRAM103の構成例)
図7は、遊技制御基板100におけるメインRAM103の構成例及びメインRAM103に格納される各種情報を説明するための説明図である。図7に例示されるように、メインRAM103には、判定用記憶領域1030、第1保留記憶領域1031、第2保留記憶領域1032、第3保留記憶領域1033、第4保留記憶領域1034、第1保留記憶領域1035、第2保留記憶領域1036、第3保留記憶領域1037、及び第4保留記憶領域1038が設けられている。
判定用記憶領域1030は、特別図柄判定が実際に実行されるときにその特別図柄判定に使用される各種情報が記憶される記憶領域である。第1保留記憶領域1031〜第4保留記憶領域1034は、第1始動口11に遊技球が入賞する毎に第1保留記憶領域1031から順に第1特別図柄判定に係る各種情報が記憶される記憶領域である。第1保留記憶領域1035〜第4保留記憶領域1038は、第2始動口12に遊技球が入賞する毎に第1保留記憶領域1035から順に第2特別図柄判定に係る各種情報が記憶される記憶領域である。
例えば、特別図柄が変動表示されているときや大当たり遊技中(又は小当たり遊技中)に第1始動口11又は第2始動口12に遊技球が入賞しても、特別図柄判定や特別図柄の変動表示を直ちに行うことはできない。このような状況下では、メインCPU101は、特別図柄判定に係る各種情報を、特別図柄判定の保留を示す情報として保留記憶領域1031〜1038に格納する。一方、特別図柄が変動表示されておらず、特別図柄判定が保留されておらず、また、大当たり遊技中(又は小当たり遊技中)でもない場合には、メインCPU101は、取得した各種乱数等を、遊技球が入賞した始動口に対応した第1保留記憶領域(1031又は1035)に記憶した直後、判定用記憶領域1030にシフトさせる。
例えば、第1保留記憶領域1031〜第4保留記憶領域1034のいずれにも情報が記憶されていない状態で第1始動口11に遊技球が入賞した場合、この入賞により取得された第1特別図柄判定に係る各種情報は、空きエントリの最上位である第1保留記憶領域1031に格納される。また、例えば、第1保留記憶領域1031及び第2保留記憶領域1032に情報が記憶された状態で第1始動口11に遊技球が入賞した場合、この入賞により取得された第1特別図柄判定に係る各種情報は、空きエントリの最上位である第3保留記憶領域1033に格納される。
また、例えば、保留記憶領域1031〜1038には「事前判定情報」も記憶される。本実施形態では、始動口に遊技球が入賞した際に、大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数に基づいて、特別図柄判定に先立って大当たりか否か等を判定する事前判定が行われる(図9のステップS2109、図10のステップS2209)。事前判定情報は、事前判定によって得られる情報であり、「入賞始動口情報」、大当たりであるか否かを示す情報、大当たりである場合には大当たり図柄の種類を示す情報、小当たりである場合には小当たり図柄の種類を示す情報、特別図柄の変動パターンを示す情報、遊技状態を示す情報等を含んでいる。「入賞始動口情報」は、同じ保留記憶領域内に格納される各乱数が、第1始動口11及び第2始動口12のうちの何れの始動口に入賞したことを契機として取得されたのかを示す情報である。これらの情報を含む事前判定情報は、事前判定に使用された大当たり乱数等と同じ保留記憶領域内に格納される。
第1特別図柄判定の実行に際して第1保留記憶領域1031に記憶されている情報が判定用記憶領域1030にシフトされると、第2保留記憶領域1031より下位のエントリに記憶されている情報が1エントリずつ上位にシフトされる。例えば、第1保留記憶領域1031〜第3保留記憶領域1033のそれぞれに情報が記憶された状態で第1保留記憶領域1031に記憶されている情報が判定用記憶領域1030にシフトされると、第2保留記憶領域1032に記憶されている情報が第1保留記憶領域1031にシフトされると共に、第3保留記憶領域1033に記憶されている情報が第2保留記憶領域1032にシフトされる。
このような情報のシフト処理は、第2特別図柄判定に係る情報が記憶される第1保留記憶領域1035〜第4保留記憶領域1038においても同様に行われる。本実施形態における遊技機1では、第1特別図柄判定及び第2特別図柄判定の両方が保留されている場合、すなわち第1保留記憶領域1031及び第1保留記憶領域1035の両方に情報が記憶されている場合、第1保留記憶領域1031〜第4保留記憶領域1034におけるシフト処理に先立って、第1保留記憶領域1035〜第4保留記憶領域1038におけるシフト処理が優先して行われる。よって、第2特別図柄判定が保留されている場合、判定用記憶領域1030には、第1保留記憶領域1035に記憶されている各種情報がシフトされる。また、第2特別図柄判定が保留されていない場合、すなわち第1特別図柄判定のみが保留されている場合には、第1保留記憶領域1031に記憶されている各種情報がシフトされる。なお、第1特別図柄と第2特別図柄とを同時に変動表示可能な構成を採用してもよい。このような構成では、第1特別図柄判定用と第2特図判定用との2つの判定用記憶領域1030を備えてもよい。この場合、第1保留記憶領域1031〜第4保留記憶領域1034におけるシフト処理は、第1保留記憶領域1035〜第4保留記憶領域1038におけるシフト処理と独立して行われてもよい。
[演出制御基板130の構成例]
図4に例示されるように、演出制御基板130は、サブCPU131、サブROM132、サブRAM133、RTC(リアルタイムクロック)134、及び乱数回路135を備えている。サブCPU131は、サブROM132に記憶されたプログラムに基づいて、演出を制御する際の演算処理を行う。サブRAM133は、サブCPU131が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。RTC134は、現時点の日時(日付及び時刻)を計測する。
サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、事前判定情報、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて各種演出の演出内容を設定する。例えば、演出内容を決定するための各種「演出制御用乱数」を用いた抽選により、設定する演出内容を決定する場合がある。また、サブCPU131は、演出ボタン26又は演出キー27からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合もある。サブCPU131は、設定した演出内容での演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信する。
「演出制御用乱数」は、例えば、演出制御基板130によるタイマ割込み処理(後述する)が行われていないときに乱数回路135において適宜更新される乱数である。本実施形態の遊技機1では乱数回路135を用いて演出制御用乱数を生成することで、サブCPU131が乱数を生成するのに比べてサブCPU131の処理負担を軽減している。
なお、サブCPU131が、例えば、演出制御基板130によるタイマ割込み処理を行う毎に「1」加算されるループカウント等を用いて各種演出制御用乱数を適宜更新する乱数更新処理を行ってもよい。
[画像音響制御基板140の構成例]
画像音響制御基板140は、液晶画面5の画像表示制御と、スピーカ24の演出音出力制御とを行う。画像音響制御基板140は、図4に例示されるように、統括CPU141、VDP(Video Display Processor)142、音響DSP(Digital Signal Processor)143、制御用ROM144、及び制御用RAM145を備えている。また、音響用ROM、SDRAM、CGROM、及びVRAM(何れも不図示)を備えている。
統括CPU141は、制御用ROM144に記憶されているプログラムやディスプレイリスト作成テーブルなどの各種テーブル、演出制御基板130から受信したコマンド等に基づいて、VDP142に対して、CGROMに記憶されている画像データを表示させる指示を行う。この指示は、主にディスプレイリストの出力によって行われる。
ここで、ディスプレイリストは、フレーム単位で描画の実行を指示するためのコマンド群で構成されており、描画する画像の種類、画像を描画する位置(座標)、表示の優先順位、表示倍率、回転角、透過率等の各種パラメータを含むものである。また、ディスプレイリスト作成テーブルは、このディスプレイリストを作成するために使用されるテーブルである。
統括CPU141は、音響DSP143に対しても、音響用ROMに記憶されている音響データをスピーカ24から出力させる指示を行う。
制御用ROM144は、マスクROMで構成されており、統括CPU141の制御プログラム、ディスプレイリストを生成するためのディスプレイリスト生成プログラムが記憶されている。
制御用RAM145は、統括CPU141が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。
CGROMは、特別図柄の変動表示に伴う演出や、大当たり遊技に伴う演出などを実行するために必要な演出データを記憶するものである。このCGROMは、フラッシュメモリ、EEPROM、EPROM、マスクROM等から構成され、所定範囲の画素(例えば32×32ピクセル)における画素情報の集まりからなるスプライトデータ(1枚の画像データ)、複数の画像データの集まりからなるムービーデータ等を圧縮して記憶している。なお、画素情報は、それぞれの画素毎に色番号を指定する色番号情報と画像の透過率を示すα値とから構成されている。また、CGROMは、色番号を指定する色番号情報と実際に色を表示するための表示色情報とが対応づけられたパレットデータ等を圧縮せずに記憶している。
なお、CGROMに記憶される画像データの一部のみを圧縮しておくようにしてもよい。また、ムービーデータの圧縮方法としては、MPEG4等の公知の種々の圧縮方式を用いることができる。
VRAMは、画像データを高速に書き込んだり読み出したりすることができるSRAMで構成されており、ディスプレイリスト記憶領域、展開記憶領域、液晶画面用フレームバッファなどを有して構成されている。
ディスプレイリスト記憶領域は、統括CPU141から出力されたディスプレイリストを一時的に記憶するものである。展開記憶領域は、CGROMから読み出された後に伸長された画像データを記憶するものである。液晶画面用フレームバッファは、液晶画面5に表示される画像データの描画及び表示のために用いられる。液晶画面用フレームバッファは、2つのバッファを備えるダブルバッファ方式のメモリであり、一方のバッファに記憶された画像データが表示のために出力されている間に他方のバッファに次の画像データが描画されることによって、画像データの描画と表示とが行われる。
VDP142は、CGROMに圧縮された状態で記憶されている画像データを伸長して、伸長した画像データを展開記憶領域に格納する。また、VDP142は、ディスプレイリスト記憶領域に記憶されたディスプレイリストに基づいて、展開記憶領域に格納した画像データを用いて、液晶画面用フレームバッファに対する描画処理を行う。また、VDP142は、VRAM内の表示用フレームバッファに記憶された画像データから画像の色を示す映像信号としてのRGB信号を生成し、生成したRGB信号を液晶画面5に出力する。
音響DSP143には、楽曲や音声、効果音等に関する各種音響データを記憶する音響用ROMと、音響DSP143によるデータ処理等の作業領域として使用されるSDRAMと、アンプが接続されている。音響DSP143は、統括CPU141からの指示に対応する音響データを音響用ROMからSDRAMに読み出してデータ処理を実行し、データ処理後の音響データを(アンプを介して)スピーカ24に出力する。アンプは、統括CPU141から音響DSP143を介して得られる音量に関する指示に従って音量を調整して音響データをスピーカ24に出力させる。詳細な説明は省略するが、例えば、スピーカ24が設置された位置以外の仮想的に形成される音源の位置から演出音が聞こえるような立体音響効果ありの演出音、及び立体音響効果なしの演出音に対応する音響データを出力させる。
なお、本実施形態では、VDPが描画管理を担うと共に音響DSPがサウンド管理を担う場合について説明するが、VDPが描画管理とサウンド管理との両方を担うような構成を採用してもよい。この場合、音響DSPを別途設ける必要はない。
[ランプ制御基板150の構成例]
図4に例示されるように、ランプ制御基板150は、ランプCPU151、ランプROM152、及びランプRAM153を備えている。ランプCPU151は、ランプROM152に記憶されたプログラムに基づいて、演出役物7が備える発光素子、盤ランプ25、枠ランプ37、演出役物7を動作させる演出役物用モータ71、演出ボタン26を動作させる演出ボタン用モータ261等を制御する際の演算処理を行う。また、ランプCPU151は、遊技者によって演出ボタン26または演出キー27が操作された場合に、その旨を通知する操作コマンドを演出制御基板130に送信する。演出制御基板130は、操作コマンドの受信に伴って、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に対して演出を実行するためのコマンド(以下、「操作演出開始コマンド」と呼ぶ。)を送信する。画像音響制御基板140は、操作演出開始コマンドを受信することで液晶画面5やスピーカ24において画像や音による演出を実行できる。また、ランプ制御基板150は、操作演出開始コマンドを受信することで各種ランプを発光させる演出を実行できる。
ランプROM152には、例えば、各演出手段を発光制御するための発光パターン、及び演出ボタン26及び演出役物7を動作制御するための動作パターンが予め記憶されている。発光パターンデータには、例えば、発光させるランプの種類、発光色、発光時間等を示す情報が含まれる。ランプRAM153は、例えば、ランプCPU151が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。
ランプCPU151は、演出の開始タイミング毎に、開始に係る演出の発光パターン(及び動作パターン)を指定するデータ(以下、「画像音響制御に関するデータ」と呼ぶ場合もある。)を、演出制御基板130を介して画像音響制御基板140から受信する。例えば、ランプCPU151は、受信したデータが指定する発光パターン(及び動作パターン)をランプROM152から読み出してランプRAM153に一時記憶(セット)し、そのパターンに基づく制御を行う。これにより、例えば、液晶画面5で行われる画像を表示する演出と同期するように(又は非同期に)各演出手段が発光したり動作したりする制御が実現される。
例えば、ランプCPU151は、変動演出の開始タイミングにおいて今回の変動演出が開始される際の発光パターンを指定するデータを受信したことに応じて、変動演出開始時から指定された発光パターンに基づく発光制御を実行する。また、例えば、変動演出中に、所定の演出(例えば、後述するリーチ演出)の開始タイミングで上記所定の演出用の発光パターンを指定するデータを受信し、上記所定の演出の開始に伴って指定された発光パターンに基づく発光制御を実行する。
本実施形態では、各演出用の発光パターン(及び動作パターン)は、ランプRAM153において各演出用に予め用意された異なる領域に記憶される。このような構成に限らず、例えば、ランプRAM153における1つの領域が1以上の演出用の発光パターン又は動作パターンを記憶する領域として用いられてもよい。
また、画像音響制御に関するデータは、1以上の演出に係る発光パターン(及び動作パターン)を一括して指定するデータでもよい。一例として、ランプCPU151は、変動演出中に所定の演出(例えば、後述するリーチ演出)が開始されるタイミングで、上記所定の演出以降に実行される複数の演出に対応する発光パターンを一括して指定するデータを受信し、上記所定の演出の開始に伴って指定された発光パターンによる発光制御を開始してもよい。また、他の例として、ランプCPU151は、変動演出の開始を指示するデータを受信したことに応じて、今回の変動演出中に実行される全ての演出に対応する発光パターンをランプRAM153にセットして、この発光パターンによる発光制御を変動演出中に行ってもよい。
図1〜図7を参照しつつ上述した遊技機1の構成は単なる一例であって、他の構成でもよい。また、図5を参照しつつ説明した割合は一例に過ぎず、どのような割合でもよい。
図8は、時短状態用の演出モードについて説明するための説明図である。本実施形態では、大当たり遊技終盤で、この大当たり遊技終了直後の時短状態用の演出モードを遊技者が選択できる「モード選択演出」が実行される。モード選択演出の具体的な演出態様については図9等を参照して後述するが、モード選択演出では、互いに異なる演出モードを表す複数のモード画像が表示される。この複数のモード画像のうち1つのモード画像だけが選択された状態で表示され、他のモード画像は選択されていない状態で表示される。本実施形態では、遊技機1の電源投入直後など、遊技者により演出モードの選択が行われていない初期的な状態では、グループA(図8(A)参照)の演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶されている。本実施形態では、この設定値によって、最初に選択された状態にされるモード画像の種類が決まる(すなわち、初期画面の構成が決まる)。すなわち、初期的な状態のモード選択演出では、最初にグループAの演出モードを表すモード画像が選択された状態で表示され、グループBの演出モードを表すモード画像が選択されていない状態で表示される。なお、遊技機1の電源投入直後など初期的な状態において、演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶されていなくてもよい。このように設定値が記憶されていない場合における初期的な状態のモード選択演出では、最初にグループAの演出モードを表すモード画像が選択された状態で表示され、グループBの演出モードを表すモード画像が選択されていない状態で表示されてもよい。
ここで、例えば夜モードを好む遊技者は、グループBよりもグループAの演出モードを好む傾向がある。また、例えば新章モードを好む遊技者は、グループAよりもグループBの演出モードを好む傾向がある。そこで、本実施形態の遊技機1では、遊技者の傾向を考慮して、モード選択演出の初期画面において最初に選択された状態にされる演出モードを変える構成を採用している。本実施形態では、初期画面において最初に選択された状態にされる演出モードは、モード選択演出の終了時に演出モードを示す設定値を更新することによって変える。
本実施形態のモード選択演出は、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3に係る大当たり遊技終盤に実行され、大当たり図柄A及びD並びに小当たり図柄1が停止表示されたことに基づいては実行されない。以下、モード選択演出の流れについて説明する。
本実施形態では、モード選択演出中の所定タイミング(例えば、モード選択演出開始時から2秒が経過したとき)からモード選択演出終了時まで、予め定められた演出ボタン26の有効期間(例えば7秒間)が設定される。本実施形態では有効期間中はボタンランプが白色に発光され、有効期間中以外はボタンランプが消灯される。この有効期間中は、互いに異なる演出モードを表す複数のモード画像が表示されており、演出モードを示す設定値によって最初に選択された状態にされるモード画像の種類が決まる。例えば、初当たりで大当たり図柄Cを引き当てた場合、グループAの演出モードを示す設定値が初期的に記憶設定されているので、有効期間の開始時に選択された状態で表示されるのは、夜モードを表すモード画像である(図8(A)及び(B)(a)参照)。
モード選択演出の有効期間中に演出ボタン26を1回操作すると、選択された状態のモード画像が切り替わる。例えば、大当たり図柄Cが初当たりの場合、モード選択演出の有効期間中における1回目の操作に応じて、新章モードを表すモード画像が選択された状態に切り替わる(図8(B)(b)参照)。そして、2回目の操作に応じて、夜モードを表すモード画像が選択された状態に切り替わる(図8(B)(c)参照)。モード選択演出の有効期間中に演出ボタン26が操作されない場合、選択された状態のモード画像が切り替わることがない。実行中の大当たり遊技終了直後の演出モードは、操作の有無に関わらず、モード選択演出の有効期間終了時(すなわちモード選択演出終了時)において選択された状態のモード画像が表す演出モードである。
本実施形態では、最終的に選択された状態のモード画像が表す演出モードに移行することが決定される。本実施形態では、モード選択演出の終了時に、移行先となる演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。この記憶処理により、大当たり遊技終了直後の時短状態用の演出モードが設定される。また、次回の大当たり遊技におけるモード選択演出の初期画面において最初に選択された状態にされる演出モードが設定される。
具体的には、例えば、大当たり図柄Cが初当たりの場合、モード選択演出の終了時に新章モードを表すモード画像が選択された状態である場合、新章モードに移行することが決定される(図8(B)(d)参照)。モード選択演出の終了時には、新章モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。これにより、新章モードに移行することが設定されると共に、次回の大当たり遊技におけるモード選択演出の初期画面は、グループBの演出モードを表すモード画像が選択された状態となる。
一方、モード選択演出の終了時に夜モードを表すモード画像が選択された状態である場合、夜モードに移行することが決定される。モード選択演出の終了時には、夜モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。これにより、夜モードに移行することが設定されると共に、次回の大当たり遊技におけるモード選択演出の初期画面は、グループAの演出モードを表すモード画像が選択された状態となる。
このように、本実施形態では、モード選択演出の終了時に何れのモード画像が選択された状態であっても移行先となる演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。これにより、モード選択演出によって、実行中の大当たり遊技終了直後の演出モードが決定できるのみならず、次回の大当たり遊技におけるモード選択演出の初期画面の状態を変更できる。本実施形態によれば、遊技者は、1回のモード選択演出により好みの演出モードを1回決定するだけで、その後は希望に沿った演出モードがモード選択演出の初期画面において選択された状態にできる。ここで、本実施形態では操作の有無に関わらず、モード選択演出の有効期間終了時に選択された状態の演出モードに移行する。このため、遊技者は、モード選択演出中に選択操作せずとも有効期間の経過を待てば希望に沿った演出モードに移行可能である。このように、本実施形態によれば、モード選択演出が実行される度に何度も演出モードを選択し直す煩わしさを解消できる。
なお、モード選択演出の有効期間中に、選択された状態のモード画像を演出キー27の左右キーで切り替えて演出ボタン26の操作によって演出モードを確定する構成でもよい。このような構成の場合、モード選択演出の有効期間中の演出ボタン26の操作に応じて、移行先の演出モードを確定すると共に有効期間を終了する。また、移行先の演出モードの確定に伴って、この演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。このような構成の場合、モード選択演出の有効期間中には、演出キー27を模した選択キー画像と、この画像の近くに表示される「選択」との文字と、演出ボタン26を模したボタン画像90と、「演出ボタンで決定」との文字と、有効期間の残り時間を示唆するゲージ画像91とが表示される。これらの画像は、演出ボタン26の操作により移行先の演出モードが確定したことに応じて消去される。
なお、モード選択演出の終了時には、個々の演出モードを示す設定値ではなく、演出モードのグループを示す設定値が記憶されてもよい。具体的には、例えば新章モードする場合、モード選択演出の終了時にグループBを示す設定値がサブRAM133に記憶される。
なお、演出制御基板130は、モード選択演出の終了時に、移行先の演出モードを示す設定値がサブRAM133に既に記憶されている設定値と同じグループの演出モードか否かを判定する処理を実行してもよい。そして、移行先の演出モードが記憶済みの設置値と同じグループの演出モードではない(すなわち異なるグループ)と判定された場合にのみ、移行先の演出モードを示す設定値をサブRAM133に記憶してもよい。
図9〜図11を参照して、初当たりから新章モードへの移行が確定するまでの具体例について説明する。図9は、初当たりにおいて大当たり図柄Cが停止表示されているときからモード選択演出が開始されるまでの具体例について説明するための説明図である。図10は、モード選択演出の具体例について説明するための説明図である。図11は、モード選択演出を介して新章モードに移行する具体例について説明するための説明図である。
図9(A)は、初当たりで大当たり図柄Cが停止表示したときの液晶画面5の様子を例示している。図9(A)では、大当たり図柄Cと同じ内容を報知するために、装飾図柄55として2を示す2図柄が3つ停止表示されており、青の第4図柄57が停止表示されている。このとき、小図柄56は、装飾図柄55と同じ組み合わせで停止表示されている。図9(A)の状態で図柄確定時間(例えば1秒)が経過するまで保たれた後、大当たり図柄Cに係る大当たり遊技が開始される。図9(B)は、大当たり遊技が開始したことを報知する大当たり用OP演出が実行されている様子を例示している。大当たり用OP演出は、今回の大当たり遊技の種類を示唆する文字を表示する演出であり、大当たり遊技開始時から1R目のラウンド遊技開始時まで実行される演出である。図9(B)では、大当たり図柄Cに係る大当たり遊技であることを示唆するために「ボーナス」との文字が表示されている。大当たり用OP演出の終盤には、遊技者に右打ちを指示する「右を狙ってね」との文字が液晶画面5に表示されたり、「右を狙ってね」との音声がスピーカ24から出力されたりする。
図9(C)は、1R目のラウンド遊技が開始されたときの様子を例示している。本実施形態では、大当たり図柄Cに係る大当たり遊技の場合、1R目のラウンド遊技時からモード選択演出で移行先の演出モードが確定するまでキャラDの動画が表示される(図9(C)〜図11(B)参照)。この動画は、その開始時から終了時まで、液晶画面5の上端と下端とにピンク色の帯を表示する。
図9(C)に例示するように、1R目のラウンド遊技開始時から液晶画面5の右端隅に「右打ち>>」との文字が表示される。「右打ち>>」との文字は、遊技者に右打ちを指示するためのものであり、大当たり遊技の種類に関わらず、大当たり遊技開始後からの1R目のラウンド遊技開始時から最終ラウンド遊技終了時まで継続して表示される。「右打ち>>」との文字は、ED期間の開始時に一旦消去され、時短状態が開始したときから非時短状態に転落するまで表示される。ED期間は、最終ラウンド遊技が終了したときからこの大当たり遊技が終了するときまでの期間である。
大当たり図柄B、C、E、及びFに係る大当たり遊技の場合、図9(C)に例示するように、1R目のラウンド遊技であることを報知する「ラウンド1」との文字が1R目のラウンド遊技開始時から表示される。「ラウンド1」との文字は、2R目のラウンド遊技が開始されるまで継続して表示されており、2R目のラウンド遊技開始時に「ラウンド2」との文字に更新される。その後、現在のラウンド数に対応して更新され続け、最終ラウンド遊技の終了時に消去される。
本実施形態では大当たり遊技の種類に関わらず、今までの大当たり遊技で得られた合計賞球数を示唆する「○○pt」との文字が1R目のラウンド遊技開始時から表示される。図9(C)は初当たりの1R目のラウンド遊技開始時なので、合計賞球数が0であることを示唆する「0pt」との文字が表示されている。合計賞球数はED期間の開始時に消去される。
本実施形態の大当たり遊技では、大当たりの種類に関わらず1R目のラウンド遊技開始時から所定時間(例えば10秒間)、楽曲の曲名が液晶画面5の右端に表示される。この楽曲は、大当たり図柄A及びD、並びに小当たり図柄1に係る大当たり遊技以外では、大当たり遊技開始後からの1R目のラウンド遊技開始時からED期間開始時までに亘ってスピーカ24から出力される。大当たり図柄A及びD、並びに小当たり図柄1に係る大当たり遊技では、1R目のラウンド遊技開始時から神ラッシュ又は悪魔ラッシュが終了するまでに亘って出力される。
図9(D)は、最終ラウンド遊技が終了する直前に、8R目であることを報知する「ラウンド8」との文字と、「右打ち>>」との文字と、合計賞球数「547pt」との文字が表示されている様子を例示している。また、図9(E)は、図9(D)の状態から「ラウンド8」との文字だけが最終ラウンド遊技の終了時に消去されたときの様子を例示している。
本実施形態では、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3に係る大当たり遊技におけるED期間の開始時から、モード選択演出が開始される(図9(F)参照)。図10及び図11では、初当たりであって且つ大当たり図柄Cである場合のモード選択演出を例示する。このときのモード選択演出は、実行中の大当たり遊技が終了した後の演出モードとして、夜モード及び新章モードから何れか1つを決定するために実行される。図10及び図11は初当たりの例なので、モード選択演出の初期画面において最初に選択された状態にされる演出モードは、グループAの夜モードである。
モード選択演出の開始(及びED期間の開始)に伴って、「モードを選んでね」との文字の表示が開始される。また、モード選択演出の開始に伴って、図10(A)〜(E)に例示するように夜モードを表す夜モード画像40と、新章モードを表す新章モード画像41との移動表示が開始される。この移動表示中は演出モードを選択できず、移動表示が完了したときから演出モードの選択が可能になる。図10(A)〜(E)に例示するように、夜モード画像40及び新章モード画像41は、モード選択演出の開始時から移動表示が完了したときまで暗い色合い(例えば、彩度が低い状態やグレースケール)で表示される。これにより、現在は演出モードを選択できず、これから演出モードを選択可能になることを示唆できる。
なお、モード画像はどのような方法で色合いを暗くしてもよい。例えば、半透明の黒色の画像を通して遊技者に見せることにより、モード画像の色合いを暗くしてもよい。具体的には、例えば、「モードを選んでね」との文字の後ろ側であって夜モード画像40及び新章モード画像41の手前側に、透過率が高く後ろが透けて見える黒色の画像を全面表示する。この黒色の画像は、モード選択演出開始時から、夜モード画像40及び新章モード画像41の移動表示が完了したときまで表示される。夜モード画像40及び新章モード画像41はこの黒色の画像を通して見えることにより、モード選択演出の開始時から移動表示が完了したときまで暗い色合いで表示されることになる。
本実施形態では、夜モード画像40及び新章モード画像41の移動表示中に以下のような演出表示が行われる。まずモード選択演出の開始に伴って、画面左上隅から夜モード画像40がキャラDの動画の手前側に重畳表示され始める。このとき、新章モード画像41はまだ表示が開始されていない。本実施形態では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によってモード選択演出が開始されたときに先に表示されるモード画像の種類が決まる。図10及び図11は初当たりの例なので、モード選択演出が開始されたときに最初に表示されるのはグループAの夜モードを表すモード画像である。
夜モード画像40の表示が開始されたのに続いて、新章モード画像41が、夜モード画像40と同様に画面左上隅から表示され始める(図10(A)参照)。新章モード画像41は、夜モード画像40と同様に、キャラDの動画の手前側に表示される。後から表示開始された新章モード画像41は、表示開始時から図10(E)のタイミングまでは夜モード画像40の手前側に表示される。そして、図10(E)のタイミングから図11(A)のタイミングまでは夜モード画像40の後ろ側に表示される。このように、本実施形態では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値と異なるグループのモード画像を、移動表示の途中まで表示優先度を高くして遊技者に見せることとしている。なお、モード画像の移動表示中は常に、設定値と同じグループのモード画像を設定値と異なるグループのモード画像よりも表示優先度を高くして表示してもよい。
ここで、本実施形態では、時短状態から非時短状態に転落してから所定回転目(例えば30回転目)までの第1特別図柄判定で大当たりとならなかった場合に、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値が、グループAの演出モードを示す設定値にリセットされる。上記所定回転目までに大当たりを引き当てた場合、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値がサブRAM133に残っている。このような場合、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値によってモード選択演出が開始されたときに先に表示されるモード画像の種類が決まる。例えば新章モードを示す設定値が残っている場合には、モード選択演出が開始されたときに先に新章モード画像41が表示される。なお、本実施形態では時短状態から非時短状態に転落してから所定回転目までの第1特別図柄判定で大当たりとならなかった場合に演出モードを示す設定値をリセットしたが、設定値をリセットする条件は他の条件でもよい。例えば、上記所定回転目以上のときに大当たりとなった場合に、グループAの演出モードを示す設定値にリセットされてもよい。また、時短状態から非時短状態に転落してから所定時間(例えば20分)以上が経過したときに大当たりとなった場合に、グループAの演出モードを示す設定値にリセットされてもよい。
なお、サブRAM133に記憶されている演出モードを示す設定値の種類に関わらず、夜モード画像40が新章モード画像41よりも先に表示が開始されてもよい。また、モード選択演出の開始に伴って、夜モード画像40及び新章モード画像41は同時に表示が開始されてもよいし、新章モード画像41が夜モード画像40よりも先に表示が開始されてもよい。
図10(A)〜(C)に例示するように、表示が開始された夜モード画像40は、次第に拡大しながら画面右上隅に向かって移動表示される。夜モード画像40は、画面右上隅まで移動表示すると、今度は画面左端に向かって次第に拡大しながら移動表示される(図10(D)参照)。画面左端まで移動表示された夜モード画像40は、左半分が見切れており右半分しか見えない状態になる。
図10(A)〜(C)に例示するように、表示が開始された新章モード画像41は、次第に拡大しながら画面中央まで移動表示される。新章モード画像41は、画面中央まで移動されると、今度は次第に縮小しながら画面右端まで移動表示され、夜モード画像40と横並びになる(図10(D)参照)。画面右端まで移動表示された新章モード画像41は、右半分が見切れており左半分しか見えない状態になる。ここまでの新章モード画像41の移動表示は、夜モード画像40の移動表示と同じ時間をかけて行われる。このため、夜モード画像40が画面左端に表示されるのと同時に、新章モード画像41が画面右端に表示され、これらが横並びになる。
夜モード画像40及び新章モード画像41は、図10(E)の状態から画面中央に向かって移動表示される。図10(F)に例示するように、夜モード画像40と新章モード画像41との距離が次第に縮まって、夜モード画像40の後ろ側に新章モード画像41の左端が重なる。このように、本実施形態では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によって、重なったときに手前側に表示される(すなわち、表示優先度が高い)モード画像の種類が決まる。
その後、夜モード画像40(及び新章モード画像41)の見切れていた部分が全て見えるようになると、夜モード画像40及び新章モード画像41が静止される。ここまでで夜モード画像40及び新章モード画像41の移動表示が完了する。移動完了時点では、夜モード画像40の方が新章モード画像41よりも大きく表示されている。このように、本実施形態では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によって、他のモード画像と比べて大きく表示されるモード画像の種類が決まる。
上述したように、本実施形態では、時短状態から非時短状態に転落してから所定回転目(例えば30回転目)までに大当たりを引き当てた場合、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値がサブRAM133に残っている。このような場合、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値によって、図10(F)の状態のときに手前側に大きく表示される(すなわち、表示優先度が高い)モード画像の種類が決まる。例えば、新章モードを示す設定値が残っている場合には、図10(F)の状態のときに新章モード画像41が夜モード画像40よりも手前側に大きく表示される。
図11(A)に例示するように、移動表示が完了したことに応じて、「モードを選んでね」との文字が消去される。これに伴って、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印(例えば「<< >>」のような画像)の表示が開始される。これらの画像は、選択された状態のモード画像が演出ボタン26の操作によって切り替わることを示唆するために表示される。本実施形態では、ボタン画像90の表示開始と同時に、演出ボタン26の有効期間が開始する。有効期間の残り時間は、ゲージ画像91によって示唆する。
ボタン画像90の表示が開始されるのと同時に、夜モード画像40の表示態様が明るい色合い(例えばフルカラー)に変化する(図11(A)参照)。これにより、現在夜モード画像40が選択された状態であることが示唆される。一方、新章モード画像41は、演出ボタン26が操作されることによって選択されない限り暗い色合い(例えばグレースケール)のままである。これにより、現在新章モード画像41が選択されていない状態であることが示唆される。このように、初当たりの場合はグループAの演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶されているため、モード選択演出では、夜モード画像40が最初に選択された状態の初期画面が表示される。
なお、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値がサブRAM133に残っている場合、前回の時短状態のときの演出モードを示す設定値によって、最初に選択された状態のモード画像の種類が決まる。例えば、新章モードを示す設定値が残っている場合には、新章モード画像41が最初に選択された状態の初期画面が表示される。
なお、ボタン画像90の表示が開始されるのと同時に、全てのモード画像が明るい色合いに変化してもよい。具体的には、夜モード画像40の表示態様が明るい色合いに変化すると共に、新章モード画像41の表示態様も明るい色合いに変化する。このように変化しても、夜モード画像40は、新章モード画像41よりも手前側に大きく表示されているため、現在選択されているのが夜モード画像40であることを示唆できる。
演出ボタン26が1回操作されると、夜モード画像40が選択された状態から新章モード画像41が選択された状態へと切り替わる(図11(A)から(B)の流れ)。本実施形態では、この1回目の操作に応じて夜モード画像40の表示態様が暗い色合いに変化すると共に、新章モード画像41が明るい色合いに変化する。また、この1回目の操作に応じて、夜モード画像40が次第に縮小しながら新章モード画像41の後ろ側へと移動表示すると共に、新章モード画像41が次第に拡大しながら夜モード画像40の手前側へと移動表示する。
モード選択演出の有効期間中に演出ボタン26に対して2回目の操作がされると、新章モード画像41が選択された状態から夜モード画像40が選択された状態へと切り替わる(図11(B)から(A)の流れ)。本実施形態では、この2回目の操作に応じて夜モード画像40の表示態様が明るい色合いに戻ると共に、新章モード画像41が暗い色合いに戻る。また、この2回目の操作に応じて、夜モード画像40が次第に拡大しながら新章モード画像41の手前側へと移動表示すると共に、新章モード画像41が次第に縮小しながら夜モード画像40の後ろ側へと移動表示する。ここで、図11(A)は有効期間開始時のゲージ画像91を表記している。2回目の操作に応じて夜モード画像40が選択された状態へと切り替わったときには、ゲージ画像91は、図11(B)に例示するゲージ画像91が示唆する残り時間よりも少ない残り時間を示唆した状態となる。
その後、予め定められた有効期間の終了時に、この時点で選択された状態のモード画像が表す演出モードへの移行が確定する。図11(C)は、有効期間終了時に新章モード画像41が選択された状態であり、新章モードへの移行が確定した例を示している。この例では、有効期間終了時に新章モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。この記憶処理により、実行中の大当たり遊技終了直後に新章モードで演出が制御される。そして、このときの新章モードにおいて小当たり又は大当たり(具体的には、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3)を引き当てた場合には、グループBの演出モードが選択された状態の初期画面のモード選択演出が、2回目の大当たり遊技中に実行される。このように、次のモード選択演出において新章モード(又はグループBのうち他の演出モード)を選択し直さなくてもグループBの演出モードが選択された状態になっているので、選択し直す煩わしさがない。
図11(C)及び(D)に例示するように、有効期間終了時から新章モード画像41が拡大を開始し、新章モード画像41が全画面表示される。夜モード画像40、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印、及びキャラDの動画は、有効期間終了時に消去される。
夜モード画像40が選択された状態のまま操作されることなく有効期間が終了する場合、又は、操作された結果夜モード画像40が選択された状態で有効期間が終了する場合、有効期間終了時に夜モードへの移行が確定する。このような場合、有効期間終了時に移行先が夜モードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。この記憶処理により、実行中の大当たり遊技終了直後に夜モードで演出が制御される。そして、このときの夜モードにおいて小当たり又は大当たり(具体的には、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3)を引き当てた場合には、グループAの演出モードが選択された状態のモード選択演出が、2回目の大当たり遊技中に実行される。このように、次のモード選択演出において夜モード(又はグループAのうち他の演出モード)を選択し直さなくてもグループAの演出モードが選択された状態になっているので、選択し直す煩わしさがない。
有効期間終了時に夜モードへの移行が確定する場合、有効期間終了時から夜モード画像40が拡大を開始し、夜モード画像40が全画面表示される。新章モード画像41、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印、及びキャラDの動画は、有効期間終了時に消去される。
新章モード画像41が全画面表示されてから所定時間(例えば7秒)経過時に、この新章モード画像41が消去される。これと共に、新章モードへの移行を報知する演出モードタイトルを表示する演出が開始される。この演出では、以下の演出表示が行われる。まず、舞台の幕を模した画像が画面全体に表示された状態となる。そして、舞台の幕が上がりきったことに応じて、「新章 バトル勝利でラッシュ突入」との文字が表示される(図11(E)及び(F)参照)。新章モードへの移行を報知する演出モードタイトルを表示する演出はED期間中に終了する。そして、このED期間中に新章モードの画面構成に切り替わり、ED期間の終了後に第2特別図柄の変動表示が開始されるのに伴って新章モードでの1回転目の変動演出が開始される(図11(G)及び(H)参照)。新章モードの画面構成については、図13を参照して後述する。
本実施形態では、新章モードへの移行を報知する演出モードタイトルを表示する演出中において舞台の幕が上がる途中で、注意喚起が表示される。この注意喚起は、初当たりのED期間中に表示される一方、2回目以降の大当たり遊技中には表示されない。また、この注意喚起は、演出モードタイトルよりも表示優先度が高く、演出モードタイトルを表示する演出が終了する前までに消去される。図11(E)は、遊技者に遊技にのめり込まないように注意を促す第1注意喚起と、プリペイドカードを取り忘れないように注意を促す第2注意喚起とが同時に表示開始される様子を例示している。なお、第1注意喚起の消去後に第2注意喚起の表示が開始されてもよいし、第2注意喚起の消去後に第1注意喚起の表示が開始されてもよい。
本実施形態のモード選択演出では2つの選択肢の中から1つの演出モードを選択する。なお、モード選択演出は、3つ以上の選択肢の中から1つの演出モードを選択する演出でもよい。このような構成の場合、選択された状態のモード画像が一番大きく表示されると共に、選択された状態のモード画像からの距離が遠いモード画像ほど小さくなるように各モード画像の大きさを異ならせてもよい。
3つ以上の選択肢の中から1つの演出モードを選択するモード選択演出の場合、各モード画像の並び順が予め定められていてもよい。このような構成において、モード選択演出の初期画面では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によって、設定値と同じグループのモード画像が中心となるように上記並び順が再編されてもよい。
本実施形態では、モード選択演出ではモード画像を横並びに表示する。なお、モード選択演出は、各モード画像が奥行き距離を有してもよい。このような構成の場合、選択されていない状態のモード画像は、選択された状態のモード画像よりも奥にあるように表示される。例えば、選択されていない状態のモード画像に対し、奥行き距離に応じたボケが付加されて表示される。一方、選択されている状態のモード画像はボケが付加されることなく表示される。モード選択演出の初期画面では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によって奥行き距離に応じたボケの有無が決定され、設定値と異なるグループのモード画像に対し、奥行き距離に応じたボケが付加されて表示される。
本実施形態のモード選択演出では、選択可能なモード画像が全て液晶画面5に表示されている。なお、モード選択演出では、選択可能なモード画像の一部が液晶画面5に表示されており、他部は非表示にされてもよい。具体的には、夜モード画像40が選択された状態であり新章モード画像41が選択されていない状態である場合、夜モード画像40は液晶画面5に表示され、新章モード画像41は非表示にされる。すなわち、モード選択演出の初期画面では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値によって表示か非表示かが決定され、設定値と異なるグループのモード画像が非表示にされる。このように非表示にされても、モード画像の移動表示中に選択可能なモード画像を遊技者に見せることが可能であるため、どのような演出モードに移行できるかを遊技者に認識させることが可能である。
[新章モードにおける1回転目および2回転目の変動演出について]
大当たり図柄Cを引き当てたことによって新章モードに移行した場合、1回転目および2回転目の第2特別図柄の変動表示中には、リーチ演出が行われることを期待させることによって小当たりを期待させる。リーチ演出は、変動演出のうち、左右の装飾図柄55が同じ図柄で仮停止表示された(すなわち、リーチが成立した)ときから、特別図柄判定の判定結果を報知する組み合わせで装飾図柄55(又は小図柄56)が仮停止表示されるまでの演出の総称である。仮停止表示は、装飾図柄55(又は小図柄56)の表示位置をほとんど変化させずに上下方向に揺れるように微動させたり、わずかな拡大と縮小とを繰り返させたりする表示態様である。リーチ演出は、小当たり(又は大当たり)の場合やハズレであって特別図柄の変動時間が相対的に長い場合に実行され易い。このため、リーチ演出は信頼度が相対的に高い演出であり、小当たり(又は大当たり)となることを期待させる演出である。
本実施形態では、新章モード(及び通常モード)で実行可能なリーチ演出の演出態様として、「ノーマルリーチ演出」、「SPリーチ演出」、及び「SPSPリーチ演出」がある。「ノーマルリーチ演出」は、例えば、リーチ成立状態の左右の装飾図柄55(以下、「リーチ図柄」と呼ぶ。)を液晶画面5の中央に大きく表示した状態で、真ん中の装飾図柄55を相対的に遅いスピードでスクロールする演出態様である。本実施形態では、ノーマルリーチ演出の開始時から左右の小図柄56がリーチ図柄と同じ組み合わせで仮停止表示されるが、真ん中の小図柄56は真ん中の装飾図柄55と異なり高速で変動表示される。ノーマルリーチ演出でハズレとなる場合、ノーマルリーチ演出終盤にリーチ図柄と真ん中の装飾図柄55とがハズレを示す組み合わせ(以下、「リーチハズレ目」と呼ぶ。)で停止表示する。一方、ノーマルリーチ演出で小当たり(又は大当たり)となる場合、ノーマルリーチ演出終盤に小当たり(又は大当たり)を示す組み合わせで装飾図柄55が停止表示される。
ノーマルリーチ演出は、例えば、小当たり(又は大当たり)用変動パターンに対応して実行されるときがあるものの、特別図柄の変動時間が相対的に短いハズレ用変動パターンに対応して実行され易い。このため、ノーマルリーチ演出は、信頼度が相対的に低いリーチ演出であるといえる(例えば信頼度0.01%)。
「SPリーチ演出」は、例えば、キャラA〜Dのうち何れかのキャラクタのSPSPリーチ演出に発展することを期待させる演出である。装飾図柄55は、SPリーチ演出開始時から当落報知直前まで非表示にされる。SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展する場合、SPリーチ演出では、キャラA〜Dが表示された後に何れか1人だけが表示されている状態となる演出が実行される。SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展せずにハズレる場合、SPリーチ演出では、SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展する場合と同様の流れでキャラA〜Dが表示された後、全キャラクタが消えてから装飾図柄55がリーチハズレ目で停止表示する。SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展せずに小当たり(又は大当たり)となる場合、SPリーチ演出では、SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展せずにハズレる場合と同様の流れでキャラA〜Dが消えてから小当たり(又は大当たり)を示す組み合わせで装飾図柄55が停止表示される。
SPリーチ演出は、例えば、小当たり(又は大当たり)用変動パターンに対応して実行されるときがあるものの、特別図柄の変動時間が少し長めのハズレ用変動パターンに対応して実行され易い。このため、SPリーチ演出は、信頼度が中程度のリーチ演出であるといえる(例えば信頼度7%)。本実施形態では、SPリーチ演出には、リーチ成立からノーマルリーチ演出を介して発展する場合と、リーチ成立からノーマルリーチ演出を介さずに直発展する場合とがある。
「SPSPリーチ演出」は、キャラA〜Dのうち何れか1人が敵と戦う演出である。小当たり(又は大当たり)の場合、SPSPリーチ演出終盤で敵が敗北してから小当たり(又は大当たり)を示す組み合わせで装飾図柄55が停止表示される。ハズレの場合、SPSPリーチ演出終盤で敵が勝利してから装飾図柄55がリーチハズレ目で停止表示する。
SPSPリーチ演出は、ノーマルリーチ演出及びSPリーチ演出よりも長い時間をかけて行われる演出であり、特別図柄の変動時間が相対的に長い変動パターンに対応して実行され易い。SPSPリーチ演出は、特別図柄判定の結果がハズレの場合は実行され難く、特別図柄判定の結果が小当たり(又は大当たり)の場合は実行され易い。SPSPリーチ演出の信頼度は比較的高く、例えば40%である。このため、SPSPリーチ演出は、ノーマルリーチ演出及びSPリーチ演出よりも信頼度が高いリーチ演出である。本実施形態では、SPSPリーチ演出には、リーチ成立からノーマルリーチ演出を介して発展する場合と、リーチ成立からSPリーチ演出を介して発展する場合と、リーチ成立からノーマルリーチ演出を介してSPリーチ演出から発展する場合と、リーチ成立からノーマルリーチ演出もSPリーチ演出も介さずに直発展する場合とがある。
ここで、本実施形態では、小当たりとなることを期待させるために、SPリーチ演出中の所定タイミング(例えば、キャラA〜Dの全キャラクタが表示された状態のとき)、及び、SPSPリーチ演出中の所定タイミング(例えば、SSPリーチ演出終盤の操作促進演出(後述する)直前)のうちの何れかで、群演出が実行される場合がある。本実施形態では、SPリーチ演出中またはSPSPリーチ演出中の群演出(以下、「リーチ演出中の群演出」と呼ぶ。)は、上述した再抽選演出中の群演出と同一の表示態様となっている。
リーチ演出中の群演出は、遊技制御基板100から変動開始コマンド(後述する)を受信したときに演出制御基板130による乱数抽選により実行の有無が決定される。リーチ演出中の群演出は、小当たり用変動パターン又はハズレ用変動パターンが選択された場合に実行される。小当たりである場合の方がハズレの場合よりもリーチ演出中に群演出が実行され易い。ここで、図12は、リーチ演出中の群演出の実行割合について説明するための説明図である。本実施形態では小当たりである場合、リーチ演出中に群演出が実行される割合は25%であり、リーチ演出中に群演出が実行されない割合は75%である(図12参照)。ハズレである場合、リーチ演出中に群演出が実行される割合は10%であり、リーチ演出中に群演出が実行されない割合は90%である。
本実施形態では、SPリーチ演出中に群演出が実行された場合、SPリーチ演出からSPSPリーチ演出に発展する場合と、SPSPリーチ演出に発展することなくSPリーチ演出で当落が報知される場合とがある。上述したように、本実施形態ではSPSPリーチ演出もハズレの場合は実行され難く、小当たりの場合は実行され易い。このため、結果として、SPリーチ演出中に群演出が実行されたときの方が実行されないときよりも、SPSPリーチ演出に発展する可能性が高いことを間接的に示唆可能である。
なお、SPリーチ演出中に群演出が実行されない場合でもSPSPリーチ演出が実行される場合があることを前提として、SPリーチ演出中の群演出によって、SPSPリーチ演出に発展するのが確定であることを示唆してもよい。
なお、本実施形態では群演出の演出態様が1種類である場合について説明するが、群演出には複数の演出態様があってもよい。例えば、群演出には、大量のキャラAが画面を横切る演出態様A、大量のキャラBが画面を横切る演出態様B、大量のキャラCが画面を横切る演出態様C、及び複数種類のキャラクタ(例えばキャラA〜C)が大量に画面を横切る演出態様Dがある。リーチ演出中の群演出は、小当たりである場合に演出態様A〜Dの順に選択される割合が高く、演出態様Dは小当たりである場合に限って実行される。再抽選演出中の群演出は、演出態様A〜Dの何れが実行されても小当たり図柄1であることが確定する。このため、再抽選演出中の群演出の演出態様としては、演出態様A〜Dが均等な割合で選択される。なお、再抽選演出中の群演出として、演出態様A〜Dの順に選択される割合が高くてもよい。
なお、小当たりとなることを期待させるために実行される群演出の実行タイミングはリーチ演出中に限らない。例えば、リーチが成立したことに応じて群演出を実行することにより、小当たりとなる割合が高いことを示唆してもよい。
以下、図13〜図15を参照して、大当たり図柄Cを引き当てることにより移行した新章モードにおける、1回転目の変動演出の具体例について説明する。図13は、新章モードにおける1回転目の変動表示が開始されたときの様子について説明するための説明図である。図14は、図13に続くリーチ演出について説明するための説明図である。図15は、再抽選演出について説明するための説明図である。
図9〜図11を参照して上述したように、大当たり図柄Cを引き当ててこの大当たり図柄Cに係る大当たり遊技のED期間中に移行先の演出モードが新章モードに決定された場合、上記ED期間終盤で新章モードの画面構成になる。図13(A)は上記ED期間終盤で新章モードの画面構成になったときの様子を例示しており、図11(G)のときの液晶画面5の様子に対応している。図13(A)のとき、装飾図柄55(及び小図柄56)は、前回停止表示されたのと同じ組み合わせ(具体的には、小当たり図柄3であることを示唆する組み合わせ)で停止表示される。第4図柄は、前回青で停止表示されたときから図13(A)のときに亘って停止表示され続けている。装飾図柄55、小図柄56、及び第4図柄は、新章モードにおける1回転目の第2特別図柄の変動表示が開始されるのと同時に変動表示が開始される。ここで、図13(A)のとき、第1特別図柄判定および第2特別図柄判定の保留数は0である。
本実施形態では新章モードに移行した場合、3回転目の第2特別図柄判定に係る特別図柄がハズレ図柄で停止表示すると、時短状態での制御が終了してしまう。そこで、本実施形態では、第2特別図柄判定の残り回数が減っていく様子を強調して遊技者にドキドキ感を与えるために、3回転目の第2特別図柄判定が実行されるまでの第2特別図柄判定の回数を示唆する数字が液晶画面5の左上隅に表示される。図13(A)の状態では、まだED期間中であるため1回転目の第2特別図柄判定が実行されていない。このため、液晶画面5の左上隅には、「2.0」との数字が表示されている。この数字は、1回転目の変動表示を「1.9」から「1.0」で表し、2回転目の変動表示を「0.9」から「0.0」で表す。上記数字は、図13(B)に例示するように、1回転目の第2特別図柄の変動表示が開始されたことに応じて「2.0」から「1.9」に変化し、その後、所定時間毎(例えば5秒毎)に0.1ずつ減っていく(図13(C)参照)。本実施形態では、1回転目の変動表示において上記数字が「1.8」から「1.0」であるとき、及び2回転目の変動表示において上記数字が「0.8」から「0.0」であるときにリーチが成立する可能性がある。本実施形態では、上記数字が0.1減る毎に、リーチが成立するか否かを煽るリーチ成立煽り演出が実行される。リーチ成立煽り演出の結果、リーチが成立した場合はカウントダウンが停止して上記数字が非表示にされると共に、リーチ演出に発展する。このときのリーチ演出後の流れについては、図14〜図16を参照して後述する。リーチ成立煽り演出の結果、リーチが成立しない場合は上記数字のカウントダウンが継続される。そして、カウントダウンで上記数字が「1.0」(なお、2回転目の変動表示中においては「0.0」)になったときのリーチ成立煽り演出でリーチが成立しない場合は上記数字が変化せずに装飾図柄55(及び小図柄56)がハズレを示す組み合わせで仮停止表示してから停止表示する。
本実施形態では、1回転目の変動表示中において上記数字が「1.0」になるタイミングが、当該アイコン53の表示位置によって示唆される。本実施形態の当該アイコン53は、第2特別図柄の変動表示が開始されるのに伴って液晶画面5の左下隅に表示される画像である。当該アイコン53は、背景ゲージ60の手前側で少しずつ右方向に移動表示し続け、1回転目の変動表示中において上記数字が「1.0」になるタイミングで液晶画面5の右下隅まで移動表示される(図13(B)〜(D)参照)。背景ゲージ60は、上記タイミングまでの残り時間を示唆する画像であり、当該アイコン53と同時に表示が開始される画像である。背景ゲージ60は、表示開始時には全体が黒色で表示された後、左から右に向かって白色に変化していき全体が白色になる(図13(B)参照)。そして、当該アイコン53が通過したところから順に再び黒色に変化していき、当該アイコン53が画面右下隅に到着する直前に全体が黒色に変化する(図13(C)参照)。本実施形態の当該アイコン53及び背景ゲージ60は、新章モードにおいて1回転目の第2特別図柄の変動表示中と同様に2回転目の第2特別図柄の変動表示中にも表示される。2回転目の変動表示中には、当該アイコン53が液晶画面5の左下隅から右下隅まで移動表示を完了するタイミングによって上記数字が「0.0」になるタイミングが示唆される。ここで、図13(C)は、当該アイコン53の移動表示中に第2特別図柄判定の保留数が2になったことにより当該アイコン53及び背景ゲージ60の手前側に保留アイコン54が2つ表示された様子を例示している。内部に1と表記された保留アイコン541が最初の保留に対応しており、内部に2と表記された保留アイコン542が最先の保留に対応している。
本実施形態では、リーチが成立するか否かが報知されるまでに、キャラクタとセリフとを表示するセリフ演出が実行される(図13(B)及び(C)参照)。セリフ演出は、画面左上隅に表示された数字が0.1減ったとき毎にキャラクタ等を表示し、このキャラクタとセリフとの種類によって信頼度を示唆する。セリフ演出で表示されるキャラクタにはキャラA〜Cがあり、キャラA、B、Cの順に小当たりである場合に表示され易くハズレである場合に表示され難い。
図13(D)に例示するように液晶画面5の左上隅の数字が「1.0」である場合、リーチ成立煽り演出の結果リーチが不成立となると、その直後にハズレを示す組み合わせで3つの装飾図柄55が仮停止表示してから停止表示する(図13(D)参照)。このように停止表示されるのと同時に、当該アイコン53及び背景ゲージ60が画面の下へと退避することにより消去される。そして、新章モードにおける2回転目の第2特別図柄の変動表示が開始されるのに伴って、新たな当該アイコン53及び背景ゲージ60がいきなり表示される(又は、画面の下から順次現れる)と共に、画面左上隅に表示された数字が「1.0」から「0.9」に変化する。この2回転目の変動表示中には1回転目と同じような変動演出が実行される。
図13(F)に例示するように、リーチ成立煽り演出の結果リーチが成立すると、リーチ演出が実行される。図13(F)及び(G)の例では、液晶画面5の左上隅の数字が「1.0」であるときにリーチが成立し、SPリーチ演出が開始される様子を例示しているが、変動パターンの種類によってはノーマルリーチ演出が開始される場合またはSPSPリーチ演出が開始される場合がある。本実施形態では、リーチが成立したことに応じて、装飾図柄55、当該アイコン53、背景ゲージ60、画面左上隅に表示された「1.0」との数字、及び合計賞球数が非表示にされる。
図14(A)は、SPリーチ演出中に群演出が実行される様子を例示している。SPリーチ演出中の群演出の有無に関わらず、SPリーチ演出後にはSPSPリーチ演出に発展する場合(図14(A)から(B)の流れ)と、SPSPリーチ演出に発展せずに第2特別図柄判定の判定結果が報知される場合(図14(A)から(C)の流れ)とがある。
図14(B)は、キャラCが敵と戦うSPSPリーチ演出が開始される様子を例示している。図14(C)に例示するように、SPSPリーチ演出終盤には操作促進演出が実行される。操作促進演出では、ボタン画像90及びゲージ画像91を予め定められた有効期間に亘って表示することによって、遊技者に演出ボタン26の操作を促す。操作促進演出の有効期間は、モード選択演出の有効期間と異なり、1回の操作に応じて終了する。有効期間中に操作がなかった場合は、予め定められた有効期間終了タイミング(例えば、有効期間開始時から3秒経過時)で有効期間が終了する。
ハズレの場合、有効期間の終了に応じてキャラCが敵に負ける演出が開始される。この演出の開始と同時に、図14(E)に例示するように、小図柄56がリーチハズレ目で仮停止表示する。その後、このとき仮停止表示された小図柄56と同じ組み合わせで装飾図柄55(及び小図柄56)が仮停止表示された状態の新章モードの通常画面に復帰する。新章モードの通常画面は、新章モードでの遊技の大半において液晶画面5に表示される画面であり、例えば図13(B)〜(F)に例示するような画面構成である。具体的な演出態様については図16を参照して後述するが、通常画面に復帰した後には、ハズレが報知される場合と小当たり図柄3であることが報知される場合とがある。ハズレが報知される場合、第2特別図柄がハズレ図柄で停止表示されるのに伴って、装飾図柄55(及び小図柄56)が仮停止表示されたのと同じ組み合わせで停止表示すると共に白の第4図柄57が停止表示される。小当たり図柄3であることが報知される場合、小当たり図柄3が停止表示されるのに伴って、装飾図柄55(及び小図柄56)及び第4図柄57が小当たり図柄3を示す組み合わせ(図5(E)参照)で停止表示される。
小当たり図柄2又は3である場合、SPSPリーチ演出終盤における操作促進演出の有効期間の終了に応じて、キャラCが敵に勝つ演出が開始される。この演出の開始と同時に、図14(G)に例示するように、演出役物7が初期位置から進出位置に動作すると共に、小図柄56が例えば2図柄揃いで仮停止表示される。その後、図14(H)に例示するように、演出役物7の退避が完了すると同時に装飾図柄55が小図柄56と同じ組み合わせで仮停止表示される。この仮停止表示に続いて、再抽選演出が開始される。
なお、小当たり図柄1である場合、小当たり図柄2又は3である場合と同様にキャラCが敵に勝つ演出が開始されると共に、小図柄56が「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いで仮停止される。その後、装飾図柄55が小図柄56と同じ組み合わせで仮停止表示される。そして、再抽選演出が実行されることなく、第2特別図柄の停止表示に伴って装飾図柄55及び小図柄56はそのままの組み合わせで停止表示される。
図15(A)及び(B)に例示するように、再抽選演出の開始に伴って、装飾図柄55及び小図柄56が再変動を開始する。これと共に、装飾図柄55が次第に縮小表示されながら液晶画面5の上方へ移動表示される。図15(C)は、この再変動中(すなわち再抽選演出中)に群演出が実行される様子を例示している。このときの群演出によって、小当たり図柄2であり、装飾図柄55(及び小図柄56)が昇格することが示唆される。このときの再抽選演出後には7図柄揃いが仮停止表示した後に、小当たり図柄2の停止表示に伴って装飾図柄55及び小図柄56が停止表示される(図15(D)参照)。この停止表示後に実行される小当たり図柄2に係る小当たり遊技中および大当たり遊技中の演出については、図29及び図30を参照して後述する。
図15(F)は、再抽選演出中に群演出が実行されないときの様子を例示している。このときの再抽選演出後には、装飾図柄55(及び小図柄56)が昇格しない場合と昇格する場合とがあり、前者の方が後者より割合が高い(図15(G)及び(D)参照)。昇格しない場合、再抽選演出後には例えば2図柄揃いが仮停止表示した後に、小当たり図柄3の停止表示に伴って装飾図柄55及び小図柄56が停止表示される(図15(H)参照)。この停止表示後に実行される小当たり図柄3に係る小当たり遊技中および大当たり遊技中には、基本的には図29及び図30を参照して後述する小当たり図柄2が停止表示された場合の演出と同様の演出が実行される。
図16は、図14(E)に続く演出の具体例について説明するための説明図である。SPSPリーチ演出終盤における操作促進演出の有効期間の終了に応じて小図柄56がリーチハズレ目で仮停止表示した場合、図16(A)に例示するように新章モードの通常画面に復帰する。このときの通常画面では、液晶画面5の左上隅に1回転目の変動表示であることを表す「1.0」との数字と、画面右下隅に移動表示を完了した当該アイコン53と、全体が黒色の背景ゲージ60とが表示される。このとき、図14(E)のときに仮停止表示された小図柄56と同じ組み合わせで装飾図柄55が仮停止表示されている。本実施形態では、このような状態に続いてハズレが報知される場合と小当たり図柄3であることが報知される場合とがある。ハズレが報知される場合、第2特別図柄がハズレ図柄で停止表示されるのに伴って、装飾図柄55(及び小図柄56)が仮停止表示されたのと同じ組み合わせで停止表示すると共に白の第4図柄57が停止表示される(図16(A)から(B)の流れ)。
ここで、本実施形態では、小当たり図柄3であることを報知するために、リーチハズレ目の仮停止表示中に、群演出が実行される場合がある(図16(D)参照)。本実施形態では、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出は、上述したリーチ演出中および再抽選演出中の群演出と同一の表示態様となっている。図16(D)に例示するように、本実施形態では群演出に係るキャラクタの後ろ側に、当該アイコン53、背景ゲージ60、及び保留アイコン54が表示されるが、これらの画像の手前側に群演出に係るキャラクタが表示されてもよい。
リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出は、遊技制御基板100から変動開始コマンド(後述する)を受信したときに演出制御基板130による乱数抽選により実行の有無が決定される。リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出は、小当たり図柄3である場合に実行され、他の特別図柄である場合に実行されない。本実施形態では、小当たり図柄3である場合、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出が実行される割合は20%であり、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出が実行されない割合は80%である。すなわち、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出が実行されたか否かに関わらず、リーチハズレ目の仮停止表示後に小当たり図柄3が停止表示される場合がある。本実施形態では、ハズレ、小当たり図柄1又は2、並びに大当たりである場合、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出が実行されない。
本実施形態では、リーチハズレ目の仮停止表示後に小当たり図柄3が停止表示される場合、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出の有無に関わらず、大当たりが復活したように見せる復活演出が実行される。図16(E)に例示するように、復活演出の開始時には、リーチハズレ目が仮停止表示された通常画面全体にひびが入る演出が開始される。これに続いて、復活演出では、図16(F)に例示するように、例えば2図柄揃いが仮停止表示した後に、小当たり図柄3の停止表示に伴って装飾図柄55、小図柄56、及び紫の第4図柄57が停止表示される(図16(F)参照)。この停止表示後に実行される小当たり図柄3に係る小当たり遊技中および大当たり遊技中には、基本的には図29及び図30を参照して後述する小当たり図柄2が停止表示された場合の演出と同様の演出が実行される。
なお、小当たり図柄3であることを報知するために実行される群演出の実行タイミングは通常画面に復帰した後に限らない。例えば、通常画面に復帰する直前(例えば、図14(E)に例示する状態のとき)に群演出を実行することにより、小当たり図柄3となることを報知してもよい。
なお、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出は、小当たり図柄1であることを報知するために実行されてもよい。このような場合、リーチハズレ目の仮停止表示中の群演出は、小当たり図柄1である場合に実行され、他の特別図柄である場合に実行されない。このときのリーチハズレ目の仮停止表示中の群演出後には、復活演出を介して、装飾図柄55、小図柄56、及び緑の第4図柄57が小当たり図柄1を示す組み合わせで停止表示される。
[新章モードにおける3回転目の変動演出について]
新章モードにおける1回転目および2回転目でハズレとなった場合、3回転目の第2特別図柄の変動表示が開始される。新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中には、この変動表示に係る第2特別図柄判定と、保留されている4回の第2特別図柄判定との合計5回で、どうにか小当たりとなるかを分かり易く報知するバトル演出が実行される。このバトル演出は、上記5回の第2特別図柄判定の判定結果を一連の流れで報知する変動演出である。上記5回の第2特別図柄判定の判定結果に小当たり(又は大当たり)があれば、3回転目の変動表示中に小当たり(又は大当たり)であることが示唆される。小当たり(又は大当たり)であることを示唆する演出としては、バトル演出でキャラA〜Dの何れかが敵に勝つ演出や、演出役物7が初期位置から進出位置まで動作する演出が行われる。一方、上記5回の第2特別図柄判定の判定結果が全てハズレであれば、3回転目の変動表示中にはキャラA〜Dが敵に5回負けるバトル演出が実行される。そして、このバトル演出が終了した後から7回転目の第2特別図柄の変動表示が終了するまでに亘って、一連の流れでハズレを報知するシャッター閉鎖演出(後述する)が行われる。
本実施形態では、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示用に専用の変動パターンが1種類予め用意されている。このため、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中における第2特別図柄判定の保留がいくつであっても、同じ時間をかけた変動演出が実行される。上記変動パターンは比較的変動時間が長い。このため、3回転目の第2特別図柄の変動表示中に第2特別図柄判定の保留を十分4つ貯めることが可能である。
新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中は、バトル演出でキャラA〜Dが敵に勝つ期待感を効果的に高めるために、バトル演出の前にカウントダウン演出、キャラストック演出、及びバトル発展演出をこの順で実行する。バトル発展演出は、バトル演出に発展することを示唆する演出である。以下、図17〜図28を参照しつつ、上記各演出について説明する。
カウントダウン演出は、所定のタイマ値(例えば5)をカウントダウンしていき、その値が0になることを示唆する。カウントダウン演出の終了に応じてキャラストック演出が開始される。これにより、カウントダウン演出によって、時短状態における最後の第2特別図柄の変動表示が始まってしまった危機感と、間もなくキャラストック演出が開始されることに対する遊技者の緊張感とを高めていく。なお、本実施形態では、カウントダウン演出がタイマ値をカウントダウンしていく演出である場合について説明するが、カウントダウン演出は、途中でタイマ値をカウントアップしてから再びカウントダウンする演出パターンでもよいし、タイマ値を初期値から所定の値(例えば10)までカウントアップしたことに応じて終了する演出パターンでもよい。
図17は、カウントダウン演出の具体例について説明するための説明図である。図17(A)に例示するように、本実施形態のカウントダウン演出は、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示開始時から開始される。カウントダウン演出開始時には、装飾図柄55が非表示にされると共に、黒色の画像を全画面でいきなり表示する演出が開始される。図17(A)に例示するように、新章モードにおける3回目の変動表示中には、新章モードにおける1回転目および2回転目の変動表示中と異なり、当該アイコン53、背景ゲージ60、及び保留アイコン54が表示されない。
図17(B)に例示するように、変動表示開始時から所定時間(例えば1秒)が経過したタイミングで、変動表示開始時から表示されていた黒色の画像が消去される。これと共に、タイマ値の初期値(本実施形態では5)の表示が開始される。本実施形態のタイマ値は、装飾図柄55に見えてしまわないように装飾図柄55と異なる表示態様となっている(図17(B)及び(D)参照)。これにより、図17(B)及び(D)に例示するように同じタイマ値が同時に複数表示された場合に、図柄揃いの装飾図柄55が表示されたと遊技者が勘違いすることを抑制可能である。5のタイマ値が所定時間(例えば0.5秒間)表示された後、このタイマ値が消去されると共に図17(C)に例示するキャラクタ画像が、5のタイマ値の表示時間と同じ時間をかけて全画面で表示される。このように、本実施形態では、タイマ値が所定の値(例えば2)になるまでは、タイマ値の表示とキャラクタ画像の表示とが一定間隔(例えば0.5秒間隔)に交互に行われる。そして、タイマ値が所定の値になった後はタイマ値が表示されることなく一定間隔毎(例えば0.5秒間毎)に異なるキャラクタ画像の表示が行われる。このため、本実施形態のカウントダウン演出は、5の表示(図17(B)参照)→キャラクタ画像の表示(図17(C)参照)→4の表示→キャラクタ画像の表示→3の表示→キャラクタ画像の表示→2の表示(図17(D)参照)→キャラクタ画像の表示→キャラクタ画像の表示(図17(E)参照)、という流れになる。各タイミングで表示されるキャラクタ画像は互いに異なる画像である。このように、本実施形態のカウントダウン演出ではタイマ値が0になることを示唆する演出態様を、タイマ値とキャラクタ画像との組み合わせの切り換えから、キャラクタ画像だけの切り換えに変化させる。これにより、キャラストック演出が差し迫っていることをより効果的に強調できる。
上述したように、バトル演出では5回分(具体的には、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示、及び保留されている4回の第2特別図柄判定)の結果を1つの演出で見せる。このため、バトル演出開始前に、第2特別図柄判定が保留されていることが必要である。本実施形態では、第2特別図柄判定の保留を貯めることを促す演出として、カウントダウン演出終了時(すなわち、新章モードにおける3回転目の変動表示中)に図17(F)に例示する画面を表示する。この画面では、液晶画面5の右上隅に常時表示されている「右打ち」との表示に追加して、新たに「右打ち」との文字と「少女をためろ!」との文字が表示される。
本実施形態では、新章モードにおける3回転目の変動表示が終了するまで時短状態に制御されるため、遊技者が右打ちしていれば容易に第2始動口12に遊技球が入賞する。このため、図17(F)に例示する画面の表示が開始される前に第2特別図柄判定の保留が貯まっている場合がある。現在の保留数は、液晶画面5の左端に小さく表示される保留数字を見ることにより認識できる。ここで、本実施形態では、特別図柄判定の保留数に関わらず図17(F)に例示する画面が表示される。本実施形態では、第2特別図柄判定の保留がなく、且つ図17(F)に例示する画面を見た後に遊技者が右打ちしても第2特別図柄判定の保留を十分4つ貯められるように、図17(F)に例示する画面の表示時間と、キャラストック演出の実行にかかる時間とが相対的に長く設定されている。後に詳述するが、図17(F)に例示する画面の消去後に開始されるキャラストック演出では、1つの第2特別図柄判定の保留に対応して、少女のパネル画像が1つ表示される。このため、図17(F)に例示する画面では、第2特別図柄判定の保留をためさせることを「少女をためろ!」との文字で示唆する。本実施形態では、後述するキャラストック演出中に第2始動口12への遊技球の入賞に応じて少女(具体的にはキャラA〜Cの何れか)を表すパネル画像が表示される。これを見た遊技者は、図17(F)に例示する画面における「少女」が第2特別図柄判定の保留を指していたことを認識可能である。本実施形態では、「少女を」との文字が表示されてから「ためろ!」との文字が遅れて表示される。
図17(F)に示す画面の表示開始時から所定時間(例えば4秒)が経過したことに応じて、キャラストック演出が開始される。キャラストック演出は、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中に実行される。本実施形態では、キャラストック演出中に最大5つのパネル画像が表示される。1つ目に表示されるパネル画像は、今回の変動表示に対応するパネル画像である。2つ目以降のパネル画像は、第2特別図柄判定の保留に対応するパネル画像である。本実施形態では、第2特別図柄判定の保留の上限数が4つであるため、第2特別図柄判定の保留に対応するパネル画像の数は最大4つとなる。
本実施形態では、パネル画像の表示が開始されたときのパネル画像の表示態様は3種類ある。1つのパネル画像に対して、キャラA〜Cのうち何れか1人が表されている。本実施形態では、キャラA、B、Cの順に信頼度が高い。パネル画像は、その表示中に異なるキャラクタのパネル画像に昇格する場合がある。具体的には、キャラAのパネル画像は、キャラAのパネル画像のまま表示が継続される場合と、キャラB〜Dのうち何れかのパネル画像に昇格する場合とがある。ここで、キャラDは、キャラA〜Cよりも信頼度が高い。また、キャラBのパネル画像は、キャラBのパネル画像のまま表示が継続される場合と、キャラC又はDのうち何れかのパネル画像に昇格する場合とがある。キャラBのパネル画像からキャラAのパネル画像に変わることはない。また、キャラCのパネル画像は、キャラCのパネル画像のまま表示が継続される場合と、キャラDのパネル画像に昇格する場合とがある。キャラCのパネル画像からキャラA又はBのパネル画像に変わることはない。本実施形態では、パネル画像の昇格可能なタイミングが予め3つ用意されており、パネル画像は最大2回昇格する可能性がある。
上記より、パネル画像には最終的に、キャラA〜Dのうちの何れか1人が表示される。バトル演出では、パネル画像に表示されたキャラクタが敵と戦う演出が繰り広げられる。基本的に小当たりの場合はキャラA〜Dが敵に勝ち、ハズレの場合はキャラA〜Dが敵に負ける。後に詳述するが、キャラストック演出によって複数のパネル画像が表示された場合は、パネル画像が表示された順に、パネル画像に表示されたキャラクタが敵と戦う。本実施形態では最大5つのパネル画像が表示されるため、バトル演出では最大5回の戦いが繰り広げられて勝敗が最大5回報知される。
ここで、パネル画像を表示する演出パターンについて図18を参照しつつ説明する。図18は、キャラストック演出でパネル画像を表示する演出パターンについて説明するための説明図である。この演出パターンで決定されるものは、パネル画像で最初に表示されるキャラクタ、昇格後のキャラクタ、及び昇格タイミング(1〜3)である。演出パターン1〜3は、パネル画像が昇格しない演出パターンである。演出パターン1〜3のパネル画像は、それぞれキャラA、キャラB、キャラCである。演出パターン4〜27は、パネル画像が昇格する演出パターンである。例えば、演出パターン4は、パネル画像の表示が開始されたときにキャラAであり、昇格タイミング1でキャラAからキャラBに昇格する演出パターンである。また、演出パターン18は、パネル画像の表示が開始されたときにキャラBであり、昇格タイミング1でキャラBからキャラDに昇格する演出パターンである。
ここで、本実施形態では、昇格タイミング1〜3において、パネル画像の昇格を期待させる昇格示唆演出が実行される。昇格示唆演出に続いて昇格する場合(すなわち昇格成功)と、昇格しない場合(すなわち昇格失敗)とがある。
具体的には、パネル画像は、バトル発展演出が開始されるまでの昇格タイミング1〜3で昇格する。昇格タイミング1は、後述する「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に1つ目の遊技球が入賞したことに応じて到来する。また、昇格タイミング2は、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に2つ目の遊技球が入賞したことに応じて到来する。また、昇格タイミング3は、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に3つ目の遊技球が入賞したことに応じて到来する。このため、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に4つ目以降の遊技球が入賞したことに応じては、昇格示唆演出が実行される一方、パネル画像が昇格することがない。
上述したように、本実施形態の昇格タイミングは予め決まったタイミングで到来するものでなく、遊技球の入賞状況に応じた不特定なタイミングで到来する。仮に、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に遊技球が入賞しなかった場合、パネル画像の昇格が決まっていても実際には昇格しないままになる。すなわち、本実施形態では、パネル画像は第2始動口12に遊技球が入賞したことを条件に昇格する。これにより、「フルチャージ」の文字が表示された後も右打ちを継続させる動機づけを遊技者に与えることが可能である。
図18のテーブルで特徴的なことは、以下の通りである。小当たりの場合、キャラA〜Cの順に決定割合が高く、ハズレの場合、キャラA〜Cの順に決定割合が低くなるように予め設定されている。これにより、キャラA〜Cの順に信頼度が高くできる。小当たりの場合の方がハズレの場合よりも、キャラDの決定割合が高い。小当たりの場合、遅く昇格する方が早く昇格するよりも決定割合が高く、ハズレの場合、遅く昇格する方が早く昇格するよりも決定割合が低い。これにより、遅く昇格する方が早く昇格するよりも小当たりを期待できるので、いつまでも昇格しなくても小当たりに対する期待感を持ち続けることが可能である。小当たりか否かに関わらず、キャラAからキャラCに昇格する割合は、キャラBからキャラCに昇格する割合よりも高い。また、小当たりか否かに関わらず、キャラAからキャラDに昇格する割合は、キャラBからキャラDに昇格する割合とほぼ同じである。これにより、パネル画像の表示開始時にキャラAである場合に、パネル画像の表示開始時にキャラBが表示された場合と同じくらいキャラC又はDに昇格することを期待できる。
ここで、図19(A)を参照してキャラストック演出(1人目)処理について説明する。図19は、遊技制御基板100から変動開始コマンド又は保留コマンド(何れも後述する)を受信したことに応じて演出制御基板130において実行される、キャラストック演出の演出パターンを決定する処理について説明するための説明図である。図19(A)に例示するキャラストック演出(1人目)処理は、キャラストック演出における1つ目のパネル画像を表示する演出パターンを決定する処理である。上述したように、1つ目のパネル画像は、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示に対応する。例えば、演出制御基板130は、大当たり図柄Cの停止表示後から3回目の第2特別図柄の変動表示が開始される場合に、キャラストック演出(1人目)処理を実行する(図19のステップS1514)。この処理におけるキャラ抽選処理(図19(A)のT11)により、今回の変動表示が小当たりであるかハズレであるかに基づいて、1つ目のパネル画像の演出パターンが、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示開始時に決定される。このように、1つ目のパネル画像の態様は変動表示開始時に決定されるが、実際に1つ目のパネル画像が表示されるのはその変動表示中においてキャラストック演出が開始してからである。本実施形態では、今回の第2特別図柄判定の判定結果が小当たりであるかハズレであるかによって異なる演出テーブルを参照して(図18参照)、キャラ抽選処理(図19(A)のT11参照)を実行する。キャラ抽選処理では、小当たりである場合もハズレである場合も、27種類の演出パターン(図18参照)の中から、変動表示開始時に取得されたキャラ抽選処理用の乱数の値と一致する判定値が予め割り当てられた演出パターンが1つ決定される。この決定された演出パターンによって、1つ目のパネル画像の表示態様が決まる。
図19(A)T12に例示するように、演出制御基板130は、キャラ抽選処理に続いて復活抽選処理を実行する。上述したように、バトル演出では、パネル画像に最終的に表示されたキャラクタが敵と戦う。図18に例示する演出パターン1〜27に従った場合、小当たりの場合はキャラA〜Dが敵に勝つ変動演出が実行される。本実施形態では、バトル演出の興趣を高めるために、小当たりの場合であってもハズレの場合と同様にキャラA〜Dが敵に負け続ける演出を行ってから、小当たりが復活したように見せる復活演出を行う場合があるようにしている。このような復活演出は、復活抽選処理に当選した場合に実行される。復活抽選処理では、変動表示開始時に取得された復活抽選処理用の乱数を用いた乱数抽選で、小当たりである場合は3%の割合で復活演出を実行し、97%の割合で復活演出を実行しないことを決定する。ハズレである場合は100%の割合で復活演出を実行しないことを決定する。以上の処理により、キャラストック演出以降の変動演出の内容が決まる。
なお、キャラストック演出(1人目)処理の実行タイミングは上記に限らない。例えば、キャラストック演出(1人目)処理の実行タイミングは、カウントダウン演出開始時でもよいし、キャラストック演出開始時でもよい。このような場合、演出制御基板130は、例えば、変動開始コマンド(後述する)を受信したことに応じてこの変動開始コマンドを解析し、解析結果をサブRAM133に保持する。そして、キャラストック演出(1人目)処理の実行タイミングに、上記解析結果(具体的には、小当たりであるかハズレであるか)に基づいて乱数抽選する。また、演出制御基板130に代えて画像音響制御基板140においてキャラストック演出(1人目)処理を実行してもよい。
次に、キャラストック演出(2〜5人目)処理について説明する。キャラストック演出(2〜5人目)処理は、キャラストック演出における2〜5つ目のパネル画像を表示する演出パターンを決定する処理である。上述したように、2つ目以降のパネル画像は、第2特別図柄判定の保留に対応する。例えば、演出制御基板130は、大当たり図柄Cの停止表示後から1〜3回目の第2特別図柄の変動表示中である場合にキャラストック演出(2〜5人目)処理を実行する(図18のステップS1315)。キャラストック演出(2〜5人目)処理では、まず、第2始動口12に遊技球が入賞したか否かを判定する(図19(B)のT21)。本実施形態の保留コマンド(後述する)には、第1特別図柄判定の保留に係る保留コマンドと、第2特別図柄判定の保留に係る保留コマンドとがある。本実施形態では、例えば、演出制御基板130は、遊技制御基板100から第2特別図柄判定の保留に係る保留コマンドを受信した場合、図19(B)のT21の処理でYESと判定する。ここで、保留コマンドは、小当たりであるかハズレであるかを示す事前判定情報を含む情報である。上記保留コマンドが受信されていない場合はNOと判定されてキャラストック演出(2〜5人目)処理が終了する。
演出制御基板130は、図19(B)のT21の処理でYESと判定した場合、キャラ抽選処理を実行する(図19(B)のT22)。この処理により、本実施形態では、保留コマンドに含まれる事前判定情報(具体的には、小当たりであるかハズレであるか)に基づいて、2つ目以降のパネル画像の演出パターンが、第2始動口12に遊技球が入賞したとき(すなわち保留発生時)に決定される。図19(B)のT22のキャラ抽選処理では、小当たりである場合もハズレである場合も、27種類の演出パターン(図18参照)の中から、保留コマンド受信時に取得されたキャラ抽選処理用の乱数の値と一致する判定値が予め割り当てられた演出パターンが1つ決定される。現在の第2特別図柄判定の保留数が1であれば2つ目のパネル画像の演出パターンが決定され、現在の第2特別図柄判定の保留数が2であれば3つ目のパネル画像の演出パターンが決定される。また、現在の第2特別図柄判定の保留数が3であれば4つ目のパネル画像の演出パターンが決定され、現在の第2特別図柄判定の保留数が4であれば5つ目のパネル画像の演出パターンが決定される。
図19(B)のT23に例示するように、演出制御基板130は、キャラ抽選処理に続いて復活抽選処理を実行する。このときの復活抽選処理では、保留コマンド受信時に取得された復活抽選処理用の乱数を用いた乱数抽選で、小当たりである場合は3%の割合で復活演出を実行し、97%の割合で復活演出を実行しないことを決定する。ハズレである場合は100%の割合で復活演出を実行しないことを決定する。以上の処理により、キャラストック演出以降の変動演出の内容が決まる。
本実施形態では、図19(A)及び(B)の処理が実行される度に復活抽選処理が実行される。このため、例えば、図19(B)のT23の処理が実行された時点ですでに図19(A)のT12の処理によって復活演出を実行することが決定されている場合がある。このため、図19(B)のT23の処理は、未だ復活演出を実行することが決定されていない場合にのみ実行されるようにしてもよい。
ここで、図19(A)の処理と、図19(B)T22の処理との結果、昇格前および昇格後の何れかのタイミングで1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタになる演出パターンが決定される場合がある。そこで、本実施形態では、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果、又は第2特別図柄判定の保留に小当たりがある場合と小当たりがない場合とで異なる処理を行う。具体的には、小当たりがある場合、1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタになる演出パターンが決定された場合であってもこの決定された演出パターンでバトル演出を行う。一方、小当たりがない場合、5つ目のパネル画像の演出パターンを決定するときに、1〜5つ目のパネル画像が何れかのタイミングで同じキャラクタのパネル画像になる演出パターンを決定不可能に禁則をかける。すなわち、小当たりがない場合、5つ目のパネル画像の演出パターンは、1〜5つ目のパネル画像が何れのタイミングでも同じキャラクタのパネル画像にならない演出パターンの中から決定される。上記のような禁則があることにより、1〜5つ目のパネル画像が全て同じであることによって、小当たりであることを示唆可能になる。
ここで、小当たりの場合において、図19(A)の処理と、図19(B)T22の処理との結果、1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタであったにも関わらず、昇格によって異なるキャラクタのパネル画像が混ざった状態になる場合がある。これにより、キャラストック演出中において1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタになった期間でだけ小当たりであることを示唆可能になる。一例として、キャラストック演出中において1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタになったときから小当たりを示唆する発光パターンで枠ランプ37を発光させる。これにより、パネル画像が全て同じであるときはパネル画像と枠ランプ37との態様によって小当たりを示唆可能であり、パネル画像が昇格した後は枠ランプ37の態様によって小当たりを示唆可能である。
なお、小当たりの場合において、1〜5つ目のパネル画像が全て同じ状態になった後は何れのパネル画像も昇格しないように、演出パターンを書き換える処理を行ってもよい。これにより、キャラストック演出中において1〜5つ目のパネル画像が全て同じキャラクタになったとき以降はずっとパネル画像の態様によって小当たりであることを示唆可能になる。
なお、昇格示唆演出が実行されるタイミング(すなわち、昇格タイミング1〜3の到来タイミング)は、上述したタイミングに限らない。例えば、昇格示唆演出中に第2始動口12に遊技球が入賞した場合はこの入賞に応じて昇格示唆演出を実行せず、実行中の昇格示唆演出に係る昇格成功または昇格失敗が完了してからの第2始動口12への遊技球の入賞に応じて昇格示唆演出が実行されてもよい。また、昇格示唆演出は、第2始動口12への遊技球の入賞毎に実行されなくてもよい。例えば、昇格タイミング1は、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に2つ目の遊技球が入賞したことに応じて到来し、昇格タイミング2は、「フルチャージ」の文字が表示されてから第2始動口12に4つ目の遊技球が入賞したことに応じて到来してもよい。このような場合、「フルチャージ」の文字が表示されてからの第2始動口12への遊技球の入賞に応じてパネル画像が必ず昇格しない昇格示唆演出と、パネル画像が昇格する可能性がある昇格示唆演出とを設けることが可能である。なお、昇格示唆演出は、予め定められた時間の到来により実行されてもよく、例えば、「フルチャージ」の文字が表示されてから2秒経過する毎に実行されてもよい。
図20〜図28を参照して、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中における、キャラストック演出開始時以降の変動演出の具体例について説明する。この例では、キャラストック演出開始時に第2特別図柄判定の保留が0であり、キャラストック演出中に第2特別図柄判定の保留が4になる場合を例示している。図20は、4回の第2特別図柄判定の保留が貯まるまでのキャラストック演出の具体例について説明するための説明図である。図21は、4回の第2特別図柄判定の保留が貯まった後のキャラストック演出の具体例について説明するための説明図である。図22は、図21に続くキャラストック演出の具体例について説明するための説明図である。図23は、バトル発展演出開始時の具体例について説明するための説明図である。図25は、バトル発展演出からバトル演出に発展する具体例について説明するための説明図である。図26は、図25に続くバトル演出の具体例について説明するための説明図である。図27は、図26に続くバトル演出の具体例について説明するための説明図である。図28は、キャラA〜Dが敵に5回負けるバトル演出が実行された後の変動演出の流れについて説明するための説明図である。
図20(A)は、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中にキャラストック演出が開始されたときの様子を例示している。本実施形態では、キャラストック演出開始時からバトル発展演出開始時までの時間が予め20秒間に決められている。キャラストック演出開始時からバトル発展演出開始時までの時間が相対的に長く設定されているため、キャラストック演出が開始してから遊技者が右打ちしても第2特別図柄判定の保留を十分4つ貯められる。液晶画面5の中央上部には、バトル発展演出開始時までの残り時間を示唆する数字が表示される。図20(A)はキャラストック演出開始時なので、残り時間を表す数字として初期値である「20.00」が表示されている。残り時間は時間の経過に伴って減っていく。残り時間が「00.00」になるまでの20秒間の間に、最大5つのパネル画像を表示可能であり、パネル画像が昇格可能である。ここで、バトル発展演出以後も新章モードにおける3回転目の第2特別図柄の変動表示中であるため、第2始動口12への遊技球の入賞に応じて第2特別図柄判定を新たに保留可能である。しかしながら、本実施形態では、残り時間が「00.00」になった後は、新たに第2特別図柄判定の保留が発生してもこれに応じて新たなパネル画像が表示されることがない。
本実施形態では、キャラストック演出開始時からバトル演出開始直前までに亘って、液晶画面5が5つの表示領域81a〜85aに区画されている(図20(A)〜図25(A)参照)。図20(A)に例示するように、上記5つの表示領域81a〜85aの内部には、それぞれ1〜5の数字が表記されている。各表示領域に対して、パネル画像が1つずつ手前側に表示される。内部に1と表記された表示領域81aには、1つ目のパネル画像が表示され、内部に2と表記された表示領域82aには、2つ目のパネル画像が表示され、内部に3と表記された表示領域83aには、3つ目のパネル画像が表示される。また、内部に4と表記された表示領域84aには、4つ目のパネル画像が表示され、内部に5及び「フルチャージ」との文字が表記された表示領域85aには、5つ目のパネル画像が表示される。
ここで、本実施形態では、各パネル画像が表示される前に遊技球を模した遊技球画像が移動表示される。各遊技球画像の表示開始時から移動表示が完了して消去されるまでの時間は0.5秒間である。遊技球画像は、第2始動口12の位置を示唆する表示位置(具体的には、液晶画面5の右下隅)から画面中央に向かって移動表示される。(図20(B)参照)。遊技球画像を移動表示してからパネル画像を表示することにより、第2始動口12への遊技球の入賞とパネル画像の表示とが密接に関係していることを示唆する。
図20(B)及び(C)に例示するように、本実施形態では、遊技球画像がキャラストック演出開始時から表示され、1つ目のパネル画像がキャラストック演出開始時から0.5秒後に表示が開始される。この例では1つ目のパネル画像としてキャラBのパネル画像が表示されている。なお、キャラストック演出が開始されてから第2始動口12に1つ目の遊技球が入賞したことに応じて、1つ目のパネル画像に係る遊技球画像が表示されてから1つ目のパネル画像が表示されてもよい。
2つ目以降のパネル画像については、キャラストック演出中に第2始動口12に遊技球が入賞したことによって第2特別図柄判定の保留が発生した場合は、この入賞に応じて遊技球画像が表示されてからパネル画像が表示される(図20(C)及び(D)参照)。図20(C)は、第2始動口12に遊技球が入賞したことによって第2特別図柄判定の保留数が1になり、この入賞に応じて2つ目のパネル画像に係る遊技球画像が表示されている様子を例示している。
本実施形態では、キャラストック演出開始時までにすでに第2特別図柄判定の保留がある場合は、保留数分のパネル画像が、1つ目のパネル画像が表示された直後に順次表示される。ここで、本実施形態では、前のパネル画像の表示が完了してから1秒経過するまでは、次のパネル画像に係る遊技球画像の表示は開始されない。すなわち、キャラストック演出開始時までに第2特別図柄判定の保留が複数ある場合、又はパネル画像の表示が完了するまでに第2特別図柄判定の保留が発生した場合であっても、前のパネル画像の表示が完了してから1秒経過したときに、次のパネル画像の表示が開始される。これにより、各パネル画像を遊技者が認識し易くすることが可能である。例えば、図20(D)は、2つ目のパネル画像の表示が完了するまでに第2特別図柄判定の保留数が4になり、2つ目のパネル画像の表示が完了してから1秒経過したことに応じて3つ目のパネル画像に係る遊技球画像が表示されている様子を例示している。この例では2つ目のパネル画像としてキャラAのパネル画像が表示されている。
図20(E)は、5つ目のパネル画像の表示が完了したときの様子を例示している。この例では3つ目のパネル画像としてキャラAのパネル画像が、4つ目および5つ目のパネル画像としてキャラBのパネル画像が、それぞれ表示されている。図20(F)に例示するように、パネル画像が最大数である5つ表示されたことに応じて「フルチャージ」との文字が表示される。これにより、第2特別図柄判定の保留数が上限数まで貯まったことを示唆可能である。上述したように、本実施形態では、遊技球画像の表示開始時から消去時(すなわち移動表示完了時)までが0.5秒間であり、この遊技球画像の消去に伴ってパネル画像の表示が開始される。このときのパネル画像の表示開始時から1秒が経過するまでは次のパネル画像に係る遊技球画像の表示がされない。このため、1枚のパネル画像の表示が完了するまでに1.5秒間かかる。よって、5つのパネル画像が表示されることに応じて「フルチャージ」との文字が表示されるまでの時間は、最短でもキャラストック演出の開始時から7.5秒後である。
なお、キャラストック演出開始時までに第2特別図柄判定の保留が複数ある場合や、パネルの表示が完了するまでに第2特別図柄判定の保留が発生した場合、前のパネル画像の表示が完了する前に、次のパネル画像の表示が開始されてもよい。
図21(A)に例示するように、「フルチャージ」との文字が表示されたことに応じて、パネル画像が昇格可能なキャラ昇格可能期間が開始される。本実施形態では、キャラ昇格可能期間の開始を報知する演出として、「まだまだ」との文字が表示される(図21(A)参照)。「まだまだ」との文字は、キャラ昇格可能期間の開始時から所定時間(例えば0.5秒間)表示される。本実施形態では、キャラ昇格可能期間は、画面中央上部の残り時間が「00.00」になるまでの期間である。図21(B)に例示するように、キャラ昇格可能期間中であっても第2始動口12への遊技球の入賞がなければパネル画像は昇格せず、昇格を期待させる昇格示唆演出も実行されない。本実施形態では、「まだまだ」との文字の表示中に第2始動口12に遊技球が入賞しても昇格示唆演出が実行されない。なお、「まだまだ」との文字の表示中に第2始動口12に遊技球が入賞したときに昇格示唆演出が開始されてもよい。このような構成の場合、昇格示唆演出が開始されることによって表示される遊技球画像は、「まだまだ」との文字よりも優先して手前側に重畳表示される。なお、「まだまだ」との文字は、上記遊技球画像よりも優先して手前側に重畳表示されてもよい。
図21(C)は、「フルチャージ」との文字が表示されてから第2始動口12に1つ目の遊技球が入賞したときに昇格示唆演出が開始されたときの様子を例示している。図21(C)に例示するように、本実施形態では、昇格示唆演出開始時には、パネル画像が表示される直前と同様に遊技球画像が所定時間(例えば、0.5秒)表示される。続いて昇格示唆演出では、図21(D)に例示するように、パネル画像および画面中央上部の残り時間が表示されていない表示領域が発光する。続いて昇格示唆演出では、図21(E)に例示するように、全てのパネル画像が発光する。このとき、図21(D)のときに発光していた部分は発光していない(又はあまり発光していない)。
ここで、本実施形態では、「フルチャージ」との文字が表示されてから第2始動口12に1つ目の遊技球が入賞したことに応じて昇格タイミング1が到来する。このため、図21(C)〜(E)に例示する状態に続いて、少なくとも1つ以上のパネル画像の昇格が成功する場合と(図22(A)参照)、パネル画像が全く昇格しない場合(すなわち昇格失敗)とがある(図22(D)参照)。昇格するか否かは、図19に例示する処理によって現在の変動表示の開始時または第2特別図柄判定の保留発生時に決まっている。
図22(A)に例示するように、昇格成功の場合、昇格後のパネル画像の表示が開始されるのと同時に、この昇格後のパネル画像の手前側に「アップ↑」との文字が表示される。「アップ↑」との文字により昇格成功したことを認識できるものの、昇格後のパネル画像が「アップ↑」との文字で隠れるため、何れのキャラクタに昇格したかが見難くなる。これにより、何れのキャラクタに昇格したのかドキドキ感を与えることが可能である。図22(B)に例示するように、「アップ↑」との文字が所定時間後(本実施形態では1秒後)に消去されると、昇格後のパネル画像をはっきりと見ることができるようになる。本実施形態では、1回の昇格示唆演出の開始時から、この昇格示唆演出の結果としての昇格後のパネル画像をはっきりと見ることができるようになるまで2秒かかる。図22の例では、1つのパネル画像が昇格した場合について説明するが、図19に例示する処理によって決まった演出パターン(図18参照)によっては、全てのパネル画像が同時に昇格する場合もある。
図22(C)に例示するように、昇格失敗の場合、何れのパネル画像も変化せず、「アップ↑」との文字が表示されない。本実施形態では、昇格失敗である場合、1回の昇格示唆演出はその開始時から1秒間で終了する。昇格成功の場合、又は昇格失敗の場合、その後に昇格タイミング2及び3が到来したときはパネル画像が昇格する可能性がある(図22(D)参照)。一方、昇格タイミング2及び3が到来しなかったとき(すなわち、キャラ昇格可能期間中に第2始動口12に遊技球が入賞しなかったとき)は、パネル画像は昇格しない。その後、キャラ昇格可能期間の終了に応じて、バトル発展演出を介してバトル演出に発展する。このバトル演出では、表示された5つのパネル画像のキャラクタ達が、パネル画像が表示された順に1人ずつ敵と戦うことになる。
図23(A)は、図22(B)の状態からパネル画像が昇格せずにキャラ昇格可能期間が終了したときの様子を例示している。キャラ昇格可能期間の終了に応じて開始されるバトル発展演出では、図23(B)〜図25(B)に例示する演出が実行される。具体的には、図23(B)に例示するように、バトル発展演出開始時には、各パネル画像が表すキャラクタと同じキャラクタのキャラアイコン81〜85が表示領域81a〜85aの手前側に重畳表示される。キャラアイコン81〜85は各パネル画像を用いて導出され、キャラアイコン81〜85の表示が開始されたのと同時に、各パネル画像は消去される。バトル演出中はキャラアイコン81〜85によって敵と戦うキャラクタの種類が示唆される。図23(B)に例示するように、キャラアイコン81〜85は、空になった5つの表示領域81a〜85aの手前側に表示されることになる。本実施形態では、キャラアイコン81〜85の枠の色がキャラクタの種類によって異なる。具体的には、枠の色は、キャラA〜Cである場合は白であり、キャラDである場合は赤である。なお、バトル演出中にパネル画像を表示することによって敵と戦うキャラクタの種類を示唆する構成でもよく、この場合、キャラアイコン81〜85は表示しない。
図23(B)に続いて、図23(C)に例示するように、キャラアイコン81〜85が、表示領域81a〜85aから表示領域81b〜85bに向かって次第に縮小しながら移動表示を開始する。ここで、図24は、バトル演出中のキャラアイコン81〜85の表示領域81b〜85bについて説明するための説明図である。図24(A)に例示するように、本実施形態では、バトル発展演出開始時からバトル演出終了時までに亘って、液晶画面5に表示領域81a〜85aが設けられる。表示領域81b〜85bに対しては、キャラアイコン81〜85が1つずつ表示される。キャラアイコン81〜85が表示された表示領域81b〜85b以外の表示領域を用いて、バトル発展演出およびバトル演出が実行される。
図24(B)に例示するように、表示領域81bには、1戦目のバトルで敵と戦うキャラクタ(すなわちキャラアイコン81)が表示され、表示領域82bには、2戦目のバトルで敵と戦うキャラクタ(すなわちキャラアイコン82)が表示され、表示領域83bには、3戦目のバトルで敵と戦うキャラクタ(すなわちキャラアイコン83)が表示される。また、表示領域84bには、4戦目のバトルで敵と戦うキャラクタ(すなわちキャラアイコン84)が表示され、表示領域85bには、5戦目のバトルで敵と戦うキャラクタ(すなわちキャラアイコン85)が表示される。バトルでキャラクタが敵に敗北すると、表示中のキャラアイコンが表示領域81b側に1つシフトされる。
ここで、図24(B)ではキャラストック演出終了時に第2特別図柄判定の保留が4つあるために5つのキャラアイコンが表示される場合について例示する。キャラストック演出終了時に第2特別図柄判定の保留が4つよりも少ない場合は、5つよりも少ないキャラアイコンが表示されることになる。例えば、キャラストック演出終了時に第2特別図柄判定の保留が2つである場合は、表示領域81bにキャラアイコン81が表示され、表示領域82bにキャラアイコン82が表示され、表示領域83bにキャラアイコン83が表示される。そして、表示領域84b及び85bにはキャラアイコンが表示されない。本実施形態では、第2特別図柄判定の保留数に関わらず最後のバトルの開始時期が同じになるように、第2特別図柄判定の保留数に応じて1戦目の開始時期が前後する構成である。このため、第2特別図柄判定の保留が2つの場合における1戦目のバトルの開始時期は、第2特別図柄判定の保留が4つの場合における3戦目のバトルの開始時期と対応する。
本実施形態では、バトル演出にて敵と戦う最先のキャラクタを分かり易く示唆するために、最先のキャラアイコンは他のキャラアイコンに比べて大きく表示される。具体的には、図24(B)に例示するように、バトル演出で最も早く敵と戦うキャラアイコン81がキャラアイコン82〜85よりも大きく表示される。
本実施形態では、バトル発展演出の開始に応じてキャラアイコン81〜85が、パネル画像が表示された順番に表示領域81b〜85bに向かって順次移動表示を開始する。このため、1つ目のパネル画像を用いて導出されたキャラアイコン81が最も早く移動表示を開始し、5つ目のパネル画像を用いて導出されたキャラアイコン85が最も遅く移動表示を開始する。図23(C)は、キャラアイコン81が表示領域81aから表示領域81bに向かって移動表示している様子を例示している。本実施形態では、移動表示している様子を分かり易くするために、移動表示中はキャラアイコン81〜85の順に表示優先度が低くなるように設定されている。このため、移動表示中のキャラアイコン81の後ろ側には、いまだ移動表示を開始していないキャラアイコン85が重畳表示される(図23(C)参照)。本実施形態では、キャラアイコン81の移動表示開始時から、バトル演出が開始されることを示唆する「バトルスタート」との文字が液晶画面5の左側から中央に向かって次第に拡大されながら移動表示される(図23(C)〜図25(A)参照)。
図23(D)は、キャラアイコン81が表示領域81bに移動表示を完了したときを例示しており、キャラアイコン81の後ろ側にいまだ移動表示を開始していないキャラアイコン85が重畳表示されている様子を例示している。このとき、キャラアイコン82は、表示領域82aから表示領域82bに向かって移動表示している。また、キャラアイコン83は、表示領域83aから表示領域83bに向かって移動表示を開始している。
図23(E)は、キャラアイコン82が表示領域82bに移動表示を完了したときの様子を例示している。このとき、キャラアイコン83は、表示領域83aから表示領域83bに向かって移動表示しており、キャラアイコン84は、表示領域84aから表示領域84bに向かって移動表示している。また、キャラアイコン85は、表示領域85aから表示領域85bに向かって移動表示を開始している。なお、図23〜図27では、図面を見易くする目的で表示領域82b〜85bに表示されたキャラアイコン82〜85としてキャラクタの種類を表すアルファベットだけ表記する。表示領域82b〜85bに実際に表示されるのは、図24(B)に例示したのと同様にキャラクタを表したキャラアイコン81〜85である。
図25(A)は、キャラアイコン81〜85の移動表示が完了した状態を例示している。図25(B)は、バトル発展演出が終了する直前に、新章モードに係る演出のもととなる劇場版アニメのタイトルが表示される様子を例示している。図25(C)に例示するように、バトル演出の開始に伴ってまず敵が表示される。その後、図25(D)に例示するように、1戦目の開始時には、バトルの開始を示唆するカットイン画像86が表示される。カットイン画像86は、最先のキャラアイコンが表すキャラクタの顔を表示する画像である。本実施形態では、カットイン画像86の表示が開始されるのに伴って最先のキャラアイコンが暗い色合いに変化されてそのまま消去される(図25(D)及び(E)参照)。
図25(E)に例示するように、カットイン画像86の消去後には、カットイン画像86で表示されたキャラクタ(この例ではキャラB)と敵とが押し合う押し合い演出が開始される。本実施形態では、押し合い演出中に操作促進演出が開始される。図25(F)に例示するように、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果が小当たり図柄2又は3である場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に勝利し、1〜6、8、9図柄揃いのうち何れかの態様で小図柄56が仮停止表示される。これと同時に、演出役物7が初期位置から進出位置に動作される。小当たり図柄2である場合は、仮停止表示後の再抽選演出を介して「神」との文字を重畳表示しない7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される(図25(G)参照)。一方、小当たり図柄3である場合は、再抽選演出を介して、上記仮停止表示時の小図柄56の組み合わせと同じ組み合わせで装飾図柄55及び小図柄56が停止表示される(図25(G)参照)。
図25(H)に例示するように、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果が小当たり図柄1である場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に勝利し、「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が仮停止表示後に停止表示される。
新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果がハズレである場合、又は小当たりであって復活演出の実行が決定されている場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に敗北する(図25(I)参照)。この場合、図26(A)に例示するように、操作に応じて1戦目の敗北を示唆する演出が開始される。この演出では、キャラアイコン82〜85以外の表示領域において暗くノイズがかった敵が表示される。図26(B)に例示するように、1戦目の敗北を示唆する演出中に2戦目の準備が開始される。2戦目の準備開始時には、最先のキャラアイコン82が拡大表示されると共に下側に移動表示される。これに伴って、キャラアイコン83〜85が下側に移動表示される。
その後、図26(C)に例示するように、1戦目の敗北を示唆する演出が終了すると共に「残り4回」との文字が表示される。これにより、残り4回の第2特別図柄判定で小当たりを狙うことが示唆される。図26(D)に例示するように、2戦目の開始時には、1戦目の開始時と同様にカットイン画像86が表示される。この例では、カットイン画像86によって、最先のキャラアイコン82が表すキャラAの顔が表示されている。その後、1戦目と同様の流れで2戦目の押し合い演出中に操作促進演出が開始される。
図26(F)に例示するように、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄3である場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に勝利し、左右の小図柄56が1〜6、8、9図柄であり、真ん中の小図柄56がVの文字で仮停止表示される。この組み合わせは、ハズレを示す組み合わせであり、保留内の小当たりを示唆する組み合わせとして機能する。この小図柄56の仮停止表示と同時に、演出役物7が初期位置から進出位置に動作される。演出役物7の退避完了に伴って液晶画面5には「おめでとう」との文字が表示される。これに伴って、仮停止表示していた小図柄56がそのままの組み合わせで停止表示される(図26(G)参照)。このとき、第4図柄57が白の図柄で停止表示される。これにより、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果がハズレであったことが報知される。上記「おめでとう」との文字の表示中において、第2特別図柄の次変動表示の開始に伴って小図柄56が変動表示を開始する(図26(H)参照)。そして、装飾図柄55(及び小図柄56)が例えば2図柄揃いで仮停止表示した後、再抽選演出が実行される。その後、第2特別図柄が小当たり図柄3で停止表示されるのと同時に、再抽選演出実行前と同じ組み合わせの装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される(図26(I)参照)。このとき、第4図柄57が紫の図柄で停止表示される。なお、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄2である場合は、再抽選演出を介して「神」との文字を重畳表示しない7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される。また、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄1である場合は、再抽選演出が実行されることなく「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される。
図示は省略しているが、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄1の場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に勝利し、図26(F)〜(H)までと同様の流れで新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果がハズレであったことが報知される。その次変動において第2特別図柄が小当たり1で停止表示されるのと同時に、「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される。
第2特別図柄判定の最先の保留がハズレである場合、又は小当たりであって復活演出の実行が決定されている場合、操作促進演出中の操作に応じて敵に敗北する(図26(J)参照)。この場合、図27(A)に例示するように、操作に応じて2戦目の敗北を示唆する演出が開始される。図27(A)は、キャラアイコン83〜85以外の表示領域において暗くノイズがかった敵が表示される。図27(B)に例示するように、2戦目の敗北を示唆する演出中に3戦目の準備が開始される。3戦目の準備開始時には、最先のキャラアイコン82が拡大表示されると共に下側に移動表示される。これに伴って、キャラアイコン84及び85が下側に移動表示される。
その後、図27(C)に例示するように、2戦目の敗北を示唆する演出が終了すると共に「残り3回」との文字が表示される。これにより、残り3回の第2特別図柄判定で小当たりを狙うことが示唆される。その後、例えば、1戦目および2戦目と同様の流れで3戦目および4戦目で敗北した場合、5戦目が開始される。5戦目では、1〜4戦目と同様に押し合い演出が実行され、この押し合い演出中に1〜4戦目と同様に操作促進演出が開始される。操作促進演出中の操作に応じて5戦目の敗北を報知する演出が開始される場合、この演出の開始と同時に小図柄56がリーチハズレ目で仮停止表示される(図27(E)参照)。その後、5戦目の敗北が報知する演出に係る画像の手前側に、液晶画面5の左右両端から画面中央に向かって覆うようにシャッターを模したシャッター画像が移動表示するバトル終了示唆演出が実行される。本実施形態では、バトル終了示唆演出中において、演出ボタン26の連打を促す操作促進演出が開始される。この操作促進演出中の操作に応じて、左右のシャッター画像が開くことを期待させるようにガタガタ動きながら間隔が広くなる(図27(F)参照)。
新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果、又は第2特別図柄判定の保留の中に小当たりがある場合、バトル終了示唆演出中における操作促進演出中の操作に応じてシャッター画像が開き切る演出が実行される。例えば、最先の保留が小当たり図柄3である場合について説明する。このような場合、左右の小図柄56が1〜6、8、9図柄であり、真ん中の小図柄56がVの文字で仮停止表示される。この組み合わせにより、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果がハズレであり、保留内に小当たりがあることが示唆される。この小図柄56の仮停止表示と同時に、演出役物7が初期位置から進出位置に動作される。演出役物7の退避完了に伴って液晶画面5には「おめでとう」との文字が表示される。これに伴って、仮停止表示していた小図柄56がそのままの組み合わせで停止表示される(図27(2)参照)。このとき、第4図柄57が白の図柄で停止表示される。これにより、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果がハズレであったことが報知される。上記「おめでとう」との文字の表示中において、第2特別図柄の次変動表示の開始に伴って小図柄56が変動表示を開始する(図27(3)参照)。そして、装飾図柄55(及び小図柄56)が例えば2図柄揃いで仮停止表示した後、再抽選演出が実行される。その後、第2特別図柄が小当たり図柄3で停止表示されるのと同時に、再抽選演出実行前と同じ組み合わせの装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される(図27(4)参照)。このとき、第4図柄57が紫の図柄で停止表示される。なお、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄2である場合は、再抽選演出を介して「神」との文字を重畳表示しない7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される。また、第2特別図柄判定の最先の保留が小当たり図柄1である場合は、再抽選演出が実行されることなく「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いで装飾図柄55(及び小図柄56)が停止表示される。
新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果、及び第2特別図柄判定の保留が全てハズレである場合、バトル終了示唆演出中における操作促進演出中の操作に応じてシャッター画像が開き切らない。そして、有効期間の終了時に、シャッター画像が完全に閉鎖するシャッター閉鎖演出が実行される(図28(A)参照)。シャッター閉鎖演出は、新章モードにおける3回転目の第2特別図柄判定の判定結果、及び第2特別図柄判定の保留が全てハズレであることを報知するまでシャッター画像が閉鎖した状態のまま継続される。
シャッター閉鎖演出が開始される場合、小図柄56はリーチハズレ目で仮停止表示されたままである。新章モードにおける3回転目の第2特別図柄がハズレ図柄で停止表示されるのに伴って、小図柄56は仮停止表示した組み合わせのまま停止表示する(図28(B)参照)。また、第4図柄57が白で停止表示される。この停止表示の開始に伴って、新章モードの終了を示唆するために、新章モードに係る演出のもととなる劇場版アニメのタイトルと「終」との文字とが表示される。このタイトルと「終」との文字は、第2特別図柄判定の保留が全てハズレであることを報知するまで継続して表示される。第2特別図柄の次変動表示の開始に伴って、シャッター画像が閉鎖した状態のまま小図柄56が変動表示を開始する(図28(C)参照)。その後、第2特別図柄がハズレ図柄で停止表示されるのに伴って、ハズレを示す組み合わせで小図柄56が停止表示される(図28(D)参照)。また、第4図柄57が白で停止表示される。以下同様に、第2特別図柄判定の4つ目の保留が消化されるまで小図柄56及び第4図柄57の変動表示と、ハズレを示す組み合わせでの小図柄56の停止表示および第4図柄57の白での停止表示とが繰り返される(図28(E)〜(J)参照)。シャッター閉鎖演出では、第2特別図柄判定の4つ目の保留に対応するハズレ図柄が停止表示されたことに応じて、シャッター画像が開く演出が実行される(図28(K)及び(L)参照)。ここで、本実施形態では、小図柄56の停止表示開始時に、シャッター画像の後ろ側において、小図柄56と同じ組み合わせで装飾図柄55が停止表示される。シャッター画像が開くことによって、シャッター画像で隠れていた装飾図柄55が見えるようになる。本実施形態では、シャッター画像が開き切ったときに、遊技者に左打ちを促すために「ハンドルを左に戻してね」との文字の表示が開始される。
図29は、新章モードにおいて小当たり図柄2を引き当てた場合におけるモード選択演出について説明するための説明図である。図30は、図29に続くモード選択演出について説明するための説明図である。図29(A)は、新章モードにおいて小当たり図柄2の停止表示が開始したときの液晶画面5の様子を例示している。図29(A)では、小当たり図柄2と同じ内容を報知するために、装飾図柄55として「神」との文字を重畳表示しない7図柄揃いが停止表示されており、白の第4図柄57が停止表示されている。このとき、小図柄56は、装飾図柄55と同じ組み合わせで停止表示されている。
図29(A)の状態で図柄確定時間(例えば1秒)が経過するまで保たれた後、小当たり図柄2に係る小当たり遊技が開始される。図29(B)は、小当たり遊技が開始したことを報知する小当たり用OP演出が実行されている様子を例示している。小当たり用OP演出は、今回の小当たり遊技の種類を示唆する文字を表示する演出であり、小当たり遊技開始時から小当たり遊技に係るラウンド遊技終了時まで実行される演出である。図29(B)では、小当たり図柄2に係る小当たり遊技であることを示唆するために「キャラボーナス」との文字が表示されている。小当たり用OP演出の終盤には、遊技者にV入賞を促す「Vを狙え」との文字、及び複数の「右打ち」との文字が液晶画面5に表示されたり、「Vを狙え」との音声がスピーカ24から出力されたりする。本実施形態では、遊技者に対して具体的にどの位置を狙えばいいのかを分かり易く示唆するために、「Vを狙え」との文字の背景以外の部分(具体的には、図29(C)のうち格子模様部分以外)に、本実施形態の遊技盤2を模した画像が表示される。遊技盤2を模した画像は、例えば、小入賞口19を閉塞するプレートに表記された「V」との文字(すなわち、V入賞口スイッチ116b)を中心として小入賞口19の周辺を表す画像である。図29(C)に示す例では、遊技盤2を模した画像は、小入賞口19を閉塞するプレートと、液晶画面5の右下部分と、普通入賞口14とが含まれている。ここで、図29(C)では、図面を分かり易くする目的で、遊技盤2を模した画像内の役物に対して引き出し線および符号を付している。実際には引き出し線および符号がない状態で遊技盤2を模した画像が表示される。
小当たり遊技に係るラウンド遊技中にV入賞したことに応じて、液晶画面5の右下隅から四方八方に向かって光が放たれる様子を表すエフェクト(不図示)が表示される。このエフェクトは、V入賞を報知するために、V入賞に応じて表示が開始される画像である。そして、小当たり遊技に係るED期間開始時からこの小当たり遊技に続く大当たり遊技のOP期間終了時までの期間に亘って、上記エフェクトが広がって液晶画面5全体を光が覆いホワイトアウトする演出表示が行われる。ホワイトアウトに続いて、大当たり遊技のラウンド演出が開始される。図29(D)は、大当たり遊技開始後からの1R目のラウンド遊技(小当たり遊技の分を加えると2R目のラウンド遊技)開始時からラウンド演出が開始されている様子を例示している。本実施形態では、小当たり図柄2に係る大当たり遊技の場合、ラウンド演出開始時からモード選択演出で移行先の演出モードが確定するまでキャラA〜Cの動画が表示される(例えば、図29(D)〜図29(F)参照)。この動画は、その開始時から終了時まで、液晶画面5の上端と下端とにピンク色の帯を表示する(図29(D)〜図29(F)、図30(A)〜(C)参照)。
小当たり図柄2に係る大当たり遊技の場合、図29(D)に例示するように、8R分のラウンド遊技が行われることを示唆するために〇が8つラウンド演出開始時から表示される。小当たり図柄2に係る大当たり遊技の場合、上記〇は1R終了毎に1つずつ白から黒に変わりながら表示され続け、最終ラウンド遊技の終了時に消去される(図29(E)参照)。
図29(F)〜図30(C)では、新章モードで小当たり図柄2を引き当てた場合のモード選択演出を例示する。このときのモード選択演出は、実行中の大当たり遊技が終了した後の演出モードとして、バトルモード及びストーリーモードから何れか1つを決定するために実行される。サブRAM133には新章モードを示す設定値が記憶されているため、モード選択演出の初期画面において最初に選択された状態にされる演出モードは、グループBのストーリーモードである。
モード選択演出の開始(及びED期間の開始)に伴って、「モードを選んでね」との文字の表示が開始される。また、モード選択演出の開始に伴ってバトルモードを表すバトルモード画像42と、ストーリーモードを表すストーリーモード画像43との移動表示が開始される(図29(F)及び図30(A)参照)。新章モードを示す設定値が記憶されているため、モード選択演出が開始されたときに最初に表示されるのはグループBのストーリーモードを表すモード画像である。この例では、バトルモード画像42及びストーリーモード画像43の移動表示中には、図10(A)〜(E)に例示するモード画像の移動表示と同様の演出表示が行われる。具体的には、ストーリーモード画像43は、図10(A)〜(E)に例示する夜モード画像40の移動表示と同様の移動表示を行う。また、バトルモード画像42は、図10(A)〜(E)に例示する新章モード画像41の移動表示と同様の移動表示を行う。
図29(F)及び図30(A)に例示するように、バトルモード画像42及びストーリーモード画像43は、モード選択演出の開始時から移動表示が完了したときまで暗い色合いで表示される。移動表示が完了したことに応じて開始される有効期間中に演出モードの選択が可能になる。
図30(B)に例示するように、移動表示が完了したことに応じて、「モードを選んでね」との文字が消去される。これに伴って、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印の表示が開始される。ボタン画像90の表示開始と同時に、演出ボタン26の有効期間が開始する。
ボタン画像90の表示が開始されるのと同時に、ストーリーモード画像43の表示態様が明るい色合いに変化する(図30(B)参照)。これにより、現在ストーリーモード画像43が選択された状態であることが示唆される。一方、バトルモード画像42は、演出ボタン26が操作されることによって選択されない限り暗い色合いのままである。これにより、現在バトルモード画像42が選択されていない状態であることが示唆される。このように、グループBの演出モードを示す設定値がサブRAM133に記憶されているため、モード選択演出では、ストーリーモード画像43が最初に選択された状態の初期画面が表示される。
演出ボタン26が1回操作されると、ストーリーモード画像43が選択された状態からバトルモード画像42が選択された状態へと切り替わる(図30(B)から(C)の流れ)。本実施形態では、この1回目の操作に応じてストーリーモード画像43の表示態様が暗い色合いに変化すると共に、バトルモード画像42が明るい色合いに変化する。また、この1回目の操作に応じて、ストーリーモード画像43が次第に縮小しながらバトルモード画像42の後ろ側へと移動表示すると共に、バトルモード画像42が次第に拡大しながらストーリーモード画像43の手前側へと移動表示する。
モード選択演出の有効期間中に演出ボタン26に対して2回目の操作がされると、バトルモード画像42が選択された状態からストーリーモード画像43が選択された状態へと切り替わる(図30(C)から(B)の流れ)。本実施形態では、この2回目の操作に応じてストーリーモード画像43の表示態様が明るい色合いに戻ると共に、バトルモード画像42が暗い色合いに戻る。また、この2回目の操作に応じて、ストーリーモード画像43が次第に拡大しながらバトルモード画像42の手前側へと移動表示すると共に、バトルモード画像42が次第に縮小しながらストーリーモード画像43の後ろ側へと移動表示する。ここで、図30(B)は有効期間開始時のゲージ画像91を表記している。2回目の操作に応じてストーリーモード画像43が選択された状態へと切り替わったときには、ゲージ画像91は、図30(C)に例示するゲージ画像91が示唆する残り時間よりも少ない残り時間を示唆した状態となる。
その後、予め定められた有効期間の終了時に、この時点で選択された状態のモード画像が表す演出モードへの移行が確定する。図30(D)は、有効期間終了時にストーリーモード画像43が選択された状態であり、ストーリーモードへの移行が確定した例を示している。この例では、有効期間終了時にストーリーモードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。この記憶処理により、実行中の大当たり遊技終了直後にストーリーモードで演出が制御される。そして、このときのストーリーモードにおいて小当たり又は大当たり(具体的には、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3)を引き当てた場合には、グループBの演出モードが選択された状態の初期画面のモード選択演出が、3回目の大当たり遊技中に実行される。このように、次のモード選択演出においてストーリーモード(又はグループBのうち他の演出モード)を選択し直さなくてもグループBの演出モードが選択された状態になっているので、選択し直す煩わしさがない。
図30(D)に例示するように、有効期間終了時からストーリーモード画像43が拡大を開始し、ストーリーモード画像43が全画面表示される。バトルモード画像42、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印、及びキャラA〜Dの動画は、有効期間終了時に消去される。
操作された結果バトルモード画像42が選択された状態で有効期間が終了する場合、有効期間終了時にバトルモードへの移行が確定する。このような場合、有効期間終了時に移行先がバトルモードを示す設定値がサブRAM133に記憶される。この記憶処理により、実行中の大当たり遊技終了直後にバトルモードで演出が制御される。そして、このときのバトルモードにおいて小当たり又は大当たり(具体的には、大当たり図柄B、C、E、及びF、並びに小当たり図柄2及び3)を引き当てた場合には、グループAの演出モードが選択された状態のモード選択演出が、3回目の大当たり遊技中に実行される。このように、次のモード選択演出において夜モード(又はグループAのうち他の演出モード)を選択し直さなくてもグループAの演出モードが選択された状態になっているので、選択し直す煩わしさがない。
有効期間終了時にバトルモードへの移行が確定する場合、有効期間終了時からバトルモード画像42が拡大を開始し、バトルモード画像42が全画面表示される。ストーリーモード画像43、ボタン画像90、ゲージ画像91、「モード切替」との文字、左右方向の矢印、及びキャラA〜Cの動画は、有効期間終了時に消去される。
ストーリーモード画像43が全画面表示されてから所定時間(例えば7秒)経過時に、このストーリーモード画像43が消去される。これと共に、ストーリーモードへの移行を報知する演出モードタイトルを表示する演出が開始される(図30(F)参照)。この演出では、以下の演出表示が行われる。まず、「少女ラッシュ」との文字が表示された状態となる。そして、この文字が表示されたことに応じて、「ストーリーモード 突入」との文字が表示される(図30(F)参照)。ストーリーモードへの移行を報知する演出モードタイトルを表示する演出は、第2特別図柄の変動表示が開始された後に終了する。そして、この変動表示中にストーリーモードの画面構成に切り替わる(図30(H)及び図31(A)参照)。
[ストーリーモードで小当たり図柄1を引き当てた場合]
次に、図31及び図32を参照して、ストーリーモードで小当たり図柄1を引き当てた場合の大当たり遊技中の演出について説明する。図31は、ストーリーモードで小当たり図柄1を引き当てた場合に大当たり遊技が開始されたときまでの演出例について説明するための説明図である。図32は、ストーリーモードに即したラウンド演出後に悪魔ラッシュに移行する演出例について説明するための説明図である。
本実施形態のストーリーモードは、遊技者が好みのストーリー動画をリーチ成立後に観られるところに特徴がある演出モードである。遊技者は、例えば、リーチが成立するまでの期間中に好みのストーリ−動画の種類を第1〜4話から選択可能であり、このストーリー動画をリーチ成立後に観られる。図31(A)は、リーチが成立するまでにおけるストーリーモード中の基本的な画面構成である。図31(A)の画面で特徴的なことは、ボタン画像90と、演出ボタン26の操作によりストーリー動画の話数を変更できることを示唆する「話数選択」との文字と、現在選択されているストーリー動画を報知する「第1話 ミッション キャラCを説得せよ!」との文字が表示されていることである。
図31(B)に例示するように、ストーリーモードで第2特別図柄の変動表示中にリーチが成立すると、リーチ成立前に選択していたストーリー動画が再生される。図31(C)は、上記変動表示の結果、小当たり図柄1の停止表示が開始したときの液晶画面5の様子を例示している。図31(C)では、小当たり図柄1と同じ内容を報知するために、装飾図柄55として「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いが停止表示されており、緑の第4図柄57が停止表示されている。このとき、小図柄56は、装飾図柄55と同じ組み合わせで停止表示されている。
図31(C)の状態で図柄確定時間(例えば1秒)が経過するまで保たれた後、小当たり図柄1に係る小当たり遊技が開始される。図31(D)は、小当たり図柄1の小当たり用OP演出が実行されている様子を例示している。図31(D)では、小当たり図柄1に係る小当たり遊技であることを示唆するために「神ボーナス」との文字が表示されている。小当たり用OP演出の終盤には、遊技者にV入賞を促す「Vを狙え」との文字、遊技盤2を模した画像、及び複数の「右打ち」との文字が液晶画面5に表示されたり、「Vを狙え」との音声がスピーカ24から出力されたりする。このV入賞を促す演出は、小当たり図柄2が停止表示された場合に実行されるものと、ボーナス帯46が表示されることを除いて同じである。ボーナス帯46は、小当たり図柄1に係る小当たり遊技(及び大当たり遊技)であることを報知する画像であり、小当たり遊技開始時に表示が開始され、大当たり遊技終了時に消去される画像である。
小当たり遊技に係るラウンド遊技中にV入賞したことに応じて、V入賞を報知するエフェクトが表示される。そして、小当たり遊技に係るED期間開始時からこの小当たり遊技に続く大当たり遊技のOP期間終了時までの期間に亘って、上記エフェクトが広がって液晶画面5全体を光が覆いホワイトアウトする演出表示が行われる。ホワイトアウトに続いて、大当たり遊技のラウンド演出が開始される。本実施形態では、遊技者が選択したストーリー動画を楽しませるべく、小当たり図柄1が停止表示された場合、再生されていたストーリー動画のダイジェスト映像をラウンド演出として再生する(図31(F)参照)。ストーリー動画はストーリーモードでのみ再生される、グループBの演出モードに即したリーチ演出である。このため、このストーリー動画のダイジェスト映像を再生する演出は、グループBの演出モードに即したラウンド演出である。
図32(A)に例示するように、本実施形態では、最終ラウンド遊技終了時にもストーリー動画のダイジェスト映像を再生するラウンド演出が継続される。続いてED期間の開始に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が開始されると共に、上記ラウンド演出が継続される(図32(B)参照)。このときのED演出は、上記ラウンド演出の手前側に重畳表示される。ED演出は、時間の経過に伴って表示領域が増えていき最終的に全画面に表示される(図32(C)参照)。このため、上記ラウンド演出はED期間中に最終的に見えなくなる。ED期間の終了に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が終了し、ED期間の終了直後に悪魔ラッシュに移行する(図32(D)参照)。
本実施形態では、小当たり図柄1が停止表示された場合、神ラッシュ又は悪魔ラッシュのうち、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値と同じグループの演出モードに大当たり遊技終了直後に自動的に移行する。このため、本実施形態では、小当たり図柄1が停止表示された場合、この大当たり遊技中にモード選択演出は実行されない。これにより、演出モードの選択に気を散らせることなくストーリー動画と関連のある動画に遊技者を集中させることが可能である。
[バトルモードで小当たり図柄1を引き当てた場合]
次に、図33及び図34を参照して、バトルモードで小当たり図柄1を引き当てた場合の大当たり遊技中の演出について説明する。図33は、バトルモードで小当たり図柄1を引き当てた場合に大当たり遊技が開始されたときまでの演出例について説明するための説明図である。図34は、バトルモードに即したラウンド演出後に悪魔ラッシュに移行する演出例について説明するための説明図である。
本実施形態のバトルモードは、ストーリーモードと異なり、遊技者が好みの演出を選べない演出モードである。このため、図33(A)に例示するように、ストーリーモード中に表示されていた「話数選択」との文字等(図31(A)参照)は表示されない。
図33(B)に例示するように、バトルモードで第2特別図柄の変動表示中にリーチが成立すると、バトルモードでのみ実行可能なバトルリーチ演出が実行される。図33(C)は、上記変動表示の結果、小当たり図柄1の停止表示が開始したときの液晶画面5の様子を例示している。図33(C)では、小当たり図柄1と同じ内容を報知するために、装飾図柄55として「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いが停止表示されており、緑の第4図柄57が停止表示されている。このとき、小図柄56は、装飾図柄55と同じ組み合わせで停止表示されている。
図33(C)の状態で図柄確定時間(例えば1秒)が経過するまで保たれた後、小当たり図柄1に係る小当たり遊技が開始される。図33(D)及び(E)に例示するように、小当たり遊技開始時から大当たり遊技開始時までの演出は、ストーリーモードで小当たり図柄1を引き当てたときの演出(図31(D)及び(E)参照)と同じである。
図33(F)に例示するように、バトルモードで小当たり図柄1を引き当てた場合、大当たり遊技のラウンド演出として、グループAの演出モードに即したラウンド演出が実行される。図34(A)に例示するように、本実施形態では、最終ラウンド遊技終了時にも上記ラウンド演出が継続される。続いてED期間の開始に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が開始されると共に、上記ラウンド演出が継続される(図34(B)参照)。ED演出は、上記ラウンド演出の手前側に重畳表示され、時間の経過に伴って表示領域が増えていき最終的に全画面に表示される(図34(C)参照)。このため、上記ラウンド演出はED期間中に最終的に見えなくなる。ED期間の終了に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が終了し、ED期間の終了直後に悪魔ラッシュに移行する(図34(D)参照)。
このように、本実施形態では、ストーリーモードとバトルモードとの何れで小当たり図柄1が停止表示された場合でも、大当たり遊技中にモード選択演出は実行されない。これにより、演出モードの選択に気を散らせることなく各グループに即したラウンド演出に遊技者を集中させることが可能である。
[悪魔ラッシュで小当たり図柄1及び小当たり図柄3を引き当てた場合]
次に、図35〜図37を参照して、悪魔ラッシュで小当たり図柄1を引き当てた後、悪魔ラッシュで小当たり図柄3を引き当てた場合の演出例について説明する。図35は、悪魔ラッシュで小当たり図柄1を引き当てた場合の演出例について説明するための説明図である。図36は、悪魔ラッシュで小当たり図柄3を引き当てた場合に大当たり遊技が開始されたときまでの演出例について説明するための説明図である。図37は、悪魔ラッシュで小当たり図柄3を引き当てた場合、悪魔ラッシュに即したラウンド演出後にストーリーモードに移行する演出例について説明するための説明図である。
本実施形態の悪魔ラッシュは、大当たり遊技が連続していることを強調するために、ラウンド遊技が行われることを示唆するために表示される〇を、大当たり遊技終了後も継続して表示する。図35(A)は、悪魔ラッシュ中に小当たり図柄1を引き当てたことにより10R分のラウンド遊技がすでに実行された状態で、小当たり図柄1の停止表示が開始したときの液晶画面5の様子を例示している。図35(A)では、小当たり図柄1と同じ内容を報知するために、装飾図柄55(及び小図柄56)として「神」との文字を手前側に重畳表示した7図柄揃いが停止表示されており、緑の第4図柄57が停止表示されている。
図35(A)の状態で、図柄確定時間(例えば1秒)が経過した後、小当たり図柄1に係る小当たり遊技のOP期間が開始されたときまで装飾図柄55、小図柄56、第4図柄57が保たれる。図35(B)に例示するように、上記OP期間開始時からは悪魔ラッシュに即したOP演出が開始される。このときのOP演出では、例えば、悪魔ラッシュであることを報知する悪魔ラッシュ帯45の手前側に、ボーナス帯46が重畳表示される。
上記OP演出の終盤には、遊技者にV入賞を促す「Vを狙え」との文字、及び複数の「右打ち」との文字が液晶画面5に表示されたり、「Vを狙え」との音声がスピーカ24から出力されたりする。このV入賞を促す演出は、悪魔ラッシュに即した右打ち演出であり、他の演出モードにおいてV入賞を促すときには表示されない背景画像(例えば、悪魔ラッシュであることを示唆する画像)が表示される。
小当たり遊技に係るラウンド遊技中にV入賞したことに応じて、V入賞を報知するエフェクトが表示される。そして、小当たり遊技に係るED期間開始時からこの小当たり遊技に続く大当たり遊技のOP期間終了時までの期間に亘って、上記エフェクトが広がって液晶画面5全体を光が覆いホワイトアウトする演出表示が行われる。ホワイトアウトに続いて、大当たり遊技のラウンド演出として、悪魔ラッシュに即したラウンド演出が開始される(図35(D)参照)。このとき、悪魔ラッシュ帯45が消去されてボーナス帯46だけが表示が継続される。
図35(E)に例示するように、本実施形態では、最終ラウンド遊技終了時にも悪魔ラッシュに即したラウンド演出が継続される。続いてED期間の開始に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が開始されると共に、上記ラウンド演出が継続される(図35(F)参照)。このときのED演出は、上記ラウンド演出の手前側に重畳表示される。ED演出は、時間の経過に伴って表示領域が増えていき最終的に全画面に表示される(図36(A)参照)。このため、上記ラウンド演出はED期間中に最終的に見えなくなる。ED期間の終了に伴って悪魔ラッシュに即したED演出が終了し、ED期間の終了直後に悪魔ラッシュが継続する(図36(B)参照)。ボーナス帯46は、ED期間の終了時に消去され、悪魔ラッシュの開始と同時に悪魔ラッシュ帯45が表示される。このとき、終了したラウンド遊技の数を示唆する黒丸の表示を継続する。
図36(C)は、悪魔ラッシュ中に小当たり図柄1を2回引き当てたことにより20R分のラウンド遊技がすでに実行された状態で、小当たり図柄3の停止表示が開始したときの液晶画面5の様子を例示している。図36(C)では、小当たり図柄3と同じ内容を報知するために、装飾図柄55(及び小図柄56)として6図柄揃いが停止表示されており、紫の第4図柄57が停止表示されている。
図36(C)の状態で、図柄確定時間(例えば1秒)が経過した後、小当たり図柄3に係る小当たり遊技のOP期間が開始されたときまで装飾図柄55、小図柄56、第4図柄57が保たれる。悪魔ラッシュで小当たり図柄3を引き当てた場合、悪魔ラッシュで小当たり図柄1を引き当てたときと、ラウンド演出が終了するまで基本的には同じ演出が行われる。このため、本実施形態では、本来悪魔ラッシュの演出ができない小当たり図柄3を用いて、悪魔ラッシュで大当たり遊技が連続していることを演出できる。
図37(E)に例示するように、本実施形態では、悪魔ラッシュで小当たり図柄3を引き当てた場合、最終ラウンド遊技終了時に悪魔ラッシュに即したラウンド演出が終了する。続いて図37(B)に例示するように、ED期間の開始に伴って、悪魔ラッシュの終了を報知する演出が開始される。このED期間中に、移行先の演出モードを示唆する「NEXT 少女ラッシュ」との文字が表示される(図37(C)参照)。少女ラッシュはバトルモードとストーリーモードとを総称する語である。続いて図37(D)に例示するように、ストーリーモードへの移行を報知する演出モードタイトルの表示が開始される。このときの演出モードタイトルでは、新たにストーリーモードが開始されることを示唆するために「少女ラッシュ ストーリーモード 突入」との文字が表示される。図37(E)に例示するように、この演出モードタイトルの表示中に、第2特別図柄の変動表示が開始され、この変動表示中にストーリーモードの画面構成になる。
本実施形態では、悪魔ラッシュで小当たり図柄3が停止表示された場合、悪魔ラッシュと同じグループBのストーリーモードに移行する。このように、本実施形態では、サブRAM133に記憶された演出モードを示す設定値と同じグループBのストーリーモードに大当たり遊技終了直後に自動的に移行する。このように、本実施形態では、悪魔ラッシュで小当たり図柄3が停止表示された場合、この大当たり遊技中にモード選択演出は実行されない。これにより、悪魔ラッシュが遊技者の選択で選べる他の演出モードと異なる特別な演出モードであることを効果的に表現できる。
以下、上述した各種演出を実現するために遊技機1で行われる処理の一例について詳細に説明する。
[遊技制御基板100によるタイマ割込み処理]
次に、図38を参照しつつ、遊技制御基板100において実行されるタイマ割込み処理について説明する。ここで、図38は、遊技制御基板100において実行されるタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。遊技制御基板100は、電源投入時や電源断時等の特殊な場合を除く通常の動作時において、一定時間(例えば4ミリ秒)毎に定期的にタイマ割込みがかかるように設定されている。タイマ割込みが発生すると、遊技制御基板100は、図38に例示されている一連の処理を実行する。なお、図38〜図44に示す処理は、メインROM102に記憶されているプログラムに基づいてメインCPU101が発行する命令に従って行われる。
まず、遊技制御基板100のメインCPU101は、図柄乱数、リーチ乱数、変動パターン乱数、及び普通図柄乱数をソフトウェアにより更新するための乱数更新処理を実行する(ステップS1)。
例えば、各乱数は、このステップS1の処理が行われる毎に「1」加算される。なお、このステップS1の処理を行うカウンタとしてはループカウンタが使用されており、各乱数は、予め設定された最大値に達した後は「0」に戻されて更新される。なお、大当たり乱数をソフトウェアにより更新したり、乱数回路104を用いて生成した値とソフトウェアにより生成した値との演算によって各乱数を生成したりするように予め設定されていてもよい。
ステップS1の処理に続いて、メインCPU101は、第1始動口11に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ111、第2始動口12に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ112等の各スイッチから入力される検知信号の状態を判定するスイッチ処理を実行する(ステップS2)。このスイッチ処理については、図39に基づいて後に詳述する。
ステップS2の処理に続いて、メインCPU101は、特別図柄判定を実行し、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させてから特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる処理等を含む特別図柄処理を実行する(ステップS3)。特別図柄処理では、大当たりであるか否か、大当たり種別、特別図柄の変動パターン等が決定される。この特別図柄処理については、図42に基づいて後に詳述する。
ステップS3の処理に続いて、メインCPU101は、普通図柄判定を実行し、普通図柄表示器45に普通図柄を変動表示させてから普通図柄判定の結果を示す普通図柄を停止表示させる処理等を含む普通図柄処理を実行する(ステップS4)。
ステップS4の処理に続いて、メインCPU101は、普通図柄判定を行った結果、第1始動口11bを開放すると判定した場合に、電動チューリップ制御部113を介して電動チューリップ17を動作させる電動チューリップ処理を実行する(ステップS5)。
ステップS5の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS3の処理で小当たりであると判定した場合に、小入賞口制御部118を制御して小入賞口19を開放する小入賞口開放制御処理を実行する(ステップS6)。小入賞口開放制御処理は、小当たり遊技を制御する処理であり、小当たり遊技を実行すると判定されたことを示す特別図柄(小当たり図柄)が第2特別図柄表示器42に停止表示された場合に行われる。この小入賞口開放制御処理については、図45に基づいて後に詳述する。
ステップS6の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS3の処理で大当たりであると判定した場合に、大入賞口制御部117を制御して大入賞口13を開放する大入賞口開放制御処理を実行する(ステップS7)。この大入賞口開放制御処理については、図46に基づいて後に詳述する。
ステップS7の処理に続いて、メインCPU101は、遊技球の入賞に応じた賞球の払い出しを制御する賞球処理を実行する(ステップS8)。
ステップS8の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS8以前の処理ステップにおいてメインRAM103にセット(格納)された各種コマンドや演出内容を決定するために必要な情報を演出制御基板130に送信する送信処理を実行する(ステップS9)。
[遊技制御基板100によるスイッチ処理]
図39は、図38のステップS2におけるスイッチ処理の詳細フローチャートである。ステップS1の処理に続いて、メインCPU101は、第1始動口スイッチ111からの検知信号の入力の有無を監視して、第1始動口スイッチ111からの検知信号が入力された時点の特別図柄判定用の乱数(大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数)を取得する処理等を含む第1始動口スイッチ処理を実行する(ステップS21)。この第1始動口スイッチ処理については、図40に基づいて後に詳述する。
次に、メインCPU101は、第2始動口スイッチ112からの検知信号の入力の有無を監視して、第2始動口スイッチ112からの検知信号が入力された時点の特別図柄判定用の乱数を取得する処理等を含む第2始動口スイッチ処理を実行する(ステップS22)。この第2始動口スイッチ処理については、図41に基づいて後に詳述する。
そして、メインCPU101は、ゲートスイッチ114からの検知信号の入力の有無を監視して、ゲートスイッチ114からの検知信号が入力された時点の普通図柄乱数を取得するゲートスイッチ処理を実行する(ステップS23)。
[遊技制御基板100による第1始動口スイッチ処理]
図40は、図39のステップS21における第1始動口スイッチ処理の詳細フローチャートである。図40に例示されるように、メインCPU101は、第1始動口スイッチ111からの検知信号が入力されたか否かに基づいて、第1始動口スイッチ111が「ON」になったか否かを判定する(ステップS2101)。例えば、第1始動口スイッチ111が「ON」になったことを示すON信号が入力された場合に、第1始動口スイッチ111が「ON」になったと判定される。
メインCPU101は、第1始動口スイッチ111が「ON」になったと判定した場合(ステップS2101:YES)、第1特別図柄判定に使用する取得情報として、大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数を取得する(ステップS2102〜2105)。
次に、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が、メインROM102に記憶されている第1特別図柄判定の最大保留数Umax1(本実施形態では「4」)未満であるか否かを判定する(ステップS2106)。
メインCPU101は、保留数U1が最大保留数Umax1未満であると判定した場合(ステップS2106:YES)、保留数U1の値を「1」加算した値に更新する(ステップS2107)。
ステップS2107の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103に記憶された時短遊技フラグが「ON」であるか否かを判定する(ステップS2108)。この時短遊技フラグは、現在の遊技状態が時短状態である場合に「ON」に設定され、逆に、非時短状態である場合に「OFF」に設定されるフラグである。
メインCPU101は、時短遊技フラグが「ON」ではない(すなわち「OFF」)と判定した場合(ステップS2108:NO)、事前判定処理を実行する(ステップS2109)。具体的には、メインCPU101は、後述する大当たり判定処理(図43参照)や変動パターン決定処理(図44参照)に先立って、ステップS2102〜2105の処理によって取得された取得情報に基づいて、大当たりと判定されるか否か及び変動パターンがどの種別に決定されることになるか等を事前判定する。
メインCPU101は、ステップS2109の処理に続いて、ステップS2109の事前判定処理によって得られた事前判定情報と、ステップS2102〜2105の処理で取得した各種乱数とをメインRAM103における保留記憶領域に格納する(ステップS2110)。
メインCPU101は、時短遊技フラグが「ON」であると判定した場合(ステップS2108:YES)、ステップS2102〜2105の処理で取得した各種乱数をメインRAM103における保留記憶領域に格納する(ステップS2111)。
メインCPU101は、ステップS2110又はステップS2111の処理を実行した場合、第1特別図柄判定に係る保留コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS2112)。この保留コマンドは、第1特別図柄判定が保留されたことを通知するコマンドであって、ステップS2109の処理で得られた事前判定情報を含むものである。保留コマンドは、ステップS9の送信処理によって演出制御基板130に送信される。
ステップS2112の処理を実行した場合、第1始動口スイッチ111が「ON」になっていないと判定した場合(ステップS2101:NO)、又は、保留数U1が最大保留数Umax1未満でないと判定した場合(ステップS2106:NO)、メインCPU101は図40に示す処理を終了する。
[遊技制御基板100による第2始動口スイッチ処理]
図41は、図39のステップS22における第2始動口スイッチ処理の詳細フローチャートである。図41に例示されるように、メインCPU101は、ステップS21の第1始動口スイッチ処理に続いて、第2始動口スイッチ112からの検知信号が入力されたか否かに基づいて、第2始動口スイッチ112が「ON」になったか否かを判定する(ステップS2201)。例えば、第2始動口スイッチ112が「ON」になったことを示すON信号が入力された場合に、第2始動口スイッチ112が「ON」になったと判定される。
メインCPU101は、第2始動口スイッチ112が「ON」になったと判定した場合(ステップS2201:YES)、第2特別図柄判定に使用する取得情報として、大当たり乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数を取得する(ステップS2202〜2205)。
次に、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が、メインROM102に記憶されている第2特別図柄判定の最大保留数Umax2(本実施形態では「4」)未満であるか否かを判定する(ステップS2206)。
メインCPU101は、保留数U2が最大保留数Umax2未満であると判定した場合(ステップS2206:YES)、保留数U2の値を「1」加算した値に更新する(ステップS2207)。
ステップS2207の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS2108の処理と同様に、メインRAM103に記憶された時短遊技フラグが「ON」であるか否かを判定する(ステップS2208)。メインCPU101は、時短遊技フラグが「ON」であると判定した場合(ステップS2208:YES)、事前判定処理を実行する(ステップS2209)。
メインCPU101は、ステップS2209の処理に続いて、ステップS2209の事前判定処理によって得られた事前判定情報と、ステップS2202〜2205の処理で取得した各種乱数とをメインRAM103における保留記憶領域に格納する(ステップS2210)。
メインCPU101は、時短遊技フラグが「ON」ではない(すなわち「OFF」)と判定した場合(ステップS2208:NO)、ステップS2202〜2205の処理で取得した各種乱数をメインRAM103における保留記憶領域に格納する(ステップS2211)。
メインCPU101は、ステップS2210又はステップS2211の処理を実行した場合、第2特別図柄判定に係る保留コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS2112)。この保留コマンドは、第2特別図柄判定が保留されたことを通知するコマンドであって、ステップS2210の処理で得られた事前判定情報を含むものである。保留コマンドは、ステップS9の送信処理によって演出制御基板130に送信される。
ステップS2212の処理を実行した場合、第2始動口スイッチ112が「ON」になっていないと判定した場合(ステップS2201:NO)、又は、保留数U2が最大保留数Umax2未満でないと判定した場合(ステップS2206:NO)、メインCPU101は図41に示す処理を終了する。
[遊技制御基板100による特別図柄処理]
次に、図42を参照しつつ、遊技制御基板100によって実行される特別図柄処理の詳細について説明する。ここで、図42は、図38のステップS3における特別図柄処理の詳細フローチャートである。
図42に例示されるように、メインCPU101は、大当たり遊技中または小当たり遊技中であるか否かを判定する(ステップS301)。メインCPU101は、例えば、メインRAM103に記憶されている大当たり遊技フラグが「ON」に設定されているか否かに基づいて、大当たり遊技中であるか否かを判定する。この大当たり遊技フラグは、大当たり遊技の実行中であるか否かを示すフラグであり、大当たり遊技の開始時に「ON」に設定され、大当たり遊技の終了時に「OFF」に設定される。また、メインCPU101は、例えば、小当たり遊技フラグが「ON」に設定されているか否かに基づいて、小当たり遊技中であるか否かを判定する。この小当たり遊技フラグは、メインRAM103に記憶されている小当たり遊技の実行中であるか否かを示すフラグであり、小当たり遊技の開始時に「ON」に設定され、小当たり遊技の終了時に「OFF」に設定される。ここで、大当たり遊技中または小当たり遊技中であると判定された場合(ステップS301:YES)、ステップS4の普通図柄処理に処理が進められる。
メインCPU101は、大当たり遊技中ではないと判定した場合(ステップS301:NO)、特別図柄の変動表示中であるか否かを判定する(ステップS302)。ここで、特別図柄の変動表示中ではないと判定した場合(ステップS302:NO)、メインRAM103に記憶されている第2特別図柄判定の保留数U2が「1」以上であるか否かを判定する(ステップS303)。ここで、保留数U2が「1」以上であると判定した場合(ステップS303:YES)、保留数U2を「1」減算した値に更新する(ステップS304)。
メインCPU101は、保留数U2が「1」以上ではないと判定した場合(ステップS303:NO)、メインRAM103に記憶されている第1特別図柄判定の保留数U1が「1」以上であるか否かを判定する(ステップS305)。ここで、保留数U1が「1」以上ではないと判定された場合(ステップS305:NO)、ステップS4の普通図柄処理に処理が進められる。
メインCPU101は、保留数U1が「1」以上であると判定した場合(ステップS305:YES)、保留数U1を「1」減算した値に更新する(ステップS306)。
ステップS304の処理又はステップS306の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103の保留記憶領域に対するシフト処理を実行する(ステップS308)。具体的には、メインCPU101は、ステップS304の処理に続いてシフト処理を実行する場合には、第2特別図柄判定用の保留記憶領域に記憶されている最先の取得情報を判定用記憶領域にシフトさせると共に、残りの取得情報を1エントリずつ上位にシフトさせる。判定用記憶領域は、特別図柄判定が実際に実行されるときにその特別図柄判定に使用される各種情報が記憶される記憶領域である。また、ステップS306の処理に続いてシフト処理を実行する場合には、第1特別図柄判定用の保留記憶領域に記憶されている最先の取得情報を判定用記憶領域にシフトさせると共に、残りの取得情報を1エントリずつ上位にシフトさせる。
ステップS308の処理に続いて、メインCPU101は、判定用記憶領域に記憶されている乱数に基づいて、大当たり判定処理を実行する(ステップS309)。この大当たり判定処理については、図43に基づいて後に詳述する。
ステップS309の処理に続いて、メインCPU101は、特別図柄の変動パターンを選択する変動パターン決定処理を実行する(ステップS310)。この変動パターン決定処理については、図44に基づいて後に詳述する。
ステップS310の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS309の処理で決定した特別図柄の設定情報、この特別図柄の設定情報が第1特別図柄判定に係るものであるか或いは第2特別図柄判定に係るものであるかを示す情報、ステップS310の処理で決定した変動パターンの設定情報、遊技機1の遊技状態に関する情報等を含む変動開始コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS311)。
この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の開始を指示するコマンドであって、ステップS9の送信処理によって演出制御基板130に送信される。これにより、液晶画面5における装飾図柄55の変動表示等が開始されることになる。
ステップS311の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS311の処理でセットした変動開始コマンドに含まれている変動パターンの設定情報に基づいて、特別図柄の変動表示を開始する(ステップS312)。その際、判定用記憶領域に第1特別図柄判定に係る取得情報(乱数)が記憶された状態でステップS309〜311の処理が行われた場合には、第1特別図柄表示器41において特別図柄の変動表示を開始する。一方、第2特別図柄判定に係る取得情報(乱数)が記憶された状態でステップS309〜311の処理が行われた場合には、第2特別図柄表示器42において特別図柄の変動表示を開始する。
次に、メインCPU101は、ステップS312における変動表示を開始してからの経過時間である変動時間の計測を開始する(ステップS313)。
メインCPU101は、ステップS313の処理を実行した場合、又は特別図柄の変動表示中であると判定した場合(ステップS302:YES)、ステップS313における変動時間の計測開始から、ステップS310の処理によって選択された変動パターンに対応する変動時間が経過したか否かを判定する(ステップS315)。ここで、変動時間が経過していないと判定された場合(ステップS315:NO)、ステップS4の普通図柄処理に処理が進められる。
メインCPU101は、変動時間が経過したと判定した場合(ステップS315:YES)、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄が停止表示されることを通知する図柄確定コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS316)。この図柄確定コマンドは、ステップS9における送信処理によって演出制御基板130に送信される。これにより、液晶画面5に変動表示されていた装飾図柄55を特別図柄判定の判定結果を示す態様で停止表示させる処理等が行われることになる。
ステップS316の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS312の処理で開始した特別図柄の変動表示を終了させる(ステップS317)。具体的には、ステップS309の処理で決定した特別図柄(大当たり図柄又はハズレ図柄)を、変動表示させていた特別図柄表示器に停止表示させる。なお、この特別図柄の停止表示は、少なくとも所定の図柄確定時間(例えば1秒)が経過するまで継続される。
このように、メインCPU101は、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させてから大当たり判定処理の判定結果を示す特別図柄を第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に停止表示させる。
ステップS317の処理に続いて、メインCPU101は、上記ステップS313の処理で計測を開始した変動時間をリセットし(ステップS318)、大当たりである場合に大当たり遊技を開始させ、小当たりである場合に小当たり遊技を開始させるためのオープニングコマンドをセットする処理等を含む停止中処理を実行する(ステップS319)。このオープニングコマンドがステップS9(図38参照)の送信処理によって演出制御基板130に送信されると、演出制御基板130のサブCPU131は、例えば、大当たり(又は小当たり)の種類に対応したOP演出の開始を指示するOP演出開始コマンドをサブRAM133にセットする。このOP演出開始コマンドがステップS30(図46参照)の送信処理によって画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信されたことに応じてOP演出が開始される。
[遊技制御基板100による大当たり判定処理]
図43は、図42のステップS309における大当たり判定処理の詳細フローチャートである。メインCPU101は、判定用記憶領域に記憶された大当たり乱数に基づいて大当たり判定を実行する(ステップS3091)。例えば、大当たり判定テーブルには、大当たり乱数と比較される判定値が大当たり、小当たり、又はハズレに予め割り当てられている。メインCPU101は、図40のステップS2102の処理(又は図41のステップS2202の処理)で取得した大当たり乱数の値が、メインRAM103にセットされた大当たり判定テーブルに定められた判定値の何れと一致するかに基づいて、大当たりであるか否かを判定する。
ステップS3091の処理に続いて、メインCPU101は、大当たり判定の判定結果が大当たりであるか否かを判定する(ステップS3092)。ここで、大当たりであると判定された場合(ステップS3092:YES)、メインCPU101は、メインROM102に予め記憶されている図柄決定テーブルを参照して、ステップS3091の大当たり判定に使用された大当たり乱数と一緒に判定用記憶領域に記憶されている図柄乱数に基づいて大当たり図柄の種類を決定し、その設定情報をメインRAM103にセットする(ステップS3093)。大当たり図柄の種類が決定されることによって、大当たりの種類が決定されることになる。具体的には、例えば、図柄乱数が第1特別図柄判定に係るものである場合には、メインCPU101は、その図柄乱数が、第1始動口用図柄決定テーブル(不図示)に規定されているどの判定値と一致するかに基づいて、大当たり図柄を決定する。また、図柄乱数が第2特別図柄判定に係るものである場合には、メインCPU101は、その図柄乱数が、第2始動口用図柄決定テーブル(不図示)に規定されているどの判定値と一致するかに基づいて、大当たり図柄を決定する。
一方、メインCPU101は、大当たりではないと判定した場合(ステップS3092:NO)、メインCPU101は、小当たりであるか否かを判定する(ステップS3094)。ここで、小当たりであると判定された場合(ステップS3094:YES)、メインCPU101は、メインROM102に予め記憶されている図柄決定テーブルを参照して、図柄乱数に基づいて小当たり図柄の種類を決定し、その設定情報をメインRAM103にセットする(ステップS3095)。
一方、メインCPU101は、小当たりではないと判定した場合(ステップS3094:NO)、ハズレ図柄の設定情報をメインRAM103にセットする(ステップS3096)。これにより、ステップS317の処理において、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42にハズレ図柄が停止表示される。この場合、大当たり遊技は行われない。以上でメインCPU101は図43に示す処理を終了する。
[遊技制御基板100による変動パターン決定処理]
図44は、図42のステップS310における変動パターン決定処理の詳細フローチャートである。メインCPU101は、大当たり図柄Cが停止表示してから3回転目の第2特別図柄の変動表示であるか否かを判定する(ステップS3101)。この処理でYESと判定された場合、今回の変動パターンとして専用の変動パターンを決定し(ステップS3102)、変動パターン決定処理を終了する。
ステップS3101の処理でNOと判定された場合、メインCPU101は、ステップS3091の判定結果が大当たりであるか否かを判定する(ステップS3103)。ここで、大当たりであると判定した場合(ステップS3103:YES)、現在の遊技状態に対応した大当たり用変動パターンテーブル(不図示)をメインROM102から読み出してメインRAM103にセットする(ステップS3102)。なお、変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターンと、変動パターン乱数と比較するための判定値とが対応付けられたテーブルであり、遊技状態毎にメインROM102に予め記憶されているテーブルである。
一方、メインCPU101は、大当たりではないと判定した場合(ステップS3103:NO)、小当たりであるか否かを判定する(ステップS3105)。小当たりであると判定した場合(ステップS3105:YES)、現在の遊技状態に対応した小当たり用変動パターンテーブル(不図示)をメインROM102から読み出してメインRAM103にセットする(ステップS3106)。
一方、メインCPU101は、小当たりではないと判定した場合(ステップS3103:NO)、すなわちハズレである場合、リーチ演出を実行不可能な変動パターンから決定するか否かを決定する(ステップS3107)。具体的には、メインCPU101は、入賞始動口が同じ特別図柄判定の保留数に基づいて、ステップS3091の処理で使用した大当たり乱数と共に判定用記憶領域に記憶されたリーチ乱数の値がリーチ乱数と比較するための判定値の何れと一致するかを判定する。
メインCPU101は、特別図柄の変動パターンをリーチ演出を実行不可能な変動パターンから決定する場合(ステップS3107:NO)、リーチ用変動パターンテーブルをメインROM102から読み出してメインRAM103にセットする(ステップS3108)。一方、リーチ演出を実行不可能な変動パターンから決定する場合(ステップS3109:NO)、非リーチ用変動パターンテーブルをメインROM102から読み出してメインRAM103にセットする(ステップS3107)。
続いて、メインCPU101は、ステップS3104の処理、ステップS3106の処理、又はステップS3108、又はステップS3109の処理によってメインRAM103にセットされた変動パターンテーブルを参照して、特別図柄の変動パターンを決定し、その設定情報をメインRAM103にセットする(ステップS3110)。具体的には、メインCPU101は、ステップS3091の処理で使用した大当たり乱数と共に判定用記憶領域に記憶された変動パターン乱数が、変動パターンテーブルに規定された判定値のうちのどの値と一致するかに基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。例えば、大当たり用変動パターンテーブルがメインRAM103にセットされた場合、メインCPU101は、変動パターン乱数が、大当たり用変動パターンテーブルに規定された判定値のうちのどの値と一致するかに基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。また、例えば、非リーチ用変動パターンテーブルがメインRAM103にセットされた場合、メインCPU101は、変動パターン乱数に基づいて、ステップS308のシフト処理後の保留数に対応した変動パターンを決定する。変動パターンの設定情報は、上述したステップS309の大当たり判定処理によってメインRAM103にセットされた特別図柄の設定情報と共に変動開始コマンドに含められて、ステップS9の送信処理によって演出制御基板130に送信される。以上でメインCPU101は図44に示す処理を終了する。
[遊技制御基板100による小入賞口開放制御処理]
以下、図45を参照しつつ、遊技制御基板100によって実行される小入賞口開放制御処理について説明する。この小入賞口制御処理は、メインROM102に記憶されている小当たり時の図柄決定テーブルに基づいて選択した小当たり遊技を実行する処理である。ここで、図45は、図38のステップS6における小入賞口開放制御処理の詳細フローチャートである。メインCPU101は、ステップS5の電動チューリップ処理に続いて、図38に例示されるように、小当たり遊技フラグが「ON」に設定されているか否かを判定する(ステップS641)。ここで、小当たり遊技フラグが「ON」に設定されていないと判定された場合(ステップS641:NO)、ステップS7の大入賞口制御処理に処理が進められる。
メインCPU101は、大当たり遊技フラグが「ON」に設定されていると判定した場合(ステップS641:YES)、停止中処理によって小当たり遊技に係るオープニングコマンドをセットしてからの経過時間が所定のオープニング時間に達したか否かに基づいて、小当たり遊技のオープニング期間中であるか否かを判定する(ステップS642)。ここで、オープニング期間中であると判定した場合(ステップS642:YES)、同じく経過時間が所定のオープニング時間に達したか否かに基づいて、オープニング時間が経過したか否かを判定する(ステップS643)。ここで、オープニング時間が経過していないと判定された場合(ステップS643:NO)、ステップS7の大入賞口制御処理に処理が進められる。
メインCPU101は、オープニング時間が経過したと判定した場合(ステップS643:YES)、小入賞口制御部118の動作パターン等を設定して、その設定情報をメインRAM103に格納する(ステップS644)。このステップS644の処理が実行されることによって、ラウンド終了後のエンディング時間等の小当たり遊技に関する各種時間も併せて設定される。
ステップS644の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている小入賞口19への遊技球の入賞数Xをリセットする(ステップS645)。
ステップS645の処理に続いて、メインCPU101は、小入賞口の開放制御を開始する(ステップS646)。次に、メインCPU101は、この開放制御が開始されてからの経過時間である開放時間の計測を開始する(ステップS647)。
メインCPU101は、小当たり遊技におけるオープニング中ではないと判定した場合(ステップS642:NO)、例えばメインRAM103に記憶されている現在の状態が小当たり遊技におけるどの時点であるかを示す情報に基づいて、エンディング期間中であるか否かを判定する(ステップS648)。ここで、エンディング期間中であると判定された場合(ステップS648:YES)、後述するステップS659に処理が進められる。
メインCPU101は、小当たり遊技におけるエンディング中ではないと判定した場合(ステップS648:NO)、小入賞口スイッチが「ON」になったか否かを判定する(ステップS649)。具体的には、小入賞口スイッチ116aからの検知信号の有無に基づいて、小入賞口スイッチ116aが「ON」になったか否かを判定する。
ここで、メインCPU101は、小入賞口スイッチ116aが「ON」になったと判定した場合(ステップS649:YES)、小入賞口19に1個の遊技球が入賞したと判断して、遊技球の入賞数Xを「1」加算した値に更新する(ステップS650)。
ステップS650の処理に続いて、メインCPU101は、V入賞口スイッチ116bが「ON」になったか否かを判定する。V入賞口スイッチ116bが「ON」になったと判定した場合(ステップS651:YES)、V入賞コマンドをセットし(ステップS652)、大当たり遊技フラグを「ON」にする(ステップS653)。
メインCPU101は、ステップS653の処理を実行した場合、ステップS647の処理を実行した場合、又は小入賞口スイッチ116aが「ON」ではないと判定した場合(ステップS649:NO)、小入賞口19の開放開始から規定開放時間が経過したか否かを判定する(ステップS654)。具体的には、上記ステップS647の処理によって計測が開始された開放時間が、メインROM102に記憶されている規定開放時間に達したか否かを判定する。
メインCPU101は、規定開放時間が経過していないと判定した場合(ステップS654:NO)、メインRAM103に記憶されている今回のラウンド遊技における遊技球の入賞数Xが、メインROM102に記憶されている大入賞口13の閉塞タイミングを規定する遊技球数Xmax(例えば「9」)と一致するか否かを判定する(ステップS655)。ここで、入賞数Xが遊技球数Xmaxと一致しないと判定された場合(ステップS655:NO)、ステップS7の大入賞口制御処理に処理が進められる。
一方、メインCPU101は、入賞数Xが遊技球数Xmaxと一致すると判定した場合(ステップS655:YES)、小入賞口制御部118にステップS646の処理で開始した小入賞口19の開放制御を終了させる(ステップS656)。
ステップS656の処理に続いて、メインCPU101は、エンディング時間の計測を開始し(ステップS657)、エンディングコマンドをメインRAM103にセットする(ステップS658)。このエンディングコマンドは、小当たり遊技のラウンド遊技が終了したことを通知するコマンドであり、ステップS9の送信処理によって演出制御基板130に送信される。
メインCPU101は、ステップS658の処理を実行した場合、エンディング時間が経過したか否かを判定する(ステップS659)。エンディング時間が経過していないと判定された場合(ステップS659:NO)、ステップS7の大入賞口制御処理に処理が進められる。
メインCPU101は、エンディング時間が経過したと判定した場合(ステップS659:YES)、小当たり遊技を終了させるために、小当たり遊技フラグを「OFF」に設定する(ステップS660)。
[遊技制御基板100による大入賞口開放制御処理]
以下、図46を参照しつつ、遊技制御基板100によって実行される大入賞口開放制御処理について説明する。この大入賞口制御処理は、メインROM102に記憶されている大当たり時の図柄決定テーブルに基づいて選択した大当たり遊技を実行する処理である。ここで、図46は、図38のステップS7における大入賞口開放制御処理の詳細フローチャートである。メインCPU101は、ステップS5の小入賞口開放制御処理に続いて、図38に例示されるように、大当たり遊技フラグが「ON」に設定されているか否かを判定する(ステップS601)。ここで、大当たり遊技フラグが「ON」に設定されていないと判定された場合(ステップS601:NO)、ステップS8の賞球処理に処理が進められる。
メインCPU101は、大当たり遊技フラグが「ON」に設定されていると判定した場合(ステップS601:YES)、停止中処理によって大当たり遊技に係るオープニングコマンドをセットしてからの経過時間が所定のオープニング時間に達したか否かに基づいて、大当たり遊技のオープニング中であるか否かを判定する(ステップS602)。ここで、オープニング中であると判定した場合(ステップS602:YES)、同じく経過時間が所定のオープニング時間に達したか否かに基づいて、オープニング時間が経過したか否かを判定する(ステップS603)。ここで、オープニング時間が経過していないと判定された場合(ステップS603:NO)、ステップS8の賞球処理に処理が進められる。
メインCPU101は、オープニング時間が経過したと判定した場合(ステップS603:YES)、大当たり遊技のラウンド数Rmax、大入賞口制御部117の動作パターン等を設定して、その設定情報をメインRAM103に格納する(ステップS604)。このステップS604の処理が実行されることによって、ラウンドと次のラウンドとの間のインターバル時間、最終ラウンド終了後のエンディング時間等の大当たり遊技に関する各種時間も併せて設定される。
ステップS604の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている大入賞口13への遊技球の入賞数Yをリセットし(ステップS605)、同じくメインRAM103に記憶されている大当たり中のラウンド数Rを「1」加算した値に更新する(ステップS606)。このラウンド数Rは、大当たり開始前は「0」に設定されており、ステップS606の処理が行われる毎に「1」加算される。
ステップS606の処理に続いて、メインCPU101は、大入賞口の開放制御を開始する(ステップS607)。次に、メインCPU101は、この開放制御が開始されてからの経過時間である開放時間の計測を開始する(ステップS608)。そして、大入賞口13を開放するラウンド遊技が開始されたことを通知するラウンド開始コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS609)。
メインCPU101は、大当たり遊技におけるオープニング中ではないと判定した場合(ステップS602:NO)、例えばメインRAM103に記憶されている現在の状態が大当たり遊技におけるどの時点であるかを示す情報に基づいて、最終ラウンド終了直後のエンディング中であるか否かを判定する(ステップS611)。ここで、エンディング中であると判定された場合(ステップS611:YES)、後述するステップS625に処理が進められる。
メインCPU101は、大当たり遊技におけるエンディング中ではないと判定した場合(ステップS611:NO)、例えばメインRAM103に記憶されている現在の状態が大当たり遊技におけるどの時点であるかを示す情報に基づいて、インターバル中(ラウンドと次のラウンドとの間)であるか否かを判定する(ステップS612)。ここで、インターバル中であると判定した場合(ステップS612:YES)、前回のラウンド遊技終了時に大入賞口13が閉塞してから、ステップS604の処理によって設定されたインターバル時間が経過したか否かを判定する(ステップS613)。ここで、インターバル時間が経過したと判定された場合(ステップS613:YES)、次のラウンド遊技を開始するタイミングになっているため、上記ステップS605に処理が進められる。逆に、インターバル時間が経過していないと判定された場合(ステップS613:NO)、ステップS8の賞球処理に処理が進められる。
一方、メインCPU101は、インターバル中ではないと判定した場合(ステップS612:NO)、ラウンド遊技中であると判断して、大入賞口スイッチが「ON」になったか否かを判定する(ステップS614)。具体的には、大入賞口スイッチ115からの検知信号の有無に基づいて、大入賞口スイッチ115が「ON」になったか否かを判定する。
ここで、メインCPU101は、大入賞口スイッチ115が「ON」になったと判定した場合(ステップS614:YES)、大入賞口13に1個の遊技球が入賞したと判断して、遊技球の入賞数Yを「1」加算した値に更新する(ステップS615)。
メインCPU101は、ステップS615の処理を実行した場合、ステップS609の処理を実行した場合、又は大入賞口スイッチ115が「ON」ではないと判定した場合(ステップS614:NO)、大入賞口13の開放開始から規定開放時間が経過したか否かを判定する(ステップS616)。具体的には、上記ステップS608の処理によって計測が開始された開放時間が、メインROM102に記憶されている規定開放時間に達したか否かを判定する。
メインCPU101は、規定開放時間が経過していないと判定した場合(ステップS616:NO)、メインRAM103に記憶されている今回のラウンド遊技における遊技球の入賞数Yが、メインROM102に記憶されている大入賞口13の閉塞タイミングを規定する遊技球数Ymax(例えば「9」)と一致するか否かを判定する(ステップS617)。ここで、入賞数Yが遊技球数Ymaxと一致しないと判定された場合(ステップS617:NO)、ステップS8の賞球処理に処理が進められる。
一方、メインCPU101は、入賞数Yが遊技球数Ymaxと一致すると判定した場合(ステップS617:YES)、又は規定開放時間が経過したと判定した場合(ステップS616:YES)、大入賞口制御部117にステップS607の処理で開始した大入賞口13の開放制御を終了させる(ステップS618)。
ステップS618の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている大当たり遊技の現在のラウンド数Rが、上記ステップS604の処理によって設定されたラウンド数Rmaxと一致するか否かを判定する(ステップS619)。ここで、ラウンド数Rがラウンド数Rmaxと一致しないと判定した場合(ステップS619:NO)、次のラウンド遊技の開始タイミングを制御するために、大入賞口13が閉塞されてからの経過時間であるインターバル時間の計測を開始する(ステップS620)。このステップS620の処理によって計測が開始されたインターバル時間は、上記ステップS613の処理に使用される。
一方、メインCPU101は、ラウンド数Rがラウンド数Rmaxと一致すると判定した場合(ステップS619:YES)、エンディング時間の計測を開始し(ステップS622)、メインRAM103に記憶されているラウンド数Rをリセットし(ステップS623)、エンディングコマンドをメインRAM103にセットする(ステップS624)。このエンディングコマンドは、最後のラウンド遊技が終了したことを通知するコマンドであり、ステップS8の送信処理によって演出制御基板130に送信される。なお、このエンディングコマンドは、大当たり遊技終了後の遊技状態に関する情報(遊技情報)を含む。
メインCPU101は、ステップS624の処理を実行した場合、又はエンディング中であると判定した場合(ステップS611:YES)、設定エンディング時間が経過したか否かを判定する(ステップS625)。具体的には、上記ステップS622の処理によって計測を開始したエンディング時間が、上記ステップS604の処理によって設定された設定エンディング時間に達したか否かを判定する。ここで、エンディング時間が経過していないと判定された場合(ステップS625:NO)、ステップS8の賞球処理に処理が進められる。
メインCPU101は、設定エンディング時間が経過したと判定した場合(ステップS625:YES)、大当たり遊技終了後のパチンコ遊技機1の遊技状態を設定する遊技状態設定処理を実行する(ステップS626)。この処理により、大当たり図柄(又は小当たり図柄)の種類に対応した遊技状態に設定される。
メインCPU101は、ステップS626の処理の後、大当たり遊技を終了させるために、大当たり遊技フラグを「OFF」に設定する(ステップS627)。
[演出制御基板130によるタイマ割込み処理]
以下、図47を参照しつつ、演出制御基板130において実行されるタイマ割込み処理について説明する。ここで、図47は、演出制御基板130において実行されるタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。以下では、図47〜図50に示す処理を演出制御基板130が行うものとして説明するが、これらの処理の一部または全部は、演出制御基板130、画像音響制御基板140、およびランプ制御基板150の何れにおいて実行されてもよい。
演出制御基板130におけるサブCPU131は、遊技制御基板100で行われるタイマ割込み処理と同様に、図47に例示される一連の処理を一定時間(例えば4ミリ秒)毎に繰り返し実行する。なお、図47〜図50に示す処理は、サブROM132に記憶されているプログラムに基づいてサブCPU131が発行する命令に従って行われる。
サブCPU131は、まず、遊技制御基板100からのコマンドに応じた処理を行うコマンド受信処理を実行した後(ステップS10)、送信処理を実行する(ステップS30)。コマンド受信処理では、遊技制御基板100及びランプ制御基板150から各種コマンドを受信したことに応じた処理が行われる。具体的には、サブCPU131は、例えば、遊技制御基板100から遊技情報としてのコマンドを受信し、受信したコマンドに応じた演出内容を設定する。例えば、サブCPU131は、特別図柄の変動パターンに対応した変動演出パターンを決定し、決定した変動演出パターンにおいて実行可能な予告演出の実行の有無および内容を決定する。そして、サブCPU131は、例えば、決定した演出の実行を指示するコマンドを生成し、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信する。これにより、演出制御基板130において決定された内容の演出が、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150で実行されることになる。コマンド受信処理については、図48に基づいて後に詳述する。
ステップS30の処理に続いて、サブCPU131は、データ転送処理を行う(ステップS50)。サブCPU131は、例えば、各演出の開始に伴って枠ランプ37等を発光制御させたり演出役物7等を制御(例えば動作)させたりするために、画像音響制御基板140から送信されたデータをランプ制御基板150に転送する。このデータ転送処理が行われることによって、例えば、液晶画面5に表示された演出画像やスピーカ24によって出力された演出音と連動して盤ランプ25と枠ランプ37とを発光させる発光制御が行われたり、演出役物7が動作されたりする。以上でサブCPU131は、図47に示す処理を終了する。
[演出制御基板130によるコマンド受信処理]
図48は、図47のステップS10におけるコマンド受信処理の詳細フローチャートである。図48に例示されるように、サブCPU131は、まず、遊技制御基板100又はランプ制御基板から送信されたコマンドを受信したか否かを判定する(ステップS11)。ここで、コマンドを受信していないと判定された場合(ステップS11:NO)、ステップS30に処理が進められる。
サブCPU131は、コマンドを受信したと判定した場合(ステップS11:YES)、そのコマンドがステップS2112(図40参照)又はステップS2212(図41参照)の処理に応じて遊技制御基板100から送信された保留コマンドであるか否かを判定する(ステップS12)。ここで、受信したコマンドが保留コマンドではないと判定された場合(ステップS12:NO)、後述するステップS14に処理が進められる。
サブCPU131は、受信したコマンドが保留コマンドであると判定した場合(ステップS12:YES)、保留コマンド受信処理を実行する(ステップS13)。保留コマンド受信処理では、サブCPU131は、例えば、キャラストック演出で表示されるパネル画像の表示態様に関する設定情報等を含むアイコン表示コマンドをサブRAM133にセットする。この保留コマンド受信処理については、図49に基づいて後に詳述する。
サブCPU131は、受信したコマンドが保留コマンドではないと判定した場合(ステップS12:NO)、そのコマンドがステップS311(図42参照)の処理に応じて遊技制御基板100から送信された変動開始コマンドであるか否かを判定する(ステップS14)。ここで、受信したコマンドが変動開始コマンドではないと判定された場合(ステップS14:NO)、後述するステップS16に処理が進められる。
サブCPU131は、受信したコマンドが変動開始コマンドであると判定した場合(ステップS14:YES)、変動開始コマンド受信処理を実行する(ステップS15)。変動開始コマンド受信処理では、サブCPU131は、例えば、変動開始コマンドに含まれる特別図柄の変動パターンに対応した変動演出パターンを決定する。この変動開始コマンド受信処理については、図50に基づいて後に詳述する。
サブCPU131は、受信したコマンドが変動開始コマンドではないと判定した場合(ステップS14:NO)、そのコマンドがステップS316(図42参照)の処理に応じて遊技制御基板100から送信された図柄確定コマンドであるか否かを判定する(ステップS16)。サブCPU131は、図柄確定コマンドであると判定した場合(ステップS16:YES)、変動演出終了コマンドをサブRAM133にセットする(ステップS17)。この変動演出終了コマンドがステップS30の送信処理によって画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信されることで、特別図柄の停止表示に伴って、装飾図柄55および小図柄56が液晶画面5に停止表示されることになる。
サブCPU131は、受信したコマンドが図柄確定コマンドではないと判定した場合(ステップS16:NO)、そのコマンドがランプ制御基板150から送信された操作コマンドであるか否かを判定する(ステップS18)。この操作コマンドは、ランプ制御基板150のランプCPU151が演出ボタン26や演出キー27の操作を検知した場合に、その情報を通知するためにランプ制御基板150から送信されるコマンドである。操作コマンドは、演出ボタン26及び演出キー27のうち何れが操作されたかを示す情報、演出キー27が操作された場合にはどのキーが操作されたかを示す情報等を含む。
サブCPU131は、操作コマンドを受信したと判定した場合(ステップS18:YES)、操作演出開始コマンドをサブRAM133にセットする(ステップS19)。このコマンドは、ステップS30の送信処理によって画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信される。画像音響制御基板140は、このコマンドを受信することで、例えば、有効期間中の操作に応じて液晶画面5やスピーカ24を用いて画像や音による演出(例えば、モード選択演出での選択された状態のモード画像を切り換える演出)を実行できる。また、ランプ制御基板150は、このコマンドを受信することで、有効期間中の操作に応じて各種ランプを発光させる演出を実行できる。
一方、受信したコマンドが操作コマンドではないと判定された場合(ステップS18:NO)、そのコマンドに応じた処理を実行する(ステップS20)。一例として、サブCPU131は、遊技制御基板100から送信されたオープニングコマンドを受信したと判定した場合は、大当たり(又は小当たり)の種類に対応した大当たり遊技(又は小当たり遊技)の演出の開始を指示するオープニングコマンドをセットする。
[演出制御基板130による保留コマンド受信処理]
図49は、図48のステップS13における保留コマンド受信処理の詳細フローチャートである。サブCPU131は、受信したコマンドが保留コマンドであると判定した場合(ステップS12:YES)、図49に例示されるように、サブRAM133に記憶されている特別図柄判定の保留数を「1」加算した値に更新する(ステップS1311)。具体的には、保留コマンド内の事前判定情報に含まれている入賞始動口情報に基づいて、第1特別図柄判定に係る保留コマンドであるか或いは第2特別図柄判定に係る保留コマンドであるかを判別し、その判別結果に基づいて、第1特別図柄判定に係る保留数又は第2特別図柄判定に係る保留数を「1」加算した値に更新する。
ステップS1311の処理に続いて、サブCPU131は、受信した保留コマンドに含まれている事前判定情報を解析し、解析結果をサブRAM133に格納する(ステップS1312)。
ステップS1312の処理に続いて、サブCPU131は、特別態様の保留アイコン54を表示する演出、及びキャラストック演出で2〜5枚目のパネル画像を表示する演出といった先読み演出が実行可能か否かを判定する(ステップS1313)。例えば、何れかの先読み演出の設定情報がサブRAM133に既にセットされている場合、大当たり遊技中(又は小当たり遊技中)である場合等に、先読み演出が実行可能ではないと判定される。先読み演出を実行可能ではないと判定された場合(ステップS1313:NO)、ステップS1316に処理が進められる。
サブCPU131は、先読み演出が実行可能であると判定した場合(ステップS1313:YES)、大当たり図柄Cの停止表示後1〜3回転目の第2特別図柄の変動表示中であるか否かを決定する(ステップS1314)。サブCPU131は、ステップS1314の処理でYESと判定した場合、キャラストック演出(2〜5人目)の処理を実行する(ステップS1315)。この処理については図19(B)を参照して上述したため、ここでの説明は省略する。
ステップS1315の処理を実行した場合、ステップS1314の処理でNOと判定された場合、又はステップS1313の処理でNOと判定された場合、サブCPU131は、アイコン表示コマンドをサブRAM133にセットする(ステップS1316)。アイコン表示コマンドは、保留コマンドに基づいて得られた事前判定情報、入賞始動口情報等を含み、ステップS1315の処理が実行された場合にはこれらの設定情報を含む。このアイコン表示コマンドは、ステップS30の送信処理(図47参照)によって画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信される。これにより、演出制御基板130において決定された態様でキャラストック演出が、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150によって実現されることになる。
[演出制御基板130による変動開始コマンド受信処理]
以下、図50を参照しつつ、遊技制御基板100から送信された変動開始コマンドを受信したことに応じて演出制御基板130において実行される変動開始コマンド受信処理について説明する。ここで、図50は、図48のステップS15における変動開始コマンド受信処理の詳細フローチャートである。
図48に例示されるように、サブCPU131は、遊技制御基板100から受信したコマンドが変動開始コマンドであると判定した場合(ステップS14:YES)、変動演出パターン乱数を取得してサブRAM133に格納する(ステップS1511)。変動演出パターン乱数等のサブCPU131は、変動開始コマンドを受信した時点の値を変動演出パターン乱数として取得する。
ステップS1511の処理に続いて、サブCPU131は、遊技制御基板100から受信した変動開始コマンドを解析する(ステップS1512)。変動開始コマンドには、上述したように、大当たり判定(図43参照)の判定結果を示す大当たりか否かの情報、特別図柄の種類、特別図柄の変動パターンの設定情報、遊技機1の遊技状態を示す情報等が含まれている。サブCPU131は、この処理を行うことにより、変動演出パターンを決定するのに必要な情報を得ている。
ステップS1512の処理に続いて、サブCPU131は、大当たり図柄Cの停止表示後3回転目の第2特別図柄の変動表示であるか否かを判定する(ステップS1513)。ステップS1513の処理でYESと判定された場合、サブCPU131は、キャラストック演出(1人目)の処理を実行する(ステップS1514)。この処理については図19(A)を参照して上述したため、ここでの説明は省略する。
ステップS1513の処理でNOと判定された場合、サブCPU131は、現在の遊技状態に応じた変動演出パターンテーブル(不図示)を参照して変動演出パターンを決定する(ステップS1515)。変動演出パターンテーブルは、予めサブROM132に記憶されたテーブルであり、大当たりか否かと、大当たり図柄(又は小当たり図柄)の種類と、特別図柄の変動パターンとの組み合わせのそれぞれに対して1又は複数種類の変動演出パターンが予め対応付けられたテーブルである。サブROM132には、例えば、非時短状態用と、時短状態用との変動演出パターンテーブルが予め記憶されている。
ステップS1515の処理を実行した場合、又はステップS1514の処理を実行した場合、サブCPU131は、これらの処理で決定した設定内容を含む変動演出開始コマンドをセットする(ステップS1516)。変動演出開始コマンドは、ステップS30の送信処理(図47参照)によって画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信される。これにより、演出制御基板130において決定された態様の変動演出が、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150によって実現されることになる。
ステップS1516の処理に続いて、サブCPU131は、サブRAM133に格納されている保留数の値を「1」減算する(ステップS1517)。以上でサブCPU131は、図50に示す処理を終了する。
[本実施形態の作用効果]
本実施形態では、キャラA〜Dを用いたバトル演出を実行可能である。バトル演出は、敵と戦うキャラクタがキャラA〜Dである順に信頼度が高い。バトル演出に用いるキャラクタは、第2特別図柄判定の保留数が1増えたことに応じて、事前判定情報(具体的には、小当たりであるかハズレであるか)に基づいて表示領域81a〜85a(及び表示領域81b〜85b)に表示可能である。表示領域81a〜85a(及び表示領域81b〜85b)に例えばキャラAが表示される場合よりも、キャラDが表示される場合の方が、信頼度が高い。これにより、キャラクタを用いて、表示領域81a〜85a(及び表示領域81b〜85b)のキャラクタの種類とバトル演出の種類とで信頼度を示唆可能である。
また、本実施形態では、バトル演出に用いるキャラクタとしてキャラA〜Dを表示可能である。キャラクタの信頼度は、キャラA〜Dの順に高い。小当たりとならない場合は、パネル画像(及びキャラアイコン81〜85)として同じ種類のキャラクタを5人同時に表示不可能である。一方、小当たりとなる場合は、パネル画像(及びキャラアイコン81〜85)として同じ種類のキャラクタを5人同時に表示可能である。これにより、パネル画像(及びキャラアイコン81〜85)が表示されるときに遊技者にドキドキ感を与え、遊技の興趣を高めることが可能である。
また、本実施形態では、キャラアイコン81〜85が表示された表示領域81b〜85b以外の表示領域において、バトル発展演出およびバトル演出が実行される。本実施形態では、キャラA〜Dを用いたバトル演出を実行可能であり、敵と戦うキャラクタがキャラA〜Dである順に信頼度が高い。表示領域81b〜85bにおいて、キャラアイコン81〜85を表示する演出を実行可能である。キャラアイコン81〜85としてキャラA〜Dを表示可能であり、例えばキャラAが表示される場合よりも、キャラDが表示される場合の方が、信頼度が高い。これにより、表示領域81b〜85b以外の表示領域と、表示領域81b〜85bとによってそれぞれ信頼度を示唆することが可能である。
また、本実施形態では、グループAの演出モードである夜モード、バトルモード、及び神ラッシュと、グループBの演出モードである新章モード、ストーリーモード、及び悪魔ラッシュとのうちの何れかの演出モードで演出を実行する。演出モードを選択可能なモード選択演出として、選択された状態にて1つのモード画像を表示し、選択されていない状態にて他のモード画面を表示する。サブRAM133は、演出モードを示す設定値を記憶可能である。モード選択演出を実行する際に、例えば、夜モードを示す設定値が記憶されている場合には、グループAを示すモード画像を選択された状態にて表示し、グループBを示すモード画像を選択されていない状態にて表示する。モード選択演出を実行する際に、例えば、新章モードを示す設定値が記憶されている場合には、グループBを示すモード画像を選択された状態にて表示し、グループAを示すモード画像を選択されていない状態にて表示する。これにより、モード選択演出が実行される度に何度も演出モードを選択し直す煩わしさを解消することが可能である。
また、本実施形態では、モード選択演出で選択された状態にて表示されたモード画像は、選択されていない状態にて表示されたモード画像よりも大きい。これにより、選択された状態にて表示されたモード画像を優先的に表示でき、分かり易くできる。
また、本実施形態では、モード選択演出で選択された状態にて表示されたモード画像は、選択されていない状態にて表示されたモード画像よりも優先して表示される。これにより、モード画像がどのように配置されていても、選択された状態にて表示されたモード画像を優先的に表示できる。
また、本実施形態では、変動演出中に群演出を実行可能である。変動演出には、例えば、SPリーチ演出、SPSPリーチ演出、再抽選演出、復活演出がある。SPリーチ演出中またはSPSPリーチ演出中に群演出が実行された場合、小当たりとなる期待度が高いことが示唆される。再抽選演出中に群演出が実行された場合、小当たり図柄2となることが示唆される。復活演出直前のリーチハズレ目の仮停止表示中に群演出が実行された場合、小当たり図柄3となることが示唆される。これにより、実行されるタイミングによって同一態様の群演出を用いて異なる内容を示唆可能である。
[変形例]
本発明は、例えば、1種タイプの遊技機、回胴式遊技機、スロットマシン等の他の遊技機にも適用可能である。
なお、遊技者が操作することによって操作情報を入力するための操作手段はどのようなものでもよい。操作手段として、例えば、遊技者が指でタッチ操作を行うことによって操作情報を入力可能な表示画面であるタッチパネルを備えてもよい。また、遊技者がガラス板へのタッチ操作を行うことによって操作情報を入力可能なように、枠部材3に備えられた光センサ等を操作手段としてもよい。
なお、画像音響制御基板140及びランプ制御基板150において実行される処理の一部を演出制御基板130に実行させたり、或いは、演出制御基板130において実行される処理の一部を画像音響制御基板140又はランプ制御基板150に実行させたりしてもよい。また、演出制御基板130と、画像音響制御基板140と、ランプ制御基板150との何れを一体に構成してもよく、一例として、演出制御基板130と画像音響制御基板150とにおいて実行される処理を1つの制御基板で実行させてもよい。
また、上記実施形態において説明した遊技機1の構成や各部材の発光態様および動作態様は単なる一例に過ぎず、他の構成、発光態様、及び動作態様であっても本発明を実現できることは言うまでもない。また、上述したフローチャートにおける処理の順序、設定値、判定に用いられる閾値等は単なる一例に過ぎず、本発明の範囲を逸脱しなければ他の順序や値であっても、本発明を実現できることは言うまでもない。上記実施形態で例示した説明図等も単なる一例であって、他の態様であってもよい。
なお、上述した演出は単なる一例であり、本発明は、上記実施形態に限定されず、様々な変形および応用が可能である。また、上記実施形態および変形例は互いに適用可能であり、様々な組み合わせで本発明が実現されてもよい。