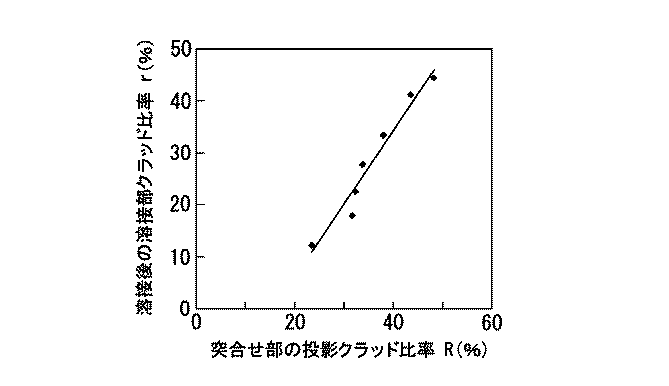JP2018008310A - 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 - Google Patents
電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2018008310A JP2018008310A JP2016177940A JP2016177940A JP2018008310A JP 2018008310 A JP2018008310 A JP 2018008310A JP 2016177940 A JP2016177940 A JP 2016177940A JP 2016177940 A JP2016177940 A JP 2016177940A JP 2018008310 A JP2018008310 A JP 2018008310A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- clad steel
- clad
- steel strip
- steel pipe
- welded
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 152
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 152
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims abstract description 22
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 68
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 21
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 11
- 238000003466 welding Methods 0.000 abstract description 57
- 238000002788 crimping Methods 0.000 abstract 1
- 239000002648 laminated material Substances 0.000 description 31
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 18
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 18
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 5
- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4
- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 4
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 4
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
【解決手段】炭素鋼または低合金鋼からなる第1層11と、ステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層12とが圧着されてなるクラッド鋼帯10を用意する。クラッド鋼帯の幅方向両端部を第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が第2層側からクラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdがクラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行う。その後、クラッド鋼帯を管状に成形し、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接する。
【選択図】図2
Description
[1]母材である炭素鋼または低合金鋼からなる第1層と、合せ材であるステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層とが圧着されてなるクラッド鋼帯を用意し、
前記クラッド鋼帯の幅方向両端部を前記第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が前記第2層側から前記クラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdが前記クラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、下記(1)式で定義される投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行い、
その後、前記クラッド鋼帯を管状に成形し、
該クラッド鋼帯の前記幅方向両端部を、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接して、電縫溶接クラッド鋼管を得る
ことを特徴とする電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。
記
R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)
ここで、R:投影クラッド比率
tc *:ルート面における前記第2層の厚み(mm)
d:開先深さ(mm)
t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm)
ここで、h:偏平割れ高さ(mm)
D:管外径(mm)
記
R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)
ここで、R:投影クラッド比率
tc *:ルート面における前記第二層の厚み(mm)
d:開先深さ(mm)
t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm)
表1に示す成分組成を有し、表2に示す厚みを有する母材である低炭素低合金鋼と、表1に示す成分組成を有し、表2に示す厚みを有する合せ材であるステンレス鋼(SUS316L)からなる2層の種々のクラッド熱延鋼帯を用意した。図1に示したように、アンコイラー30とロール成形機50との間に、図4に示す圧延式開先加工機40を配置した電縫溶接鋼管製造設備により、用意した各クラッド熱延鋼帯を素材として、クラッド鋼帯の幅方向両端部に表2に示す形状の開先加工を行い、表2に示すアプセット量として、外径300mmの電縫溶接クラッド鋼管を製造した。なお、合せ材を内層、母材を外層とした。
表3に示す成分組成を有し、表4に示す厚みを有する母材である低炭素低合金鋼と、表3に示す成分組成を有し、表4に示す厚みを有する合せ材であるニッケル含有合金(Alloy625)からなる2層の種々のクラッド熱延鋼帯を用意した。実施例1と同様の方法で、表4に示す形状の開先加工を行い、表4に示すアプセット量として、外径300mmの電縫溶接クラッド鋼管を製造した。なお、合せ材を内層、母材を外層とした。
11 第1層(母材)
12 第2層(合せ材)
13 クラッド界面
14 溶接シーム部
15 メタルフロー
20 電縫溶接クラッド鋼管
30 アンコイラー
40 開先加工機
42 上側サイドロール
42A 圧延部
44 下側サイドロール
50 ロール成形機
60 高周波加熱装置
70 スクイズロール
90 ビード切削機
96 切断機
θ ベベル角度
d 開先深さ
t クラッド鋼帯(鋼管)の厚み
tm 第1層(母材)の厚み
tc 第2層(合せ材)の厚み
tc * ルート面における第2層(合せ材)の厚み
tw 溶接シーム部における第2層の厚み
Claims (2)
- 母材である炭素鋼または低合金鋼からなる第1層と、合せ材であるステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層とが圧着されてなるクラッド鋼帯を用意し、
前記クラッド鋼帯の幅方向両端部を前記第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が前記第2層側から前記クラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdが前記クラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、下記(1)式で定義される投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行い、
その後、前記クラッド鋼帯を管状に成形し、
該クラッド鋼帯の前記幅方向両端部を、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接して、電縫溶接クラッド鋼管を得る
ことを特徴とする電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。
記
R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)
ここで、R:投影クラッド比率
tc *:ルート面における前記第2層の厚み(mm)
d:開先深さ(mm)
t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm) - 得られた前記電縫溶接クラッド鋼管は、JIS G 3445の規定に準拠した90°偏平試験における偏平値h/Dが0.3未満を満足するものである、請求項1に記載の電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。
ここで、h:偏平割れ高さ(mm)
D:管外径(mm)
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016132986 | 2016-07-05 | ||
| JP2016132986 | 2016-07-05 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2018008310A true JP2018008310A (ja) | 2018-01-18 |
| JP6520876B2 JP6520876B2 (ja) | 2019-05-29 |
Family
ID=60994777
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2016177940A Active JP6520876B2 (ja) | 2016-07-05 | 2016-09-12 | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6520876B2 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6343777A (ja) * | 1986-08-07 | 1988-02-24 | Kawasaki Steel Corp | クラツド鋼管の製造方法 |
-
2016
- 2016-09-12 JP JP2016177940A patent/JP6520876B2/ja active Active
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6343777A (ja) * | 1986-08-07 | 1988-02-24 | Kawasaki Steel Corp | クラツド鋼管の製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6520876B2 (ja) | 2019-05-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6323626B1 (ja) | クラッド溶接管およびその製造方法 | |
| JP6265311B1 (ja) | 電縫溶接ステンレスクラッド鋼管およびその製造方法 | |
| JP6319528B1 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管およびその製造方法 | |
| KR101257360B1 (ko) | 고밀도 에너지 빔으로 접합한 용접 강관 및 그의 제조 방법 | |
| JP6164368B2 (ja) | 電縫溶接ステンレスクラッド鋼管の製造方法 | |
| WO2013051249A1 (ja) | 溶接熱影響部靱性に優れた溶接鋼管およびその製造方法 | |
| JP2003136130A (ja) | シーム溶接部靭性に優れた内外面サブマージアーク溶接鋼管の製造方法 | |
| JP6500810B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |
| JP6536518B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |
| JP6520876B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |
| WO2023058463A1 (ja) | ステンレス鋼と銅の接合体およびその製造方法、ならびに、ステンレス鋼と銅の接合方法 | |
| JPH09168878A (ja) | 2相ステンレス溶接鋼管の製造方法 | |
| JP7435909B1 (ja) | 電縫管およびその製造方法 | |
| JP7456559B1 (ja) | ステンレス鋼と銅の接合体およびその製造方法、ならびに、ステンレス鋼と銅の接合方法 | |
| JP4586515B2 (ja) | 溶接部に母材並の二次加工性を有する溶接鋼管及びその製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180221 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20190128 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190212 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190320 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190402 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190415 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6520876 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |