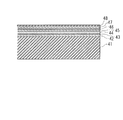JP5019120B2 - 検出センサ - Google Patents
検出センサ Download PDFInfo
- Publication number
- JP5019120B2 JP5019120B2 JP2007304936A JP2007304936A JP5019120B2 JP 5019120 B2 JP5019120 B2 JP 5019120B2 JP 2007304936 A JP2007304936 A JP 2007304936A JP 2007304936 A JP2007304936 A JP 2007304936A JP 5019120 B2 JP5019120 B2 JP 5019120B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- vibrator
- actuator
- vibration
- detection sensor
- sensor according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01G—WEIGHING
- G01G3/00—Weighing apparatus characterised by the use of elastically-deformable members, e.g. spring balances
- G01G3/12—Weighing apparatus characterised by the use of elastically-deformable members, e.g. spring balances wherein the weighing element is in the form of a solid body stressed by pressure or tension during weighing
- G01G3/16—Weighing apparatus characterised by the use of elastically-deformable members, e.g. spring balances wherein the weighing element is in the form of a solid body stressed by pressure or tension during weighing measuring variations of frequency of oscillations of the body
- G01G3/165—Constructional details
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Micromachines (AREA)
Description
また近年、燃料電池の開発が盛んに行われている。燃料電池は水素を用いるため、水素ステーションや、燃料電池を使用する車両や装置、機器等において、水素の漏れが無いか監視するのが好ましい。このような用途にも、上記センサは適用できる。
上記用途以外にも、特定種の分子を吸着することで、その吸着の有無あるいは吸着量を検出するセンサは、例えば食物の鮮度や成分分析、快適空間を提供・維持するための環境制御、さらには、人体等、生体の状態検知等に用いることが考えられる。
こうした従来のカンチレバーの共振周波数変化を用いてガス検知をする方法においては、センサ自体を、微細加工技術で製作する大きさ数十〜数百μmのカンチレバーで構成することができる。したがって、センサの小型化が可能であり、また前述のように振動Q値も高くできる特徴があるので、小型化、高感度化の面で優れた構成であると言える。
圧電層を形成する圧電材料としては、Pb(鉛)、Zr(ジルコニウム)、Ti(チタニウム)を含む原料から形成した、いわゆる強誘電体薄膜が注目されている。
ここで、カンチレバー表面には、強誘電体薄膜からなる圧電層や電極層が設けられている。これら圧電層や電極層は、それ自体が減衰を有し、カンチレバーの振動エネルギにロスが生じる。その結果、カンチレバーのQ値の低下を招き、センサとしての感度の低下につながる。この点において、現状の技術には改善の余地がある。
本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、より高感度化を図ることのできる検出センサを提供することを目的とする。
このような検出センサにおいては、アクチュエータを振動させると、アクチュエータの振動が連結部材を介して振動子に伝達され、これによって振動子を駆動することができる。このようにして、振動子とは別体に設けたアクチュエータで振動子を振動させることで、従来のように振動子の表面に圧電材料からなる圧電層や駆動電極等を設ける必要がなくなる。その結果、振動子の振動特性が阻害されることなく、高い振動特性で振動子を駆動することができる。
このような検出部は、いかなる方式のものを用いてもよいが、振動子の固定端部近傍に設けられ、振動子の振動によって生じる応力変化を検出するピエゾ抵抗素子からなるものを用いるのが好ましい。
さて、振動子を2次以上の高次の振動モードで駆動する場合、振動子の振幅がゼロとなる節が存在する。そこで、連結部材を、この節の位置、またはその近傍にて振動子に連結するのが好ましい。これにより、振動子を前記の特定の振動モードで駆動すること等が可能となり、エネルギのロスも抑えることができる。
[第一の実施の形態]
図1および図2は、本実施の形態における検出センサ10の構成を説明するための図である。
この図1および図2に示すように、検出センサ10は、検知対象となる特定種の分子(以下、単に分子と称する)を吸着することで、ガスや匂い等の存在(発生)の有無、あるいはその濃度の検出を行うものである。この検出センサ10は、分子を吸着する吸着部20を備えた振動子30、振動子30を駆動するアクチュエータ40、吸着部20への分子の吸着を検出する検出部50とから構成されている。これら振動子30、アクチュエータ40、検出部50は、シリコン系材料からなる基板60に、MEMS技術を用いることによって形成されている。
吸着部20は、無機系材料や、有機系材料からなる膜によって形成することができる。吸着部20を構成する無機系材料とすれば、代表的なものに二酸化チタン(TiO2)があり、吸着効率を高めるために二酸化チタンを多孔体状とするのが好ましい。そして、この吸着部20を、振動子30の上面を覆うように形成するのが好ましい。吸着部20を構成する有機系材料としては、ポリアクリル酸、ポリスチレン、ポリアクリルアミン、 ポリジメチルシロキサン、 ポリ塩化ビニル、 ポリメタクリル酸メチル等のあらゆる高分子等がある。この吸着部20では、特定種の分子のみを吸着する、分子に対する選択性を有したものとすることができ、その選択性は、高分子を形成する官能基や、架橋の状態等の様々な要素で決まると考えられる。
圧電層44を形成する圧電材料としては、Pb、Zr、Tiを含む原料から形成した、いわゆる強誘電体薄膜が注目されている。より詳しくは、圧電層44は、Pb、Zr、Tiを含む材料(以下、これをPZT材料と称することがある)から形成され、これが結晶化した状態で、例えば500nm〜2μm程度の厚さに形成されている。この圧電層44は、例えば一層当たり100〜130nmの薄膜を複数層積層することで、上記の厚さを実現することができる。
このような材料としては、例えば、Pbペロブスカイト二成分・三成分系強誘電体セラミックス、非鉛系ペロブスカイト構造強誘電体セラミックス、BaTiO3(チタン酸バリウム)セラミックス、KNbO3(ニオブ酸カリウム)−NaNbO3系強誘電体セラミックス、(Bi1/2Na1/2)TiO3系強誘電体セラミックス、タングステン・ブロンズ型強誘電体セラミックス、(Ba1−xSrx)2NaNb5O15[BSNN]、BaNa1−xBix/3Nb5O15[BNBN]、ビスマス層状構造強誘電体と粒子配向型強誘電体セラミックス、ビスマス層状構造強誘電体(BLSF)等を用いることができる。
また、PZT材料以外にも、ZnO(酸化亜鉛)や、AlN(窒化アルミニウム)等を圧電層44に用いても良い。
ここで、アクチュエータ40の自由端40bは、振動子30に対し、所定のクリアランスC1を隔てて対向している。アクチュエータ40や振動子30が振動するときには、アクチュエータ40や振動子30の表面近傍には、アクチュエータ40や振動子30に接触する雰囲気(空気)との間で生じる摩擦により境界層が存在する。前記のクリアランスC1を境界層の厚さよりも大きく設定することで、アクチュエータ40と振動子30の挙動が境界層によって互いに影響を受けないようにするのが好ましい。
なお、この矯正ビーム49は、アクチュエータ40に反りが生じていても問題にならないような反り量である場合や、アクチュエータ40の反りを抑えることができた場合には、これを省略することも可能である。
このようにして、振動子30は、振動子30とは別に設けられたアクチュエータ40によって駆動されるのである。このとき、振動子30上の吸着部20に質量を有した物質が付着すると、その質量の影響を受けて振動子30の振動数が変化する。
検出部50としては、いかなる方式を用いてもよいが、ピエゾ抵抗検出方式を用いるのが好ましい。図2に示したように、振動子30の固定端30aの近傍に、検出用ピエゾ抵抗素子51を配置する。さらに、振動子30の振動による応力が作用しない位置に、基準用ピエゾ抵抗素子52を配置する。そして、図示しない処理回路により、検出用ピエゾ抵抗素子51と基準用ピエゾ抵抗素子52における検出値を比較することで、振動子30の振動周波数の変化を検出する。これによって、吸着部20への分子の吸着の有無またはその量を測定することが可能となっている。
ここで、図7は、アクチュエータ40に静的な駆動力を与えたときの、アクチュエータ40および振動子30の挙動の解析結果である。なお、アクチュエータ40および振動子30の挙動は、S1〜S9の9段階の変位で示した(S1が最小、S9が最大であり、濃色であるほど変位が大きい。)。この図7に示すように、振動子30は、固定端30aから自由端30bに行くにしたがいその変位が大きくなっていることがわかる。一方、アクチュエータ40は、カンチレバー式でありながら、その中央部近傍における変位が大きくなっている。これは、アクチュエータ40が、固定端40aと自由端40b側の矯正ビーム49の3点によって支持されているため、極端に大きな変形を振動子30に与えることなく振動を駆動できることを示している。また、アクチュエータ40の残留応力による変形が振動子30に影響しにくいことも示している。
ここで、従来の駆動方式の振動子は、SiO2基材上に、Ti層(バインダ層)、Pt層(電極層)、PZT材料層(圧電層)、Ti相(バインダ層)、Pt層(電極層)、Ti層(バインダ層)、SiO2層(表面保護層)を順次積層したものとした。これに対し本発明における駆動方式の振動子30は、単結晶Siにより形成した。これらの振動子について、幅を90μm、厚さを3.4μm、3.7μm、4.1μmの3通り、長さを150μm、200μm、250μmの3通りとした場合について、Q値を算出した。その結果を表1に示す。
次に、検出センサ10の他の形態について示す。ここでは、振動子30が2次以上の高次の振動モードで挙動する場合についての例を示す。
なお、以下に示す第二の実施の形態における検出センサ10は、上記第一の実施の形態で示した検出センサ10に対し、振動子30とアクチュエータ40とを連結ビーム70で連結する位置が異なるのみであるため、相違点のみを説明し、上記第一の実施の形態と共通する構成についてはその説明を省略する。
図8に示すように、振動子30は、一端が固定端30aとされ、他端が自由端30bとされた片持ち梁状のカンチレバー式である。振動子30を駆動するアクチュエータ40は、振動子30の両側にそれぞれ設けられている。
アクチュエータ40の自由端40bと振動子30との間には、これらを連結する連結ビーム70が設けられている。連結ビーム70は、アクチュエータ40で駆動する振動子30に発生させる振動モードの次数に応じた位置にて、振動子30に連結されている。すなわち、連結ビーム70を、図4に示した、アクチュエータ40によって所定の振動モードで駆動されることで振動子30に生じる振動のノードポイント(振幅がゼロとなる位置)において、振動子30に連結する。
一端を固定端とし、他端を自由端としたビーム状の振動子の振動モードは、次式Ui(x)で表わされる。
Ui(x)=Bi・sin〔{(2i−1)・π/2L}・x〕
ここで、xは振動子の長さ方向における任意の位置における固定端からの距離であり、Ui(x)はxの位置におけるZ方向の変位量、Lは振動子の全長、iは振動モードの次数、Biは振動モードの次数iにおける定数である。
次数iを1、2、3、4とした場合、Ui(x)=0となるのは、以下の通りとなる。
i=1の場合:x=0、
i=2の場合:x=0、2L/3、
i=3の場合:x=0、2L/5、4L/5
i=4の場合:x=0、2L/7、4L/7、6L/7
i=2の場合:x=2L/3、
i=3の場合:x=2L/5、4L/5
i=4の場合:x=2L/7、4L/7、6L/7
ただし、振動子30に対する連結ビーム70を連結するノードポイントは、振動子30の固定端30aに近い側のものを選択するのが好ましい。連結ビーム70を固定端30aから離れた位置で振動子30に連結すると、振動子30の大きな振幅が連結ビーム70に伝達されてしまい、振動子30からのエネルギロスが大きくなってしまうからである。
このようにして、振動子30は、振動子30とは別に設けられたアクチュエータ40によって駆動されるのである。このとき、振動子30上の吸着部20に質量を有した物質が付着すると、その質量の影響を受けて振動子30の振動数が変化する。
これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
Claims (8)
- 一端部が固定された梁状であり、質量を有した物質の付着または吸着により振動特性が変化する振動子と、
一端部が固定された梁状であり、固定端と自由端を結ぶ軸線が前記振動子軸線方向とほぼ直交する方向に一致するように前記振動子の近傍に設けられて、設定された駆動特性で振動するアクチュエータと、
前記アクチュエータと前記振動子を連結し、前記アクチュエータの振動を前記振動子に伝達することで前記振動子を振動させる連結部材と、
前記アクチュエータとは別体で構成され、前記振動子における振動の変化を検出することで、前記物質を検出する検出部と、
を備えることを特徴とする検出センサ。 - 前記アクチュエータは、
振動を生じさせるための圧電材料からなる圧電層と、
前記圧電層に電圧を印加する駆動電極と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の検出センサ。 - 前記圧電層に内在する残留応力による前記アクチュエータ本体の反りを矯正するための矯正部材が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の検出センサ。
- 前記アクチュエータと前記振動子は、前記振動子が振動するときに前記振動子の表面近傍に形成される境界層の厚さよりも大きな間隔を隔てて設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の検出センサ。
- 前記検出部は、前記振動子の固定端部近傍に設けられ、前記振動子の振動によって生じる応力変化を検出するピエゾ抵抗素子からなることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の検出センサ。
- 前記連結部材は、前記振動子が前記アクチュエータによって2次以上の高次の振動モードで駆動されるときに、前記振動子の振幅がゼロとなる節の位置またはその近傍にて前記振動子に連結されることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の検出センサ。
- 前記検出部は、前記振動子に付着した前記物質の量を検出することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の検出センサ。
- 前記物質が特定の分子、あるいは特定の特性または特徴を有する複数種の分子であることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の検出センサ。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007304936A JP5019120B2 (ja) | 2007-03-16 | 2007-11-26 | 検出センサ |
| PCT/JP2008/053793 WO2008114603A1 (ja) | 2007-03-16 | 2008-03-03 | 検出センサ、振動子 |
| CN200880005713.XA CN101617208B (zh) | 2007-03-16 | 2008-03-03 | 检测传感器、振子 |
| US12/555,221 US8336367B2 (en) | 2007-03-16 | 2009-09-08 | Detection sensor, vibrator |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007068570 | 2007-03-16 | ||
| JP2007068570 | 2007-03-16 | ||
| JP2007304936A JP5019120B2 (ja) | 2007-03-16 | 2007-11-26 | 検出センサ |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2008261838A JP2008261838A (ja) | 2008-10-30 |
| JP2008261838A5 JP2008261838A5 (ja) | 2010-07-01 |
| JP5019120B2 true JP5019120B2 (ja) | 2012-09-05 |
Family
ID=39984409
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007304936A Expired - Fee Related JP5019120B2 (ja) | 2007-03-16 | 2007-11-26 | 検出センサ |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8336367B2 (ja) |
| JP (1) | JP5019120B2 (ja) |
| CN (1) | CN101617208B (ja) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5419767B2 (ja) * | 2010-03-24 | 2014-02-19 | オリンパス株式会社 | 検出センサ、物質検出方法 |
| CN102269615B (zh) * | 2011-05-07 | 2012-11-14 | 大连理工大学 | 一种基于槽型悬臂梁结构的微质量传感器 |
| JP5690207B2 (ja) * | 2011-05-11 | 2015-03-25 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 半導体装置 |
| US20130047710A1 (en) * | 2011-08-26 | 2013-02-28 | Purdue Research Foundation | Nonlinear, bifurcation-based mass sensor |
| US9695036B1 (en) | 2012-02-02 | 2017-07-04 | Sitime Corporation | Temperature insensitive resonant elements and oscillators and methods of designing and manufacturing same |
| JP6086347B2 (ja) * | 2013-02-16 | 2017-03-01 | 国立大学法人信州大学 | 共振型質量センサ |
| US9705470B1 (en) | 2014-02-09 | 2017-07-11 | Sitime Corporation | Temperature-engineered MEMS resonator |
| US9712128B2 (en) | 2014-02-09 | 2017-07-18 | Sitime Corporation | Microelectromechanical resonator |
| CN104001660B (zh) * | 2014-04-29 | 2016-05-25 | 国家电网公司 | 吸附式压电激励振子 |
| US10676349B1 (en) | 2016-08-12 | 2020-06-09 | Sitime Corporation | MEMS resonator |
| JP6871823B2 (ja) * | 2017-08-10 | 2021-05-12 | ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 | 果実生育監視システム、及び果実生育監視方法 |
| KR102471291B1 (ko) * | 2018-09-27 | 2022-11-25 | 아이펙스 가부시키가이샤 | 물질 검출 소자 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2849697B2 (ja) | 1993-03-12 | 1999-01-20 | 工業技術院長 | 2自由度振動型マイクロアクチュエータ |
| JPH10282130A (ja) | 1997-04-01 | 1998-10-23 | Canon Inc | プローブとそれを用いた走査型プローブ顕微鏡 |
| CN1243604A (zh) | 1997-09-08 | 2000-02-02 | 日本碍子株式会社 | 压电/电致伸缩器件 |
| JPH11113920A (ja) * | 1997-10-13 | 1999-04-27 | Yasuto Takeuchi | 多周波調和振動を用いる超音波手術装置 |
| JP2000180250A (ja) * | 1998-10-09 | 2000-06-30 | Ngk Insulators Ltd | 質量センサ及び質量検出方法 |
| JP3744913B2 (ja) * | 2003-03-20 | 2006-02-15 | 株式会社オーバル | 渦流量計センサ及び渦流量計 |
| JP2004297951A (ja) | 2003-03-27 | 2004-10-21 | Olympus Corp | 超音波振動子及び超音波モータ |
| JP2006071371A (ja) | 2004-08-31 | 2006-03-16 | Kyoto Univ | カンチレバーおよびその利用 |
-
2007
- 2007-11-26 JP JP2007304936A patent/JP5019120B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-03-03 CN CN200880005713.XA patent/CN101617208B/zh not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-09-08 US US12/555,221 patent/US8336367B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20100107736A1 (en) | 2010-05-06 |
| CN101617208A (zh) | 2009-12-30 |
| CN101617208B (zh) | 2013-03-27 |
| US8336367B2 (en) | 2012-12-25 |
| JP2008261838A (ja) | 2008-10-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5019120B2 (ja) | 検出センサ | |
| JP5083984B2 (ja) | 検出センサ、振動子 | |
| JP5130422B2 (ja) | 検出センサ | |
| JP5242347B2 (ja) | 検出センサ | |
| JP4963159B2 (ja) | 圧電/電歪デバイス | |
| Kabir et al. | Piezoelectric MEMS acoustic emission sensors | |
| JP2009133772A (ja) | 検出センサ、振動子 | |
| US9478728B2 (en) | Piezoelectric devices | |
| US20150330785A1 (en) | Angular velocity sensor and manufacturing method therefor | |
| Isarakorn et al. | Finite element analysis and experiments on a silicon membrane actuated by an epitaxial PZT thin film for localized-mass sensing applications | |
| JP2011099675A (ja) | 圧力センサー、センサーアレイ、及び圧力センサーの製造方法 | |
| CN109848022A (zh) | 超声波器件以及超声波测量装置 | |
| JP2006147839A (ja) | 圧電/電歪デバイス | |
| JP2007326204A (ja) | アクチュエータ | |
| JPH02248865A (ja) | 加速度検出装置 | |
| Jang et al. | Design, fabrication, and characterization of piezoelectric single crystal stack actuators based on PMN-PT | |
| JP2020156015A (ja) | 超音波デバイス、及び超音波装置 | |
| JP2009198493A (ja) | 角速度検出装置 | |
| KR20030013130A (ko) | 고감도 초소형 캔틸레버 센서 및 제조 방법 | |
| JP2010223622A (ja) | 角速度検出装置 | |
| Kim et al. | Materials and devices for MEMS piezoelectric energy harvesting | |
| Pachkawade | NEMS Based Actuation and Sensing | |
| JP7316926B2 (ja) | 圧電memsデバイス、製造方法および駆動方法 | |
| WO2022091178A1 (ja) | 静電トランスデューサおよび静電トランスデューサの製造方法 | |
| Abd. Rahman et al. | Response analyses of micro-ultrasonic sensor devices for underwater robotic applications |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100517 |
|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20101116 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20101118 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111207 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120203 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120229 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120420 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120516 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120530 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150622 Year of fee payment: 3 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |